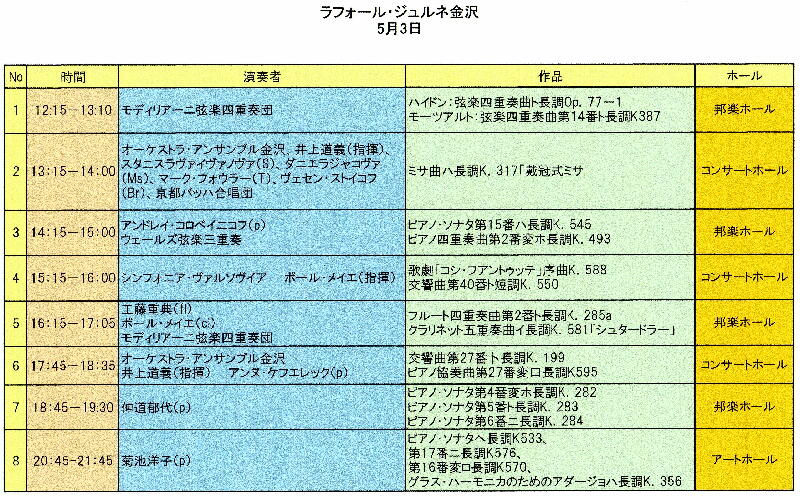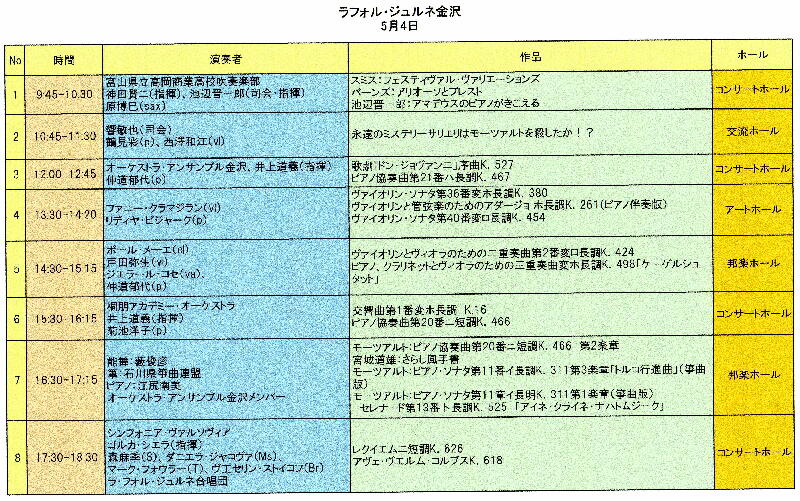|
オーケストラ・アンサンブル設立25周年記念演奏会
2013年9月7日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
ヴァイオリン 諏訪内 晶子 |
|
9月となり、定期の新シーズンが始まる。
定期演奏会の始まりの前に、創立25周年の記念演奏会が開催された。OEKの今シーズン最初の演奏会。
25周年記念のプログラムは個性的なプロ。
祝祭的な雰囲気を盛り上げる、ヘンデルの「王宮花火の音楽」序曲で始まり、ショスタコーヴィッチのヴァイオリン協奏曲第2番(ヴァイオリン 諏訪内 晶子)、後半がモーツアルトの交響曲25番ト短調、最後が西村朗の「鳥のヘテロフォニー」
OEKらしい、内容の多彩なプログラム。そして、OEKの室内オーケストラという特長を最大限に生かしたプログラム。
この日は久しぶりに、音楽堂も超満員、3階まで補助席が出る盛況。
演奏会前に長い間企業としてOEKを支えてきたレンゴーの社長に、谷村会長・石川県知事より感謝状の贈呈があった。レンゴーは経済面で創立当初よりOEKを支えてきており、コンサートマスターが弾いているストラディヴァリウスもレンゴーより貸与されている。
さて、最初のヘンデル。トランペツトとバロックティンパニーが心地よく炸裂し、祝典的な雰囲気を盛り上げる。
アンコールに演奏された同組曲の「メヌエット」とともに、25周年を祝うのに最適な音楽。
2曲目はガラッと色彩が変わり、ショスタコーヴィッチのヴァイオリン協奏曲第2番。
第1番は比較的演奏される機会も多いが、2番は珍しい。ショスタコーヴィッチ晩年の、複雑な心境を感じさせる作品。1番がドラマティックで悲劇的な音楽であるのに比較し、2番はモノローグ的で、より内面的である。
しかし、ショスタコーヴィツチ独特の楽器の使い方、特にフルート、ホルン等管楽器、更に打楽器とヴァイオリンの絡みなど魅力的な部分も多い。
ベートーヴェンの中期の作品と、後期の作品の違い、ドラマティツクな闘争性から内面的なものへの傾斜、それがこの2つのヴァイオリン協奏曲の性格の違いにもあてはまる様に思える。
さて、諏訪内晶子のヴァイオリン、実に濃厚な厚ぼったい音楽。低音が支配的な1,2楽章だが、出だしの低音の濃厚な音に驚く。かつての、巧さは感じるが、作品へのアプローチとしては、薄っぺらい感じが否めなかった諏訪内のイメージとはまったく異なる、作品の本質に迫ろうとする鬼気迫る演奏。
井上道義のアプローチもさすがショスタコーヴィッチを得意とする指揮者。ショスタコーヴィッチ独特の鋭角的な管楽器・打楽器の響きが冴え渡り、ヴァイオリンの太いモノローグを際立たせる。ホルンも指揮者の要求にこたえた熱演。2楽章のフルートの独奏、客演の奏者の様だが、はっとするような豊かな音色でヴァイオリンと対峙する。
カディンツアを含め、暗いモノローグが続く2楽章だが、1番の協奏曲のパッサカリアの様なドラマ性でない、心の襞のつぶやきの様なものが聴こえる。切れ目無く続く第3楽章は一転して激しく鋭い切れ味のヴァイオリンとオーケストラ。諏訪内のヴァイオリンはここでは、鋭く激しく切り刻む。そして、ティンパニーの炸裂と、管楽器、弦楽器の刻むショスタコーヴィッチ独特のリズムと、魅力満載。
畳み掛けるような迫力で全曲が閉じられる。ヴァイオリン、オーケストラとも作品の本質に迫ろうとする力を強く感じさせる熱演だった。
休憩を挟んで、モーツァルトの交響曲25番。40番に対し、小ト短調と呼ばれることのある中期の傑作。映画「アマデウス」でも1楽章がテーマ音楽として使われていた。弦と小編成の管楽器のみの規模の小さい作品だが、内容は濃い作品。悲劇的な色彩の強い作品なので、25周年というお祝いの音楽会のプロとして何故?という疑問もわいたが、井上マエストロのアンコールでの語りによると、OEKが最も得意としてきた作品ということと、25周年と25番を意味づけしたようだ。OEKの弦はさすが思わせるアンサンブル。ホルンはかなりの強奏をマエストロに要求されているので、かなり苦しそうではあったが、迫力ある音を聴かせていた。
「疾走する悲しみ」で突き抜けていくような演奏。
最後は西村朗の「鳥のヘテロフォニー」。コンポーザー・イン・レジデンスという試みを設立当初から行い、日本の現代作曲家の新作を積極的に紹介してきたOEKならではのトリのプログラム。日本の現代音楽をプログラムの最後にメーンとして据えるというのは、OEKの25周年ならではとも思う。
この作品は1963年の委嘱作品だが、再演も繰り返し行われ、OEKのヨーロッパ公演でも演奏されたOEKお得意の作品とも言える。とはいうものの、演奏者にとっては大変な技巧と力を要求される作品。
編成はOEKの標準編成に、打楽器群が加わった程度の小編成のための作品であるが、各パートには特殊な奏法が多く要求されたり、独特な原始的ともいえるようなリズムが要求されたりと、過酷な作品でもある。
中間部では、打楽器奏者3人がビブラフォン、木琴を弓で縦にこすり、グラスハーモニカの様な音を出させたり、終結部の将にアクロバティックな饗宴の部分では(作曲者はインドネシアのケチャの音楽をイメージしているとのことだが)、何と大きいティンパニーをボンゴの様に手で叩きリズムを刻むなど、演奏者には技術と体力が要求される。
鳥が鳴き交わすような静かな導入部から始まり、体を揺すられるようなリズムの饗宴の部分が続き、更に点滅するような鳥の声のような描写が続き、終結部は原始的とも言えるリズムの乱打。
小柄でおとなしそうな西村朗のどこから、こんなエネルギーが噴出するかと思うような激しい作品。
この様に現代作曲家の作品でも再演が続くと、次第に聴衆もそれを聴くのが楽しみとなる。よく言われることだが。「最初からの名曲は無い」のであつて、演奏者と聴衆が名曲を作り出し、育てていくのだと思う。
それにしても、今日の井上マエストロの熱のこもった指揮が、この作品の面白さを際立てていた。激しいリズムの部分では、身体全体を揺り動かしオーケストラを牽引、踊りの名手でもあるマエストロの面目躍如という演奏。
アンコールが、ヘンデルの「王宮花火の音楽」からメヌエット。バロックティンパニの炸裂で華々しくエンディング。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第340回定期演奏会
2013年7月18日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
バス 森 雅史 |
|
今期最後の定期。例年なら9月に行われる「岩城宏之メモリアルコンサート」、今年はOEK25周年の記念行事が9月から始まるので、7月にずらしての開催となったようだ。
今年の岩城宏之音楽賞の受賞者は、高岡市出身のバス歌手、森雅史氏。現在ドレスデンのゼンパー・オーパーに所属する中堅の歌い手。今日は2部でその歌が披露される。
今日のプログラムは森雅史の歌を除くとメンデルスゾーンの交響曲が2曲。3番「スコットランド」、4番「イタリア」
メンデルスゾーンの交響曲2曲のプロ、ありそうでそんなに無いプロではなかろうか?
来年2月には2番「賛歌」という珍しい作品が山田和樹の指揮で演奏される。OEKの編成にもピタッとあうことでもあり、とりあげられる回数も多いということか。
さて、前半は3番「スコットランド」。 シューマンの3番「ライン」とも近似性を感じるロマン派交響曲の名曲。
この作品の絵画的な色彩感を強調した様な端正な演奏。きつちりとした造形感、整ったアンサンブル。
低音の厚みと、ティンパニーの輝きがやや足りなく、響きが薄く聴こえたのが、やや物足りなく感じさせた。
この作品のもう一つの側面として、情緒纏綿と歌わせ、濃い色付けをする演奏もあるし、その方が聴く方にとっては面白いとも思うのだが、井上マエストロはそのあたりはあえて外して、淡色系の演奏を狙っていたよう。
今日はフルート主席に、工藤重典が座っており、さすがに輝きのあるフルートが出色。
後半は森雅史が登場。バス独特の太い輝きとでも形容出来る声の質。
モーツァルト2曲。「ドンジョバンニ」から「カタログの歌」、「魔笛」から「この聖なる殿堂では。」
動と静の対比のある2曲。前半のややコミカルな味付け、後半の堂々たる貫録の歌、個性的な味付けのある歌いっぷり。さすがにオペラ座の経験が生きている。
フレンニコフ「酔っ払いの歌」の超低音、最後の部分のどこまで下がるかという低音は、バスの魅力たっぷり。
最後はプッチーニの「ラ・ボエーム」から「外套のアリア」。プッチ-ニらしい甘く切ないリリカルな情緒をたっぷりと聴かせてくれた。映画俳優にも劣らないルックスと、豊かな声質と表現力、オペラでの活躍を是非見てみたい歌手である。
最後はメンデルスゾーンに戻り4番「イタリア」
疾走する様なリズムにのり、歌が溢れた快演。一気呵成の様に流れる作品だから、どこかで停滞すると、とたんに流れが止まり、魅力の無くなる演奏と化すが、この日の演奏はそんな憂いが全くなく、充実した躍動感が満ちていた。
1楽章開始の木管の魅力的な和音、2楽章の憂い、3楽章の柔らかい舞踊、そして4楽章の激しいタランテラと各楽章の個性がきっちりと描き出されていた。
弦楽器、管楽器とも早いパッセージが早いので、ひとつ狂うと収拾がつかなくなると思うが、OEKは細部をごまかすことなく、クリアに演奏していたので、アンサンブルの妙がくっきりと聴こえ魅力的。
この演奏会が今期の定期の最後。今期も、個性ある演奏会を多く聴く事が出来た。
来期は、マイスターシリーズで5回シリーズでのベートーヴェンの交響曲全曲演奏。中にOEK得意の日本の現代作曲家の代表作の再演も加わり、25周年という節目にOEKの成長を聴く事のできるシリーズとなりそう |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第338回定期演奏会
2013年6月29日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮・ピアノ シュテファン・ヴラダー |
|
今月は、フィルハーモニー、マイスター両シリーズ共、ピアノの弾き振りというのも珍しい。
先回の巨匠レオン・フライシャーに続いて、今回はウィーンのピアニストシュテファン・ヴラダーの登場。
シュテファン・ヴラダーもピアニストから指揮者への道を歩みつつあることから、今回も前半は指揮での登場。
プログラムは前半がベートーヴェンのレオノーレ序曲第1番、モーツァルトの交響曲第25番ト短調K183、後半がベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」。
2004年にフランスの名ピアニスト、フィリップ・アントルモンがやはり定期でこの作品を弾き振りしている。
その時の私の記録を見ると、エレガントで暖かい演奏であったようだ。
9年後の今日、果たしてヴラダーは弾き振りという、珍しいスタイルでどの様な演奏を聴かせてくれるか楽しみ。
ベートーヴェンのレオノーレ序曲第1番、演奏される事が珍しい作品でなかろうか。3番の劇的緊張度の高さに比べると、ややおとなしいとも聴ける作品だが、ヴラダーはアンサンブルをきちんとまとめ、完成度の高い演奏を聴かせてくれた。出だしの静かな中に張りつめた緊迫感の満ち満ちた部分の弦と管の厚い響きは印象的。
モーツァルトの25番、40番と比較し小ト短調とも呼ばれ、映画「アマデウス」のテーマ音楽ともなった、モーツァルト初期の名作。ヴラダーはやや早めのテンポをとり、疾走する様な緊張感を表出。ヴィブラートを控えめにし、シャープな響きを追求しているよう。もう少し、豊潤な響きも欲しい気もしたが、この作品に対するヴラダーの表現意欲は伝わってくる。
休憩後はベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」。この大作を弾き振りというのは、ピアニストにとっても、オーケストラにとっても大変な冒険の様に思えるが、この日の演奏はその杞憂を吹き飛ばすような快演。
ピアノは非常にクリアで、音の泡立ちが良い。決して派手さをひけらかす演奏でないが、内容はぎしっとつまった聴きごたえのあるもの。表面的な華麗な演奏ではないが、一つ一つのテーマをじっくりと丁寧に描き出しながら、スケール大きく描き出した演奏。
アンコールのリストでもそうだが、濃厚さとか、華やかさとは異なるのだが、それでいて非常に濃密な世界を描き出していくのが特長か。オーケストラも指揮者ヴラダーの意図に忠実に、そしてピアニストヴラダーにもしっかりとサポートするという、充実したアンサンブル。ヴラダーもピアノの応答にオーケストラが敏感に反応するので、気持ちのこもった弾き振りが出来ているよう。このあたりが、協奏曲の弾き振りの醍醐味であろうか。ピアニストの息づかいとオーケストラの息づかいが一致し、阿吽の呼吸で音楽が進んでいく。オーケストラと独奏者のバラバラな感じが無い。しかし、これはやはりOEKが成熟したオーケストラだからだろう。
先回のフライシャーの円熟の弾き振り、今回ヴラダーの充実の弾き振りと、二人の個性ある弾き振りの対照の妙を聴く事が出来、興味深い6月の定期だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
スイス・バーゼル歌劇場日本公演 モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」
2013年6月27日 オーバードホール
アルマヴィーヴァ伯爵 クリストファー・ボルダック
伯爵夫人 ジャクリーン・ワーグナー
スザンナ マヤ・ボーグ
フィガロ ユン・カン・リー
ケルビーノ フランツィスカ・ゴットヴァルト
マルツェリーナ ジェラルデン・キャシデー
バルトロ アンドリュー・マーフィー
バジリオ カール・ハインツ・ブラント
バーゼル歌劇場合唱団 バーゼル・シンフォニエッタ
音楽監督・指揮 ジュリアーノ・ベッタ
演出 エルマー・ゲールデン
衣装 リディア・キルヒライトナー
舞台美術 シルヴィア・メルロ&ウルフ・シュテングル
合唱指揮 ヘンリク・ポラス |
|
スイス・バーゼル歌劇場の初来日公演。富山でこの話題のオペラ座を聴く機会が出来た事は嬉しい。
今回は、富山新聞・富山市の共催で、ユニークなことに富山薬業連合会が協力となっている。
企業メセナということだが、富山の伝統的地場産業がオペラの後援を行った事は初めてではなかろうか。
今後とも是非この様な試みは続けてほしい。金がかかるオペラ公演、企業の後援は、聴衆にとっても有り難い事である。
さて、今回の公演、今まで富山で行われたオペラ公演の中でも、群を抜く、内容の充実した、そして新鮮な舞台だった。
まず、演出の新鮮さ、そして歌手たちとオーケストラ・指揮者の充実、舞台装置の美しさ、それらが一体となって、このオペラの面白さ、モーツァルトの音楽の天才的な閃き、が見事に表現されていた。
まず、演出。エルマー・ゲールデンは、何と舞台を現代のロサンゼルスに置き換えている。
そして、演者は、総て現代風な衣装をまとう。
これが、違和感が有るかというとさにあらず、実にピッタリとモーツァルトの音楽にはまり込んでいて、不自然さが全くない。
ゲールデンは、このオペラの神髄は、舞台を現代に移すことにより、より身近な出来事として、見るもの、聴くものの心に響くに相違ないと考えたのだろう。
それだけ、モーツァルトの音楽には、時代に捉われない普遍性があるということを、この演出は示している。
更には、様々な仕掛けで、見る者の想像心をかきたてる。
たとえば、序曲ではもう既にオペラは始まっている。幕の無い舞台には、序曲の最中に暗い照明の中、伯爵夫人がたたずんでいる。これは果たして何を暗示しているのか、華やかな序曲の響きの中、暗い中に孤独に立つ伯爵夫人。
そして序曲が終わり、舞台が明るくなるとそこは、おもちゃが散乱する子供部屋。子供部屋がスザンナとフィガロの新居に模様替えとなる。何故子供部屋?
更に、オペラの中で盛んに飛ばされる紙飛行機。
こんな仕掛けが随所にあり、見る者を果てしない想像の中に引き込む。
又舞台装置。舞台装置は正面でなく、やや斜めに設置されている。人間の心理の不安定さを象徴しているのだろうか?
4幕とも装置は簡略化されてはいるが、生活感が現われている。1幕は前述したように子供部屋、大きなトラのぬいぐるみやおもちゃが散乱している。2幕はスザンナの寝室、沢山の衣装ダンス、バスタブ、洗面所、4幕は庭園だがサボテン(何故サボテン?)が生え、その向こうにはロサンゼルスの街の夜景が広がる。この様に、舞台装置と照明が、このオペラのドラマの背景を物語っている。そして非常に美しい。特に第4幕の夜景の美しさは印象的。
モーツァルトのオペラには、音楽に会った色彩感が必須と思うが、そのあたりも見事。
そして、歌手達。
フィガロの韓国出身のユン・カン・リー、幕開けの「三尺、四尺、五尺」の採寸のアリアからぐっと聴く者を魅了する。伯爵のクリストファー・ボルダック、伯爵夫人のジャクリーン・ワーグナーとも、ドラマの複雑な役をくっきりと描きわけ、声量も豊か。
そしてなにより、ケルビーノのメゾ・ソプラノ、フランツィスカ・ゴットヴァルト。清楚でありながら、茶目っ気たっぷりのケルビーノ役にぴったり、その柔らかいソプラノ、情感こもった歌は魅力的。有名な「恋とはどんなものかしら?」は素晴らしい名唱。
そして、アリアとともに重唱の見事さ。モーツァルトのオペラに聴く事の多い、それぞれの役がそれぞれの思いを歌う場面。各歌手の実力が確かなので、くっきりとした、ドラマティックな重唱となり、劇的興奮を高める。
オーケストラは小ぶりの変則的な10型だが、弦楽器の柔らかい響き、歌と共に良く歌う木管、そして生き生きとしたリズム感など、指揮者の的確な指示にピタッと寄り添い躍動。レシタティーボに寄り添うチェンバロの響きも魅力的。
劇の筋は、どちらかというと通俗的なドダバタ。現代の三谷幸喜ばりの喜劇である。しかし、モーツァルトはそのドタバタにとてつもなく美しい音楽を添えた。たとえば、終幕のエンディングの部分、ドダバタが極まるのだが、その部分の音楽の清冽な美しさは、果たしてどうしてという驚きを与えられる。
モーツァルトの音楽の持つ不思議さが、このオペラでも端的に現わされている部分でもある。
モーツァルト自身、人生は、その音楽ほど美しいものでなかったも言える。実際の人生のどろどろとしたもの、それだからこそ、美しいものに対する憧憬、人間の根源的な美しさに対する信頼、それを音楽で表現したともいえるだろう。
この演出でも、伯爵のみならず、ケルビーニは当然として、伯爵夫人、スザンヌまでも欲望を心の底に秘めた人間として描かれる。だから、最後に総て許し合うという、人間への暖かい賛歌の様にモーツァルトは描いたのではないか。そのあたりが、如実に描かれた面白い演出でもあった。
サボテンのトゲ、飛び交う紙飛行機、そのあたりの小道具も暗示的である。
この様に、色々深読みさせられた演出だったが、それを見事に表現した、歌手、指揮者、オーケストラ、合唱団、更には舞台装置、照明、衣装、総てがその役割を見事に果たし、見る者にこのオペラの神髄を見せ、聴かせてくれた。
その意味で非常に感銘深い舞台だった。
今年はオーバードはオペラの年の様で、秋には同じモーツァルトの「魔笛」がプラハ国立歌劇場で演じられるし、コンサート形式ではあるが、チョン・ミョンフンがワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」を演じる。後者は富山初演でなかろうか。楽しみなシーズンである。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第338回定期演奏会
2013年6月13日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮・ピアノ レオン・フライシャー
ピアノ キャサリン・ジェイコプソン・フライシャー |
|
レオン・フライシャー、はるか昔にその名を聴いた記憶がある伝説的ピアニスト。
それもそのはず、約50年前に指の突然の故障でビアニストを引退、その後60代で奇跡的に回復、現役復帰を果たすという劇的な人生を歩んできた音楽家。今年85歳になるという。
ビアニストを断念してからは指揮に転向したとのこと。
私が音楽に親しみ始めた頃は、既に引退していたのだろう。その名前は頭の隅にあるから、当時は相当なピアニストであったのだろう。
今日のプログラムは、ラヴェル「クープランの墓」、モーツァルト「2台のピアノのための協奏曲ヘ長調k.242」、
ベートーヴェン「交響曲第一番」。
音楽を聴くのに余計な先入観は不要なのだろうが、今日のフライシャーの音楽を聴きながら、一人の音楽家の人生の波乱の軌跡と不思議な静寂の中の平穏を聴いた気がした。
既に85歳の高齢、指揮台に椅子を置き座っての指揮。楽器配置は古典的な、コントラバスを左に配置した対向配置。
最初のラヴェル、きらきらと輝くのでなく、モノトーンの中に漂う様な静かなラヴェル。木管群のさざめきの様な響き、弦のビロードの様な柔和な響き、そして洒落たリズムと、夢幻的な響き。
次のモーツァルト。訂正が貼られていたが、当初は良く演奏されるk.365変ホ長調の作品(ピアノ協奏曲10番とされている。)とされていたが、この日取り上げたのは「3台のピアノのための協奏曲」を「2台のピアノのために」編曲したもの。
初めて聴く珍しい作品。
ここでは、夫人とのデュオ。弾き振りとなるため、ピアノが縦に2台並んだ珍しい配置。
曲想はサロン風な華やかな曲想だが、ここでの演奏も二人寄り添う様な滋味豊かなもの。
これみよがしな派手さが一つもない、誠実で語りかける様なピアノ。夫婦二人の親密な会話を聴く様なしみじみとした演奏。伴奏のOEKも弦を中心とした厚く柔らかい響きでサポート。
休憩後のこの日のメーンは、ベートーヴェンの1番の交響曲。
この選曲にもフライシャーの思いが込められている様に感じた。メーンの交響曲は普通はもう少し大きな物を持ってくると思うが、フライシャーはベートーヴェンの1番という、やや小ぶりながら充実した内容の交響曲を選曲。
「もう、そんなに大きいものは演奏したくないのですよ。」というメッセージにも聴こえる。
実に充実した内容がびっしりと詰まった様な演奏。テンポは1楽章からやや遅めで、インテンポ。遅めでありながら、決して力んでいたり、誇張が有るわけでない。一つ一つのテーマをじっくりと歌わせながら、ベートーヴェンの新鮮な響きと雄大さを描き出していく。2楽章も淡々としいるようでありながら、豊かな歌がおおらかに歌われていく。
決して個性的なぎらぎらした主張はしないが、しかし溢れる様な歌と、厚い充実した響きに満ちた演奏。
自然体とはこの様な演奏をいうのだろう。豊かにいつまでも心に残っていくであろうベートーヴェンだった。
先回の定期はやむをえぬ事情で聴けなかったので、久しぶりの定期。心にしみるコンサートだった。 |
|
|
|
|
|
|
ラ・フォール・ジュルネ金沢2013
2013年5月3日~4日
石川県立音楽堂 コンサートホール 邦楽ホール
アートホール |
|
今年もラ・フォール・ジュルネ金沢が開催された。今年で既に6回目、この行事もすっかり金沢に定着し、楽しみにしているファンも多い様だ。
運営も年々スムーズになっており、第一回の頃と比べると、ずっと落ち着いた雰囲気の音楽祭となってきた。
今年は集中開催日が2日間と短くなったが、プログラミングの点で工夫が見られ、一層鑑賞しやすくなっていた。
そのひとつは、コンサートホールの演奏会と、邦楽ホール、アートホールの音楽会が交互に開催され、コンサートホールの演奏会の後、邦楽ホールかアートホールの演奏会のどちらかを選択できるようになっており、ハシゴをする場合もわかりやすくなっていた。ただ、演奏会の間の間隔が15分が多く、相変わらず忙しい事は従来通り。
最終の閉演時間を遅らせても、もう少し演奏会の間隔を長くできないものだろうか。
昨年もあつた曲順の変更が今年も数回あったが、総て直前の放送で変更が紹介され、昨年の様なとまどいもなかった。
飲食ブースも色々あるのだが、合い間の短時間でお腹を満たせるような工夫も欲しかった。
スイーツの様なものが多く、腹を満たすのが、冷たいホットドックとサンドイッチ程度というのは寂しい。
私の場合はせっかくならと欲が出て、1日8公演、2日間で16公演をハシゴしたので、好きとはいえ疲労感と空腹?も覚えた。次からは、もう少し余裕を持った鑑賞プランをと反省している。
今年は、「パリ至福の時」のテーマで、フランスとスペインの音楽が特集されたが、内容は例年以上に充実している様に感じた。
オーケストラはOEKの他が、大阪フィルとロワール管弦楽団、でいずれも個性的な演奏を聴かせてくれた。
室内楽もモジリアーニ弦楽四重奏団、パスキエを中心としたトリオが素晴らしいドヴュツシーとラヴェルを聴かせてくれたし、独奏者もいずれも内容の濃い演奏。
世界のトツプアーティストらしい力のこもった演奏会が多かった。
下記に聴いた音楽会の短い感想を記す。
5月3日
ラヴェル オペラ「子どもと魔法」
オーケストラ・アンサンブル金沢
びわ湖ホール声楽アンサンブル
指揮 園田隆一郎
|
ラヴェルのミニオペラ。
演奏会形式だが、舞台装置が無いだけで、演出はオペラ。
びわ湖ホール声楽アンサンブルの各メンバーの実力が発揮されたオペラ。
独唱者としての実力、重唱の巧さ、レベルの高い演奏。
おとぎ話の世界が、ラヴェルの夢幻的な音楽の世界で表現され、魅惑的。
|
音楽の印象派Ⅰ
モディリアーニ弦楽四重奏団
ドビュッシー 弦楽四重奏曲
ラヴェル 弦楽四重奏曲
|
2楽章にピチカート、3楽章のアダージョ等、構成が相似の2作品。
アンサンブルの緻密さ、表現力の豊かさが音楽的興奮を高める。
音楽的説得力の濃い演奏。
|
フランス国立ロワール管弦楽団
指揮 井上道義
ピアノ アンヌ・ケフェレック
ラヴェル ラ・ヴァルス
ピアノ協奏曲
ボレロ
|
フランスらしい輝かしく繊細な音かと思いきや、かなり厚い色彩の音を出すオーケストラ。
ラ・ヴァルスはやや重い演奏。
ピアノ協奏曲のケフェレックは繊細で詩的だが、協奏曲としてはもう少し音量も欲しい。
ボレロでは、独奏者をズラリと最後部に並ばせ、立ったままの演奏。
小太鼓も後ろの部分と、オーケストラ中央に2台配置。
一部の独奏者がやや不調だったのは残念だが、各奏者はさすがと思わせる響き。終結部の最強奏は、分厚い音の競
演。
|
音楽の印象派Ⅱ
レジス・パスキエ(Vn)
ロラン・ピドウ(Vc)
ジャン=クロード・ベヌティエ(P)
ドビュッシー ピアノ三重奏曲
ラヴェル ピアノ三重奏曲
|
ベテラン3人によるピアノトリオ。
ドヴュッシー、ラヴェルの室内楽作品を纏めて聴けるのは、この音楽祭ならでは。
四重奏曲と並べて聴いてみると、構成、音楽の作り方など酷似しているのを聴く事が出来る。濃い色彩と緻密なアンサ
ンブル。
|
フランス国立ロワール管弦楽団
指揮 パスカル・ロフェ
ドヴュッシー 牧神の午後への前奏曲
ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ
ドヴュッシー 交響詩「海」
|
油彩を連想させる様なぶ厚い色彩の音楽。
特に「海」は、音が幾重にも重なり、色彩の洪水の様。
「海」の最終章の終結部の盛り上がりは圧巻。ホールに音の洪水。
|
「サティと仲間たち」
ピアノ アンヌ・ケフェレック
|
LFJでは常連のケフェレック。
繊細で詩的なピアニストだが、今回はサティを中心とした小品のコンサート。
自由闊達な表現。サティの作品は様々な演奏スタイルが許容されるが、ケフェレツクは将に自由自在。テンポも微妙に
動かしながら、繊細でありながら味付けは濃く、ロマン性豊か。セヴラック、フェルー、アーン等、サティを取り巻く他の作
曲家の小品も魅力的。
|
オーケストラ・アンサンブル金沢
指揮 井上道義
ギター パブロ・サインス・ヒジェカス
|
今回のテーマの一つスペインの音楽。
ロドリーゴの「アランフェス協奏曲」を中心としたプログラム。
他にラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」、ファリャの「三角帽子第一組曲」
ギターのパブロ・サインス・ヒジェカスは、さすが本場スペインのギタリストと思わせる、雰囲気豊かな演奏。テクニックも
音量も豊か。
スペインの香りが満ちた、雰囲気の濃い演奏。
ファリャはオーケストラのリズムのノリがもう一つ。
|
「能舞とボレロ」
ピアノ 田島 睦子
相良 容子
ソプラノ 熊田 祥子
能舞 渡辺 荀之介
渡辺 茂人
|
LFJ金沢の個性的なプログラム、能とクラシックのコラボ。
今回は、ラヴェルのボレロ(ピアノ4手版)とドビュッシーの歌曲「まぼろし」
に合わせての能舞。
本来バレー音楽である、ボレロを能舞にすると?という興味ある試み。
私は能には全く疎いので、理解できない点が多いが、進むにつれて、能にしてはかなり動きが大きく、激しい様に見え
た。ラヴェルのボレロのバレエの展開を能で表現すると、こうなるという面白さか。フランス人の評を聴いてみたい気もす
る。ピアノとソプラノ、いずれも石川氏出身のアーティスト。石川の音楽土壌の豊かさを証明する音楽家達。
|
5月4日
坂口 昌優 ヴァイオリン
石本 えり子 ピアノ
アルベニス「エヴォカシオン」他
ラヴェル 「ツィガーヌ」
西沢 和江 ヴァイオリン
鶴見 彩 ピアノ
プーランク 即興曲より
フランク ヴァイオリンソナタ
2楽章
|
昨日3日の最後の演奏会同様、地元石川出身で、世界に羽ばたいている新進演奏家たちのリサイタル。
OEKの存在、IMAや新人登竜門オーディションの存在等により、年々石川からプロを目指そうとする音楽家が増えているようで頼もしい事である。
現在はやや荒削りな印象もあるが、レベルの高い演奏も聴く事が出来て石川の音楽レベルの高さを聴く事が出来た。
LFJでのこの様な企画により、沢山の聴衆にその存在を知らしめることは、新進演奏家の今後の活躍に大いに役立つ事となろう。
|
オーケストラ・アンサンブル金沢
指揮 現田 茂夫
ヴァイオリン レジス・パスキエ
サラサーテ カルメン幻想曲
ビゼー アルルの女第1、第2組曲
|
日本人のゲストコンダクター、今年は現田茂夫。
北陸では比較的なじみの薄い指揮者だが、オペラ指揮者として定評のあるという実績通り、堅実な実力派指揮者という印象。
バランスのとれたアンサンブル、色彩感の豊かさ、劇的表現の巧さ等、劇音楽にはふさわしい指揮者の印象。「アルルの女」、第2組曲は良く演奏されるが、1.2を同時に演奏するのは珍しい。特に第1組曲は久しぶりに聴く懐かしさを覚えた。
パスキエはさすがのテクニシャン。トリオで聴かせたヴァイオリンと又異なる華麗なヴァイオリンを聴かせてくれた。
|
「動物たちの音楽会」
リディヤ・ビジャーク
サンヤ・ビジャーク
サンサーンス「動物の謝肉祭」(2台のピアノ版)
プーランク「子象ババールの物語」
語り しゅうさえこ
|
ビジャーク姉妹の楽しいリサイタル。
サンサーンス「動物の謝肉祭」は2台のピアノによる演奏だが、テクニックの確かさと、表現力の強さは凄い。「ピアニスト」「化石」等のユーモアと皮肉に溢れた作品の徹底したデフォルメは見事、思わず笑いを誘う。この作品の鮮やかな動物表現とユーモアを十分に聴かせてくれた。
プーランク「子象ババールの物語」はしゅうさえこの巧みな朗読とピアノが見事に一致し、絵本をめくる様な楽しさ。プーランクの洒落た音楽が充満。
|
大阪フィルハーモニー交響楽団
指揮 現田茂夫
ベルリオーズ 「幻想交響曲」
|
今年の日本のゲストオーケストラは大阪フィル。
久しぶりに聴く大フィルの充実したサウンドを大いに楽しんだ。
大曲なので、まとめ方も大変と思うが、1楽章に多少のもたつきを感じたものの、楽章が進むにつれてエンジンがかかってきたよう。
最終楽章の「ワルプルギスの夜の夢」の悪魔的な高笑い、エンディングの狂騒、など将に興奮物。
3楽章の羊飼いの吹く笛を舞台裏から響かせたり、「ワルプルギスの夜の夢」の鐘をやはり舞台裏で遠近感をつけて鳴らしたり、音響の演出も満載。
現田茂夫は時に指揮台で飛び上がったりの大熱演。大フィルもそれに応えて全力投球。力のこもった「幻想」
|
ヴァイオリン キリル・トリソフ
ピアノ 広瀬 悦子
フォーレ ヴァイオリンソナタ
ラヴェル ヴァイオリンソナタ
|
フランスの近代名ヴァイオリンソナタ2曲。
トリソフと広瀬悦子という、スケールの大きな演奏家が演奏する、将に壮大なスケール感のある演奏。
フランスものという先入観にとらわれない、個性的で、堂々とした演奏。
フォーレの溢れる様な熱いロマン、ラヴェルの原始的とも感じられる激しさ。
二人の演奏家が火花を散らす様な凄さがあった。
|
大阪フィルハーモニー交響楽団
指揮 井上 道義
オルガン 黒瀬 恵
シャブリエ 狂詩曲スペイン
サンサーンス 交響曲第3番「オルガン付き」
|
今回のLFJの目玉の一つ。
最近オルガン付きホールも増え、この交響曲の演奏される機会も増えたようだが、地方では中々聴けない作品。
私も生で聴くのは初めて。聴いてみると、なるほどこの音はいくら優秀なオーディオでも再現できないであろうと思えるほどの重低音の迫力。
最後のエンディングの壮麗なオルガンに至るまで、井上マエストロはかなり丁寧な音楽づくり。一楽章出だしの最弱音の繊細な響きから、サンサーンス独特の華麗な旋律まで、実に魅力的に響かせる。やや、遅めのテンポで音楽のうねりをあらわし、堂々と華麗に展開されていく。
オルガンの壮麗な音は勿論だが、アダージョの部分で響く重低音は将にホールを震わせる。サンサーンスはこの効果を狙っていたというのが体感できるのは生ならでは。貴重な音楽体験であった。
|
音楽の印象派Ⅲ
ピアノ 広瀬 悦子
ドヴュッシー 沈める寺
西風の見たもの
ラヴェル 悲しい鳥たち
海原の小舟
夜のガスパール
|
初めて聴くピアニストだが、スケールの大きさと華麗なテクニックに脱帽。
席が、ピアニストの鍵盤に置く手が良く見える好位置だったが、その手の動きは将に自由自在。流れる様な美しい手の動きから、時には優しく、時には激しい音か出て来る様はまるで魔法の様。
総ての表現が多彩で輝いている。
「夜のガスパール」の超絶技巧も易々と弾かれていく。
アンコールの2曲も圧巻。
|
オーケストラ・アンサンブル金沢
指揮 井上 道義
ヴァイオリン キリル・トルソフ
オッフェンバック 「天国と地獄」序曲
ビゼー 「カルメン」第2組曲
ドヴュッシー 「月の光」
サン=サーンス 「序奏とロンドカプリチオーソ」
|
お馴染みの「フレンチカンカン」の「天国と地獄」序曲。オペレッタの序曲らしい劇的な緩急の表現も見事。「フレンチカンカンも賑やかではあるが、泥臭くない洒落た演奏。
「カルメン」第2組曲もドラマティツクな表現。
管弦楽版の「月の光」は色彩的で夢幻。
トカレフのサン=サーンスは粗っぽいと感じさせるほどの激しさで迫る。
この後、交流ホールでクロージング・コンサートが開かれるのだが、実質上のクロージングコンサートの様な楽しさ。
来年も、果たしてこのLFJ、聴きに来る事が出来るだろうかという寂しさも。
|
|
|
|
|
|
|
|
サンクトペテルブルグ交響楽団演奏会
2013年4月10日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義 |
|
最近は外国からのオーケストラの来日公演を日本の指揮者が振るケースも多くなったようだ。
それだけ、日本の指揮者の海外での活躍が際だっているという事。
今回は、サンクトペテルブルグ交響楽団を井上道義が率いての日本公演。その最初の公演地が井上道義のホームグランド金沢。通常は東京でオープニングが行われるのが普通だが、トップバッターの公演地として金沢を選んだのは当然マエストロ井上の強い意向が有っての事と思う。
さて、サンクトペテルブルグには、ややこしいが良く似た名称のオーケストラがあり、もう一つのサンクトペテルブルグフィルハーモニー交響楽団の方が、ムラヴィンスキーのオーケストラとして日本では著名。
しかし、この2つのオーケストラともテミルカーノフが指揮していたこともあり、ややこしい。
遡れば1942年ショスタコーヴィッチの交響曲7番「レニングラード」をナチのレニングラード包囲網の中でレニングラード初演を行ったという歴史的な記録もこのオーケストラが持っている。
5年ほど前に東京日比谷公会堂で井上道義によるショスタコーヴィッチの交響曲全曲演奏会が開かれた際、中心オーケストラとして演奏したのがこのサンクトペテルブルグ交響楽団。
ということで、井上道義とこのオーケストラは非常に親密な関係を築いているといえる。
この日のプロはオールロシア。
前半がチャイコフスキーの幻想的序曲「ロミオとジュリエット」、ストラヴィンスキーのバレー「火の鳥組曲(1919年半)」、後半がショスタコーヴィッチの交響曲5番。
ロシア音楽の王道ともいうプロで、なお且つ井上マエストロの得意とするショスタコーヴィッチとあつて、期待の大きい演奏会。
最初のチャイコフスキーの幻想的序曲「ロミオとジュリエット」。出たしの木管の太い音からロシアのオーケストラの厚い響きのアンサンブルの特長を感じさせる。
主部は早いパッセージを、嵐の如くとも形容出来るような、激しく、しかしきっぱりとした明確な響きを刻みながら進める。この辺りは井上マエストロの要求がオーケストラにぴちっと行きわたり劇的な盛り上がりをしつかりと描き出す。弦は分厚いのだが、指揮者が細部までのクリアな表現を要求しているようで、濁る事がない。
ヴァイオリンの強奏部分では硬質な響きで、もうすこし柔らな響きをとも感じないでもないが、これが指揮者の個性か。緊張感と劇的盛り上がりを聴かせてくれた名演。きつちりとした構成感と、その中での劇的展開、痛快な演奏でもある。
次のストラヴィンスキーバレー「火の鳥組曲(1919年半)」。ここでは、情景描写が鮮やかに色彩的に表現されていた。
特に、火の鳥が羽をはばたかせて踊る様な弦楽器の描写は見事。ところどころで管楽器のアンサンブルの乱れもあったが、これだけ強い音を要求されると、仕方のない部分もあるのだろう。「乙女たちのロンド」が意外にあっさりと演奏されていた。このあたりもう少し豊かな歌が聴きたかったきらいもあるが。
「子守唄」からフィナーレへの鮮やかな盛り上がり、終結部の乾坤一擲というようなドラムの響き、思わず「決まった」といいたくなるようなフィナーレであった。
休憩後はこの日のメーン、ショスタコーヴィッチの交響曲5番。
余りにも良く演奏される名曲、そして様々な解釈が物議をかもしだす作品。今でも、この作品、ショスタコーヴィッチの真意が斟酌され、それにより解釈もまだ色々とされている不思議な名曲である。
それだけに、井上マエストロがどの様な演奏をするのか、興味のあるところだった。
この日の演奏は、感傷的な解釈を排しながら、このシンフォニーの音楽的構成を厳格に表現し、旋律、リズム、アンサンブルの緻密さを厳しく追及した演奏と聴いた。
一楽章は遅めのテンポで主題が提示されるが、テンポの遅い割にはもたれることなく、静かな緊張感に満ちた開始。
展開部も、勇壮さや華麗さよりも、厳しいきっちりとした、それでいて大きく激しい展開。
終結部の静けさに満ちた、つぶやくような終わり方も印象的。
第2楽章は弦楽器の刻む様な強い響きが、木管のヒステリックな響きとこだまし、強烈なスケルツォ。
第3楽章はこの交響曲の頂点を築く様な、アダージョ。ここでも井上マエストロは感傷的な虚飾は排し、楽譜から聴こえる音をどの様に再現するかを追求しているかのよう。終結部のハープの音が実に心に響く。
アタッカの如く第4楽章に突入。この最初の主題の提示が指揮者により様々な解釈がされるところだが、井上マエストロは誇張せず、かといって控えるでもなく、厳格なテンポでのしっかりとした提示。展開部はえてして派手で、華麗に演奏されがちだが、ここでも音は大きく、激烈ではあるが、浮かれ過ぎる事のない厳しい演奏。
静謐な中間を経ての再現部と終結部。壮大なドラマを締めくくるのにふさわしい、フィナーレ。
大きなテーマを管楽器群が高らかに奏し、弦楽器が支え、そこへティンパニーの連打、最後のティンパニーの一打は、この日の激烈な演奏を象徴する様な一打。
このシンフォニーは名曲であるが故に多く演奏され、指揮者による解釈も千差万別、どれもそれなりに聴かせる事の出きる名曲ではあるが、あまりにも主観的に解釈する指揮者の多い中で、自らの思い入れを排し、楽譜の中に書かれた音楽をどのように忠実に表現するかに腐心した井上マエストロの演奏であったように思う。
それだけに、果たしてショスタコーヴィッチはこの交響曲に何を託したのか、改めて深く考えさせられる演奏だった。
アンコールはショスタコーヴィッチの組曲「ボルト」から「荷馬車曳きの踊り」。
すさまじい金管の咆哮。ホールが揺れるよう。そして、井上マエストロの荷馬車弾きを想像させる様な、全身を使っての指揮のパフォーマンス。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第336回定期演奏会
2013年4月10日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響
ピアノ 外山啓介
協力 大阪フィルハーモニー交響楽団 |
|
当初は金聖響が首席指揮者を務めたベルギーのフランダース交響楽団を率いてのコンサートの予定だったが、どの様な事情か、早々と変更が発表され、OEKと大阪フィルとの合同演奏会の形となった。
大阪フィルからは主に弦楽器の奏者が入り、コントラバス6代の14型の大きな編成となってのコンサート。
ブログラムは前半がワーグナー「ニュールンベルクのマイスタージンガー第一幕への前奏曲」、ピアノに外山啓介を迎えてのラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」、後半がブラームスの交響曲第一番。重厚なプログラム。
編成も通常のOEKより相当大きいが、楽器配置は従来の金聖響の配置。左側にコントラバスを置き、他の弦は対向配置。管楽器は従来、トランペット、トロンボーンを極端に右側に配置していた事が多かったが、今日は右やや奥の通常のオーケストラの位置。そして、今回はティンパニーもバロック型でなく、通常の大型のもの。今日のプロがロマン派ということで、この様な配置となったのと思うし、弦もヴィブラートは通常にかけていた。
さて、最初のワーグナー。どの様なテンポをとるか、興味が有ったが、オーソドックスな、早くも遅くもない中庸のテンポで始まった。ワーグナーの複雑に絡み合うテクスチュアをかなり明快に鳴らすので、その面白さはあるが、反面ワーグナー独特のぶ厚い響きにはやや欠けていた。明快な部類のワーグナー。
終結部も大いに盛り上げたが、それほどテンポを落とす事もなく、むしろあっさりと締めくくったという感じ。
ワーグナーのうねりの様な音楽とはやや離れた、ドライなワーグナーか。
次のラフマニノフ。ここでは、ワーグナーと異なり、金はかなりロマン性を意識した音楽づくり。低音の弦の滔々と流れる様な分厚い調べ。濃いロマン性を表出。
ピアノの外山啓介は、瑞々しいピアノ。ラフマニノフの濃厚さ・力強さというより、むしろ歌う美しさを表出しようとしている様に聴こえた。弱音の美しさがそれを象徴している様。
勢いに任せるのでなく、一つ一つの音に意思を込めながら弾いていく。であるから、外向けに派手な演奏でなく、内省的なラフマニノフ。
それは、アンコールのベートーヴェンの悲愴ソナタの2楽章の演奏にも端的に表現されていた。淡々としているようで、流れる様な旋律の美しさ。そして、ベートーヴェンの旋律に込めた思いを確かめていくようなしっかりとした歩み。
後半はブラームス。既にOEKとLiveのCDを全曲完成するなど、金聖響が力を入れている作曲家の一人。
この日は通常のOEKよりも大型の編成とあって、より壮大なブラームスを聴かせてくれた。
1楽章序奏部はソステヌートの指示そのままに、実に堂々としたテンポ。主部からの展開も大きくテンポを動かすことなく、きつちりとした構成感とアンサンブル。OEK単独よりも編成が大きい分、アンサンブルの厚みを聴く事が出来る。
そして、堂々としたスケールの大きさは金聖響の一層の円熟を聴くよう。
2楽章は、以前の演奏よりも一層の優しさ、柔軟さを感じる。これも、円熟か。オーボエ、クラリネツト、フルート、ホルン等の管楽器の独奏、そして終結部のヤングのヴァイオリンの美しさも特筆。
古典派を演奏する際の、ピリオド奏法であるが故の、緊張感はあるものの、ややふくよかさに欠けるきらいがあった従来の金聖響の音楽と比較し、実に暖かさと、ブラームスらしい壮大なロマンを感じさせる演奏。
以前のブラームスと比較し一段とゆとりと大きさを感じさせる演奏となっていた。これは、単に編制の大小によるもののみでなく、明らかに金聖響の音楽の捉え方の変化によるものと思われる。
最近はロマン派からマーラー迄得意範囲を広めている金聖響の成長を聴いた演奏会。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第335回定期演奏会
2013年4月4日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ダグラス ボストック |
|
今期の定期もシーズン半ばを過ぎ、来期の定期の予定も早々と発表された。
来期は25周年ということで、記念の企画も色々と予定されている様で、興味ある所。
特にマイスターシリーズは来期はベートーヴェンの交響曲全曲演奏が企画されており、OEKの一つのエポックとなるシリーズとなることだろう。
さて、今月は地味と派手の2つの定期が続き面白い。
今日は、ボストックという指揮者で、OEKらしいこじんまりとした、しかし味わい深いプロ。
そして来週のフィルハーモニーシリーズは大阪フィルのメンバーを加えて金聖響指揮のの重厚壮大なプロ。
面白い組みあわせの今月の定期。
さて、今日のプログラム。前半がドヴォルザークの管楽セレナーデと弦楽セレナーデ、後半がモーツァルトの交響曲38番「プラハ」。
ドヴォルザークの2曲は、CDではカップリングされている事もある様だが、生の演奏会で同時に演奏される事は珍しいのではないか。どちらも、ドヴォルザークらしい名旋律に満ちた、隠れた名曲。
管楽セレナーデは「管楽」というものの、チェロとコントラバスが加わっている。
OEKの管のメンバーは健闘と言ってよい出来だが、全体的にはやや硬さが見られた。
この作品、指揮者が果たして必要な作品かということもあるが、奏者の自発性が損なわれ、のびのびとした愉悦にはやや欠けていた。もっと、各奏者が生き生きと躍動しても良いのにと、やや残念。
次の弦楽セレナーデ。出だしにややアンサンブルの硬さが有ったが、進むにつれOEKの弦の優秀さを聴く事が出来た。管セレと異なり、ここでは弦のアンサンブルが生き生きと躍動し、指揮者の細かいニュアンスの要求にも各奏者は的確に反応、気持ちの良い流れのある音楽が生まれていた。
後半はモーツァルトの交響曲38番「プラハ」。
前半は気付かなかったが、ボストックはモーツァルトでは、ピリオド奏法の音楽づくり。
ティンパニーも小型のバロックティンパニー。そのティンパニーが一楽章序奏部から炸裂。
ノンヴィブラートなので、全体として硬質の音楽の響き。モーツァルトには、もう少し暖かさがあってもと思わぬでもないが、これがこの指揮者の個性か。がっちりとした古典的構築感を再現した音楽。
長調の音楽でありながら、全体的に暗い色彩を漂わせた音楽。オペラ「ドンジョバンニ」に続く、濃い悲劇性を感じた。
アンコールにドヴォルザークの「チェコ組曲からポルカ」
途中からボストックはオーケストラに流れを委ね、指揮台を下り、オーケストラの後方に座り、音楽に身をゆだねていた。
拍手にも、「私でなく、オーケストラにどうぞ」とでもいう様に、オーケストラを引き立てていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第334回定期演奏会
2013年3月13日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ヴァイオリン ボリス・ベルキン
アビゲール・ヤング |
|
今回の定期はハップニングが続いた。
一つは、音楽会にあるまじき右翼の街宣車が音楽堂近くに陣取り、声高に演説をしていたこと。これについては、後述する。
もう一つは、井上マエストロがインフルエンザにかかり、一部プロが指揮者無しで演奏された事。
滅多にお目にかかれない春の珍事であった。
プログラムは前半が、モーツァルトの交響曲40番ト短調、2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ(独奏 ボリス・ベルキン、アビゲール・ヤング)、後半がプロコフィエフ、ヴァイオリン協奏曲第2番、古典交響曲。
プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第2番のみが、井上マエストロが指揮、後はアビゲール・ヤングのリーダーヴァイオリンで指揮者無しの演奏となった。指揮者の急病により、急遽代演を立てるという例はある様だが、今回は突然のことであったのか、又はオーケストラの実力を井上マエストロが信じての事であったのか、例のない指揮者なしでの演奏となったようだ。
プレトークで池辺晋一郎氏が述べていたが、小型の室内オーケストラとしいう特色が存分に生かされた今回の定期。
OEKの底力が試されたコンサートとなったが、その実力をOEKは遺憾なく発揮した。
モーツァルトの40番、さすがに細部の表情付けや音楽としての個性という点では、指揮者がいないのであるから不十分である事は仕方ないが、アンサンブルの精緻さ、細かいフレーズの受け渡し等においてほぼ完璧で、オーケストラとしての実力が相当なものである事が示された。
そして、今回驚いたのはフルート界のトップ工藤重典が客演としてフルートの主席に座っていた事。今年から、主席客演奏者としていくつかの演奏会に出演するとのことで、楽しみである。非常にふくよかな、輝きのあるフルートの音がオーケストラの中から浮かび上がり、なるほどさすがと思わされた。
次の 2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ、モーツァルトの作品としては地味で演奏される機会も少ないのでないかと思われる。私も初めて聴く作品。
ここでは、二人のヴァイオリニスト、ボリス・ベルキンとアビゲール・ヤングが、見事にオーケストラをリードし、指揮者がいない事を忘れさせる演奏となった。オーケストラが二人のヴァイオリンと一体化し、将に協奏交響曲の楽しさ。ベルキンのしっかりとしながら、どこか悠然と構えた風格のヴァイオリン、ヤングのそれに寄り添うかのような艶麗な響き、そして特筆はオーボエの独奏の素晴らしさ。更にカンタのチェロがからみ、室内オケの為のコンチェルトの様なモーツァルトの音楽の愉悦を聴かせてくれた。
後半はプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第2番。ここではマエストロ井上の登場。インフルエンザの不調を押して、この作品のリハーサルだけに集中しようとした執念を感じた。指揮者とは大変な職業である。
ベルキンのヴァイオリン。スケールの大きい、悠然と構えたプロコフィエフ。プロコフィエフの抒情性、シニカルな冷笑、茶目っけのある遊び、それら複雑な要素を的確に表現しながら、全体としては大きな風格と余裕を感じさせる演奏。先日、ロッテルダムフィル・セガン、庄司沙矢香のコンビで聴いたばかりだが、フレッシュ・誠実な庄司の演奏とは異なる、円熟の演奏。やはり長い年月が作り出した、造詣の深い音楽か。
井上・OEKもさすがのサポート。複雑なテクスチュアを、生き生きと彩りよく表現。ここでも工藤のフルートの響きが生きていた。そして、大太鼓、小太鼓、カスタネットを一人で操っていた打楽器奏者の奮闘も素晴らしい。
さすがロシア音楽を得意とする井上マエストロ、プロコフィエフの音楽の複雑なテクスチュアを読み解きながら、音楽の持つ人間の感情の複雑な要素を的確に表現していた。
最後はプロコフィエフの古典交響曲。故岩城監督の時代からOEKが得意にしていた作品だけに、指揮者がいなくても全く齟齬の無い演奏。古典的なスタイルを借りながら、プロコフィエフ独特の語法が生きる、一気呵成の様な魅力ある小交響曲。これだけ短い楽章の中に、よくもこれだけ魅力を盛り込んだものとプロコフィエフの天才に脱帽。
弦、管、それぞれ実力が試されるフレーズも沢山あるが、さすかOEK、表情豊かな演奏。
終曲のモルト・ヴィヴァーチェもまさに、その指示通りのスピードで乱れることなく駆け抜けていった。
この快演に聴衆も大拍手。アクシデントに立ち向かったオーケストラの熱演を讃えていた。
さて、最初に書いた、右翼の街宣車の件。
発端は報道によると、井上道義氏が北朝鮮を訪問した事。北朝鮮では地元のオーケストラとベートーヴェンの第9を演奏し、素晴らしい演奏を行い、ピョンヤンの聴衆から大きな賞賛を受けたとの事。
石川県議会の自民党議員が谷本知事に対しこの件を質問し、不適切でないかと質したとのこと。
文化と政治を混同した、本質的におかしい質問だが、この根底にはOEKに対する「税金の無駄遣い」というような思いが根っこにあるような気がする。質問の中で、「井上マエストロに年間700万円の報酬が支払われている。」ことをとりあげたり、OEKへの補助金を取り上げたりしていることからもそれが伺われる。
年間700万の報酬が高いか安いかの問題でいえば、月50万強の給与は、決して高くはなく、その経済的効果を推し測っても、さらに石川県への文化的貢献度からみても、むしろ低いくらいの水準ではなかろうか。
「文化には金がかかる」、常に言われる事だが、OEKが金沢・石川県に存在することの経済的効果も推し測られるべきだろう。広告宣伝費として考えるなら、莫大なものとなるだろう。
更には、OEKの存在する事による、北陸の文化的指数の高さ、石川県民、あるいは北陸の住民への貢献度、それらを総合的に考慮すれば、結論は自ずと明らかであろう。
そのあたりのことを考えない、無駄遣いとの指摘は、何か為にする悪意を感じる。
それが、井上道義氏の北朝鮮訪問という、攻撃の絶好の機会を捉えたとばかりに出てきたようだ。
どの国であれ、文化交流は重要であり、その事が政治をも動かしていく事もありうる。北朝鮮に関して言えば、数年前にはマゼール・NYフィルが訪問し大きな話題となった事もあった。
今回、井上道義氏はベートーヴェンの第9を持ってピョンヤンに行った。ベルリンの壁が崩壊した際の。バーンスタインの壁の前での第9の演奏を思い起こす。「総ての世界の人間よ抱き合え」と訴えかけるベートーヴェンの精神は北朝鮮の聴衆にも大きな感動をもたらしたことだろう。それが文化交流であると思うのだが。
そして、この様なことが話題となり、街宣車まで出てくる異様な事態に、この国の現在に心寂しい不安を感じる。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第332回定期演奏会
2013年3月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 エンリコ・オノフリ
リコーダー 濱田 芳通
オーボエ 水谷 元
トランペット ガブリエリ・カッソーリ
チェンバロ 桒形 亜樹子 |
|
今回の定期は、オノフリは勿論だが、独奏者にバロックの実力奏者を並べた豪華な顔合わせ。
この様なメンバーでバツハ、ヴィヴァルディを聴けるチャンスは滅多にないだろう。
という期待を裏切らない、格調の高いバロックを聴けた時間だった。
前半が、J.S.バッハで、ブランデンブルグ協奏曲3番、2番、真ん中にヴァイオリン協奏曲BWV1056、後半が、ヴィヴァルディ「調和の幻想より11番」、そしてJ.S.バッハ「管弦楽組曲3番」というプロ
オノフリは、鬼才とか、超絶の技巧、とか呼ばれて、やや異端のバロック奏者というイメージを持たせがちだが、この日の演奏を聴くと、とんでもない、実に正統的なバロック奏者という印象。
むしろ、イムジチ等で聴く、豪華で華麗なバロックとは一線を画し、バロック本来の素朴な生命力とも言える物を生き生きと再現している、本来のバロックの再現者とも言えるように感じた。
最初のブランデンブルグ協奏曲3番は10名の奏者による簡素な編成により、全員が立っての演奏。
オノフリは第一ヴァイオリンのパートを弾きながらのリード。やや早めのテンポの推進力に満ちた演奏。
オノフリのヴァイオリンのヴィヴィツトな響きが際だち、OEKの奏者はモダン楽器の為、音色が柔らかくもう一つ調和がとれないのがもどかしい。やはり、バロック楽器の響きと、モダン楽器の響きは相当異なる印象。
次のヴァイオリン協奏曲。通常はチェンバロ協奏曲5番として演奏されるが、原曲はヴァイオリン協奏曲とのことで、この日の演奏は本来の形を復元しての演奏。
編成はやや大きくなり、オノフリは独奏者としての弾き振り。オノフリの音色は素朴だが、新鮮で生々しい。
古楽器なので当然ノンビブラートだが、強靭な生命力を感じさせる。バロックの原点を聴く様で刺激的。
又、チェンバロが実に良い。それ程音量のある楽器で無いのだが、しっかりとアンサンブルの中で存在感を示し、バロックらしい風格を漂わせる。
OEKのアンサンブルも最良なのだが、やはりヴァイオリンの刺激的な音色に比較すると、おとなしい。
これは、モダン楽器の限界かもしれない。
前半最後のブランデンブルグ協奏曲3番では独奏ヴァイオリンにリコーダー、オーボエ、トランペットが加わり、生き生きとした新鮮な響き。
リコーダー、オーボエの活躍も見事だが、ここでは何といってもトランペット。ナチュラルトランペットの高い、囀りの様な音色。超絶技巧と思えるが、ガブリエリ・カッソーリは何事もないという風に軽々と吹きこなす。
ヴァイオリン、リコーダー、オーボエはそれに負けじとばかり、生き生きと弾き、吹きまくる。バロックの音楽的興奮が沸騰するような鮮やかさ。バロックの華やかさを祝典的というような形容をすることがあるが、もっと原始的、本能的な音楽の興奮を感じる。
後半の最初はヴィウァルディの「調和の霊感より11番」
ここでは、オノフリの独奏に、OEKの江原千絵のヴァイオリンとルドヴィート・カンタのチェロが独奏者として加わる。
ここでも、オノフリは輪郭のはっきりとした音楽づくり。各フレーズが強く、くっきりと響くため、力強いヴィヴァルディー。
この後のバッハの管弦楽組曲3番でもそうだが、オノフリは作品を表面的に美しく演奏しようということは全くない。その音楽のもっと奥深い所にある根源的な美を表現しようとしているよう。。
プログラム最後はバッハの管弦楽組曲第3番。編成はトランペットが3本になるなど、この日最大の編成。
このバッハも壮麗・壮大というものと対極にある、アグレッシブでスリムな演奏。
有名なアリアも、これほど厳しく、緊張感に満ちた演奏は聴いた事が無い。この楽章が、レクィエムの様に演奏される事が多いため、ついその様な先入観を持ちがちだが、本来は古典的緊張感と形式感に支えられた静謐な音楽である事を再認識させられた。
各舞曲も生き生きとした躍動感と緊張に溢れていた。
従来解釈されていたバロックとは異なり、音楽の虚飾を排し、素のままの音楽が聳えている様な印象。そこに、バロック音楽の本来の美しさが有るのだということを演奏で認識させてくれた様な、オノフリの音楽だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第332回定期演奏会
2013年2月26日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 マルク・ミンコフスキー
管弦楽 レ・ミュジシャン・デュ・ルーブル・グルノーブル |
|
1月のニューイヤーコンサトから暫く間合いのあいた定期は、OEKの定期でありながら他のオーケストラの出演の変則的な定期。時々この様な定期が挟まる事が有る。他のオーケストラを聴けるというチャンスとも言えるが、OEK定期で、どうしてという異論も出そうでもある。
さて、この日は昨年OEKに出演、2009年にはこのレ・ミュジシャン・デュ・ルーブル・グルノーブルを率いて金沢で演奏会を開いたマルク・ミンコフスキーの登場。
2009年のハイドン、モーツァルトの新鮮で刺激的な演奏が蘇る。
この日のプログラムは「2つの未完成」のテーマで、シューベルトの交響曲第8番「未完成」とモーツァルトのミサ曲ハ短調というもの。ユニークなプログラムである。
この日は最初にグルックの歌劇「アウリスのイフゲニア」序曲が追加された。2009年の演奏会でも同様のハップニングがあったのを思いだいすが、ミンコフスキーらしい即興性である。
この作品、久しぶりに聴いたが、古典的なドラマテイツクさに溢れた良い作品。演奏もスケールがあり、そして美しい。古典的な端正さがありながら、劇的な厚さも兼ね備えた名演。テンポが実に堂々としていて、悠揚迫らざるという風格。
このオーケストラのアンサンブルの見事さ。ピリオド楽器の楽団なので、当然ノンビブラートなのであるが、それが貧弱でなく、ふくよかで分厚い響きとなるのが凄い。木管も金管もバルブの極端に少ない古楽器であるので、相当な技術的な難度が有るはずだが、少しもそれを感じさせない。古楽器独特の柔らかい音色。
楽器配置もユニークで、正面にコンドラバス、左にホルンと木管、右にトランペット、トロンボーンを配置、弦は当然対向配置。
次のシューベルト。この作品、有名な作品であるが故に、細かい細工を施したくなるような演奏が多いが、ミンコフスキーはその様な小細工は何もしない。それでいて、シューベルト独特の素朴な美しさが溢れだしている。
1楽章の劇的な展開、2楽章の吶々とした語り口。そしてバランスの良い磨き抜かれたアンサンブル。ホルンの柔らかい超高音の響き、クラリネット、オーボエの木管特有のふくよかな響き。
シューベルト本来の素朴な美しさが輝いている演奏。
次にアンコールにはびっくり。演奏会最後のアンコールがあたりまえ。ソリストを除いて、オーケストラが途中でアンコールというのは、初めての経験。これも、型に捉われないコンサートを目指す、ミンコフスキーの姿勢か。
先回の来日公演では、東京での演奏会のアンコールが1時間続いたという伝説的事件があったが、その点では将に鬼才である。
そのアンコールはシューベルトの3番からのフィナーレ。これも、素朴な喜びの歌が溢れる演奏。アンサンブルの乱れが全くないので、早いパッセージが実に心地よく流れていく。初期のシューベルトの素直な音楽性が的確に表現された演奏。2番などこのコンビで聴いてみたいという欲求がふくらむ。
休憩を挟んで、モーツァルトのミサ曲ハ短調。
ここでも、ミンコフスキーの工夫が光る。
まず、合唱団がいない。ソロと合唱部分を10人の独唱者がつとめる。Sop4、Art2、Br2、Bs2の合計10名。
この独唱者達が凄い。まるで合唱団の声量。舞台を見ずに聴いたら、合唱団がいるものと錯覚するのでなかろうか。
そして、各章で、あるいは章の途中でも、目まぐるしく配置が変わる。
最初はSp,Ar,Br,Bsの配置だが、時には対向配置になったり、順序が変わったりする。そして、その中から独唱部分は、中央に配置された台の上に独唱者が出て歌う。独唱者も決まっておらず、部分部分で異なる独唱者が歌う。
楽器の配置もユニーク。弦は対向配置だが、前半同様コントラバスは正面に配置。管楽器は弦楽器を挟み左にホルン、オーボエ、クラリネット、フルート、右側にトロンボーン、トランペット。テインパニーとオルガンも右側。
この作品は短調ではあるが、全体の雰囲気は祝典的で典雅。しかし、やはりモーツァルト独特の憂いも満ちている。
ミンコフスキーは実に淡々と、しかし古典的な造形をがっちりと作り出し、そして豊かな厚い響きでこの作品を彩る。
細部までくっきりと描きこんでいるのだが、全体のスケールは雄大。そして生々しいモーツァルトの声も聴こえるようでさえある。この意味ではオペラ的でさえある。(グローリアのある部分は魔笛のアリアを彷彿とさせる。)
優しくではなく、大きく激しくもそして生々しくという、ミンコフスキーの演奏はこの作品の神髄を聴かせてくれた。
アンコールにクレドの前半。これも、一層激しい音楽であった。
ミンコフスキーを聴くのはこれで3度目だが、どのコンサートでも新しい刺激を与えてくれる希有な鬼才である。
そして、ミンコフスキーが育てたレ・ミュジシャン・デュ・ルーブル・グルノーブルという彼の素晴らしい楽器。
次も是非金沢に来て欲しい。 |
|
|
|
|
|
|
|
NHK交響楽団演奏会
2013年 2月3日 オーバードホール
指揮 下野 竜也
ピアノ インゴルフ・ヴンダー |
|
2009年以来4年ぶりのN響の富山公演。
前回の2009年、前々回の2005年と外国人指揮者であったが、今回は日本の注目の中堅、下野竜也の登場。
OEKも何回か指揮し、その中でも2007年の故岩城宏之の代演で指揮したベートーヴェンが印象に残っている。
その下野ももう40歳を過ぎ、堂々たる中堅としての活躍は目を見張るものがある。
今日のプログラムは、前半が2010年ショパンコンクール2位(1位があのアヴデーエワ)のインゴルフ・ブンダーをソリストにショパンのピアノ協奏曲第1番、後半がブラームスの交響曲第2番。
以前の演奏の印象でもそうであったが、下野竜也は誠実で衒いの無い演奏。以前はそれ故にやや物足りない部分もあったが、現在はその誠実さが堂々たるスケールに変化し、骨太で骨格のしっかりとした演奏を聴かせてくれた。
最近は、非常に凝ったプログラムで話題をさらっているが、(OEKでも、シェーンベルク、ウェーベルンとズッペの序曲集というプロがあった。) 今日は古典的でオーソドックスなプログラムでその実力を聴かせてくれた。
最初のショパン、編成がこの協奏曲にしては大きいコントラバス6本の14型。
出だしの堂々たる序奏から、底力のある分厚い響き。そして表情豊かな木管。
長い序奏が終わり、ピアノの入り。ヴンダーはそんなオーケストラの勢いを抑える様に、淡々とした入り。
非常に詩的で繊細なピアノ。主題の旋律の歌わせ方の独特な節回し。この作品の持つ、せつないセンチメンタルな面を色濃く現わした演奏。音の一つ一つが良く歌い、独特のタッチの柔らかさ。音の粒が揃っている。
2楽章も全体の流れが自然で、淡々としている様でありながら、その実濃いロマンチシズム。ショパンの旋律が生々しく、しかし自然に息づく。
細部でかなりの表情付けをしているのだが、それが嫌みでなく自然。これは感性の素晴らしさ。
ショパンコンクールはやはり逸材を次々と生み出す場と再認識。アブデーエワとヴンダー、個性の違いはあるが、それぞれ自分の表現意欲を強く持った個性的なピアニスト。これからが楽しみだ。
後半はブラームスの2番。一昨日セガンの4番を聴いたばかりだが、この二人の指揮者の音楽の性格の相違にやはり驚く。
自らの個性を強烈に押し出そうとするセガン、自然体で、余計な思い入れはせず、書かれた楽譜の内容を忠実に描き出そうとする下野。
同じブラームスでも、再現者によってこれほど色合いが異なってくる。これが、音楽再現の不思議さであり、面白さでもある。
下野のブラームスからは、ブラームス独特の骨太で分厚い響き、ほの暗い色彩感、そしてうねるような高揚感を聴く事が出来る。
第1楽章の主題が執拗に繰り返され、それが強烈な叫びとなって高揚する部分の音楽のうねるような高揚感。
第2楽章の思索にふけるかの様な静けさ、3楽章の優しい舞曲、しかしそれらが4楽章の歓喜の爆発につながる前奏である事を聴きとる事が出来る。個々の楽章がそれぞれのドラマを持ちながら、終曲にいたる音楽の連続した流れがあることが明確。
個々の部分を丁寧に描き出しながら、それが全体の大きな流れに収束していく。滔々たる流れの様で雄大なスケール。
ブラームスの生の声が聴こえる演奏と言ってよいだろう。
やはり私はセガンのアプローチよりも、下野のそれが好きである。
アンコールのバッハのアリアの厚く柔らかい弦の響きは、さすがN響と認識させてくれた。
下野竜也、これから益々楽しみな指揮者。N響を下野竜也の指揮で聴けた事は幸せ。
前回書いたオーケストラの登場の仕方、N響も定時にまとまって団員が出てくる方法。最近は、これが主流なのだろう。 |
|
|
|
|
|
|
|
ロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団演奏会
2013年2月1日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ヤニック・ネゼ=セガン
ヴァイオリン 庄司沙矢香 |
|
毎年この時期に海外のオーケストラを招へいする東芝グランドコンサート、今年はセガン指揮のロッテルダムフィルの来日公演。
コンセルトヘボウに比較すると日本では知名度がいま一つの感が有るロッテルダムフィルだが、さすがオランダの名オーケストラ、その実力を十分に聴かせてくれた。
指揮は俊英セガン、ヴァイオリンがこれも今盛りの庄司沙矢香という、興味ある顔合わせ。
プログラムは前半が、シューマン「ゲノフェーファ」序曲、プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲、後半がブラームスの交響曲第4番。
セガンは38歳の若さ。今年はフィラディルフィア管弦楽団の音楽監督に就任するという注目の若手。
シューマンの「ゲノフェーファ」序曲は演奏会で聴くのは珍しい作品。
シューマンらしい鬱々たる情熱が溢れている作品。セガンは厚いハーモニーの中に旋律線をくっきりと浮き立たせ、明快にこの作品を演奏。シューマンというと、ドロドロとした情念を聴かせる演奏も多いが、むしろくっきり造形が浮き出て、なお且つドラマティツクな語り口を見事に聴かせてくれた。そして、特筆はオーケストラの巧さ。
指揮者の要求にピシッと合わせ、弦も管も雄弁で鮮やか。柔らかい響きと、低音の厚みが魅力的。そして、きちっとした引き締まったアンサンブル。魅力的なオーケストラである。
この日の配置は対向配置だが、コントラバスを8本舞台奥正面に配置。これがかなり低音の厚さに貢献している。
プロコフィエフでは、オーケストラと庄司沙矢香がぴったりと組み合い、素晴らしい名演。
庄司のヴァイオリンは益々その完成度を高めている。いくぶん抑え気味の、だから緊張感に満ちているのだが、ピシッとしながら、透徹した意思のはっきりした演奏。音に演奏者の魂を感じる。
美しさに溢れる第2楽章も、そっけないほど素朴に弾くのだが、それが一層プロコフィエフの旋律の美しさを際立出せる。オーケストラも庄司とすっかり溶け合い、同質の響き。フロコフィエフ独特の複雑なテクスチュアがくつきりと浮かび上がり、その中でヴァイオリンが生き生きと躍動する。セガンのサポートの見事さ。この作品の面白さを最大限聴かせてくれた。
休憩を挟んで、ブラームスの4番。
ここでは、セガンはかなり大胆な解釈。1楽章の遅めのテンポでの濃厚な味付け。3楽章から4楽章へのアタッカの様な休みの無い入り。テンポも微妙に揺れ動く。全体にセガンが聴かせようとする意図が明確。
ブラームスが、こんなに濃いロマン性を持っていたかと、少々異質さを感じてしまう様な演奏。
色濃いブラームスだが、果たして?との思いもある。
このあたり俊英であることは間違いないが、作曲家をどの様に再現するかという、基本的な部分の違和感を覚えた。
しかし、オーケストラを存分にドライブする力量はたいしたもの。そして、それに応えるオーケストラの実力も凄い。
別の日のプロ、ラフマニノフの交響曲の方が、この指揮者の適性に合っているかも。
この日面白かったのはオーケストラ団員の登場の仕方。
最近は定時直前に一斉に団員が登場、拍手を受けるのが普通となっているが、このオケは三々五々と舞台に団員が集まる。そして、拍手を受けるのは指揮者と同時。
昔はこれが普通であったので、最近の方法は何か違和感を感じていたので、何かほっとした感じ。
私がN響の定期に通っていた頃は、もっとも50年ほど前だが、この様な登場の仕方であったが、最近はどうなのか、明日のN響の富山公演で確認したいものだ。 |
|
|
|
|
|
|
|
二つのニューイャーコンサート 2013
オーケストラ・アンサンブル金沢第331回定期演奏会
ソプラノ 中島 彰子
テノール 吉田 浩之
ヴァイオリン サイモン・ブレンデス
2013年1月7日 石川県立音楽堂コンサートホール
ニューイャーコンサート2013
ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団演奏会
指揮 ヨハネス・ヴィルトナー |
|
今年のOEKのニューイャーコンサート。
昨年は、山田和樹とモナ・飛鳥オットーの二人の若手を迎えてのがっちりとしたブログラムのニューイヤーだったが、今年はガラコンサート風の楽しいプログラム。
というものの、ニューイヤー定番のシュトラウス一家中心のプログラムとは異なる、井上マエストロ風の一ひねりある、クセのあるプログラム
前半がゴルンゴルドというレアな作曲家を中心としたプログラム。後半がウィーン音楽だが、ここでも一ひねりがある。
独唱にウィーンフォルクスオーパーの専属歌手だった中島彰子、テノールの吉田浩之を迎えてのニューイャー。
ゴルンゴルドはウィーンの作曲家であったが、ユダヤ系であつたためナチスに追われ、アメリカへ亡命、アメリカでは映画音楽作曲家として活躍したという作曲家。ライナーノートによると、井上マエストロは日本でのゴルンゴルド紹介の推進者とのこと。
コンサートは井上マエストロの軽妙な語りを交えて進められていった。
ゴルンゴルドの作風、やはりウィーンの人という印象。世紀末の濃厚なロマンを漂わせ、それがアメリカのゴージャスな装いを纏っている様な不思議な音楽。ヴァイリオリン協奏曲の2番の2楽章など将に爛熟の極み。前後の楽章も聴いてみたい誘惑。歌劇「死の都」からのソプラノとテノールによるアリアも、ミュージカルのアリアの様な甘くせつない雰囲気。
一部最後の「シュトラウシァーナ」はゴルンゴルドの望郷の思いか。
休憩後は、本場ウィーンの音楽。
この日の井上マエストロ・OEKは一段と好調の様で、数年前に同じウィーンものを聴いた時のややドライで素っ気ない印象と異なり、歌うところはたっぷりと歌い、華やかに盛り上がる部分は思い切り歌い上げるという、ウィーン音楽の楽しさを存分に聴かせてくれた。
後半最初のツェラーのオペラ「小鳥売り」から「私は郵便配達のクリスタル」でのコミカルな歌、レハールのメリーウイドウからの二人の有名なアリアなど聴かせどころ満載。
中島彰子の豊かで暖かい声と、巧みな演技力、吉田浩之のテノール独特の輝かしい高音も特筆。
ズッペの「詩人と農夫」序曲も、緩急自在なマエストロの指揮にOEKは見事に従い、指揮者とオーケストラの呼吸ぴったりの白熱した演奏となっていた。
その他に、シュトルツ、ジーツィンスキー(「ウィーンわが夢の街」)など多彩、J・シュトラウスは二世のポルカ「狩り」とワルツ「南国のバラ」の2曲のみ。
有名なズッペ、ボッカチオ「恋は優し野辺の花よ」は、浅草オペラ版の日本語歌詞で歌われた。
アンコール(カールマンの「チャルダーシュの女王から?)では、井上マエストロが中島彰子とダンスを踊り始め、指揮を吉田浩之がするというパフォーマンスも。
最後は昨年38歳での引退を発表した石川の英雄松井秀喜への応援歌「栄光の道」を中島と吉田が歌い、聴衆が手拍子という盛り上がで締めくくり。お決まりの「ラディツキーマーチ」よりOEKらしいニューイヤーコンサートの締めくくり。
年初の楽しい音楽のひと夜。
富山オーバードホールでのニューイヤーコンサート
久しぶりにウィーンからの恒例のシュトラウスオーケストラの富山への来演ということで、出かける。
若い頃の一時、シュトラウス一家を中心としたウィーン音楽を随分溺愛し聴いたものだ。それが高じてウィーンにも出かけ、ウィーンフィルのコンサートは残念ながら聴けなかったが、トンキュンストラー管弦楽団のジルベスターコンサートをムジークフェラインで聴いたり、「チャルーダッシュの女王」をフォルクスオーパーで聴いたりの、懐かしい思い出がウィーンのオーケストラを聴くたびに蘇る。
最近は、正月にウィーンからの様々なオーケストラが出稼ぎ公演の如く日本へやって来る様になり、その中には随分いい加減な即席オーケストラもあるようだが、今回のオーケストラはその歴史から見ても、まともなオケと見た。
演奏も、決して巧いというものでは無いが、素朴なアンサンブル、そしてなによりも独特のウィーン節、そして盛り上げ方を心得た演奏スタイルなど、ウィーン音楽の楽しさを十分に味あわさせてくれた。
指揮者はヴィルトナー、かつてはウィーンフィルのヴァイオリンパートを弾いていたとのこと。
日本語を交えた軽妙なトークで聴く人を引き付けながら、楽しいコンサートを作り上げていた。
プログラムは有名なポルカ、ワルツばかりでなく、ヨーゼフのポルカ「前進」、ワルツ「ディナミーデン」、ヨハン2世の「仮面舞踏会カドリーユ」など、珍しいものも聴かせてくれた。
ヨーゼフのワルツ「ディナミーデン」は、「天体の音楽」にも雰囲気が似た、ヨーゼフらしいしっとりとした美しさを持つワルツ。
最後に「美しき青きドナウ」を持ってきて、アンコール最後は「ラディツキーマーチ」で締めくくるというのは定番。
ウィーンフィルの気品と風格のある演奏と比べると、ずっと素朴で親しみやすいウィーンナワルツとポルカでもある。
正月の日本で、この様にウィーン音楽が盛んに演奏されるのは、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートの影響もあろうが、ウィーン音楽の明るく楽しい雰囲気が正月のうきうきした気分とぴったり合うことにもよるのだろう。
ただ、こう毎年のようにとなると、マンネリのきらいもないわけではない。
OEKのニューイャーでも、そのあたりのマンネリをどのように払拭していくか苦労の跡が見えるが、ニャーイャーコンサートとは難しいものでもある。 |
|
|
|
|
|
|
|
辻井 伸行 日本ツァー 2012~3年
2012年 12月14日 オーバードホール |
|
昨週に続いて、現在話題のピアニストの登場。
大きいオーバードホールの座席が即日完売に近い状況となるという。富山でも珍しい現象の出現。
私も5階の最後部の座席をようやく確保できた状況。
何か、音楽の内容以外の部分で動いているような不思議な現象。
この日の演奏会は、その内容においても優れたものであったことは疑いがないが、例えば優れた演奏家が登場する入善コスモホール(座席数はオーバードホールの1/4程度)では、満席になることすら珍しいという、不思議な現象。
これは、どの様に解釈したら良いのだろうか?
さて、この日の演奏。
プログラムは前半がドビュッシー、後半がショパン。
ドビュッシーは、「2つのアラベスク」「ベルガマスク組曲」「版画」「喜びの島」、ショパンは「華麗なる大円舞曲(ワルツ第一番)、スケルツォ第2番、幻想ポロネーズ、英雄ポロネーズというもの。
11月から翌年2月まで、日本列島縦断のコンサートで、計28回の演奏会、同一プログラムでのコンサート。
このピアニストの真価を聴いた気がした。
前半のドヴュッシー。誰のものでもない彼の世界。分厚い音で、油彩的に響く独特のドヴュツシー。
後半のショパン。やはり誰のものでもない辻井の歌の世界。
この人の演奏には、音楽を自分のものとして歌い、鳴り響かせる個性が際立つ。
これは、彼のハンディーである盲目という世界が、ハンディでなく長所として作用していることを強く感じる。
彼の目には、楽譜が見えない。その見えないというハンディの代わりに、聴き、そしてそれを頭の中で楽譜に置き換え、自分の音楽として表現するという、類まれな才能を彼は与えられている。そして表現できるだけの驚異的なテクニツクを持っている。
これは、誤解を恐れずに表現すると、「神から与えられた才能」とも感じてしまう。
かつて、リパッティーに与えられた「彼は神から選ばれた楽器である。」ということを想起してしまう程。
その意味で彼のハンディは個性となりきっている。
多くの演奏家が、楽譜から何を表現しようかと苦労する作業を、彼は何とも直感的に成し遂げてしまう。
前半のドヴュッシーの最後の「喜びの島」の豊かで、喜びに満ちた歌。
通常ドビュツシーというと、フランス的エスプリと、霧に包まれた様な曖昧模糊とした色彩感を想像し、多くのピアニストはその様に演奏する。しかし辻井のドビュツシーは、音も明確に響き輝かしく、歌もはっきりとしていいる。それでいて、ドヴュッシーの明るい色彩感が音によってきちんと表現されている。ドビュツシーを自分の声で歌おうとする瑞々しさ。それは、一種の即興性であろうが、彼の音楽への深い洞察力による即興性でもある。
ショパンも輝かしく、そして優しく鳴り響く。
ワルツの独特なリズム、スケルツォのドラマ、ポロネーズのスケールの大きさと抒情性。
アンコールのリスト「カンパネラ」の輝かしい歌。
そして、自作の「それでも生きてゆく」「花は咲く」の素朴でありながら、心に染み入る彼の歌。
これらの要素総てで彼の音楽の世界が作り上げられている。
完成された大家のピアノではない。それが又現在の辻井の素晴らしさ。
ひたむきに表現しようとする真摯な音楽への傾倒。
そこには、音楽を聴く喜びを分かち合いたいという彼の聴衆に対する強烈なアピールを聴く様でさえある。
これからの彼の音楽が益々楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
イングリット・フジコ・ヘミング&ラトビア国立交響楽団
2012年12月 7日 オーバードホール
ピアノ イングリット・フジコ・ヘミング
指揮 ロベルタス・シャーヴェニカス |
|
1999年にマスコミで不遇な生涯が紹介され、話題となり、それがきっかけとなり大ブレークを起こしたピアニスト、イングリット・フジコ・ヘミング。それ以来、度々舞台に立っているようである。
今回はラトビア国立交響楽団とのショパンのピアノ協奏曲第一番。
どうも、マスコミが作り出した伝説に載せられて、音楽以外の要素で話題をさらったピアニストという捉え方は悪いかもしれないが、演奏を聴く限りその域を脱していない様に思える。
確かに再デビューの頃のリストの演奏は、輝きが聴けたが、現在のフジコ・ヘミングは残念ながらその残像によりかかっているのみの感が有る。
独りよがりの解釈、過度なセンチメンタリズム。技術的にも、音楽的にも、現在のその姿は残念な思いがする。
恐らく、音楽プロモーションが作り出した伝説の上で、舞台に立っているのだろうが、この様なプロモーションのあり方も問題がある。
この様な取り上げ方は、フジコ・ヘミングに対しても気の毒であり、失礼でさえあると思うが。
シャーヴェニカス指揮のラトビア国立交響楽団。ベートーヴェンのエグモント序曲とブラームスの交響曲第一番。
こちらも、かなり荒っぽい演奏。
エグモント序曲はがっちりとした構成で、なかなか聴かせたが、ブラームスは単調。
早いテンポで押しまくった様な演奏だが、細部の磨きあげが粗雑。序奏部は実に早いテンポで、このまますっきりとした演奏になるのかと思うと、主部に入り急に勇ましくなる。
指揮も単調だが、オーケストラもかなり荒っぽい。
残念ながら、比較的高い料金のコンサートだが、内容が伴わない。
こんな演奏会も有るものだという悪い見本。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第330回定期演奏会
ビゼー作曲 歌劇「カルメン」 Alkor版 全4幕
2012年11月21日 石川県立音楽堂コンサートホール
カルメン リナ・シャハム
ドン・ホセ ロゼリオ・デ・スピナ
エスカミーリョ ジョジア・ブルーム
ミカエラ ジョシュア・ブルーム
スニガ 小川 里美
モラレス 三塚 至
ダンカイロ 晴 雅彦
フラキスータ 鷲尾 麻衣
メルセデス 鳥木 弥生
レメンタード ジョン・健・ヌッツオ
管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢
合唱 OEKカルメン特別合唱団
児童合唱 OEKエンジェルコーラス
ダンス Dance Sanga、OEKカルメン特別バレエ
演出 茂山あきら
台本 小宮 正安
指揮 佐藤 正浩 |
|
今回のマイスターシリーズ定期は、コンサートホールでのオペラ「カルメン」
コンサートホール形式でのオペラは過去2007年に2回、定期演奏会で催されている。
オーケストラの定期でオペラを取り上げるのは珍しい試みと思うが、地方都市で中々本格的なオペラに接する事が難しい中で、低料金で、その機会を得られる事は有り難い。
今回は、金沢、福井、富山県魚津、東京、宮城県名取と5都市で開催され、5都市の共同制作公演となつている。
経費の面でも大変な公演であったと思われるが、私たち音楽愛好家にとっては有り難い試みである。
指揮がどの様な事情か、石川、福井公演が佐藤正浩、その他が井上道義となっており、名取公演はオーケストラが仙台フィルが担当となっている。
当初、カルメン役で出演予定スカラ座の歌姫ミリヤーナ・ニコリッチが妊娠のため、リナ・シャハムが代演となったが、素晴らしい歌手で、見事に代演の役割を果たしていた。
この日の演出は狂言師の茂山あきら、そして台本を横浜国大准教授の小宮 正安が担当。
さて、この日の公演、通常のビセー「カルメン」と大きく異なる点が2つあった。
一つは、通常使われている版でなく、原典版のAlcor版が使われていること。
通常の版はビゼーの死後、友人のギローが改訂した版によって演じられているとのこと。
大きな相違は、改訂版がセリフの部分を歌のレシタティーボに置き換えていること。原典版では、セリフの部分も多く、劇の進行に緊迫感が感じられる。初演の失敗の後ビゼーは急死し、再演に当たり、ギローが当時流行のグランドオペラ風に改訂したということ。
第2に台本の小宮氏が舞台をスペインのセルビアから、19世紀末のフィリピン・マニラに移したこと。
これについては、小宮氏がその理由をライナーノートで詳述している。
しかし、正直、これには違和感。
いろいろ理由を述べておられるが、舞台を移した必然性が感じられない。
又舞台を移した事により、闘牛士のエスカミーリョが遠くフィリピンまで興業のために訪れたという無理な設定が生まれたり、フィリピンでスペイン風な音楽が流れたりする違和感があり、ドラマの必然性としての変更が感じられない。
茂山あきらの演出が抽象的な舞台装置に現れている通り、国籍をそれ程意識していないことと合わせてみると、特に舞台の国籍を変更する必然性があったのだろうか?
さて、その他にも今回は特筆すべき演出が多くあった。
一つは合唱の存在。普通は合唱団が演技をしながら歌うのだが、今回は合唱団は舞台を半円形に囲んだアリーナ風の席に座ったままで歌う。そして、バレエ団が舞台で、合唱に合わせて象徴的に舞う。
これは、合唱団がプロでなく、地元の合唱団(児童合唱ともども大変な熱演)であることも考慮しての演出とも考えられるが、バレエが象徴的に音楽の内容を表現しており面白い試み。
更に、暗く重い運命のテーマに合わせて、このテーマが現われる度に女性バレリーナが象徴的に舞う演出。
聴覚と視覚に訴え、運命を象徴する方法は、このオペラを見る者により深くこのオペラのテーマを植え付ける。
非常に効果的な演出。
この様に抽象的でありながら、このオペラのテーマを明確に表現する方法は、狂言師ならではの演出。
舞台装置も極めてシンプルでありながら、見る者の想像性を限りなく広げ効果的。これも、能・狂言の世界と通じる事。
半円形に広がるアリーナの後ろには、テント風の布がかけられており、第3幕の岩山の場面では、この装置が暗い中に照明で浮き上がり、連なる山の様に見えたのも印象的。
第4幕の闘牛場の中と外の装置の入れ替えも、数人の人間が布を持ち囲みをつくり表現するなど、工夫が凝らされている。
この第4幕では、通常大きい舞台では闘牛場が遠くにあり、遠くから闘牛士の歌と歓声が聴こえてくるという演出が多いが、コンサートホールではその様な演出は難しく、簡素な舞台装置の使用により、闘牛場の中と外のドラマを描き分けた工夫は秀逸。
又中央に、大きな塔のような字幕装置があり、時には大きな墓石の様にも見え、暗示的。最後のドン・ホセがカルメンを刺殺する場面では、この塔の最上部が赤く光る。
この様に、演出は舞台装置を含め、さすが狂言師と思わせる象徴的な手法が多く見られ刺激的。
そして、原典を使用することにより、劇の緊迫感も増し、このオペラの真のテーマ、「運命から逃れない人間、死によつてのみ得られる自由」が浮かび上がる。
歌手も粒が揃っている。主役のカルメン役のリナ・シャハムは自由奔放でありながら、暗い影を宿すカルメンを好演。アルトの艶やかな伸びのある声、声量も十分。
ドン・ホセ役のロゼリオ・デ・スピナの輝かしいテノール、エスカミーリョ役のジョジア・ブルームの堂々としたバリトン、そして一番輝いていたのがミカエラ役の小川里美。柔らかく、温かみのあるソプラノでミカエラのしっとりとした情感にぴったり。一番多くの拍手を得ていたようだ。
佐藤正浩の指揮もやや早めのテンポで劇の緊張感を高めていた。
OEKは熱演であったが、やはりオペラホールのオーケストラとしての経験はまだまだの様で、ドラマのメリハリがやや単調で、ドラマに音楽が乗り切っていない感もあり。
先日のソフィアのオペラ座のオーケストラなど、オケとしての技術はともかくとして、オペラを知り尽くした流れがあり、オケ自身がオペラをリードする雄弁さがあつた。このあたりは、伝統の差であり、いたしかたないところだろう。
全体として非常に刺激的な舞台で、コンサートホールのオペラとしての新しい試みも随所に見られ、後まで印象に残る公演となることだろう。 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフィア国立歌劇場 2012年日本公演
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスチカーナ」
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」
2012年11月7日 オーバードホール
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスチカーナ」
サン・トゥッツア ラドスティーナ・ニコラエヴァ
トゥリッドゥ ダニエル・ダミャノフ
ルチア ルミャーナ・ペトロヴァ
アルフィオ ニコラ・ミハイロヴィッチ
ローラ ブラゴヴェスタ・メッキ=ツヴェトコヴァ
指揮:アレッサンドロ・サンジョルジ
管弦楽:ソフィア国立歌劇場管弦楽団
合唱:ソフィア国立歌劇場合唱団
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」
ジャンニ・スキッキ ビセル・ゲオルギエフ
ラウレッタ 小林. 沙羅
ツィータ ツヴェタ・サランヴェリエヴァ
リヌッチョ キリル・シャルバノフ
指揮:ヴエリザル・ゲンチェフ
管弦楽:ソフィア国立歌劇場管弦楽団 |
|
2009年以降になると思うが、オーバードホールで毎年秋行われている海外歌劇場の引っ越し公演。
今回は、ブルガリアのソフィア国立歌劇場の5回目の来日公演。
地方では中々本格的なオペラを見る機会が少ないので、この様な公演は有り難い。
又、海外の著名なオペラ座の引っ越し公演と異なり、ややローカルなオペラ座の公演とあって、オペラ公演としては比較的安価な料金も嬉しい。
今回は、マスカーニの「カヴァレリア・ルスチカーナ」とプッチーニの「ジャンニ・スキッキ」の二本立て。
「カヴァレリア・ルスチカーナ」はレオンカヴァッロの「道化師」と一緒に演じられる事が多いが、今回はプッチーニの唯一の喜劇「ジャンニ・スキッキ」との組み合わせで、悲喜劇の二本立てとなった。
「カヴァレリア・ルスチカーナ」は1時間余りの短い時間の中で、シチリア島のある村で起こる1日の悲劇を描いているが、筋立ては至って単純。現代の社会では、あちこちで起こっている様な男女の愛憎事件ではあろうが、19世紀末のイタリアの小さな村では、衝撃的な事件であったのだろう。更に、それまでの歌劇が、「カルメン」等を除いては、この様な男女の愛憎の末の殺人という題材を扱ったものは少なかった事を考えると、やはりその時代では先進的なオペラということになるのだろう。
更に、ドロドロとした愛憎劇なのに、音楽が非常に美しく、シチリアの太陽を思わせるような明るさに満ちていることもこのオペラの特色。
さて、ソフィア歌劇場の公演。
弦の美しい響きで開始されるが、ソフィア国立歌劇場管弦楽団の響きは、総ての場面でオペラ座のオーケストラらしいドラマティックで雄弁な語り口。長いオペラ座の伝統を感じさせる。
主役のサン・トゥッツアのラドスティーナ・ニコラエヴァ、トゥリッドゥのダニエル・ダミャノフを初めとする歌手も粒が揃っている。
そして、質素でありながら、情景を象徴的に現わしている舞台装置も美しい。特に背景のブルーの照明、教会をモチーフとしたルミナリエに見られるような装置など、印象的だ。
合唱もアンサンブルが見事で、厚い響きが有る。「オレンジの花は香り」など聴かせどころの合唱をドラマティックに聴かせる。復活祭の合唱の盛り上がりも見事。
有名な間奏曲、透明な響きと、悲劇を予感させる様な劇的な響きが印象的。
「ジャンニ・スキッキ」は「私のお父さん」が余りにも有名だが、歌劇全体を見る機会は少ないのでなかろうか。
プッチーニ唯一の喜劇ということだが、喜劇というより人間の物欲を赤裸々に描いたシリアスな歌劇という感もする。
そういう意味では、センチメンタルな題材が多いプッチーニにしては、珍しい作品。
音楽も、非常に激しく動き回り、プッチーニらしいアリアは「私のお父さん」程度。
登場人物も多く、各登場人物の重唱が中心となるが、さすが伝統のあるオペラ座と思わせる巧みな各歌手の重唱。
オーケストラも早い動機の連続をキビキビと聴かせ秀逸。指揮者のヴエリザル・ゲンチェフは日本では著名で無いが、さすがオペラ座の指揮者と思わせる、ドラマティックな響きを聴かせる。
劇の中心はジャンニ・スキッキ。バリトンのビセル・ゲオルギエフは声も良く通るが、この役の狡猾な面白さを巧みに演じていた。
ラウレッタ役の小林沙羅。唯一の聴かせどころの「私のお父さん」で、透き通った情感たっぷりのアリアを披露。
しかしこのアリア、どたばた劇の中で突然鳴りだす、悪く言えば、「ごみための中の鶴」の様。
きっと、プッチーニも作っているうちにフラストレーションに駆られたのでないかと想像させる。
この日のリヌッチョ役、キリル・シャルバノフやや、不調だったのか、声が通らない。それだけが残念。
演出、舞台装置も面白い。
劇の始まりで、子供がラジコンカーの様なおもちゃで遊んでいるが、現代にも通じる話ですよ、というメッセージか。
又、劇終盤で、欲にかられた親族がジャンニ・スキッキに追い出されるシーン、上着を全部脱いでしまうが、欲に駆らられると、結局スッテンテンになるという暗示か。
舞台中央に、ブオーゾの寝室を現わした屋上付きの建物があり、それがぐるぐると回る仕組み。
「カヴァレリア・ルスチカーナ」の装置同様、質素だが、象徴的で面白い。
全体として、歌手の巧みさ、オーケストラの巧さ、合唱団の迫力、そして演出・舞台装置の面白さと、さすが伝統のあるオペラ座の公演と思わせる安定した舞台だった。ヨーロッパのオペラ座の奥は深い。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第329回定期演奏会
2012年11月1日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 エミール・タバコフ
コントラバス マルガリータ・カルチェバ |
|
今回の定期は「東欧の響き」のテーマ。ブルガリアから指揮者と独奏者を迎えて、スメタナとドヴォルザークの名曲2曲と、作曲家でもある今回の指揮者タバコフの作品を加えた、オール東欧のプロ。
ブルガリアというと、私たちに馴染みなのはヨーグルトと琴欧州だが、音楽の面でも、11月に来日するソフィア国立歌劇場を代表とする音楽先進国の一つでもある。
さて、今日のプログラム、前半がスメタナの歌劇「売られた花嫁」序曲、タバコフのコントラバス協奏曲、後半がドヴォルザークの交響曲第8番。
タバコフはOEK初登場とのこと。
この日の楽器の配置は通常のOEKと異なり、対向配置でない、Vn、Vra、Ceと並べ、Ceの後ろにコントラバスを配置した、以前普通に見られた配置。最近は古楽志向が強くなり、この様な配置は珍しくなってきた。
タバコフは、コントラバスも指揮法と同時に学んだとの事で、珍しいコントラバスを独奏者とした自作の協奏曲をプログラミング。
スメタナの歌劇「売られた花嫁」序曲。出だしの木管に続いての、弦の特長的なリズム感を持つ合奏。この部分の激しい、叩きつけるような弦の響き。ここに象徴されるように、タバコフという指揮者、鋭い響きとがつちりとした構成を作り上げるタイプの指揮者。ここでのOEKはタバコフのかなり強烈と思われる要求にしっかりと応え、早く激しいパッセージをしっかりと表現していた。鋭い管楽器の叫びの様な響き、そして弦の堅く鋭い響き、そしてかなり早いスピードで駆け抜ける、一気呵成な音楽。この序曲では、それらが効果的で、歌劇の序曲にふさわしい色彩感の溢れた演奏。
次に、やはりブルガリア出身のコントラバス奏者、マルガリータ・カルチェバを迎えての、タバコフの自作のコントラバス協奏曲。マルガリータ・カルチェバはOEKの客演首席奏者として2009年よりOEKと協演を重ねたているとのこと。なるほど、何回もOEKの団員としてお見かけした気がする。
タバコフの作品、様々なパーカッションにピアノまで加えた大きな編成。ピアノも打楽器的な扱いも多く、第2楽章では、ピアノの中の弦を奏者が手で擦る個所もあり、色彩感溢れる作品。
時にストラヴィンスキー、プロコフィエフ、バルトーク等を想起させる部分もあり、現代音楽としては、非常に聴きやすく、面白い。特に打楽器群の特長的なリズム感ある響きと、重い響きのコントラバスとの対比が面白い。
第2楽章では、コントラバスの沈痛なモノローグがあり、この楽器の鈍重な特長を表現、第3楽章ではそれを逆手に取った様な技巧的なパッセージが続くなど、コントラバスの多様な個性を聴く事が出来興味深かった。
休憩を挟み後半はドヴォルザークの交響曲第8番。9番の「新世界より」があまりに有名だが、旋律の美しさ、構成の巧みさ、飽きさせない曲想等、この作品の方がむしろ面白いし、それだけに人気のある作品でもある。
ここでも、タバコフは、この作品の柔和で人懐っこい面よりも、激しく勇壮である面を強調するような演奏。
もうすこし、じっくりとこの作品の細部まで丁寧に描き出して欲しい感もありだが、これがこの指揮者の個性か。
たっぷりと歌ってほしい部分もさらりと流す。
全体的に音楽の流れがやや単調であり、部分的な効果を狙いすぎるきらいもある。この交響曲、もう少し自然な流れが有った方が、ドヴォルザークの意図が表現されると思うのだが。面白い交響曲だけに、それを更に強調したくなるのかもしれない。
アンコールに何とも激しく燃え盛るような作品が演奏されたが、何とこれがタバコフの作品「ブルガリアンダンス」とのこと。パーカッションが活躍、炸裂、その中に弦、管の早いパッセージの踊りが躍動する。
今日の演奏会では、スメタナとこの作品が、タバコフ一番のノリ。オーケストラも良くついていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
庄司沙矢香ヴァイオリンリサイタル
2012年10月21日 入善コスモホール
ヴァイオリン 庄司沙矢香
ピアノ ジャンルカ・カシオーリ |
|
庄司沙矢香のリサイタルはここ入善コスモで4回目となる。2005年、2009年、2010年、そして2012年。
一つのホールでこれだけこだわって一人のヴァイオリニストを取り上げるというのは珍しいのではないだろうか?
それも、大都市ならまだしも、一地方の小さい町の小さいホールで。
このホールのコンサートは、最近開催数が一時より減ったのが残念ではあるが、ユニークで魅力的である。
さて、2005年と2009年はピアノがイタマール・ゴラン、2010年より今回のジャンルカ・カシオーリに変わっている。
そして、前回はベートーヴェンの3つのソナタ。これは、その後カシオーリとのコンビで全曲版のCDが進行中であり、第一巻は大変な反響を呼んでいる。
今回のプロクラムは、そのベートーヴェンの中から前回も演奏された5番「春」、そしてヤナーチェックのヴァイオリンソナタ、後半がドウュッシーのヴァイオリンソナタ、シューマンのヴァイオリンソナタ第2番というもの。
ソナタ4曲を並べた実に大きなプログラム。そして、ドイツ古典派、ロマン派から近代フランス、チェコまで網羅した多彩さに驚く。
庄司沙矢香とカシオーリはこの4つのソナタで、それぞれの作品の核心に迫る、それでいて二人の世界を明確に示す、大きなスケールの演奏を聴かせてくれた。
最初のベートーヴェンでは、「春」という愛称に惑わされない雄大で刺激的なベートーヴェン像が提示された。
前回の演奏で、1楽章のテンポの遅さにびっくりした記憶が蘇るが、今回はややそれより早めか。それでも、一般的な解釈よりもゆったりとしている。
その最初のテーマのテンポの取り方に、この作品への二人のアプローチの鋭さを聴いた。
一般的には「春」の愛称の如く、軽やかに優雅に提示されるテーマが、実にしっかりとしたテンポで大きいスケール感を持って示される。
この作品が、ベートーヴェンの初期から中期にかけての革新的な作品群の中の一つである事がはっきりと理解できるアプローチ。
カシオーリのピアノが全体の骨格をきちんと押さえ、その中でヴァイオリンが豊かに歌う。
この二人のコンビの円熟を聴く思い。
庄司のヴァイオリンは従来にも増して、厳格で重い。しかし、今回はその中にしなやかさともいえる柔軟な歌も聴く事が出来た。
次は、ヤナーチェックの激しさと優しさが混在する不思議なソナタ。
ここでは、二人は劇的とも形容出来る世界を表現。表面的なモラヴィアの旋律の美しさの奥にある、ヤナーチェツクの苦悩の世界を、深い陰影でえぐり出した様な演奏。
旋律の美しさによりかからない、たたきつけるような表現。ヴァイオリンの音は暗く重い。そしてピアノは鋭く激しい。
拍手のフライングは残念。折角の音楽への沈潜を阻害されてしまう。
後半、最初はドヴュッシー。ここでも音楽は暗く重い。
たゆたうような独特の色彩感のある作品だが、二人のドヴュッシーは暗色系の重いドヴュッシー。
やはり音一つ一つに籠められた意味を的確に表現しよううとする意欲が聴く者にひしひしと伝わってくる。
最後のシューマン。ここでは、烈しくのたうつようなシューマンの情熱が、非常にはっきりとした形で表現されていた。
複雑で絡み合ったようなシューマンの音楽を、直接的でわかりやすい形で聴く者に示してくれる。
熱いロマン的感情に満ち満ちた音楽。それでいて、ドイツ音楽らしいがっちりとした構成感が示され、シューマンの音楽はこんなに魅力的だという事を再認識。
4曲を通して、音楽語法の違いを乗り越えた、作曲家の声が生々しく聴こえてくる演奏。
カシオーリの豊かで大きなスケールの構成感に、庄司が安心してよりかかり、自分の作品に対する訴えたい総てをヴァイオリンに託し歌い上げていた。
プロの演奏家の中に多々見られる、作曲家を無視した、ひとりよがりの音楽でない、作曲家が自らの作品にどの様な思索を籠めているのかという事を真剣に追求し、聴衆に示そうという誠実な意欲に満ちた二人の演奏であった。
この二人の名コンビ、長く続いて欲しいものである。
アンコールはシュニトケの「古い様式の組曲」からの様である。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第328回定期演奏会
2012年10月18日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 高関 健
ピアノ ハオチェン・チャン |
|
高関健は私が定期を聴き始めて、初めての登場。OEKは以前振った事が有るのだろうか?
と書いたところで、過去を見てみると、201年7月に登場している。記憶とは実にあいまいなもの。
今日は、更に辻井伸行とクライバーンピアノコンクール同時優勝という話題のハオチェン・チャンの登場。
プログラムは前半がロツシーニ歌劇「セビリアの理髪師」序曲、ストラヴィンスキーバレエ音楽「カルタ遊び」、後半がラヴェルピアノ協奏曲(独奏 ハオチェン・チャン )、ベートーヴェンの交響曲第2番。
高関健はオーケストラの長所を手堅く引き出していくという印象。
ロッシーニはアンサンブルもきちっとまとまり、独奏楽器のソロも魅惑的、クレッシェンドもわくわくするような迫力を作り上げ、ロツシーニの魅力満載の演奏。OEKのアンサンブルの良さを最大限生かした演奏。
ストラヴィンスキーも新古典的な、すっきりとした側面と、カラフルで色彩的な面を描き出し、魅力的。
後半のラヴェル。ハオチェン・チャンはすがすがしいラヴェル。音色はややおとなしく、ラヴェルにしては、もう少しクリスタルな輝きも欲しいと思うが、この何か水墨画を想起させるような落ち着いた音色が、この人の個性か。
第2楽章と、アンコールの「亜麻色の髪の乙女」に特にこの人の音色の落ち着いた個性を聴く気がした。
オーケストラも良く鳴っているのだが、やや重い。ラヴェルらしい切れ味も聴きたかった。
ベートーヴェンの第2番。今日の演奏は弦は対向配置。といはいうものの、ピリオド演奏では無い。テインパニーも通常のもの。であるから、全体のアンサンブルに豊かな重さが有る。
この作品の特に序奏から、新たなベートーヴェンの挑戦の声が聴こえる作品だが、序奏に大きな意思がある演奏。
この作品のスケールの大きさ、同時代のハイドン、モーツァルトと異なるベートーヴェンらしい気宇壮大さが聴こえてくる演奏。余計な小細工の無い、楽譜に忠実に正面からベートーヴェンを描き切った演奏。
かといって流行のピリオド奏法の痩せた音と異なる、豊かな音量が特色。
重厚さと、美しさと、推進力に溢れた演奏だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第327回定期演奏会
2012年9月20日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ソプラノ 森 麻季 |
|
マイスターシリーズの今期初定期。今日のプログラムはやや変則的で、前半がベートーヴェンの交響曲6番「田園」、後半が森麻季を迎えてのオペラアリアというもの。やや、ごちゃまぜの印象もあるプログラムではある。
井上監督のベートーヴェンが最近は充実してきている様に感ずる。先の定期の第9の4楽章も主張の明確な熱の籠った演奏だったが、今日の6番もこの作品の精神性が明確に表現された演奏。
この作品、ベートーヴェンの作品の中では、珍しく温和で柔和である。ベートーヴェン特有のドラマ性も薄いし、劇的な緊張感とも遠い距離がある。それだけに、どの様に演奏するかという点、大変難しい作品であり、えてして平凡な演奏に陥るか、あるいはその逆に極めて個性的な色彩になるかという、どちらかの演奏が多い。
今日の演奏は、この作品の内包する、自然と人間の関わり、自然への人間の感謝と喜び、その様な感情が素朴に表現されており、内容の充実した演奏と聴く事ができた。特に第5楽章の主題が、嵐の過ぎ去ったあとに晴れ晴れと、しかし素朴に奏でられる部分は印象的で、ベートーヴェンの喜びの感情がストレートに表現されていた。
3楽章の農民たちの素朴な踊り、そして4楽章の嵐の厳しくありながらアンサンブルの調和がきちっとした部分など、決して演出を過剰にしていないにも関わらず、鮮やかに光景が見えてくる点は秀逸。ティンパニーはバロックティンパニーを使用しているが、嵐の部分でも決して突出せず、調和のとれたアンサンブル。
井上監督のベートーヴェンの交響曲全曲演奏も是非聴いてみたいという思いが強くなる今月の定期であった。
プログラム後半はソプラノの森麻季を迎えてのオペラアリア。その中にグノーの小交響曲から2、3楽章、モーツァルトの「コシ・ファントゥッテ」序曲等の小曲をまじえたプログラム。
森麻希はヘンデル、歌劇「セルサ」から「オンブラ・マイフ」、「リナルド」から「涙の流れるままに」、モーツァルトの「コシ・ファントゥッテ」から「岩のように動かず」、プッチーニの「ボエーム」から「ムゼッタのワルツ」、そして久石譲るのテレビドラマ「坂の上の雲」の主題歌「スタンド・アローン」、アンコールにプッチーニの「ジャンニ・スキッキ」から「私のお父さん」。
森麻季のソプラノは硬質でクリスタル。ロマン的で濃厚な役柄よりも、古典的なオペラに似合う様だ。
勿論、イタリアオペラやワーグナー等ドイツロマン派オペラもそれなりにこなすのだろうが、やはり古典が似合う。
この日もヘンデル、モーツァルトが中心で、それは誠に気品の高い歌唱。低域から広域までのガラスの様な繊細な歌声はこの人の特質。そして、最後の「坂の上の雲」の主題歌「スタンド・アローン」の劇的で堂々とした歌いっぷりは独壇場。
ただ、いかにも曲数が少なく、聴く方にももっと聞きたいというストレスが残る。これは、先年の佐藤しのぶを招いての定期の際も感じた事。
珍しいグノーの小交響曲。管楽器のみで演奏されるが、小気味の良いエスプリに富んだ佳品。埋もれている名曲も多いのだろう。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第326回定期演奏会
「岩城宏之メモリアルコンサート」
2012年9月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 天沼 裕子
山田 和樹
井上 道義
ピアノ 田島 睦子
ソプラノ 森 麻季
メゾソブラノ 鳥木 弥生
テノール 吉田 裕之
バリトン 木村 俊光 |
|
今期最初の定期公演。毎年9月は故岩城宏之名誉音楽監督の命日にちなみ、「岩城宏之メモリアルコンサート」とすることが定例となっている。
早いもので、マエストロ岩城が亡くなって6年がたつ。マエストロ逝去の後、OEKの先行きも心配されたが、井上道義監督、その他関係者、そして多くのファンの支えで、一層の輝きを聴かせてくれている事に、マエストロ岩城もきっと喜んでいる事だろう。
井上監督の談話にあった通り、音楽文化の未開地であった金沢がOEKの活躍により、以前では考えられない様な音楽文化の花咲く街となりつつあるのは、マエストロ岩城の残した大きな遺産である。
今回の定期も、その功績を偲ぶにふさわしいブログラムとなっていた。
前半が、池部晋一郎の「悲しみの森」(1998年OEK委嘱作品)、独奏者に今年の岩城宏之音楽賞を受賞した金沢出身のピアニスト田島睦子を迎えて、プーランクのピアノ協奏曲、後半が西村朗の「ベートーヴェンの8つの交響曲による小交響曲」
そして、ベートーヴェンの9番の第4楽章。
初演魔と言われるほど日本の現代音楽家の作品の紹介に尽力をつくした側面、そして若い音楽家を育てようと懸命だった側面、そして限りないベートーヴェンへの畏敬と愛着、その様な岩城マエストロの足跡を端的に現わしたプログラム。
指揮者も、OEKの初期に盛んに指揮をした天沼裕子、そしてOEKで育てられた若手指揮者といっても良い山田和樹、そして井上監督と賑やかな顔ぶれが揃った。
演奏会が始まる前に今年度の岩城宏之音楽賞の授賞式が催され、賞状と記念品が田島睦子に渡された。
ブログラム最初は、池辺晋一郎の「悲しみの森」1998年のOEKコンポーザー・イン・レジデンスの時の作品。
さわさわと揺れ、時には強いざわめきとなる森の心象風景が、弦楽と、管楽器の巧みな表現で描かれる。
爽やかな風が吹き抜ける様。その中で、どこがとはいえない、日本の風が聴こえる、懐かしい日本の森でもある。
森の息づかいが聴こえる様な作品。
次はプーランクのピアノ協奏曲。ソリストは田島睦子。先日もミンコフスキーの指揮の下、同じプーランクの「二台のピアノのための協奏曲」を鮮やかに弾いたばかりだが、プーランクが好きなのだろうか。
プーランクという作曲家、不思議な魅力を持つ作曲家。フランスらしいエスプリと、ユトリロの絵を思い起こさせる庶民的な親しみ、それとプロコフィエフに似通った皮肉なアイロニー。エスプリと野暮ったさが同居する様な不思議な魅力。
このピアノ協奏曲も将にその様なプーランクの魅力満載。一楽章出だしのピアノの魅惑的な旋律、どこかで聴いた事がありそうな、しかし個性的なプーランクそのものの旋律で一気に聴衆を引きずり込む。ピアノの簡潔なタッチ、そして崩れない端正さが、この作曲家の面白さを浮かび出す。
2楽章の洒落た歌も素敵、そして3楽章のパリの雑踏を想像させるような騒がしい猥雑な雰囲気。
ピアノの乾いたタッチとクリアな音色がこの作曲家の魅力を鮮やかに描き出していた。
プログラム後半はベートーヴェンの世界。
というものの、限られた残りの時間の中で表現するには余りに巨大な世界。
ということで、西村朗の「ベートーヴェンの8つの交響曲による小交響曲」
11分程の時間でベートーヴェンの8番までの交響曲のサワリを紹介しようという無謀な?試み。
しかし、器用な作曲家である。1楽章から4楽章まで、それぞれ各交響曲の主題をちりばめ、1つの小交響曲に纏めるという離れ業。一度聴いただけでは8番までの総ての楽章のテーマが入っているのか聴きわけることは難しいが、「ああ、あの主題」というものが現われてはすぐ消え、時には主題同士のからみあい。ベートーヴェンの音楽の小宇宙。
プログラム最後は9番の4楽章。
「4楽章のみ」という思いはあるが、今日のこの演奏は誠に素晴らしいもの。
以前も書いた事が有るが、9番という交響曲は特別なもの。「暮れに第9」という安易な演奏はしてほしくないもの。
OEKが12月に第9を定例的に演奏しないのは日本のオーケストラの中でも大変な見識、さすがマエストロ岩城と思っていた。
それだけに、この日の演奏は、井上監督、OEK、そして素晴らしい独唱陣と合唱団を得て、この交響曲の神髄が表現された様に聴く事が出来た。やはり、マエストロ岩城への思いが、この様な名演を生み出したのか。
出だしはやや気負いが勝ち、オーケストラにも堅さと乱れが有ったが、歓喜の歌が静かに低音弦によって歌いだされ、繰り返され大きな高揚に至る辺りから、音楽が生き生きと躍動し始めた。
そしてバリトンの独唱。木村俊光さん、大ベテラン、70歳近いお年と思うが、「フロイデ!!」と歌いだした瞬間、ホールが揺れる様な感覚に襲われた。そして、その後の合唱団の歓喜の合唱、決して力まない、語りかける様な躍動感に溢れた歌声、厚い響きのハーモニー。
80名あまりの合唱団だが、その豊かな声量と、見事なハーモニー。ソプラノの森麻季さんの透き通った、クリスタルなソプラノ、鳥木弥生さんのしっかりと支えるアルト、輝かしく神々しく歌い上げた吉田裕之さんのテノールと、独唱陣も見事。
この交響曲に籠めたベートーヴェンの人間に対する熱い信頼と希望を、総ての演奏者が見事な技術と熱い心で表現していた。
井上道義監督の自在な指揮ぶり。中間部の荘厳な表現、そしてエンディングでは、思いっきり音楽をため込み最後のブレストに突入するなど、引き締まったなかにもかなり自在に音楽をドライブしていく即興性に満ちた演奏。
この様に第9を新鮮な感覚で、感動を持って聴く事が出来たのも珍しい経験。
やはり第9は大切に演奏して欲しいものと再認識させられた。
休憩後の最初に池辺晋一郎氏と西村朗氏の、マエストロ岩城にまつわる逸話の紹介もあり、「岩城宏之メモリアルコンサート」にふさわしい内容の濃い定期演奏会だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
IMA環日本海交流コンサート
2012年8月23日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
チェロ 工藤 すみれ
ジャン・ワン
ヴァイオリン クララ=ジュミ・カン
神尾真由子
ピアノ 後藤正孝
管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢 |
|
8月は定期公演の夏休み。このIMAのコンサートが定期の合間に毎年開かれている。
IMAは石川ミュージックアカデミーの略。
15年前より、毎年夏に短期間で集中レッスンが開かれ、世界から若い俊英の音楽家がレッスンを受けるため、金沢に集まる。
講師陣も充実し、原田幸一郎、レジス・パスキエ等世界の指導者が金沢に集まる。
7月の定期でハーディングと共演したシン・ヒョンス、庄司沙矢香、神尾真由子等素晴らしい俊才がこのアカデミーから輩出している。
今回は15周年記念として、「アカデミー15年の至宝を聴く」と副題がつけられたコンサートで、15年間でこのアカデミーから世界へ飛び立った豪華なソリストが集まり、OEKと協演するという興味深い演奏会。
トップバッターはチェロの工藤すみれ。チャイコフスキーの「ロココ風の主題による変奏曲」
現在は主にニューヨークに活動の中心を移し、室内楽に重点を置いた活動をしているとのこと。
豊かな歌心が印象的。自分の個性を主張するよりも、オーケストラとのアンサンブルを重視している印象。凄さはないが、良く歌うチェロ。低音の伸びやかさかも印象的。
次はクララ=ジュミ・カンのヴァイオリン、ジャン・ワンのチェロによるブラームスの「二重協奏曲」
これは又激しいぶつかりあいの演奏。二人とも一歩も引かず、各々を主張する。ブラームスの鬱々たる情熱というより、烈しい熱情が溢れている様な激しさ。さすがに、韓国と中国の血をひく二人、訴えかける力のみなぎる演奏であった。
3楽章のヴァイオリンとチェロ双方の主題の展開、激しさと、良く歌う伸びやかさの対比が鮮やか。
井上道義・OEKも二人の熱情に負けじとの熱い演奏。
休憩後の最初は昨年のリスト国際ピアノコンクール優勝者の後藤正孝。得意のリストのピアノ協奏曲第一番。
小柄で少年の様な容姿だが。ピアノに向かうと一回り大きく見える。そして、そのピアノは正確なタッチと強い打鍵で聴く者を圧倒する。濃厚なロマン性と異なる、フレッシュで爽やかなリスト。今の彼の年代にふさわしい、衒いの無いリストではある。井上道義の指揮も、構成感をしっかりと出した堅固なリスト。3楽章の有名なトライアングルとピアノの掛け合いも魅力的。
最後は、神尾真由子のバーンスタイ「セレナーデ(プラトンの『饗宴』による)
弦楽器、各種打楽器、ハープと独奏ヴァイオリンという特殊な編成。5楽章からなり、長大で複雑な印象も感じさせる作品。
神尾真由子は1楽章の独奏ヴァイオリンの憂いに満ちた旋律から聴く者を引き込む。
この作品のシリアスで複雑な感情を深く深く掘り下げた演奏。
音楽を主観的に捉え、自らの感情を臆することなく音楽の中に表現しようとする、濃厚な音楽世界を作り上げる彼女の演奏スタイルだが、益々そのスタイルに円熟さが加わりつつある。
バーンスタインの複雑な感情がからみあった、ある意味難解な音楽とも言えるが、彼女のヴァイオリンは難解さを感じさせず、楽譜に籠められた深いシリアスな感情を豊かに表現していた。そして、全曲を弛緩することなく表現しつくす集中力の凄さ。
5楽章の前半のチェロとの対話、そして後半の疾走する様なジャズのリズム感の激しい表現。(有名な五嶋みどりの「タングルウッドの奇跡」の部分)
井上道義・OEKも打楽器奏者の熱演、そして5楽章終盤のリズムの難しい部分でのノリの良さ等、見事なサポート。
アンコールとして、終結部が再演されたが、更に一層のノリがあった。
「環日本海交流コンサート」と銘打たれたコンサート。ここ最近の、韓国・中国との不協和音を聴くにつけ、文化交流の大切さを再認識する。妙で危険なナショナリズムを払しょくするだけの力が音楽にある事、音楽はそれだけの力を持っている。そのことを今日の中国、韓国、日本の音楽家は示してくれた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第324回定期演奏会
2012年7月25日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 マルク・ミンコフスキー
ピアノ ギョーム・ヴァンサン 田島 睦子 |
|
今期最後の定期。注目の指揮者、ハーディングに続いてミンコフスキーの登場。
この音楽堂で3年前、自ら創設のルーブル宮音楽隊を率い行った演奏会の新鮮で生彩に満ちたハイドン、モーツァルトを思いだすが、今回はフランス近・現代の作品を中心としたプロ。ミンコフスキーとOEKの組み合わせと聴き、古典派の作品のプロがすぐ頭に浮かんだが、発表されたものは全く意外なものであった。
クルト・ヴァイルの交響曲2番、プーランクの2台のピアノのための協奏曲、後半がラヴェル・マメール・ロア(バレエ版)
というもの。個性的でマニアックな選曲ではある。しかし、ミンコフスキーがフランス人である事を考えれば、納得のいくプロでもある。
この日の楽器配置はほぼルーブル宮音楽隊と同様。対向配置だが、コントラバスは正面に置いている。そしてティンパニーは通常のティンパニー。近現代作品であれば当然か。
さて、最初のクルト・ヴァイルの交響曲2番。ヴァイルというとブレヒトの「三文オペラ」の作曲家という程度の知識のみであるが、交響曲は珍しい。
全体は暗い雰囲気に彩られているが、その中にアイロニーが漂い、作風は異なるがショスタコーヴィッチのある種の作品も想起させるような交響曲。作曲された1930年代という時代背景と切り離して聴くことの出来ない作品。
時にジャズのブルースの様な曲想も聴かれ、第2楽章のトロンボーンの印象的なソロは哀愁に溢れており、ヴァイルの個性を聴く事ができる。3楽章では行進曲風な曲想が続き、終結部は急速な激しさで終わる。これは、その時代のナチの台頭と、戦争の危機を暗示させるようで印象的。
ミンコフスキーの指揮は、古典を演奏する時と同様、音のクリアさが際立ち、響きが輝かしく艶やか。
音楽が生き生きと躍動し、生彩に満ちている。
その点が次のプーランクでは将にピタリとはまり、プーランク独特の洒落たエスプリと小気味の良い躍動感が全体を支配し、ある意味知的な興奮を音楽から感じ取れるような演奏。
ピアノの二人も熱演。フランスと日本という二人の音の個性があり、輝かしさのヴァンサン、落ち着いた音色の田島と個性の相違が興味深い。華やかな技巧も見せる作品だが、軽快な疾走と、2楽章でのしっとりとした抒情など聴かせどころをきちんと押さえた演奏。
アンコールに3楽章が繰り返されたが、アンコールの演奏は更にバワーアップ。オーケストラとピアノが猛烈な疾走。
終わるとヴァンサンの顔が紅潮していたのが印象的。
休憩後はマメール・ロア(バレエ版)。組曲版では無く、バレエ全曲版。
精緻で色彩的な管弦楽法で造られている作品だが、全曲は至って平明、それだけに演奏は難しい。
色彩的ではあるが、それはパステル画の様に淡い色彩であるので、オーケストラにはデリケートな響きとアンサンブルが求められる。
ミンコフスキーの演奏は、透明さよりも、グラデーションの様な音の重なりを追求しているようで、クリスタルというより暖かさの感じられる響きを聴いた。
各場面の描写的な表現が、場面ごとに鮮やに応え、まるで絵本をめくっていく様な楽しさ。
各管楽器がデリケートで色彩的な響きを聴かせ熱演、特にコントラファゴット、ホルンが良い響きを聴かせていた。
清明な全体の中で、盛り上がりを見せる、「パゴダの女王レドロネット」そしてフィナーレ、自然で色彩鮮やかな盛り上がり。
この日のミンコフスキーを聴いて、この指揮者のフランス人らしいエスプリと、音楽を新鮮に楽しく表現しようとする意欲を改めて感じた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第324回定期演奏会
2012年7月13日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ダニエル・ハーディング
ヴァイオリン シン・ヒョンス |
|
今季最後の定期は、フィルハーモニー、マイスター共注目の指揮者の登場。
今日のフィルハーモニーはハーディング、後日のマイスターはミンコフスキーという、いずれも現在世界で注目の指揮者の登場。
ハーディングはドイツカンマーフィルへ20代前半で登場、CDでの「ベートーヴェン序曲集」の超名演で話題をさらったことが記憶に残る。
金沢でもマーラーチェンバーオーケストラとともに2003年にベートーヴェン、昨年はブラームスが演奏され、その新鮮な演奏が印象に残っている。
今回はOEKからどの様なベートーヴェンを引き出すかが興味の中心。更に韓国の新鋭、シン・ヒョンスを迎えてのヴァイオリン協奏曲も注目。
プログラムはオールベートーヴェンで、前半がヴァイオリン協奏曲、後半が交響曲第5番。正面から真っ向勝負でベートーヴェンに取り組む様な堂々たるプログラム。
楽器配置は対向配置だが、コントラバスを左側奥に、第一Vn,、Ce、Vra、第二Vn、トランペット、ホルンは左側木管の隣という配置。後半の交響曲ではトロンボーン・トランペットは右側奥に配置。そしてティンパニーはバロックティンパニーを使用。ベートーヴェンの時代の響きを再現させようという試みか。
シン・ヒョンスを迎えてのヴァイオリン協奏曲。出だしのティンパニーの乾いた響きの後、木管が主題を奏するが、その響きにまず魅せられた。いつものOEKの音と微妙に異なる芯のはっきりとした主張のある音。いつものOEK の管が下手だという事でなく、音の性質が変化しているのだ。輪郭が明確で主張のある音といつったら良いだろうか。
長いオーケストラの前奏が終わり、シン・ヒョンスの登場。出だしが緊張のためかやや乱れがあったが、すぐに透徹した硬質な響きが鳴り始めた。
この協奏曲の室内楽的な魅力がきっちりと表現された演奏。独奏ヴァイオリンとオーケストラがお互いの歌を調和を持って歌い上げていく、その魅力に溢れた演奏。
しかし演奏全体は緊張に満ち満ち、その緊張が崩れたら演奏が滅茶苦茶になってしまいそうなギリギリのバランスで成り立っているスリリングな演奏とも言える。もう少し肩の力を抜いたら、聴く方も楽に聴けるのにと思ってしまいそうだが、それを許さないのがこの演奏の魅力か。
シン・ヒョンスのヴァイオリンの音の透き通ったクリスタルな響きは勿論美しいのだが、彼女はそこに埋没しないで、自らを戒める様にベートーヴェンの音楽の品格を保とうとする。そしてハーディングも勿論作品全体の構築性を明確に表現していく。
その意味で禁欲的な演奏である。自分勝手な解釈でなく、ベートーヴェンの楽譜に書かれた中からこの作品の真の美しさを探し出そうとする真摯さと言えようか。
いずれにしても、息の詰まるような名演ではあった。
後半の交響曲5番。ある意味、あまりにも雑に扱われてきた名作。名作であるが故に、手あかにまみれてしまった印象もある名作。
今日の演奏はそれらの垢を落とし、この作品の真価を再認識させてくれた様な新鮮な演奏。
無駄を総てそぎ落とし、音楽のエキスのみが響いている様な凄さ。
一気呵成の演奏であるが、細部までクリアな見事なアンサンブル。
OEKにとつては自家薬籠中の作品であろうが、この日のOEKは初めてこの作品に取り組む様な真剣さを聴かせた。
たたみかける様な迫力の第一楽章、早めのテンポをとりながら神々しく奏でられた2楽章、3楽章の劇的な緊張感、そして一気に緊張がとかれ歓喜が爆発する第4楽章。この作品の劇的な構築感が見事に再現されていた。
以前のMCOとの5番を聴いた際も、4楽章の提示部の繰り返しの意味をはっきりと聴く事が出来たが、今日の演奏でもそれを再確認。繰り返しによりベートーヴェンの喜びの歌が一層増幅され響き渡る。ベートーヴェンの意図の明確な表現。
最後までゆるぎない緊張感と力感に溢れた演奏。
音楽が終わったとたん、久しぶりに音楽堂の補助席まで埋めた聴衆から、ブラボーの嵐と熱狂的な拍手。
それに応え「フィデリオ序曲」がアンコールされた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第322回定期演奏会
2012年6月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 秋山 和慶
ヴァイオリン 戸田 弥生 |
|
発表当時のアメリカの女性指揮者ファレッタが何らかの事情で来日出来ず、早い段階で指揮者秋山和慶と変更が発表されていた。プログラムは予定通りアメリカ音楽で変更は無かった様である。
秋山和慶は大ベテランの指揮者であるが、OEKは初登場とのこと。
プログラムは前半がバーバー2曲、「弦楽のためのアダージョ」、戸田弥生をソリストに迎えての「ヴァイオリン協奏曲」、後半がウイリアムズの映画「シンドラーのリスト」テーマ曲、コープランド「劇場のための音楽」というもの。
どちらかというと、ヨーロッパ系の音楽が中心のOEKにとって、アメリカ音楽のみのプログラムは珍しいが、前半のバーバーはヨーロッパ系の音楽に近いものであり、それほど違和感のあるプログラムでもない。むしろ、弦楽の美しさが際立つ作品のプログラムはOEKにふさわしい。
バーバーの「弦楽のためのアダージョ」は昨年の東日本大震災後、数多く演奏されたが、バッハの「G線上のアリア」と同様、いつのまにか「鎮魂のための音楽」というレッテルが張られてしまっているが、この作品の静かで痛切な音楽がそのようなレッテルとなってしまったのだろう。
この作品を聴くたびに40年ほど前に旧観光会館でオーマンディー率いるフィラデルフィア管弦楽団の演奏会を思いだす。ムソルグスキー(ラベル編曲)の「展覧会の絵」のラスト、「キェフの大門」がホール割れんばかりの大音響でフィナーレを迎えた後、大きな拍手に応えて演奏されたのが、この作品。大きな音楽的興奮の後に、静謐な弦の調べが流れだしたとき、このオーケストラの弦の美しい響きとこの作品の深い弦の響きの魅惑にびっくりとした事を鮮やかに思い出す。
今日の演奏も、OEKの弦の絶妙なアンサンブルがこの作品の魅力を際立させていた。秋山の指揮は、決して感傷に陥ることの無い、気品の高い音楽となっていた。中間部の弦の合奏の大きな盛り上がりも見事。
次は戸田弥生を迎えての同じくバーバーの「ヴァイオリン協奏曲」。有名な作品でありながら、演奏される機会のそれ程多くない作品、ヴァイオリン協奏曲には名曲が多いからであろう。
戸田弥生も初めて聴くヴァイオリニスト。もう中堅の実力派である。しっとりと落ち着いた音色。これは楽器がガルネリということにもよるのだろう。楽曲を崩すことなく、端正に、そしてしっかりと組み立てていく誠実な演奏。
この協奏曲はメロディーがバーバーらしく際立って美しいので、そこにおぼれてしまうと作品全体の気品が損なわれてしまうと思うが、戸田はその様な事が無く、淡々としかししっかりとメロディーラインを紡いでいくので、気品の高い演奏となっていいる。第2楽章のオーボエのソロとそれに続くヴァイオリンの歌も、決して感傷に陥らない端正な美しさ。
ヴァイオリン、オーケストラ共に、禁欲的とさえいえる様な抑えた美しさがある。
短い第3楽章の技巧的なパッセージも、しっかりとした演奏。決してこれみよがしでない、楽譜の音符を確実に表現しようとするような演奏。
後半のウィリアムスの「シンドラーのリスト」のヴァイオリン独奏も同様の格調の高さを聴く事が出来た。
最後はコープランド。「劇場のための音楽」と題されているが、小曲が5曲組み合わされた、小オーケストラのための組曲。
バーンスタインが将に現代的・都会的なアメリカを描き出したのに比べ、コープランドはアメリカの田舎的な風景の描写とも言える作風の音楽が多い。この作品も、のどかで素朴な部分にアメリカのジャズブルースなどのリズムが混在し、アメリカの懐かしい雰囲気を感じさせる作品となっている。
小オーケストラではあるが、独奏楽器、打楽器、ビアノ等、個々の楽器の活躍が浮き出て、楽しい演奏となっていた。
第3曲のコールアングレの旋律は特に魅力的。しみじみと全曲を結ぶ「エピローグ」も印象的。 |
|
|
|
|
|
|
|
カンタータ「悪魔の飽食」第23回全国縦断コンサート石川公演
2012年6月17日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 池辺晋一郎
オーケストラ・アンサンブル金沢
合唱 カンタータ「悪魔の飽食」を歌う石川合唱団・同全国合唱団
演出 片岡輝 |
|
森村誠一の「悪魔の飽食」は第二次世界大戦中のハルピンで、日本の軍医・石井中将率いる731部隊が行った人体実験の詳細を描き、発表当時センセーショナルな話題を引き起こしたドキュメンタリー。その後使われた写真が一部偽造されたものと言う批判を浴び、作品全体の信ぴょう性が問題となり、発売元の光文社は書籍を絶版としたが、その後森村誠一自身の手で改訂され、現在はその改訂版が角川書店より発売されている。
カンタータ「悪魔の飽食」は、神戸市役所センター合唱団の委嘱により、作者自身が詩として作り直し、それを池辺晋一郎がカンタータとして作曲完成、1984年に初演、1995年より全国縦断コンサートが開始、今回の石川公演で17年目、第23回目を数えるという、希有な歴史を持つ作品である。
回を重ねるごとに合唱団も大きくなり、今回は400名を越える全国から集まった合唱団と石川県で集まった100名、合計500名の合唱団とオーケストラ・アンサンブル金沢がこのカンタータを歌い上げた。
全体は7つの章より成り、6章までは詩の内容は重く、暗い。731部隊が引き起こした人体実験のむごさと、被害者と加害者の苦しみを描き、更に平和への祈りと不戦の誓いを歌い上げる。
1章の「731の重い鎖」では劇的なオーケストラの叫びに導かれ、合唱団が731部隊の起こした悲劇を告発する。重厚で劇的な管弦楽と合唱団の厚い響きが、悲劇をリアルに現わし、心を直接わしづかみにする。
2章の「生体の出前いたします。」は生体実験を映した詩の生々しい描写を、音楽はシニカルに描き出す。詩の残酷な内容を音楽がシニカルに伴奏づけるのが、一層不気味である。
3章の「赤い支那靴」はこの作品の中でも頂点を成す優しさと悲しみをたたえた章。どこかで聴いた様な懐かしく心深く染み入る旋律が静かに流れる。池辺の音楽は、懐かしさが溢れながら作曲者の声が聴こえ、個性的。
4章「反乱」は生体実験の材料とされたマルタの絶望的な怒りの表現。終結部ではマルタの人間の尊厳への決然とした宣言が明確な音楽で締めくくられる。
5章「37年目の通夜」はマルタの親子を毒ガスで殺した兵の悔悟を描く。途中でその兵の毒ガス注入の際のナレーションが入る。ナレーションは放送で入っていたようだが、やや切迫感に欠けており、合唱団の中で叫ばせた方が効果的でなかったろうか。この章では、殺されたロシア人の親子の様子がバレー団員により舞台上で演技された。子供のつぶらな瞳が印象的。
6章「友よ白い花を」は全章を締めくくる様な祈りと希望の音楽。舞台上にはバレリーナにより、詩の内容を表す白い花が静かに置かれる。
そして最終章はガラット雰囲気が変わり、明るく爽やかな、しかし力強い合唱が響き、「君よ目を凝らしたまえ、目を背けたくても、背けてはならない。一人になってはならない、一人にならない様に、私たちは集まろう。」と高らかに歌い上げる。森村誠一と池辺晋一郎の対談の中で、全国から毎年集まる合唱団はこの章を歌いたくて集まる人が多いと語られていた。勇ましい行進曲で無い、明るく爽やかな曲調は作曲者池辺の真骨頂を聴く様であった。
大変な力作であるが、音楽は平易で聴きやすく、歌詞も明確に聴こえる。伴奏の管弦楽も雄弁に語られ、管弦楽法の巧みさを感じる。OEKは極く短期間の合唱との練習と聞いたが、さすがにプロの演奏。生き生きと表情豊かな音楽。
勿論のこと、舞台上溢れるばかりの合唱団は熱い熱演。全国からこの作品を歌う為に自費で参加したとのことで、その熱意に敬服。
暗い内容の作品でありながら、音楽の持つ力の強さを改めて感じさせてくれる池辺晋一郎の力量に感服。
総ての章に作者と作曲者のこの詩を表現する上での強い意志がみなぎり、音楽の持つ力の強さを再認識させてくれた。
この様な作品を実現させるには色々な意味で大変な努力が必要とされたことであろう。関係者の努力を讃えたい。
ホールの入口に「この公演を妨害する様な方の入場はお断りします。」という通告文が貼られていたが、残念ながらそんな窮屈な日本の現状である。
石川県立音楽堂とオーケストラ・アンサンブル金沢の実現にあたっての英断にも敬意を表したい。
カンタータの前の第一部では、地元の太鼓サークル鼓風楽による太鼓、二胡の李彩霞とチェロのルドヴィード・カンタ、ピアノの清水史津による「トリオ・アジアの風」による演奏があった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第321回定期演奏
2012年5月24日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 下野 竜也
トランペット カボール・タルケヴィ |
|
今日の定期はベルリンフィルのトランペット主席、カボール・タルケヴィをソロに迎えてのバロックから古典派にかけてのプログラム。
非常にマニアックでレアな作品が並んだ。
前半がボッケリーニの交響曲「悪魔の家」、タルティーニのトランペット協奏曲、後半がネルーダのトランペットと弦楽のための協奏曲、ハイドンの交響曲第55番「校長先生」というもの。
編成も小さく、弦楽合奏に、ホルン、オーボエ、ファゴット、チェンバロを加えた程度。クラリネットもフルートもティンパニーも無し。
それだけに、オーケストラの素の実力が試されるプログラムでもある。
この日の楽器配置は対向でなく、Vnからチェロ迄を左から右に並べたオーソドックスなもの。
下野竜也は凝ったプログラミングをするので有名だが、今回もその典型。
ボツケリーニはチェロ協奏曲が有名だが、この作品は珍しい。バロック後期の作品らしい端正で調和のとれた響きが印象的。三楽章の激しく早いパツセージの連続が印象的。弦楽器には過酷なアンサンブルが要求されると思うが、OEKは下野の要求に反応し、緻密で表情豊かな表現を聴かせてくれた。
次はタルケヴィの登場で2曲。タルティーニは「悪魔のトリル」で著名だが、ネルーダは初めて聴く作曲家。
両曲とも時代的にはほぼ重なりバロックの後期。曲想も似通っており、この時代の協奏曲の典型的な作品と感じられる。タルケヴィは伸び伸びとそして華麗なトランペット。ネルーダでは、この時代特有の高い音域での転がす様な奏法が多用されるが、楽々と吹き切り、全く難しさを感じさせない快演。
アンコールはヴイヴァルディーか。Vn、Ceをバックに澄み切ったトランペットの響き。
プログラム最後はハイドンだが、これも珍しい55番「校長先生」
アンサンブルのきちんと整った、温かみのある演奏。最近のピリオド奏法と違う、豊かな響きのアンサンブル。
第2楽章は後の「時計交響曲」を想起させる美しく端正に歌う楽章。
3楽章の中間部では、管楽器のトリオでなく弦楽器の独奏によるトリオが珍しい。落ち着いた室内楽的なアンサンブルが心地よい。他にも、管楽器のみのパッセージがあったり、オーケストラの聴かせどころの多い作品だが、OEKは難なくこなし、アンサンブルの徹底を図る下野竜也の意図にきちんと応えていた。
非常に地味なプログラムで、高い心の高揚感をもたらすプログラムではないが、後々心の隅に残る様な淡々とした滋味豊かな演奏だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
ラ・フォール・ジュルネ金沢2012
2012年5月3日~4日
石川県立音楽堂 コンサートホール 邦楽ホール アートホール |
|
今年もラ・フォール・ジュルネが金沢にて開催された。今年で5年目、この音楽祭も定着しつつあるようだ。
今年は、「サクル・リュス(ロシアの祭典)」のテーマで、国民楽派以降のロシア音楽が取り上げられた。
今年は5月3日からの3日間が集中開催日。例年より集中開催日が1日増え、その分公演数も増えたようだ。
その所為か、あるいは4日の天候が優れなかった所為か、公演にやや空席が目立ったのが気になった。
内容は例年以上に充実していたが、ロシア音楽、それもやや馴染みの少ない作品の演奏会が多かった為か、やや客足に鈍りが見られたようだ。
運営もすっかり落ち着き、目立ったミスも少なかったようだが、4日ポゴレリッチの演奏家時間が延びた(十分に予想できた事だか゛)影響で、その後の演奏会の開始時間が遅れ、一部でいらいらしていた観客もいたようである。
又5日のツェムリンスキー弦楽四重奏団の演奏会では、演奏曲順が逆となっていたのが、訂正されなかった。
今年は3日、4日の二日間の演奏会を聴いた。
演奏の内容では、オーケストラでウラルフィルのロシアのオーケストラらしいパワフルな響き、庄司沙矢香のショスタコーヴィッチの緊張感、トリオ・ショーソンのチャイコフスキー、ラフマニノフの大熱演、そしてポゴレリツチの異常さ等が強い印象に残った。下記に短い感想を記す。
5月3日の演奏会から
アンドレイ・コロベイニコフ
ラフマニノフ 「13の前奏曲より第5.1012番
スクリャーピン 9つのマズルカOp.25
スクリャーピン ピアノソナタ第7番「白ミサ」
ラフマニノフの独特の間合いとゆったりとしたテンポ、強い打鍵、終結部の長い残響が印象的。
スクリャーピンは、初期と後期の作品の違いが明瞭。ソナタ「白ミサ」の終結部の宗教的高揚感、恍惚たる響き。なるほど神秘主義とはこういうものかと納得。ライブでないとスクリャービンのこの様な面白さは体験できない。
コロベイニコフはいかにもロシアの伝統的なピアニズムの継承者という印象。粘液質と、輝かしい打鍵。
ウラルフィルハーモニー
ドミトリー・リス(指揮) 庄司沙矢香(Vn)
ショスタコーヴィッチ ヴァイオリン協奏曲 第一番
庄司のヴァイオリンは以前の硬質なものから、柔軟さが加わった印象。
緊張感に満ち満ちたスケールの大きな演奏。第3楽章カディンツァの抑えた情熱がすさまじい厳しさを与えていた。
ウラルフィルはスケールの大きさが印象的。ただ、細部がやや雑。
アンヌ・ケフェレック
カトワール
3つの小品Op.12
レビコフ
秋の夢、ミニュチュアールのアルバムOp8より「悲しみの時、忍耐」
プロコフィエフ
年をとった祖母の物語Op31
スクリャーピン
10つのマズルカOp.3より第2.3.5番
チャイコフスキー
12の小品Op.40より第6,10番
チャイコフスキー
「四季」より 1月「炉端にて」
2月「謝肉祭」
同じロシア音楽でも演奏家の個性が異なるとガラっと印象が変わる。
懐かしさと、優しさとほっとするひと時の様な音楽。
優しい作品を慈しみを持って演奏していた
台北市立交響楽団
西本智美(指揮)
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」
珍しい台湾のオーケストラ。
編成も大きく、音量も豊か。ただ、細部のアンサンブルが粗く、磨かれていない。このあたりは今後の課題か。
西本の指揮は、スケールの大きさの表出が見事だが、細かい部分から全体を作り出す構成感が不足で、やや荒っぽい感じ。細部への丁寧なアプローチが欲しい。
ブラジャーク弦楽四重奏団
チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第1番
ボロディン 弦楽四重奏曲第2番
チェコ伝統の素朴で柔らかい弦の響きが印象的。
4人が共通した音のトーンを有しているので、調和がとれたアンサンブル。
鋭さと大きさを追求するのでなく、調和と充実した響きの追求。
ウラルフィルハーモニー管弦楽団
井上道義(指揮)
ショスタコーヴィッチ 交響曲第12番
大きいスケールのオーケストラ。
編成も大きいが、金管、打楽器の爆発的な迫力は相当なもの。
この交響曲のスペクタクルな面白さを存分に発揮。井上監督も大きいおもちゃを手に入れたようで、実に楽しそうでパワフルな指揮。
台北市立交響楽団
ドリアン・ウィルソン(指揮)
アンドレイ・コロベイニコフ(P)
チャイコフスキー
バレエ「眠りの森の美女」よりパ・ダクション、
ワルツ
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番
ドリアン・ウィルソンという指揮者、大きいスケールの持ち主。オーケストラから底力のある分厚い響きを引き出す。
チャイコフスキーはバレー音楽としてはやや重すぎる感もあるが、雄大な表現は見事。
ピアノのアンドレイ・コロベイニコフは、オケの圧力にやや押され気味。ソロリサイタルの時に比べ、やや弾きにくそう。指揮者もピアニストにもう少し配慮が欲しかった。
5月4日の演奏会から
トリオ・ショーソン
ラフマニノフ
悲しみの三重奏曲第1番「偉大な芸術家の思い出に」
アレンスキー
ピアノ三重奏曲第1番
2曲とも追悼の音楽。曲想も明らかにチャイコフスキーの同名の三重奏曲からの影響を強く感じる。
アレンスキーは初めて聴く作曲家。抒情的な魅力を感じるが、特異な個性は感じられない。
トリオ・ショーソンは感情をあらわに表した熱演。
オーケストラ・アンサンブル金沢
山田和樹(指揮) アンドリ・マルケット(Vc)
グリンカ 幻想曲「カマリンスカヤ」
R.コルサコフ「スペイン奇想曲」
チャイコフスキー ロココ風の主題による幻想曲
OEKの円熟した響き。他のオケと比較して聴くと、OEKのレベルがかなり高い事を感じる。大型オケと異なり、室内オケで緻密なアンサンブルを追求してきた結果であろう。
山田和樹のフレッシュで躍動する音楽も魅力的。R・コルサコフ「スペイン奇想曲」での、リズム感の躍動は心躍る。
アンドリ・マルケットのチェロの伸びやかで艶やかな音色が印象的
ドミトリ・マフチン(Vn)
エカテリーナ・デルシャヴィナ(P)
プロコフィエフ ヴァイオリンソナタ第一番
チャイコフスキー 瞑想曲
プロコフィエフの寒々とした心の風景が胸に迫る。
マフチンのヴァイオリンは表現力の強さが魅力的。デルシャヴィナのピアノもしっかりとヴァイオリンを支える。
イーゴ・ポゴレリッチ(P)
ショパン ノクターン
ラフマニノフ ピアノソナタ第2番
バラキレフ イスラメイ(東洋風幻想曲)
今回の目玉の一つポゴレリッチの登場。
本人の強い希望とのことでショパンが追加となる。
何とも形容しがたいピアニスト。
作品を再構築し、自らの編曲としてしまう様な異様さ。ショパンもラフマニノフもポゴレリッチというピアニストの作品となってしまう。
停止するかのような遅いテンポ、一つ一つの音に意味を込めようとする意志。ポゴレリッチでなければ、許されないし又不可能であろう異様さ。
バラキレフでは一転して鬼気迫る様な超絶技巧。
ラメナ・マンゴーヴァ(P)
クバイトゥーリナ シャコンヌ
チャイコフスキー 「四季」より10月「秋の歌」
チャイコフスキー ドゥムカ
ショスタコーヴィッチ 24の前奏曲より
1.2.5.3.6.13.14.10.16.17.21.20番
ポゴレリッチの異様さの後では、マンゴーヴァの個性も普通に聴こえてしまう。
大きな身体から、優しい歌が聴こえてくる。打鍵の強さもその身体なみ。
ショスタコーヴィッチは各曲の多彩な性格を明確に描き出し、ショスタコーヴィッチの多面性を聴くことが出来た。
台北市立交響楽団
ドリアン・ウィルソン(指揮)
チャイコフスキー
「エフゲニ・オネーギン」より ポロネーズ
チャイコフスキー 交響曲第4番
ドリアン・ウィルソンの本領発揮。
4番の交響曲の骨格のしっかりとした、滔々とうねる波のような音楽の流れ、金管と打楽器の咆哮。魅力存分の演奏。
トリオ・ショーソン
チャイコフスキー
ピアノ三重奏曲 「偉大な芸術家の思い出に」
出だしは淡々と主題が歌われるが、曲が進むにつれてピアノの情熱的な歌が全曲を高揚させ、熱を帯びる。
3人が1つの心で、チャイコフスキーの哀歌を雄弁に奏でる。熱い演奏である。
オーケストラ・アンサンブル金沢
井上道義(指揮) ミリャーナ・ニコリッチ(Ms)
プロコフィエフ シンフォニエッタ
プロコフィエフ
カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」より
第6曲「死の原野」
チャイコフスキー
オペラ「オルレアンの少女」よりジャンヌのアリア
「森よ、さようなら」
ボロディン ダッタン人の踊り
スカラ座の歌姫、ミリャーナ・ニコリッチを迎えてのコンサート。
ミリャーナ・ニコリッチは11月にOWK定期でビゼー「カルメン」を歌うことになっているので、その顔見世か。
2曲のアリア以外に管弦楽曲が2曲
プロコフィエフのシンフォニエッタというレアな作品。プロコフィエフらしい皮肉っぽい音楽。
ニコリッチはドラマティックで透徹した歌声。もう少し歌ってほしかった。11月が楽しみ。
ボロディン ダッタン人の踊りは迫力満点、室内オケでもやや増員することでここまでスケールの大きな演奏が出来ることをOEKの実力が示していた。
井上監督のがっちりとした造形が作品の面白さを際立てていた。
ツェムリンスキー弦楽四重奏団
チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第3番
ボロディン スペイン風セレナーデ
ブラジャーク弦楽四重奏団と同じ、チェコの団体だが色合いはかなり異なる。
この四重奏団は、かつてのスメタナあたりを想起させる、鋭く迫力のあるアンサンブルを聴かせる。
チャイコフスキーの大曲を弛緩することなく、緊張感を持って再現。
美しい旋律の歌わせ方と共に、構成ががっちりとした、スケールの大きな演奏を聴かせてくれた。
演奏曲順が発表のものと異なり、とまどいを感じたし、そのためチャイコフスキーの1楽章後に拍手が入ったりして、緊張感が中断されたのは残念。運営上の改善点。 |
|
|
|
|
|
|
|
諏訪内晶子ヴァイオリンリサイタル
2012年4月25日 入善コスモホール
ピアノ イタマール・ゴラン |
|
5年ぶりの諏訪内晶子のヴァイオリンリサイタル。今回はピアノがイタマール・ゴラン
ゴランはコスモホールではお馴染みのピアニスト。かつて、樫本大進、庄司沙矢香、ワデム・レーピン等と協演、圧倒的な存在感を示した名ピアニスト。今回は事前の印象としては、果たして合うかしらと危惧を抱いた諏訪内との協演。
結果としてこの危惧は、杞憂で、ゴランのがつちりとして、挑戦的なピアノが、諏訪内の新しい境地を引き出していたように思える。
プログラムは前半がシューマンの「ヴァイオリンソナタ1番」、ベートーヴェンのソナタ5番「春」、後半がバルトーク「ルーマニア民族舞曲」、エネスコ「ヴァイオリンソナタ3番『ルーマニアの民族様式で』」
前半がドイツ、後半がルーマニアというきちんと色分けされたプログラミング。
以前は優等生的、模範的演奏でありながら、何か主張が乏しいと思えた諏訪内だが、今回はかなり趣が異なり、この作品はこの様に主張したいという熱い声が聴こえてくる演奏だった。これまで、越えられない壁を一つ乗り越え、新たな境地に踏み込んだと感じられる演奏。
最初のシューマン。古典的な形式の中に、ロマン的な情熱が込められた作品だが、その調和が均整良く整い、シューマンの暗い情熱が聴こえてくる演奏。1楽章冒頭の低音のうつうつたる主題が心を奪う。ピアノのゴランの強い主張と堅固な構成感がヴァイオリンをがっちりと支える。
次のベートーヴェン。昨年の庄司紗矢香の個性的な演奏が印象深いが、諏訪内はそれほど踏み込まず、ベートーヴェンの音楽の古典的構成と、雄大なスケールを正面から描こうとした様な演奏。ただ、以前の諏訪内のベートーヴェンの様に淡々としたものでなく、激しさと強さを求め、描き切ろうとした熱い思いが感じられた。ゴランのピアノの力強い堅固な打鍵による雄大なピアノもそれを支える。ベートーヴェンの雄大な世界が満ち満ちた演奏。
後半はバルトークの「ルーマニア民族舞曲」第一曲冒頭のピアノの強烈な一打にまず引きこまれる。ゴラン、物凄い主張の激しいピアニストである。そのピアノに応えるかのように諏訪内も激しく熱い演奏。面白いのは、目を閉じて聴いていると、渦巻く様な激しさに満ちているのだが、目を開けて見ると、ゴランは身体全身でピアノに立ち向かっている様な激しさが見られるが、諏訪内はその音とは反し、比較的冷静に、淡々と演奏している。そのあたりが、このヴァイオリニストの特長であり、又凄さなのだろうか?
民族色溢れる小品6曲からなる魅力的な作品だが、各小品の特長ある面白さと、激しい舞曲のリズムと5曲に聴く素朴な歌など、この作品の特色を色濃く描き出していた。
最後のエネスコのヴァイオリンソナタ第3番。1楽章のメランコリックで暗いが、色濃い民族色に溢れた歌、2楽章の清冽な歌と中間部の激しい盛り上がり、第3楽章の生き生きとした舞曲とコーダの堂々としたエンディング、初めて聴く作品だが、魅力溢れる作品。同時代のヤナーチェクのヴァイオリンソナタとならぶ、傑作であろう。
ここでもゴランのピアノの激しさと繊細さの対比が見事。諏訪内のヴァイオリンも豊かに歌い、第2楽章のフラジオレットが極めて印象的に響く。
3楽章のエンディングは高揚が極限まで高まり、ヴァイオリンとピアノの強奏で堂々と全曲が閉じられる。
内容の濃い、訴えかける力の強い演奏で、これまでの諏訪内の印象が一変させられた。
アンコールは3曲。クライスラー、ブロッホ、ドヴュッシー。
特にブロッホの「祈り」は壮絶。深い瞑想から、烈しい慟哭にいたり、深い祈りで終わる。これもヴァイオリン、ピアノとも主張の強い演奏。
今回はピアノにゴランを迎え、プログラミングも訴求力の強いものとなり、諏訪内の新しい境地を聴くことが出来、興味深かった。以前の彼女であったら、どこかで行き詰っていただろうが、今回の演奏でこれからの演奏がどの様に変貌するかの楽しみが増した。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第319回定期演奏
2012年4月13日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 広上 淳一
ピアノ 河村 尚子 |
|
広上淳一は私がOEK定期に通い始めてから3度目の登場。最初の2006年故岩城監督の逝去直後の演奏会でのモーツァルトのグランパルテータの名演が思いだされる。
今回も非常に凝ったプログラムで。前半がアッテルベリ「ヴェルムランド狂詩曲」、ヒンデミット「4つの気質 主題と4つの変奏曲」、後半がシューベルト交響曲第2番。
広上淳一の音楽の特徴は、オーソドックス、厚みのある重厚さ、そして集中力の高さというところだろうが、今回の定期も将にその通りの演奏。
選曲にしても、一見特異であるようながら、ドイツ的正当さを正面に打ち出した選曲と感ずる。
2006年の、モーツァルト、2009年のメンデルスゾーン、ハイドン、そして今回のヒンデミット、シューベルトとドイツ音楽の王道の選曲だ。ただ、それらの作曲家の隠れた名曲ともいえる、通常聴くことの少ない作品を取り上げるところに特長を見ることが出来る。
といいながら今回はアッテルベリという馴染みの全くない作曲家の作品が最初に演奏された。20世紀スエーデンの作曲家ということだが、作風は穏健で保守的。イギリスのディーリアスを想起させるところもある。
際立った個性も無いが、心地よい音楽の流れ。北欧らしい透き通った空気が聴こえてくる。編成は金管にトロンボーンも使用され、ティンパニーは使われず大太鼓とシンバルという、やや変わった編成。
ヒンデミットの「4つの気質 主題と4つの変奏曲」。ピアノ独奏と弦楽合奏による作品だが、構成の大きい作品。
ヒンデミットはドイツロマン派の終焉の作曲家だが、R・シュトラウス等と異なり、ブラームスの流れを継ぐ、やや晦渋ともいえる作風を持つ作曲家で、演奏によっては退屈ささえ感じさせる様な作品が多いが、今日の演奏はヒンデミツトの音楽の個性的な面白さが十分に表現されていた。
最初に3つの主題が提示され、その主題を用いて4つの楽章とも言える4つの変奏曲が展開される。
各楽章はそれぞれ、「黒胆汁質」「多血質」「粘液質」「胆汁質」が表現されており、それぞれの気質の特徴が音楽によって表現される。
ヒンデミットの音楽の持つ構造的な緻密さと、響きの独特な重さとハーモニーの厚さ、そして独奏ピアノの表現力の多彩さ。それらが混然となり、ドイツ後期ロマン派の最後の暗く重厚な世界が展開されていた。
ここでは、OEKの弦の厚ぼったい響きが効果的であり、そこに河村尚子の表現力豊かなピアノが協奏曲風にからみ、ヒンデミットの音楽の構造的な面白さが際立っていた。
河村尚子のピアノのしっかりとした打鍵に裏付けられた表現力が秀逸。
後半はシューベルトの交響曲第2番。前半のヒンデミツトとがらりと変わり、古典的明快さと優しく、喜びに溢れた歌が湧き出てくるような魅力的な作品。後期の代表作、未完成、9番にも劣らない魅力的な交響曲。
1楽章は堂々とした序奏に始まり、その後はシューベルトらしい抒情的で感傷的な歌が溢れる。
4楽章のたたみかける様な喜びに満ちた劇的な迫力は、後の9番の4楽章を思い起こさせる。
広上淳一の指揮は、表情の豊かさ、構成の確かさ、そしてシューベルトの音楽で大切な瑞々しい流れに溢れ、この交響曲の魅力を存分に描きしていた。
第2楽章の管楽器にもう一つのアンサンブルの磨きと、奏者の自発的な歌が聴けたらと言う欲も感じたが。
アンコールに2楽章がもう一度演奏された。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第318回定期演奏会
2012年3月23日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
独奏
ヴァイオリン アビゲイル・ヤング
チェロ ルドヴイート・カンタ
オーボエ 加納 律子
ファゴット 柳浦 慎史
オーボエ カイ・フレブゲン
クラリネット ギュンター・フォレストマイアー
ファゴット アレクセイ・トカチャク
ホルン ザボルクス・ツェンプレーニ |
|
今回のマイスターシリーズ定期はOEKの最も得意とする、ハイドン、モーツァルトの古典派の作品。
そして、なかなか聴くチャンスの少ない2曲の協奏交響曲。
独奏者が、ハイドンがOEKのトップ奏者、モーツァルトがドイツ・バンベルク交響楽団のトップ奏者という、ユニークな組み合わせ。後半はハイドンの交響曲第94番「驚がく」
2つのオーケストラの独奏者が2つの協奏交響曲で競演するというのは実に珍しいこと。
最初のハイドンの協奏交響曲は、独奏者がヴァイオリン、チェロの弦楽二人と、オーボエ、ファゴットの木管二人の組み合わせ。協奏交響曲という分野は、その名の通り協奏曲でありながら、全体のアンサンブルが重視されるので、この様に同じオーケストラの団員で演奏される例が多い。その点、このハイドンはその典型。各奏者は巧みでありながら、全体のアンサンブルと音の個性という点で一体である。
それに比較し、次のモーツァルトは全く異なるオーケストラの奏者との協演となるので、協奏曲としての面白さも聴ける。
その様な意味で、この2つの協奏曲の演奏は実に面白いもの。
最初のハイドン。ハイドンの作品としては実に優美なもの。各独奏者は比較的自制的で、オーケストラとの調和を図っている様。その中でヴァイオリンが、やや目立っているという印象。ヤングのヴァイオリンは1楽章では、ややその楽器の所為か(ストラディヴリウスであると思うが)、やや華美に過ぎ、全体から浮き出している様にも聴こえたが、3楽章に入り、音が柔らかく落ち着きだした。チェロは底支えとともに、時に早い技巧的な聴かせどころも十分。木管の二人も、実に落ち着いた優美な響き。井上監督のメリハリと優しさを兼ね備えた古典的な端正さに溢れたオーケストラの響きと、独奏者群が一体となり心地よい調和を作り出していた。
次のモーツァルト。モーツァルトの作品かどうかの真贋が話題の作品だが、メロディーの優しい親しみやすさなど実に魅力的な作品。
以前、デュトワのモントリオール交響楽団が入善でこの作品をとりあげ、デュトワ・モントリオールらしい華麗な響きのモーツァルトの演奏を聴かせてくれたのを思いだすが、この日の演奏はそれと違う、落ち着いた響きのモーツァルト。
出だしの弦楽器の低い音域の主題から、落ち着いた調和が聴こえてくる。
バンベルグ響の4人のトップ奏者、さすがという演奏。各奏者の個性が凄い。オケの団員でありながら、それぞれ主張する音楽を持っている。個性のひらめきが素敵な音を生み出し、それが一つのアンサンブルとなつていくのは、ぞくっとする様な快感。オーボエとクラリネットの対話、それを支えるファゴットとホルン、巧みな技巧に支えられたしっかりとしたアンサンブル。
オーケストラも独奏者群の響きに触発され、オケとしての個性的な響きを紡ぎだしていた。
協奏交響曲という分野は名手が揃わないと演奏が難しい分野で、それ故にオーケストラの団員が独奏者を務める例が多いのは、先に記したとおりだが、この様に異なるオーケストラの奏者が独奏者となると、協奏としての面白さが浮き出るということを認識させてくれた。その意味で貴重な体験。
プログラム後半は、ハイドンの交響曲第94番「驚がく」
井上監督のハイドンはこれまでも何回か聴いており、監督のある意味、力を入れている作曲家でないかと思うが、この日の94番も力の入った演奏。
今回は古典ということで、バロックティンパニーを使用していたが、この演奏ではその乾いた強烈な響きが印象的。
全体としては、きびきびとした演奏で、端正さと優美さを兼ね備えた演奏と言えるが、部分的には井上節とも言える様な独特のアクセントをつける部分があり、その点が面白い。3楽章メヌエットの中間部の微妙なテンポの動かし方、最終楽章終結部のアッチェランドとティンパニの強打などその典型で、井上節ハイドンの面白さ。
「ハイドンはこういうところが面白いんだよ。」というマエストロの声が聴こえるよう。
第2楽章の例のびつくりの部分では、一瞬場内の照明を消しびっくりさせるなど、監督らしいパフォーマンスと茶目っけ。
アンコールは武満徹「他人の顔」からワルツ
この日定年退団の二人、ヴァイオリンの大沼さん、フルートの上石さんの紹介があった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第316回定期演奏会
2012年3月3日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
ソプラノ アンナ・シャファジンスカヤ
バス ニコライ・ディディンゴ |
|
この日のプログラム、非常に刺激的で知的なもの。
前半がシチェドリン編曲によるビセー「カルメン」組曲。後半がショスタコーヴィッチの交響曲第14番。
第2次世界大戦後のソヴィエトの作曲家二人の作品。そして、共にソヴィエト政府による社会主義リアリズムの芸術への干渉の嵐の中をかいくぐり、生き抜いてきた芸術家。
ということで、ある意味「音楽と政治」という難しいテーマを掲げたプログラムともいえよう。
そして。音楽として見てみると、この日の編成はどちらも、弦楽器と打楽器のみで、管楽器は無し。
幾重にも知的に構成されたプログラム。
前半のシチェドリン。原曲はビゼーのカルメン。
シチェドリンの妻で名バレリストのプリセツカヤの要請で作曲されたバレー音楽からの抜粋。
編曲とはいうものの、歌劇「カルメン」の題材を用いシチェドリンの意のままに新しく作曲された作品というのが適当か。
バレーの筋も、歌劇の筋が基本となっているようだが、音楽自体は個性的なもの。
まず、編成。この日は正面前面に多数の打楽器が配置され、その後ろにヴァイオリン、ビオラ群、そして一番後ろにチェロとコントラバスを一列に配置した独特のもの。
この時代では、ウェーベルンがやはり個性的な編曲を多く残しているので、そのあたりも想起させる。更に音楽の個性としては、クルト・ワイルあたりの音楽に似通っている感もある。
全体的には世紀末的な、ある意味退廃的な臭いを感じさせる音楽。あの時代のソヴィエトであえてこの様な音楽を発表したシチェドリンの音楽での抵抗の姿勢を見ることができる。
打楽器の多様な使い方が特に効果的。特に序奏でベルが「ハバネラ」を断片的に鳴らす場面は、全曲の悲劇性を象徴している様で効果的。最後の部分でこの「ハバネラ」が効果的に回想されるので、全曲のシンボル的存在と感じさせる手法。
演奏は、弦楽器群の硬質な響きが印象的。そして、各曲の色彩的で個性的表現の面白さを井上監督は的確に描き出していた。原曲があまりにも有名な作品が多いので、それがどの様に料理されているか、聴きとることが出来るので、そのあたりの面白さも抜群。時にはにやりとさせられる部分も多い。
打楽器群の熱演に拍手。
休憩を挟んで後半は、ショスタコーヴィッチ交響曲14番。ショスタコーヴィッチ晩年の問題作。1969年の作曲なので、わずか40年程前の作品。
ソプラノとバスによる11の歌曲集とも言える作品。編成はやはり個性的。弦楽器群と打楽器のみで、管楽器は無し。
打楽器群はシチェドリン同様、舞台前面に配置されているが、シチェドリンよりやや小ぶり。
作品全体が、暗い色彩に覆われている。詩は、スペイン、ロシア、フランス、ロシアの4人の詩人の詩によるとされている。いずれの詩も、死をテーマとし暗い色彩に彩られている。歌詞は正面オルガンBOXの下の電光板にて示されるが、いずれも即理解するには難解な詩。
1曲目の弦楽器群による、痛切なテーマで開始。無調を基本としているようだが、全体は複雑なテクスチャーよりも、非常に透徹したシンプルさで覆われている。
各所でヴイヴラフォン、シロフォン、カスタネット、チェレスタ、ベル等の打楽器群が効果的に使用されている。
鋭い悲痛な叫びと、悲痛を底に沈めた静謐さが全曲を支配する。
弦楽器は低音部、ビオラ、チェロ、コントラバスに旋律が多く割り当てられ、より深い暗さに包まれている。
この日の独唱者、ソプラノ、バスとも大変な熱唱。ソプラノのドラマティックな叫び、バスのロシア独特の低く深い響き。
そして、打楽器群の効果的な響きと、チェロ、コントラバス等弦楽器群の暗く、厚い響き。
選ばれた詩の中には7章、9章など、明らかにショスタコーヴィッチの生涯にわたるファシズム・ソヴィエト当局との戦いを象徴するものがあり、作曲者晩年の集大成とも言える音楽が全曲に溢れている。その意味で、ショスタコーヴィッチの音楽の集大成と聴くことができる。
この後15番で、又別の透明さを示しながら、生涯を閉じるわけだが、激動の時代を生き抜いた音楽家の最後の痛切な告白を聴くようである。
この日の演奏は、この作品のその様な側面が強く描き出され、心に強く迫った。指揮者、独唱者、オーケストラ一体となった劇的な演奏。
最後の部分、11章で冒頭の低音の静謐な主題が戻り、最終章は突然の強奏で終結。強烈な余韻が残された。
ショスタコーヴィツチの大作であり、問題作でありながら、滅多に演奏される機会の無い作品を取り上げてくれた井上監督に感謝。恐らく北陸では初演ではなかろうか?、 |
|
|
|
|
|
|
|
南西ドイツ放送交響楽団バーデ=バーデン&フライブルク演奏会
2012年2月19日 石川県立音楽堂
指揮 フランソワ=グザヴィエ・ロト
ピアノ 萩原 麻未 |
|
今年最初の本格的な外国オーケストラの演奏会。
何といっても注目は、ジュネーブ国際コンクールピアノ部門2010年優勝の萩原麻未の登場。
この日のプロは、前半がその萩原麻未を迎えてのラヴェル「ピアノ協奏曲」、後半がマーラー交響曲第5番。
ラヴェルのピアノ協奏曲は、何度聴いても魅力溢れる作品。管弦楽の魔術師ラヴェルらしい輝きと色彩感に溢れた管弦楽をバックにピアノが実に洒落た、そしてこれも輝きと、ある意味古典的な端正さを繰り広げる。
この日の萩原麻未のピアノは十分にその様なこの作品の魅力を描き出していた。
まず、ピアノのエレガントで柔らかい響き。1、3楽章はピアノの打楽器的な扱いも多いが、そこはあまり強調せず、この協奏曲の端正な美しさを描き出そうとした様に聴けた。
パリ音楽院に学んだとのことだが、なるほどフランスのピアノ演奏の伝統を正統的に受け継いでいるようだ。
音のひとつひとつに深い意味を込めて、丁寧に、情感を籠めて紡ぎ出す音楽は実に魅力的。
第2楽章の木管との絡み合いは絶品であった。
アンコールのショパンが又名演。ポーランドの土の匂いと、フランスの気品のあるエレガントさが混じり合った独特のショパンの世界が見事に描き出されていた。ショパンのワルツ独特の三拍子が見事に歌われていた。
聴衆にお辞儀をする際や、その容姿はまだ初々しい若手の印象だが、ピアノは円熟した大人のもの。
管弦楽も、リズムはやや重くはあったが、ピアノとの技巧的なやりとり、第2楽章のフルート、コールアングレのしっとりとした音色など、この作品の魅力を存分に引き出していた。
ロトという指揮者、堅実な指揮者という印象。
さて、後半のマーラー。
コントラバス6本の巨大な編成。
しかし、マーラーの演奏は難しいな、ということの再認識。
非常に堅実、堅固な演奏で、マーラーの交響曲の複雑なテクスチャーの細部迄、クリアーに演奏している。
ダイナミックな面も十分。計算しつくされたような演奏。
しかし、それでいて、マーラーの肉声が聞こえてこない。
一つ一つの楽譜に描かれた音は、正確に演奏され、楽譜に指示されたことは忠実に再現されているのだが、それでいて、マーラーの音楽の叫びの様なものが聴こえてこない。ダイナミックレンジは広いのだが、それが音楽の広さとなっていないで、ただ音の強弱に聴こえてしまう。
マーラーの音楽の持つ多様性、、叫び、不安、卑俗な歌、世紀末の退廃した雰囲気。それらが混然としてマーラーの世界が築かれていると思うが、それらの複雑さが聴こえてこないで、一本調子の、ただ音の強弱の鋭い、堅固な世界になっており、マーラーの複雑な心情が聴こえてこない。
勿論、マーラーはどろどろととした情念の様な演奏が総てだとは思わないが、この演奏では細部に対する丁寧さにもやや欠けているきらいがある。それは、技術的な問題というより、楽譜の持つ連続した意味を丁寧に解き明かしていくという作業の不足の様に思える。
部分的には非常に面白く、美しい部分が有るが、それが全体としての音楽のスケールの大きさにつながってこない。
というわけで、私にとっては心に迫るマーラーとはなってこなかった。
古楽を志向する人にありがちな、ひとりよがりの傾向もありと感じる。
アンコールはプロコフィエフの「ロミオとジュリエット」組曲から。このアンコールはロトの特徴にぴったりの様で、重々しく激しいプロコフィエフサウンドを聴かせてくれた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第314回定期演奏会
2012年1月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮・ピアノ ラルフ・ゴトーニ |
|
ラルフ・ゴトーニは2008年、2010年に続いて、OEK定期3回目の登場。それ以前に、故岩城監督の代演として。オーストラリア公演を振っているとのことで、OEKとは4度目の共演。
2008年、2010年とも聴いているので、その時の記録を振り返ってみると、独特のプログラムで、なおかつ安定した音楽をOEKから引き出していたのが記憶に蘇る。両定期とも、現代音楽と古典とを組み合わせた点が独特だった。
今回は2008年に続いての弾き振り。そして、マイスターとフィルハーモニーの両シリーズを振る。マイスターでは、古典作品を揃えたどっしりとしたプロ。3月のフィルハーモニーシリーズの定期では、古典と現代を入れた個性的なプログラムとなっている。
今日のプロはベートーヴェンの「コリオラン」序曲、ゴトーニの弾き振りでピアノ協奏曲第3番、後半がシューベルトの交響曲第6番。プレトークで池辺晋一郎氏が述べていたように、ハ短調とハ長調の調性の作品。そして、堂々たる古典派のプログラム。
この日の楽器配置が面白い。かつて、日本のオーケストラで主流だった、第一Vn、第二Vn、Vra、Ce、Cbという左から右へ高音弦~低音弦と並べた編成。最近は対向配置、あるいはVraを右端に置く配置が多く、この様な配置は珍しい様に思える。それだけに、古くからの聴衆には懐かしく思える配置。
さて、ゴトーニという指揮者、北欧フィンランドの出身であるが、作り出す音楽は落ち着いた響きの分厚い重厚なもの。これは、イギリスでの活躍が長かった影響であろうか。
最初のベートーヴェンの「コリオラン」序曲の序奏の響きから、重い存在感を感じさせる。それが、この序曲の悲劇的な性格を強く打ち出し、説得力のある演奏。OEKの弦から重々しい響きを見事に引き出していた。管楽器に一層の伸びやかさがあれば、尚印象深い演奏となっていただろう。
次のベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第3番」。ここではゴトーニの弾き振りが注目。
ピアノはオーケストラ中央に縦に置かれ、ゴトーニは客席に後ろ向きとなる形でオケを指揮。ピアノは蓋が取り払われていた。オーケストラとの調和を重視した配置といえよう。
演奏は将にオーケストラとピアノの調和が絶妙に取られていた。ゴトーニはピアノを弾きながらも、かなり細かい指示をオーケストラに出していた。故に、この作品のオーケストラとピアノの語り合いという性格が如実に表現され、統一感のある古典的な端正さと、ロマン的な歌が溢れた演奏となっていた。ピアノが歌うとオーケストラがそれに絶妙にこだまする、細部までオーケストラとピアノの呼吸があった、気持ちの良い演奏。
ティンパニーにバロックティンパニーが使用されていたようだが、乾いた音ではなく、ずしりとくるような重さが印象的。
1楽章展開部のピアノが歌い、木管がそれに応える部分の両者のぴったりとした呼吸は、弾き振りの魅力。
協奏曲の面白さは、独奏楽器と指揮者・オーケストラの丁丁発止のやりとりも面白い一面だが、今日の演奏はそうではない調和の魅力を存分に聴かせてくれた。
品格と歌に溢れたベートーヴェンの協奏曲。
アンコールに応え、ゴトーニが一曲。シューベルトの歌曲をブゾーニが編曲したもの。これはまたシューベルトの優しい歌、しみじみと響く歌が見事。
休憩を挟んで、シューベルトの交響曲第6番。
比較的演奏されることの少ない作品だが、端正さと瑞々しさが溢れた作品。4月には、広上淳一が2番の交響曲を取り上げているが、未完成や8番だけが多く取り上げられる中で、シューベルトには他にも魅力的な交響曲が多いので、それらを聴かせてくれるのは嬉しい限りである。
ゴトーニはここでも、バランスの良い響きをOEKから引き出していた。特に弦楽器群の厚い響きがそして、その中に浮かび上がる管楽器の歌が魅力的。
形式感がきちんとし、その中でシューベルトの歌が溢れているのは、この交響曲の大きな魅力。それをゴトーニは存分に聴かせてくれた。
欲をいえば、シューベルト独特の弾ける様な生き生きとした躍動感が出ていたらとは感じた。
ゴトーニという指揮者、今回も実力のある正統的な指揮者という感を強く印象付けてくれた。OEKとの相性も良さそうである。 |
|
|
|
|
|
|
|
アドリアン・ユストゥス ヴァイオリンリサイタル
2012年 1月17日 名古屋 宗次ホール
ヴァイオリン アドリアン・ユストゥス
ピアノ ラファエル ゲーラ |
|
かつて、日本の若手ヴァイオリニィストのホープであった黒沼ユリ子氏が、メキシコでヴァイオリンアカデミー「アカデミア・ユリコ・クロヌマ」を設立、数多くのヴァイオリニストを育ててきたが、その中の逸材、アドリアン・ユストゥスが東京他数か所でリサイタル、名古屋でも開催とのことで、ユリ子氏からもお誘いを受け、名古屋へ出かけた。
黒沼ユリ子氏とは、私たちの大学時代にサークルの自主コンサートを開催、その第一回コンサートにお招きしたのが御縁で、40数年経た今も親しくお付き合いをさせていただいている。
黒沼ユリ子氏は、現在はメキシコに定住、メキシコと日本の文化交流に大きな足跡を記し、メキシコの優れた音楽家・団体を日本に招へいするなど、メキシコの音楽文化の発展に大きく寄与してこられている。
最近では3年ほど前、メキシコの音楽家のみによる、歌劇「夕鶴」をメキシコシティーで公演、その引っ越し公演を日本で行うなど、とてつもない企画を行う情熱の音楽家である。
そのユリ子氏が高く評価し、世界に是非羽ばたかせたいと熱望するヴァイオリニィストがアドリアン・ユストゥス。
今回が4回目の来日となると思うが、今回はパガニーニの「24のカプリス」全曲演奏という大きなプログラムを掲げての登場。
全曲で1時間30分以上の無伴奏の大曲、そしてこれ以上の難曲はないであろうという超絶技巧の連続。彼の日本公演への大きな意気込みを感じさせるプログラム。更にプログラムには、ドヴュツシーのソナタも組み込まれており、巨大なプログラムとなっていた。
パガニーニの「24のカプリス」、有名な13番、24番等数曲はアンコールピース等で聴くことも多いが、生で全曲を通して聴くという経験はまずないし、その様な冒険に挑戦するヴァイオリニストも稀であろう。そして、1時間30分以上を聴く者を集中させ、酔わせるというのはヴァイオリニストにとって至難の技であろう。
ところが、ユストゥスはそれを当り前の様にこなしてしまう。そして、長い時間があっという間の時間である様な音楽世界を展開する。作品の途中に彼自身の言葉で作品を紹介するのだが、それも音楽の内で、語学の素質の無い私には断片しか理解できないのだが、彼の言葉がヴァイオリンの一部の様にさえ聴こえる。熱い語りである。
それにしても、このパガニーニの作品の中に展開される、ヒューマンな情熱はなんと生々しく魅惑的であるのだろうか。赤裸々なパガニーニの告白を聴く様でさえある。超絶技巧が表現するための絶対的な条件であることがパガニーニにとっては必然であったことを確認。選ばれた者しか、この巨大な音楽世界を表現することを許されないであろう。
ユストゥスは、それを将に実証して体験させてくれた。
技巧がこの作品の必然であることが彼のヴァイオリンによって語られる。
それにしても、何という瑞々しくも豊かに息づく音楽であろうか。歌うことが楽しくてしょうがない、そして聴衆全員にこの作品の魅力を共有しようではないかという様な熱い語りかけ。
今まで聴いてきた多くのヴァイオリニストが小さく見えてしまうような、あっけらかんとしたスケールの大きさ。
有名な13番の語り口の巧みさは、ユストゥス自信がパガニーニになりきり、語りかけている様な生々しさがあった。
テンポも歌わせ方も自由なのだが、わざとらしさの少しも無い自然体。
演奏曲順は最初と最後が1番と24番以外はユストゥス自身の構成により自由に並べられている。
長くもあつという間の時間が過ぎ、最後の24番の圧倒的な響き。ここでパガニーニはそれまでをまとめ上げる様な壮絶なテクニックを要求。両手によるピチカートなど、神がかり的。しかし、それはユストゥスには何でもないようにさえ見える。技巧を楽しんでいるかのような余裕。技巧が歌うために必要な要素であると言わんばかりの豊かな歌。
圧倒的な盛り上がりで全曲を閉じる。途中数分の休憩のみ、体力も大変なものである。聴く方もヘトヘト。しかし、充実した余韻にふける。
そういえば、無伴奏なのにピアノが蓋をあけたまま舞台中央に陣取っている。黒沼ユリ子氏によると、ピアノにも共鳴させ歌わせるとのこと。そうか、そういう方法もあるかと納得。
始まりが6時45分、ここで既に時間は8時40分。休憩の後更にドヴュッシーのソナタ。
ここで少し疑問。ドヴュッシーを最初に持ってくるべきではなかっただろうか?
あのパガニーニの大曲の後では、さすがのドヴュッシーも小さく聴こえてしまう。それに、聴く方も少々疲れ気味。
しかし、これも又独特のドヴュッシー。フランス的エスプリよりも、図太く、大きなスケールのドヴュッシー。
ピアノ伴奏のゲーラの詩情豊かな寄り添い。素敵なピアニストとである。昨年の紀尾井ホールでも同様のコンビだった様で、昨年のCDを聴いてみるとこのピアニストのすっきりとした素直なな音楽性が一層印象的であった。
プログラムの解説も西野裕之氏の解説に加え黒沼ユリ子氏の個性的な解釈の解説がつき、作品の理解を助けてくれた。
アンコールはファリャのスペイン舞曲、サンサーンスの「序奏とロンドカプリチオーソ」、そしてメキシコ民謡による組曲。
ここでは、将に自由闊達。最後は一緒に楽しみましょうという様な楽しさの極致。
聴く者を音楽の魔法の世界へ引きずりこんでくれた3時間。それにしても、リサイタルで3時間?
時計を見た時はびっくりであった。タフな方である。
それにしても、この様なヴァイオリニストがメキシコは別にして、世界的には未だ無名に近いというのはどの様なことだろう?
何か、音楽ジャーナリズムの偏り、作られた商業音楽の世界の閉鎖性を考えてしまう。
私たち聴衆にもっと開かれた音楽世界の提供があって然るべきでなかろうか?
もっとも、その責任の一端は私たち聴衆にもあるのだろうが。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第313回定期演奏会
2012年ニューイヤーコンサート
2012年1月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 山田 和樹
ピアノ モナ=飛鳥・オット |
|
2012年初のOEK定期。とはいうものの、定期の新年は10月からなので、今期半ばというところか。
恒例の館長挨拶では、昨年の東日本大震災の2つのチャリティーコンサート、4月の仙台フィルを招いてのもの、11月のチッコリーニのコンサートの2つを特筆するものとして取り上げ、今年は、ハーディング、ミンコフスキー等がOEKを振ることが紹介されていた。
今回は若手の二人、指揮者の山田和樹、ピアニストのモナ=飛鳥・オットの登場。
プログラムはモーツァルト歌劇「魔笛」序曲、グリーグの「ピアノ協奏曲」、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」というもの。ニューイヤーコンサートと銘打っているが、ガラコンサートではなく、しっかりとしたプログラムによるコンサート。3年前の2009年も、ベートーヴェンを中心としたコンサートでこの時はピアノ協奏曲5番「皇帝」(今日のモナ=飛鳥・オットのお姉さんのアリス・沙良・オットが独奏)、交響曲7番というものだった。その後2年間ガラコンサートが続いたが、今年はオーソドックスなプログラミングに戻った。
さて、この日の注目は何と言っても若手二人の協演。
オーケストラの配置はOEKの通常とは異なり、対向配置でなく、第一・第二Vn、チェロ、ビオラ、ビオラの後ろにコントラバスというもの。ということは、配置からしても山田和樹は近年主流のピリオド的な音楽づくりではないということだろう。
最初のモーツァルト歌劇「魔笛」序曲。序奏の分厚い和音がホール一杯に響き渡り、一気にモーツァルトの音楽の世界に引き込んでくれる。キビキビとして、響きは古典的な落ち着いた演奏。
次がモナ=飛鳥・オットを迎えての、グリーグのピアノ協奏曲。出だしの華やかなパッセージからして、豪壮華麗な印象を持ちがちなこの作品だが、実際は北欧的な透明な抒情に溢れた作品と思える。そのあたりをモナ=飛鳥・オットは丁寧に描き出していた。弱音の美しさが印象的。大変丁寧な演奏ではあり、部分的にははっとするような瞬間も訪れるのだが、残念ながら彼女自身のピアノの肉声が聞こえてこない。おとなしいのだ。楽譜をミスなく、楽譜の指示通りに美しく演奏すること以上に、楽譜に描かれた作曲者の思いをどのように受け止め表現し、自分の声で聴衆に伝えていくか、そのあたりがまだ希薄であるように思える。これは、お姉さんのアリス・沙良・オットの時も感じたことで、もっと冒険をしても、違う言葉でいえば自己主張があっても良い様な気がするのだが。でも、これが又彼女の個性なのだろうか?
伴奏の山田和樹はメリハリをきっちりとつけた、明快な演奏。
アンコールにシューベルト・リスト編曲の「セレナーデ」
さて、この日の後半は大曲、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」。若き山田和樹(そういえば、かつての大御所山田和男に比してヤマカズ2世と呼ばれているそうだが。)がこの大曲をどの様に表現するのか、興味津津であった。
この日、不思議なことが、私の耳には第2楽章から起こった。第1楽章は正直なところ、可もなし、不可も無し、平凡な演奏。この演奏に50分余りつきあうのは、少々しんどいかな、提示部の繰り返しをしないだけに早く終わるかな、などと、不謹慎なことを考えていた。
ところが、第2楽章が始まると、私の耳は点?となった。そのテンポの取り方にもよったのだろう。第一楽章からは、想像できない、遅いテンポで始まった。ここから、オーケストラの音も変わったように聴こえた。軽い音ではない、身体の底から音を絞り出している様な。
葬送行進曲であるから、遅いテンポであることは当然なのだが、その当然さと異なる山田和樹の肉声をオーケストラを通じて聴く様な生々しさ。
この楽章からオーケストラもただ楽譜を演奏しているのではなく。自らの自発的な意思でベートーヴェンを表現しようとしている様に、私には新鮮に聴くことが出来た。指揮者の表現意欲が、オーラの如くオーケストラに火をつけた様な状況というと、大袈裟であろうか。
第3楽章、第4楽章にもそれは継続され、生き生きとしたベートーヴェン像が展開された。この様な状況だと、多少のアンサンブルのミスも気にならず、大きな音楽の流れの中に身を委ねることが出来る。
4楽章の変奏曲の管楽器の生き生きとした響き、そしてコーダに至るスケールの大きさ。
この様な経験は初めてであった。不思議な指揮者である。時に本番でとてつもなく大きな演奏をする、しかしそうでない時もある、こんなタイプの指揮者なのだろうか?かつての巨匠の時代の様に。
昨年6月のブトリーの病気による代演の時の演奏とは明らかに異なる彼の個性を聴くことが出来た。
アンコールに8番の第2楽章。
山田和樹は今年スイス・ロマンド管弦楽団の主席客演指揮者、日本フィルの正指揮者に就任するとのこと。忙しくなるのだろうが、年1度程度はOEKも振って貰いたいものだ。そしてまた、マジックを聴かせてほしい。 |
|
|
|
|
|
|
|
ウィーン・ヨハンシュトラウス管弦楽団 ニュー・イャー・コンサート2012
2012年1月8日 オーバードホール
管弦楽 ウィーン・ヨハンシュトラウス管弦楽団
指揮 ヨハネス・ヴィルトナー |
|
2012年最初のコンサート。今年はどの様な感動が待っていてくれるのだろうか。そのためにも平穏無事でな年であってほしいものである。
オーバードホールのニューイヤーコンサート、例年は日本人演奏家によるガラコンサート風が続いていたが、今年は久しぶりにウィーンからのオーケストラを迎えての、日本の新春お馴染みのシュトラウス一家のワルツ、ポルカのコンサート。
記録を見るとオーバードでは2006年にフォルクスオーパーのオーケストラを招いての同様のコンサートが開かれている。
どうも、オーバードのニューイヤーコンサートについての捉え方が明確でなく、年によってバラバラの感があるのは、いかがなものだろうか。新年はウィーンからのオケを招いてのコンサートとしてしまえば、それを楽しみにするファンも固定的に増えるのではなかろうか?あるいはそれに代わるテーマを設けても良いが。
さて、今日のコンサート、さすが本場というワルツ・ポルカを聴かせてくれた。
新年になるとウィーンから様々なシュトラウスを冠したオーケストラが出稼ぎ公演に日本を訪れるので、ファンとしても
、「一体どの団体がまともなのか?!」と困惑してしまうほどであるが、今回のオーケストラは、質の高い本場のワルツ・ポルカを聴かせるオーケストラという印象。
43名と言う小編成のオーケストラであるが、個々のプレーヤーの質の高さ、アンサンブルの調和など、充実したオーケストラ。この日の編成ではヴィオラが見たところ1基しかないことが興味深い。第一ヴァイオリン10名、第二ヴァイオリン6名、ヴィオラ1名、チェロ・コントラバス3名という様に見えたが。木管は2名づつ、ホルン4名、トランペット2名、トロンホーン1名、ハープ、ティンパニー、ドラムという編成。
J・シュトラアウス2世の創設によるオケとのことなので、ワルツ・ポルカを最も効果的に聴かせることを目的としてこの様な編成になったのだろう。
指揮は、ウィーンの指揮者、ヨハネス・ヴィルトナー。日本では無名に近い指揮者であるが、棒さばきの鮮やかさ、そしてウイットに富んだおしゃべりなど、ワルツ・ポルカの音楽会のウィーンの伝統を見事に再現させていた。
今日の演奏会ではJ・シュトラウス1世、2世、ヨーゼフ・シュトラウス、エドゥアルト・シュトラウスの作品が演奏されたが、一家でもそれぞれ個性の相違があるのを再確認。
J・シュトラウス二世の艶やかで流麗な世界、エドゥアルトの華麗活発な世界、ヨーゼフのしっとりとした抒情の世界、それらが聴き分けられたのもこのオーケストラの伝統の力か。
最初の「こうもり」序曲。緩急の入り混じる楽想が、自然に流れ、わざとらしさが皆無。それでいて流麗に歌う部分などの弦楽器と木管の歌わせ方の絶妙さ、うきうきと踊りだしたくなるような楽想の表現等オペレッタの舞台の楽しさを彷彿とさせる演奏。エンデイングのたたみかける様な早いパッセージもピタリと決まる。
エドゥアルト・シュトラウスの珍しい「ヘクトグラフ」というポルカの爽快さ。このうきうき感は独特なもの。
ヨーゼフのワルツ「うわごと」は序奏の不気味な不協和音がワルツとは思えない出だしであるが、主部ではしっとりとした歌が続く。各ワルツへの移行の間の取り方、各ワルツの出だしの絶妙さなど、ただ技術的な巧みさだけでは出しえない、呼吸の見事さがあり、音楽が豊かに息づいている。これこそ、ウィーンナワルツの醍醐味である。
一部最後のJ・シュトラウス2世の「ウィーン気質」では、指揮者のヴィルトナーのヴァイオリンの弾き振り。序奏のチェロとヴァイオリンの2重奏の気品のある艶やかさ、その気分ががそのまま主部のワルツに移り、流麗に流れていく。
各曲間でのヴィルトナーのおしゃべりもユーモアたっぷり、ドイツ語なので理解できない部分が多いが、その表情だけでなごむ。
第2部では、有名な「皇帝円舞曲」、最後にお馴染み「美しき青きドナウ」も演奏された。「皇帝円舞曲」の中間部のトランペットとトロンボーンによる堂々としたテーマの吹奏、「美しき青きドナウ」の序奏のさざめきの様なヴァイオリンの弱奏など、聴かせどころもしっかりと押さえた将に堂にいった演奏。
「鍛冶屋のポルカ」での打楽器奏者のパフォーマンスなど、恒例のユーモアもあるが、過度にならず上品である。
アンコールには最初堂々と「1月1日」が演奏、サービス精神たっぷり。その後ポルカ2曲(「シャンペン・ポルカ」「憂いも無く」と思うが。)、最後が恒例の「ラデイツキー行進曲」、これも決して派手にならない洒落た演奏、ヴィルトナーの手拍子の指揮もしっかりとしたもの。
常々、「ウィーンナワルツはウィーンの民族音楽、神髄を表現できるのはウィーンの人たちだけ。」と思ってきたが、今回もそれを再認識したというわけ。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第311回定期演奏会
2011年11月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ギュンター・ピヒラー
フルート 高木 綾子
ハープ 吉野 直子 |
|
今年最後の定期は、2年ぶりのピヒラーの登場。前回のやや渋いプロと異なり、今回は「ウィーンの古典」と題され、オーソドックスな古典派のプログラム。ロッシーニ「シンデレラ序曲」に始まり、モーツァルト「フルートとハープのための協奏曲」、後半がベートーヴェン、交響曲第6番「田園」。
ロツシーニでは弦楽器の柔らかく繊細な音と、管楽器の飛び跳ねる様な音が印象的。息の長いロッシーニクレッシェンドの表現が音楽的興奮を高めていく。キリリと引き締まったアンサンブルが、ロツシーニの音楽の本質である、音楽の愉悦を的確に表現していた。
モーツァルトも落ち着いた典雅な演奏。フルートの高木綾子の明るく、輝かしいフルートと吉野直子の落ち着いて優しいエレガントなハープ。もう少しハープが前へ出ても良い様にも聴いたが、これが個性か。ピヒラーの指揮もフルートとハープにぴったりと寄り添い、全体としてしっとりとした落ち着きを感じさせる、古典的優美さを持った真面目なもの。
モーツァルトの音楽の喜悦の様な側面が聴ければ、尚一層心に染み入る演奏となっただろう。やや、真面目さが勝った印象。
後半のベートーヴェン。ピヒラーのベートーヴェンはOEKで2回、この6番と8番が過去に演奏されている。
私の過去の記録では、2003年にこの6番を聴いており、その際はあまり良い感想を持っていないようであった。
その後の2006年の8番は、かなり気合が入った演奏だった様で、その対比というか、相違に驚いた記憶がある。
ピヒラーはこの6番「田園」がお気に入りの様で、今回も6番ということ。
6番という作品、ベートーヴェンの交響曲の中でも、表現の幅というか、指揮者の個性が明確に現れる作品でなかろうか?
作品の性格が再現方法により難しい作品であるからだろうか?
描写音楽的でありながら、奥にはベートーヴエンの人間的な熱い感情が秘められている作品。そこをどの様に表現するのか、聴き手もそのあたりが一番聴いてみたいところだと思うのだが。
古典的均整のとれた演奏、ロマン的な感興に溢れた演奏、華やかな演奏、渋い演奏、色々である。テンポも1楽章からして様々で、指揮者のこの作品に対する解釈が様々であることを伺わせる。
ピヒラーは1楽章からかなり早いテンポで、余分な思い入れを排し、この作品の古典的厳格さを表現しようとしているように思える。細部まできちんと各パートが鳴り響き、均整のとれた、厳格な演奏。
ただ、その上の表現、この作品の中に籠められているベートーヴェンのヒューマンな息吹というものが、どうも聴こえてこない。5楽章はそれまでの楽章の物語の頂点とも言える、壮大な人間賛歌であると思うのだが、実に淡々としている。
エンディングの部分で、思い切ったテンポの落とし方で全体の印象付けを図ってはいるようだが。
このあたりは、この作品に対する捉え方の相違によるものだろうか?
演奏そのものは立派なものなのだが、私のこの作品に対する思い入れとは方向性が異なる演奏の様に聴いた。
といわけで、6番という作品の表現の難しさを再認識した演奏ではある。 |
|
|
|
|
|
|
|
ユリアーナ・アヴデーエワ ピアノ リサイタル
2011年11月19日 入善コスモホール |
|
2010年の16回ショパンコンクールで優勝のピアニスト、ユリアーナ・アヴデーエワのリサイタル。
まず、プログラミングが個性的。
前半が、ショパン「舟歌」、ラヴエル「ソナチネ」、プロコフィエフ「ピアノソナタ第2番」、後半がリスト、「悲しみのゴンドラ」、「灰色の雲」、「調性の無いバガテル」、ワーグナーの「タンホイザー序曲 リスト編曲」というもの。
普通、ショパンコンクール優勝をひっさげての日本ツァーであれば、オールショパンか、少なくともショパンのソナタ中心のプログラムかと思いきや、ショパンは一曲のみ(アンコールには2曲演奏)。ここに、このピアニストの気概というものを見た気がする。「私は決してショパン弾きでない。もっと沢山の作品を表現したい。」という。
そして強い表現意欲、聴衆を納得させる強烈な個性を有したピアニストの登場は、その気概を見事に表していた。
アルゲリッチ以来の女性ピアニストのショパンコンクール優勝という話題が先行しているが、ショパンコンクールという豊かな個性のピアニストを多く生み出してきたコンクールを象徴するような、強烈な自己主張と個性を持ったピアニストの登場と言えるのではなかろうか。
まず、その分厚い響き。和音にかなりの残響を与え、その和音の残響の上に旋律が浮かび上がるので、全体に分厚い音楽が形作られる。
ショパンの「舟歌」では、最初その分厚い響きにやや違和感を感じたが、聴き進めるにつれて、その独特な濃い表現の世界に魅了されていく。
ショパンの音楽はややもすると繊細なロマンチシズムが重視されがちだが、本質的にはスケールの大きいロマン性が表現されていると感じる。その点が、彼女の演奏では極めて明確に語られ、骨太で、それでいて濃厚なロマンチシズムが描き出されている。本年初めに聴いたエルバシャのショパンも実に雄大、雄渾なショパンであったが、その性格とまた異なる、しかしやはりスケールの大きいショパン像が表出されていた。
総ての作品に効果的に使われているテンポルバートは大きな特長であろうが、そこには彼女の作品表現の本質的なものが秘められているように思える。
ラヴェルのソナチネでは、全楽章に共通して使われる主題の表現が明確で、かつ特長に満ちている。2楽章のテーマの最後に使われる下降音符が異様な輝きを持って表現されている様は極めて印象的。ラヴェル独特のきらめきの様な表現も勿論あるが、構成ががっちりとした、やはりスケールの大きいラヴェル。
前半最後のプロコフィエフは、将に圧倒的な打鍵で表現される作曲者の咆哮。プロコフィエフ独特のシニカルな面、暴力的ともいえる叩きつける様な表現、そのいずれもが的確に表現され、聴く者を圧倒させる。
後半のリストでは前半2曲の静謐で濃厚なロマン性の表現と、後半2曲の激しいロマン性の表現の対比が見事。
「灰色の雲」の、打鍵の静かな力強さは、リスト晩年の心情の深い表現。
ワーグナーの「タンホイザー序曲 リスト編曲」は将に驚異的なテクニックに支えられた、巨大な世界の表現。
中間部のヴェヌスブルグの音楽のうねる様なテンポルバート、そして現われるタンホイザーの歌の堂々とした表現。
終結部の巡礼の合唱は、テンポをずっと落とし、未来への希望を託すように高らかで輝かしい終結。
26歳の女性が2つの手で表現しているとはとても信じられない、巨大な音楽の世界。
前後半のプロ総てを通し、強い表現意欲と、それぞれの作曲家の描き出す世界を自らの感性で解釈し再現する才能。
そして、勿論それを支える驚異的なテクニック。
アンコールのショパンのマズルカの複雑なリズムを難なく表現し、ポーランドの土の香りさえも感じさせる表現能力。
正直、凄いピアニストの出現である。
ここ数カ月、ここ北陸で、アシュケナージ親子、チッコリーニ、そして今回のアヴデーエワと、個性はそれぞれ異なるが、ピアノ音楽の神髄の様なものに触れられたことは記憶に残る年となりそう。 |
|
|
|
|
|
|
|
コスモホール開館25周年記念公演 第九演奏会
指揮 山下 一史
管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢
ソプラノ 平井 香織
アルト 串田 淑子
テノール 土崎 譲
バリトン 竹内 雅挙
合唱 コスモホール開館25周年記念合唱団 |
|
入善コスモホールが今年で開館25周年ということだ。一地方の小さな町で、年に数回ではあるが、内外の優れた演奏家を招いて開かれてきたコンサートは、富山の音楽の歴史の中でも重要な位置を占めていると考える。
アルゲリッチ、マイスキー、クレメルは数回にわたりこのホールを訪れているし、その他富山市や高岡市などの大きな街ですら取り上げる機会の少ない優れた演奏家を呼んでのコンサートは、聴衆にとって貴重な機会であり、私も退職後には頻繁にこのホールを訪れ、その度に新鮮な感動を与えられてきた。
ここ数年聴衆の減少傾向があり、訪れる度にこの先大丈夫だろうかという不安がよぎるが、熱心なこのホールのファンのためにも、何とか続けて欲しいものだ。
25周年を記念して、11月に毎週土曜日、3回の公演が行われる。今日が第9演奏会、来週がギターの村治佳織とチェロのリチャード・ヨンジュ・オニールのデュオリサイタル、翌々週がピアノのユリアンナ・アブデーエワのリサイタルと続く。
この日は山下一史とオーケストラ・アンサンブル金沢を迎えての第9演奏会。合唱は地元を中心とした特別編成の合唱団で60名あまりの編成。ホールがこの大曲を演奏するにあたっては、やや小ぶりでもあり、合唱団もホールとオケの規模にあわせてやや小さめの合唱団としたのだろう。私の学生時代の友人で入善在住のY氏も合唱団に加わっている。高校時代に合唱団であったとのことだか、数十年ぶりの大きな舞台はさぞ、緊張されたことと想像する。
今日の編成・配置は最近のOEKにしては珍しい、ビオラを右に配置した、かつて多く採用されていた楽器配置。どういう試みかティンパニーが左側に位置していたのが珍しい。対向配置が最近は主流となっている中でのこの配置は指揮者山下一史の意図であろう。
演奏も最近主流の古典的アプローチというより、スケール感を大きく持たせたロマン的なアプローチ。
1楽章の最初から緊張感のある激しい出だし。スケール感と激しさを追求するあまり、やや細部への丁寧なアプローチに欠けるきらいはあるが、山下はそんな細部よりも、大きな全体像を描き出したいようだ。更に特長的なのは、ベートーヴェンの音楽に聴くことの多い、特長的なリズムの強調。1楽章では、タッタラ・タッタラというリズムが全曲を支配し、第2楽章で更にそのリズムが大きく強調されていく様を明瞭に聴くことが出来る。
第3楽章も大きな構成感を打ち出したいようだが残念ながらこの楽章の神秘的ともいえる転調の妙が聴こえてこない。難しい楽章ではある。第4楽章は独唱も合唱も見事。特に合唱団のアンサンブルの良さ。楽譜を持っていないので、総て暗譜でなのだが、楽譜も歌詞も明瞭で、楽曲と歌詞を自分のものとして歌い上げた立派な演奏であった。短期間でここまでまとめ上げた合唱指揮の内山太一氏の功績大である。
独唱陣も輝かしい歌。各地で第九が演奏される為であろう、昔の様に限られた独唱者でなく、多くの日本人の歌手が第九を歌うようになった為であろうが、ソリストの底が厚くなっているようだ。
第九という巨大な作品は、小手先の器用さで演奏できるものでない、全エネルギーをぶつけてこそという山下一史の情熱を聴くことのできる演奏であった。
ただ、細かい部分での乱れが聴かれたのが残念。細部の磨きあげと、細部から全体を作り上げる丁寧さがあれば、尚一層の感銘深い演奏となったと思える。 |
|
|
|
|
|
|
|
アルド・チッコリーニ チャリティコンサート
ピアノ : アルド・チッコリーニ
指 揮 : トーマス・カルブ
管弦楽:オーケストラ・アンサンブル金沢 |
|
今年、OEKのヨーロッパ公演での、ダンテロン音楽祭でのチッコリーニとのベートーヴェンとシューマンの協奏曲をネット配信で聴き、特にベートーヴェンの3番の協奏曲に圧倒的な印象を受けた。その録画を見た直後にチッコリーニの金沢演奏会との報を聴き、この日を待ちわびていた。
既に86歳の高齢、果たして来日されるのかという不安もあったが、元気な姿を金沢の聴衆に見せてくれた。
前半がトーマス・カルブ指揮のOEKとのモーツァルトの20番の協奏曲、後半がモーツァルトの15番と13番のソナタ。
オールモーツァルトであり、又協奏曲、ソナタの2大傑作が揃うという、垂涎物のブログラム。
当初のプロでは、オーケストラの初めにディヴェルティメントが予定されていたようだが、ドンジョバンニ序曲に変更されていた。20番のニ短調の協奏曲との関連性を考慮しての変更と思われるが、この方がプログラムとしては落ち着いている。トーマス・カルブの演奏は堅実なもの。ドンジョバンニ序曲は最初の曲とあって、オケのアンサンブルの粗さがやや目立っていた。というものの、この日の本番はチッコリーニ、その協奏曲への誘いという意味では効果的。
さて、20番の協奏曲。モーツァルトの協奏曲の中でも2つだけの短調の協奏曲の一つ。
全体に悲劇的な曲想が支配する作品。オーケストラの激しく、悲劇的な序奏の嵐が治まり、ピアノが静かに入ってくる部分。チッコリーニはオケの激情を沈めるように淡々と、しかし深い音色で入ってくる。独特な歌い回しがあるが、されも全体の中での違和感は全くない。この作品がモーツァルトがこのように鳴らしたかったのだというそのままの無垢の姿で迫ってくる。もうそこには、チッコリーニというピアニストの音楽ではなく、モーツァルトの音楽がそのままの姿で現われている。これが、円熟というものだろうか。円熟という安易な言葉が届かない境地でさえある。
86歳とは思えないテクニックの冴えは言うまでもないが、テクニックが音楽表現の基礎にあるのなら、その意味で驚がく的なテクニックである。この様に聴かせてやろう等というレベルでない、音楽が総ての垢を脱ぎ捨てて純化されている様な境地。演奏家の辿りつく最後の高みであろうか。
指揮者もオケも良い音楽を作っているのだが、残念ながらここではその伴奏すら邪魔と思わせる部分すらある。
1楽章のカディンツアでの自由な遊び、2楽章のピュアーな素朴さ。2楽章も、妙な思い入れを排し淡々としているようで、その表現する世界は広大。
後半のソナタはチッコリーニ一人の世界。自由自在に音楽は飛びまわり、モーツァルトの音楽の素朴な喜び、遊びの境地が繰り広げられる。
演奏曲順は変更となり、13番K333、11番「トルコマーチ付き」k.311の演奏順。
総てがチッコリーニのモーツァルトの世界。テクニックの冴えをひけらかすわけでなく、自分の個性をこれ見よがしに披露することでもないのに、現われる音楽は将に個性的。前述の様に、チッコリーニのモーツアルトでなく、モーツァルトの音楽の純粋な喜び、悲しみが迫ってくる。11番の1楽章の変奏曲など将にモーツァルトの自由な遊びが、そして音楽の喜びが飛び跳ねているよう。13番の1楽章も、素っ気ないように入ってくるのだが、その後の展開は自由そのもの。
かなり思い切ったテンポの揺れなども聴くのだが、それは将に呼吸の様なもので、嫌みは全くない。
最後の11番3楽章の「トルコマーチ」、これはもう形容の及ばない世界。だだただ、モーツァルトとチッコリーニに脱帽。
聴衆の熱狂的な拍手に応えて、アンコールが3曲。1曲目はシューベルトだろうか?他にドヴュッシーとグラナドス。
最後は聴衆総立ちのスタンディングオベーション。金沢では珍しい光景。それだけ、多くの人の心にその感動が刻み込まれたということだろう。一生の内にそう多くはめぐり合えないコンサートといったら大げさだろうか?
東京と金沢でのチッコリーニの演奏会は、東日本大震災へのチャリティーコンサートとなっており、チッコリーニのギャラは被災地への寄付に充てられるとのこと。 |
|
|
|
|
|
|
|
プラハ国立歌劇場 2011年日本公演
プッチーニ 歌劇「トスカ」全3幕
2011年10月22日 オーバードホール
トスカ/アンダ=ルイゼ・ボグザ
カヴァラドッシ/エマニュエル・ディ・ヴィッラローザ
スカルピア/フランティシェク・デュラチ
指揮:
ジョルジョ・クローチ
管弦楽:
プラハ国立歌劇場管弦楽団
合唱:
プラハ国立歌劇場合唱団
|
|
プラハには3つの主要な歌劇場があるそうで、その内の一つ、1887年創立の「新ドイツ劇場」を母体としたプラハ国立歌劇場の10回目の日本公演。
今年は東日本大震災の影響で、来日する歌劇場の多くがキャスト変更を余儀なくされているようだ。この公演でも、メインのトスカの目玉エヴァ・マルトンが来日しなかったようである。
もっとも富山公演の場合は最初から、トスカはアンダ=ルイゼ・ボグザと発表されていたので変更はない。ただ、スカルピア役が変更となっているようだ。
今回の「トスカ」、主役のアンダ=ルイゼ・ボグザの素晴らしい声と、表現が聴衆を魅了。
大きいオーバードホールの隅々まで響き渡るような輝かしい声量には圧倒される。トスカ役は、リリックからドラマティックまで要求される、又性格表現も複雑に要求される役がらだが、アンダ=ルイゼ・ボグザは最初から最後まで緊張感に満ちた歌唱と演技。
カァバラドッシ役のエマニュエル・ディ・ヴィッラローザも輝かしいテノールで、激情を披露。有名なアリア「星は光ぬ」でも、情感のこもった熱唱。
それに比較してスカルピア役のフランティシェク・デュラチはやや弱い。声量もやや細く、性格表現もあくどさが足りない。主要な役どころが総て好調というのは、オペラ公演で至難なのだろうか?
クローチ指揮のオーケストラは、さすがというか、堂にいった伴奏。アリアに寄り添い雄弁に語りかける。アンサンブルが極上とはいかないが、オペラの聴きどころをしっかりと押さえ、ドラマを作り上げる技は、さすがにオペラの盛んな国の伝統を感じさせる。クローチの指揮も良く歌い、劇的。最初の入りの金管の咆哮も、このドラマの悲劇性を象徴し、最後の幕切れの切々と高まるオーケストラの響きも心を打つ。
舞台装置もリアルで伝統的。奇異を衒ったところがない、安心して見ていられる舞台背景。
やはり、日常的にオペラが上演されている国の安定した公演という印象。いくつか見てきた外国のオペラ座の公演の中でも、印象に残る舞台となりそう。
富山の地元の子供たちが1幕に登場、しつかりとした演技を見せていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第309回定期演奏会
2011年10月14日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響
ピアノ 山本 貴志 |
|
久しぶりの金聖響の登場。初めて、OEKで金を聴いた時の衝撃。確かもう10年近くなるだろうか、ベートーヴェンの「英雄交響曲」が新鮮に、そして生き生きと、輝きと鋭さを持って再現されたのが、今も鮮やかに蘇ってくる。
それ以来、私にとっての注目の指揮者であり、ベートーヴェン、ブラームスの全曲演奏をOEKで行うなど、OEKとはぴつったりと息が合う指揮者。3年ほど前からか神奈川フィルの音楽監督となり、最近ではマーラーの全曲演奏に挑むなど、レパートリーの幅も広げている。1年に一度はOEKに戻ってほしい指揮者でもある。
一時、金の指揮では補助席まで出る公演があるなど人気の指揮者だが、今日は少し寂しい8割ほどの聴衆。
プログラムはオールシューマンで、「マンフレッド」序曲、新鋭山本貴志を迎えてのピアノ協奏曲、後半が交響曲第一番「春」。
コントラバスを左に置いた古典的な対向配置、そしてトロンボーン、トランペットを右に寄せるなど、金独特の配置。
この日のティンパニーはロマン派の作品ということもあり、通常の大型のティンパニー。
最初の「マンフレッド」序曲は、まだ楽器が温まっていないせいか、若干音質が硬く、またアンサンブルもやや粗い。
ただ、独特のスケールの大きさは感じられる演奏。
さて、ピアノ協奏曲。様々な解釈があるこの作品だが、山本の演奏は実に清新。繊細な息づかいに満ちた演奏で、特に弱音の美しさは比類がない。誠実で、はったりの無い演奏。この作品では、シューマン独特のドロドロしたものもあり、それを強調する演奏も多いが、山本はそうでなく、この作品の旋律の美しさを浮き出す様なやさしい演奏。これも大事な個性であるが、今後どのように演奏が変化していくかの期待も持たせる。更に一皮むけると、とてつもなく大きな演奏を聴かせるのではという期待。ここでの金の伴奏は、ピアノにぴったりと寄り添った確かなもの。ピアノと木管の対話など実に美しい。2楽章の弦のぶ厚い音質も特筆。
後半はシューマンの交響曲第一番「春」
以前は三番「ライン」を聴き、雄大な造形感、しっかりとした構築を記憶しているが、この日の一番も雄渾。
常に音楽が前へ進んでいく。クライマックスへひたひたと迫っていく気持ちの昂ぶりが、オーケストラの息づかいとなって迫ってくる。細部まで神経が行き届いているので、音楽に緊張感が支配し、弛緩することがない。
トライアングルの繊細な音が効果的に使われていることを初めて聴くことができた。それ程細部までクリァーでありながら、響きは分厚く、シューマン独特の暗い情熱も浮き出てくる。
終楽章の、引いては押し寄せ、又引いては押し寄せる波の様にクライマックスに向かう緊張の持続。そして、クライマックスの堂々たるエンディング。決して興奮の極致ではなく、冷静に最後を締めくくる。
聴きごたえのある、作品の本質を的確に描き出した名演。久しぶりに聴いた金聖響は健在であった。
アンコールに珍しいベートーヴェンの序曲「アテネの廃墟」。これも、しつかりとした構成感と迫力に満ちた演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第308回定期演奏会
2011年10月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮・クラリネット ポール・メイエ |
|
名クラリネット奏者、ポール・メイエが指揮にも登場するという注目の演奏会。
ピアノの弾き振りというのは最近多いが、クラリネットの吹き振り?というのは珍しい。
ポール・メイエはクラリネット奏者としては世界でも有数の名手であるが、そこだけに飽き足らずオーケストラの表現力に挑戦するということなのだろうか?
先日のアシュケナージ、又名ピアニストであったエッシェンバッハやバレンボイムの指揮者への転向も、その道の大家でありながら、より広い世界への飽くなき要求と挑戦がなせる技であったのだろうが、メイエも又名手であるが故にの新世界への挑戦であるのだろう。
プログラムはメイエ自身のクラリネットによるモーツァルトのクラリネット協奏曲をメインに、モーツァルトの珍しい劇付随音楽「エジプト王タモス」、後半がベートーヴェンの交響曲7番という、がっちりとしたプロ。
古典ということで、編成もOEKの標準編成、対向配置である。ただ、ティンパニー奏者に客演が入っていたようで、何か理由があったのだろうか?
さて、最初は珍しいモーツァルトの劇付随音楽「エジプト王タモス」。4曲からなる組曲だが、全曲に渡り短調の色彩と、悲劇的な緊張感に溢れた作品。モーツァルトの短調は数少ないが、いずれも劇的な緊張感に満ちた名作が多いが、この作品も同様、劇的な迫力が溢れている。
メイエは作品の色彩を明確に打ち出し、やや早めのテンポで、煽りたてる様な情熱に溢れた指揮。
次はこの日の中心、モーツァルトのクラリネット協奏曲。長調でありながら、暗く寂しい色調に彩られた作品。最初に短調の作品を配したのも、この作品とのつながりを意識したのであろうか。
メイエのこの協奏曲は、富山でのN響の演奏会でも聴いたが、この日は指揮をしながらの演奏。
といっても楽器から手を離すことは難しいので、自らのクラリネットと表情でオーケストラをリードしているよう。
さすがという演奏で、この作品のクラリネットの低い音域の魅力を存分に引き出していた。
第2楽章の寂寥感はやはり絶品。オーケストラもメイエのクラリネットの作りだす豊かな表情にぴったりと寄り添っていた。第3楽章の飛び跳ねる様な楽節もメイエのクラリネットは楽々と余裕のある演奏。作品の持つ性格をぴたりと描き出していた。
休憩後はベートーヴェンの7番。この作品はOEKの十八番とでもいえよう。故岩城監督の追悼演奏会で、指揮者なしで演奏するという離れ業もやってのけ、今年の海外公演でも取り上げており、得意中の得意と言える作品。
ということで、極めて安定したアンサンブル。そこにメイエは安心してのっかり、気持ちよさそうに指揮をしていたのが印象的。
緊張感と堅固さが全曲を支配し、特に際立った演出も無いのだが、この作品の本質であるリズムの支配が巧みに描き出されていた。各楽章の性格の描きわけもきっちりとしながら、全体の音楽の巨大性も浮き上がってくる演奏。
第4楽章エンデイングも、決して煽るようなことはしないが、それでいてややテンポを早めながら、造形の崩れることのないしっかりとしたエンディングを築いていた。
この演奏でのOEKはやはり最近の好調さを示す様に、総てのパートにわたり乱れの見られないしっかりとしたアンサンブルを聴かせてくれた。 |
|
|
|
|
|
|
|
ウラディミール&ヴォフカ・アシユケナージ ピアノ・デュオ
2011年9月29日 石川県立音楽堂 |
|
ピアノ・デュオという分野は、名手二人が揃わないと実現できないもので、それだけに聴く機会が少ない分野でもある。
今回アシュケナージ親子という名手二人が、素晴らしく楽しいコンサートを開き、ピアノ・デュオの面白さを堪能させてくれた。
プログラムは次の通り。
プーランク 2台のピアノのためのソナタ、ラフマニノフ 組曲第1番「幻想的絵画」、休憩を挟みムソルグスキー禿山の一夜、ラヴェル マメール・ロワ、ラ・ヴァルス。
ピアノの質は親子といえどもかなり異なり、ウラディミールは温かみと円熟を、ヴォフカは輪郭のはっきりとしたクールな音質を特長としているよう。お互いに個性を発揮しながら、時には挑発し、時には調和し、息の合った見事なアンサンブルを聴かせてくれた。
さすが親子だけあって、お互いの意思の疎通がスムーズで、「お前がそうするなら、俺はこうする。」というような丁丁発止とも形容できるようなやりとりが面白い。
最初のプーランク。プーランク独特の、歪な端正さというものが良く表現されていた。プーランクにしては珍しい激しさも感じる曲想で、出だしの不協和音はどきっとするような迫力。
次のラフマニノフ。音で表す絵画という趣だが、ここでのデュオは濃密な世界が表現されていた。
二人の演奏には、色彩的ではあるのだが、淡彩ではなく、油絵的な濃さを感じた。
「舟歌」「夜―愛」「涙」「復活祭」と題された4つの小品は、詩の内容が音で見事に表現されていた。ラフマニノフ独特の濃密なロマンが二人の演奏で再現され、聴きごたえのあるものとなっていた。
後半の最初は、ヴォフカの編曲によるムソルグスキーの「禿山の一夜」。R・コルサコフの管弦楽版が一般的な色彩豊かな作品を、ピアノ・デュオでどのように表現するのかという興味と危惧。しかし、危惧は杞憂であり、オーケストラ版とは又異なる、ピアノ・デュオの面白さを満喫。前半のグロテスクな踊りが、叩きつける様な激しいピアノによって表され迫力満点。後半の夜明けの部分のゆったりと歌われるピアノの響きも印象的。これも、大きな油絵を見る様な迫力。
ラヴェル、マ・メール・ロワも管弦楽版とは又一味異なる面白さ。ピアノ・デュオでもここまで色々な色彩を表現できるのだということを再認識。特にグリッサンドなどはピアノでなければ表現できないところであり、ピアノ独特の技巧をこらした面白さ。
最後の、ラ・ヴァルスも同様。管弦楽版の色彩豊かな表現が、ピアノの技法に置き換えられ、別の魅力が充満。
特に、このワルツ独特の粘っこいリズムが二人のピアノから濃密に描き出され、最後の爆発の瞬間に向かい進んでいく様が緊張感と迫力に満ち表現されていた。管弦楽版と異なる、ピアノの技巧を駆使した、ピアノ・デュオならではの面白さ。
アンコールはシューマンと言うように聴こえたが。
ウラディミールはピアニストとしての活動より、指揮者としての活動のキャリアが長くなっているが、こうして聴いてみると、暖かく円熟した音色は魅力的であり、技巧もまだまだ達者、現役のピアニストとしても聴かせて欲ししいと思うのだが。
ピアノの表現力の多彩さが、名手によって存分に発揮されたコンサート。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第307回定期演奏会
2011年9月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ロルフ・ベック
ロマン・ロラン役 西村 雅彦
ヘンデル役 井上 道義
合唱 シュレスヴイッヒ・ホルシュタイン音楽祭合唱団 |
|
マイスターシリーズ、新シーズン最初の定期。
「汝、調和の司祭よ ヘンデル合唱祭 神々しき調べ」と題された、ヘンデルのオラトリオからの合唱曲、管弦楽曲を抜粋した作品の演奏と、ヘンデルの生涯、作品を、ロマン・ロランとヘンデル自身に語らせるという、趣向を凝らしたコンサート。
ロマン・ロラン役に西村雅彦、ヘンデル役に何と、井上道義音楽監督を配した、やや際物的とも思わせるコンサートだが、いやいや、内容は極めて充実した、音楽物語となっていた。
ロマン・ロランがヘンデルの生涯の事件と背景を、ヘンデル自身が自らの作品について語るという、時空を超えた、非現実的な構成だが、ヘンデルの時代と音楽を明確にあぶりだすという点では成功していた。
井上監督のヘンデル役は、プロの役者も食う程の熱演、やはり音楽を音楽家が語ると、このように熱く語れるのだと納得させられる名演技。全く器用な方である。
そして、何よりも音楽の内容、ロルフ・ベックのしっかりとした構成感、歯切れの良いリズムが、ヘンデルの華麗な世界を堂々と描き出し、シュレスヴイッヒ・ホルシュタイン音楽祭合唱団の素晴らしい合唱とともに、ヘンデルの音楽世界が見事に展開されていた。
OEKの編成は基本的な編成にホルン、トランペットを増強したもの。配置は対向配置。
増強した金管と、バロックティンパニーの炸裂するような迫力ある音色が印象的。
音楽劇の原作はドイツのリヒャルト・アルムブルスターという作者の創作によるものだが、響敏也氏が日本版脚本を担当。ヘンデルの生涯と音楽の特色を端的に描き出した脚本は理解しやすく秀逸。ヘンデルという名前だけ有名だが、音楽の本質があまり知られていない作曲家の、本質を解りやすく描き出していた。
演奏作品はオラトリオが中心で、作曲年代順に並べられ、前半が「エジプトのイスラエル人」「メサイア」「マカベウスのユダ」、後半が「ソロモン」、その後有名な管弦楽曲、「水上の音楽から」「王宮花火の音楽から」と続き、「イェフタ」、そして最後に再びメサイアから「アーメン」で締めくくるという構成。
いずれも長大なオラトリオなので、その極一部の抜粋である。
何といっても、シュレスヴイッヒ・ホルシュタイン音楽祭合唱団の素晴らしい合唱。40名あまりの合唱団だが、伸びやかで、艶やかなアンサンブル、特に低音部の豊かさなど特筆もの。豊かな声量、輝かしく響き渡るハーモニーと、弱音部での柔らかいアンサンブルのコントラスト、明確できっちりとした輪郭線など、ヘンデルの合唱曲の魅力を存分に聴かせてくれた。
後半の管弦楽曲「水上の音楽から」「王宮花火の音楽から」も、華やかな色彩感が存分に出ていた。バクパイプを連想させる管楽器の響きも印象的。OEKもロルフ・ベックの指揮に良く反応し、生彩のある古典を聴かせてくれた。
ヘンデルの極く一部を凝縮して表現したようなコンサートだが、ヘンデル入門としては良く出来たコンサート。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第306回定期演奏会
2011年9月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ソプラノ 濱 真奈美 |
|
7月、8月と定期公演はお休み。ということで、新シーズンの始まりの定演は2か月ぶりのOEK。
毎月の様にOEKを聴いていると、2ヶ月間の空白は寂しく、久しぶりにOEKの音が身体に染み入ってくるように聴こえる。
毎年9月のシーズン初めのコンサートは、岩城宏之永久名誉音楽監督の名を冠した「岩城音楽賞」の受賞者の発表と、その年のコンポーザー・オブ・ザ・イヤーの作曲者の新作の発表が定例化している。
コンサートの前に濱さんに県知事の代理山腰音楽堂館長から表彰状の授与がある。
本年の岩城音楽賞の受賞者は金沢市出身のソプラノ濱 真奈美さん、コンポーザー・オブ・ザ・イヤーは望月京さん。
前半が濱 真奈美さんのオペラアリアと望月京さんの新作「三千世界」、後半がドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」というプログラム。
濱 真奈美さんは、ラフマニノフ「ヴォカリーズ」とお得意のプッチーニの「蝶々夫人」から「ある晴れた日に」、ベルディの「運命の力」から「神よ平和を与えたまえ」の3曲を熱唱。
大変柔らかい声でありながら、ドラマティックな表情も豊かで、声量も十分、2曲のオペラアリアは聴きごたえのあるもの。
「蝶々夫人―『ある晴れた日に』」の切々とした心情の表現、「運命の力―ある晴れた日に『神よ平和を与えたまえ』」の悲劇的なドラマの表出など、役に撤した表現力の強さは、オペラ歌手としての経験の深さをうかがわせる。
オーケストラの劇的な表情も独唱と一体となり、オペラの舞台を想起させる。わずか2曲のオペラアリアだったが、感銘深い歌唱。
さて。望月京の新作「三千世界」。大きな輪ゴムをブルンブルンと打楽器奏者が振り回す、その音から始まる。
空虚さから、徐々に様々な音が集合していくが、どの音も決して確信を持った音で無く、結びつきが大きくなるが、どこか虚無的で、空中に漂っているようでもある。弦楽器、管楽器いずれも明確な旋律性は有せず、点描のようでもある。
打楽器の中には、カーテンを垂らしたようなものがあり、後半ではそれをこすることにより、風の音を思わせる「ブーン、ブーン」という音が空中を漂う。
終結部では、後の井上監督のトークによると、「指揮者のカディンツァが楽譜に書かれている」とのことで、井上監督が楽譜を持ちながら、のたうちまわる様なパフォーマンスが入る。監督自身の解説によると、「故岩城監督が、若い頃、腰痛に悩まされ、マリンバを叩くのに、四苦八苦していた」様子を表したものだとのことだが、私には「楽譜の音をどの様に表現して良いものか」、苦闘する指揮者の姿に見えたが!?
楽器の使い方、構成の鋭さなど、才能溢れる作曲家という感はあるが、現代音楽共通の課題と思われる、「果たして何を語りたいのか」という疑問はやはり払拭されない。
後半は4月の仙台フィルとの復興支援コンサートでも演奏された、ドヴォルザークの新世界交響曲。
際立っていたのは、指揮者とオーケストラの呼吸のぴったり合った見事さ。指揮者の要求に対して、オーケストラが自発的な音で応える。指揮者がオーケストラを引っ張りまわすのでなく、オーケストラの自発的な呼吸を大切に引き出していく。であるから、音楽の自然な流れと、音楽の訴える力が生き生きと表現される。音楽の内容が生き生きと、輝きと推進力を持って表現される。このあたりに、現在の井上監督とOEKの蜜月を感じるし、円熟した関係を聴くことが出来る。
特に弦楽器群の新鮮で生彩に満ちたアンサンブルは見事。管も良い音を出しているのだが、欲を言えば、もう少し表現意欲を強く前面に出してほしい気もする。
「新世界交響曲」という、言って見れば少々聴き飽きたというような名作が、このように新鮮に生彩を持って演奏されると、やはり素晴らしい作品と再認識させられる。再現芸術の面白い由縁であり、難しい由縁でもある。
アンコールはドヴォルザークの「スラブ舞曲集」からと思われる。
今期のOEKの定期の新シリーズに大いに期待を持たしてくれる好調なスタートの音楽会だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7月、8月はOEKの定期もお休み、新シーズンは9月から、その他も夏枯れか、めぼしい音楽会も無く、少々寂しい2ヶ月間である。
そんな中、関係のある方から地元の音楽会のお誘いをいただき、7月、8月3回ほど出かけることとなる。
7月はその内2回。
7月9日、10日と開催された富山商業吹奏楽部の定期演奏会。オーバードホールという大きい会場で2日間、計4回の演奏会が行われるが、いずれも満員となるというから、さすが富商ブラスバンドと感心する。
富山のブラスバンドは長い間、富山商業と高岡商業が先頭に立ち活発に活動を展開しており、全国的にも高い水準を持っていると聴く。今回初めて富商ブラスバンドの演奏を聴き、なるほどと再認識させられた。
私がブラスバンドで活動していた時と大違いで、部員の大半が女子、そして楽器もピカピカの素晴らしいもの、演奏曲目も古典から現代までと幅広い、などとびっくりさせられることが多かった。
プログラムは3部構成で、一部が古典、2部がポピュラー、3部がマーチングとなっており、ブラスバンドの醍醐味を十分に堪能させてくれるものとなっていた。
一部のクラシックステージでは東京フィルの古田俊博さんを迎えてのハイドンのトランペット協奏曲が好演だった。
弦楽パートを木管で受け持つという、アンサンブルの精妙さが要求される作品だが、木管パートの非常に緻密なアンサンブルが印象的。トランペットの古田氏はさすが、伸び伸びとした曲想を豊かに歌いあげていた。
このステージのその他の作品も面白かったが、金管のアンサンブルが、弱音の部分でやや粗さが目立ったのが残念。
このあたりの緻密さがないと全国レベルでは中々好位置につけられないのではなかろうか。
第2部はポピュラーステージで、中ではロックン・ロール・メドレーのリズム感が抜群。特にパーカッションは見事。
各パートのソロが途中入るが、高校生離れした即興性を感じた。静かなアメージング・グレースでは、やはりアンサンブルの粗さが残念。このあたりが課題か。
最後のマーチングでは、実力を十分に発揮。パーカッションの超絶的な技巧を皮切りに、華やかなマーチングを展開。
このあたりになると、音楽的才能のみでなく、運動能力の高さも要求されるが、厳しい練習を重ねてきたことを十分に伺わせるパフォーマンスだった。
後で聴くと、衣装なども父兄の手づくりとのこと、父兄一体となり子供たちを応援する富商ブラスバンドの底の厚さに感心する。
最後に3年間活動しこの定期を最後に退く3年生の紹介、厳しい活動をやり遂げたもののみが持つ爽やかさが各人の表情に表れていた。(7月10日 オーバードホール)
次の音楽会は7月24日に行われた「第11回都子さんメモリアル 愛とヒューマンのコンサート」
オーム真理教に殺害され、僧ヶ岳の中腹で発見された坂本都子さん、龍彦ちゃん、そして坂本堤さん一家の悲劇を風化させてはならないと、有志によって続けられてきた音楽会。早いものであの事件から22年が経つ。
今回は、この音楽会に最初からかかわりを持っている、坂本堤さん、都子さんの友人でもあった日本フィルのヴァイオリン奏者松本克己さんを中心に、フランスから来日のヴァイオリンのアラン・ペルシオさん、ピアノのベッセラ・ブロスカさんご夫妻、ピアノの中島彩さんが出演。
第一部では地元で組織された合唱団「SAYTOKO」が坂本都子さんの詩に川崎祥悦氏が作曲した「あなたの心に」を中心とした合唱曲を演奏。都子さかの詩を聴くにつけ、このような不条理とも言える犯罪が何故起こったのかという無念さを改めて思う。後半はお馴染みの童謡メドレー、川崎祥悦さんの編曲の巧みさと、地元合唱団の暖かいハーモニーを讃えたい。
第2部は器楽演奏。ヴァイオリン、ピアノのご夫妻のエスプリと情熱に溢れた演奏。フランス人らしい、明るく輝かしい演奏。中島彩さんの、リスト「ラ・カンパネラ」も技巧に濁りの無い輝かしいリスト。
ヴェッセラさんはベートーヴェンの「悲愴ソナタ」、アランさんのヴァイオリンとの協演でベルディ「椿姫幻想曲」他。
残念だったのは予定時間が大幅に延び、最後のバッハが、音楽会後の予定もあり、聴けなかったこと。このあたり構成上の問題を感じる。
音楽の持つ力、それが強いメッセージとなり、社会性を持つことを再認識させられた演奏会。(7月24日新川文化ホール)
次は、「さわやかコンサート」と題された音楽会。主催が(財)あすを拓くとやま文化協会で、毎年この頃に開かれているとのこと。
OEKの主席フルート奏者、岡本えり子さん、ドイツ在住で富山に縁のあるピアニスト柳瀬敦子さん、富山在住のバリトン秋原伸行さんを迎えての、副題に「フルートとピアノでつづる音楽の旅」と題された音楽会。
岡本えり子さんは毎度OEKでおなじみで、オーケストラでの優れた独奏がいつも印象に残るフルーティストだが、独奏で聴くのは初めて。
前半と後半の最初に日本の歌曲を2曲づつ、フルートとピアノの伴奏で秋原伸行氏が歌う。かなりの高齢とお見受けしたが、年齢を感じさせない輝かしく、滑らかな声質は見事。フルートの間奏も印象的。
ピアノの柳瀬敦子さん、前半がベートーヴェンの「悲愴ソナタ」、後半がモーツァルトの「きらきら星変奏曲」、リストの「ラ・カンパネラ」。
好感が持てたのは細部までごまかさずに丁寧に弾いていたこと。モーツァルトの各変奏の表情の細かいつけ方、リストの難しいパッセージの鮮やかな表現など印象的。音質も、明るく、輝かしい。
ベートーヴェンは、やはり楽曲へのもう一歩の踏み込み、自らの個性の表出が課題でなかろうか。
岡本えり子さんは、さすかという安定した演奏。
前半にバッハ「フルートと通奏低音のためのソナタ」、後半にフォーレ「シチリアーノ」、ドップラー「ハンガリー田園幻想曲」、ジョリベ「リノスの歌」
フルートをバッハ、フォーレでは木製で、他は金属製という使い分けは的確。
バッハではややテンポが安定しなかったのが気になる。古典的なテンポの取り方は難しいのだろうか。
最後のジョリベ「リノスの歌」の鮮やかな表現力は、ピアノ伴奏の熱演と共に強烈な印象を与えてくれた。
全体として水準の高いフルート、ただややおとなしい。もっと自己主張があってもという印象。
曲間の司会者河内麻美さんの解説が短いが的確な解説で作品の理解を助ける。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第304回定期演奏会
2011年6月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 山田 和樹
ドラム ディヴィット・ジョーンズ |
|
今期フィルハーモニーシリーズ最後の定期。
当初予定の指揮者、ロジェ・ブトリーが病気で来日出来ないとのことで、山田和樹が代演となる。
山田和樹は以前にも岩城監督の代演となったことがある様で、若い指揮者にとっての腕試しのチャンスでもある。
とはいうものの、昨年ブザンソン指揮者コンクールでの優勝という経歴をひっさげての今回の指揮なので、聴く側の期待も大きい。
プログラムはブトリーのものをそのまま引き継ぎ、渡辺俊幸のドラムの協奏曲を中心としたプロ。
前半がプロコフィエフ「古典交響曲」、ラヴェルの「クープランの墓」、後半が渡辺俊幸「Essay for Drums and Small Orchesta(ドラム ディヴィット・ジョーンズ) プーランク「2つの行進曲と間奏曲」、ファリャ「バレー音楽三角帽子第一組曲」という、色彩豊かなもの。
一見して、オーケストレーションが多彩で色彩豊かなので、大きな編成を要するかと思うが、総ての作品がOEKの標準編成で演奏できる作品ばかり。トロンボーンも使われていないので、客演はパーカッションとピアノ程度か。弦楽器もコントラバス2台の8型の小さいもの。
さて、期待の山田和樹。各作品とも、個性的な響きが要求されるが、その点がやや不満。
元気がよく、バトンテクニツクも確かなので、アンサンブルに不足はなく、若さが弾ける演奏でその点では質が高いのだが、各作品の個性を描き分けるという点での不満が残る。
プロコフィエフの機知に富んだ、又ユーモアも感じさせる「古典交響曲」。誠実で真面目な演奏だが、プロコフィエフ独特の鋭さと、旋律の弾ける様な諧謔さが聴こえてこない。
ラヴェルでは、やはり色彩感の豊かさがもっと欲しい。ラヴェルのキラキラとした輝きが聴こえてこない。
プーランクでも、エスプリと遊びの自由さがもっと出ても良い。
ファリャは、たたみかける様なリズムの激しさと、クリアな響きの音が欲しい。
といわけで、期待の指揮者であるだけに、要求も多くなるのだろうが、やはり各作品の個性への肉薄、そして指揮者としての個性の発揮、そのあたりがこれからの課題となるのではなかろうか?
その中で、面白かったのは、ディヴィット・ジョーンズを迎えての渡辺俊幸のドラムの協奏曲。
2006年9月の定期で外山雄三の指揮で初演され、今回が再演となる。その時も感じたが、人間の原始的なエネルギーの奔流という感覚。根源的と言おうか、本能的土俗的と言おうか、そのようなリズムが身体を揺するような感覚。
ドラムのビートと、管弦楽の饗宴。カディンツアの部分では、ドラム以外に、おりん、仏事で用いる鐘、更には不思議な響きを出す見たことも無い様な楽器を駆使し、激しさから、静けさまで描き分ける独奏は見事。
作品の出だしでおりんをなでながら登場するが、その静かな響きも人間の本能的な静けさを感じさせる。
例えは極端だかストラヴィンスキーの「春の祭典」をも想起させるような、リズムの激しさを感ずる。
そして激しさと静けさの対比、相対する激しさと静けさでありながら、どちらも人間の根源の本能というものを感じさせられる。
今回はブトリーのプログラムをそのまま代演の山田和樹が演奏したが、ブトリーだったらどの様な個性的な響きとなったのだろうという妙な比較が心の隅に残っている。思い切って、プログラムを変更する勇気もあって良かったようにも思うがどうだろうか? |
|
|
|
|
|
|
|
五嶋みどり&オズガー・アイデン デュオ・リサイタル
2
011年6月14日 黒部市国際文化センター コラーレ |
|
五嶋みどりを聴くのは2回目。以前は6年前、ヤンソンス・バイエルン放送響との協演のシベリウスの協奏曲。
その際の、集中力に満ち満ちた演奏は印象に強く残っている。
今回は、ピアノのオズガー・アイデンとのデュオ。
プログラムは、前半、モーツァルト、「ピアノとヴァイオリンのためのソナタK.526」、ブラームス「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第一番」、後半がウェーベルン「4つの小品」、ベートーヴェン「ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第九番クロイツェル」
ここでの表記は当日の五嶋みどり自身が書いたプログラムノートによっている。ここで明らかなように、ヴァイオリンリサイタルでなく、あくまでも「ピアノとヴァイオリンのデュオ リサイタル」なのだ。通常、どのソナタも「ヴァイオリンソナタ」と記される例が多いが、ピアノが重要な役割を果たしており、対等な関係であり、ここでの五嶋みどりのこだわりは、この日の演奏の内容を端的に語っている。
それだけ、この日のピアノのオズガー・アイディンの演奏は内容の濃いものであった。
五嶋みどりのヴァイオリンの集中力は並々のものでないが、それは緊張感というものでなく、彼女自身の内面から湧き上がってくる音楽の迸りによる緊張感。決してこれみよがしに、あるいは大きな音で吠えるのではなく、作品の中で作者は何を語りたかったのかということを、楽譜から謙虚に読み取り、自分の音で表現する。これは簡単なことでないだろうが、彼女の演奏する音楽からは、それがいとも簡単なように、当たり前のように聴こえてくるから不思議である。
モーツァルト、ブラームス、ウェーベルンそしてベートーヴェン、どの作品もその作曲家の肉声が明らかに聴こえてくる。
モーツァルト。スタイルは古典的で端正であるが、その中に複雑な感情が語られる。音一つ一つに込められたモーツァルトの叫びが聴こえてくる。ここでのピアノは、その音の端正さと重さが際立っており、ヴァイオリンとの対話でモーツァルトの光と影が浮かび上がる。
ブラームスでは一転して、濃いロマンチシズム。独特のつぶやきが、時には激しい独白となり、最後には諦観のような静けさが支配。第一楽章、第三楽章の終結の音のディミヌエンド。遠くかなたに思いを馳せる様な終結、音が消えてもそこにまだ音は続いている。ブラームスの心情の痛いほどの表現。二人のデュオは雄弁というのと対極の、深い語り合いのようでもあった。二楽章の葬送を思い起こさせるような重音の凄さ。
休憩を挟んで、ウェーベルン。ウェーベルンの作品に多い、ごく小さな作品。しかし、その緊張感は並々でない。わすが、5分弱の間に展開される世界は広く激しい。聴こえない様な超弱音からたたきつけるような強い音まで、これもモーツァルトと同様、時代と手法は異なるが、やはりウェーベルンの悲痛な叫びか。
最後の「クロイツェル」ソナタ。ここでも、二人は決して激情に身を任せない。音の一つ一つを確かめるようにしっかりと進む。雄大なソナタだけに、多くの演奏はその激しさに身を任せ気味だが、二人はそれを極力内面に抑えながら、優美で雄大な世界を作り上げる。
プログラムノートの中で、五嶋は「演奏をする際には、私はいつも純然たるエネルギーに圧倒されると同時に激情を抑えるのに苦労します。」と記しているが、その通りの演奏。
第2楽章はややテンポを速めながら、歌が溢れる変奏が繰り広げられる。終結部の高音でヴァイオリンが伸びやかに歌う部分の美しさは際立っている。
第三楽章も早いテンポだが、勢いに任せず、しつかりと一音一音に意味が込められる。ピアノの雄渾な響きとヴァイオリンの表情豊かな響きの対話が楽しい。五嶋のヴァイオリンは細部にかなりの意味合いを込めているように、いつくしんでいるように響く。細部まで磨きこまれた演奏。
この作品の雄大さ、気品の高さを細部まで入念に表現しつくした演奏。
アンコールにしっとりと、ドウュッシーの「亜麻色の髪の乙女」 |
|
|
|
|
|
|
|
マーラーチェンバーオーケストラ演奏会
指揮 ダニエル・ハーディング
2011年6月11日 石川県立音楽堂コンサートホール |
|
前回の金沢公演は2003年なので、もう既に8年経ったわけである。
前回のベートーヴェンの新鮮な演奏は今も印象に強く残っているが、今回はブラームス。
前半が交響曲第4番、後半が第1番。交響曲が2曲というプロはあるようで少ない。
全曲演奏会は別として、珍しいのではなかろうか?
大阪でブラームスの全曲演奏を行うので、このようなプログラミングとなったのかと思うが、ブラームスの交響曲の中でも大曲2曲での演奏会は珍しい。
さて、ハーディングとMCO、8年前と同様の新鮮な印象を強く持った。
4番の交響曲、いきなり最初に長大な交響曲ということで、やや弦楽器は出だし硬い響きであったが、楽器が温まるにつれ、強い豊かな響きとなってきた。
編成は室内オーケストラとしては大型で、コントラバス5台の12型、ティンパニーは普通のティンパニー。8年前のベートーヴェンの演奏の際のティンパニーは記憶にないが、バロックティンパニーを使わなかったのはブラームスというロマン派の作品だからだろうか?演奏スタイル全体からすると、やはりバックティンパニーの乾いた鋭い響きが合うようにも思えるのだが。
室内オケとして大型の為、ともかく音が豊か。弦も管も非常に豊かで堂々たる音を出す。
ハーディングの指揮は、以前の一気呵成さから、ややテンポも自由に動かしながらの、しかし全体の構成感をしっかりと打ち出した堂々としたもの。
この面が4番のシンフォニーの古典的な構築の作品にぴったりとはまり、がっちりとした建造物を見る様な確かな感触を聴くことが出来た。1楽章はもう少しブラームスらしい哀切な響きがあてっもと感じたが、ハーディングはそのあたりは特に強調はしないようでむしろ淡々と歩を進める。やはり全体の古典的な均整感を失わないように、彼にとって不必要な細工はしないとの思いと聴いた。この点は以前とのスタイルと同様だが、今回はスケールがやはり相当増してていることを強く感じた。非常に古典的でがっちりとしていながら、過去のどの指揮者にもない、瑞々しさを感じるのはハーディングの類まれな個性であろう。
後半の1番も同様な演奏であるが、4番と比較するとロマン的な香りの高い交響曲だけに、かなり自由さと歌が溢れており、ここでもハーディングの円熟を聴くようであった。
細かい部分に余計な小細工は全くほどこさないが、それでいて全体に豊かなロマンチシズムを感じさせる。
2楽章の木管の独奏、特にオーボエの深く朗々とした歌、又ヴァイオリンの独奏も決して甘く歌わせず、それがかえって瑞々しいロマン性を感じさせ秀逸。第3楽章も淡々としているようで深い味わいがある。
フィナーレではかなり自由にテンポを動かしているようだが、決してわざとらしくなく全体の統一感を壊すことはない。
コーダの部分の堂々たるインテンポでの終結も見事。
全体に衒いの無い解釈でありながら、過去の演奏例に惑わされない自由さと清新さを聴くことができた。
ハーディングは間違いなく進化してきていることを再認識させられた。
アンコールの2番の3楽章も。4楽章の興奮の前のひと時の安らぎを感じさせ、そのまま4楽章を聴きたくなる誘惑を起こさせる。
ハーディングは来年の7月にはOEK定期に登場とのこと、楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第303回定期演奏会
2011年6月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 板倉 康明
ピアノ 舘野 泉 |
|
マイスターシリーズ今期最後の演奏会は、極めてマニアックなプログラム。
前半が、シェーンベルク「室内交響曲第一番」、次にピアノに舘野泉を迎えて、吉松隆「左手のための協奏曲<ケフェウスノート>」、後半がリンドベルイ「ジュビリーズ」、最後がアダムズ「室内交響曲」というもの。
定期とはいえ、これだけ馴染みの無い作品が並ぶのも珍しい。
指揮者の板倉康明は現代音楽を得意とする指揮者ということで、これだけ挑戦的でマニアックなプロとなったのだろう。
それぞれウィーン、日本、フィンランド、アメリカの作曲家ということで、現代音楽の国際色も多彩。さらに、20世紀初頭のシェーンベルクから、現代活躍中の作曲家までの20世紀音楽の系譜と個性を聴くことでも興味あるプロ。
全体を聴き終えてみると、シェーンベルクすら、やや古く正統的に聴こえるから不思議である。
そのシェーンベルクの「室内交響曲第一番」無調の音楽の先駆けとはいうものの、ホ長調という調性を明記した作品。
編成が独特で弦楽器が各パート1名ずつ、他は総て管楽器。バスクラリネット、コントラファゴット等低音の木管楽器が使われていることも独特。世紀末のウィーン独特の不安定な曲想、その中で中間章にはロマン的で印象的な旋律が現われ生成発達する。シェーンベルクの生活した当時のウィーンの不安定な世相、又音楽的にはワーグナーからマーラーに至るドイツロマン派音楽の行き詰まりと終焉、そんな中でのシェーンベルクのなんとも不安な心情を強く感じる作品。
次は左手のピアニスト舘野泉を迎えての吉松隆「左手のための協奏曲<ケフェウスノート>」
非常に平明な手法をとりながら、訴えかけてくる力は強く、個性的な作品。星座からインスピレーションを得たという通り、静かな夜の星のまたたきを感じさせる様な出だし。ピアノは静かに、時には強い星の光の様に輝く。中間部では、心の高まりを抑えきれない様なパッションがピアノと管弦楽で激しく表現され、終結部では初めの静けさの内に終わる。
舘野泉は、かつての元気な頃の激しさは影を潜めているが、内側からこみあげてくる瑞々しさは一層輝きを増しているようだ。
次のリンドベルイ「ジュビリーズ」が私にとっては非常に難解な音楽であったことと比較し、この吉松隆の平明さは一層印象的であった。
現代音楽の大きな潮流が、難解さをあたりまえとし、何か独りよがりで、聴衆からかい離したものとなっているように感じるのは私の不勉強の所為であろうか?
聴衆を置いてきぼりにした、ひとりよがりは、音楽としてやはり一面的である様に思うのだが。
というわけで、リンドベルイの作品に対する感想は現在持ち合わせていない。
ただ、大太鼓、ヴィブラフォーン等打楽器の響きは印象的。ヴィブラホーンをティンパニ奏者の菅原さんが叩いているのを見て、なるほどヴィブラフォーンは打楽器だったと妙に納得。
最後はアメリカの作曲家アダムスの「室内交響曲」
シェーンベルクの「室内交響曲第一番」に対するオマージュとして作曲されたというこの作品、なるほど楽器編成が凝っている。シェーンベルクと同様の楽器編成に、ドラムスとシンセサイザーを加え、更にピッコロの鋭い響きを用いている。
作品の印象は、やはりアメリカの他のミニマル・ミュージックと同様、刺激と興奮を呼び起こすような印象。
ポップなノリと言い、2部のブルースを思わせるトロンボーンの旋律、3部の身体を揺すられるようなリズムの饗宴など、アメリカ以外のどこでもない、将にアメリカの音楽。個性的である。
色々な打楽器の特色ある音色が全体を作り上げているが、特にドラムスは種々の打楽器のソロで多彩。奏者の渡辺さんも見事。
終章では、ヴァイオリンのカデインツア風の独奏が最後を飾るのも印象的。
こうして、20世紀から21世紀に渡る現代音楽を聴いてみると、このわずか数曲のプログラムの中でも様々な傾向を聴くことが出来興味深い。
やはり、最後に残るのは作曲家の個性が聴衆をとらえて離さない、そんな音楽ではなかろうか?
仕掛けやテクニックだけが先行し、聴く者にとって印象が散漫になってしまうような音楽は生き残ってはいかない。
但し、真に個性的とはどのようなものかの問いの答えは難しいが。「創造された音楽のみが答えを語る」というと、禅問答のようになってしまうが。 |
|
|
|
|
|
|
|
ロシア国立交響楽団演奏会
2011年5月31日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 西本 智美
マルク・ゴレンシュタイン
チェロ アレクサンドル・ブズロフ |
|
東日本大震災の影響で、外国からの多くの演奏家が来日を中止する中で、このオーケストラは予定通りやってきた。
指揮は西本智美と音楽監督マルク・ゴレンシュタイン、チェロが変更となりアレクサンドル・ブズロフ。
旧ソヴィエト国立交響楽団で、前監督はスヴェトラーノフ、幾度となく来日し、その都度重戦車の様な響きで聴衆を圧倒してきたオーケストラ。スヴェトラーノフ亡き後のこのオーケストラの状況を聴きたく、足を運んだ。
プログラムは得意のオールチャイコフスキーで、前半が劇的付随音楽「雪姫」より3つの小品、「ロココ風の主題による変奏曲」、後半が交響曲第5番。
編成は大型で、16型。最近珍しいオーソドックスな楽器配置で、左から第一Vn、第二Vn、Vra、Ce、Ceの後ろにCb。
変わっていたのは、ティンパニーが左側に位置し、ホルンが右側に位置していたこと。
さて、前半は西本智美の指揮。今回の日本ツァーでは西本が交響曲第5番を指揮したプロが多かったようだが、金沢は5番は音楽監督ゴレンシュタイン。
西本の指揮ぶりは相変わらず華麗で、花がある。長身、美人であるので、指揮ぶりはピシット決まり、見ていて気持ちの良い指揮姿である。これで3回目聴くことになるが、回を重ねるごとに指揮のテクニックが鮮やかになっているよう。
最初の「劇的付随音楽「雪姫」より3つの小品」は珍しい作品。このオーケストラの特長である厚い響きをたっぷりと聴かせながら、3曲目では劇的な盛り上がりを巧みに作り上げていた。西本はバレエ音楽等、小品の積み重ねの様な作品の演奏を得意にしているようで、劇的効果の盛り上げ方など堂にいっている。
「ロココ風の主題による変奏曲」は当初の予定のアレクサンドル・クニャーノフが来日せず、アレクサンドル・ブズロフのチェロに変更となった。これも、震災の影響か。
アレクサンドル・ブズロフというチェリスト、その音色の柔らかい暖かさは格別であった。チェロは豪放に弾くソリストが多いが、ブズロフは繊細で暖かい。それが、この作品の気品の高さとマッチングし、密度の高く、しかしおおらかな演奏となっていて気持ちが良い。特に終結部の前のアダージョの部分のゆったりと、しみじみと歌う部分は聴きごたえがあった。終結部も決して弾きまくるのでなく、歌を感じさせる終結部。アンコールに終結部を再演。
さて、後半の交響曲5番。このオケ、おはこの作品。安定した演奏。ゴレンシュタインはこの作品をいじりまわすことなく、正面からの堂々とした演奏。オケも作品を知り尽くした演奏で、安心して身をゆだねられる。
ただオケとして、スヴェトラーノフの時代よりやや安定感を欠いているようで、特にホルンのパートなど、数回音を外すなど、気になる点があった。第2楽章の大切なホルンの独奏も、やや不安定。
金管の咆哮など、そのすさまじい迫力は十分だが、細部に緊張感が欠けていたのは、やや残念。慣れ過ぎている作品の演奏の陥りやすい穴である。
アンコールに「東日本大震災の被災者に捧げます。」とのコメントに続いて、ラフマニノフのヴォカリーズが、静かに演奏された。厚い弦の響きと木管の悲哀の響きが印象的。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第302回定期演奏会
2011年5月25日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 アレクサンダー・リープライヒ |
|
ミュンヘン室内管弦楽団の芸術監督、アレクサンダー・リープライヒを客演に迎えてのコンサート。
プログラミング、内容とも極めて個性的な演奏会。
前半が、ペルト「レナルトの追憶に」、ハイドン「交響曲第98番」、後半が、ルトスワフスキー「葬送曲(バルトークの思い出の為に)」、ハルトマン「交響曲第4番」というもの。
ハイドンを除いては総て弦楽合奏によるもの。
全体を通して、メッセージ性の強さ、表現意欲の強さが、弦楽合奏を強靭に響かせることで、聴衆に強く伝わってくるのを感じる。
作品もハイドンを除いて総て現代のレクィエム、それもその時代に殉じていった人たちへのレクイェムということで、音楽と政治・社会ということを深く考えさせられる内容を含んだ、含蓄のあるプログラミングであった。
最初のペルトは、以前クレメルの率いるクレメラータ・バルティカでその作品を初めて聴き、印象に残った作曲家。
今日の作品は、前エストニア大統領の死を追悼する音楽として書かれたとのこと。ペルト独特の繰り返し奏されるしみじみとした旋律が印象的。ペルトの個人への強い思いと痛みが伝わってくる。
ハイドンではサプライズがあった。チェロ、コントラバス、ティンパニーを除く全員を立たせての演奏。
イムジチ等、10数名のアンサンブルで全員起立しての演奏の記憶はあるが、オーケストラでは前代未聞。
リープライヒが、どの様な意識の下でこの様にしたのか興味深いことだ。
ハイドンの音楽の持つ、生き生きとしたリズム感を身体全体を通して表現して欲しかったのだろうか?
オーケストラにとっては過酷な演奏ではあった。
ハイドンはOEKにとって得意の分野で、これまでも故岩城監督、井上マエストロ、つい先日は安永徹と、名演が思い浮かぶが、この日の演奏も極めて個性的。整然とした隙の無いハイドンというより、荒々しさと新鮮さを追求した様な演奏。
管楽器、ティンパニーの強奏、弦楽器の強い響き等、調和よりもヴィヴイットな荒々しさを表現しようとした様な演奏。
ハイドンがその時代において、先鋭的な音楽家であったことが改めて認識させられた。
この演奏のみ対向配置で、演奏スタイルもピリオド奏法に近い。古典音楽の鋭さを感じた。
後半は更に深遠な弦楽合奏の世界。
ルトスワフスキーはポーランド前衛音楽の旗手の様な印象を持つが、この作品では旋律の美しさと、構成の巧みさが際立っていた。初めのチェロの唸るような痛切な旋律から始まり、それがビオラ、ヴァイオリンと次々に受け渡され、中間部の慟哭の様な激しさから、最初に帰り、最後はピチカートで静かに終わる。各弦楽パートの合奏の太い響きや、ヴァイオリンの叫びの様な鋭い合奏が際立つ。中間部では、リズミックなジャズ的とも聴こえる高揚が聴かれるのも印象的。
12音技法で書かれているというが、ルトスワフスキーにとって、技法が目的でなく、表現の手段であることがよく聴き取れる作品。
最後は、ハルトマンの交響曲第4番。ハルトマンも中々演奏会では聴くことの出来ない作曲家。ナチスの時代に公然とナチスを批判し発表、その時代のドイツ音楽界から追放された作曲家。第2次世界大戦後、再評価され、8曲の交響曲は彼の代表作とのこと。
この4番はナチスによって犠牲となった多くの人たちのレクイェムとして作曲されたようだ。
弦楽合奏のみによる3楽章の作品。特筆すべきは、痛切な第一楽章に続く第2楽章スケルツォの激しさ。
弦楽器を叩きつける様な強い響きとリズム、この楽章で゛何を表現しようとしたのか?
ハルトマンの怒りか、戦争への怒りか、ナチスの虐殺に対しての憤りか、様々な事を考えさせられる激しさ。
OEKのこの部分での合奏の凄さは鬼気迫るものがあった。
そして怒りの後の、祈りの様な第3楽章。消え入るような終結。
指揮者は音楽が消えても、暫くはタクトをあうげたまま。その間、静かな空間にレクイェムがまだ聴こえている様な空間。
指揮者が静かにタクトをおろすと、静かな拍手が広がっていった。
音楽に高揚と沈潜を形容するなら後者、いつまでも心の記憶に残るような作品と演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第300回定期演奏会
2011年5月13日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ヴァイオリン ボリス・ベルキン |
|
記念すべき節目、300回の定期公演のプログラムはオール・ショスタコーヴィッチ。
ショスタコーヴィッチを最近ライフワークにしているような井上監督の気鋭のプログラム。
来年のシリーズでは、14番の交響曲が予定されている様で、「ショスタコーヴィッチの作品はOEKの編成では小さいので、今後はあまりやりませんので、ご安心を。」という監督のアンコール時のお話とは裏腹に、かなりショスタコーヴィッチにこだわっているようにも思える。
さて、この日のプロは、バレエ組曲「黄金時代」、ボリス・ベルキンを独奏者に迎えてのヴァイオリン協奏曲第1番、後半が交響曲第1番。興味あるプログラム。
編成も客演奏者を増やし、コントラバスが4本、第一Vn11の、やや変則的な12型。
バレエ組曲「黄金時代」は知られた作品であるが、全曲を生で聴くのは初めて。(ポルカのみ、以前このコンビで聴いたが。)
ショスタコーヴィッチらしい、皮肉とアイロニーに溢れた作品。
解説プロのこのバレエのあらすじを読むと、ショスタコーヴィッチのせせら笑い、嘲笑が聴こえてくるようで、面白い。
当時のソビエト当局が、真面目な顔で、このバレエを見ていたことを想像すると、それも又愉快ではある。
それにしても、ショスタコーヴィッチの管弦楽法の見事さが浮き彫りになったような作品で、実に面白い。
1楽章では、小型オルガン(ハーモニウムと記されているが)の前板を外し、音が前面に強く出るように工夫されたオルガンの音が印象的。
切れ味鋭い井上監督の指揮ぶり、それに応えるOEK、各セクションの独奏も効果的で、実に痛快な演奏。
2曲目のヴァイオリン協奏曲第一番。うってかわってシリアスなショスタコーヴィッチの側面を強く出した作品。
全曲に渡り、暗澹たる緊張感が支配し、作曲家の心情が吐露される。
特に3楽章のパッサカリアのヴァイオリンの長い独奏は心を打ち印象的。
この日の独奏者ボリス・ベルキン、安定した演奏。ただ、音色が柔らかい分、この作品の鋭い緊張感がやや不足していた感があった。
前述の3楽章に特にそれを感じた。4楽章は鮮やかな技巧を聴かせてくれたが、全曲を通してのこの作品の鋼鉄の様な冷たい緊張感を期待するものとしては、物足りなさを感じたのも事実。
休憩後は交響曲第1番。第1番とはいうものの、個性あふれるショスタコーヴィッチの世界の展開。
後期ロマン派から現代への移行期であるが、それまでのロシア音楽の系譜から見事に離れた個性の展開。
ロシア音楽新時代を強く感じさせる音楽。
作曲者独特の言語が飛び交うが、各パートにそれを託しているので、アンサンブルの妙より、各パートの独奏の面白さが大切な作品だが、OEKの各パートは見事に表現していた。
井上監督のキリリと引き締まりながら、アクセントの強い指揮ぶりはこの作品の面白さを際立てていた。
第3楽章の耽美的な表現、第4楽章の緩急の切り換え、金管、ティンパニーの鋭い響き等、強烈な印象。
それにしても、19歳のショスタコーヴィッチの天才的な出現と、当時の人は感じたことだろう。この後、15番まで、20世紀の激動期のソビェト社会で、閉塞的な状況の中で、時代と自らを個性的に表現し、生き抜いたショスタコーヴィッチの凄さを、この交響曲は改めて考えさせてくれる。、
アンコールに時代を遡って、チャイコフスキーのオペラ「エフゲニオネーギン」からポロネーズ。これも鮮やかで力強い演奏。井上監督の踊るような感性が光る。 |
|
|
|
|
|
|
|
ソウル・フィルハーモニー管弦楽団演奏会
2011年5月12日 オーバードホール
指揮 チョン・ミュンフン
ヴァイオリン 庄司沙矢香 |
|
ラフォル・ジュルネに登場のウォンジュフィルに続いて、韓国のオーケストラ、ソウルフィルの日本初登場。
ソウルフィルは60年の歴史というから、韓国の代表オーケストラと言えよう。韓国の音楽的英雄、チョン・ミョンフンを音楽監督に迎え、最近飛躍的な活躍を見せているという。
今回の演奏会は初の日本ツァー、東京、大阪、富山のみの公演とのこと。
今回は当初発表のプロがドヴュッシーの交響詩「海」が中心の前半のプロと、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」
だったが、東日本大震災に鑑み、「海」を外し、前半が庄司沙矢香を迎えてのチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲に変更となった。チョン、庄司のコンビは中止となったチェコフィルの演奏会で同じ協奏曲を演奏することとなっていたので、急遽の変更に対応することとなったのだろう。
さて、ソウルフィル、期待にたがわぬパワフルで情熱的な演奏を聴かせてくれた。
編成は大きく、後半は18型の大編成、コントラバスが10台ずらりと並んだ舞台は、楽団員で溢れそう。
楽器配置もオーソドックスで、1Vn、2Vn、Ce、Vra。Ce、Vraの後ろにCbというもの。
面白かったのは、最近のオーケストラは演奏直前に拍手に迎えられて楽団員が登場というスタイルが多いが、ソウルフィルは管楽器奏者が先に席につき各々練習、その後三々五々と他の楽団員が並ぶという、昔N響等が行っていたスタイル。
私たちの様な時代の愛好家にとってはこのスタイルに馴染んできているので、この方が違和感がない。
さて、最初のヴァイオリン協奏曲。庄司のシャープで堅固、スケールの大きなヴァイオリンと、チョンの叩きつけ、えぐり取るようなオーケストラが正面からぶつかりあい、火の出る様な白熱した音楽世界を作り上げていた。
1楽章では、ゆつたりと歌う部分は図太く、緊張感を持った独奏ヴァイオリンに豊かな音量を持つ木管が豊かに寄り添い歌い、早いパッセージではオーケストラのたたきつけるようなパッションにヴァイオリンも負けじと応じるなど、コンチェルトの醍醐味十分。終結部では、両者ともやや早くテンポをあおり、炎が燃え盛るような激しさで閉じる。
2楽章の豊かな歌、ここでも管楽器の太く豊かな音色と独奏ヴァイオリンのからみが魅力的。両者の息を呑むような緊張感に包まれながら、2楽章と3楽章のパッセージが、なだれ込むように3楽章に続く。3楽章は将に激情の音楽。
両者とも激しくぶつかり合うのだが、そこには恣意的に崩すことはなく、総ての音がクリアに厳格に響く。
音楽の枠組みをきちんと守った、全体としてのスケールがとてつもなく大きな演奏。
この協奏曲は魅力的な旋律、躍動感に溢れているので、それを強調するあまり、構成感が崩れた演奏を聴くこともあるが、今日の演奏は崩すところが全くない真面目な演奏。やはり、庄司の作品に対する真摯な取り組みが聴こえてくる演奏。
大きなホールでの大編成のオケを伴奏での演奏だが、庄司のヴァイオリンは埋没することなく、朗々とホール一杯に響き渡る。とてつもなく豊かな音色の持ち主。しかし、それは鋼鉄の様な強い意思を持った響きでもある。
後半は、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」
名曲中の名曲であり、何度聴いたことか。しかし、今日の演奏は圧巻。
チョン・ミョンフンも幾度となく聴いてきたが、今日は自国のオケを引き連れての公演、意気込みが違ったようだ。
1楽章のCbの低音に支えられてファゴットが主題を奏でる部分、その繰り返しの部分で、思い切って長い休止を置き印象を深くする。展開部の金管の咆哮、特にトロンボーンとチューバを最後の最後まで力強く吹かせる部分の凄さ。
オケの音質としては硬めなのだが、その硬質の響きが、チョンの厳格な指揮に会っているようだ
2楽章のワルツはやや厚めの音色が印象的。3楽章。マーチだが、4楽章の前のこの楽章の激しさには常に驚きがあるが、この日の驚きは将に極大。終結部の激しさは尋常でない。巨大な構築物が目の前に現れ、崩れ落ちる様な凄さ。
ソウルフィルの全力をつくしての強奏はホールを揺るがす。
続く4楽章、ここでも中間部での悲劇的なテーマの盛り上がりは異常な程。指揮者の歌う声が3階最前列まで届くような熱演。しっかりとした構築の上に、豊かな音と大きな感情が息づく、スケールの大きな人間ドラマを聴くよう。
高まりが収まり、ドラの印象的な響きで静かに締めくくられるが、終結部の管楽器の厚い静謐な響きも印象的。
この作品は拍手のタイミングが難しいが、チョンは暫く指揮棒を上げたまま動かず、タクトを置くのを待って静かに拍手が広がっていったのは良かった。
アンコールは何と同じチャイコフスキーの交響曲第4番第4楽章。交響曲の1楽章のアンコールも珍しいが、「悲愴」最後の静けさの後に、指揮台に上るなりさつとタクトを振り、あの激しい出だしが響いてきたのにはびっくりした。
これは将に手に汗握るという形容がふさわしい快演。管楽器群の早く強いパッセージ、それに負けじとやはり早いテンポの弦楽アンサンブル、そして打楽器群の激しい響き、指揮者の容赦ない要求にオーケストラは見事に応えていた。
初めて聴くソウルフィルだが、その技量の高さと、個々の奏者の音楽に向かう真剣な姿勢に驚いた。
時々、気の抜けた様な演奏をする日本のオケもあるが、見習うべき音楽への姿勢である。 |
|
|
|
|
|
|
|
ラ・フォル・ジュルネ金沢2011 ウィーンのシューベルト
2011年5月3日~4日 石川県立音楽堂コンサートホール、邦楽ホール、アートホール |
|
4回目を迎えたラ・フォル・ジュルネ金沢、今年は「ウィーンのシューベルト」をテーマに4月29日より開催された。
今年は集中公演日が3日、4日と二日間。東北関東大震災の影響を受けて、出演者の辞退があったりと、開催するのに困難な状況が多い中での開催、主催者も大変なご苦労があったことと推察する。
そんな状況の中でも、各公演の水準は高く、又聴衆もすっかりこの音楽祭に慣れてきたこともあり、各公演とも「熱狂の日」の言葉通り、大きな盛り上がりと感動をもたらしてくれた。
シューベルトを2日間に渡って聴いたわけだが、膨大な作品の中の、ごく一部とはいえ、シューベルトの音楽世界を集中的に体験できたことは、この音楽祭ならではの貴重な体験。
今年は特に、室内楽、ピアノ等の分野で、充実した演奏会が多かったように思える。
この分野では、後期のシューベルトの作品の演奏が多く、その点でも特筆すべきであるように思う。
後期の作品は、ベートーヴェンの後期の作品に匹敵するような、深遠な世界が展開される点で、演奏者と聴衆には異常な緊張が要求されるが、今回の各奏者たちの演奏は、その息をひそめる様な緊張感に満ち満ちた演奏が多く聴かれ、聴く者に、心にしみこむような感動を与えてくれた。
ピアニストに個性的な奏者が揃い、その個性がシューベルトの音楽の解釈に多様に現れていたことも興味深かった。
又、今年はウォンジュフィルハーモニーという韓国の若いオーケストラが出演、韓国の音楽水準の高さを認識させてくれたことも貴重な体験。
OEKはホストオケとして、今回も安定した水準の高い演奏を聴かせてくれた。
4回目ということもあって、運営も手慣れてきたことを感じさせたが、何点か気のついたこともあった。
①例年配布されていた作品と演奏者の紹介のチラシが今年は配られなかった。演奏者、プログラムの変更が相次ぎ、準備が出来なかったのかとも考えるが、今年は特に変更が多かったので、何とか配布していただきたかった。
②プログラムの変更について、ホール入口に掲示されていただけで、変更のアナウンスなどが一部では無かった。これは、やはり不親切である。掲示に気づかない人も多いと思える。
③スタッフの方たちは例年以上に気遣いが良く、特に公演間の移動の際、次回の公演時間を遅らせていること等を知らせていただいたのは良かった。出来れば、終演後のアナウンスでも案内をしていただければ尚良いのではなかろうか。
会場の外では、例年通り音楽パフォーマンスが種々繰り広げられ、金沢駅前一帯は音楽祭一色に塗りつぶされ、ラ・フォール・ジュルネが金沢の年間の重要行事として定着してきたことをうかがわせた。
私が聴いた個々の演奏会について短い感想を下記していく。
庄司 紗矢香(vl)
タチアナ・ヴァシリエヴァ(vc)
※ミシェル・ダルベルト(p)
シューベルト:ピアノ三重奏曲第2番 変ホ長調 D929
3日11:00~11:45
邦楽ホール
ダルベルトのピアノがアンサンブルをリード。構成のしつかりした、がつちりしたピアノ。シューベルトの古典的造形がくつきりと浮かび上がる。又、弱音の柔らかい響きも印象的。
庄司のヴァイオリンはやや控えめ、独奏者としての彼女を聴いているものとしては意外な程おとなしい。チェロもアンサンブルとしてのチェロに撤し、落ち着いたハーモニーを響かせ
る。
2楽章の沈潜した行進曲風の歩み、4楽章のスケールの大きさが印象的。 |
田部 京子
シューベルト:ピアノソナタ第21番 変ロ長調 D960
3日12:30~13:15
アートホール
出色のシューベルト。
長大な後期のソナタが、息を呑むような緊張感をもって演奏された。
1,2楽章では音のひとつひとつに祈りが込められたような、深い思索が展開される。
3、4楽章では、絶望から立ち上がるろうとする希望、祈りを聴く。
田部の作品に込められた思い、思索の表現力が鬼気迫る。
テクニックとか、音色の美しさとかを超越した、プロの音楽家としての表現力の大きさに敬意。 |
オーケストラ・アンサンブル金沢
指揮 井上 道義
ソプラノ 森岡 紘子 テノール 志田 雄啓
オーケストラ・アンサンブル金沢合唱団
シューベルト:交響曲第5番 変ほロ長調 D485
シューベルト:キリエ ニ短調 D31
キリエ ヘ長調 D66
3日14:00~14:45
コンサートホール
5番のマエストロは平服とズックで登場、会場を沸かせる。
編成の小さな交響曲だが、弦楽器の気持ちの良いアンサンブル。ただ、今日のOEKはやや、元気不足。キリエは短い作品だが、シューベルト初期の瑞々しさに溢れた作品。
OEK合唱団も相変わらず好調。1曲だけに出演した声楽、贅沢なプロクラムではある。 |
オリヴィエ・シャルリエ(vl)
アンドレイ・コロベイニコフ(p)
シューベルト:ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第2番イ短調D385op137-2
シューベルト:さすらい人幻想曲 ハ長調
3日15:00~15:45
邦楽ホール
ヴァイオリンのシャルリエは端正で堅実なヴァイオリン。
対するピアノのコロベイニコフは若々しく激情的。アンサンブルとしては、もう少しヴァイオリンに主張が欲しい気がした。
「さすらい人幻想曲」のコロベイニコフは、実にロマン的で、かつ自由奔放。
この作品の激情とロマンティックな歌を存分に表現。 |
ライプツィヒ弦楽四重奏団
アンリ・ドマルケット(vc)
シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D956
3日16:30~17:15
邦楽ホール
50分以上の演奏時間のシューベルト晩年の大作。
柔らかく、尚深く芯の強いアンサンブルはこの作品にぴったり。豊穣のアンサンブルとでも言えようか。
言いようの無い寂寥感の表出、全曲に絶望的な響きが充満し、シューベルト晩年の心情が再現される。 |
オーケストラ・アンサンブル金沢
井上 道義(指揮)
オリヴィエ・シャルリエ(vl)
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
3日16:30~17:15
コンサートホール
今回シューベルト以外ではベートーヴェンのみを聴いた。
その中の一公演。
端正で美しい音はこの協奏曲の性格にあっている。ただ、強い個性的の表出にはややもの足りなさも感じられた。
OEKはこの作品手慣れたもので、堂々とした演奏。特に木管は独奏ヴァイオリンと絶妙の絡み合い。 |
鈴木秀美(vc)/若松夏美(vl)
高田あずみ(va)
シューベルト:弦楽三重奏曲第1番 変ロ長調 D471
ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 ト長調 op.9-1
3日19:00~19:45
邦楽ホール
古楽アンサンブル、・リチェルカール・コンソートの代演だが、日本トップの古楽奏者によるアンサンブルで豪華な代演となった。
古楽アンサンブルの極みとでも形容できるような名演。
素朴な中に、暖かさと情熱を備えた響き、古典のパッションとでも言えようか。
興味深かったのは、ノンヴィブラートではなく、必要な部分ではヴィブラートをかけていたこと。表現の自由さを感じた。 |
ウォンジュ・フィルハーモニー管弦楽団
ヨンミン・パク(指揮)
シューベルト:交響曲第9番 ハ長調 D944
3日20:00~21:00
コンサートホール
珍しい韓国のオーケストラの登場。19日には富山で韓国を代表するソウルフィルの演奏会がある等、興味津津であった。
結果として、想像以上の力量のオーケストラであり、韓国の音楽水準の高さを感じた。
指揮者のバクも若い指揮者でありながら正統的な音楽づくりで好感をもった。
編成は12型で、配置は最近では珍しい、1Vn、2Vn、Vra、Ce、Cbと並べたスタンダードなもの。最終楽章にいたり、やや粗さも露呈したが、この長大な交響曲を弛緩することなく演奏
したことは見事。
指揮者次第では相当レベルの高い演奏を行うのではないかと想像する。 |
ミシェル・ダルベルト(ピアノ)、ラファエル・ピドゥ(チェロ)
シューベルト:楽興の時 1, 2, 5 D780
シューベルト:即興曲 D899-3,2
シューベルト:アルペジョーネ・ソナタ イ短調 D821
4日10:30~11:15
コンサートホール
ダルベルトのシューベルトは作品をいじりまわすことなく、正面から堂々と打ち出すような明確な解釈。スケールの大きな歌を聴くことができた。
ピドゥは出だしやや不安定だったが、1楽章後半からよく歌いだし、ノリノリの演奏となり、最終楽章は伸びやかで艶やかなチェロの音色が朗々と歌い、この作品の魅力を存分に聴か
せてくれた。 |
オーケストラ・アンサンブル金沢
山田 和樹(指揮)
松原混声合唱団
シューベルト:「キプロスの女王ロザムンデ」 D797より
羊飼いの合唱「野原を越えて」
ブラームス:悲歌op.82
シューベルト:交響曲第3番 ニ長調 D200
4日 12:00~12:45
コンサートホール
特筆は合唱団。声量の豊かさ、表現力の大きさは素晴らしいもの。雄大な合唱団。
山田和樹は瑞々しいシューベルトを聴かせてくれた。
ブラームス、聴くのが珍しい作品だが、悲劇的な色彩に彩られたドラマティックな作品で、合唱団の素晴らしさが際立っていた。
3番の交響曲は若々しさが弾けるようで、山田のフレッシュな感覚の気持ちの良い演奏。
今回、オーケストラ演奏会がやや寂しい入りで、この日もOEKの演奏には珍しく空席が目立っていたのはどうしたことか。 |
トリオ・ヴァンダラー(ピアノ三重奏)
シューベルト:ピアノ三重奏曲 D897「ノットゥルノ」
シューベルト:ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 D898
シューベルト(マントヴァーニ編曲):フランツ・シューベルトの名による8つの楽興の時
4日 13:00~14:10
邦楽ホール
シューベルト晩年のトリオの1番だが、晩年の作品に珍しい明るい色調。演奏もフランスのアンサンブルらしく、輝かしく明るい。歌に満ち溢れスケールも大きな演奏。
ピアノの転がるような美音が印象的。
最後の作品は、想像と全く異なる、現代的激しさを有した前衛作品。「楽興の時」がどの部分に使用されているのかわからなかったが、全くシューベルトを意識させない別の作品と聴
こえた。ここでは、トリオのたたきつけるような激しさが印象的。 |
ライプツィヒ弦楽四重奏団
シューベルト:弦楽四重奏曲第13番 イ短調 「ロザムンデ」 D804
4日 15:00~15:45
邦楽ホール
ライプツィヒ弦楽四重奏団の大きな特長と思われる厚く軟らかい響きが全曲を彩る、
豊穣のアンサンブル。
1楽章のヴァイオリンの素朴で柔らかく寂しい響きが全曲を支配。
緊張と集中力に溢れた演奏だが、決して力まない、自然な旋律の流れが、シューベルトの歌の素晴らしさを表現する。 |
オーケストラ・アンサンブル金沢
井上 道義(指揮)
ミシェル・ダルベルト(p)
シューベルト:交響曲第2番 変ロ長調 D125
シューベルト(リスト編曲):さすらい人幻想曲 ハ長調
D760(ピアノ・オーケストラ版)
4日 16:00~16:55
コンサートホール
2番のシンフォニー、私が一番好きな交響曲。
この日の井上・OEKのコンビは最高の演奏。この作品の弾ける様な快感を見事に表現。
弦楽器を究極まで追い立て、たたみかけるような迫力を生み出していた。
指揮者の酷なと思われる要求にOEKは見事に応じ、隙の無い、ピシットしたアンサンブルを聴かせてくれたのはさすが。
リスト編曲のさすらい人幻想曲。リストらしい豪放さと、濃いロマンチシズムに溢れた作品。リスト編曲は原曲とは異なる劇的迫力を生み出している。
ピアノとオーケストラの豪快なぶつかり合いも見事。
オケもピアノも互いを主張しながらも、よく溶けあい、ドラマを感じさせる演奏。 |
ヴォルフガング・ホルツマイアー(Br)
ジュゼッペ・マリオッティ(p)
シューベルト:歌曲集「白鳥の歌」 D957より
「アトラス」「彼女の絵姿」「漁夫の娘」
「海辺で」「都会」「影法師」「鳩の使い」
「愛の使い」「兵士の予感」「春の憧れ」
「セレナード」「別れ」
4日 17:15~18:00
邦楽ホール
劇的で迫力のある表現力。声質は柔らかというより輝かしく豊か。
「アトラス」「都会」「影法師」等の劇的迫力に溢れた歌唱は見事。
「セレナード」等抒情的な歌では、柔らかさが欲しい気もした。
ピアノの表現がやや弱く、引き気味であったのは残念。 |
アンヌ・ケフェレック(p)
吉田 秀(cb)
ライプツィヒ弦楽四重奏団
シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 D667「ます」
4日 18:30~19:15
アートホール
ケフェレックの華やかで弾ける様なピアノはこの作品にぴったり。
ただ、弦楽のアンサンブルがやや粗い。
コントラバスが張り切りすぎ、その音が前に出て邪魔をしている。
やはり、急造のアンサンブルの難しさか。
皮肉な言い方をすると、コントラバスが活躍する作品という再認識。 |
仲道 郁代(p)
シューベルト:4つの即興曲集 D899より第2番 変ホ長調
シューベルト:4つの即興曲集 D935より第3番 変ロ長調
シューベルト:ピアノ・ソナタ第13番 イ長調 D664
4日 19:30~20:15
邦楽ホール
今回はピアノに個性的な奏者が揃い、それぞれの個性でシューベルトを聴かせてくれた。最後が仲道郁代。
気品の高い、又人懐っこいシューベルトといえようか。
他の奏者に比較すると強い個性の無いように聴こえるが、それがこの人の個性。
これだけ自然に、美しく弾くことは中々出来ないだろう。
独特な歌わせ方も随所にあるのだが、それが嫌みでなく自然に聴こえる。
アンコールのショパン、エルガーなどはその極み。音楽が美しく、優しく語りかけてくる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第299回定期演奏会
2011年4月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
リーダー&ヴァイオリン 安永 徹
ピアノ 市野あゆみ 神永睦子
独奏 サイモン・ブレンディス 江原 千絵 ヴォーン・ヒューズ(ヴァイオリン)
ルドヴィード・カンタ(チェロ) |
|
私の記録によると、以前の登場が2007年7月なので、4年ぶりのOEKへの登場の安永徹。5回目の共演ということになるのだろうか?
3回目から聴いているが、いつもながらの安永徹の作りだす精緻なアンサンブルが更に進化していることに驚愕である。
今日のプログラムは前半が、モーツァルト「ピアノ協奏曲第10番(2台のピアノのために)」、後半がヴィヴァルディ「4つのヴァイオリンとチェロの為の協奏曲(合奏協奏曲「調和の霊感」より)、ウェーベルン「弦楽四重奏より緩徐楽章」、
最後がハイドン交響曲第92番「オックスフォード」というもの。
楽器配置はコントラバスを左側に配置した対向配置。ティンパニーはバロックティンパニーを使用。
最初のモーツァルト。市野、神永の息のあったデュオが見事。市野のモーツァルトは音色、フレーズの歌わせ方、テンポ等総てが心地よく流れる。モーツァルトの音楽の気品高い愉悦が、生き生きと弾け出てくる。
この日はデュオだが、この二人の呼吸がぴったり。お互いに相手の投げかけてくるフレーズを、自分の気持ちを籠めて返していく。絶妙な呼吸であり、モーツァルトが2台のピアノの為に作った意図が、聴く側にも明確に聴こえてくる。
第3楽章のロンドはその典型で絶妙。カノン風の展開が、2台のピアノのこだまのようなやりとりで、生き生きと進行していく。モーツァルトの音楽の神髄が示されたような演奏。ころころと、心弾けるような音楽。
伴奏も指揮者無しで合わせるのも大変と想像するが、安永の弾きぶりは大きな動作もないのに、ぴったりとピアノに寄り添っていくのは見事。木管がピアノにからまるフレーズなども、安永リーダーが目で小さく合図しているようだが、独奏者との呼吸もぴったりと合う。オーケストラもピアノも同じ呼吸をしているような気持ちよさを感じた。
休憩を挟んで、後半の最初はヴィヴァルディ。ピアノに変わり弦楽との協奏交響曲。ここでは、なんといっても安永徹の輝かしいヴァイオリンの独奏が聴きもの。オーケストラも独奏者にひっぱられ、華麗で明快な合奏の響き。
OEKのヴァイオリン、チェロのトップを独奏者としているが、これもモーツァルトと同様、呼吸がぴったりで、互いの独奏者の受け渡しもスリリングに展開。絶妙なアンサンブルである。
次が、珍しいウェーベルンの作品。無調音楽しか想起しないウェーベルンのこれは又何と繊細で、ロマンティックな作品。
まるで映画音楽の様な濃いロマンチシズム。シェーンベルクの「浄夜」を思い起こさせるような部分もある。
ここでの合奏も柔らかく厚い。弦楽合奏の各パートの磨き抜かれたアンサンブルは、OEKの合奏能力の高さと、安永徹の感性の豊かさの結合した頂点を示している。
最後はハイドン。過去も、最後はシンフォニーで、モーツァルトの38番、シューベルトの3番と続いていたが、今回はハイドン。ここでも安永は指揮台に立たず、トップヴァイオリンの位置。
過去の演奏の自らの感想を顧みると、シンフォニーの場合、アンサンブルの精緻さとうらはらに、音楽の自発的な発露にやや欠けているような印象を感じていたようだが、今回はそのあたりが払拭されていた。
各パートか゛安永リーダーの意思をしっかり受け取り、自らの音楽として表現していることを感じた。
単にアンサンブルが見事というだけでない、オーケストラとしての個性が感じられ、ハイドンの音楽の躍動感、古典的造形美が生き生きと表現されている。
ハイドンの演奏スタイルも色々あるが、安永は古典的なアプローチをきちっと押し出しており、色々いじくりまわすことは一切せず、きちっとしたアンサンブル、明確なリズム感を追求することで、ハイドンの音楽の美しさを十分に表出していた。
特長的なバロツクティンパニの乾いた、ビシツというような強打がところどころで全体を引き締めているのも印象的。
OEKは規模からしてもハイドンを演奏するにはぴったりであり、過去にも色々な指揮者のハイドンの名演があったが、今回のハイドンはその中でも出色。
アンコールにメンデルスゾーンの初期の交響曲の第一楽章。これも、柔らかく、躍動感に満ちた弦のアンサンブル。
丁寧なアンコール曲の紹介に好感を持った。 |
|
|
|
|
|
|
|
大震災からの復興支援コンサート
仙台フィルハーモニーを迎えて
2011年4月4日 石川県立音楽堂コンサートホール
仙台フィルハーモニー管弦楽団
オーケストラ・アンサンブル金沢
指揮 井上 道義
山下 一史
リーダー・ヴァイオリン 安永 徹 |
|
大震災から1カ月。死者・行方不明者3万人に迫るという大災害は、原発事故の不安感もあり、まだまだその全容がつかめない状況だ。
そんな中、被災地の仙台フィルが音楽による復興支援を被災地でいち早く打ち出し音楽活動を再開している。
今回は、石川県音楽文化振興事業団(OEK、県立音楽堂)が主催し、収益金は仙台フィルに託すという、復興支援のコンサート。会場には「仙台フィル頑張れ」という署名ボードも用意され、多くの人が書き込みをしていた。
仙台フィルは東北被災地でのミニコンサートを再開しているが、フル編成での演奏会は今回が震災後初めてとのこと。
被災されている楽団員も多いだろうし、金沢まで来ることも大変であったろうと想像するが、楽団員たちは音楽の力を信じるかのように、心をこめた素晴らしい演奏を聴かせてくれた。
私ごとだが、このHPを開いた最初が2003年9月のOEKと仙台フィルの合同演奏会の感想だった。故岩城宏之監督と外山雄三の指揮。最後のスラブ行進曲のスケールの大きい演奏を思い出す。
それから8年後、この様な事態が起こるとは、想像すら届かない世界ではある。
さて、この日は最初に亡くなった方への追悼の献奏として、安永徹のリーダー・ヴァイオリンの下でバッハの組曲第3番から「アリア」が演奏された。この作品は、今回の災害で、日本全国のみならず、世界のあちこちで演奏されているようだが、追悼にふさわしい名曲である。分厚い弦の響きに彩られた、レクィエム。
本プログラムでは一転して、合同演奏でのグリンカの歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲で幕開け。
プログラムを見たとき、「えっ」と驚いたが、この時期だからこそ井上マエストロはあえてこの作品を選んだのであろう。
演奏も、前へ前へと前進するような激しさ。「今、とどまってはいられない」という声が聴こえる様な激しさだった。
次が仙台フィル・山下一史指揮で、シューベルトのロザムンデから間奏曲1番、2番とシベリウスの「フィンランディア」。
厚い響きで重厚で劇的に開始された1番、木管の優しくうら哀しい響きに彩られた第2番。
弦の響きが実に柔らかく、前回聴いた仙台フィルの印象と異なるのに驚いた。先回はやや硬質に聴こえた弦が、今回は優しく柔らかい。指揮者による個性の相違もあるのだろうが、今日は楽団員の気持ちの持ちようがやはり響きに影響しているのだろうか、心に深く染み入ってくる優しく軟らかい響き。
第2番の木管の中間部の歌も、震災前の東北の里、山を思い出すように懐かしく優しい。
次はシベリウスの「フィンランディア」。単に勇ましい印象が強いこの作品だが、この日の演奏では、絶望から希望を切望するような力強さを聴いた。特に最終部の合唱でも歌われる有名な主題。平和な暮らし、平穏な暮らしへの希望が切々と歌われているような、楽団員の声を聴く気がした。
この様に思い入れを持って音楽聴くことは良くないことかもしれないが、このような暮らしが破壊されるような日々には、音楽がそのように聴こえ、そしてそれに力づけられるということは、それこそ「音楽の力」であろう。
まだ、音楽を聴くような状況ではない被災地だろうが、そんな時こそ音楽を聴いていただきたいし、仙台フィルも厳しい状況ではあろうが、仙台に戻り、1日でも早く心をこめた響きを被災地で聴かせてほしいものだと思う。
後半は再び合同演奏でドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」
井上マエストロの、シャープて切れ味鋭いドウォルザーク。総ての部分がクリアで明快。第2楽章も、テンポをやや早めにとり、そっけないようでありながら、要所はきちんと押さえて歌っている。ところどころで、独特な節回しが聴かれるのは、マエストロの個性か。
各パートのトップは総て仙台フィルが担当。音楽をすることの喜びに満ちた、各パートのソロに心打たれる。
群馬交響楽団が創立当時、苦労しながら戦後の荒廃した群馬県下を巡り、人々に感動を与えていったように、仙台フィルも東北の人々の心に希望の灯をともし続けていただきたいと念ずる。将に「新世界」である。
アンコールに大河ドラマ「利家と松」「独眼竜正宗」のテーマ音楽と、金沢と仙台にゆかりのある音楽で締めくくられた。
最後に山下一史仙台フィル正指揮者が、「今日は音楽を演奏することのできる喜びをずっと感じてきました。演奏しながら、皆さんからいただいた励まし、元気を持って仙台に戻ります。」と挨拶。スタンディングオベーションの続く大きな拍手に包まれて楽団員たちは退場。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第298回定期演奏会
2011年4月4日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響 |
|
3月の定期は都合で聴けなかったので、2月の定期以来の音楽堂。
その間、大震災という思いもかけない事態が発生し、日本全体が暗いムードに包まれている。
普通に音楽を聴くことのできる環境、平凡な日々がどれ程大事なことかを痛感させられる。
それでも、3月の定期では、被災地の多賀城市から12時間かけてやってきた郷古廉さんが熱演されたという報を聴き、音楽の持つ力の大きさを感じる。
18日には仙台フィルを迎え、OEKとの合同で復興支援コンサートも開かれるとのこと、音楽を普通に楽しめる日々が一日も早く戻ってほしいと思う。
そんな中での定期。
久しぶりの金聖響の登場。オールメンデルスゾーンプロ。
前半が、序曲「フィンガルの洞窟」、ヴァイオリンに三浦文彰を迎えてのヴァイオリン協奏曲、後半が交響曲第4番「イタリア」
今回は、ロマン派の作品ということで、ティンパニも通常、金の特長であるピリオド奏法的な激しさも影を潜め、バランスのとれた演奏と感じた。ロマン派といっても、ブラームスへのアプローチとメンデルスゾーンとは異なる様である。
OEKとは、この後シューベルト、シューマンとロマン派の作曲家への取り組みが続くようであるが、それぞれどの様なアプローチを聴かせるのか興味津津。
序曲「フィンガルの洞窟」。風景描写的な音楽ではあるが、メンデルスゾーンの心象風景とも感じ取れる作品。
いつもは引き締まった剛直な響きが印象の金だが、メンデルスゾーンでは厚い響きの豊潤さをも感じる。
器用な指揮者なのであろう。
次のヴァイオリン協奏曲、若いヴァイオリニストの爽やかな演奏。鮮やかで、伸び伸びとした若者らしい響きは、この作品にあっている。今後、どのような成長を見せるか、期待がもてる新進ヴァイオリニストである。
後半の交響曲第4番「イタリア」。序曲「フィンガルの洞窟」の演奏と印象は同じ。
非常に豊かなアンサンブル。バランスが良く、総ての楽器が良く響いている。
第1楽章の弾けるような出だし、第2楽章の憂い、第4楽章の激しさなど、この作品の魅力が溢れている。
ただ、メンデルスゾーンという作品の性格からしてか、やや金にしてはおとなしいという印象ではあったが。
同じロマン派であっても、シューマン、ブラームスあたりの激情の方が、金には向いているのであろうか。
まだ、落ち着いてしまうには若すぎると思うのだが。 |
|
|
|
|
|
|
|
住友生命25th全国縦断チャリティコンサート
清塚信也 ピアノとトークのコンサート
2011年2月26日 オーバードホール |
|
住友生命からチケットをいただいたので、最近注目の若手ピアニスト、清塚信也のコンサートに出かけた。
清塚は、最近ではNHKの大河ドラマ「竜馬伝」のエンディングテーマの作曲・演奏、ドラマ「のだめカンタービレ」のピアノの吹き替えなどで話題を呼んでいるピアニスト。
今日は、ショパンとリストの名曲を中心としたプロだが、ピアノと共に、そのトークの巧みさに脱帽。
まるで、ピアノ界のさだまさしのようである。
ユーモアを交えながら、ショパン、リストの音楽をわかりやすく、身近に感じさせるようなトークは、今までクラシックに縁の無かった人をも、クラシック音楽を、ごく近い世界と感じさせる様になることだう。
ただ、気になったのはショパンへのやや偏った紹介の仕方。
確かにショパンの世界は、甘く、センチメンタルである面もあるが、それだけではない。
熱い激情、祖国ポーランドに対する熱い思いなど、逞しいショパンの思いも音楽の中に溢れているのだから。
それを、何かひ弱い、ストーカーの様な青白い青年という印象を与えるのはどうかなと感ずる。ショパンを初めて聴く人に、先入観を与える様なトークはやはりまずいのではなかろうか。
それは彼のショパンへのある思いではあろうが、それを押し付けるのはいかがなものか。
しかし、口八丁、手八丁、器用な方ではある。
肝心のピアノ。ショパンは、美しく感傷的である。最初のノクターンの2番など、あの美しい旋律を、これでもかという程、感傷的に奏でる。それは、やはり、現在の清塚のショパンへのアプローチなのであろう。
ショパンには、もう少し気品の高い美しさがあると思うのだが。それは感傷とギリギリの境目ではあろうが。
又、タッチの弱さもあるのだろうが、英雄ポロネーズなど、スケールの大きさと風格が欲しいと感じた。
というわけで、トークと同様、ピアノもショパンの本質とやや離れているものを感じた。
この日のハイライトは、アンコールの「ラプソディー・イン・ブルー」の即興演奏。
クラシックの名曲から、住友生命のコマーシャルソングまで、「ラプソディー・イン・ブルー」の中にごちゃまぜに放り込み、そこに彼の独特なアレンジとジャズのビートのノリを加え、それこそ超絶的な技巧で弾きまくる、本領発揮の様な楽しさ。今回、これを一番やりたかったのではないかと思うほどの力演だった。
次から次へと音楽がマグマの如く噴き出してくる、15分程の即興演奏。
ショパンにはやや不満も残ったが。この様なトークとピアノというコンサートを行っているクラシックピアニストは彼以外に無いのではと思うので、これからの動向が注目。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第295回定期演奏会 2011年2月20日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ニコラス・クレーマー
ソプラノ 小林 沙羅
バリトン 与那城 敬
合唱 オーケストラ・アンサンブル金沢合唱団
合唱指揮 本山 秀毅 |
|
2月のOEKの定期は、過去声楽曲を中心に、宗教的作品を多く取り上げてきたが、今回の定期もその流れ。
フォーレの「レクィエム」をメーンとした、フランスの音楽。
バロックのラモーと近代のフォーレ、ラベルまでのフランス音楽のエッセンスを聴くようなプログラム。
指揮はイギリスのニコラス・クレーマー、OEKでは既にお馴染みの指揮者。
前半はラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」、フォーレの「パヴァーヌ」の中間に珍しいラモーの歌劇「プラテ組曲」を挟んだプロ。
ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」。ホルンの高音のテーマから始まるアンサンブルの精緻さが要求される作品。
プログラムの最初に取り上げるにはオーケストラに酷な感もあり、やや精緻さには欠ける演奏。特に肝心のホルンが、楽器も温まっていない為でもあろう、不安定なのが惜しまれる。クレーマーの指揮は、やや早めのテンポで、この作品の心地よい古典的な流れを作り出していた。過度な思い入れを排した気品の高い音楽づくり。
次のラモー。初めて耳にする作品。フランスバロックの典雅さと、機知にとんだ曲想が魅力的。
「嵐」の描写の巧みさ、メヌエットの野暮と洒落が同居した様な面白さなど、ラモーの魅力が溢れた曲想。
バロックの生き生きとした息吹を感じさせる、溌剌とした演奏。最後にソプラノ小林沙羅が登場、アリアで締めくくられた。
典雅でありながら、どこか人間臭いフランスバロックの面白さを感じることが出来た。
フォーレの「パヴァーヌ」 優しく魅力的な小品。合唱も柔らかく落ち着いていて、OEKの柔らかい弦の響きと調和し、これもまた典雅な世界。クレーマーの音楽の、、余計な虚飾を排し、自然の流れを大切にした作り方が好ましい
後半はメーンのフォーレの「レクイェム」
オーケストラの配置は、前にヴィオラ、チェロ、コントラバスを並べ、ヴァイオリンは左後方に4人のみ、左奥にホルン4、右にトランペット、トロンボーン各2、テインパニ、全面奥に木管、左側にハープ。独唱者は左側奥に座り、歌う際に前面、あるいは合唱の横に移動。更にオルガン。
編成としては大きいが独特。フォーレの初版ではヴァイオリンはソロのみであったようなので、作品自体が低弦に重心を置いたものといえる。
低音が重視されていながら、全体の響きは透明で、静けさが充満している。金管、ティンパニが強調される6曲「リ・ベラメ」ですら、激しさは限定的である。総ては平穏な気分に満たされた、静謐な世界。オルガンの厚い響きが全体を支え効果的。
「レクイェム」というより、フォーレの死に対する憧れのようなものさえ感じさせられる平穏な世界。
ここでも、クレーマーは余計な装飾や効果は狙わず、淡々と歩を進める。
ソプラノの透明な響きは第4曲の「ピエ・イエズ」で最高潮。これも虚飾を排した誠実な歌唱。
テノールも美しく柔らかく歌い上げていた。
全体を支える合唱、クレーマーの抑えた要求に応じた、緊張と抑制の利いた合唱。
この作品には様々な解釈が存在するだろうが、今日の演奏は虚飾を排し作品の神髄に迫ろうとする誠実な演奏。
平穏さと憧れに満ちた終結。曲が終わり数秒の静けさがホールを支配。この日の拍手も暖かかった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第294回定期演奏会 2011年2月2日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ジョルジォ・メッザ・ノッテ
独唱 ソプラノ 濱 真奈美
テノール ルカ・ボテーニ |
|
2月のマイスターシリーズは金沢出身のソプラノ、濱真奈美を中心とした、イタリアオペラアリアとカンツォーネの夕べ。
指揮者にイタリアのジョルジォ・メッザ・ノッテ、テノールにルカ・ボテーニを迎え、イタリアの香り高いひと夜となった。
盛りだくさんのプロで、前半のオペラアリアの部だけで1時間10分、後半も1時間なので休憩を含めて2時間半という長いコンサートとなった。というわけで、残念ながら最終バス時間の関係で最後の2曲とアンコールは聴くことが出来なかった。
まず、指揮者のジョルジォ・メッザ・ノッテ。
イタリアのベテランらしい、歌心に溢れた指揮。オーケストラコントロールも巧みで、OEKの弦の柔らかい美音、管のカンタービレを巧みに引き出し、アンサンブルのきちっとまとまった、躍動感あふれる演奏を聴かせてくれた。
前半の管弦楽曲が3曲、ベルディの「ルイザミラー」序曲、ジョコンダの「時の踊り」、珍しいマルトゥッチの夜想曲というもの。いずれも整然とまとまり、コントラストのはつきりとした演奏。「ルイザミラー」序曲ではカンタービレが魅惑的で、弦の柔らかい響きも効果的。OEKのアンサンブルの美しさを存分に引き出した演奏。
ジョコンダの「時の踊り」も曲想の転換を巧みに描き出し、エンディングの劇的な盛り上がりなど楽しく聴かせてくれた。
ソプラノの濱真奈美は、ソフトな音質で表情豊か。ヴェルディの「オテロ」から「柳の歌」の複雑な心情の吐露。クラリネットの魅惑的なカンタービレと弦の柔らかい響きか歌声とぴったりと寄り添い魅力的。アイーダからの「勝ちて帰れ」でも、複雑な心情を劇的に表現し秀逸。表現力の強い歌手と感じた。
テノールのルカ・ボテーニも本格的なイタリアオペラのテノールという印象。声量はやや小さいが、輝かしい声の響きは、典型的なイタリアテノール。プッチーニのトゥランドットの「誰も寝てはならぬ。」の劇的表現の大きさは会場のあちこちから、ブラボーの声があがった。
ソプラノが3曲、テノールが2曲、ソプラノとテノールで2曲、更に管弦楽曲が3曲、計10曲という盛沢山な前半であった。
後半はカンツォーネ。
ここでも、オーケストラ作品が2曲、ベックッチという珍しい作曲家の作品だが、これが面白い。
ワルツとポルカなのだが、まるでウィンナワルツとそっくり。何も知らないで聴いたらJ・シヨトトラウス一家の音楽と思いそう。
「フィレンツェからフィエーソレまで」など、曲想がポルカ「観光列車」とそっくり。
時代でみると、J・シュトラウスの活躍した時代と重なる部分もあるので、何らかの意図があってこの様なコピー作品を作ったのであろうか?
後半の歌は、美しい歌声に身を任せてという感で、特筆すべきことも無いが、最後の二人の「サンタ・ルチア」とアンコールを時間の関係で聴けなかったことが心残り。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第293回定期演奏会 2011年1月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
リーダー&ヴァイオリン マイケル・ダウス |
|
今年のOEKのニューイヤーコンサート
OEKを聴き始めて8年ほどになるが、ニューイヤーコンサートも様々な変化を辿っているようだ。
定番のシュトラウス一家のワルツ・ポルカの時代から、井上道義監督になつてからは、ベートーヴェンもあり、武満徹や一柳慧等現代音楽が入ったり、ショスタコーヴィッチを入れたりと、新年に音楽の楽しさをてんこ盛りにするという工夫を聴くことが出来、刺激的な面白さがある。
今年も一風変わったプログラムで、前半がマイケル・ダウスのヴァイオリンと指揮で、ピアソラの「ブエノスアイレスの四季」、後半が井上監督の指揮というもの。
後半の曲目は、J・シュトラウスⅡ「喜歌劇こうもり序曲」、バルトーク「ルーマニア民族舞曲」、リスト「メフィスト・ワルツ第1番」、J・シュトラウスⅡ&ヨゼフ・シュトラウス「ピッツィカート・ポルカ」、レハール「喜歌劇パガニーニよりカプリッチョ」、ワルツ「金と銀」という、多彩なもの。
今年は昨年のアンコールであった定番「美しき青きドナウ」も無しで、ワルツはレハールと、このあたりもひとひねりを感じる。
さて、前半のピアソラ。原曲はバンドネオンを中心とした小さなアンサンブルの作品だが、今回は弦楽合奏用に編曲されたもの。マイケル・ダウスが指揮と独奏ヴァイオリンを担当。
以前クレメルがクレメラータ・バルティカを引き連れて、ヴィヴァルディの四季とピアソラの四季を交互に演奏するというユニークなプログラムを聴いたことがある。ピアソラの四季は明らかにヴィヴァルディを意識し、春、夏、秋、冬のそれぞれの終りの部分にヴィバルディの四季の断片を組み込むという手法をとっている。ピアソラらしい、憂愁に溢れたタンゴの傑作。この日は、夏から始まり、春に終わるという順番で演奏された。
ヴェノスアイレスの街の四季を印象画風に生き生きと描いている。
ここでは、マイケル・ダウスの柔らかく優しいヴァイオリンが印象的。それ故に、ピアソラの線の鋭さが欠けている憾みはあるが、これはこれで優しく美しい演奏。タンゴの複雑なリズムをOEKは弦楽合奏で巧みに描き出していた。
後半はいつもの井上ワールド。
「こうもり序曲」のめりはりのはっきりとした、リズム感溢れる演奏で開始。テンポと曲想が目まぐるしく変わる難曲だが、テキパキとした早いリズム、ゆっくりとウィーン情緒たっぷりと歌う部分と、描き方が明確であり、オーケストラもその指揮にのせられ、生彩感溢れる演奏。
次のバルトーク「ルーマニア民族舞曲」は、通常ヴァイオリン独奏で演奏される場合が多いが、この日は弦楽合奏版。
これも、テンポの変化が激しく、ルーマニア独特の民族的な雰囲気溢れる作品だが、指揮者の要求にぴったりとはまったOEKの弦楽合奏は見事。
この日一番面白かったのが、次のリスト「メフィスト・ワルツ第一番」
偶然か、今年のウィーンのニューイヤーコンサートでもウェルザー・メストが取り上げていた。
この作品の悪魔的な嘲笑の様な金管の叫びが強調され、ベルリオーズの幻想交響曲の5楽章を想起させるグロテスクで狂気の様な雰囲気が醸し出され、面白さ抜群だった。
次のピッツィカート・ポルカは一転して清楚な弦のピッツィカート。OEKの弦の柔らかいピッツィカートは出色。
最後は、レハールが2曲。
オペラ・パガニーニからの「カプリッチョ」という珍しい曲は、ダウスがオルガンバルコニーで独奏。柔らかく優しい独奏ヴァイオリン。
最後は有名なワルツ「金と銀」。レハール独特の感傷的で、やや野暮ったい旋律に溢れた作品だが、井上マエストロはその部分を特に念入りに、やや遅めのルバートのかかったような音でえぐりだし強調していたのが効果的。
アンコールはブラームスのハンガリアンダンス6番と、ダウスのヴァイオリンを交え「メリーウィドウ」から。
井上マエストロがダウスに、「アイラブユー」と寄り添う気味の悪いパフォーマンスで笑いを誘う。
ニューイヤーらしい楽しさに溢れたコンサート。 |
|
|
|
|
|
|
|
ダン・タイ・ソン ピアノリサイタル&室内楽プロジェクト
ピアノ ダン・タイ・ソン
弦楽四重奏 クヲルテット・エクセルシオ
コントラバス 赤池 光治
2010年11月30日 入善コスモホール |
|
2日前にエル・バシャのショパンを聴き、直後の演奏会だけに、比較の思いが入ってしまうのはやむをえないこと。
プログラムの組み方が変わっていて、前半がピアノ独奏、後半が室内楽版のピアノ協奏曲というもの。
ダン・タイ・ソンは相当以前一度だけ聴いた覚えがあるが、記憶が定かでない。
前半はワルツ8曲。随所に音の輝くような箇所もあるのだが、ワルツにしてはやや重く、鈍重。
ショパンのワルツの高貴なエスプリの香りが薄い。テンポの取り方、強弱の付け方も弱く、全体に平板な単色模様。
やたら、バリバリと弾くという感じ。
エル・バシャも弾いたOp34-3のワルツ。一気呵成に弾きまくったという感じで、エル・バシャのクリスタルで、ころころ転がりまわるような鮮やかさに比べると、厚く重い。これが、この人の特長か。
その点では、前半で最も良かったのが、次に弾いたボレロ。タイ・ソンの鮮やかな技巧と、曲のエキゾチックで厚ぼったい色彩感がぴったりとはまり、面白い。
一部最後の「英雄ポロネーズ」も、これでどうかというような豪快な弾きっぷりである。しかし、細部にわたるデリケートさが薄いので、作品の全体像が見えてこない、ただ、豪快さだけが残っていく。この人、若いころ、こんなだったかしらと思う。
後半は非常に珍しい、ピアノ協奏曲1番の室内楽版というもの。当日の配布レジメを見ても、編曲者については触れられていないが、ショパン自身の編曲では無いのだろう。
オーケストラ伴奏版でも、複雑なオーケストレーションがあるわけでないので、室内楽版でも違和感はない。むしろ、この協奏曲の裸の姿が見えて興味深い物がある。
タイ・ソンの演奏はここでも弾きまくりという感じ。伴奏とは頭だけ揃えて、後は各々勝手にという風な演奏。
クヲルテット・エクセルシオは、この入善で最初の演奏会、10年ほどまえだったか、聴き、巧みさはあるものの、作品の性格の表現に浅さを感じたことがあつたが、その時に比較しはるかに鮮やかな演奏をするようになったという印象。
この協奏曲、伴奏部分とピアノの独奏部分とはつきり二分されているようなところがあるので、伴奏を聴かせる部分では思いっきり張り切り、協奏部分ではしつかりと伴奏に徹するというような風。
タイ・ソンはテンポルバートも思いっきり聴かせた、厚ぼったい、妖艶なショパン。
これは、好き好きであろうが、私には少し重すぎる。
アンコールのノクターンも同様の印象、やはりアンコールで演奏したエル・バシャの演奏の気品の高さとどうしても比較してしまう。 |
|
|
|
|
|
|
|
アブテール・ラーマン・エルバシャ ピアノリサイタル
2010年11月27日 婦中ふれあい館(ベートーヴェン4大ピアノ・ソナタの夕べ)
11月28日 富山市民プラザアンサンブルホール(ショパンの調べ) |
|
今年のラフォール・ジュルネ金沢でも、ショパンで完成度の高い演奏を聴かせてくれた、エルバシャが、何と二日間富山でリサイタルを開いてくれた。
一日目はベートーヴェン、2日目はショパンという魅力的なプログラム。
初日は音楽ホールとしてはどうかと疑問符がつく会場でのリサイタルだったが、見事な演奏でその不安を払しょくしてくれた。
この日のプログラムは、8番「悲愴」、14番「月光」、21番「ワルトシュタイン」、23番「熱情」という、初期から中期にかけての傑作、名作をずらりと並べたプロ。
音色の明るい輝かしさ、打鍵の強い大きなスケール、細かい細工は一際無し、正面からベートーヴェンを表現しようとする強い意欲、これらが聴きごたえのあるベートーヴェン像を描き出していた。
8番「悲愴」の序奏の強い和音で一辺に聴衆を引きずり込んでいく。1楽章主部も虚飾の無い、落ち着いた展開。
テンポが遅からず速からずの独特のテンポ。そして音色の色彩の豊かさ、特に高音部の輝くような色彩感。
2楽章の確かめるような主題の緊張に満ちた静けさ、3楽章も決して疾走することなく、確実な足取りで進んでいく。
古典的な枠組みを大切にした誠実な演奏。
21番「ワルトシュタイン」はこの日の白眉。
古典的なスケールの大きさ、そして聳え立つ峰の様な神々しさ、この作品の真価が示された演奏。
2楽章の緊張感、そして3楽章の爆発の予感を秘めながら進む緊張の持続。そして、3楽章初めテーマが提示される部分、最初は淡々と、そして次に強い打鍵で示されるこのテーマの扱い方の対比は絶妙。
雄大な主題の展開、ベートーヴェン中期の作品の壮大な世界が堂々と展開され、まるで大きな叙事詩が閉じられるようなエンディング。
休憩を挟んで、後半が14番「月光」、23番「熱情」
14番では、1楽章のテンポはやや早めに、さらりと弾かれている。妙な思い入れや、虚飾は排し、客観的、古典的なスタイルを堅持しているよう。3楽章は、強弱がくっきりと描き出され、この楽章の激しさが一層強調される。
23番では、2楽章が意外に淡々としている。これだけの大曲を並べると、集中力の維持が大変なことと想像されるが、前半に比べ、後半はこのあたりやや緊張が欠けていたようにも聴こえた。このあたりが、このようなプログラムの組み方の難しさかもしれない。
全体として、ベートーヴェンのピアノソナタの激しさ、スケールの大きさを余すところなく表現した演奏。
音色は明るく、ドイツのベートーヴェンに比較すると燦々と太陽が輝くようなベートーヴェンだが、スケールの大きさは大変なもの。
久しぶりに、ベートーヴェンのソナタの凄さを再認識させてくれた。
第2日めはショパン。
スケルツォ2番、ノクターン9,10番、ワルツの2番、3番、4番、マズルカ14,15,16,17番、バラード1番、休憩後が「24の前奏曲」というプログラム。
前半は、最初と最後に大曲を配し、その中に小品を散りばめたプロ。
スケルツォとバラードの構成感のがっちりとした、雄大なショパンが印象的。
エルバシャのショパンは「音楽の詩人」というショパンの印象を一変させるような、感傷性を排し、ショパンの音楽の持つ強い意志、激しさを堂々と打ち出したような印象。
ノクターン、ワルツ、マズルカ等のショパンの静の音楽でも、音は大きく、テンポも極端には動かさず、むしろ淡々と進むような印象。それでいて、それぞれの作品の持つ、微妙な色合い、民族的な香りは十分に描き出される。気品の高いショパンである。
ノクターンの高貴な静けさ、ワルツの転がるような高音の魅力、マズルカの楽しげな踊りと、それぞれの特長が明確に描きだされていた。
後半の「24の前奏曲」は圧巻。静と動が明確、そしてドラマティツクな展開、小品の連続が一つの大きな作品として展開される。有名な15番「雨だれ」など、このように激しい曲だったかと思うような後半の強い打鍵。
アパショナートと指示された24番が激しく高らかにエンディングを告げる。輝かしく、神々しいショパンであった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第291回定期演奏会
2010年11月19日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ギュンター・ピヒラー
ヴァイオリン リディア・ヴァイチ |
|
OEK定期で久しぶりのオールベートーヴェンプロ。現代音楽も得意にしているOEKであるから、普段聴くことの少ない作品での定期というのも一つの方向性であろうが、このように正統的なプログラムもほつとするところがある。
ということで、聴く側もそのような傾向もあつたのか、今回の定期は久々に満席に近い盛況。
指揮がピヒラーということで、ウィーン伝統のベートーヴェンが聴けるのではないかという期待。そして、ヴァイオリンのヴァイチも出身はロシアといえ、ウィーンで勉強し、活躍している俊英、ピヒラーとどの様な競演をするのかという期待も高まる。
序曲「コリオラン」。ヴァイオリン協奏曲、交響曲第2番というプログラム。
ピヒラーを聴くのは今回で4回目となると思うが、音楽の印象としては前回同様だが、完成度はずつと高くなっていた。
ベルク四重奏団で聴くことのできる、厳しく、スケールの大きな演奏を、オーケストラを指揮する場合も同様に追求しようとする姿勢。四重奏団では4人の意思は合わせやすい点もあると思うが、それをオーケストラで実現するのは、大変難しい事と思えるが、今回のピヒラーの演奏は自らの意思をオーケストラで実現するという点で、実に完成度の高い演奏であったように思える。
以前の演奏では意図は十分に理解できるが、オーケストラのアンサンブル、技術の面でピヒラーの意図が十分に表現されているとは言えない面も散見した。
今回の演奏では、ピヒラーの要求する音楽がオーケストラに浸透し、指揮者の呼吸とオーケストラの自発性が一致し、完成度の高い演奏となっていた。
序曲「コリオラン」、交響曲第2番の強烈な出だしの一撃、そして主部の疾走するような前進性、展開部の激動など、指揮者の要求にオーケストラがぴつたりとはまった時の凄さを感じた。
ピヒラーの特長として、管楽器を鋭く鳴らせる点があるが、それが今回はアンサンブルの中で的確に決まり、ベートーヴェンの音楽の持つ厳しさ、鋭さが浮かび上がっていた。
ヴァイオリンのバイチ。総ての面で完成度の高い演奏。まず、音色が美しい。そして、オーケストラとのアンサンブルが際立つ。この協奏曲の特長として、オーケストラとの掛け合いの妙味があるが、その点の素晴らしさ。
自らの独奏をひけらかし、自分勝手に進むのでなく、オーケストラが何を歌い、何を訴えかけようとしているのかをじっくりと探りながら、自らの独奏を合わせていく。故に、この協奏曲の真の気品の高い美しさが浮かび上がる。
ヴァイオリンが歌い、オーケストラも歌う、この協奏曲の凄さを改めて知らせてくれた。
交響曲第2番はベートーヴェンが高らかに人生に挑みかかることを宣言した様な音楽、そしてヴァイオリン協奏曲は最も充実した創作時期の美しく壮大な音楽、同じニ長調の音楽のそれぞれの持つ個性を明確に聴きとらせてくれたピヒラーのベートーヴェンを十分に堪能した一夜。 |
|
|
|
|
|
|
|
キエフ・オペラ
プッチーニ「トゥランドット」
2010年11月9日 オーバードホール
トウランドット テチヤナ・アニシモヴァ
カラフ ヴァレーリー・ベンデロウ
リュー リリア・フレヴツヴォヴア
ピン ペトロ・プリイマク
パン セルフィ・パシューク
ポン ミコラ・シャリーク
他
指揮 ヴォロディミール・コジュハル
管弦楽 ウクライナ国立歌劇場管弦楽団
合唱 ウクライナ国立歌劇場オペラ合唱団
バレー ウクライナ国立歌劇場バレー団
|
|
旧ソ連では「キエフ・オペラ」として有名であったが、ソ連崩壊で独立し正式名称をウクライナ国立歌劇場として活動を続けているオペラ座の日本公演。
今回の日本公演ではベルディ「アイーダ」、ビゼー「カルメン」、ムソルグスキー「ボリス・ゴドゥノフ」、そしてプッチーニ「トゥランドット」の5つのオペラを、全国で35公演行うという、タフなオペラ座である。
富山はプッチーニの「トゥランドット」
全体の印象としては、オーソドックスで正統的。
美術、衣装、舞台装置、総て気を衒ったところのない堂々としたもの。
特筆は合唱団の凄さ。人数は30人ほど思われるが、その声量はホール一杯に響き渡るほど。このオペラは合唱部分も聴きどころなので、これはなかなかのもの。
そしてオーケストラ、さすがにロシアのオケ、分厚い響きはイタリアオペラというより、ロシアのオペラを聴くよう。
指揮のコジュハルも壮大な音楽の作りで、このオペラのスペクタクル的な面白さを際立てていた。
歌手では、3人の主役、トゥランドットのアニシモヴァ、カラフのベンデロウ、リュー のフレヴツヴォヴア、それぞれに個性的な好演。
又、脇役のピン、パン、ポンの3人の巧みさも特筆。
特にトゥランドットのアニシモヴァ、低音にやや物足りなさがあるが、その高音のドラマティックな輝きある声は、トゥランドットにぴったり。激しい性格の主役を見事に描き出していた。
ということで、このオペラの舞台としては、相当レベルの高いものと思えるが、そうであると一層、このオペラの底の浅さということも感じてしまう、不思議なギャップ。
堂々と、壮大に、そしてセンチメンタルに演じれば演じるほど、ちょつと白々しい、覚めた感覚に襲われる。
ベルディのオペラの壮絶な人間ドラマと、次元の異なる底の浅さといおうか。
プッチーニのファンには怒られそうだが、「松竹大悲劇」、あるいは「宝塚大悲劇的」な、リアリティーとかけ離れた底の浅い人間ドラマを見せられているようである。
このあたりが、プッチーニのオペラを上演する際の演出上の難しさかもしれない。そのようなものと割り切って、美しくも切ない音楽を、それなりに演じた方が良いのかもしれない。正面から堂々と取り組むと、少々照れくさくなってしまう。
こう考えるのは、つむじが曲がっているのだろうか? |
|
|
|
|
|
|
|
パリ・ギャルド・レピブリュケーヌ吹奏楽団 演奏会
2010年10月31日 石川県立音楽堂
指揮 フランソワ・ブーランジュ |
|
久しぶりの2日続いての音楽会。静と動の音楽会の対称といおうか、今日は気軽に楽しめるような音楽会。
世界最高のブラスバンドという名声はずっと聴いており、少しでもブラスをかじった人間なら、一度は聴いてみたい楽団である。下手とはいえ、中学時代にブラスバンドに所属していた私には、是非一度聴いてみたかったブラスバンド。
というわけで、今日の演奏会、高校、中学の生徒たちが目立ち、身を乗り出して聴いている様子が、初々しかった。彼らにしてみれば、この様なブラスバンドの存在は、将に驚異であり、又憧れでもあるのだろう。
それにしても、評判通り、というより評判を上回る、素晴らしいアンサンブルのブラスであり、このような音がブラスから生れるということが、奇跡のような楽団である。
バーンスタインのキャンディード序曲で幕開け。ブラスでこの序曲の飛び跳ねるようなリズム感を出すのは至難であろう。この幕開けもやはり少し重たげではあったが、アンサンブルは精緻。各楽器の歌心が凄い。
次に、ハチャトーリアンが3曲。ガイーヌから「剱の舞い」「レズギンカ舞曲」、仮面舞踏会から「ワルツ」
これはもうお手の物。鮮やかなリズムと激しく輝かしい盛り上がり。有名な仮面舞踏会・「ワルツ」も、憂いに満ちた旋律が大波の様に寄せてくる。
編成は80人ほどか。オーケストラの弦楽器のパートを担う木管楽器群が前面に並び、独奏の木管は後に配置、ホルンが左手、トランペツト、トローンボーンが奥、右手にはチェロの役割のユーフォニウム、更にチューバ、コントラバスが弦楽器としては唯一使用されている。他にハープが2台、ピアノ、チェレスタ、オルガンも入り、大きな編成。
プログラムではここで休憩となっていたが、続けてレスピーキ「ローマの松」。前後半のバランスからいってこれは当然。
この「ローマの松」そして、後半の「ボレロ」には、ただただ呆然とする程の名演。
「ローマの松」第2章のカタコンブのユーフォニウムを中心とした低音の分厚く、かつ柔らかい音色、これが金管の音色であろうかと思うような凄さがある。
3章の「ジャニコロの松」では客席が真っ暗となり、舞台上の照明も暗く落とされ、おそらくテープであろうが小鳥たちのさえずりが、闇夜に響き、そこにクラリネットの静かな歌が流れる、そして静かな盛り上がりのうちに最後の「アッピア街道の松」の遠くから近付く軍隊の行進が聴こえてくる。このあたりの、各独奏者(トランペット一人はオルガンバルコニー席の左側)の描写的な表現力は見事。
そして「アッピア街道の松」のオルガンが加わった、金管の恐ろしいほどのど迫力。この作品の描写力の魅力を存分に発揮した演奏。
後半始まりは、有名なフランスの行進曲2曲。「サンブル・エ・ミューズ行進曲」「ロレーヌ行進曲」
マーチの演奏の見本の様な堂々たる演奏。輝かしい主題の提示部、そしてトリオの部分の優しく、柔らかい色調と、コーダの盛り上がりと、メリハリの聴いた、心たかぶる名演。
最後はラベルの「ボレロ」 ラベル自身がこの吹奏楽編曲版を初演指揮したというほどの、ギャルドの定番。
小太鼓の連打から始まり、各楽器の独奏が繰り返され徐々に盛り上がっていくこの作品は、各独奏者の腕が将に試される作品だが、この名手の集まりでは、全く余裕のある演奏で、各奏者の伸び伸びとした個性が輝くよう。
凄いとしか言いようの無い演奏だが、面白かったのは、名手でもミスがあるということ。トロンボーンが独奏部分の最初でちょっとしたつまづき。面白かったのはその後、くだんの奏者、ソロが終わると照れくさそうに両隣の奏者と話し合い、言葉は聴こえないがその表情から、「やっちゃったよ。おかしいな、こんなことは無いんだけど」と言い訳をしているよう。
そして、演奏後に指揮者が各独奏者を立たせた際、この奏者だけには楽団員から床を踏みならす手洗い祝福を受けていた。
フランス人のユーモア精神を見るようでほほえましかった。
それにしても、フランスの輝かしい管の名手がこれだけ集まると、こんな演奏が生まれるという典型的な名演であった。
アンコールが3曲。R・コルサコフ「くまばちは飛ぶ」ビゼー「カルメン前奏曲」、最後がニノ・ロータ「8 1/2」という映画音楽よりだったよう。 |
|
|
|
|
|
|
|
庄司紗矢香ヴァイオリンリサイタル
2010年10月30日 入善コスモホール
ピアノ ジャンルカ・カシオーリ |
|
庄司紗矢香、2005年、2009年に続き3度目の入善への登場。今回はピアノに注目のカシオーリを迎え、オール・ベートーヴェン。庄司紗矢香の挑戦であろうか、意欲的なプロである。
3番、5番「春」、9番「クロイツェル」、前回も7番のソナタが入っていたので、ベートーヴェンの「ヴァイオリンとピアノ為のソナタ」の大半を聴くこととなる。
今回は、前回までのピアノ、ゴランからカシオーリに変わった。ゴランの構築性が高く、ドラマティックで激しいピアノに比較し、音の柔らかさと明るさ、そして明確な打鍵、すつきりとした見通しの良い音楽性、それらが又前回と異なベートーヴェンの印象を与えてくれた。とはいうものの、庄司紗矢香のアプローチは前回から変化しているわけではなく、ピアノが変わったことによる印象の変化と言って良いだろう。
庄司の楽譜から総てを読み取り、自分の余計な主観を交えず、楽譜の意味するところを追求し、再現しようとする誠実なアプローチは、常に聴く者に新鮮で深い感銘を与えてくれる。今回は、全演奏で譜面台を用意しているのも、彼女の真面目で誠実な演奏を象徴している。
今回、特に印象的であったのはそのテンポの独特な個性。特に、5番「春」の出だしの主題のテンポ。ゆったりとしたテンポ、深々とした音色。普段聴く演奏の、明るく、若々しく軽めの歌い方ではない、思索を深く込めたような歌。
これは、「春」というソナタの今までの印象を一変させるような個性的なとらえ方。
このテンポの設定は、庄司、カシオーリどちらの主張なのかと、興味深く聴いた。おそらく、双方相当真剣な話が行われたのではないかと想像される。
庄司の音はいつも真面目。美しく甘いヴァイオリンで聴く者に媚びるようなヴァイオリンでない。時には、粗暴とも言えるような音も駆使し、挑みかかるように聴く者に迫る。カンタービレも甘くなく、深い思索を湛えていて図太い。
これらの特長が、9番「クロイツェル」に満ち満ちており、この作品の論理的でありながら、時には粗暴で挑戦的な側面が聴く者に迫ってくる。第一楽章の壮大で激しい楽想は、ベートーヴェンのおたけびを聴く様でさえある。第2楽章の変奏曲も、充実と緊張に満ちた音で、淡々としているようでいながら、深い静けさを湛えている。
第3楽章も輝かしくスケール大きな楽想が浮かび上がってくる。
カシオーリのピアノの音の明晰さは特筆。その絶妙なタッチから生み出される、なんとも深い音色。
時には確かめあうように、時には激しく競うように、絶妙な呼吸の二人。
3番。5番、9番、それぞれ各楽章の個性がくつきりと描き出されていた。
ベートーヴェンの音楽世界のスケールの大きさ、革新性、劇的な構成というものを明確に描き出した演奏。
アンコールに他のソナタから2つの楽章。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第289回定期演奏会
2010年10月20日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 オリヴァー・ナッセン |
|
オリヴァー・ナッセンは2004年と2007年にOEK定期を振っているとのことだが、私が聴いたのは2004年。
その際のプログラムも個性的なもので、やはり武満作品が含まれていた。
今回のプログラムも自身の作品を含め、武満作品を入れるなど前回同様の構成となっている。
今回は、楽器編成・配置が作品により独特なものとなっており、その点でも興味深いものがあった。
又、全体を通して室内オーケストラとしての精密なアンサンブルの極致を聴くようで、ナッセンの現代音楽の表現者としての力量の凄さを再認識させられた。歩くのも苦労するような巨体から発せられる音楽は、その体躯とは正反対に繊細で、細やかである。しかし、その細やかさは、前回の印象と同様、日本的な単色の細やかさでなく、油彩的な、厚い色彩に彩られた繊細さという印象。
さて、今日のプログラム最初は、マデルナ「フィッツウィリアム・ヴァージナル・ブックによる陽気な音楽」。勿論初めて聴く作品であり、マデルナという作曲家の名前も初見。ヴァージナルというのは16世紀後半のチェンバロ型の楽器だそうで、その楽器の為のルネッサン期の音楽を、マデルナが室内オーケストラの為に編曲した作品とのこと。
マデルナは前衛作曲家とのことだが、この作品は調性の明確な、ルネッサンス期の音楽であり、パーセルやヘンデル等のイギリスルネッサンス、バロックを想起させるような親しみやすい典雅な音楽。
全5曲の短い作品から成り立っており、全曲でヴァイオリンとオーボエが協奏曲風に活躍する。ここでの、コンサートミストレルのヤングさんとオーボエの独奏は鮮やか。第一曲では、バグパイプの印象を想像させる響き。弦楽器の柔らかく厚い響き、そして独奏者とのアンサンブル、非常に細部に渡るまで磨き抜かれたアンサンブル。第4曲の静けさの中の弦の厚く柔らかいアンサンブルが凄い、そしてそのあとの舞曲の早い部分への移行、精密に描かれたルネツサンス期の油絵の様な印象。
次が注目の、武満徹の「群島S」21人の奏者のための。ナッセンが初演した作品とのこと。
ここでは21人の奏者が5つのグループに分けられ、その内2つのグループはクラリネットの独奏で2階客席後部左右に配置。これにより、音が立体的にホールに響く。
私は2階席中央後部の座席。クラリネット奏者が丁度左右斜め前に位置し、オーケストラの立体的な響きに包まれる好位置。興味あるのは、その他の席でどう響いているかということだが、それぞれの席で興味ある響きがきけたのではなかろうか。作品自身は、武満独特のシャープな響きの中に、印象的な旋律が各楽器により形を変え現われ、特に金管とクラリネットのこだまのようなやりとりが印象的。大きなたゆたう海に浮かぶ島から聴こえるこだまのような響き。近くなり、遠くなり漂っているよう。
武満徹に限らずこの後のナッセンも非常に変わった楽器の配置をするなど、現代作品には楽器の配置にこだわる作品が多い。故にCD等録音で聴くと、その立体的音空間の感覚が聞こえず、その作品の面白さの半分も理解できないように思える。その点このように生で聴くと、ホール全体に響き交錯する音空間の素晴らしさが実感でき、感銘がより深く、その作品の真価が聴きとれるようだ。、
休憩を挟み、後半の最初はナッセン自身の作品、「『括り人形の宮廷の音楽』、2つの室内管弦楽のためのジョン・ロイド(16世紀)によるパズル集」。題名の通り、左右2つに分けられたオーケストラの編成。管楽器が前面に位置し、後部にヴァイオリン、その前にヴィオラ、チェロ、コントラバス、管楽器、打楽器が左右対称、左右にベル1台づつが配置されるという、特殊な編成。更にギター、ハープ、チェレスタが使用され、点描の様な効果をもたらしている。
1曲目のマデルナは原曲を忠実に室内オケ用に移し替えているようだが、ナッセンは原曲を解体し再構築しているようである。第1曲から3曲までの、知的・現代的な音の交錯、そして第4曲の古典的な合奏の盛り上がりが対照的で印象深い。特に第4曲は弦の合奏の静かな迫力が迫ってくる感じ。
最後は、レスピーギ。「ボッティチェリの3枚の絵~『春』『東方3博士の礼拝』『ヴィーナスの誕生』。
前回聴いたナッセンは、最後にラベルの「マ・メール・ロア」を持ってきていたが、ナッセン、この様な音の描写力が多彩な音楽が好みの様であり、又素晴らしい。3曲各々その絵の個性をくつきりと音で描き出した作品だが、演奏も鮮やかに彩られていた。特に「ヴィーナスの誕生」は、あの有名な絵の様子が音で描かれ、海の底の貝殻から生れ出るヴィーナスの様子が、徐々に力を増すアンサンブルで表現され圧巻。
非常にユニークなプログラムで、普段聴くことの無い作品が総てであったが、ナッセンの表現力の強さ、オーケストラの統率力の見事さ、そしてそれに応え緻密なアンサンブルを聴かせたOEKの実力と、聴きごたえのあるコンサートだった |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第288回定期演奏会
2010年10月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ケン・シェ
ヴァイオリン 吉田 恭子 |
|
この日の指揮は、カナダ生まれの指揮者、ケン・シュ。聴くのも初めてだが、名前も初めて耳にする指揮者。
日本で指揮の研修をしたようだが、まだ30前後と思える若手の指揮者。OEKとは、以前にもCD録音などで、競演しているようだ。しつかりとした、堅実な音楽づくりをする指揮者の様である。
プログラムは前半が、シューマン、序曲、スケルツォと終曲、吉田恭子を迎えてのチャイコフスキー、ヴァイオリン協奏曲。後半がビゼーの交響曲第一番。
最初のシューマン、明晰で見通しの良い音楽づくり。シューマンの作品の中では、屈折することのない、素直でロマン的な香気に満ちた音楽だが、ケン・シェは若々しい元気のよい感性で、この作品の新鮮さを表現。オケとの練習時間が少なかったのか、アンサンブルにやや粗さが表れたのが残念。又、もう少し音楽の陰影が現われていたらという感もある。
吉田恭子とケン・シェのチャイコフスキー。これも、若手同士のフレッシュなチャイコフスキー。ヴァイオリン出だしの旋律の歌わせ方にはっとさせる個性があった。ただ、全体を通して、やや音程が上ずり気味なのが気にかかる。さらに、細部の早いパッセージにも粗さがあり、部分的には個性的で魅力的な部分があるだけに、全体の完成度に不満が残る。
これだけの名曲になると、相当な完成度と、個性的な表現の表出がないと、中々感動をもたらすことが難しいということだろう。
後半のビゼー。この作品の弾けるような若さと、旋律の魅惑的な香りに溢れた面白さを、十分に聴くことが出来た。
オーボエの活躍が多いが、この日のオーボエの独奏は素敵だった。
ただ、やはり部分的にアンサンブルの粗さがあり、OEKのアンサンブルとしてやや不満足。
フランス音楽には、磨きぬかれたアンサンブルの魅力が不可欠だと思うのだが。
しかし、全体的には、「この作品は、やはり魅力的だな!!」と再認識させてくれた演奏。
この日は、珍しくヴァイオリンにも、オーケストラにもアンコールが無かった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第287回定期演奏会
2010年9月18日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ピアノ 広瀬 悦子 |
|
この日のプログラムは、メンデルスゾーン弦楽のための交響曲第10番(当初の発表は12番だったが、変更)、ピアノの広瀬悦子を迎えてのラベルのピアノ協奏曲、後半が武満徹「地平線のドーリア」、モーツァルト「交響曲第39番」。
OEKの標準編成に見合った落ち着いたプログラム。
最初のメンデルスゾーン、12歳から14歳にかけて12曲の交響曲を作っているというのだから驚きの早熟天才。
成熟期の交響曲が名作揃いなので、演奏される機会が少ない作品だが、ロマン的な雰囲気に満ちている佳品といえる。
憂いに満ちた弦の旋律、OEKの弦は柔らかく優しい。このあたり、井上道義の作品の個性に即した描きわけが巧み。後のモーツァルトがくっきりとした古典的明晰さを描き出しているのに比し、このメンデルスゾーンは柔らかく、しっとりとした情感。
そして、次のラベルのオーケストラは、色彩豊か。ジャズ的なリズムの乗り、管楽器の即興的な歌など魅力全開。
ピアノの広瀬悦子、輝かしい音色。野性的なオーケストラにひるむことなく、ラベルの上品でありながら自由奔放でもあるピアノを巧みに表出。
2楽章のピアノソロ、淡々としているようで、典雅な静けさに満ちている。3楽章は、オーケストラとピアノのリズムの競演。ピアノの打楽器的な響きとオーケストラのリズムの錯綜。
ピアノのアンコールのリストの「ラ・カンパネラ」。力任せに弾きがちなこの曲を、そうではなく丁寧に、しかし激しく、リストの歌が奏でられる。
武満徹の「地平線のドーリア」 ここで、井上道義は興味深い演出。舞台上には8人の弦楽奏者。指揮者が登場。舞台脇左右の出入り口が開かれ、正面の音響反射板の2枚が左右に開かれるとその奥に3人のコントラバス奏者。開け放たれた左右の舞台脇には3人づつのヴァイオリン奏者。音の広がりを意図した演出。
「地平線」の名前通り、音の空間がf果てしなく広がっていく。
40年以上前の作品だが、音の点描ともいえるその手法は、みずみずしさを今もたたえている。この個性は他の作曲家が入り込めない、独特の武満ワールド。
最後のモーツァルト39番の交響曲。
ここでも、井上ワールドの個性が全開。ティンパニーにバロックティンパニー、ノンヴィブラートに近い弦の奏法など、いわゆるピリオド演奏に近いのだが、決してドライな演奏でなく、古典的で明晰な響きに満ちている。
特に、2楽章、3楽章が秀逸、2楽章は甘くなく、しかし清楚で気品が高い。3楽章の中間部のフルートの主題も典雅。
壮大で過度にロマンティツクなモーツァルト、それに対抗し現代的な乾いた鋭いモーツァルトなど色々な解釈が聴かれるが、井上マエストロのモーツァルトは独特の個性が輝き、それがモーツァルトの音楽の本質を描き出しているように思える。
更に、ここ数年のOEKはアンサンブルの精緻さが一段と増している。晩年の岩城監督の時代、スケールの大きな演奏が聴けた反面アンサンブルの精緻さにやや欠ける面もが見られたが、ここ数年の合奏能力の向上は井上マエストロの奮闘の結果であろう。
パフォーマンスが目につく監督だが、音楽づくりの確かさは本物である。いよいよ、OEKの井上時代がやってきたようである。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第286回定期演奏会
2010年9月4日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
チェロ ルドヴィート・カンタ
ピアノ 加古 隆 |
|
新シーズンの幕開け。今年は7月、8月と定期オフの時期に、他の演奏会にも事情が重なり行かなかったので、2か月ぶりの音楽会。これだけ。間が空くのも珍しい。それだけに、一層新鮮な気分にもさせられる。
さて、今シーズン幕開けの演奏会は、9月定例の「岩城宏之メモリアルコンサート」
マエストロ岩城が亡くなってもう4年、早いものだ。心配された、その後のOEKだが、井上新監督の下、着実にその実力を高め、ユニークな活動を展開しているのは頼もしい限り。
さて、今日は、コンポーザー・オブ・ザ・イヤー(コンホーーザー・イン・レジデンスの名称が今年から変更)の加古隆の新曲の発表、そして今年度の岩城宏之音楽賞の受賞者の発表と披露というシーズン幕開けにふさわしい演奏会。今年の岩城宏之音楽賞はルドヴィート・カンタが受賞。今までは、新進演奏家に与えられてきたが、今年は優秀な新人がいなかったのか、ベテランのカンタが受賞。金沢においての20年に渡る音楽活動が評価されてのことと思える。
というわけで、この定期のプログラム、前半が、ハイドン交響曲第103番「太鼓連打」、そしたてカンタを独奏に迎え、サンサーンスのチェロ協奏曲第一番、後半が加古隆の作品と、新作「ヴァーミリオン・スケープ 朱の風景」
幕開けの定期とあって、会場は満員。今年度から設けられた500円で鑑賞できるという天井桟敷のスターライト席もほぼ満席。
演奏会前に岩城宏之音楽賞の授賞式。
ハイドンの103番の交響曲。その題名通りティンパニーの連打で開始されるユニークな出だし。その連打の後の、低音弦による序奏部が実に印象的。コントラバスとチェロの低い艶やかな音色がなんとも魅力的で、OEKの弦セクションの優秀さを再認識。
この序奏部は、一楽章コーダの再現部でも再現されるというユニークな工夫がされていて、ハイドンの才人ぶりを印象付ける。
第2楽章のハイドン独特の魅力的な歌、そして3楽章中間部の独特な踊り、4楽章の溌剌としたリズムと、この交響曲の面白さを生き生きと表現した上質な演奏。弦の柔らかい響き、管の生き生きとした歌、アンサンブルが溶け合い、溌剌、生き生きと音楽が躍動する。さすがに、OEKのハイドンは素敵だ。
サンサーンスのチェロ協奏曲。サンサーンスらしい華麗で、熱い音楽が渦巻く作品。カンタは上品、高貴に表現。この作品で゛は、もう少し泥臭く、熱く歌ってもと思わせるほど控えめなチェロ。これが、この人の個性か。オーケストラは、華麗で官能的な響きで盛り上げるが、チェロは動じず、楚々とした歌を紡ぎあげていく。
後半は加古隆ワールド。クラシックからジャズという多彩な才能の持ち主という経歴通り、この人は色々な世界を持つ人という印象。最初の三曲、「黄昏のワルツ」、「ポエジー グリーンスリーブス」、「フェニックス」は加古隆のピアノとオーケストラの協演。テレビのドキュメンタリーのテーマ音楽が中心ということで、ここでは聴きやすい、ムード音楽的な世界が展開。
委嘱作品「ヴァーミリオン・スケープ 朱の風景」はその傾向とは一線を画す、抽象的な世界。
「朱」とは、金沢の印象の心象風景。古い金沢のベンガラの色であり、現代の金沢の賑やかな朱であろうか。
和の静寂な世界と、ドラムセットを中心としたジャズ的な独特なリズムが交錯する不思議な世界。
コンポーザー・オブ・レジデンスの作品の中には、石川や、金沢をテーマにした作品も多い。このような作品がまとめて再演される機会があったらと思う。折角、OEKが委嘱した作品、一度だけの演奏でお蔵入りにしてしまうのは勿体ない。
現代音楽は耳になじみの無い音楽、再演されてこそ評価が定着するのではなかろうか?
今年も色々な世界が楽しめそうと、期待させる幕開けの定期だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第284回定期演奏会
2010年7月9日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 高関 健
ヴァイオリン 渡辺 玲子 |
|
今季最後の定期。先回の定期と共に、珍しい作品が並ぶ内容の濃い定期。作品の取り上げ方も、先回のゴトーニと近く、アメリカの現代作品2曲とハイドンという並び。もっとも、ワイルはアメリカというより、ドイツの作曲家としての認識があるが。そして先回はミニマル・ミュージックという独特のアメリカ音楽の色彩があったが、今回はアメリカというごちゃまぜの人間がうごめくアメリカ音楽という感じ。それにしても、珍しいが、内容の濃い作品を聴かせてもらったという印象。
最初のクルト・ワイル。「三文オペラ」の作曲家として有名で、組曲等での、一種独特な暗い影を持つ、黴びたような音楽が印象にある作曲家。今日は珍しい「交響曲第2番」。古典的な3楽章形式で書かれおり、プロコフィエフの古典交響曲を想起させるような作品だが、内容はかなり自由。1933年の作品ということだが、その時代の暗い雰囲気、そしてワイルの絶望的ともいえる暗澹たる心情を痛烈に表現していた。
曲冒頭から、暗く重い雰囲気が支配。管楽器の使い方が巧みで、フルート、オーボエのソロ、トロンボーンのソロなど印象的。第2楽章は「葬送行進曲」とのことだが、この時代のワイル独特の「歌」が延々と続く。それは、ワイルの絶望的なモノローグの様でさえある。第3楽章は中間部にマーチをはさんだ激しい楽章。馬鹿騒ぎの様でありながら、重く暗い感情が底に蠢く。ピッコロの甲高い、耐えきれない叫びが印象的。最後激しい早さで、絶望に突き進むようにして終わる。
演奏されることが珍しい作品だが、もっと聴かれて良い作品であろう。
次が渡辺玲子を独奏者に、これも珍しいバーンスタインの「セレナード」。副題に「プラトンの『饗宴』による、独奏ヴァイオリン、弦楽オーケストラ、ハープと打楽器のための。」とあるように、ヴァイオリン協奏曲。
編成も非常にユニークで、管楽器が使用されず、打楽器とハープが大活躍という珍しい編成。打楽器も、ティンパニー、大太鼓、小太鼓、タムタム、ビブラフォン、タンバリンなど多彩。
作品の内容は、プラトンの「饗宴」を題材にしたものとのことだが、その名の「セレナード」という言葉通り、「愛」をテーマに繰り広げられているとのことだが、これについては諸説あるようで、バーンスタインの有名な性癖を表現したものとの説もあるよう。
それは、ともかくとして、この日は渡辺玲子のヴァイオリンが圧巻。音質はソフトなのだが、明るく華やか。中間楽章の早いパッセージの力感あるスピード、その後の楽章のしびれるようなハイトーンの歌、そして最終楽章のジャズ的なノリ、全て完璧で酔わせてくれた。管楽器は使用されていないのだが、まるで管楽器が使われているような色彩感が鮮やか。
チェロ、ハープとのヴァイオリンのデュオなど、魅力的な部分が満載。
終楽章は、「ウェストサイドストーリー」に聴くことが出来る、ニューヨークの下町の雑沓を思わせるようなジャズ的な
のり。このあたりのOEKのリズム感もピタッとはまり、ヴァイオリンとのかけあいの面白さ、ノリの見事さ。
最後はハイドンの90番の交響曲。先回のゴトーニに続いてのハイドン。
今回は、ゴトーニの典雅さと異なり、やや重いハイドン。ティンパニーにバロックティンパニー、ヴィブラートもやや控えめにと工夫はしているのだが、表情がやや平凡。メリハリが弱い分、ハイドンの交響曲のスリリングな面白さが若干欠けていた。
勿論これは好みの問題、十分に充実した演奏ではあるのだが。OEKのハイドンは現在もっとも充実したアンサンブルであることは疑問の余地がない。
終楽章は、ハイドンのユーモア。この部分をどうするのという興味が深々。高関健は高らかにコーダを鳴らし、終了と思わせ、拍手が起こるとおもむろに振りかえり、「まだ、終わりじゃないの」という仕草で、コーダを再開、2度目も同様、3度目でようやく終了。聴衆も大いに面白がっていた。
ここ2回、ユニークなプロの定期だったが、定期演奏会はこのような冒険があつて然るべき。聴衆も様々な音楽世界に触れられて面白い。来年の定期もその意味では、凝った演奏会が多いようで、期待が大きい。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第283回定期演奏会
2010年6月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮・ピアノ ラルフ・ゴトーニ |
|
今回の定期はフィンランドの指揮者、ラルフ・ゴトーニの登場。2008年4月以来3年ぶり2回目の定期への登場。
この日のプロは、ハイドン交響曲第83番「雌鶏」、グラス、ピアノとオーケストラのためのチロル協奏曲、後半がアダムズ、シェイカー・ループス。かなりマニアックなプログラミング。そして、オーケストラ編成もOEKの基本形の小さなもの。ハイドンのみ管楽器が入るが、その他は弦楽合奏、そして打楽器も無しというごく地味なもの。その分、オーケストラの真の実力が試されるといえよう。
さて、この日はオープニングでちょっとしたハップニンク。定刻かなり過ぎてもオーケストラ団員は登場せず、ちょっと会場がざわつき始めたころ。楽団長が登場、「管楽器にトラブルが発生し、修理にかなり時間を要するので、プログラムの順番を変更したい。最初にグラス、次にハイドンとする。」とのこと。珍しいトラブルである。結果としてこの変更の方が、座りの良いプログラムとなったような気がする。ハイドンを挟んでの現代音楽2曲という配置の方が安定している。
最初のグラス、ピアノをゴトーニが弾きながらの指揮。3楽章形式だが、リズムパターンが統一されている中で、ピアノと弦楽合奏の対話の様な懐かしい歌が展開される。いわゆる「ミニマル・ミュージック」の範疇の音楽とのことだが、旋律性よりも、リズムパターンの点滅、そして単純な音の繰り返しによる音楽の高揚という、不思議な感覚の音楽。絵画でいうと、点描の様な印象を想起する。現代音楽の複雑さから脱却しようという試みの様にも思える。
ゴトーニのピアノは静かだが、柔らかく深い響き。2楽章の、ひとつひとつの音を確かめるかのような響きは印象的。オーケストラも単純ではあるが、その中にある色彩的な複雑さを巧みに表現していた。
2曲目のハイドン。実に安定した、ふくよかなハイドン。オーケストラのアンサンブルが見事で、安定した響き。メリハリの効いたハイドンも良いが、このように穏やかで、ふくよかなハイドンも良い。最近流行のピリオド奏法のハイドンとは一線を画す、ロマン的なハイドンである。OEKはハイドンの演奏が多いが、色々な指揮者により個性の異なるハイドンの表現を聴かせる技は、このオーケストラの成熟度の証といえよう。
最後のアダムスの作品。これも、ミニマルミュージックの範疇の作品。弦楽合奏のみによる演奏だが、まるで木管が加わっているような色彩的なアンサンブルも聴こえる。非常に細かいパッセージが緻密に詰まったような音楽。それだけに、各パートに要求されるテクニックは相当高いと思えるが、OEKは実に巧み。(シェイカー)という言葉が、「振動」と訳されているが、シェーカーという言葉の感覚通り、狭い空間でごちゃまぜにシェイクされているような感覚。中間の楽章では、ループという言葉通り、シェイクと対立する広がりのある空間。この部分では、日本の雅楽を想起させるような響きも聴こえる。終結部の「最後の振動」の部分では、各弦楽パートが更に細かくフーガの様に重なりあい高揚するが、この部分の各パートの演奏はまさしく壮絶。最後は、平穏に戻り静かに終結。オーケストラにとっては過酷な作品といえようが、ゴトーニの要求にOEKはよく応えていた。
極めてマニアックな演奏会ではあったが、その分緊張感に支えられ、内容の充実した演奏会となっていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
西本智実指揮 スミ・ジョウ インコンサート
2010年6月22日 オーバードホール
指揮 西本 智美
ソプラノ スミ・ジョウ
管弦楽 リトアニア国立交響楽団 |
|
この一週間で外国からのオーケストラ3(南西ドイツ響、ブタペスト祝祭管、リトアニア国立響)、旬の独奏者3(庄司沙矢香、神尾真由子、辻井伸行)、注目の指揮者4(クリストプリス、フィッシャー、アシュケナージ、西本智実)と集中して聴くこととなる。何年かに一度、このような週間が訪れるが、中央ではともかく、北陸の様な地方では珍しく、比較して聴ける絶好の機会である。
この日は、西本智実とソプラノのスミ・ジョー、リトアニア国立交響楽団の協演。前半が。スミ・ジョーのオペラアリアを中心としたプロ、後半が、R・コルサコフ「シェエラザード」、ラベル「ボレロ」という、色彩感溢れる楽しいプロ。
J・シュトラウスの「こうもり・序曲」で幕開け。最初はどうしても音が硬くなるようで、この序曲の弾けるような楽しさには欠けるうらみがある。難しい序曲で、ウィーン独特のリズムとワルツが混在する難曲なので、これはいたしかたないことかもしれない。この序曲の名演奏にはなかなかめぐり合えない。
序曲についで、アデーレのアリア「田舎娘を演じる時には」。スミ・ジョーのコケティッシュな歌が実に楽しい。声の質は、透明で柔らかいが、このアリアのアデーレのお茶目な性格を巧みに演じていた。オペラの演技力の確かな歌い手。
次に珍しい、デラクアという作曲家のヴィラネル(牧歌)「つばめが飛び行くのを見ていました。」柔らかいコロラトゥーラの高音が心地よい。かなりの技巧を要するアリアだが、中間部のホカリーズの超高音をソフトに転がすように歌う部分は見事。高音なので、下手すると絶叫になってしまうが、抑えたソフトな音質が余裕を持って響いていた。
ベルディー椿姫「第一幕の前奏曲」、続いてアリア「ああ、そはかの人か、花から花へ」
「第一幕の前奏曲」はやや荒っぽい演奏、もう少し落ち着いた弦の歌が欲しかった。このあたりは、まだオケも指揮者ももう一つ乗りきっていない感じ。スミ・ジョーのアリア、これも表情豊かな歌と演技。有名な「ああ、そはかの人か」では、せつないヴィオレッタの感情を抑えながら、柔らかく歌い、後半の「花から花へ」では複雑な心情を迫力を持って表現。表現力が豊かな歌手である。
アンコールに2曲。最初はオッヘンバックの「ホフマン物語」からの人形のアリア。これも、コケティッシュな
歌と、ゼンマイ人形の振りが見事。途中ゼンマイが緩み、巻きなおす場面では、西本智実が指揮台から下り、巻きなおす仕草に会場は沸く。続いて、プッチーニのジャンニ・スキキッキから「私のお父さん」。これも、落ち着いた歌で、柔らかい表情豊かな歌唱。オペラのプリマとしてのキャリアを十分に感じさせる楽しいステージだった。
後半は管弦楽の色彩豊かな作品が2曲。
まずR・コルサコフ「シェエラザード」。この作品に最近縁があるのか、ここ3年間で4度ほど聴くこととなる。
西本智実は実に詩情豊かで、ドラマティックなシェエラザードを聴かせてくれた。様々な楽器の独奏があらゆる部分を彩り、エキゾティックな歌を奏で、物語を進行させながら、劇的な盛り上がりを築きあげる。丁寧な指揮ぶりで、作品の面白さを存分に表現していた。オーケストラの音質はやや硬質、ロシアのオケと異なり冷たい空気を感じさせる。各独奏者も優秀。ヴァイオリンの印象的なテーマの独奏、チェロ、木管楽器と表情が豊か。
西本智実は堅実な指揮の様でありながら、ある部分ではテンポも動かし、ドラマティックな世界を作り上げる。
彼女の場合、交響曲の様な、構成的・論理的な作品より、バレー音楽や組曲などの描画的・色彩的な作品を得意としているようだ。交響曲でもマーラーの様な、かなり直観的多彩さを有している作品も良いようだ。
又、最初の活動拠点がロシアであったので、ロシア作品を中心としたプログラミングが多いが、色彩的で詩情豊かな音楽を作り上げるところからみても、フランス物などももっと取り上げても良さそうである。
女性であるからということでは無いだろうが、音楽の作り方は、直観的で、即興的な要素が強いように思える。
そのため、気分の乗りによって、かなり出来の良しあしが左右されるのではないだろうか。職人的な指揮者でなく、瞬間の感性を大切にするタイプのようだ。シェエラザード最後の部分の大波の描写、そして岩にぶつかる部分の壮大なスケールなど、それを良く象徴している。
ラヴェルの「ボレロ」は、どういうわけか生で聴く機会が少なかったが、この様に大きな編成のオーケストラで聴くと、実に面白い作品ということを再認識。各楽器の独奏者の妙味、個性が裸で現われ面白い。同じ旋律を異なる楽器、異なる奏者で繰り返す面白さ。そして繰り返しながらの大波の様な盛り上がり、興奮。
西本は各独奏者の個性を尊重しながら進めていくが、進むにつれて、ややテンポを上げながら最後のエンディングの大きな盛り上がりを作り上げる。なかなのドライブテクニックである。
会場は大きな拍手、1階前列の学生たちは、立って大きな拍手を贈っている。何度も呼び出される指揮者、拍手は絶えることなく、ホール照明が明るくなりオーケストラが退場するまで拍手は続いていた。オーケストラの退場後、西本智実とコンサートマスターが再び登場、声援に応えていた。
珍しい女性指揮者ということで、やや色眼鏡をつけて見ていたようなところがあったが、この日の演奏でそのような偏見でない実力を再認識。日本のオーケストラも、もっと積極的に振って欲しいと思う。 |
|
|
|
|
|
|
|
ウラディミール・アシュケナージ 辻井伸行 オーケストラ・アンサンブル金沢 演奏会
2010年6月20日 石川県立音楽堂
管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢
指揮 ウラディミール・アシュケナージ
ピアノ 辻井 伸行 |
|
今旬の注目のピアニスト、辻井伸行がいよいよ金沢に登場、そして名匠アシュケナージ・OEKとの競演という期待のコンサート。
さすがにチケットも早々と完売で、会場は補助席まで出る盛況。そして、目立ったのは障害を持った子供たちの姿。
辻井伸行も勿論だが、アシュケナージがどの様にOEKを指揮するのかという期待度も大きい。
最初はメンデルスゾーンの八重奏曲の弦楽合奏版。通常は8人の弦楽奏者での室内楽だが、今回は弦楽による合奏。
各パートのアンサンブルの精緻さが試される作品だが、OEKの各パートのアンサンブルの冴えが際立ち、厚みのある、そして躍動感に満ちた音楽が展開された。アシュケナージの指揮ぶりは、見た目ぶきっちょで、決して流麗というものではないが、機械仕掛けの人形の様な正確さで、指示が送られ、見事にその指示通りの音楽が生まれてくる、その様子は見ていても実に心地よい。OEKのオーケストラとしての合奏能力の高さを最大限引き出した演奏。音楽は、前へ前へという推進力が強く、柔らかいアンサンブルと分厚い響き、そして生気に満ちたリズム感に溢れた見事なメンデルスゾーン。
ラフォール・ジュルネ金沢では、IMA合奏団による、韓国のメンバーによるシャープで新鮮な演奏が記憶に残るが、今日の演奏は円熟した大人の風格。
さて、辻井伸行の登場。ショパンのピアノ協奏曲第一番。辻井の十八番。
アシュケナージが辻井の手を引き、エスコートしながら登場。終始、辻井のエスコートをする巨匠の姿が暖かく印象的。アシュケナージの人間性の暖かさをかいま見た思い。
辻井のピアノは将に音楽の申し子。今、ショパンを弾くことがこんなに楽しいのたという思いが、ひしひしと伝わってくる。ロマンティックな作品なので、感傷過多になりがちなこの作品を、辻井は衒いなく堂々と自らの感性で弾き切っていた。
青白いショパンでなく、お日様のさんさんと輝くような健康的なショパン。この感性をいつまでも大切に保ち、音楽の楽しさを私たちに伝え続けてほしいと願う。アシュケナージ・OEKの伴奏も、堂々とピアノと渡り合い迫力ある演奏。
会場に多く見られる障害を持った子供たちにも、勇気を与える演奏だっただろう。
アンコールにショパン2曲。これも、よく歌う、そしてポーランドの香りがする演奏。感性の豊かさを示した。
大きな拍手に応え、四方の聴衆に丁寧にお辞儀をし、不自由にもかかわらずオーケストラに向かい深々とお辞儀をする姿に熱いものを感じた。
後半はベートーヴェンの交響曲第4番。スケールの大きな4番の演奏。
第一楽章序奏の緊張感のある和音から一転して跳ねるような主部に入る部分、演奏の成否を分ける部分だが、鮮やかな入りであった。躍動感に満ちながら、十分な重量感を保った演奏。一気呵成に走り抜けがちな第一楽章だが、アシュケナージは歌う部分を十分に歌わせ、どっしりとした厚みのある音楽を展開していく。
第2楽章のしっとりとした抒情性、3楽章中間部の牧歌的なのびやかさ、4楽章の前へ前へと進んでいく音楽の心地よさ。
全体としては、伝統的なドイツ風のロマンティックな演奏だが、マンネリに陥らず、生気に満ちた演奏であったのはさすが。
この日のOEKの音色は柔らかく、かつ厚みがあり、十分に鳴りきっていた。特にアシュケナージの細かい指示通り木管群がよく歌うのは特筆もの。、40名あまりのオーケストラとは思えない、充実したアンサンブル。
アンコールにシベリウスの静かな小品。冷たい空気を感じさせる抒情。 |
|
|
|
|
|
|
|
ブタペスト祝祭管弦楽団演奏会
指揮 イヴァン・フィッシャー
ヴァイオリン 神尾 真由子
2010年6月17日 オーバードホール |
|
初来日の際の衝撃的な話題に一度聴いてみたいと思っていたフィッシャーのブタペスト祝祭管弦楽団が富山にやってきた。独奏者に神尾真由子という魅力的な顔ぶれで。
今日のプログラムは、ロッシーニ「アルジェのイタリア女」序曲、メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲」、シューベルト交響曲第8番というもの。
まず、意表をつく楽器の配置に驚く。
コントラバスを中央奥に、弦楽器は対向配置だが、何と木管楽器が弦楽器を割って入るような形で舞台中央最前面に。更にシューベルトでは、その木管を弦楽器の前にオーボエ、フルート、ファゴット、クラリネットと弧状に配置するというもの。
コントラバスを中央奥に配置する方法は、ノリントンのシュトゥットガルト放送響の際にもあつたし、OEKの故岩城監督のブラームスの演奏の際もその様に配置された記憶がある。ブラームスの交響曲の初演時には、そのような配置であったと、岩城監督が述べていたのを思い出す。しかし、管楽器のこの様な配置はいまだかつて出会った記憶がない。
弦楽器も対向配置だが、左右の奥に高台を置き、立体的に配置している。
これは、明らかに立体的な響きの再現を意図したものであろう。
なるほど、低音は正面から迫ってくるし、木管が弦楽器よりもくっきりと前面に浮かび上がってくる。
フィッシャーの異才ぶりを見たようである。
さて、最初のロッシーニ。ここでは、パーカッションを弦楽器が挟むような形で、中央コントラバスの前に配置、これも立体的な音の構図を意図しているよう。
音楽は、非常にシンプル。ロッシーニの色彩的ではあるが、古典的な簡素さを表現しているよう。派手に鳴らしたがるロッシーニだが、フィッシャーはそうではなく、歌劇の序曲らしく、むしろ音量は抑えめ。故に、木管の魅力的なフレーズが、オペラアリアの様に優雅に歌う。そして、ロッシーニクレッシェンドも、大げさでなく、テキパキと進む。
普段聴きなれているロッシーニと比較し、物足りなさを感じるほどの抑え方だが、その分躍動的で、よく歌う。
神尾真由子を独奏者に迎えたメンデルスゾーン。昨晩の庄司沙矢香のプロコフィエフ、2日続けての若手代表のヴァイオリンだが、タイプがかなり異なる。神尾は天性の音楽へのアプローチを持っているようで、天真爛漫、パッションの溢れた演奏。庄司は作曲者の表現しようとするものに自らの個性を殺しても鋭く肉薄しようとする。どちらも、見事な表現。
メンデルスゾーンの音楽の上品で、せつない抒情を、神尾は一層切々と訴える。音質も艶やかで、高温の冴え、低音の太さ、そして独特の粘りつくような表現、濃い表情のメンデルスゾーン。伴奏のオーケストラの表情豊かなアンサンブル、特に随所に聴こえる木管のヴァイオリンとからむオブリガートなど見事。気持ちの良いメンデルスゾーンであった。
アンコールにパガニーニのカプリッチョから。おなじみのアンコール曲だが、相変わらず見事。
休憩後は大曲、シューベルトの交響曲8番。前述したように、独特な配置への驚き、それにより生まれる音の色彩的な重なり。この演奏では、他にトランペットを古楽器、ティンパニーもバロックティンパニーにと特徴的。ティンパニーも高台でなく、弦楽器群の中に埋め込むように配置、全体の音のバランスを取るような配置。
生まれる音楽は、古典的な典雅さの中に、シューベルト独特のローカルな香りが溢れ魅力いつぱい。
そして、各楽器がクリーンに浮かび上がり、この部分でこんな音楽が鳴っていたのだという新鮮な驚きが随所で聴ける。
音質は明るめであるが、素朴な温かさがある。
第2楽章の木管の歯切れのよいテンポ、そして自然な感興の盛り上がり、どこにも余計な装飾は施していないが、だからこそシューベルトの溢れる歌が聴こえる。第3楽章の中間部、田舎の踊り、そこで楽しく優雅に踊る人たちが目に見えるよう。
フィッシャーは踊るような指揮ではないが、音楽は明らかに優雅な踊りのリズム。第4楽章も、音楽を煽るようなことは決してなく、丁寧な繰り返しにより、次第に盛り上がりが築かれていく。細部まで神経の行き届いた、フレッシュな魅力。
アンコールが2曲。最初がバルトークのルーマニア民族舞曲から。ここでは、弦楽器のいかにもハンガリーの血を感じさせる生々しさが魅力的。短い作品なので全曲を聴きたかった。
2曲目は、ハンガリー民謡のよう。ジプシーヴァイオリンと太鼓の様な民族楽器と、フィッシャーが指揮台に座りながら鈴の様なパーカッションを伴奏。これもハンガリーの土地の香り。ジプシーヴァイオリンの心湧き立つようなリズム。
心浮き立つ音楽の楽しさを満喫したひと夜。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第282回定期演奏会
2010年6月16日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ヴァシリス・クリストプリス
南西ドイツフィルハーモニー交響楽団
ヴァイオリン 庄司 沙矢香 |
|
今回の定期は変則的で、OEK以外のオーケストラによるもの。オケの定期演奏会で、他のオケを出演させるということは、常識的には考えられず、日本ではOEK定期のみの試みではなかろうか。賛否は分かれるだろうが、聴く側にとっては、刺激があり、面白い試みではある。今回は、南西ドイツフィルハーモニー交響楽団によるもの。ドイツは音楽国。相当数のオケが各地で活動しているので、日本人にとっては同じような名前が色々あり紛らわしいが、このオーケストラはスイス国境に近いコンスタンツという町に本拠を置くオーケストラ。日本には2度目の来日とのこと。札幌、東京、京都では、オールモーツァルトプログラムを組み、特に東京では3日間に渡り、交響曲31番から41番までの連続演奏会を行ったそうである。
金沢のプロは異なり、モーツァルトの交響曲第31番「パリ」に始まり、庄司沙矢香を独奏者に、プロコフィエフ「ヴァイオリン協奏曲第2番」、後半がドヴォルザーク交響曲第8番という、なかなか聴きごたえのあるもの。
17日には、富山で、フィッシャー指揮ブタペスト祝祭管弦楽団、神尾真由子という演奏会があり、2日間に、2つの外国オケと日本を代表する旬のヴァイオリニスト二人を聴き比べられるという贅沢な2日間。
この日は、OEKのメンバーが、チェロの大沢氏を初めとして数人加わっていた。
指揮のヴァシリス・クリストプリスは2月定期でOEKを振ったばかり。その際は、小ぶりな作品が多かったので、堅実で、自然な音楽づくりをする指揮者という印象を持ったが、今回はプログラムが多彩で、個性的な作品が揃ったので印象はかなり異なった。
まず、モーツアルトのパリ交響曲。オケの音質が実に重い。ドイツ的なモーツァルトといおうか、躍動的でたおやかなモーツァルトと正反対の、腰のしっかりとした重々しいモーツァルト。若手の指揮者でありながら、かつてのドイツの巨匠たちの様な重厚さを意識したような演奏。ホルンにナチュラルホルン、ティンパニーはバロックティンパニーを使うなど、ピリオド奏法を意識した編成だが、スタイルは逆。テンポは遅く歌わせ方も濃厚。ティンパニーもバロックティンパニー独特の乾いた音でなく、ドスドスというような重量感のある音を出していた。管楽器も暗い音色で、かつてのドイツのオーケストラはこのような音質だったかと想起させられる様な音色。
庄司沙矢香を独奏者としたプロコフィエフ。演奏によっては、怜悧でシャープな印象を持つ作品だが、この日の演奏は重く、暗い。庄司のヴァイオリンは、まるで求道者の如く、この作品の本質を探り出そうとする様。ティンパニを使用せず、代わりに大太鼓を使っている珍しい作品だが、この日の演奏ではその作曲者の意図が明瞭に現れていた。重く、太い大太鼓の低音が、全体の重苦しい雰囲気を一層強調している。ヴァイオリンの呟くような暗くざらざらちとした音色、そしてそれに絡む低音の管楽器。第2楽章の印象的な旋律も、甘くなく、沈潜した抒情。
いつもながら庄司のヴァイオリンは自らをひけらかすことなく、作品の本質にいかに迫るかという気迫に満ちている。真面目な演奏者である。アンコールのバッハも、地味な様でいて、スケールの大きな、堅固な演奏。
ドヴォルザークの8番。1楽章出だしから、テンポの遅さが目立つ。ひとつひとつのフレーズを十分に歌わせながら、クライマックスを築きあげていくていくような、堅固な構成感のある演奏。テンポが遅く、オーケストラの音質が重い分、この作品の牧歌的な明るさが損なわれるきらいもある。第2楽章では、音楽が止まりそうになる瞬間もある。流麗さと対極的な重々しいドヴォルザーク。第4楽章フィナーレのコーダのクライマックス前の弦楽器のしみじみととした語りかけは印象的。
かなり細部にこだわりながら、全体を築いていこうとする意図が明瞭。その分、音楽の即興的とも言える、自在な興奮には欠ける。
好き嫌いの分かれる演奏だが、個性的なアプローチではある。
アンコールのスラブ舞曲8番も同様、弾けるような舞曲と異なり、巨象のダンスのよう。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第281回定期演奏会
2010年5月25日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
共演 兵庫芸術文化センター管弦楽団(PAC) |
|
何年か一度に行われる他のオーケストラとの合同演奏会。今回は、西宮の兵庫芸術文化センタを拠点とする兵庫芸術文化センター管弦楽団との合同公演。兵庫芸術文化センタ管弦楽団は歴史の新しいオーケストラだが、佐渡裕が薫陶し、育てたオーケストラで優秀なオーケストラとして、最近評価が高い。
プログラムはOEKがモーツァルトの交響曲第38番「プラハ」、PACがベートーヴェンの交響曲第8番、そして合同演奏でグローフェの組曲「大峡谷」という、なかなか聴きごたえのあるもの。
OEK得意のモーツァルト、骨格のしっかりとした、古典的な緊張感に溢れた演奏。各パートのアンサンブルも充実し、OEKの円熟度を感じさせる演奏。欲を言えば、もうすこし柔らかさ、ふくよかさを備えた大きさが欲しい気がした。このあたりが、ハイドンと異なるモーツァルト演奏の難しいところ。
PACのベートーヴェン。これは緊張感と、迫力、又革新的な荒々しさというベートーヴェンの特質を大いに引き出した名演。
第一楽章展開部のたたみかけるような迫力、最終楽章のはっきりとしたリズム感など、音楽的興奮に満ちた演奏。
第3楽章のホルンの重奏にやや破たんがあったのが残念だが、オーケストラははつらつとした、若さあふれる演奏。
OEKと他のオケとの共演の場合、それぞれのオーケストラの個性、音質の相違が聴けて興味深いが、この日もそう。
他のオケと比較すると、OEKは実にどっしり、しっとりした風格を感じる。音質も派手でなく、柔らかく地味である。それに比較し、PACは明るく派手。音も鮮やかさがある。金沢と西宮・芦屋という風土の相違がそうさせるのであろうか。はたまた、創設当時の指導者、岩城宏之と佐渡裕という個性の相違でもあろうか。
さて、後半は、グローフェの組曲「大峡谷」 有名な作品でありながら演奏機会の比較的少ない名曲。
舞台に溢れんばかりの人数。配置は井上マエストロ通常の対向配置でなく、第一、第二ヴァイオリン、チェロ、ビオラという近代的な配置。これは、この作品の特質を引き出すための配置であろう。チューバ、バストロンボーン、チェレスタ、ピアノ、ハープ、各種パーカッションと、賑やかな配置である。普段のOEKでは聴くことの難しいフルオーケストラの演奏。
「日の出」の小鳥たちの鳴き声から始まり、大きななクライマックス、ホール全体が鳴り響くような壮大さで、度肝を抜く。
有名な「山道を行く」での、ロバのいななきとヒヅメの音が実に効果的。このヒヅメの音は色々な楽器で奏されるが、この日はヒツメ状の道具を両手に持ち、実際に歩くように叩くという試み、描写がリアルで面白い。奏する方はリズムをとるのが大変だろうか゛「豪雨・嵐」ではウインドマシーンの嵐の音、打楽器・金管の雷鳴、更にはホールを一瞬暗くして舞台で稲津を光らせるという、井上マエストロらしい工夫も加わり、実に描写が鮮やか。最後は、有名なテーマが高らかに響き渡り全曲が閉じられる。R・シュトラウスの「アルプス交響曲」に想をえたのであろうが、いかにもアメリカ的な、屈托なく楽しめる作品。
ヤングのヴァイオリン独奏を始め、各ソリストも優秀、楽しく豪快な演奏。
アンコールにスーザのマーチ「星条旗よ永遠なれ」、ホール全体の手拍子、井上マエストロがモーニングを脱ぎ捨て、その下の派手なヤンキーのシャツで星条旗を振りまわすというパフォーマンス。少々やりすぎ?という感もなくもないが、聴衆は大喜び。それとは別に、このマーチの演奏は実にしっかりとしたアンサンブルの名演。
いつも、何かを期待させる井上監督ではある。 |
|
|
|
|
|
|
|
ラフォール・ジュルネ金沢
2010年5月4日~5日 石川県立音楽堂コンサートホール他 |
|
今年も、ラ・フォール・ジュルネ金沢「熱狂の日音楽祭2010」が4月29日~5月3日迄、石川県立音楽堂を中心にして開催された。今年は、ショパンの生誕200年ということで、ショパンとその仲間の作曲家の作品を中心に、音楽祭は構成されていた。
主催者の発表では184公演、昨年を上回る10万8000人余りの観客数とのこと、昨年以上の熱気で終了したようだ。
今回は、5月4日~5日にかけての14公演を鑑賞した。
今年は、運営面も大分手慣れてきたようで、コンサート間のインターバルの時間も比較的余裕があったり、場合によってはコンサートの開始時間を遅らせるなどの配慮があった。しんし、それでもアートホールと音楽堂の間を駆け足で移動するなど、聴く方にとっては、慌ただしい音楽祭ではある。しかし、それもラフォール・ジルネの一つの楽しみでもあるのか。
今回鑑賞した内容は別表の通り。
ショパン中心の構成だが、周辺の音楽家の作品も多く、特に私が聴いた公演の中では、メンデルスゾーンが多かった。シンフォニーが3番「スコットランド」、4番「イタリア」、有名なバイオリン協奏曲、比較的聴く機会の少ない弦楽四重奏曲が2曲、更に八重奏曲、序曲、ピアノ作品と多彩。逆に中心のショパンは意外に少ない。やはり、ピアノ作品中心のショパンのみでは、OEK中心の音楽祭であるラ・フォール・ジュルネ金沢では寂しいという配慮からであろう。
今回特に興味深く聴くことが出来たのは、ピアニストの競演。ルイス・フェルナンドーベレス、フラメナ・マンゴーヴァ、ベルトラン・シャマユ、アプデル・ラーマン・エル=パシャ、ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ、菊池洋子、若林顕、小曽根真、鶴見彩と多彩。ペレスの明るく華麗な響き、マンゴーヴァの重厚さ、エル・ヴァシャの上品、洒脱。同じショパンを演奏しても、これだけ個性が異なるという面白さ、これはこの様な音楽祭ならではの面白さと言える。
それは、オーケストラでも同様、同じメンデルスゾーンを演奏しても、フランス室内管弦楽団とオーケストラ・アンサンブル金沢では、生まれてくる響きが全く異なる、フランス室内管はやはり派手で爽快、OEKはどっしりとした落ち着きを感じさせる。
室内楽でも、トリオ・ヴェンダラーとライプチィッヒ弦楽四重奏団の個性の相違。フランスとドイツでこれだけ事なるという事を実感。
2日間の間に次から次へと聴くことにより、なるほどこれだけお国柄で音楽が異なるという事を、体感出来る面白さ、これも、ラフォール・ジュルネを聴くことの一つの楽しさである。
さて、個別の短評を。
公演番号212
山田和樹の勢いがあり、精彩に満ちた音楽づくりが、メンデルスゾーンにぴったり。「真夏の夜の夢・ノクターン」は、もう少し幻想的な雰囲気が欲しかったが。
ピアノのペレス、華麗でロマンティツクなピアノ。メンデルスゾーンの明るい憂いを的確に表現していた。
公演番号222
ヴァイオリンの西海和江とピアノの鶴見彩、強い個性は無いが清楚で可憐。
INA弦楽アンサンブルのメンデルスゾーン八重奏曲。出だしは、少々もたつき気味だったが、進むにつれ快調。見事なアンサンブル。石川ミュージックアカデミーの出身者で、韓国人のメンバーとのことだが、水準の高さは相当なもの。
公演番号233
日本の実力派、二人による珍しくも貴重な連弾のリサイタル。
前半と後半で、低音部と高音部を交代しての演奏。まるで、一人の人間が4つの手で演奏しているような錯覚を感じさせる意気のあった演奏。お互いに呼吸を図りながらの、的確なテクニック、表情豊かな演奏。シューマンの作品、演奏されるのが珍しい作品と思われるが、それぞれの小品が個性豊かで、シューマンの特長である幻想的で、気分の移り変わりの激しい情感にあふれた作品。リストは、連弾聴くのは初めてだが、ラッサの部分の濃厚な表情、フリスカの部分の圧倒的な技巧と迫力。
公演番号223
新作能「調律師-ショバンの能」。ラフォール・ジュルネ金沢では恒例となった、能と洋楽のコラボレーション。
今回は、ポーランド大使、ヤドヴィガM.ロドヴィツチの創作による台本を基とし、ショパンのピアノ曲数曲を鶴見彩が演奏、若村真由美の語りにより進行、後半から能舞が入ってくるという演出。ドラクロワとショパンの友情を軸として展開されているようだが、解説、語りとも難解。語りは、候文のような古い文体を使用、舞台奥のスクリーンにはテーマに即した写真が投影されている。残念ながら、テーマが読み取れず、ただ冗長に流れていたように感じた。
解説、語りなど入れず、ただピアノと能に世界を託した方が、想像性が広がるように思われるのだが。意欲作とは思うがろ、作者のひとりよがりであるように感じたのは、私だけだろうか?
公演番号214
オーケストラコンサート。ホストオーケストラのOEKの今回唯一のシンフォニーコンサート。
メンデルスゾーンは、この後パリ室内管弦楽団が4番「イタリア」を演奏したが、それぞれのオケと指揮者の個性の違いが明確に現れていて興味深い。
「フィンガルの洞窟」「スコットランド」と色合いの似通った2作品、くすんだ色彩感と、憂愁に満ちた旋律、しつとりとした弦の響きと、井上マエストロの堅固な構成感。素敵な「スコットランド」だった。最終楽章フィナーレの堂々たる高揚、気持ちの高ぶる演奏。
公演番号235
この後、2つ続けてピアノの演奏会。個性の異なる二人のピアスト、続けて聴くことにより、よりその違いをはっきりと認識する事が出来、興味深かった。
ペレスはスペインのピアニスト。最初と最後に、バラード1番、スケメツォ3番と大きな構成感を持つ作品を置き、中にワルツ、ノクターンと比較的小ぶりな作品を並べるというプログラム構成。
彼のショパンは華麗で、鮮やか。音楽は大柄で、豪快。繊細なショパンとはイメージを異にする。音質も非常に明るい。
公演番号225
ブルガリアの女性ピアニストマンゴーヴァ。まず、その堂々たる体躯にびっくり。椅子から身体が半分はみ出しているよう。
そのピアノも、体躯通り、重厚。この日は、ショパンは練習曲、一曲のみで、他はシューマンとリスト。
シューマンは「フモレスケ」というやや大きな作品。暗い色彩感と瞑想的な響き、重い高ぶりは、この作品の面白さを際立たせていた。ショパンはペレスの華麗さと対照的に落ち着いた色彩。
リストの2曲は圧巻。最後の「メフィストワルツ」の超絶技巧、ピアノが壊れそう。
アンコール2曲、リスト/シューベルト「魔王」のパラフレーズ 、ショパン/ノクターン(遺作)。リストの鮮やかさと、ショパンの静謐さ、このピアニストの2つの特徴を端的に表わしたアンコール。
公演番号331
フランスのピアノトリオ、「トリオ・ヴァンダラー」の演奏会。この後、ライプチッヒ弦楽四重奏団を続けて聴き、やはり2つの室内楽の個性の違いを明確に聴きとることが出来た。
メンデルスゾーンの2番のトリオ、1番が有名で頻繁に演奏されるが2番は珍しい。メンテールスゾーンらしい、憂愁さに満ちた旋律、変化に富んだ楽想と、充実した作品。
トリオヴェンダラーの演奏は情熱的で、前へ前へと進もうとする推進力に溢れていた。シューマンの2番のピアノトリオも熱い感情に満ちた演奏。音質はフランスらしく派手なのだが、表現力の強さ、熱さに圧倒される。
公演番号322
新鋭のピアニスト、シャマユとライプツィッヒ弦楽四重奏団による、シューマンの名作「ピアノ五重奏曲」に期待
この演奏会の曲目解説チラシ、裏面の記載のシューマンの作品名が全く違っている。校正ミスだろうが、みっともない事である。放送でも訂正が無かった。
最初にメンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第4番。トリオヴァンダラーの熱い演奏の後だけに、最初の音質の落ち着いていることに驚く。ホールの大きさの違いも関係しているのだろうが、実に深々と落ち着いている。ラテン気質とジャーマン気質の相違であろうか。音楽の高揚も、直線的な高揚でなく、ゆったりと、幅広く高揚していく。直観的で熱い演奏と、思索的で深い演奏とでも、その相違を例えることができようか。
さて、シューマンのピアノ五重奏曲、ピアノの新鋭シャマユ、新鮮な演奏。色合いの異なる四重奏団の中に入っても沈没することなく、若々しく歌いあげる。1楽章の堂々たる出だしから、4楽章の溌剌とした感情まで、この作品の各楽章の個性の相違を明確に描き出した演奏。ピアノ、弦楽四重奏ともピタリと意気の合った心地よいシューマン。名演だった。
公演番号323
ジャスピアニストの大御所、小曽根真とアナ・マリア・ヨペツクによるデュオ。
このコンビでCDも出しているようである。
最初に小曽根の即興演奏で、ショパンが数曲。ショパンの素材を使っているが、総ては小曽根の世界。小曽根のショパンへの心象風景とでも言えようか。ショパンも即興演奏をしたことがあるだろうから、ある意味現代のしによみがえつたショパンとでも言えるだろうか。張りつめた緊張感に満ち満ちた音楽空間。
後半が、ヨベックとのデュオ。ショパンの作品を編曲した歌曲というが、むしろ、私にはポルトガルのファドのような、民族的なフォークの匂いが強く感じられた。最後の作品など、足を踏みならし、ピアノに強いリズムを要求しながら、髪を振り乱して歌う様は、将にファドを思い起こさせた。それにしても、この二人のコンビ、鬼気迫る演奏であった。
公演番号323
ヴァイオリンのパスキエ、ピアノのエル・バシャという二人の大家と、井上道義・OEKによる協奏曲。
エル・バシャのショパン、フランスのショパンの伝統を感じさせる、洒落て上品なショパン。
キラキラと輝く音は、将にフランスのショパン。
パスキエは大御所の演奏のメンデルスゾーン。音があでやか、そしてどっしりとした存在感。音楽を細工することなく、正面から堂々と歌い上げるのは将に大家の風格。堂々たるメンコンだった。
公演番号314
通常プログラムの最後はパリ管弦楽団とピアノ、ジャン=フレデリック・ヌーブルジェによるコンサート。
メンデルスゾーンの「イタリア交響曲」。指揮者スウェンセンの個性もあるのだろうが、華麗で激しいメンデルスゾーン。
井上・OEKの堅固な構築感と対照的な自由奔放さ。オーケストラと指揮者の個性がこの様に異なる世界を作り上げることに改めてびっくりである。オーケストラを追い立てていくような激しさ、オーケストラの音質も明るく華麗。OEKの落ち着いた、柔らかい音質とは対照的。
ピアノのヌーブルジュによるシューマンの協奏曲。やはり、情熱に満ち満ちた激しいシューマン。
クロージンクコンサート
昨年と異なり、今年は閉めのコンサートが交流ホールで行われた。小曽根真、エンゲル、エル・バシャと井上道義・OEKによるコンサートで2010年ラフォール・ジュルネ金沢は締めくくられた。エル・バシャのショパンの「アンダンテ」の部分の息をのむような緊張感と美しさに、引きこまれた。
最後に、ルネ・マルタンが挨拶。来年は「ウィーンのシューベルト」をテーマとし、シューヘルトとその周辺の作曲家を取り上げるとのこと。
今年も大成功に終わった様子の、ラフォール・ジュルネ金沢、3年を経て音楽祭として定着してきたことは嬉しいことだ。
|
公演番号 |
演 奏 者
|
作 品
|
|
212 |
指揮山田和樹
ピアノ.ルイス・フェルナンドーベレス
管弦楽オーケストラ・アンサンブル金沢 |
メンデルスゾーン.「真夏の夜の夢』よりノクターン
メンデルスゾーン:序曲「美しいメルジーネの物語Jop.32
メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第2番ニ短調op、40 |
|
222 |
ヴァイオリン西海和江
ピアノ鶴見彩
IMA弦楽アンサンブル |
ショパン(サラサーテ編曲)ノクターン変ホ長調op.9-2
メンデルスゾーン:「無言歌集」より春の歌
メンデルスゾーンハ重奏曲変ホ長調op20 |
|
233 |
ヒアノ若林顕
ピアノ菊池洋子 |
シューマン:東洋の絵「6つの即興曲Jop,66
メンデルスゾーン華麗なるアレグロイ長調op.92リスト、
ハンガリー狂詩曲第2番(4手版)
ショバンムーアの民謡風な歌による変奏曲ニ長調 |
|
223 |
能舞:観世銕之丞
ピアノ:鶴見彩
語り:若村麻由美
作・解説:ヤドヴィガM.ロドヴィツチ |
新作能「調律師-ショバンの能」 |
|
214 |
指揮・井上道義
管弦楽オーケストラ・アンサンブル金沢 |
メンデルスゾーン.序曲「フィンガルの洞窟Jop.26
メンデルスゾーン:交響曲第3番イ短調op、56「スコットラ
ンド」 |
|
235 |
ピアノルイス・フェルナンド・ベレス |
ショバン,バラード第1番ト短調op.23
ワルツ変ニ長調op,70-3
2つのノクターンop.272つのノクターンop.48
ワルツホ短調KKlva-15
スケルツオ第3番嬰ハ短調op、39 |
|
225 |
ピアノフラメナ・マンゴーヴァ |
シューマン.フモレスケ変ロ長調op.20
ショバン練習曲嬰ハ短調op.25-7
リスト:巡礼の年第2年「イタリア」よりペトラルカのソネッ
ト第104番
リスドメフィスト・ワルツ第1番 |
|
331 |
トリオーヴァンダラー |
メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第2番ハ短調op.66
シューマンビアノ三重奏曲へ長調op,80 |
|
322 |
ヒアノベルトラン・シャマユ
ライフツィヒ弦楽四重奏団 |
メンデルスゾーン・弦楽四重夷曲第4番変ホ長調op.
44・2
シューマン.ピアノ五重奏曲変ホ長調op.44 |
|
323 |
歌アナ・マリア・ョベック
ピアノ小曽根真 |
ショバン(ヨペック編曲):ドウムカ(あるべきものなく)
ショパン(ヨペック編曲)「マズルカ嬰ハ短調op.6-2」によ
るポーランド風歌曲
ショバンの作品に基づく即興演奏 |
|
313 |
指揮井上道義
ヴァイオリンレジス・パスキエ
ヒアノアプデル・ラーマン・エル=パシャ
管弦楽オーケストラ・アンサンブル金沢 |
ショパン:演奏会用ロンドヘ長調op、14「ケラコヴィアクJ
メンデルスゾーン.ヴァイオリン協奏曲ホ短調op.64 |
|
334 |
ライフツィヒ弦楽四重奏団 |
メンデルスゾーン・弦楽四重奏曲第2番イ短諌op.13
シューマン弦楽四重奏曲第1番イ短調op.41・1 |
|
314 |
指揮ジョセフ・スウェンセンヒアノジャン=フレデ
リック・ヌーブルジェ
管弦楽パリ室内管弦楽団 |
メンデルスゾーン・交響曲第4番イ長調op、90「イタリア」
シューマン、ピアノ協奏曲イ短調op、54 |
|
指揮井上道義
ヒアノ小曽根 真
アプデル・ラーマン・エル=パシャ
ブリジット・エンゲラー
管弦楽オーケストラ・アンサンブル金沢 |
①小曽根 真(ピアノ) ショパンの主題による即興」
②井上 道義(指揮)
ブリジット・エンゲラー(ピアノ)
オーケストラ・アンサンブル金沢
ショパン:モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」のお手をどう
ぞ」による変奏曲
③アブデル・ラーマン・エル=バシャ(ピアノ)
オーケストラ・アンサンブル金沢
ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネ
ーズ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ショスタコーヴィッチ 弦楽四重奏曲全曲演奏会 最終回
2010年4月20日 北日本新聞ホール
大澤 明弦楽四重奏団
第一ヴァイオリン 松井 直
第二ヴァイオリン 上島 淳子
ヴィオラ 石黒 靖典
チェロ 大澤 明 |
|
5年前から開始された、富山でのショスコーヴィッチの弦楽四重奏曲の全曲演奏会、今夜でいよいよ完結である。
地方都市でのこの様な試みは、恐らく前代未聞であろうし、商業ベースで考えれば、絶対に実行しないだろうと思われる企画。それを実行した岩瀬の方々を中心とした実行委員会、そして意欲に満ちた大澤明さんを始めとしたOEKのメンバーに大いに感謝である。しかしながら、毎回ホールの8割ほどを占める聴衆が集まったこと、これも又驚き。以前よりも注目を浴びてきたショスタコーヴィッチといえども、いわゆる渋い作品の多い弦楽四重奏曲のみの連続演奏会にこれだけの富山の聴衆が集まったという事、これも事件であろう。そしてショスタコーヴィッチの真実の音楽を、集まった多くの熱心な聴衆が、再体験できたということも、大変な出来事であった。
さて、この日は6番、9番、そして最後の15番、いずれも聴く方も、演奏者にとっても、大変な緊張感をもたらす作品ばかり。
6番の第3楽章のパッサカーリア、9番の第4楽章の変奏曲、そして最後の15番と、ショスタコーヴィッチの祈りにも似た、悲壮な感情の表出、それをこの日は一番、改めて感じさせてくれた。実行委員会の犬島肇氏が当日のプログラムに書いていた、「彼は、悲歌を歌い、人間の悲しみに側鉛を深々と降ろし、私たちの心の深奥に肉薄する。そして、言語に絶する人間悲劇と不条理の悲しさに到達している(以下略)」との指摘、それを将にこれらの楽章に体験することができた。
6番は作曲意欲の旺盛な時代に作られた作品らしく、ショスタコーヴィッチの構成上、技巧上のあらゆる要素が詰まっている充実した作品。総ての楽章の終わりが決まった楽想で締めくくられるのも印象的。まるで、「はい、ここで物語は終わりです。」と念を押しているような面白さ。1楽章の、どこか、第7交響曲の有名な第1楽章を想起させるような動機も印象的。第9番、ここでもショスタコーヴィッチは特長である饒舌な語り、疾走するような激しさ、そして深い沈潜など、多様な面を様々に表出。しかし、6番も9番もその中心は、先述した6番の3楽章、9番の4楽章の、悲劇的な色彩を帯びた楽章を中心として構成されているように感じた。
最後の15番、これは実に静けさに満ちた不可解な世界。ここでも5楽章に「葬送行進曲」の様な悲壮を引きづるような楽想を持ってきており、全楽章の静けさの中で、だだ一つの激しい感情の沸騰を見せている。
大澤明弦楽四重奏団の演奏、ただただ見事なものであった。
緻密なアンサンブルとか、調和のとれた美しいハーモニーとか、そのような点から聴けば、他に優れた四重奏団はいくらでもあるだろう。
しかし、ショスタコーヴイチの弦楽四重奏曲の解釈に向けたひたむきな情熱が、この楽団には溢れている。これも、プログラムで第2ヴァイオリンの上島淳子氏が述べている。「自分のすぐ近くにある闇、絶望、怒り、憤り、祈り、そして希望。今回の演奏会に向けて、四人で様々な事を話し合いながら音を創っていきました。作曲家と演奏家、そして聴いて下さる方の人生の機微が交わる今宵、四次元の世界が広がるのかもしれません。」という言葉、これが今回の連続演奏会の総てを語っているように思える。
「音楽を創造し、演奏する。」という作業は、その人の人生を語り、そして聴衆に語りかけるもの。それが、その思いが切実であれば、作品は一層の輝きを持って迫ってくる。そのことを彼らは見事に証明してくれた。
ショスタコーヴィッチの描いた世界をどの様に解釈し表現するか、その困難さに挑戦し、そして実現してくれた。
15番第5楽章のヴィオラとチェロの唸るような図太いうめき声に思わず、ぞっとしてしまう。その様な瞬間がこの日の演奏には随所に聴かれた。
各パートが楽譜の意味するところを雄弁に語ろうとしているのである。
15番の最終楽章、将に「命つき、絶える。」という、遠くに消えていくような弦のさざめき。ショスタコーヴィッは死の前年に何を思ったのだろうか?
最後の挨拶で、主宰の大澤明氏が、「次は、バルトーク、あるいはシューベルト、色々な事を考えています。」と語っていた。それを実に楽しみにしたい、今宵の音楽会であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第279回定期演奏会
2010年4月4日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 現田 茂夫
ソプラノ 佐藤 しのぶ
アルト 井戸 靖子 |
|
4月の定期は、佐藤しのぶを迎えてのオペラアリアを中心としたプログラム。後半に、この日のメーンプロ、プッチーニの「蝶々夫人」抜粋があるが、所用で前半のみの鑑賞。
指揮は佐藤しのぶの夫君、現田茂夫、そしてアルトに井戸靖子が加わった。
前半では、オーケストラ曲が2曲、プッチーニの交響的奇想曲、そして「菊」
いずれも、演奏される機会の少ない作品。最も「菊」は過去、アンコールピースとしてなど数回OEKで演奏された記憶があるが。
現田茂夫の指揮は、オペラ伴奏らしい、雰囲気と劇的表現に長けた指揮ぶり。
「交響的奇想曲」はプツチーニのミラノ音楽院の卒業作品と言うが、後年のプッチーニのオペラを既に思わせる甘美でドラマティックな作品。
「菊」は弦楽器のみでの演奏だが、厚みのある弦楽合奏が印象的。
メーンの佐藤しのぶは前半では2曲のみ。チレア「アドリアーナ・ルクブルール」から「私は芸術の召使です。」とヴェルディーの「トロヴァトーレ」から「炎は燃えて」。
変わらぬ透明な美声がホール全体に響き、心地よい空間が作られる。ただ、「炎は燃えて」では、歌唱がやや平凡、もう少し劇的なメリハリが欲しい気もした。
アルトの井戸靖子は「アドリアーナ・ルクブルール」から「苦い喜び、甘い苦しみ。」とヴェルディーの「トロヴァトーレ」から「穏やかな夜には」。しっかりとしたアルトらしい硬質の声であるが、もう少し声の厚みが欲しい気もする。
前半はソプラノのアリアが2曲、アルトのアリアが2曲という事で、少々寂しい構成。
後半を聴くことが出来なかったので何とも言えないが、もう少し多く歌ってほしかったし、変化にもやや乏しい舞台。省力化を図りすぎた演奏会という印象。
さて、この日音楽堂前では、正装の楽団員がチラシ配り。何事かと思うと、定年制についての楽団としてのアピール。この様な問題が発生していることは初めて認識。素晴らしい音楽を創造しようとする楽団員、又経営的にそれを支える財団側、いずれも譲れないところがあるのだろうが、共にここまで金沢での音楽文化の発展に努力してきた両者。角突き合わせるのでなく、大人の知恵を出し合って良い方向の解決を図ってほしいというのが、一人の定期会員としての門外漢の切望である。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラの日コンサート
2010年3月31日 石川県立音楽堂コントホール
石川県ジュニアオーケストラ
指揮 鈴木織衛
金沢大学フィルハーモニー管弦楽団
指揮 長尾枝里子
オーケストラ・アンサンブル金沢
指揮 山田 和樹 |
|
3月31日は、「耳に良い日」ということで、数年前から「オーケストラの日」と定められ、オーケストラの各根拠地で様々なコンサートが開催されている。
金沢では、OEKを中心に、地元で活躍のオーケストラとして、ジュニアオーケストラと金大フィルハーモニーを加えての賑やかな演奏会。
ジュニアオーケストラの評判は聴いていたが、耳にしたことはなく、金大フィルは母校のオケ、そしてOEKは話題の山田和樹の指揮ということで、興味津津で、足を運んだ。
ジュニアオーケストラ、指揮の鈴木織衛の指導もあり、噂にたがわす、調和のとれたアンサンブルを聴かせてくれた。小学生から高校生まで、今日はその中にOEKのメンバーもちらほらと見えたが、メンバーは60名程とのこと。ドヴォルザークのスラブ舞曲8番、リズムの複雑な作品だが、きっちりしたリズム感があり、弦、管、打と各楽器のアンサンブルも正確。鈴木織衛の10年間の指導の賜物と感じた。OEKのメンバーも指導に入っているようであり、金沢にプロのオーケストラがあることが着実に音楽文化の底を厚くしていることを痛感した。
金大フィルは、現在120名ほどの部員とのこと。昨今、全国の大学のオーケストラの実力の高さが話題になっているが、なるほど私たちの在学時代とはレベルが違うようだ。
エルガーの行進曲「威風堂々」、J・シュトラウスの「ラデイツキー行進曲」の2曲の演奏。
アンサンブルにやや粗雑さはあるものの、堂々たる演奏。特に女性の学生指揮者の、的確な指揮ぶりにはびっくり。派手なパフォーマンスは無いのだが、きちんとタクトを振り、そのタクトの動き通りに音が生まれてくるのは見ていて快感。専門はヴァイオリンとのことだが、頼もしい指揮者である。
さて、後半は話題の指揮者、山田和樹の登場。ブザンソン指揮者コンクール優勝という、輝かしい経歴を引っ提げての登場。OEKには、2006年、故岩城宏之監督の代役として登場、残念ながらその演奏は所用で聴けなかったが、その後もOEKとは何度か共演している。
ブザンソン指揮者コンクールというと、古くは小沢征爾、最近は下野竜也が優勝しているが、指揮者の登竜門として名高いコンクールである。
この日はベートーヴェンの7番。
目を引いたのが配置、弦が、第一Vn、第二Vn、チェロ、ビオラという配置。珍しい並べ方。そして、ティンパニーかバロックティンパニーを使用。
演奏のスタイルは、最近主流のピリオド奏法に近い。テンポは早め、前へ前へと進む推進力を大切にしながら、時に動かす。典型的な例が、第3楽章スケルツォの中間部、かなりテンポを落とし、スケール大きく金管を鳴らす。ティンパニーがバロックティンパニーのため、その音の特質を最大限生かそうとして、かなり強烈に叩かせる。
古典的なアプローチながら、随所に仕掛けを施している。現時点では、その仕掛けが、やや恣意的に聴こえ、指揮者のアプローチが見え透いていて、乱暴に聴こえる部分もあり、ベートーヴェンの音楽の豊かさ、雄大さが損なわれている感もある。
一気呵成の激しさはベートーヴェンの一面ではあるのだが、反面一本調子となりがちで、更に細部の歌の豊かさ、抑揚に満ちたドラマ、それらが加われば、全体としての統一したベートーヴェン像が浮かび上がるはずなのだが。
しかし、若さゆえの推進力と、激しさは十分であり、聴く者を、その意味で興奮に導く。
オーケストラの統率力は抜群であり、一糸乱れぬアンサンブルは見事。
今後が楽しみな指揮者ではある。
2部後半は、3つのオーケストラの合同演奏でチャイコフスキーの「白鳥の湖」から「情景とチャルダーシュ」。そして、アンコールにメンデルスゾーンの「真夏の夜の夢・結婚行進曲」
200名近いオーケストラの迫力は圧巻。 |
|
|
|
|
|
|
|
小菅優&ラディク・バボラーク デュオリサイタル
2010年3月24日 入善コスモホール |
|
入善コスモホールのクラシックシリーズも数年前に比べると回数が少なくなり、寂しい気もするが、灯を絶やさないでほしいと思う。このホールでの数々のクラシックのコンサートは、その内容、聴衆の素晴らしさ等からいっても、富山県の音楽コンサートの歴史の中でひときわ輝きを放っている。アルゲリッチ、ベルク四重奏団、ギドン・クレメル、マイスキー、デュトワ等々、数えきれない程の音楽家が、この600名足らずの田舎町のホールでリサイタルを行ってきている。その意味で驚異的でさえあり、入善町の担当者の努力は大変なものであったと思う。
今年は庄司沙矢香・ジャンリカ・カシオーリのリサイタル、ダン・タイソンのリサイタル等が予定されているようだ。
さて、今日はピアノの小菅優、ホルンのラディク・バボラークという変わった組み合わせのリサイタル。ホルンのリサイタルでピアノ伴奏がつくのは当然だが、今日のコンサートはそうではなくて、主役が二つの楽器というリサイタル。
小菅優は得意のショパンを演奏、ラディク・バボラークはR・シュトラウス、F・シュトラウス、シューマンの作品を演奏。
プログラムは前半-R・シュトラウス、「前奏曲、主題と変奏」、F・シュトラウス、「ノクターン」「ファンタジー」、以上がホルンとピアノ、ピアノの小菅優がショパン、エチュード3番「別れの曲」12番「革命」、プレリュード15番「雨だれ」16番。後半-ショパン、ピアノソナタ第2番、そして最後ホルンとピアノで、シューマン「アダージョとアレグロ」というもの。
ラディク・バボラークのホルンは圧巻。R・シュトラウスの出だしではやや不安定さと、リズムの揺れが聴こえたが、徐々に調子を上げてくると、自由自在。難しいホルンという楽器から、自由奔放、色彩豊かな音がどんどん飛び出してくる。
F・シュトラウスのノクターンの柔らかく伸びやかな音色、ファンタジーの早いパッセージでの超絶的な技巧。時にはブラスの輝かしい高温、時には木管の様な柔らかいピアニシモ。いつ、息継ぎをしているかと思うようなブレス。そして、小気味の良いタンキング。
まるで、自らが歌っているように楽器を操っていた。であるから、音楽の流れが極めて自然で、爽快。ゆっくりした部分、早い部分ともリズム感が狂うことなく、流麗な流れを作っていく。これは、楽譜を読み込む力、そして読み込んだ楽譜を的確に表現する技術、更にそれを自らの個性として表現する感性、それらが合わさっていないと出来ない技。
ピアノの小菅優の伴奏も見事。単なるつけている伴奏でなく、ホルンの歌わせ方にあわせながら、自らの音楽を奏でていく。ホルンに対抗して十分に主張しているピアノであった。
そのような意味で、最後のシューマンは、ホルンとピアノが自己主張を示しながらも、統一した音楽を作り上げ、シューマンの夢幻的な世界を描き出していた。
さて、もう一つの注目、小菅優のショパン。エチュード3番「別れの曲」の出だしのフレーズから、個性ある世界が現れていた。テンポなのか、音色なのか、いやそれらが総てあわさった小菅の世界なのか。感傷的でない、といって泥臭くもない、繊細でない、不思議な落ち着きと、優しい素朴さを湛えた音楽。ショパンの演奏で多くなされる、装飾的な変化など、極めて少なく、それでいてショパンの音楽の、悲しさ、せつなさの本質が表れている。そして12番「革命」、プレリュード16番の圧倒的な迫力。ショパンの静と動を、わざとらしい演出やけれんみを避けながら、堂々と描き出していく。個性豊かなピアニストである。
ソナタ2番。第一楽章の堂々たる構築、有名な葬送行進曲の虚飾を排した旋律の歌わせ方、中間部のほつとするような印象的な明るさ、そして最終楽章の一気呵成な流れ。
このソナタの個性的な魅力を十分に聴くことが出来た。
ポーランド的な素朴さでもなく、フランス風の繊細さとも異なり、気品あるとでも言えるような静けさ、スケールの大きな作り方であり、小菅独特なショパンの世界を聴くことができた。
残念なのは、このような名手二人の演奏会では、どちらの印象も強烈で、もう少しどちらも聴きたいという贅沢な欲が出てくること。
やはり、どたらかに絞って、たっぷりと聴かせてくれた方が、聴衆としては満足度が高いのではなかろうか?
アンコールもホルン中心で3曲、小菅のショパンのアンコールも聴きたかったのだが。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第278回定期演奏会
2010年3月21日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
トランペット ルベン・シメオ
チェロ ルドヴィート・カンタ
ピアノ 小曽根真(飛び入り) |
|
今日の定期のプログラムは、なるほど井上監督と思わせる、多彩で刺激的なもの。
ハイドンの合奏協奏曲第12番に始まり、タルティーニのトランペット協奏曲、アウエル・バッハ「フラジャイル・ソリテュード(弦楽四重奏とオーケストラのための)」、後半がハイドン「トランペット協奏曲」、グルダ「チェロとブラス・オーケストラのための協奏曲」というもの。古典と現代の組み合わせ、更に様々な協奏曲の組み合わせ、極めて特異で刺激に満ちた演奏会となった。
最初のヘンデル「合奏協奏曲17番」。2つのヴァイオリンとチェロそして弦楽合奏の為の協奏曲。OEKの編成に最もあった作品ともいえる。
柔らかい弦の響き、端正な造形、気品に満ちた古典的な演奏。OEKの合奏能力の高さを示した演奏となっていた。柔らかぶ厚い弦の響きは、このオーケストラの円熟を聴く様であった。
次のタルティーニと後半のハイドンのトランペット協奏曲の独奏者、ルベン・シメオ。なんと、18歳の少年とのこと。技巧の冴え、伸びやかな音質、そして輝かしい高温、良く歌うカンタービレなどトランペットという楽器の美点を余すところなく聴かせてくれた。もう少し柔らかい音色があれば、より万全ではあったが。
さて、前半の最後はアウエル・バッハ。2004年からのシーズンで、OEKのコンポーザー・イン・レジデンスであった作曲家。今回はかなり時間的にも長い30分程の大作の登場。
弦楽四重奏が前面に位置取り、それを取り囲むようにオーケストラが配置されている。弦楽四重奏とオーケストラの為の協奏曲という作り方か。
楽器は多彩、パーカッションにチェレスタまで加わっている。であるからして、響きも透明でありながら、多彩。中間部の高揚を除いて、静かなカルテットとオーケストラの対話が続く。緊張の長い時間が続くので、やや冗長なきらいもある。もう少し、切りつめてもと思わぬでもない。前回聴いた、ヴァイオリン協奏曲等では、かなり旋律性の明確な、耳に心地よいものがあったが、今回はそれよりもやや前衛に踏み込んできたような響きが聴かれる。しかし、その底に流れる独特な情感はこの作曲家独特なものを感じる。最後の消え入るような、アビゲイル・ヤングのヴァイオリンの響きは、祈りであろうか。
さて、最後のグルダのチェロ協奏曲。
「ブラスオーケストラとチェロのための」という題名通り、ブラスバンドとチェロのための競演。そこに、ギター、コントラバスが加わる。
いやはや、奇妙奇天烈な音楽で、グルダの高笑いが聴こえてくるよう。
グルダという、ピアニスト、存命中の演奏でも特異な世界を展開し、モーツァルトの協奏曲が、ブルースの様に聴こえたことなどが思い出されるが、この作品は将にやりたい放題。
「どうだ、面白いだろう。」という、グルダの挑戦を聴く様でもある。
その演奏の方も、刺激的、チェロに電気的拡声装置?をつけ、エレキチェロとでもいえるような趣。更に、オルガン室の上に、ミラーボールをつけ、照明をあてると、ホール全体が、ディスコハウスの様な趣となる。
ビートの聴いた部分では、そのミラーボールが青や赤の奇妙な輝きの光を放つ。そして、2楽章の牧歌では一転して、柔らかい懐かしい歌が聴こえる。そう、「魔弾の射手」の有名なホルンのソロの歌を想起させるような。その時はミラーボールの回転は止まり、ホール天井にに森のささやきの様な影絵が映し出される。
チェロのカンタも、正装ではなく、ジーパン姿というリラックスモード。
第3楽章のカティンツァはその名の通り、チェロの独奏。すさまじいエレキチェロの噴出。技巧的にも難度が高いと思われるが、見事。このカディンツァは果たしてグルダの作曲なのか、それとも独奏者の即興に任せているのだろうか?
ウィーン風でありながら、どこかひねくれているメヌエットに続いて、最後はなんとマーチ。ホルンは朝顔を上向きにして、吹きまくり、将に狂乱のマーチである。そこに、チェロが割って入り、ごちゃまぜ状態。
何とも不思議な音楽ではあったが、楽しませてくれたのも事実。井上マエストロの、「音楽は楽しくなくちゃ」を地で行ったような演奏。
さて、アンコール。これがハップニング。客席に、ジャズピアニストの大御所、小曽根真がおり、それを井上マエストロが舞台に引っ張り上げ、トランペットのシメオとチェロのカンタと競演させ、即興演奏をするという趣向。思わぬプレゼントに聴衆も大喜び。
グルダのテーマによる即興のようだったが、ほぼ小曽根の独壇場。トランペットもチェロもやや引き気味だったのが残念。そのビートの聴いたリズムにあわせ、井上マエストロが得意のダンスを披露するというおまけつき。
2時間半以上の長い演奏会となったが、近来にない個性的な演奏会であったことは事実。 |
|
|
|
|
|
|
|
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニックオーケストラ演奏会
2010,年3月1日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 サカリ・オラモ
ピアノ アリス=沙良・オット |
|
サカリ・オラモは3年前にフィンランド放送交響楽団と、ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニックオーケストラは7年前にアラン・ギルバードとそれぞれ聴いた記録があり、更に面白いことにその両方の演奏会でブラームスの2番が演奏されていた。
今回は、組み合わせがサカリ・オラモとロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニックオーケストラ、そして独奏者が金沢ではお馴染みのアリス=沙良・オット。
プログラムはシベリウスの交響詩「エン・サガ」、チャイコフスキーのピアノ協奏曲、そしてドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」
北欧のオーケストラという点では、フィンランド放送交響楽団もロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニックオーケストラも同様、そしてサカリ・オラモということで、響きが非常に似通っている。透明でありながら、力強い、特に低音、金管の響きは分厚い、そして特徴的である弦楽器の柔らかい響き、個性のあるオーケストラである。外国のオーケストラを聴くたびに、日本のオーケストラと比較し、そのローカルな個性の強さに魅了される。日本のオーケストラは技術的には世界のトップに位置しているのだろうが、どうもオーケストラとしての個性の薄さを感じてしまう。やはり、日本の西欧音楽受容の歴史の浅さであろうか。
さて、今日の編成は18型で、管楽器もダブル、舞台いっぱいの大編成。
最初のシベリウス、最初の響きから、見も知らないフィンランドの森やフィヨルドの光景が想像できる。そして魅力的なフィンランドの民謡風の調べ、分厚く盛り上がり、そして潮が引くような弱音。木管やビオラの室内楽的な静けさ。強弱のコントラストが実に鮮やか。後半のドヴォルザークでもそうだが、音楽の自然な流れを、サカリ・オラモは巧みに描き出す。細部まで入念な彫刻をほどこしながら、生まれてくる音楽は自然な流れを保っている。
今日の白眉は、チャイコフスキーのアリス=沙良・オット。最初に聴いたのは3年前、ラフマニノフ2番の協奏曲、18歳の時だった。そして昨年のOEKニューイヤーコンサートでのベートーヴェンの5番「皇帝」、同じ1月には見事なリストの演奏会もあった。
大きな作品をとりあげながら、それに臆することなく作品に対峙する。
そして今回。このピアニスト、聴くたびに進化していることを実感する、鮮やかなテクニック、そしてみずみずしい抒情性、豪快な弾きっぷりなど、この協奏曲の面白さを存分に引き出していた。歌うところはたっぷりと歌わせ、早いパッセージも的確なタッチの音色、そしてオーケストラとぶつかりあうような豪快さ。どの部分をとっても、今まで聴きあきてきたともいえるこの協奏曲が新鮮な面白さを持って迫ってくる。
サカリ・オラモの指揮も見事。オーケストラの歌う部分、ピアノに寄り添う部分、ピアノとぶつかり合う部分など、丁寧に描き分けながら、滔々たる全体の流れを作っていく。
第2楽章の主題の歌わせ方など、独特なところがありながら、それが自然に聴こえる。
アリス=沙良・オットのアンコールはショパンの遺作のワルツ。過度な感傷に陥らず、それでいて十分にショパンの歌が聞こえる、ある意味節度に満ちた抒情性。ショパンの音楽の気品のある抒情性ともいえる部分を、この若さで表現するとは、という感慨すら覚える。
次にはどんな音楽を聴かせてくれるのかという、将来への期待が大いにふくらむピアニスト。
後半のドヴォルザークの9番の交響曲。あまりにも有名な交響曲ではあるが、サカリ・オラモは新しい作品を聴くような新鮮さを持って演奏してくれた。
第一楽章提示部のそれぞれの主題の描き分け方、提示部の繰り返しの際の微妙な間合い、第2楽章の有名な主題の歌わせ方、それに続く次の主題の個性的なアプローチなど、そこ、かしこにおやっと感じさせる仕掛けがありながら、それが嫌味にならず、成程このような作品だったのかと思わせる自然さ。
第2楽章のチェロの独奏のしみじみとした音色。ヴァイオリンの弱音の驚くべき繊細さ。そこかしこに、魅力的な部分がちりばめられ、それが有機的に結び付き、全体が形づくられていく、交響曲の面白さ。非凡な指揮者である。
いつも思っている、演奏者は作曲家の忠実な再現者であるべきということを改めて感じさせてくれた演奏会。
帰りの時間の関係でアンコールを聴くことができなかったのが心残り。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第276回定期演奏会
2010年2月25日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ヴァシリス・クリストプーロス
ヴァイオリン 漆原 朝子 |
|
今回の定期は、ギリシャの新鋭、ヴァシリス・クリストプーロスという指揮者を迎え、ヴァイオリンを漆原朝子という、弦楽器の魅力をたっぷりと聴かせようという趣向。
プログラムは、最初に極めて聴くことの珍しいギリシャの現代作曲家のスカルタッコスの「弦楽のための5つのギリシャ舞曲」、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番k.219「トルコ風」、後半がシューベルトの交響曲第3番。OEKの編成にびたりとあったプログラミング。
クリストプーロスはまだ30半ばの若さであるが、既にドイツの名門オケ、南西ドイツ交響楽団の音楽監督を務める程の実力者。6月にはそのオーケストラを率い金沢に再び訪れ、庄司沙矢香と共演の予定。
この日の編成はOEKの標準的な編成だが、配置はコンドラバスを左側に置いた対向配置で、ティンパニーもバロックティンパニーを使用するという古典的な編成。又、この日プレコンサートで初めて韓国のウァイオリン、ビオラろチェロの各奏者が加わって演奏し、OEKに韓国奏者が加わっていたことに初めて気がつかされた。プレコンサートでは実に勢いのある演奏が聴かれ、韓国パワーを改めて実感。
さて、最初のギリシャのスカルタッコスの作品。現代音楽とは思えない、素朴なギリシャ風舞曲集。弦楽合奏のみの演奏で、そこかしこに魅力的なフレーズが聴かれる小品。大きな特徴も無い作品だが、実に素朴で温かい。
モーツァルト、ここでは漆原朝子のヴァイオリンに魅せられる。磨き抜かれた美音ではないが、奏者の心の奥から響くような暖かく柔らかい音。そして、決して形式感を崩さないようにと、モーツァルトの音楽に寄り添う謙虚さ。モーツァルトの優しく暖かい音楽がふつふつとわいてくる。これは、見事な円熟である。終楽章のトルコ風の興奮が収まり、初めの優しさが戻り、そしてふっと消えていく終結部分、いつまでもそこにモーツァルトの音楽が残っているような終わり方、この協奏曲がこういう風に終わるのだということをしっかりと印象に刻みつけてくれた。
アンコールにバッハのパルテイ-タ1番から。昨日樫本大進で聴いたばかりの曲。ここでは、バッハの優しさと素朴さ暖かさがにじみ出ていた。やはり、これも音楽に対する謙虚さであろう。作曲家の再現者としての演奏家という意識。
さて、後半はシューベルトの交響曲第3番。この日のプロは本当につつましやかなプロ。大曲があるわけでなく、編成もごく小さい。しかし、しみじみと音楽を聴く喜びを感じさせてくれた。
シューベルトの初期の交響曲は、実に新鮮でみずみずしい。ベートーヴェンに憧れ、その作風に近づこうとしたシューベルトであるが、構成感はともかく、底に流れているものはシューベルトそのものであり、他の誰でもない歌が溢れている。
クリストプーロスはこの初期のシューベルトのみずみずしさを端正に清潔に表現していた。惜しむらくは、もう少し柔らかさ、遊びの要素が加わっていたらと思うが、それは現時点での無いものねだりか。ここでは、OEKのオーボエを始めとする木管群が、みずみずしい歌を奏でていた。
アンコールにロッシーニの「絹のはしご」序曲。躍動感に満ちた楽しい演奏。ロッシーニの音楽の前へ前へと進む興奮、そして木管のソロの美しい歌、総てが備わった演奏。ロツシーニクレッシェンドも、大げさでなく心地よい。これは見事なロッシーニ。 |
|
|
|
|
|
|
|
樫本大進 無伴奏ヴァイオリンリサイタル
2010年 2月24日 富山県民会館ホール |
|
樫本大進を聴くのは、2005年入善、2008年金沢、そして今回と3回目。天才少年と言われたヴァイオリニストも30才を超え、昨年はベルリンフィルのコンサートマスター就任という大きなニュースもあり、いよいよ円熟の時期を迎えるはずである。
5年前の入善では、その若々しい、しかし構成感のきっちりとした演奏なに魅せられた。
しかし、3年前の金沢では、ベートーヴェンを演奏しながら、何か表現方法の迷いというものを感じたのも率直なところ。
今回は、バッハの無伴奏ソナタとパルティータという超難曲を携えてのリサイタル。東京では、1日で全曲を演奏するという離れ業を行うようである。富山では、当初のパルティータ1番、ソナタ1番、パルティータ2番というプログラムが変更となり、ソナタ第2番、パルティータ1番、パルティータ2番という様に変更となった。より充実した多彩なプログラムへの変更という意図であったろうと想像できる。そして、ソナタ第2番という大曲を聴くことができたのも収穫。
富山で総ての作品をバッハの無伴奏で行う演奏会は珍しく、私の記憶では入善でハンナ・チャンがチェロの無伴奏の演奏会を行ったくらいでなかろうか。しかし、やはりこの作品群はまとめて演奏されるべきという印象を今回の演奏会で新たにした。
さて、この日の樫本大進、彼本来の艶やかな美音と超絶的な技巧で、他の奏者と明らかに異なるバッハ像を作り上げていた。
滑らかな音の連続、そして早くたたみ掛けるようなスピード感。素朴でありながら厳しく、そして暖かいというバッハとはかなり異なる、艶麗なそしてスポーティーなバッハ像。
これは、明らかに樫本大進の現在とらえているバッハ。そして、現代的感覚に満ちたバッハ像。
有名なパルティータ2番のシャコンヌも、壮大な構築物という印象でなく、細部まで磨き抜かれた宝石の積み重ねの様な印象の演奏。巧みな技巧と美しい音を紡ぎ合わせながら、人工の美しさを誇示するような演奏。これは、奏法の用い方にもあるのだろうか。一つ一つの音をしっかりと打ち出すのでなく、滑らかな音の連続として描き出す。
好みの問題といえばそれまでだが、この日のバッハは樫本大進の凄さは伝わるが、バッハの音楽の人間的な大きさ、暖かさは、残念ながら消されてしまっていた。
印象に残るのはヴァイオリニストの確かな技巧と艶麗な音という印象。
3回目の樫本大進、残念ながら聴くたびに、表現の迷いの深みに陥っている感がある。
音楽表現とは難しいものである。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第275回定期演奏会
2010年1月24日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ヘルムート・リリング
ソプラノⅠ 佐竹由美
ソプラノⅡ 沓沢ひとみ
アルト 永島陽子
テノール 鈴木准
バス 浦野智行
合唱 オーケストラ・アンサンブル金沢合唱団
合唱指揮 佐々木正利 |
|
バッハ演奏の大家、ヘルムート・リリングを迎え、大作「ミサ曲ロ短調」の演奏という期待の定期。
これで、マタイ受難曲、ヨハネ受難曲とバッハの宗教曲の三大作品の演奏がOEKにより金沢で行われたことになる。地方都市でこのように滅多に演奏される機会のない宗教曲の大作が演奏されること自体事件であるが、ペーター・シュライヤー、ヘルムート・リリングというバッハの名演奏家により演奏されるということは、これまた画期的な音楽事件である。これも、OEKの存在あってのこと、愛好家にとっては本当に有難いこと。
演奏会前に山腰音楽堂館長から、県立音楽堂が総務省の地域創造音楽大賞を受賞との報告。
「オーケストラ・アンサンブル金沢を中心とした、地方における創造的な音楽活動に多大な貢献があった。」のが受賞の理由とのこと。
確かに、この日の演奏会もそうだが、音楽堂が出来、アンサンブル金沢の拠点としてのクラシックに限らず、ポピュラー、邦楽、民族芸能、大衆芸能と多彩な活動が一地方都市に於いて幅広く展開されていることは、目を見張るばかりであり、金沢に文化の華を咲かせようという試みは着実に根付き始めているといえるだろう。
そして、この日の演奏会も期待にたがわない名演奏。
休憩を入れ2時間30分に及ぶ大作だが、少しも弛緩することなく、バッハの世界が展開し、最後まで緊張感に満ちた音楽空間が出現していた
編成は比較的大きく、弦楽器を中心に左側にトランペット4本とティンパニ、右側にホルンとオルガン奏者(リモコンパネル)、中央奥に木管楽器という配置。
第一部「キリエ」の冒頭の木管の憂いに満ちた音色に従い、合唱が静かに厳かに響いてきたとき、既にバッハの巨大な世界が出現していた。
マタイ、ヨハネ受難曲と比較し、管楽器の活躍が著しく、合唱もフーガ、カノンと構造的な面白さに満ち、ドラマティック、色彩豊かな世界が展開する作品。
この日の演奏は、バッハが古臭く、かび臭い音楽でなく、実に人間臭く、そしてドラマティックな音楽であるかを生き生きと表現してくれた演奏。
第1部「キリエ」第6曲の、ヴァイオリンの独奏とソプラノ独唱、第10曲のオーボエ・ダモーレとアルトの独唱など、実に古典的な素朴さと、哀愁に満ちており秀逸。第7曲、第12曲の壮麗な管弦楽と合唱によるフーガの展開は、合唱団が構造的な建築物の様な音楽像を見事に歌いあげ、大きな頂点を築き上げていた。
リリングの指揮ぶりは決して大げさでなく、指揮棒は大きく振られることは無いのだが、まるで魔法のように、その指揮棒の先から豊かな表現が生み出されてくる。
第2部の「クレド」のキリスト受難の激しい怒りの表現、そして第3部「サクントゥス」の輝かしい天上の世界の表現、第4部「ベネディクトゥス」第2曲のチェロの独奏とテノールの独唱、そして最後第5曲の平安への熱い願いの表現。
どの部分も生き生きと精彩に満ち、輝きに満ちていた。
ヴァイオリン、チェロ、フルート、オーボエ等独奏楽器の歌は、独唱とぴったり寄り添い、実に優しく語りかけてくる。
そして、何よりも合唱の凄さ、フーガの部分ではくっきりと各声部を浮き上がらせ、そして重なり合いも濁らず輝かしい。リズム感も明瞭、早い畳みかけるパッセージも決して乱れず。明確。音符の持つ意味をはっきりと表現する力。OEK合唱団の実力をまざまざと見せてくれたが、指導者としての佐々木正利氏の功績大なのであろう。
各独唱者も、テノールがやや線の細さを感じさせたが、それぞれ秀逸。特にアルトの柔らかく、暖かい音色は印象深い。
「ロ短調ミサ曲」、生は勿論、CD等を含めても、全曲を通して聴いたのは今回が初めてだが、バッハの巨大なスケール、フレッシュな音楽を体験させてくれた、あっという間の2時間であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第274回定期演奏会 ニューイャーコンサート
2010年1月7日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
ソプラノ メラニー・ホリデー
テノール ズリンコ・ソチョ |
|
井上道義が音楽監督となって3回目のニューイヤーコンサート。
今年のプログラミングも多彩で刺激的。昨年はオール・ベートーヴェンでの新年の幕開けだったが、ニューイヤーコンサートを単なる年中行事にはしないぞ、というような意気込みを感じさせるコンサート。
一見、ポルカ、ワルツなど定番が入っているようで、その中にショスタコーヴイッチやチャイコフスキー、更にはバッハまで紛れ込ませ、ワルツ・ポルカもシュトラウス一家のものより、カールマン、レハール、ズッペのものも多く入れたり、一見雑多ではあるが、聴いてみると音楽の楽しみがぎっしりとつまっているプログラミング。定番のウィンナワルツ・ポルカをずらっと並べたプログラムより、ずっと音楽の楽しさがはじけていたように思える。
幕開けは新年の幕開けにふさわしい、はじけるような躍動感に満ちた、ショスタコーヴィッチの「ステージオーケストラのための組曲」から「第一ダンス」。最初から、オーケストラのパワー全開の演奏。心地よい興奮がホールを包む。
コンサートは井上マエストロの巧みなトークで進行。久しぶりのメラニー・ホリデーの登場で、シュトルツの「プラター公園は花盛り」。ウィーンのプラター公園のレトロな雰囲気を哀愁豊かに、歌も伴奏も紡ぎだす。メラニー・ホリデー、60歳を超えると思われるが、初々しい歌声は健在。ナントの辻音楽師がサックスで奏でていたというトークで始まる、ショスタコーヴィッチの「ステージオーケストラのための組曲」から「リリックワルツ」。物悲しいジンタがサックスで奏でられると、その光景が目に浮かぶよう。
ベネチアに舞台は移り、J・シュトラウスのオペレッタ「ヴェネチアの一夜」から「心から挨拶を贈ろう」、オッフェンバック「ホフマン物語」から有名な「舟歌」。テノールのズリンコ・ソチョ、しつかりとした伸びのあるテノール。その後ジーツィンスキーの「ウィーン、わが夢の町」がソプラノとテノールでしっとりと歌われる。
次が意外な「J.S.バッハ、2つのヴァイオリンのための協奏曲から2楽章」
指揮者は退場し、ウアィオリンのマイケル・ダウス、江原千絵による独奏にオーケストラが寄り添う。華やかなプログラムの中だけに、この時だけの静寂な美しさが際立つ。
二人のヴァイオリンがしっとりと美しい。
次がJ・シュトラウスの「アンネンポルカ」だが、これがユニーク。最初にゆったりと典雅にオーケストラのみで通常に演奏され、その後「ヴェネチアの一夜」の中で歌われるというものが、メラニー・ホリデーで歌われたが、同じ作品でまるで異なる音楽。よっばらいながら、コケテイッシュに歌われるポルカは実に面白い。井上マエストロも「こっちの方がずっと面白いよね。」
一部最後はJ・シュトラウス2世「こうもり」から有名な「シャンパンの歌」。華やかなエンディング、手拍子も起こり、メラニー・ホリデー、ゾリンコ・ソチョは舞台いっぱい踊りながら歌う。楽しさ満点のエンターティンメント。
第2部の最初は「常動曲」、終わり方に様々な工夫があるが、この日は指揮者が曲の繰り返しの途中退場、メラニー・ホリデーを連れて再登場、次のレハールの作品に移るという趣向。スッペの「美しいガラテア」序曲を挟んで、レハールのオペレッタ「ほほえみの国」から2曲、「ジュディッタ」から1曲が歌われる。ズッペの「美しいガラテア」序曲。華麗な響きとエスプリの効いた、気持のよい演奏。ピシッと決まっている明確な旋律が好ましい。
エンディングに近い部分で、今度はチャイコフスキーの6番悲愴から2楽章の「ワルツ」。
5拍子を明瞭に聴かせる、陰のあるワルツ。華やかなワルツ、オペレッタに囲まれて異様な空間。このあたりが、井上マエストロの隠し味か。「ワルツも色々あって、面白いよな。」というマエストロのつぶやきが聞こえるよう。
「やはり楽しい方がいいよね。」というトークで、最後はカールマンの「チャールダッシュの女王」から「踊りたい。」テノールとソプラノの楽しく華やいだエンディング。有名な「ヤイ・ママン」でもアンコールで踊り、歌いまくってほしいものと思ったが、さすがにそれはなかった。
アンコールは定番の「美しき青きドナウ」。ウィーン風な纏綿たる情緒より、きっちりとしたリズム感と構成のがっちりとした、それでいてよく歌う美しい演奏。
最後は「ラディツキーマーチ」ではなく「メリーウィドウ」からの有名な二重唱。とても、甘くせつない二重唱。
来年のニューイヤーコンサートはどんな仕掛けを見せてくれるだろうという期待を、早くも抱かせるような楽しいコンサートだった。
最後に、この日はどら焼きのお土産というサービスぶり。「言い忘れましたが、どら焼きを1500個作ったので、帰りに持って行って下さい。」というマエストロのトーク。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第272回定期演奏会
2009年11月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響
ソブラノ 森 麻季
アルト 押見 朋子
テノール 吉田 浩之
バリトン 黒田 博
合唱 大阪フィルハーモニー合唱団 |
|
年末恒例の第九、という言葉はOEKにはあてはまらない。故岩城監督の時代から、年末に第九という陳腐さを嫌い、大切な作品として意味のある取り上げ方 をしてきた、日本唯一のプロオーケストラであろう。
そのOEKが今年は初めて年末定期に第九をとりあげた。しかし、これも年末ということでなく、金聖響のベートーヴェンチクルスの最後を飾るという意味の取り上げ。
2003年から足掛け7年にわたり続けてきたOEK-金聖響の総仕上げである。これで全録音が終了したので、全曲盤のCDが近々発売されることとなるのだろう。
さて、今日の序曲は、「レオノーレ3番」。序曲としては変化に飛んだ大曲。
この日の楽器配置もいつもの金聖響独特の配置。コントラバスを左に置いた、対向配置であるが、ホルン以外の金管を極端に右に寄せた独特のもの。この日は、弦、特にコントラバスを4本に増強していた。そして、ティンパニーは当然バロックティンパニー。
実に引き締まった、余分な虚飾をすべて排除したような「レオノーレ3番」。テンポは早めで、推進力に富んでいる。そして、バロックティンパニーの乾いた響きが、全体をぐいっと引き締めている。なかなか、激烈な序曲であった。
さて、第九。ここでも金聖響独特の、楽譜から総てを読み取り、従来演奏されてきたスタイルを排除し、新たな第九の解釈を打ち出したいという意欲がはっきりと打ち出されていた。特に、第一楽章、第三楽章にはその意図がはっきりと打ち出され、それ故に、今までの第九の演奏に慣れ親しんできた耳には、やや違和感を感じたのも事実。
ひとことで言えば、総ての虚飾を排し、過度な意味づけを除き、ベートーヴェンが楽譜に書きのこしたものだけを厳密に再現することということになるのだろう。
第一楽章の出だしから、神秘的なベールが取り外され、くっきりとした旋律線がうかびあがる。曖昧模糊としたところから、徐々に雄大な主題が浮かび上がってくるというより、旋律が徐々に形成され明瞭になっていくという様な感じ。その後の展開も、テンポは早くかつ動かない。展開部の頂点に達する部分もテンポは動かさず、強烈な音の塊で頂点を築く。哲学的な意味は消え、非常に激しく、ある意味スポーティーな演奏。これは従来からの金聖響の主張。これが効果的に生かされていたのは第2楽章。早めのテンポで、弦をアグレッシブに鳴らし、そこに金管の鋭い響きと、バロックティンパニーの激しい連打が炸裂。この楽章の激しさを一段と描き出していた。
第三楽章が問題。この楽章は本当に難しい。この日の演奏は、きわめて速いテンポ。
これは、金聖響が言うベートーヴェンの指示したテンポということになるのだろう。しかし、正直落着きが無い。確かに早いテンポの中で、主題も十分には歌っているのだが、果たしてこれで正解なのであろうか?第一楽章と同様、神秘的な面は消え去り、ただ旋律線の美しさのみが浮かび上がる。
第四楽章も、前へ前へと進む推進力を表面に出した演奏。最初の否定の動機が終わり低音から歓喜の歌が歌われ始める部分。歓喜の合唱が終わり、マーチの展開部が始まる部分などほとんど休止をおかず次へ進める。有名なフルトヴェングラー・バイロイトの演奏はこの部分にきわめて長い休止を置き、びっくりさせられるが、その正反対を行くほどの間合いの短さ。激しく追い立てていくような演奏。
意図は極めて鮮明なのだが、第九の演奏として果たしてこれはどうなのかと、首をかしげたくなるところも感じる。それだけ、この第九の解釈というのは難しいということなのだろう。今まで聴いてきたいわゆる第九の名演奏とは全く異なった解釈であり、それはそれで見事なものであるのだが、私の第九に対する思いとは異なった演奏であった。
しかし、これはある意味金聖響の術中にはまったということにもなる。金は自著の中で、「私の第九に喝采をする人もあれば、しかめっ面をし、苦虫をかみつぶしたような顔をして帰る人もいるだろう。」という様な意味合いを述べている。それほど現在の金においては、自らの意図する自信に満ちた演奏ということになるのだろう。
この日の独唱者、そして大阪フィルの合唱団、いずれも見事。第九をおざなりな演奏で聴くのは嫌なので、生で聴くのは久しぶりだが、独唱も合唱も一時代前とは格段の差の出来栄えである。
「第9」の演奏は一筋縄ではいかないということを再認識させられた演奏会 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第271回定期演奏会 新日本フィル&OEK合同演奏会
2009年11月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
メゾソプラノ バーナデッド・キューレン
共演 新日本フィルハーモニー交響楽団
合唱 金沢・富山マーラー特別合唱団
OEKエンジェルコーラス
AUBADEジュニアコーラス |
|
年に1回程恒例で行われる、他のオーケストラとの合同演奏会。今年は新日本フィルとの共演で、マーラーの交響曲第3番という、超大曲の演奏。又、初めての試みとして、製作が富山と石川両県の合同という試み。合唱団も富山と石川の特別編成の合唱団。公演も、富山・オーバードホール、石川県立音楽堂と2日間に渡って開催される。
富山と石川の音楽ファンにとってはまたとない贈り物で、このような大きい試みは、これからも北陸共同で行うというのは良い方向性ではなかろうか。今後は福井、新潟あたりも巻き込んでいってほしいとも思う。
さて、演奏会前のプレトークで、今回民主党政権の下で行われた事業仕訳で、「芸術拠点事業」が大幅に削減されるという動きがあり、これが実行されると、OEKなどプロオーケストラや、ホールでの音楽公演の補助金が大幅に削減され、活動に大きな障害が発生することが予想されると説明があり、文科省への削減反対の要請メールを出してほしいとの呼びかけがあった。「財政の無駄」を省くという方向性は重要だろうが、文化活動はその結果を経済的尺度で測るのがそもそも無理な話。そのような無茶をしてしまうと、日本から文化活動は絶滅してしまうだろう。欧米諸国でも、歌劇場の維持などに、多くの国家予算が使われ、それを国民も当然のこととして受け止めており、ウィーンの国立歌劇場等、そのことにより人類の宝ともいえる遺産が残されていることをしっかりと見ていくことが必要であろう。財政的な無駄と文化予算とはそもそもかみあわない議論であろうと考える。
さて、この日の演奏会、いつもと異なりホールの舞台は100名あまりのオーケストラと合唱団で埋め尽くされ、2階オルガンステージには児童合唱団が位置するという壮観。
いつものOEK定期では演奏できない大曲の演奏。ファンにとっても1年に一度は、このような大曲も聴いてみたい。
ギネスブックで世界で一番長い交響曲と認定されたという、1時間40分余りのマーラーの3番。この日の演奏は、マーラーは生で聴くのが一番面白いという当たり前のことを再認識させられた演奏。
出だしの、ホルンの迫力ある吹奏に始まり、35分近い第一楽章は、将にめくるめくような音の色彩の洪水。マーラーの混然・猥雑とした世界が、きちんと隅々まで整理されて浮き上がってくる様は、マーラーの一つの名演の典型ともいえる演奏。多様な旋律、リズム、重なり合いが続くので、演奏によっては収集のつかないものとなりがちであるが、この日の演奏は緻密・冷静でドラマティック、さすがマエストロと、圧倒されるような一楽章であった。勇壮なマーチ、葬送行進曲、世紀末を思わせる退廃的な響き、卑俗な歌、それらが混然と繰り出される様子は、マーラーの世界は刺激的で飽きさせない世界と、ぞくぞくとさせられる。
最初のホルンの斉奏では、後半ホルンを上向きにさせ迫力を増したり、途中の木管の歌でも音を前に出させるため上に向かせたりと、工夫も様々。一楽章ではOEKのメンバーがトップのパートを奏していたが(2楽章以降は新日フィルのメンバーがトップと入れ替わった。)、マイケル・ダウスのヴァイオリンで世紀末の歌がひなびて出現する部分など極めて印象深い。
再現部からコーダにかけてのきっぱりとした盛り上げ方も見事。1楽章で聴く方もかなり疲れたが、井上マエストロは全く平然とした様子。
2楽章から6楽章までは、楽章間の間隔を空けず演奏。途中での音楽の中断を避けるような演出。特に3楽章の終結部に合唱団と独奏者を舞台上に挙げたのにはびっくり。通常は楽章間で入れるのが普通だが演奏途中に入れるのは異例。これも違和感なく、楽章間の感興が継続して保たれた。
3楽章のポストホルンはオルガンの裏側から響かせる趣向。非常に難しいポストホルンの独奏だが、破たんなく聴かせてくれた。やはり、遠くからきこえてくるボストホルンの響きは、ボヘミアの里山を想像させてくれ効果的。
メゾ。ソプラノのバーナデッド・キューレン、深い声でマーラーの深遠な世界を表現。
5楽章の女性合唱、そして見事な児童合唱。鐘の音を表現するコーラスは将に天使の合唱。
5楽章から6楽章へは絶え間なく移行。ここで、独唱者・合唱団は役割を終えるのだが、最後まで、起立したままで、5楽章の音楽がそのまま6楽章に続いていることを示唆。これも、マエストロの心憎い演出。
6楽章は静謐な弦楽器の響きで始まる。柔らかく、そして厚い弦楽器の響き。
第一楽章の混然とした世俗の世界から旅をして、この6楽章の天上のような世界への到達。マーラーのこの交響曲に託した思いが、この終楽章には結実している。
エンディンクでは総ての楽器を鳴らせ壮大な世界を築き上げる。最後の全楽器の懸命の強奏、ティンパニーの決然とした連打。見事な終結。
ホルン、トランペット、トロンボーン、クラリネット、フルート、オーボエなど管楽器の独奏部分もいずれも印象的、この2つのオケには名手が揃っていると認識を新たにした。
音楽堂の歴史に残るであろうと思われる、マーラーの熱演であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
ルーブル宮音楽隊演奏会
指揮 マルク・ミンコフスキー
2009年11月3日 石川県立音楽堂コンサートホール |
|
ハイドン没後200周年の記念演奏会。今年は、メンデルスゾーンの生誕200周年でもあり、12月にはそれを記念したセミナーとコンサートがクルト・マズアを迎えて開催されるようだ。地方の都市で、このような記念演奏会が開催されることは、珍しいのではなかろうか?これも、アンサンブル金沢の活躍により、音楽を楽しむという文化要素が金沢に根付いてきた証拠でなかろうか?
さて、この日の、ミンコフスキー指揮のルーブル宮音楽隊、新鮮な刺激に満ちた楽しい演奏を繰り広げた。
プログラムは、前半がハイドンの交響曲第104番「ロンドン」、後半がモーツァルトのセレナード第9番「ポストホルン」K.320。当初の発表では、演奏順が反対になっていたため、ハイドンが突然演奏されびっくりしたが、演奏前にフランス語でその旨の案内を指揮者がしたようだが、理解できなかった。主催者側も知らない突然の変更だったのかもしれない。
さて、その最初のハップニングから始まり、この日の演奏会には刺激的な面白さが充満していた。
バロックオーケストラといううたい文句で、楽器は総てバロック時代の楽器のコピーを使用している模様。音楽史には詳しくないので、その当時の楽器がどのようなものだったのか、又ハイドン、モーツァルトの古典派の時代にも同様の楽器が使われていたのか、私には不明だが、少なくとも形も音色も現在のオーケストラの楽器とは異なる。
弦は音色からするとガット弦を使用しているように思われるし、オーボエ、フルート、ファゴット等の木管も真の木管で、構造も単純な様、トランペット、ホルン等金管は現在の楽器から比較すると、バルプ類が少なく構造が極めて単純、ティンパニーも勿論バロックティンパニー。それだけに、音色は実に素朴、艶やかさは少ないが、古典的な溌剌とした新鮮さにあふれている。
しかし、演奏する側からすると、機能的な現代の楽器と異なり、大変な技術を要求されると思うが、この日の演奏は全くそれを感じさせず、古典時代の生き生きとした音楽が蘇っている感がした。
ハイドンの最後の交響曲、第104番。序奏から堂々とした壮大な広がりを感じさせる演奏。
各パートを明瞭に鳴らし、小気味よく、また衒いなく、大きく鳴らすところは豪快に、そしてテキバキとしたリズム感の演奏は、ハイドンの交響曲を聴く楽しさを十分に味あわせてくれた。第4楽章の管楽器の持続低音に載せて、主題がうたわれるところなど、爽快であり、音楽的刺激に満ちていた。
後半は、モーツァルトのセレナード第9番「ポストホルン」。最初にミンコフスキーがまたまた作品紹介だが、フランス語なので理解できない。そして、演奏が始まると、セレナーードでなく、行進曲が演奏されるではないか。当時の演奏会で、この様に「セレナード」の前に行進曲を演奏するスタイルが多かったのかも知れない。プログラムには全くないハップニング。これも、音楽会の即興性を重視する、ミンコフスキーの姿勢なのかもしれない。この、マーチも実に気持ち良く、「この後、セレナードが始まりますよ。」というような、序曲的で祝典的な雰囲気が醸し出されていた。
本番の「ポストホルン・セレナーデ」も興味深い工夫が充満。第3楽章では、木管楽器を舞台左側、第一ヴァイオリン、ビオラの後ろに立たせ演奏。この楽章の協奏曲的な側面を強調。この木管楽器群の演奏が又秀逸。木の柔らかい、まろやかな音色が、踊り舞う様。
(この日の楽器の配置は当然、古典的な対向配置。ししかし、コントラバスは中央奥。又、ヴァイオリンは10本の10型だが、コントラバス、チェロは増強し、低音部の充実を図っているよう。)
そして、このセレナードの名前の由来となった第6楽章のポストホルンは、その名の通り、現代の郵便配達が自転車に乗って登場。舞台を周回しながら、片手でポストホルンを吹くというエンターティンメント。「ポストホルン」という楽器、ただでさえ吹くのが難しい楽器と聞くが、それを自転車で片手運転しながら吹くという、軽業師の様な技巧に脱帽。音も柔らかく、そして輝かしい。最後には、小包を指揮者に配達するという、オチまで。この奏者にはブラボーの声が自然に起こっていた。
このように、演出満載の演奏なのだが、音楽自身は実に古典的で充実した演奏。
音楽のエンターティーメントとしての、洒落た面白さを作り出すのは、フランス人の上品なユーモアであろうか。ミンコフスキーの、古典時代の音楽は、こんなに新鮮で面白いものなんですよ、というメッセージを聴くよう。
アンコールも4曲という大サービス。最後のハイドン・驚愕交響曲の第2楽章以外は馴染みの無い作品で、ラモー「瞑想の日」、モーツァルト「ロンド」、グルック(オペラの中のピースか。怒りの日の情景の様)。それぞれ特徴のある演奏で、ラモーの弦楽器を中心とした静謐な響き、モーツァルトのバロックヴァイオリンの渋い音ながら技巧的なパッセージ、グルックのバロックらしく、ドラマティックな激しさ、そしてハイドンのユーモアと、各作品の個性を楽しませてくれた。
最後の驚愕交響曲では、例の、突然のフォルテで驚かす部分を、最初は指揮者が振り上げたタクトに全くオケが反応せず沈黙、やり直しでは楽員全員が「ワァー」という声を挙げ指揮者を驚かすという趣向。このように、おふざけという部分も各所にあるのだが、それが決して嫌味にならない。これは、やはり、パアォーマンスを駆使しながらも、このオーケストラ、そしてミンコフスキーが古典としっかり取り組み、見事なオケとしての技巧を駆使し、古典の生き生きとした再現に意欲を燃やしているからであろう。 |
|
|
|
|
|
|
|
プラハ国立歌劇場公演 ベルディ作曲 歌劇「アイーダ」
2009年11月1日 オーバードホール
アイーダ イトカ・スヴォボドヴァー
ラダメス ジャンルカ・ザンピエーリ
アムネリス ガリア・イブラギモヴァ
アモナスロ ヤクプ・ケットゥネル
国王/ランフィス ルカーシュ・ヒネック=クレーマー
プラハ国立歌劇場合唱団・バレー団
プラハ国立歌劇場管弦楽団
指揮 ジョルジュ・クローチ |
|
6年前に、ドイツマグデブルグ歌劇場の同演目を同じホールで見て以来6年目の「アイーダ」、
その当時の私の感想を見てみると、その公演にはかなり不満の内容であったよう。引っ越し公演ということで、かなりお粗末な舞台装置であったようだ。
今回も、当然ながら引っ越し公演ということで、舞台装置はかなり簡略化されている。
舞台の上には、ピラミッドを象徴するような、三角錐の大きな建物が一つだけ。あとは、舞台左右の柱の数を幕ごとに調整するだけ。三角錐の頂点は、時には太陽が輝き、時には月が照らし、星が輝く。しかしながら、簡略化されることと、お粗末なこととは次元が異なるということをこの度実感。今回の公演も、野外公演であるイタリア、マチェラータ音楽祭で行われたものを、劇場用に改作されたものとのこと。元の野外劇場用の写真を見ても、スケールが大きいのみで、基本的コンセプトは変わらないようだ。
簡略化というより、きわめてシンボリックに抽象化された舞台は、そこで繰り広げられるドラマの集中力を高める役割を果たす。衣装もシンボリックに抽象化されており、僧たちの白い服、バレーの裸体に近い衣装、それらは暗示に満ちているが、アイーダ、ラダメス、アムネリス、更にはエチオピアの奴隷たち等はリアリスティックであり、この対象が実に意味深く見る者を誘う。
オペラ・アイーダというと、グランドオペラの典型という風に思いがちで、第2幕第2場の凱旋の場の壮大でスベクタクルな場面のみが強調されるが、今回の演出では、そのあたりを慎重に避けるように扱いながら、ドラマティックな面白さを浮き出させていた。
かといって、「凱旋の場」も実に壮大な音楽劇として描き、スペクタクルな要素は一切登場させずに、ドラマの一つの頂点を音楽的に描き出していた。
終幕も、リアリスティックな装置は一切出さず、凱旋の場と同じ装置で、照明を使い分けることによってのみ、アイータ゛とラダメスの悲劇と愛の成就を描き上げていた。
オペラは総合芸術と言われ、とかく音楽以外の要素で勝負をしがちであるが、今回の公演では音楽の雄弁性を最も重視し、装置、衣裳は音楽を浮き上がらせる補助要素としており、そのことがこのオベラのドラマティックな面白さを際立たせていた。
歌手では、何といってもアムネリスのガリア・イブラギモヴァが見事。安定した声量で、複雑なアムネリスの心情を歌いあげていた。アイーダのイトカ・スヴォボドヴァーも、やや線は細いが、清純なアイーダを描き出し好演。ラダメスのジャンルカ・ザンピエーリは、出だしやや苦しそう。徐々に好調さを取り戻してきたようだが、声の輝きという点では物足りない、又一部不安定な歌唱もあったよう。バスのルカーシュ・ヒネック=クレーマーもなかなか凄い声量。
指揮のジョルジュ・クローチはオペラ指揮者として、勘所を押さえた的確な指揮ぶり。
オーケストラも、弦楽器のチェコらしい柔らかいビロードの様な響き、オーボエのカンタービレ等、聴かせどころをきちんと押さえた、オペラ座のオーケストラらしい安定した演奏。さすがに、伝統を感じさせる。
さて、今日の公演は北日本放送の開局50周年の記念公演ということであったが、いくつか気になることがあった。
一つは、当日の出演者の発表が当初に無かったこと。今回の公演はダブルどころか、トリプル以上の場合もあり、当然その日の出演者は印刷物などで開演以前に周知すべきであろう。ようやく、幕間に掲示されるようでは、オペラ公演の主催者としては怠慢ではなかろうか?
二つ目は、カーテンコールの際の「ブラボー」の演出。私は事情で2階最後部の出入り口に近いところで聴いていたのだが、終幕の終わり近くになると、誰やら出入り口からの出入りがある。挙句の果てには、小声で話し始める。何の事かと思っていたら、どうやら、「ブラボー」要員の打ち合わせのよう。幕が閉じると、その連中は待っていたかのように、ブラボー。更には、後ろの通路を左右に歩き回り、「ブラボー」の連発。全くしらけてしまい、折角の良いオペラを見たという興奮が、一度に冷める思いである。
確かに、出演者に対して、会場を盛り上げたいという意味合いはわかるにしても、これではぶち壊し。
地方の放送局のいかにも非音楽的な主催公演という印象を与えられ、後味の悪い思いであった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第269回定期演奏会
2009年10月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
ピアノ 中村 紘子
指揮 藤岡 幸夫 |
|
マイスターシリーズの今季2度目の定期。定期としては異例のプログラムで、前半が、ベートーヴェン、ピアノソナタ第14嬰ハ短調「月光」、23番へ短調「熱情」、後半が、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」変ホ長調。
中村紘子のデビュー50周年の記念演奏会の一環として開催されたようである。
最近、私の旧友であるH氏が、「熱情の使徒は二度蘇る。久野久子伝Ⅰ」という力作を自費出版された。その中で中村紘子の「ビアニストという蛮族がいる。」という著書の中での、久野久子の取り上げ方に強い憤りを感じ、緻密に資料を検証し、中村紘子の「久野久子像」を痛烈に批判していた。
又、約50年前、N響の世界一周のソリストとして、振り袖姿でヨーロッパデビューしたニュースも鮮やかに蘇ってくる。
その後の活躍は周知の事実であるが、その活躍に比して、音楽内容に関しては、派手ではあるが、求心力に乏しいとう印象を私はずっと抱いてきた。
それや、これやで、今日の演奏会は複雑な思いで聴くこととなった。
ところで、まず、何故この演奏会がOEKの定期演奏会とされたのか、そこに不思議な感じを抱いた。異例と、先に述べたが、この演奏会の形態は、OEKが主役でなく、明らかに中村紘子が主役。前半にオーケストラが登場しないだけでなく、後半の「皇帝」の後のアンコールでは、オーケストラ全員が退場、指揮者だけが残り、アンコールを聴くという趣向。OEKの定期演奏会の主役はあくまでOEKであるべき。この様な形の音楽会であれば、特別演奏会とした方が妥当ではなかろうか。OEKの会員は、OEKの演奏を楽しむための会員。ソリストとして入るなら理解できるが、乗っ取られた様な印象の演奏会は不快である。
さて、オールベートーヴェン、有名なソナタ2曲と、協奏曲という、ある意味大変な体力のいる演奏会。中村紘子らしい、プログラムの組み方ともいえようか。
その意味、彼女は健在であり、バリバリと弾きまくる様は、60歳を超えたビアニストとは思えない健在ぶり。
「月光」の1楽章、「熱情」の2楽章などのゆったりとした楽章と、激しい楽章との落差を際立たせ、激しい部分は一層劇的に追い込もうという演出意図が浮かび上がる。ある意味、聴いていて、理解しやすい音楽づくりを目指しているともいえる。
しかし、「熱情」の2楽章など、あまりに淡泊すぎて、その楽章に込められたベートーヴェンの心情が聴こえてこない。音に魂が籠っていないといえば、抽象的だが、そう言わざるを得ない感情を抱く。パーツの部分の素晴らしさが、全体の素晴らしさにつながっていかない。「月光」「熱情」とも、1楽章の最後は余韻を長く保って、効果を狙っているが、そこにも演出臭さを感じてしまう。
後半の協奏曲は、将に弾きまくるという感じ。第一楽章第2主題の歌わせ方など、かなり恣意的な演出を感じる。ケレンという意味では、この協奏曲のある一面を表現しているが、細部までへの息遣いがあるかというと、やや乱暴。よくも悪しくも、このピアニストの特質が表れた演奏というべきか。
後半のオーケストラの藤岡幸夫、がっちりとして、丁寧な音楽づくり。中村紘子の自由奔放なピアノにも負けることなく、重厚な演奏。オーケストラもしっかりとした音づくり、特にこのコンチェルトで難問のホルンも見事な演奏。
アンコールはショパン3曲。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第268回定期演奏会
2009年10月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ロルフ・ベック
合唱 シュレスヴィヒ=ホルシュタイン音楽祭合唱団 |
|
この日の定期は、OEKが度々出演しているドイツシュレスヴィヒ=ホルシュタイン音楽祭の音楽監督、ロルフ・ベックの指揮、その音楽祭の合唱団の出演によるもの。
前半にシューベルトの交響曲第8番「未完成」、後半にモーツァルトの「レクイエム」というプロ。共に未完成の作品を取り上げたところが特長的。というものの、シューベルトは未完成だが、モーツァルトは弟子のジェスマイヤーが補筆完成させた版の演奏。以前はモーツァルトの絶筆「涙の日」で演奏を打ち切ることもあったが、最近はこの完成版の演奏が主流のようだ。
シューベルト、モーツァルト、双方とも、その作曲の過程が脚色され、ある意味誇張されてきたため、その側面をことさら強調する、感傷的な演奏をとかく聴くことが多いが、今日のロルフ・ベックの演奏は、その虚飾を排した、誠実で、衒いのない、堂々とした演奏となっていた。
「未完成」も、テンポは一定で中庸、シューベルトの歌の素朴な美しさと、交響曲としての形式感をくっきりと浮き上がらせた演奏。ひ弱で青白い、青年シューベルトでない、ドイツの正統的な音楽の伝統を受け継ぐ作曲家、シューベルトという面を強く感じさせる演奏。OEKのしっとりとした弦の響きと、木管の素朴な響きとのからみあいも見事。
後半のモーツァルトの「レクイエム」も、悲劇的な面の強調でなく、この作品の典礼的な堂々とした風格を浮かび上がらせるような演奏。であるから、「涙の日」以以後も、それ程違和感なく聴こえてくる。合唱団も30名余りであるが、その声量の豊かさ、そして表情の豊かさは特筆。ソリストも合唱団のメンバーの様だが、声の質、声量とも申し分ない。
「怒りの日」から「不思議なラッパ」にいたる劇的な激しさも見事。
室内オーケストラと小さい合唱団の演奏という印象とまるで異なる、スケールの大きな演奏。
ドイツの正統的な音楽を聴かせてくれたという印象の演奏会であった。
アンコールに恒例の「アヴェ・ヴェルム・コルプス」。静謐な美しさに溢れた演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第267回定期演奏会
2009年9月18日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
ピアノ コルネリア・ヘルマン |
|
新しいシーズンのマイスターシリーズの幕開けのコンサート。
プレトークで井上監督が、今期の定期シリーズの特徴について、「古典を重視したと。」解説。「古典については、前の岩城さんより僕の方が良いと思う。」というトークに思わず苦笑。半ば冗談、半ば本気であっのだろう。
というわけで、このマイスターシリーズの幕開けも、古典。
珍しい、グノーの小交響曲、モーツアルトのピアノ協奏曲第23番K.488、後半が交響曲第36番「リンツ」K.425という、比較的小ぶりなプログラム。OEKにふさわしいプロといえるか。
最初のグノー、管楽器のみによる合奏という、珍しい交響曲。オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンが各2本、フルートが一本という編成。「OEKは弦が優秀なのだが、管が------?」という井上マエストロの言葉を裏返す様な、管楽器の安定した技巧を聴くことが出来た。惜しむらくは、もう少し各奏者の遊び的な余裕があれば、この作品の愉悦をもっと高めることが出来たのではと思えた。
モーツァルトの23番の協奏曲。ヘルマンはザルツブルク出身とのことだが、なるほど音色がモーツァルトにピッタリのように柔らかく落ち着いている。丁寧で好感のもてる演奏なのだが、表面的な美しさが十分である反面、モーツァルトを自分はこのように再現するという個性的なアプローチにはやや欠け、その分面白さが感じられない。又、早いパッセージの部分が全体の流れの中から浮き上がり、音楽の流れがそこで、滞るような違和感を感じたのは、なぜだろう。
後半は交響曲第36番「リンツ」。実に暖かく、響きの充実した演奏。古典的な堂々たる形式感の中に、モーツァルトの陰影を、各パートが歌心豊かに歌い上げる。
今月、井上マエストロは、フィルハーモニーシリーズでハイドン、今回モーツァルトと古典の代表的な二人の作品を並べたが、比較して聴いてみると、アプローチの違いが明確で実に面白かった。ハイドンにおいては、溌剌として、古典的できびきびとした前進感に満ちた演奏、モーツァルトでは、むしろ厚い響きで、テンポも中庸、歌が溢れた演奏。古典的均整美のハイドン、人間臭い、厚みを感じさせるモーツァルト、このようにきっちりと性格分けをしているように聴くことができた。ハイドンでは、バロックティンパニーの使用、モーツァルトでは通常のティンパニーという、ティンパニーひとつをとってみても、きっちりと使い分けをしていたのも、その表れと思われる。
パフォーマンスの強いマエストロであるが、この「リンツ交響曲」のシリアスな演奏は、この指揮者の円熟を再確認させられる演奏。
アンコールは生誕200周年のメンデルスゾーンの八重奏曲のオーケストラ編曲バージョン。
井上マエストロの編曲によるのだろうか?「真夏の夜の夢」のスケルツォを想起させるような、幻想的な美しさ。弦、管とも独特のリズムの早いパッセージを的確に演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢 岩城宏之メモリアルコンサート 富山公演
2009年9月4日 富山県民会館大ホール
指揮 井上道義
クラリネット 豊永美恵
サキソホーン 須川展也 |
|
オーケストラ・アンサンブル金沢 岩城宏之メモリアルコンサート 富山公演
2009年9月4日 富山県民会館大ホール
毎年、9月に開催されている、「オーケストラ・アンサンブル金沢 岩城宏之メモリアルコンサート」、北陸銀行の協賛で、安い料金で富山でも聴くことができるのは有難いこと。今後も北銀さんには是非続けてほしいものである。
岩城マエストロの没後、創設された基金を基に、ジャンルを問わず、北陸の優秀なソリストに与えられる岩城宏之音楽賞、今年は福井出身のクラリネット奏者、豊永美恵さんが受賞、今日の演奏会ではモーツァルトのクラリネット協奏曲が演奏された。
その前に、ハイドンの交響曲第102番、そして最後にサクソホーンのの独奏で、今年のコンポーザー・イン・レジデンス、ロジェ・ブトリーの新作、「アルト及びソプラノサクソホ-ンの為の協奏曲」、というプログラム。
最初のハイドンの102番の交響曲。ハイドン晩年の交響曲だが、演奏される機会はそう多くはないはず。「軍隊」「驚愕」「時計」「ロンドン」などの有名交響曲の蔭に隠れている名曲。この日の演奏、溌剌として、推進力に満ちた、古典的均整感の整った演奏。
アウフタクトが主題に用いられているため、前へ前へと進む推進力が小気味良い交響曲だが、この日の演奏は将にその推進力に満ちた演奏。弦楽器、管楽器ともかなりのスピートを指揮者は要求しているが、アンサンブルの乱れもなく一気呵成に進んでいく音楽は、聴いていて気持ち良い。アンサンブル金沢の古典演奏の見事さを改めて感じた。
次の、モーツァルトのクラリネット協奏曲。今年はクラリネットの豊永美恵が受賞、そのお披露目演奏。この「クラリネット協奏曲」、陰影に満ちた部分を的確に表現した、若手と思えない円熟の演奏。特に第2楽章のゆったりとしたテンポで歌う、低音の旋律の歌わせ方は見事。えてして技術のみを見せびらかせようとする傾向になりがちだが、この奏者は技巧の安定性の上に、自らのモーツァルト像をくっきりと浮かびあがらせている。個性的な奏者で、今後が楽しみ。
この日の最後は、今年のコンポーザー・イン・レジデンス、ロジェ・ブトリーの新作、「アルト及びソプラノサクソホ-ンの為の協奏曲」
世界初演曲が、プログラムのフィナーレというのも、アンサンブル金沢らしいプログラミング。奏者に、須川展也という名匠を迎えての華々しい協奏曲。3楽章形式のきっちりとした協奏曲だが、中身は自由。第一楽章は、打楽器奏者の横で主題が奏されるという意外な出だし、その主題が様々に変奏され、印象づけられる。この主題はこの楽章のみでなく、各楽章でそのその姿が見え隠れする。パーカッション、ビブラフォーンも活躍、サクソホーンと管弦楽のかけあいも面白い。さすがに、吹奏楽の大家の作品と思わせる、サックスの魅力を存分に表現した作品。須川展也の卓越した技巧と、輝きと憂いを兼ね備えたような音色が魅力的。
アンコールにルロイ・アンダーソン、「プリンク・プランク・プルンク」
井上マエストロのパフォーマンス豊かな演奏で、地味なプログラムの演奏会の最後を盛り上げた。 |
|
|
|
|
|
|
|
いしかわミュージックアカデミー(IMA)フェスティバルコンサート
指揮 井上 道義
ピアノ 篠永 沙也子
ヴァイオリン シン・ヒョンス
神尾 真由子
オーケストラ・アンサンブル金沢
IMA受講生選抜メンバー |
|
あまり知られていないが、金沢では毎年夏、「いしかわミュージックアカデミー」が開催され、原田幸一郎初め優れた教授を迎え、様々なジャンルの音楽のアカデミーが開催されている。このアカデミーからは、庄司沙耶香、今日演奏するシン・ヒョンス、神尾真由子等、世界の音楽界で注目を浴びる若手演奏家が現われている。
毎年8月このアカデミーの開催に合わせて記念の音楽会が開かれているが、今年は、昨年のロンティボー国際コンクール優勝のシン・ヒョンス、チャイコフスキー国際コンクール優勝の神尾真由子という豪華ヴァイオリニストの協演で、メンデ゛ルスゾーン、チャイコフスキーの協奏曲を演奏するという、贅沢な音楽会となった。
最初に、やはりアカデミーで受講した地元若手ピアニスト、 篠永 沙也子による、モーツァルト「ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調k.382」、次にシン・ヒョンスのヴァイオリンでメンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲ホ短調」、休憩を挟み、IMAの選抜メンバーとOEKの合同演奏で、メンデルスゾーン「弦楽のための交響曲第10番」、最後が神尾真由子のヴァイオリンでチャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」というプロク゜ラム
超人気の2つのヴァイオリン協奏曲を、今世界で最も注目を浴びている二人の若手が演奏するという、二度と再現不可能のような演奏会とあって、会場は満員の盛況。
OEK、IMAと石川の音楽文化の底の厚さを改めて認識させられた演奏会でもある。
さて、最初の 篠永 沙也子。やや緊張気味の出だしだったが、モーツァルトの流麗な音楽を、自分の感性で紡ぎだした、清潔で均整のとれた、好感のもてる演奏。モーツァルトのピアノ独特の転がすような音を、気持ち良く再現していた。美しい音色の持ち主である。
さて、シン・ヒョンスのメンデルスゾーン。個性的なアプローチ、音質はやや硬質、ありふれた言葉でいえばクリスタルのような音質。これは、神尾真由子の温かみのある音質と対照的。
出だしの有名な主題が奏でられたとき、はっとするような引き締まった音質。しかし、進むにつれて、独特のアプローチ。テンポはかなり動き、思い入れが強い。メンデルスゾーンの場合、こんなに思いを込めなくても、流麗端正で良いのではとも感じるが、これが彼女の個性か。音質のクールさと、こめられた感情の熱さとのアンバランスが面白い。井上・OEKの伴奏がヴァイオリンのこの個性的なアプローチにピッタリとつけたのは見事。
部分的にかなり独特でありながら、全曲を通して、なるほどと納得させられるのは、彼女の全体へのアプローチがしっかりとしている上での個々へのアプローチであるからだろう。
アンコールにパカニーニの「24のカプリ-ス」から、有名な「ラ・カンパネラ」によるもの。鮮やかとしか言いようのない演奏。この技術的に高度な難曲を、いとも楽々と弾いていく。キラキラと輝くような音の飛翔。
後半はIMA選抜メンバーとOEKの合同演奏でメンデルスゾーン「弦楽のための交響曲第10番」
かなり大きな弦楽合奏。他の2曲と異なりコントラバスを正面に据えた対面配置。
これだけの弦で合わせるのは大変なことだろうが、実に厚みのある、それでいて流れるような動きのある見事な弦の合奏。IMAのメンバーの優秀な底力を認識させるような演奏。
最後は神尾真由子。おはこで注目のチャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」
3月にはブルッフの協奏曲をOEKと共演、その際の情熱的な演奏が印象に残っているが、今日はそれ以上の熱の入った演奏。
音質が実に暖かい。そしてなによりも、細部まで神経の行き届いた、ごまかしのないアプローチ。さっと流してしまいそうな細かい部分までをごまかさずに、丁寧に演奏する。
「熱い演奏家」という印象が強いため、勢いと情熱に身をゆだね、弾きまくってしまうという印象がありがちだが、実際に聴いてみると、そうではなく、部分部分に自分の思いをこめながら全体を築き上げていくという誠実な演奏。そして、豪壮でなく、素朴。第2楽章の出だしの主題の歌わせ方の素晴らしさ。感傷に身をゆだね、甘ったるく弾く演奏が多いが、彼女は深く沈潜した情念を感じさせるしっとりとした歌わせ方。この楽章でのOEKのクラリネット、オーボエ、フルート、ファゴットは、神尾にぴったりと寄り添い、見事なからみあいを聴かせてくれた。
最終楽章も、技巧を見せびらかすのでないしっかりとした演奏。
満員の聴衆からブラボーの声が飛び交い、ここでもアンコール。シン・ヒョンスと同様にバガニーニの「24のカプリ-ス」から。期せずして二人のパガニーニを聴くことができた。神尾も、温かく、太い音質で、完成されたパガニーニ。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第265回定期演奏会
2009年7月25日 石川県立音楽堂コンサートホール
リーダー&ヴァイオリン 安永 徹
ピアノ 市野 あゆみ
トランペット 藤井 幹人
チェロ ルドヴィート・カンタ
オーボエ 加納 律子
ファゴット 柳浦 慎史 |
|
自身の以前の記録を見ると、2007年7月に安永徹・市野あゆみが4回目のOEK登場となっているので、今回は2年ぶり、5回目の登場である。これだけ、回数を重ねて定期に登場するということは、お互いの相性が良く、互いに引きよせる何かがあるということだろう。
今回も、気心の知れあった同士とでもいうような、息の合ったアンサンブルを聴くことができた。
最近、安永徹のベルリンフィル退団と、樫本大進のベルリンフィル新コンサートマスター就任というニュースが飛び込んできたが、安永徹の退団後の活動に今後注目が集まることだろう。
今回も、今まで同様、指揮者というより、コンサートマスター席に座り、室内楽的なアンサンブルの中心を担うという役割の様に聞こえた。
前回はシューベルトの交響曲第3番が演奏されたが、今回は第5番。安永徹はシューベルトが大好きなようで、この日の5番の演奏も端正で、のびやかな、シューベルトらしい歌に溢れた演奏。編成も、OEKの基本的な編成で、こじんまりと、30人あまり。安永も指揮をするよりも、ヴァイオリンを弾きながら、アンサンブルを楽しんでいるような演奏。
前回も感じたが、指揮者なしでの演奏は、オーケストラに相当な実力がないと混乱をきたすと思うが、この日のOEKは安永の呼吸とぴったりと寄り合い、隙のない緻密なアンサンブルを聴かせてくれた。
前半の2曲目は、ショスタコーヴィッチのビアノ協奏曲第一番。トランペットとピアノ、室内オーケストラのための協奏曲ともいえる、トランペットが独奏者として活躍するユニークな協奏曲。この日のトランペットはOEKの藤井幹人。ピアノの色彩とトランペットの豊かな表情がマッチした、洒落た演奏。ショスタコーヴィッチの才能あふれる、擬古典的でありながら、魅力的で、色彩豊かな旋律があふれる作品だが、この日の演奏はその面白さを十分に聴かせてくれた。ピアノは、この作品の抒情的な面と機智的・技巧的で華麗な部分の対比が見事。トランペットもピアノと同様、ブラスの華やかな面と、弱音器をつけたうら哀しい部分との対比を的確に表現。この作品の一筋縄でいかない面白さを、混乱することなく、的確に表現。しかし、この作品がショスタコーヴィッチの生涯の危機的な時期に書かれていることを考えると、ショスタコーヴィッチの人間の複雑性を、改めて考えさせられる。
シューベルト以上に、指揮者なしでは難しいこの作品、ピアノもトランペットもそしてオーケストラも、それを感じさせない呼吸のぴったりあつた演奏。
後半は、ハイドンの協奏交響曲。ヴァイオリン、チェロ、オーボエ、ファゴットを独奏者とした、堂々とした交響協奏曲。この日の独奏者は安永徹以外総てOEK楽団員。
ここでは、この日の演奏会で初めてティンパニーが参加したが、この日のティンパニーはバロックティンパニーが使用され、久しぶりのトーマス・オケーリーの、小気味の良いティンパニーが演奏全体に張りのある古典的明晰さを与えていた。
各独奏者も息の合った演奏。この日の演奏会を象徴するような、室内オケのアンサンブルの緻密さを聴くことができた。欲を言えば、各独奏者の自発性がもう少し聴ければ、一層面白い協奏曲となったと思うが、その点がやや平板。真面目であるが、色気が足りないということか。
アンコールに、珍しいプッチーニの弦楽四重奏のための「菊」の室内オーケストラ版が演奏された。プッチーニのオペラの、センチメンタルな面と、一線を画すようなシリアスな美しさに満ち満ちた作品。センチメンタルとロマンテイックとどこで線を引くのかということになろうが、この作品にはわざとらしさのない、素直な歌が聴こえた。そして、OEKの弦の充実した響きを再認識。惜しむらくは、拍手が早すぎた。もう少し、じっくりとこの作品の余韻を味わいたかった。 |
|
|
|
|
|
|
|
ショスタコーヴィッチ・弦楽四重奏曲全曲演奏会 第4夜
2009年7月6日 北日本新聞ホール
大澤 明 弦楽四重奏団 |
|
2006年から始まったショスタコーヴィッチの弦楽四重奏曲全曲演奏会も3年目で第4夜。
昨年8月に第3夜が開かれた際、主宰者の大澤明氏が、第2ヴァイオリンの竹中のり子さんがウィーン留学のため変更となること、「来年桜の咲くころには第4夜を行いたい」等の案内があった。「桜の咲く頃が」が過ぎ、開催の報が聞かれず、心配していたが、梅雨の季節にようやく開催されほっとした。
今回は竹中のり子さんの代わりに、同じオーケストラ・アンサンブル金沢の上島淳子さんが加わった。
今回は、2番、5番、13番が取り上げられた。
演奏順は時代順でなく、5番、13番そして休憩後2番というもの。作品の性格、演奏する側、聴く側の集中力に配慮した演奏順と考えるが、これは適切であったように思う。
最初に、中期の完成度の高い5番、そして次に晩年の不思議な世界の13番、そして中期に戻って、「ああ、こんな作品から出発し、あの最後の世界に行き着いたのだ」と、振り返らせる2番。ショスタコーヴィッチの弦楽四重奏は、個人のモノローグであると思うが、その遍歴をじつくりと聴かせてくれた演奏順。
第2ヴァイオリンの変更があったが、この日の大澤明弦楽四重奏団は、技術的に高度で、内容的に実に色濃い演奏。ショスタコーヴィッチの弦楽四重奏曲は、各パートとも、主役を担う部分があり、合奏の重要さと同時に、各パートの主体性、表現力の重要さが試される作品ばかりだが、この日の各パートはどれも見事。作品の面白さ、そして雄弁さを、楽譜からくみ取り、自分の音楽として表出していたので、聴く側にとっても、実にスリリングで、ある意味わかりやすい演奏となっていた。第一ヴァイオリンの松井直さんの鋭くも分厚い響き、新しく加わった第2ヴァイオリンの上島淳子さんの正確、誠実な響き、内声部で特に重要な役割を担うビオラの石黒靖則さんの主張のある表現力、そしてチェロの大澤明さんのどっしりと支え、明確な響き。最近のオーケストラ・アンサンブル金沢の弦楽部門の好調さが、なるほどと理解できる、この日の演奏。
第5番。1952年、46歳の作品。既に第2次世界大戦後、2つの社会体制が確立されている時代。1953年はスターリンが没した年。年譜を見ると、交響曲第10番が1953年作。
ショスタコーヴィッチの、将来のソヴィエトに対する期待と不安が交錯していた時代かもしれない。
3楽章が切れることなく続けて演奏される。第一楽章の例のDSCHの動機の執拗な繰り返し、しかし緊密な構成力があり、明確で力強い楽章。第2楽章は中期のショスタコーヴィッチの清冽な抒情が色濃く表現されている。全楽章を通じて、DSCHのテーマが支配する、論理的で堅固な構成。
第13番。1970年、64歳の作品。ついこの間である。
晩年のショスタコーヴィッチの苦渋の心境が聴き取れる、レクイェムのような趣。
痛切で、痛々しいビオラの独奏で始まるが、途中、叩きつけるような否定の三音がくりかえされる。中間部では明らかにジャズ、ブルースの響きが聞こえる。最初のビオラの主題、否定の三音、中間部のジャズの響きが、からみあい、展開され、終結部では、ヴァイオリンの鋭い叫び、それをなだめるようなヴィオラの洞を叩く音。
一体、この作品でショスタコーヴイッチは何を語りたかったのかと考えさせられるミステリアスな作品。
第2番。2番とはいえ、1944年、38歳の時の作品。この前年には、8番の交響曲が完成されている。世界大戦終戦の前夜の作品。
ショスタコーヴィッチの弦楽四重奏曲の中では、形式的に整った、形の上では、ある意味古典的な枠に収まっている。第一楽章は、ロシア的というより、東欧的な雰囲気を感じさせるテーマ。ヤナーチェックの弦楽四重奏をも想起させるよう。5番の2楽章と似通った、歌謡的で清冽な抒情性。第3楽章はワルツだが、まるで死のワルツの様な不気味さ。中間部では、まるでウィーンナワルツを皮肉ったような盛り上がりを聴かせる。
第4楽章は、変奏曲だが、中間部分からは転調に転調を繰り返し、不安な高揚感をもたらし、最後は覚悟を決したような決然とした和音で終結。
シヨスタコーヴィッチは現代のベートーヴェンと比喩されることが多い。交響曲と室内楽での、その内容の対比。交響曲は外へ向けたアピールであって、室内楽作品は内面、心情の告白。そのような意味あいでも、確かにショスタコーヴィッチはベートーヴェンに似通っている面がある。
しかし、そのような形式的な面だけでなく、音楽がその人間の生きた時代と、時代にかかわった人間がどのように生きてきたのかを表現するという、将にヒューマニステックな面をこの音楽の巨人はあわせもっているという点で共通していると考える。
現代音楽が、何を表現するのかという課題は大きい。音楽技法が、単なる作曲家の自慰行為であってはならないということを、ショスタコーヴィッチは自身の音楽で語っている。
「政治と音楽」、「社会と音楽」という論点で論争を生んできた作曲家、ショスタコーヴィッチではあるが、彼の作品は将に真の意味で社会的な音楽であり、であるから聴く者に感動を与える。モーツァルトと同様に希有な才能を有した20世紀の天才であろう。
今回の連続演奏会を聴きながら、毎回、そのように思い、感動を新たにしてきた。
「来年、桜の咲くころ、最終回」をと、大澤明さんはまた語っていた。これだけの充実した演奏を行うためには、それだけの準備期間は当然必要であろう。最終回は6番、9番、そして最後の15番。期待は大きい。 |
|
|
|
|
|
|
|
コンサートスタイルオペラ ベルディ「椿姫」
2009年6月30日 オーバードホール
指揮 チョン・ミョンフン
東京フィルハーモニー交響楽団
ヴィオレッタ(ソプラノ) マリア・イルジ・ボルシ
アルフレード(テノール) ダニール・シュトーダ
ジェルモン(バリトン) ヴァシリー・ゲレッロ
合唱 新国立劇場合唱団 |
|
コンサートスタイルオペラと銘打ったベルディの「椿姫」が、チョン・ミョンフンの指揮によって演奏された。東フィルとの共演、新国立劇場合唱団のメンバーによる演奏で、新国立劇場の公演といっても良いような公演。
何といっても、この日のプリマドンナ、マリア・イルジ・ボルシの絶唱。ヴィオレッタはドラマティックとリリックの双方を要求される難しい役柄だが、ボルシは芯の強い情熱的な女性と、愛に身を捧げる優しい女性の両面を見事に表現。柔らかい声質、更には心情をドラマティックに歌い上げる部分とで、ヴィオレッタの人間としての苦悩を彫り深く演じきっていた。
チョン・ミョンフンの指揮も鮮やか。第一幕の前奏曲の出だしの弦の柔らかく切実な響きで、このオペラの世界に聴く者を一遍に引きずり込む。
舞台装置、衣裳、照明などがない、コンサート形式のオペラの長所を十分に生かし、音楽が語るドラマの世界を濃厚に表現。
オーケストラの編成も、コントラバスを6本使うなど、大編成。通常のオペラに比較し、一層ダイナミックな人間模様を聴くことができた。
ベルディがなるほど、音楽でここまで人間表現をしていたのかと、通常のオペラ公演では、聴き逃していた音楽の襞の深さに改めて気付かされる。
アリアの中で、クラリネット、オーボエなどの木管が切ないまでに歌う響き、鋭くドラマティックに切り込む金管の叫びなど、ヴェルディの濃厚な音楽ドラマに改めて感動。
終幕のエンディンク、ヴィオレッタがこと切れる、と同時にオーケストラが激しく慟哭、ドラマの総てを物語るようなオーケストラの強奏。心を打つエンデイング。
オーケストラもさすがに新国立の常設オーケストラだけあって、表現力が豊か。チョン・ミョンフンの意図を十分に表現していた。
テノールのダニール・シュトーダは、やや声量に乏しく、ヴィオレッタの好演と比較しやや残念。ジェルモンの、ヴァシリー・ゲレッロは滋味あふれる歌唱。「プロヴァンスの海と陸」は、なかなか納得できる演奏に出会ったことがないが、この日のヴァシリー・ゲレッロの歌唱は、感情豊かで、抑えた歌い方でありながら、真情に溢れていた。
その他のメンバーは新国立劇場合唱団が受け持っていたが、独唱者として見事な声の持ち主ばかり。新国立劇場合唱団の合唱の素晴らしさとともに、水準の高さに驚く。第2幕第2場の、「ジプシー、闘牛士の合唱」の聴かせどころの合唱も見事。
今日のような水準の公演は、世界でもトップレベルのオペラ公演ではなかろうかとも思えた。
聴衆も大満足のようで、終了後は富山では珍しくスタンディンクオベーション。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第263回定期演奏会
2009年6月26日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ギュンター・ピヒラー
ホルン ラトヴァン・ブラトコヴィッチ |
|
久しぶりのピヒラーの指揮による演奏会。ベルク四重奏団が解散して、ピヒラーは指揮活動に本腰をいれるのだろうか?
R・シュトラウスが2曲、前半が「ホルン協奏曲」(ホルン ラトヴァン・ブラトコヴィッチ)、後半が晩年の大作「メタモルフォーゼン」
最初にモーツァルトのセレナーデ第12番ハ短調k.388。数年前に広上淳一により演奏された「グランパルティータ」と同様の8本の管楽器による演奏。
「セレナード」という言葉と裏腹に、暗い色彩に彩られた、交響的な作品。ピヒラーは後半の「メタモルフォーゼン」と対の役割をこの作品に託したのかもしれない。
演奏は、その悲劇的な色彩を鋭く強調した演奏。各楽器を、柔らかく鳴らせるのでなく、鋭く鋭角的に響かせる。各奏者ともピヒラーの意図に添い、激しい響きを奏でていた。
R・シュトラウスの「ホルン協奏曲」。暗い2曲に挟まれ、よりこの作品の明るさが際立っていた。ホルンのラトヴァン・ブラトコヴィッチは、出だしの「アルプス交響曲」を想起させるような、朗々としたファンファーレを高らかに輝かしく奏し、一度にこの作品の世界へいざなってくれた。柔らかく、温かい音、そしてブラスらしい輝きに満ちた音、その双方をふんだんに聴かせてくれた。技巧的に難しいこの作品を、軽々と奏し、楽しく聴かせてくれるブラトコヴィッチの力量にただ脱帽。伴奏のオーケストラも若いシュトラウスの生気に満ちた音楽を鮮やかに描き出していた。アンコールにモーツァルトのホルン協奏曲第3番の第3楽章。これも、鮮やかな演奏。
休憩後はR・シュトラウスの晩年の大作、「メタモルフォーゼン」
弦楽のみによる演奏。配置が対向配置でなく、第1Vn、第2Vn、チェロ、ビオラ、やや後ろにコントラバスという配置。編成も低音域が増強され、コントラバスが3台、第1Vn、第2Vn、チェロ、ビオラェロがそれぞれ5台。この作品Rシュトラウスが23の弦楽器のためにと記した通り、各楽器群の中でそれぞれ独奏あり、合奏ありで、精緻な網目模様のように書かれており、演奏する側にも大変な緊張を強いる大作である。
この日の演奏は、OEKの弦楽パートのエキスを聴かせてくれたような研ぎ澄まされたような緊張感に満ち満ちた演奏。
ピヒラーはやや早めのテンポで緊張感を高め、R・シュトラウスの最後の告白ともとれる、悲壮な美しさを十分に表現していた。ベートーヴエンの第3交響曲、葬送行進曲の断片、ワーグナー的響きの断片などが入り混じり、将にドイツロマン派音楽の終焉を悼むような作品。R・シュトラウスのそれまでの甘美で、楽天的な世界とは明らかに異なり、やはりR・シュトラウスが最後に到達した、透徹した美の世界であろうか。ナチスドイツが崩壊に直面し、R・シュトラウス自身もその体制を積極的に支えた一員としての苦い苦渋の回顧であろうか。「音楽と政治」が厳しく問われるナチスドイツの時代、R・シュトラウスがこの作品を残さなければ、この大作曲家の評価も異なったものとなっていたかもしれない。
最後、静かに消え入るように終わる弦楽器の響き、ピヒラーは音が消えても、暫くは指揮棒を下さず、その間まだ、音楽が響いているよう。
このような作品の後に、アンコールは無理。聴衆もそれは十分に承知。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第262回定期演奏会
2009年6月13日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響 |
|
金聖響・OEKのベートーヴェンシリーズも今日と12月の第9を残すのみ。2003年からということなので、足かけ6年。最初に私が聴いたのは、2003年の第3番と記憶しているが、その際の鮮烈な印象はいまだ耳に残っている。
今日は、7番、8番。
楽器編成と配置はこれまでの金と同様、正面奥にコントラバスを置き、その前に木管、左側にホルン、右奥にトランペツト、その前にティンパニ(当然バロックティンパニ)、弦は左から第一ヴァイオリン、チェロ、ビオラ、第2ヴァイオリン。コントラバスが4人、チェロが6人と低音部の人数を増やしているが、第一ヴァイオリンは9人。常識的にはやや変則と思える配置だが、これは金聖響によると、ベートーヴェンの時代に演奏されたスタイルとのこと。そして、金のベートーヴェンには、この編成と配置が重要な役割を担っている。「巨匠の時代」に肥大化した編成を初演当時の編成に戻すことにより、ベートーヴェンの音楽の本来のスリムな姿を再現させたいという試みと結びついているわけ。
そして、この編成にぴったりなオーケストラがアンサンブル金沢。
というわけで、金聖響の理想的なベートーヴェン像をアンサンブル金沢との一連の演奏会で示したいという意欲。
最初の「プロメテウスの創造物」序曲の序奏の強烈な和音。この日の壮烈な演奏を予感させるような激しい出だし。そして、主部の爽快なスピード感。重量級のベートーヴェンでない、音楽の推進力と活力に溢れた演奏。わずか、5、6分の短い序曲だが、その中での緻密な構成を聴きとることができる、簡潔な演奏。
8番。私がこの作品のすごさに驚かされたのは、高校生の頃に聴いたLPでのメンゲルベルクの演奏。その第一楽章の展開部のたたみかける迫力、推進力のすごさは、音質の悪いLP盤でも十分に伝わってきた。それ以来、この作品はCDでも生でも相当数聴いてきたが、なかなかその時の驚きに匹敵する演奏に出会ったことはなかった。
今日の演奏はそれ以来の興奮を呼び起こす演奏。1楽章の提示部は簡潔に、この作品のある意味古典的な響きで始まるが、展開部からが壮絶。さあ、これから私の音楽とでも言いたいような、ベートーヴェンの音の洪水。オーケストラの総ての楽器が、たたみかけ、叩きつけ、頂点になだれ込んでいく。金管の突き刺すような響き、バロックティンパニの強烈な連打、重層的な弦の厚い響き。ここで、金は決してテンポをいじったり、オーケストラをあおったりすることはせず、楽譜に描かれたことを忠実に再現しているかのようだが、そこにベートーヴェンのすさまじい音楽が渦巻いている。「楽譜に描かれたことを、いかに読み取り忠実に再現するか」が、金聖響の指揮の根本にあると思うが、その読解力の確かさがこのような名演を生み出す。
特別な演出を加えなくても、楽譜に書かれたことを正確に再現すれば、そこにベートーヴェンの音楽の本質が再現される、これが金聖響の音楽の根本。しかし、そのことは一番難しいことであるのも事実。
2楽章の刻むような明快なリズム感と諧謔的な面白さ、そして3楽章の中間部での金管の率直で壮大な吹奏。4楽章はリズム感が抜群。コーダは狂気的な乱舞になるのだが、ここでも冷静。オーケストラを確実にドライブし、総ての楽器を正確に鳴らすことにより、頂点を築いていく。オーケストラも力を振り絞っての強い響き。それゆえ、時には金管など悲鳴を上げる場合もあるが、音楽の流れの中ではそれも好ましい。
後半の7番の演奏の前に、金聖響がマイクをとり、今日が故岩城宏之マエストロの命日であること、8番が好きだったマエストロの命日にこのコンサートが開かれることに不思議を感じること、そしてこの7番の演奏を岩城マエストロに捧げたいとのスピーチがあつた。
7番も8番と同様の演奏。第一楽章の長い序奏部が終わり、主部に突入する際の木管のリズム感が抜群。この交響曲の基幹をなすリズムが印象的に奏される。この提示部は繰り返されるが、繰り返しの際、一瞬の呼吸を置くのも絶妙。構成をきちんと聴く者にわからせる、このあたりも冷静。展開部から再現部、コーダにかけてのたたきつけるようなリズムの饗宴。この交響曲の真髄である。コーダの低音弦のソステヌートも分厚く効果的。
第2楽章は、やや早めのデンポで淡々と進む。ここでも、妙な演出は一切行わない。意図的とも思えるほど、テンボも動かさず、メロディーもいじらない。そこにむしろ、この楽章の裸の素朴さが浮き出す。
第3楽章では中間部の管楽器の吹奏の壮大さと、前後の部分の荒々しい猛々しさの対比が効果的。最終楽章はまさにリズムの饗宴だが、ここでも決して煽ることはしない。確実にリズムを刻み、確実に音符を響かせることにより、自然に音楽は盛り上がっていく。
総ての音を強く確実に鳴らすことにより、頂点を築いていく。この強靭とも思える確実性が金の真骨頂。
コーダでは、総ての楽器を力強く鳴らせることにより、そしてリズムを確実に刻ませることにより、すさまじいまでのエンディングを築いていく。
一時代前のベートーヴェン演奏と比較すると、ある意味垢を取り去った新鮮な、裸のベートーヴェン像が浮かび上がり、改めてベートーヴェンの音楽の凄さということを再認識させられた。
金聖響は最近の著書「ベートーヴェンの交響曲」の中で次のように語っている。
「至極あたりまえのことなのですが、いま名前をあげた指揮者全員に言えることは、それぞれの方が確固たるベートーヴェン像を持っており、主張を怠らない演奏をしている、ということです。それぞれが俗に言う「解釈」を持ち、なかには過度な「演出」を好み、楽譜に記されていないことや、異なったスタイルをふんだんに織り込んだ演奏もあります。
私はそれらのどれを否定するものでも肯定するものでもありません。私自身はベートーヴェンが楽譜に残した「音の事実」の再現を追及していきたいと考えていますが、すべての演奏から学ぶことは多々あります。(中略)ベートーヴェンの音楽は、じつにさまざまなあらゆるスタイルの演奏として残されており、どんなアプローチをもってしても。その曲の構造が崩れたり、説得力が薄らいだりすることはないでしょう。」
ベートーヴェンの音楽に対する強い畏敬と愛着の表現であり、彼自身のベートーヴェン像を打ち出したいという強い意欲がうかがわれる。
今年の12月、第9で、OEKとの一連のシリーズはひとまず完結する。超難曲、第9でどんな音楽を聴かせてくれるのか、今から楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第261回定期演奏会
2009年5月23日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 広上 淳一
チェロ シュテフアン・スキパ |
|
2006年6月、岩城マエストロが亡くなった直後の定期で指揮をとった広上淳一の再登場。あの時の演奏、モーツァルトの「グラン・パルティータ」の名演奏を思い出す。
今日のプログラムは、メンデルスゾーン交響曲1番、ハイドンチェロ協奏曲1番(チェロ、シュテフアン・スキパ)、後半がハイドン交響曲60番「うつけもの」
ハイドンのチェロ協奏曲を除いては、演奏されることが珍しい、凝ったプログラム。
しかし、OEKの規模にピタリとはまった好選曲。
最初のメンデルスゾーン、15歳の時の作曲とのことだが、4楽章の堂々とした古典的交響曲。シューベルトの初期の交響曲をも想起させるが、構成、展開、どれをとっても巧み。
メンデルスゾーンが駆け抜けた人生の速さを実感した作品。3番以降の交響曲の様な、メンデルスゾーン独特の憂愁の旋律はまだ聴けないが、その代りに生気溌剌、青年の心意気を聴かせてくれるような作品。広上・OEKも快調。生気に満ち、古典的な造形がくっきりと描き出されていた。
ハイドンのチェロ協奏曲第一番。独奏のシュテフアン・スキパに唖然。このハイドンの技巧的にも難しい作品を、いとも簡単に弾くように聴かせてしまう。低音の豊かさ、高音の輝かしさ、そして確かな音程。ハイドンの協奏曲は1番も2番も、ともすれば音程の不確かさが露呈しかねない難曲だが、このチェリストにはそれが微塵も無い。左手は、上から下までよどみなく動き、高音から低音まで豊かに響かせる。第2楽章の滔々とした歌、第3
楽章の飛び跳ねるような低音から高音への移行、見事の一言。広上・OEKも豊かに、情緒たっぷりとチェロに寄り添い快適。オケとチェロが混然一体となり響き、この協奏曲の醍醐味を存分に味あわせてくれた。今まで、名前も聞いたことのないチェリストだったが、世界は広いということを改めて実感。グルジアという政情不安定な祖国を持つチェリストだが、これから恐らく大きな注目を浴びていくに相違ない。
後半は、これも珍しいハイドンの交響曲第60番「うつけもの」ウェブで見てみると、広上淳一はこの作品を他のオーケストラと幾度となく演奏しているようで、お気に入りの作品のようだ。ある意味、ハイドンの天衣無縫、茶目っ気たっぷりの面を典型的に出した作品。「びつくり」「告別」などの系列に並ぶ作品だが、それ以上にふざけている。
全6楽章というのも変わっているが、各楽章とも創意に溢れている。特に第2.楽章の静かな部分での、とてつもないカーニバルかファンファーレのような、金管、木管の吹奏にはびっくり。第5楽章も静かなセレナーデの様な部分と管楽器による急速な部分とのアンバランス、第6楽章にいたっては、中途でコンサートマスターが指揮者にどなりこみ、急にチューニングを始めるというドタバタ。冗談音楽の原型かも。広上淳一の知的な「音楽の遊び」へのお誘いのような面白い作品であった。
アンコールに弦楽四重奏曲「皇帝」2楽章の弦楽合奏編曲版。OEKの弦楽器の厚くしっとりとした美しさを存分に引き出した聴きごたえのあるアンコール。 |
|
|
|
|
|
|
|
有田正広のヴィヴァルディ」
A・ヴィヴァルディ 「フルート協奏曲集 作品10 全6曲 (ヴェネツィア版)」
2009年5月22日 富山市民プラザ アンサンブルホール
有田正広(フラウト・トラヴェルソ) 本間正史(バロック・オーボエ)
堂阪清隆(バロック・ファゴット) 戸田薫(バロック・ヴァイオリン)
パウル・エレラ(バロック・ヴァイオリン) 成田寛(バロック・ヴィオラ)
山本徹(バロック・チェロ) 西澤誠治(バロック・コントラバス)
有田千代子(チェンバロ) |
|
ヴィヴァルディ時代の古楽器を使った、珍しい演奏会が、日本の古楽器演奏家のトップに位置する方たちの演奏で開かれた。
演奏曲目も「フルート協奏曲 全6曲」の全曲演奏という極めて珍しいもの。
プログラムと解説によると、この協奏曲集は従来、原典版でない、編曲版で演奏されてきた。トリノの国立図書館で保存されている原典版は、編曲版と楽器編成も全く異なり作品時代が別の作品の様なものとのこと。有田正広はこの原典版を再現し、20数年前より演奏してきている。今日の演奏会は、この原典版をヴィヴァルディ当時の楽器(レプリカも含め)を使用し、全曲演奏を行うという貴重なコンサート。
独奏のフラウト・トラヴェルソはフルートの原型のようなもので、当然木管で、バルプ類はほとんどなく、日本の横笛に近い楽器。当時は、リコーダーが主流であったようで、この作品集もリコーダーで演奏される場合もあるようだ、その他の楽器も現在の楽器の原型のようなもので、管楽器はバルプ類が少なく、弦楽器はガット弦が使用されている。それ故に、演奏は非常に難しい様に思われる。そこから出る響きは、素朴で温かいが、それでいてメリハリが効いていて、音は大きくはないがしつかりとした音質。古典派から、ロマン派と進むにつれ、演奏されるホールも大きくなり、それにつれ楽器も当然豊かな音量を要求されるようになり、改良され、元の楽器とは大きく異なるものへと変化していったことが、このような古楽の楽器を聴くとよく理解できる。
であるから、ヴィヴァルディの作品を聴く際、モダンな楽器での演奏では、当時の作品の本質から離れたものを聴くことになり、やはりこのような当時使用された楽器で聴くことが作品の本来の姿を聴くことになるのだろう。
有田正広はこの古楽の分野での日本の草分けであり、又今日演奏に加わったプレーヤーも古楽分野で活躍している方ばかり。非常に充実した演奏を聴くことができた。
フラウト・トラヴェルソの音質は、温かく、優雅。ヴィヴァルディ独特の装飾音など、この楽器で演奏されると。実に心地よい。有名な「ごしきひわ」など、モダンのフルートで演奏されると、華やかで輝かしいが、どこか金属的。このフラウト・トラヴェルソではころがるような装飾音がまろやかで、いとおしい。
他の管楽器も同様だが、特にバロック・ファゴットの音色が印象的。ヴィヴァルディはファゴツトが好きだったのか、実に効果的にこの楽器の特色を生かし、活躍させている。
弦楽器は、チェロがエンドピンが無く、抱えるように演奏される以外は、見た目には変わらないが、弦にガット弦を使用しているために、音質はややざらざらしており、強弱の差も滑らかにではなく、ゴツゴツとした感触がある。
モダン楽器で演奏されるヴィウァルディが華やかで、ゴージャスなのに比較し、古楽器での演奏は、激しく、緊張感に満ち、細部までクリアであり、劇的でさえある。
この作品集の半分にそれぞれ、「海の嵐」、「ごしきひわ」、「夜」と表題がついているように、音楽で描写を行う作風がヴィウァルディには多いことがうかがわれる。それを表現するのに、各楽器の特長を駆使して表現するので、モダンな楽器で演奏するのと当時の楽器で表現するのとでは、当然現れる音楽が異なってしまう。今日の演奏では、なるほどこのような表現方法だったのかということを、明瞭に、クリアに聴くことができた。有名な「四季」なども標題音楽の典型であるので、やはり当時の楽譜、楽器で演奏されるべきなのであろう。
アンコールに「海の嵐」の最終楽章が再度激しく演奏された。「僕も今年還暦なので、この作品の演奏も今日が最後になるかもしれません。」というアンコール前のコメントであったが、まだまだ若く、是非色々な演奏を聴かせて欲しいものである。 |
|
|
|
|
|
|
|
マリア・ジョアン・ピリス ピアノリサイタル
2009年5月10日 入善コスモホール
ピアノ マリア・ジョアン・ピリス
チェロ パヴェル・ゴムツィアコフ |
|
前々から是非聴きたいと念願していたマリア・ジョアン・ピリスが入善コスモホールにやってきた。
私の明瞭でない記憶をたどると、40年ほど前に東京でヨーロッパ室内管弦楽団と共演したときのピアニストがマリア・ジョアン・ピリスだったと記憶している。その時確かモーツァルトの協奏曲を演奏したのだが、今もその温かく、誠実な演奏が記憶の底に残っている。
最近では、オーギュスタン・デュメイと共演のベートーヴェンのヴァイオリンソナタの素晴らしいピアノに心奪われた。
今回の日本公演はチェロのパヴェル・ゴムツィアコフという若手とのデュオと独奏。
ショパンプロだが、非常に個性的なプログラミング。
まるで、ショパンの死へのオマージュの様な重いプログラム。
前半が、ショパン(グラズノフ編曲)、ピアノとチェロのためのエチュード第19番嬰ハ短調、ピアノソナタ第3番ロ短調、リスト「悲しみのゴンドラ」(ピアノとチェロ)そして後半が、2つのマズルカト短調(Op67-2)とイ短調(Op67-4)、チェロとピアノのためのソナタト短調、マズルカへ短調。
ショパンというと、ロマンティックでセンチメンタル、そしてある面華麗というイメージがあるが、この日のプロは、死の3年前からの最晩年の作品、後半は特に死の年の作品と、非常に暗く重いプログラム。
演奏会の構成も、楽章間は勿論、曲間の拍手も禁じるなど、極めて音楽の精神的緊張感の持続を大切にしたものとなっていた。そして、最後のマズルカの後は演奏者は沈黙、アンコールも無しという異例のコンサート。チェロ奏者はピアノの独奏時には、舞台から退出せず、舞台右手の椅子に座って演奏に耳を傾ける。後半ではピアノの譜めくりの方も同様という徹底ぶり。ピリスのこのリサイタルに寄せる深い思いが伝わってくる構成。
この日はコスモホールに珍しく完売となった満員の聴衆も、緊張感に満ち満ちた、重い演奏会を体験することとなった。
最初の、エチュードはグラズノフの編曲によるチェロとピアノという変わった演奏。チェロの太く、重々しい響きが印象的。
前半の中心、ソナタの3番。甘く、感傷的になるのを極力排除、しかしロマン的な旋律が満ち満ちている。禁欲的な、それでいてショパンの激情があふれているスケールの大きなダイナミックなドラマ。もう少し柔らかいピアノを想像していたが、むしろたたきつけるような激情の激しさ。ショパンは決して弱々しい、青い顔をした青年ではないということが強く印象付けられた。
前半の最後はリストの「悲しみのゴンドラ」。チェロとピアノで演奏されたが、これもリストの印象を覆されるような、極端に音の数の少ない、それでいて一つ一つの音に重い感情が宿っているような演奏。華麗で技巧的なリストとまるで異なる。
前半を通して、演奏会では珍しい、高揚した感情ではない、うつうつとした重さが残った。
後半も前半同様、深く沈潜した感情が充満。3つの最後のマズルカをはさんで、これも絶筆となったチェロとピアノためのソナタをはさむという構成。
マズルカは、ここではその舞曲的な雰囲気を失い、暗いが、透徹した響き。モーツァルトや、ベートーヴェンが晩年に達した、諦観、しかし人生へのいとおしみ、そして憧れの様な感情が、ショパンの晩年にも満ち溢れていることを改めて実感。
チェロとピアノためのソナタでは、チェロの重々しい痛切な歌。3楽章ラルゴでのピアノの透徹した憧れを感じさせるような、重いが、人生の遍歴がそこに凝縮したような響き、忘れられない響きとなる。
全てのプログラムの終了後、主催者はサービスのためか、演奏者との対話の時間を設けたが、このようなプログラムでの後では不要どころか、ある意味興ざめ。
この演奏会の思いをお互いに胸の中で反芻しながら、帰路につきたいものであった |
|
|
|
|
|
|
|
ラ・フォル・ジュルネ金沢
5月3日~5月4日 石川県立音楽堂他 |
|
いよいよ、ラ・フォル・ジュルネ金沢本番。昨年は一日のみの鑑賞だったが、今年は一泊して2日間、計16回のコンサートを鑑賞。
生涯のコンサート鑑賞の歴史の中で、2日間で16回ものコンサートを聴くというのは、勿論初めてであり、今後もあるかどうか。ラ・フォル・ジュルネ金沢ならではの楽しみ方ではある。
全体として、昨年に比較し、運営面も大幅に改善され、混乱も少なく、内容も充実した音楽祭という印象。
まず、全指定席制としたので、昨年のように廊下に並ぶという苦行がなくなったのがありがたい。その反面、多くのコンサートを聴こうと欲張ったので、移動時間が短く、極めてあわただしい聴き方となったのは仕方ないことか。別表に今回聴いたコンサートの一覧を載せたが、時間を見てわかる通り、ホール間の移動時間が最短5分間、多くが10~15分であるので、必然的に走っての移動となった。食事をゆっくりとる時間も無かったというのが正直なところ。欲張るのも程度問題と反省。
今年も大変な賑わいで公式発表によると昨年より6,000人多い、93,000人余りの参加数とのこと。1地方都市での音楽祭としては驚くべき数字。どのコンサートもほぼ満席、多くのコンサートは立ち見が出るような状況。
そして、目立ったのは子供連れの家族が多かったこと。子供への門戸を開放したことが、多くの家族連れが参加できるコンサートとなったようで、市民コンサートとしての一定の成果をあげたといえる。将にラ・フォル・ジュルネの精神が生かされた音楽祭となっていた。第一回が物珍しさの観客が多かったとすれば、今年のこの数字はこの音楽祭が根付いてきたこと、そして楽しみにしている市民が多かったことを示しているのではないだろうか。今後、倉敷、草津、別府、松本、宮崎の様な音楽祭が、その音楽祭を楽しみに全国からファンがあつまるように、ラ・フォル・ジュルネ金沢が金沢名物の音楽祭となり、全国のファンを呼び寄せることが期待できそうだ。
今年はテーマの作曲家が「モーツァルト」 150回程のコンサートを通しても、ごく一部の作品のみとなるのは当然。それでも、各ジャンルにわたって内容の濃いコンサートが多かった。
まず、オーケストラ。今年は、レジデンスオーケストラといえるオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)と、オーヴェルニュ室内管弦楽団、ポーランドのシンフォニア・ヴァルソヴィア、桐朋アカデミーオーケストラ、早稲田大学交響楽団が参加。そのうち聴けたのは、オーケストラ・アンサンブル金沢、シンフォニア・ヴァルソヴィア、桐朋アカデミーオーケストラの3つ。
OEKは井上マエストロの下で、充実した、そして溌剌とした演奏。交響曲はオープニンクの41番「ジュピター」以外は27番のみ。2日には35番「ハフナー」が演奏されたようだが、もう少し交響曲をとりあげてほしかったという思いはある。その中で「戴冠式ミサ」は、合唱の「京都バッハ合唱団」の熱演とあいまって、輝かしく、祝典的、溌剌とした演奏を聴かせてくれた。
ピアノ協奏曲の伴奏が21番(仲道郁代)と27番(アンヌ・ケフェレック)
27番のアンヌ・ケフェレックの素晴らしい演奏を好サポートしていたのが印象的。
ポーランドのシンフォニア・ヴァルソヴィアはポール・メイエの指揮で40番の交響曲、ゴルカ・シエラの指揮での最後のコンサートでの「レクイエム」。東欧のオーケストラらしい、落ち着いたトーンの、やや暗めの音色がOEKの明るさと好対照をなし、面白かった。
クラリネットの名手、ポール・メイエは40番の交響曲を感傷的にいじくらない、古典的な均整のとれた演奏としていた。
このオケのやや暗めの音色が「レクイエム」にはぴったり。ゴルカ・シエラの劇的な音楽の作り方も効果的。オーディションで北陸3県から集まったという「ラ・フォル・ジュルネ合唱団」も大変な熱演。オルガンの厚い響きも加わり、音楽祭の締めくくりにふさわしい熱演となった。ただ、モーツァルトの絶筆となった「涙の日」以降は、明らかに音楽の質が異なり、やはりこのジュスマイヤー版を演奏するかどうかは問題を含んでいる。
最後にアヴェ・ヴェルム・コルプス。静謐な、厚みのあるトーン、素晴らしい合唱。
桐朋アカデミーオーケストラは富山市にある桐朋アカデミーの学生によるオーケストラ。この学園の設立には、紆余曲折があり、富山市民の中には市からの学園への援助に対する根強い反対もあったようだ。はたして、この学園の設立が富山の文化の向上にどれだけ寄与したかというと、確かに疑問が残る。作っただけで、市民に何のアプローチもしようとしていない。このようなオーケストラが存在することも富山市民の中では殆どが知らない。定期演奏会は開かれているのだが、いつも閑散としている。そのオーケストラを金沢で聴くことになったのは富山市民としては複雑な思い。それも、コンサートホールが立ち見が出るほどの盛況。本来なら富山でこのような状況が作り出さなければいけないのにという悔しい思いが、富山市民の私にはある。
金沢にOEKがあり、県立音楽堂があり、「音楽の街金沢」というイメージが定着しつつあうことと、富山の音楽文化の現状との格差が残念である。しかし、ラ・フォル・ジュルネ金沢が北陸のオーケストラとして桐朋アカデミーオーケストラを招へいしたことは、北陸の音楽祭という自覚の高さであろう。指揮が井上マエストロで、ピアノ菊池洋子。1番のシンフォニーと20番のピアノコンチェルト。学生のオーケストラということで、おとなしく、響きもややか細いが。井上マエストロはOEKを指揮する時以上に大きなジェスチャーで、「もっと音を出せ」というように指示している。そのため、音楽が進むにつれて、響きがよくなり、大きく音楽が膨れ上がっていくのに感心。やはり、指揮者の力は大きいと改めて実感。
器楽では、ピアニストが多いのが目立つ。聴くことができたピアニストは、菊池洋子、仲道郁代、アンヌ・ケフェレック、アンドレイ・コロベイニコフ、リディヤ・ビジャーク、それにほんの少しだけだったが江尻南美、鶴見彩。
それぞれのピアニストのモーツァルトへのアプローチに興味があった。
一番印象に残ったのは、アンヌ・ケフェレック。モーツァルト最後の27番の協奏曲。2楽章、3楽章など、その透徹した響き、そして深い思索の表現はこの最後の協奏曲に託したモーツァルトの人生への諦念といつくしみがにじみ出ていた。3楽章の「春への憧れ」の旋律の淡々とした透明さ。貧困のどん底にあり、死を前にしたモーツァルトの澄み切った心情が痛切であった。
菊池洋子は、協奏曲が20番、ソナタが16番、17番、他に小品。菊池のモーツァルトへのアプローチは、ドラマ性。繊細さよりも、大柄な劇的緊張感を表現。それが、20番の協奏曲、後期のピアノソナタという選択となったのだろう。ピアノソナタはアートホールという小さいホールのせいもあったが、迫力に満ちた演奏。ソナタ、協奏曲の2楽章などはもう少し落ち着いた静けさが欲しい気はした。
仲道郁代は21番の協奏曲、初期の4、5、6番のソナタ、そしてポール・メイエらとの室内楽。この選曲も、菊池と対照的で、モーツァルトの一面である、明るい叙情、そして端正な古典美を志向しているよう。破たんの無い整った演奏。ある意味、強烈な個性が乏しいきらいもある。
アンドレイ・コロベイニコフは、ソナタ15番とピアノ四重奏曲。非常に個性的な、強烈な音の主張をもったピアニスト。モーツァルトの音楽の中に、これだけの沢山の要素があるのだということを主張するような演奏。私は聴けなかったが、短調の作品のみを弾いたコンサートは素晴らしかったよう。四重奏曲の協演は、桐朋学園のメンバーのウェールズ弦楽トリオ。優秀なトリオだが、主張が乏しく、アンドレイ・コロベイニコフが盛んに挑発するのだが、乗りきれないもどかしさがあった。技術的に優秀なだけではどうにもならないところだ。
リディヤ・ジャークはファニー・クラマジンとのヴァイオリンソナタ。ヴァイオリンソナタといいながら、実際はピアノの活躍が著しいソナタで、このビアニストも華やかで大きなスケール。フランス系のビアニストらしい外に向かって大きく歌い上げるようなおおらかな明るさ。共演のファニー・クラマジンは26歳ということだが、まだあどけない顔つき。音楽も大柄で、主張も強いが、ややモーツァルトにしては荒削りの面がある。これも、アートホールという小ホールなので、大きなホールで聴くと印象が変わるかも。
ピアニストの中で、「能舞」と共演の際の、20番のピアノ協奏曲2楽章を弾いた江尻南美が強烈な印象。魂のこもった響きといおうか、実に深い思索性を感じさせるピアニスト。ほかのソナタや協奏曲も聴いてみたかった。
室内楽では、モディリアーニ弦楽四重奏団が出色。男性ばかり4人の団体だが、その音色の明るく、輝かしいことはこの上ない。なるほど、フランスの四重奏団と思わせる。モーツァルトのラテン的な明るさを、的確に表現している。弦楽四重奏曲の14番k.387の2楽章の中間部の劇的な表現。3楽章の表情豊かなニュアンス、4楽章フーガのきびきびした音のつながりなど、この作品の面白さを堪能。ハイドン(Op-77-1)も古典的な形式感をきっちりと保ちながら、豊かな充実した響きを聴かせてくれた。
更に、この四重奏団は工藤重典とフルート四重奏曲2番k.285a、ポール・メイエとクラリネット五重奏曲k581を、豪華な共演で聴かせてくれた。どちらも管楽器の名手。息の合った気持の良いアンサンブル。
室内楽では、他にクラリネットのポール・メイエ、ビオラのジェラール・コセ、ヴァイオリンの戸田弥生、ビアノの仲道郁代という、名手ぞろいのコンサートもあった。
珍しい、ヴァイオリンとビオラの二重奏曲k.424での、戸田弥生とジェラール・コセの二人の息遣いが聴こえるような重奏は、聴きごたえ十分。戸田弥生は、実に深々とした音色、ジェラール・コセの年輪を感じさせるビオラとぴったり身を寄せ、しみじみとした歌を聴かせてくれた。ポール・メイエは指揮者として、勿論独奏者として今回のラ・フォル・ジュルネでは大活躍だったが、このコンサートでは珍しいクラリネット、ビオラ、ピアノのための三重奏曲を演奏。これも、室内楽の楽しさを十分味あわせてくれた。
朝は、高校のブラスバンドのコンサートが各日に開催、3日は高岡商業が池辺慎一郎の指揮で自作「アマデウスのピアノが聞こえる。」を演奏。主に後期のピアノソナタのテーマを基にアレンジされた楽しい作品。オルガンも加わりゴージャスな響き。ブラスの豪快な音色をコンサートホ-ールいっぱいに吹き鳴らした。朝のコンサート、それも高校のブラスバンドなのに会場は大入り。高校生たちも気持ち良く演奏できたようだ。
最後に金沢の音楽祭らしいコンサート。能舞と琴によるモーツァルト。
ピアノ(江尻南美)とOEKのアンサンブルに合わせ演じられた、ピアノ協奏曲の20番2楽章。能「葵上」をモチーフとした舞いということだか、深い悲しみをたたえた旋律にあわせゆったりと舞う女の舞い、中間部では一転して劇的な音楽の表情に鬼の面で激しく舞う。
そして、また静寂が戻り鬼は静かに退散していく。モーツァルトのこの楽章で語りたかった、人間の優しさ、醜さ、いやらしさなどを能舞いで見事に表現していた。舞の藪俊彦氏は加賀宝生流の名手ということだが、モーツァルトの音楽への深い造詣に、ジャンルを超えた芸術家の理解の深さを見た思い。先述したが、江尻南美のピアノが素晴らしかった。OEKアイネ・クライネ・ナハト・ムジークの演奏に合わせて、2楽章で胡蝶の舞いも演じられ、こちらはあでやかな舞い。
ほかに石川県箏曲連盟による。箏曲の合奏で、ピアノソナタk.311の1楽章と3楽章「トルコマーチ」が演奏された。琴によるモーツァルト、池辺先生流にならうと「ことによると、面白い。」
こうして2日間にわたり、16回のコンサートで、モーツァルトを堪能。
この音楽祭の性格上、オペラはアリア集のコンサートのみで、その点は残念ではあったが、いかに広大な世界をモーツァルトが築いていたかの一端を改めて実感した。
ラ・フォル・ジュルネならではの音楽の聴き方ではあった。
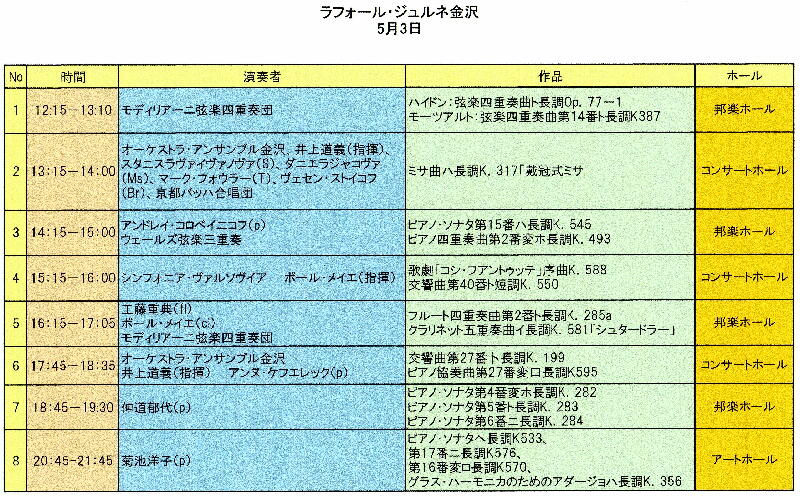
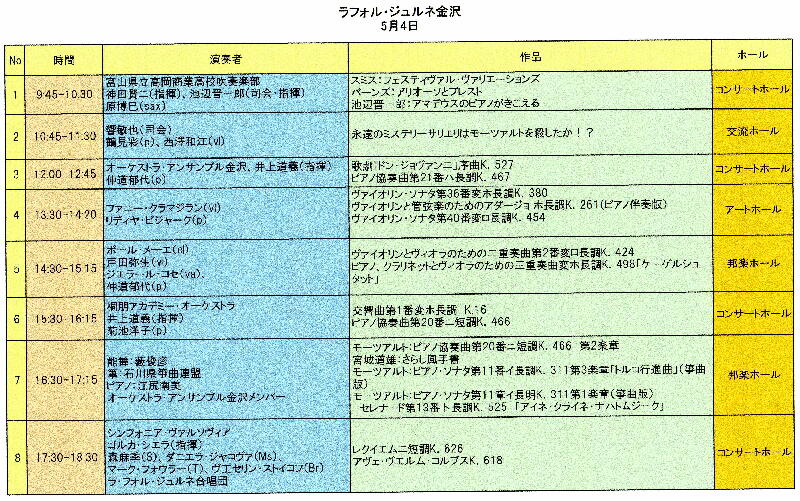
|
|
|
|
|
|
|
|
ラ・フォル・ジュルネ金沢 オープニングコンサート
2009年 4月29日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
ピアノ 中林 理力
ソプラノ スタニスラヴァ・イヴァノヴァ
バリトン ヴェセリン・ストイコフ |
|
いよいよ、今年もラ・フォル・ジュルネ金沢が開催。今年のテーマはモーツァルト。
全公演数は有料・無料公演合わせて150公演とのこと。それにしても、地方都市でこれだけの公演数は異常なほどだ。それがほぼ満席に近くなるとするとこれも驚き。
金沢駅周辺はお祭りムード。鼓門の下では、午後1時より泉野小学校のマーチングバンドがファンファーレ、モーツァルトメドレーを演奏、駅周辺に音楽祭の雰囲気をまき散らしていた。
中心の音楽界は5月2日~4日に開かれるが、開会は今日のためオープニングセレモニーとコンサートが行われた。
昨年は8万人を動員し、音楽堂周辺は大変な混雑。今年は昨年の教訓か、全公演を指定席としたので、昨年のように廊下に並ぶというような苦労は無いのがありがたい。
しかし、それでもオープニングコンサートは大変な人気のようで、1階2階とも立ち見が出るような盛況。
コンサートに先立って、池辺慎一郎さんの司会でオープニングセレモニーが開催。
いつも通りのユニークなダジャレの連発で会場を和ませる。
究極は、祝電の紹介。「何故、君だけがそんなにもてはやされる?」、発信者サリエリには、思わず、ずっこける。
今年も実行委員長は前田の「お殿様」。金沢という土地には、まだ「お殿様」の実力が根付いているところが面白い。寄付金集めには、この「お殿様」、大変な実力者らしい。
さて、オープニングコンサートはジュピター交響曲がメーンだが、その前に小品が2曲。
「ピアノと管弦楽のためのロンドK382」とオペラ魔笛から「パッパッパの二重唱」
「ピアノと管弦楽のためのロンドK382」のピアノの中林理力。このフェスティヴァルのプレイベントとして今年初めから金沢の各所で開かれた「モーツァルト・ピアノマラソン」の出演者の中から選ばれたとのこと。
恐るべき中学生。一つ一つの音の艶やかなこと、そして落ち着いた雰囲気といい、もう既に大人の演奏。モーツァルトのコスチュームを身にまとっての演奏だったが、本当にそこでモーツァルトが弾いているような幻想も起させるような雰囲気を持っていた。金沢在住なのだろうか、楽しみな中学生である。
「歌劇・魔笛」からでは、二人のブルガリアの歌手の表情たっぷりな歌唱が印象的。
さて、フェスティバル幕開けの41番交響曲「ジュピター」。モーツァルトをテーマの今年のラ・フォル・ジュルネ金沢の幕開けにふさわしい、祝典的な雰囲気に満ちた演奏。
OEKにとっては十八番だろうが、この日の演奏はいつも以上にうきうきとした楽団員と指揮者の気持ちが伝わってくるフレッシュな演奏。最終楽章の大フーガの盛り上がりも見事。
私は、3日、4日と二日間、15の公演を聴く予定だが、心浮き立つシーズンである。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第259回定期演奏会
2009年4月21日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 下野 竜也 |
|
下野竜也は2007年5月の故岩城宏之の代演でベートーヴェンを振ったのがOEK初登場。新鮮で彫の深い演奏を記憶しているが、今回は自らのプログラムを引っ提げての登場。それも、「ウィーンの光と影」というテーマで、前半がウェーベルンとシェーンベルク、後半がズッペという、実に独特のプログラミング。読響などでユニークなプログラミングの演奏会を行っている下野ならではのプログラム。
前半が、下野の言う「ウィーンの影」、後半が「ウィーンの光」であろうか。
それにしても、ほぼ時期が重なる前半の二人と、後半のズッペと、これほど対照的な音楽が当時のウィーンで存在していたとは興味深い事実である。当時の世紀末ウィーンの2つの象徴であろうか。私も個人的にはウィーンを訪れ、栄華の名残のある街の独特の雰囲気を感じたが、今でもあの街には世紀末の熟れた匂いが残っていることを感じた。
ベルク、ウェーベルン、シェーンベルクは独特の音楽技法でその当時の時代をあらわした。
後期ロマン派が行き着くところまで行き着いた後には、無調、更に12音で音楽を創造していくことが、彼らの時代の主張であった。それは、その時代のウィーンの最先端を行くという自負であったろう。事実彼らの音楽には、その手法に今でも慣れない私たちには、正直、難渋さがつきまとうが、よく聞いてみるとその当時のウィーンの街の重苦しさ、そこに生きる人たちの閉塞感を聞くことができるように思う。それがその時代の一つのウィーンであるとすれば、その反面、世紀末の重い雰囲気を、軽い音楽で吹っ飛ばそうという。シュトラウス一家や、ズッペを中心とするオペレッタの作曲家たちがいる。厭世という一点では共通しているのだろうが、表現方法が全く異なる。下野竜也の名づけた「ウィーンの光と影」というテーマを聞きながら、そんなことを感じた。
ウェーベルンはバッハの「音楽の捧げもの」から「6声のリチュルカーレ」。テーマはバッハであり、旋律もバッハであるが、音楽自体はウェーベルンそのもの。印象派の絵画を思い起こすような、点描の音楽。旋律の厚みでなく、各パートがそれぞれを主張しながら、一つの音楽を作っていく。このあたりは、同じ手法を使いながら、次のシェーベルクの旋律の厚みを大事にする方法と異なる点を感じる。非常にデリケートな音楽を、下野は細かく描き上げ、OEKの各パートもあいまいさなく描き上げ、くっきりとした演奏となっていた。この様な音楽では、オーケストラの巧さが要求されるが、さすがに現代音楽に慣れたオーケスラとうことを感じだ。
シェーンベルクの「室内交響曲」。ウェーベルンと異なり、先に述べた様にシェーンベルクは音の重なり、ハーモニーを重視する様に感じる。これはやはりドイツ音楽の伝統の先に位置するものと感じるし、この音楽では無調というより調性も感じられる。シェーンベルクは、ベルク、ウェーベルンよりも尚、つかみどころの無い、難渋さを感じるのは何故だろうか? ベルク、ウェーヘルンの音楽の表現が直截的であるのに比し、シェーンベルクが論理的である故だろうか。「室内交響曲」という名称のとおり、OEKの編成にピタリとはまる大きさの作品ではあった。
後半がズッペのオペレツタの序曲集。「ウィーンの朝・昼・晩」「怪盗団」「美しきガラテア」「スペートの女王」、そしてアンコールに「軽騎兵」
アンコールを除いては比較的なじみの少ない序曲である。
序曲といっても、総て接続曲のような作品。オペレッタの中の旋律をつなぎ合わせながら構成していくのは、J・シュトラウスの「こうもり」等のオペレッタの序曲と同様。ただ、シュトラウス一家はワルツが中心となるのに比較し、ズッペは軍楽隊長らしく、マーチが中心となっている。そして最大の特徴は、独奏楽器の活躍が多いこと。各曲とも、各パートのソロが華やかに挿入されており。独奏者にとっては自らのアピールのできるおいしい作品。しかし、巧い奏者の場合であるが。その点、OEKは達者揃いと感じた。
途中で加わったギター、またドラなど、特殊な楽器の音色を生かした効果も満点。
聞くほうにとっては軽く楽しい喜歌劇序曲ではあるが、演奏は非常に難しいと感じる。
テンポの自由な変化、ワルツ、マーチなど多彩メドレーの連続、まとめていくのが大変。
この日の下野竜也・OEKは、その点巧み。すべてを生き生きとのびやかに聞かせてくれ、面白さを満喫。細部までフレッシュな演奏。OEKも指揮者の要求によく応え、乗りまくった演奏を披露。アンコールに「軽騎兵序曲」のサービス。 |
|
|
|
|
|
|
|
オランダ・ア―ネムフィルハーモニー管弦楽団演奏会
指揮 小林 研一郎
2009年3月15日 砺波市文化会館 |
|
オランダから、珍しいオーケストラ、アーネムフィルが常任指揮者の小林研一郎に率いられてやってきた。オランダというと何と言っても、コンセルトヘボウ、他にハーグ、ロッテルダムあたりのオーケストラが馴染みで、アーネムフィルという名前は知名度として高くはない。しかし、今回の演奏会を聴いて、なるほど100有余年の歴史を有するオーケストラと再認識。ヨーロッパのオーケストラの層の厚さを実感した。
音質としては、重く、ロシアの古いオーケストラと比較的似通っている感じだが、そのパワフルな音質は将にヘビー級。決して器用なオーケストラではないようだが、コントロールの巧みな指揮者に率いられると、将に乗りまくって疾走するようなオーケストラ。その点、小林研一郎は将にうってつけ、このオーケストラの底力を見せつけてくれた。
プログラムは、リムスキー・コルサコフ「シェエラザード」、後半がムソルグスキー・ラベル編曲「展覧会の絵」という、これもヘビー級のロシア物。
最初に珍しいオランダの現代作曲家ケース・オルタウス「地蔵」という日本初演の作品が演奏された。日蘭貿易400周年記念委嘱作品ということだが、日本のお地蔵さんの民俗信仰に題材を得た作品。重々しく、重厚な慟哭のようなテーマに始まり、中間部は子供たちの遊ぶ様子、鬼が子どもたちを追いかける様等が描かれ、日本の民謡を想起させる部分などが続く。金管、パーカッション等をフルに使用した大きな編成のオーケストラを巧みに使用しながら、音の洪水絵巻が繰り広げられる。現代音楽とは思えないような明瞭なテーマの展開。印象深い作品だ。
さて、リムスキー・コルサコフ「シェエラザード」。今年になって北陸での演奏回数が3回というのも珍しく、この作品の聴き比べの趣き。
今日の演奏がやはりベスト。キタエンコ・OEKの演奏も色彩的で掘りの深い演奏で美しかったが、この日の演奏は、ロシア音楽の面白さを最大限聞かせてくれた。小林研一郎独特のうねりの続くような旋律、それにのって様々な独奏楽器が繰り広げる歌は、この作品の面白さを際立たせていた。
ともかく、小林研一郎の音楽は、独特のうねりがある。テンポもゆったりと、しかし、弛緩せずに、巨大な音楽のうねりを作り出していく様は圧巻。うねりを作り出す際は、いつものうなり声まで聞こえ、音楽がそれにあわせ、巨大な波をつくりだす。木管、金管等の歌わせ方も独特。かなり、恣意的とも思えるほどテンボを動かし、微妙なニュアンスを生み出しているのだが、それが嫌味に聞こえず、自然な流れとなって心に響いてくる、このあたりがこの指揮者独特の巧みさか。音楽が緩むことなく、いつも緊張した流れの中にあるから、聞く方もかなりの集中を要求されるが、その疲れさえ心地よく、音楽の渦の中に引き込まれる。弦楽器の響きの厚み、管楽器の重厚な響きも見事。重いオーケストラが、指揮者の燃えるような情熱にコントロールされて燃え上がっていく様子は圧巻だ。
後半のムソルグスキー「展覧会の絵」も同様の演奏。
通常はプログラムのメーンを飾るような2曲を同時に演奏するというのも尋常ではないが、それを集中力を切らさずに演奏しきるというのもすごい。
ラベル編曲版ではあるが、響きは華やかというより、重厚。総てのピースが、重心がどっしりとした、暗い雰囲気を感じる。牛車では、トローボーン奏者がユーフォニュウムを演奏するという器用さ。実に心地よいビロードの様な響きのユーフォニュウム。「サムエル・ゴールデンベルクとシュミーレ」の弦楽器のぶ厚い響き、カタコンブの重く暗い雰囲気等、ロシア的な暗さを表出した演奏。終曲の「キエフの大門」では、満を持したかのような爆発。泰然としたリズムで、ゆっくりと進む隊列を表現。最後は総ての楽器の強奏。ティンパニー、大太鼓、ドラを豪壮に響かせ、堂々たるエンディング。
アンコールに小林研一郎が好んで演奏する「ダニーボーイ」。弦楽器のみの演奏だが、優美というより、これも深々とした情念を感じるような、濃い色彩の演奏。アーネムフィルの響きの厚さが印象的。
更に、ブラームスのハンガリー舞曲の5番。コバケンワールド全開。自由自在なテンポ、疾走するリズム、オケも載りまくっている。
「ヨーロッパだと、良い演奏会の時は、聴衆が総立ちで拍手してくれるので、皆さんが座ったままだと、オーケストラは今日の演奏はよくなかったのかと思ってしまう。」との言葉に応えて、聴衆はスタンディングオベーション。演奏会の盛り上げ方まで指揮していった小林研一郎であった。
音楽は将に生き物、どこを切り取っても血が噴き出しそうな演奏、それが聴衆を熱狂させる、それを痛感した演奏会。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第256回定期演奏会
2009年3月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ヴァイオリン 神尾 真由子 |
|
今日の注目は何と言っても、ヴァイオリンの神尾真由子。チャイコフスキーコンクールに優勝という、輝かしい経歴を持って、金沢デビュー。
注目の演奏家の前に、ハイドンの交響曲第100番「軍隊」が演奏された。
ハイドンの演奏は、最近はいわゆるピリオド楽器による演奏が多く、モダン楽器であってもピリオド奏法的な演奏が主流となっているようだ。今日の演奏も、ティンパニーにバロックティンパニーを使用、ビブラートもごく控えめなど、スタイルとしてはピリオドに近いスタイルと思われる。しかし、この日の演奏では、それ以上に各楽章、特に1、2、3楽章の主要テーマの歌わせ方が、私が従来聴いてきた演奏と著しく異なり、そこにまずびっくり。CDでこの演奏は発売されるようなので、その際も再確認したいが、非常に興味ある演奏であり、楽譜と照らし合わせてみて果たしてどうなっているのか、確認してみたい程である。これは、明らかに井上マエストロの指示によるものであることは明らか。どのような、意図があつてのことか、他の演奏との比較に興味深いものがある。又、第2楽章のトランペットのファンファーレでトランペツトを起立させて吹かせたのにもびっくり。マーラーの1番で、作曲者の指示により奏者が起立して吹く例はあるが、ハイドンでは恐らく前代未聞であろう。
ということで、このハイドンの演奏には驚きがいっぱい。
全体としては、井上ワールドの典型的な演奏で、明るく活発、明晰、少しのあいまいさもない決然としたハイドンで気持ちが良い。
さて、注目の神尾真由子。今日は、ブルッフの協奏曲。濃厚なロマンチシズム溢れる曲で、神尾の個性にはぴったりと思える。出だしの、太い低音の響きから、聴く者の心をわしづかみにしようとする迫力を感じる。この協奏曲独特のうねるような激しい感情の大波、そして華やかな技巧、それらが一体となり押し寄せてくる。圧倒的な迫力。聴衆に、どうアピールするかという勘どころをピタッと押さえているところはプロの独奏者として。すでに堂々たる風格を備えている。第2楽章のオーケストラとの対話、第3楽章の激しい高揚、どの部分をとっても、新鮮でエネルギツシュ。井上-OEKも、若い奏者に遠慮することなく、その熱演にこたえるかのような激しい演奏を展開、このぶつかり合いも聞きごたえ十分。
形式がどうの、どう美しく聞かせるかなどという範疇を越えた、荒々しく、生々しい音楽の魅力。この荒削りの魅力が、今後どのように変化していくかも興味あるところ。
プログラム最後は、ビゼーの「アルルの女」。通常の第一、二組曲ではなく、劇の進行に合わせたピックアップとのこと。超有名曲だが、意外に生で聞く機会が少ない。
華やかで、明るい作品という印象があるが、この日の演奏ではむしろ、音楽の底にある暗さがにじみ出ており、劇的な緊張感溢れる演奏であった。劇自体は、非常にどろどろした暗い作品であり、それを表出した演奏といえる。
最後の「ファランドール」は、狂喜の乱舞のような趣き。2つの主要テーマが錯綜し、金管と打楽器のすさまじい咆哮の内に全曲が閉じられるが、この部分のOEKの演奏はすさまじいもの。サキソフォーン、変わったドラムと、通常の編成では聞けない楽器の面白さもあり、これも井上劇場全開。アンコールに再び「ファランドール」のフィナーレが演奏され、ここでは井上マエストロが聴衆の手拍子を呼び込み、熱狂的なエンディング。
派手なパフォーマンスに目を奪われがちな井上マエストロだが、音楽の骨格がしっかりとした、細部まで目の行届いた、磨き抜かれた彫刻のような趣の演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
NHK交響楽団演奏会
2009年3月2日 オーバードホール
指揮 カルロス・シュピーラー
クラリネット ポール・メイエ |
|
私の以前の記録を見ると、N響は2003年に魚津へ、2005年に富山へ来演している。2003年のハインツ・ワルベルクのブラームスの4番は、今でも記憶に残る演奏だったが、それ以外はあまり記憶がない。それなりに、優れた演奏ではあったのだろうが、記憶に残る程の鮮烈な演奏でなかったということだろう。それは、どうも北陸来演の際の指揮者の選定にあるようだ。前回、今回の指揮者とも、どうもとりたてて特長のある演奏をする指揮者でない。いずれも外国人の指揮者であるが、日本人の若手でももっと聞いてみたい指揮者も沢山いる。地方公演ということで、そのあたりをどういう風に考えているのか、疑問に思う所である。
しかし、さすがにN響のネームバリュー、早々と、前売り完売の人気である。公共放送のオーケストラということで、料金も安く設定されているせいもあるかもしれない。
この日の演奏会の聴きどころは、何と言ってもクラリネットのポール・メイエ。5月のラフォール・ジュルネ金沢にも来演の予定だが、さすがにフランスの管、安定した技巧と、いかにも艶やかで明るい、表情豊かな演奏。モーツァルトのクラリネット協奏曲。ハゼットクラリネットでなく、普通のクラリネットを使用しているようだが、低音から、高音まで、豊かな音量で吹きぬく様は爽快である。この協奏曲の、暗い、憂いの様は、やや不足気味だが、又一面である快活さ、明るさはモーツァルトにふさわしい。2楽章のしみじみとした歌わせ方は、絶品である。やや遅めのテンポで、朗々と吹き鳴らす、弱音の響きも豊か。3楽章のコケティッシユな歌わせ方も鮮やか、名手である。
後半は、リムスキー・コルサコフ、シェヘラザード。1月から3月にかけて、3回聴くこととなる作品。ということになると、と゜うしても比較してしまう。
1月のキタエンコ・OEKの演奏に比較し、色彩感の乏しさを感じる。オーケストラの編成は、弦は18型で大きく、響きも大きいのだが、音楽としてのスケール感はキタエンコ・OEKが大きい。
細部の色付けというか、歌わせ方も平板なので、音が大きな割に、面白さが乏しい。独奏奏者が活躍する作品なので、もっと色付けの方法があるだろうにと思うが、どうも独奏者の巧みさにまかせているような感がある。であるからして、キタエンコが、カラーでカラフルであるとすると、今日の演奏はモノクロ。この作品の面白さは、発揮されない。
N響も実に優秀なオケなのだが、どうも自発性というものが感じられず、ただ優等生的に演奏すればよいという感じで、オケとしての生命力を感じさせない。これは、やはり指揮者の個性であろうか。
アンコールはブラームスのハンガリー舞曲1番。やはり、溌剌とした、生命力に欠けていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
ケルンWDR交響楽団演奏会
2009年2月26日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 セミヨン・ビシュコフ
ヴァイオリン ヴィヴィアン・ハーグナー |
|
2日間、オーケストラの演奏会が続き、連続の金沢通いとなる。
この日は、毎年この時期に行われている、東芝グランドコンサート。企業メセナの一つであろうが、比較的低料金で聞けるのはありがたい。不景気の中で、企業メセナも大変であろうが、こういう時こそ、その企業の実態が現れるとき、是非文化活動を応援してほしいものである。
今年はビシュコフのケルンWDR交響楽団の登場。昨日のOEK定期に比較して、聴衆の少なさが目立つ。やはり、2日間連続の演奏会は難しいのだろうか。
しかしこの日の演奏、聴衆の少なさを吹き飛ばすような、見事な演奏が聴けた。
やはり、ドイツのオーケストラ、ずっしりとした重量感のある安定性のよいオーケストラである。
プログラムはシューマン「マンフレッド序曲」、ヴィヴィアン・ハーグナーを独奏に迎えてのベートーヴェン「ヴァイオリン協奏曲」、後半がブラーム、交響曲第4番という、ドイツの本道を行くプログラム。
ビシュコフという指揮者、力感、細部にわたる目配り、そして全体を見渡すしっかりとした構成感、それらが総て一体となって、重量感と高揚に満ちた音楽を作り上げる、確かな力量を持った指揮者であった。
最初のシューマンの序曲。ドイツの深い森を思わせる、厚みのあるアンサンブル。そして、シューマン独特のうつうつたる情熱があふれ、最初の曲から、ドイツのオーケストラの存在の確かさを聴くことができた。
ベートーヴェンの独奏者、ヴィヴィアン・ハーグナー。素晴らしいヴァイオリニストである。この作品、実に難しい作品で、聴くものにベートーヴェンのこの作品の凄さ、面白さを聞かせるのは至難の業といってもよいと思うが、この日の演奏は将に、この作品の総ての魅力を眼前に繰り広げてくれた。主題の展開のみならず、細部の経過的な部分まで、入念に書かれた意味のある音、それがこの日の緻密・緊張感のみなぎった演奏で明確に示されていた。決して表面的な派手さのある音ではないが、ひとつひとつのフレーズに命のこもった響きを聴くことができた。ヴァイオリンとオーケストラが対立的に対峙するのでなく、それぞれの主張をしながら、対話をしていく、それはある意味室内楽的な繊細さを要する音楽。それが表現できて、初めてこの作品の真価が現れる。そのことをはっきりと聴くことができた。
独奏者はオーケストラの語る意味をしっかりと把握しながら、それに寄り添うように奏でる部分、オーケストラも独奏者が語る時には、その意味を慎重にサポートしながら支えていく、独奏者と指揮者の意志の疎通、この作品への解釈が一致していて、この作品の巨大な全体像が浮かび上がる。ヴァイオリンの音色は勿論美しい、しかし単に美しいだけでない、気品、風格の高さがある。オーケストラの響きも実におおらかで、第2楽章、第3楽章のフアゴットの響きなど、驚くほど深く、大きい響き。
アンコールにクライスラーの無伴奏曲、「レチタティーヴォとスケルツォ・カプリース」
後半はブラームスの交響曲第4番。
プログラムの中でビシュコフはブラームスの音楽について、次の様に語っている。
「ブラームスの音楽は、たとえそれが声高に語る時でさえ、つねに親密です。私にとってブラームスの音楽が親密さの中にモニュメンタルな雄大さをもつているということが、大きなパラドックスなのです。」[解釈者にとってブラームスに関して最も難しい問題は、古典派の規範とロマン派の精神とのバランスをどう取るかということです。ブラームスは、人生にとって存在するあらゆるもの---作用と反作用、客観と主観-を葛藤や対決と調和や解決とを並置することによって統合することができたのです。]
今日の演奏は、この言葉をまさに具現していた。ブラームスの音楽の中に混在する矛盾のようなものが、表現される場合非常に難しく、部分部分をことさら強調しようとすると、音楽の流れが阻害され、一つのブラームスという人間像が見えにくくなってしまう。そして、ズタズタの部分ばかりが強調された、わけのわからない音楽となってしまう危険性があり、実際そのような演奏にも多く接してきた。
今日の演奏は、部分が全体の中でどのような意味をもつかということが、音楽的に明瞭な形で示されている。ブラームスの人間的な悩み、それを解決しようとする意志が、音楽の中に渦巻いている様が、はっきりと示される。又、古典的な形式の中で、どれほど豊かなロマン的な息吹をブラームスが描いていたかということも、明瞭である。
これは、ビシュコフという指揮者が、どれほど深く楽譜を読み込み、解釈し表現しようとしたかということが、聴衆への明確な音楽となって示されているという点で、希有な名演と言える。
最終楽章のパッサカリアにおいても、古典的な大伽藍に響く音楽でなく、ぶつぶつとしたブラームスの個人的なつぶやきが、最後には自らを鼓舞するような激しいエンディングとなっていくという昇華の過程が丁寧に描かれ、感動を呼び起こす。
これは、ブラームスを理解しやすい、典型的なスタイルの演奏といってよいだろう。
昨年、同じ東芝グランドコンサートで聞いた、ノリントンのブラームスと対極の位置にある演奏といってよいだろう。このような演奏の方が私は好きである。
指揮者はあくまでも作曲家の伝道者、下手な自己顕示欲は邪魔なだけである。それをあらためて理解させてくれた。
アンコールに、珍しい、エルガーの「エニグマ変奏曲から第9曲」。これも、厚みのあるスケールの壮大な演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第256回定期演奏会
2009年2月26日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ジャン・ヒエール・ヴァレーズ
ヴァイオリン 吉本 奈津子 |
|
先月が、ロシア物、今月がフランスと、民族色豊かなプログラムが続いているOEKの定期である。指揮者のタイプも異なり、要求される音楽も違うが、OEKの成熟度の証であろうか、好演が続いている昨今の定期だ。
今日は、フランスの指揮者、ジャン・ヒエール・ヴァレーズの登場。OEKとはなじみの深い指揮者。
プログラムは、シャブリエ「田園組曲」、サン=サーンス「ヴァイオリン協奏曲第3番」、デュパルク夜想詩曲「星たちへ」、グノー交響曲第2番。オールフランスの作品であるが、特に後半の2曲が珍しい。
ジャン・ヒエール・ヴァレーズは、瀟洒で小気味の良い演奏を聞かせる指揮者。洒脱というか、おしゃれというか、実にフランスの指揮者らしい。
シャブリエでは、出だしの管楽器の音色が、艶やかで明るい、いかにもフランス的な音色が出ているのに驚く。弦楽器の響きが、最初の曲であるせいか、強い音の際、硬い響きであるのが、やや残念。小さい作品が4つ組み合わさった、描写的な雰囲気のある作品だが、楽器の使い方など、いかにも匠の技の確かさを感じる。後の印象主義にもつながっていくような、淡い色彩感が特徴的。
次はサン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番。ヴァイオリンの名協奏曲でありながら、他のあまりにも有名ないくつかの協奏曲の陰に隠れ、冷遇されている感もある作品だが、あらためて魅力的な名曲と感じさせられた。この日のソロは、吉本奈津子。石川県新人登竜門コンサートで優秀賞を受賞、その後OEKとの協演を重ねているヴァイオリニスト。この日は、実にのびのびとした、気持のよい演奏を聞かせてくれた。過去にベートーヴェンの演奏も聞いたが、その際は巨大な協奏曲の演奏に緊張の極にあるようで、誠実ではあるが、まだ音楽の成熟度の未熟さを感じたが、この日の演奏は実におおらかで、明るく、この人のヴアイオリンの美点が最大限発揮されていた。1楽章出だしの低音の豊かな主題の歌いだしから、魅力的。自由な主題の展開と、オーケストラとの絡み合い、雄大な盛り上がりなど、この作品の聴きどころを雄弁に語ってくれた演奏。2楽章では、管楽器と独奏ヴァイオリンのこだまのような応答が気持よい。ここでのヴァレーズの丁寧なサポートが印象的。サン=サーンスの巧みな楽器の使い方を聴くことができた。
劇的な第3楽章。ヴァイオリンとオーケストラが壮大な主題を展開する部分の高揚は、十分に聴く者の心のたかぶりを誘う。吉本のヴァイオリンは、けれんさは無いが、明るく暖かい誠実さにあふれていた。アンコールにイザイの無伴奏ヴァイオリンソナタから。
後半は珍しい作品が続く。
デュバルク「星たちへ」。数分間の短い作品だが、その中にギッシリとデュバルクの思いがこめられたような美しい音楽。デリケートなガラス細工のような音楽。OEKの弱音の、アンサンブルの美しさをヴァレーズは丁寧に引き出していた。
最後は、これも珍しいグノーの交響曲。OEKの歴史に詳しいH氏の資料によると、8年前にOEKはこの作品を演奏しているようだ。それにしても、オーケストラ定期で取り上げられるのはごく珍しい作品だろう。
作品自体は、古典的な中に、ロマンティックな響きもある魅力的な作品。
形式は伝統的な交響曲で、シューベルトの初期の作品、あるいはメンデルスゾーンあたりを想起させられる。1楽章のソナタ形式など、ハイドン的な伝統的スタイル。そのあたり、が、やや古めかしさを感じさせるのかもしれない。2楽章のアダージョは、夢幻的なロマンを感じさせるし、3楽章のスケルツォはあきらかにロマン派、シューマンのフランス版のような響きも感じさせられる。このような作品でのOEKの演奏は、水を得た魚のように生き生きとしている。端正な響きのアンサンブルで、安定した演奏。ヴァレーズの的確な指揮も気持ち良い。
アンコールにビゼーの「アルルの女」からアダージョ。OEKの弦の弱音の美しさを最大限発揮。そういえば、来月定期は井上道義監督の「アルルの女」組曲 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第254回定期演奏会
2009年1月30日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ドミトリ・キタエンコ
オルガン 黒瀬 恵
ティンパニー 菅原 淳 |
|
今年の1月は音楽会も多く、今回が既に6回目。1月としては珍しい。
今回のOEK定期は、プリンシバル・ゲスト・コンダクター、ドミトリ・キタエンコの登場。
昨年10月の定期の際は、メーンがベートーヴェンの6番だったが、今回はR・コルサコフの作品が中心。キタエンコ得意の分野といってよいだろう。
前半がR・コルサコフ交響組曲「シェエラザード」、後半が珍しいプーランク「オルガン協奏曲」、そしてR・コルサコフ「スペイン奇想曲」。華やかなプロである。
そういえば、今年はR・コルサコフ没後100年ということと関係があるのか、富山でN響、砺波で小林研一郎・オランダ・アーネム・フィル、とそれぞれ「シェエラザード」をとりあげる。珍しいことである。
さすがと、うならせるキタエンコ快心の演奏。
「シェエラザード」出だしの、ヤングの独奏ヴァイオリンから心をひきつける。
相当、オーケストラを締め上げたのではないか?!と想像できるような、この日のOEKの出来だった。このオーケストラの持っている総ての美点を最大限引き出したような演奏。
かなり遅いテンポで滔々と歌う、弱音の美しさ、フォルティシモで高まる輝かしさ。
弦楽器は、ビオラ、チェロ、コントラバス等の低音部を増強していたが、その効果が大きく、厚みのある弦の響きに、管楽器が絡まっていく美しさは、この作品の色彩的で、ドラマティックな魅力を大いに聴かせてくれた。
ヴァイオリン独奏は各楽章の、シェラザードの物語の語りの特徴をそれぞれに生かし、時には優しく、時には激しく、情感タップリ。弦の低音部の増強、ホルン、トローボーン、チューバ、打楽器群の増員など、客演の奏者も加わってのOEKにしては珍しい大きな編成だが、1つのオーケストラとしてのまとまった壮大な響きが聴けた。さすがに、才人キタエンコである。大活躍の、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット等の木管郡、ホルンのトップの金星さんの見事な演奏など、個々の奏者の実力も遺憾なく発揮されていた。最終楽章の「船が岩にあたって難破」のすさまじい盛り上がりから、エンディンクの慰めるようなヴァイオリンと木管の響きで、静かに全曲が閉じられた。
客演の奏者を加えれば、このような大編成の作品の演奏も可能なのだから、たまには後期ロマン派以降の大編成の作品も聞かせてほしいものである。
後半はプーランクのオルガン協奏曲。珍しい楽器の、珍しい協奏曲。このホールのオルガンの音色を初めて耳にする。低音の強烈な迫力、高音部の輝かしい音色、そして繊細な響きも兼ね備えたオルガン。日本のオルガンの中でも名器といわれているとのことだが、なるほどとうなずける。作品は、弦楽器と独奏的な役割を果たすティンパニー、そして独奏オルガンによる協奏曲。プーランクらしい、繊細なメロディーと、独特なリズム感に満ちた魅力ある協奏曲。最初と、最後はバッハを想像させるような、トッカータ風の重厚な部分だが、中間部では、むしろ溌剌としたリズム、しっとりとした歌などがからまるプーランクの個性的な音楽が展開する。奏者の黒崎恵もしっかりとしたテクニックで堅実な演奏。
ホール付のオルガンなので、もっと活用してほしいとも思う。オルガンとオーケストラの作品は沢山あるので、今後の定期の選曲の中にも取り入れていただきたい。
最後は再び、R・コルサコフの「スペイン奇想曲」。「シェラザード」と作品番号も続いているが、作風も、独奏ヴァイオリンの活躍など、「シェラザード」とよく似ている。
ここでも、クラリネット等管楽器の独奏が大活躍。かなり、これも遅いテンポで、リズムも重い感じがするが、これがロシアの演奏なのだろう。
エンディングは、テンポを早め、全楽器を走らせ、熱狂的なフィナーレを演出。
アンコールはスペイン並びでビゼーのカルメンから。 |
|
|
|
|
|
|
|
前橋汀子 ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会 第二夜
ピアノ 江口 玲
2008年1月22日 北日本新聞ホール |
|
先週に続いて、いよいよ第2夜。3番、4番、6番、8番、そしてフィナーレ9番「クロイツェル」が演奏される。
演奏順は、3番と4番が逆となっている他は年代順。
今日も、先週と同様、緊張感と激情、雄渾さに満ちた演奏。
一晩に5曲のソナタの演奏は、相当に精神的な緊張感を保たないと不可能と思われるが、どの作品も気合のこもった渾身の演奏。
ベートーヴェンの音楽は、身体で体当たりするような演奏でなければ、跳ね返されてしまうような音楽。そして、真剣に音楽と向き合い、ベートーヴェンの声を自身のものとして再現する謙虚さがないと、とてつもなくつまらない演奏となってしまう、危険性を有している。技巧や、安っぽい演出はとても受け付ける音楽でない。ということを前橋汀子は、如実に聴衆に示してくれた。
初期の3番、4番、6番あたりのソナタでも、既に古典派の優雅さはなく、あるのは古典派の厳格な形式で、その形式もギリギリまで拡大され、一部では変奏曲でその枠を飛び出そうとするなど、随所に革新的な精神の輝きが聴ける。
そして、9番の「クロイツェル」。今回、このソナタのすごさを実感する。それまでの、ヴァイオリンソナタの中で試みてきた表現が、明確で雄大な世界として展開される。序奏のヴァイオリン独奏の重奏音が、幕開けを告げ、英雄的な激しい主題の展開。非常に明快で、聴く者の心を一瞬にしてとらえてしまう、主題の展開である。
前橋は一切の虚飾を排し、この楽器の表現の限界とも思える強い音でこの楽章を展開していく。美しく、メロディーを歌わせる必要など皆無というような激しさ。これは、初期の作品からの、このシリーズでの一貫した姿勢。
この日のピアノの江口 玲も見事なサポート。ヴァイオリンソナタというものの、ピアノがまるで主役同然に活躍するベートーヴェンのヴァイオリンソナタ。江口も前橋同様、衒いのない、誠実で大きい音楽を聴かせてくれた。第2楽章、変奏。ここでは、1楽章と一転して、気高く、浄化されるような世界が展開される。ここでのヴァイオリンの高音部の輝かしさ。それに、よりそうピアノの温かさ。第3楽章では、生き生きとしたリズムの高揚。ここでも、ヴァイオリンの雄渾な響きが印象的。たたみかけるような高揚したエンディング。
長い演奏生活で培った、表現の多彩さと豊かさは、やはり若い演奏家の比でないということを、つくづく感じさせてくれた2夜の演奏会であった。
アンコールの「タイスの瞑想曲」のビロードの様な深々とした、濃厚なロマンチシズムに、この演奏家のベートーヴェンに対すると異なった多彩さを聴く。さらにクライスラーのサービス、これも堂に入った演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
前橋汀子 ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会 第一夜
ピアノ 江口 玲
2008年1月16日 北日本新聞ホール |
|
ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会という大きな企画が、珍しくも富山で開催された。過去、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲の全曲演奏会が、OEKのメンバーで行われ、又現在進行中のショスタコーヴィッチの弦楽四重奏曲の全曲演奏(同じくOEKメンバー)もあるが、中央のプロ音楽家によるこのような試みは富山では珍しい。
前橋汀子にとって初めての挑戦ということで、東京と富山のみの開催。
前橋汀子というと、私たちの青春時代に、新鋭として大活躍し、その優美な音と、美しい容姿に、若い私も心をときめかし、聴いた記憶がある。その前橋汀子も、65歳、自分の老いを、他人の歳を見てびっくりしてしまうよう。
さて、その大ベテランにして初めてのベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会ということだが、期待にたがわぬ熱演であった。
今日は、その第一夜で、1,2,5,7,10番が演奏され、残りは来週22日。
このように、ベートーヴェンのソナタを通して聴くと、初期から後期までのベートーヴェンの大きな世界が俯瞰できるようで、改めてその巨大性に圧倒される。
9曲の交響曲の大きな世界が、ヴァイオリンとビアノという小さなアンサンブルの中にも、同様に息づいていることを改めて認識。
この日の前橋の演奏は、その巨大性を、どのように表現するかという、強い意志が感じられた。
前半の1番、2番のソナタ。1番の演奏の初め、今まで自分が勝手に思い込んでいた前橋の優美な音と、異なる、ややざらついた強い音色に、まずびっくり。初期の作品から、既にベートーヴェンの荒々しい世界が展開される。モーツァルトと全く異なる、粗野でぶっきらぼうな世界。それでいて、実に論理的で、しつこいくらいのテーマの念押し、展開。前橋は意図的に強い音を追及するなかで、初期から、既にベートーヴェンの世界は革新的であることを、理解させてくれる。
初期の後半、中期に近い5番「春」では、その意図は一層明確だ。初期に見られた、荒々しさが、激しさになっていく。音色は太く、力強い。一般的に若々しく、優雅に演奏されがちな、5番のソナタを、骨格たくましく、堂々としたソナタとして、前橋は演奏していく。そして、将に中期の7番では、それまでのソナタの集大成とでもいうべき、大きな世界が展開される。初期の、革新的な世界が、更に大きく成長し、劇的で緊張感に満ちた、人間のドラマを見るような世界が描かれる。初期のざらついたような荒々しさが、たくましく雄弁な音楽として立ち上がってくる。
そして、後期に近い10番。終楽章の主題と変奏は、後期のベートーヴェンが好んで使った形式。躁鬱とも感じ取れるような、複雑な感情の推移が感じられる。こうしてベートーヴェンは最後の透徹した世界へと踏み込んでいくのだ、そのことがこのソナタからうかがい知ることが出来る。
このように、ベートーヴェンの初期、中期、後期の入り口に至る作風の変遷を、前橋は見事に、私たちの前で聞かせてくれた。
先日は、新鋭庄司紗矢香が7番を入善で演奏、そのことについては、前述したが、1週間以内に、この新鋭とベテランのベートーヴェンを聴けたことは幸せ。
楽譜を鋭く読み込み、厳格に演奏することでベートーヴェンの世界を表現しようとした庄司、楽譜に書かれた意味を解釈し、自らの言葉で表現しようとした前橋、どちらからも誠実なベートーヴェンの音楽に対する真摯な姿勢が感じられた。
アンコールに得意な小品2曲。エルガーの「愛の挨拶」では濃厚なロマンを感じさせ、ブラームスのハンガリアンダンスでは、華やかな技巧を披露し、小品の得意な前橋の熟練の技を聞かせてくれた。
来週は、いよいよ9番「クロイツェル」をフィナーレにおく、第2夜。楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
庄司紗矢香ヴァイオリンリサイタル
2009年1月12日 入善コスモホール
ピアノ イタマール・ゴラン |
|
今年の1月は、1月には珍しく聴きたい音楽会が多く開催され、6回もコンサートに通うこととなる。又、ベートーヴェンが多いのも特徴。OEKのニューイヤーコンサートがオールベートーヴェン、今週と来週には前橋汀子のヴァイオリンソナタ全曲演奏という意欲的なリサイタルもある。そして、この日、庄司紗矢香のメインもベートーヴェンの7番のソナタ。前橋汀子、庄司紗矢香とベテランと新鋭のベートーヴェンの競演を聴けることとなった。地方に居りながらありがたいこと。
庄司紗矢香、3年ぶりの入善への登場。久しぶりの大雪にもかかわらず、満員に近い聴衆。庄司紗矢香の人気を伺わせる。
今回も前回同様、大きなプログラム。
シューベルトのソナタ第3番、ブロッホ、ソナタ第一番、ドルマン、ソナタ第2番(庄司紗矢香委嘱作品)、ベートーヴェンのソナタ第7番。すべて、集中力を要する作品ばかり。庄司の挑戦的な姿勢を見るよう。
彼女の個性である、作品にいどみかかるような攻撃的なヴァイオリンは今回のプログラムでも際立っていた。
シューベルトでは、古典的な枠組みの中で、シューベルトの歌がのびやかに歌われていた。作品の構成のきちんとした把握、主題のくっきりとした提示と展開、それぞれのテーマのもつ意味、それらが明確に打ち出され、時に歌われるシューベルト独特の旋律の歌わせ方などドキッとするような魅力を感じさせてくれた。シューベルトの音楽の持つ魅力を、一瞬のうちにわからせてくれる、これは大変な才能。作品に対する、深い読み込みのなせる技といえるか。
次は、珍しいブロッホのソナタ。シューベルトの優しいヒューマニズムから、激烈な世界への展開。効果的なプログラミングである。ヴァイオリン技巧を限界までに駆使し、激情の総てを叩きつけるような曲想を、庄司紗矢香は鮮やかに再現していた。美しい音色でなく、意図的に濁った音色を駆使し、激しい世界が展開される。ここでのゴランのピアノも激しい。叩きつけるようなタッチ。庄司もそれに挑みかかるように更に激しさを加える。
第3楽章の最後は、激しさから一転して祈りのような静けさで全曲が閉じられる。
初めて聴く作品だが、作品の意図を明快に表現した、非常に説得力のある演奏。
後半は、庄司の委嘱作品、今年初演されたアブナー・ドルマンの「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番」。作曲者自身の解説が、プログラムに詳しく載せられているので、作品の意図がつかみやすい。ヴァイオリンとピアノを2人の恋人に擬し、それぞれの人格と、出会い、別れを描くという、抒情的な作品。最近の現代作曲家の作品は、一時期の前衛的な傾向と比較し、むしろロマンティックな面に回帰しているような傾向を感じるが、この作品も詩的な美しさをもつ、小品。ここでも、庄司とゴランは緊張感に満ちた音の空間を築きあげていた。
最後は、ベートーヴェンのソナタ第7番ハ短調。中期の傑作。
ベートーヴェンの音楽の特徴である、古典的な形式を用いながら、その中で歌われる精神は、形式を超越した革新的なであるということが、明確に示された演奏。主題の提示、展開の有機的な結びつきが、明瞭に示しされ、更に、各々の主題の意味もはっきりと示され、その展開が劇的に表現される。庄司紗矢香の音楽を表現する際の、深い楽譜の読み方とその表現力の巧みさに驚く。作曲者の意思を、聴衆にはっきりと理解させる、これはこのヴァイオリニストの稀なる才能。
ベートーヴェンの音楽の持つ、革新的な精神の力の激しさを、はっきりと私たちに提示してくれる。作品に対する深い共感と、それを表現できる技術、精神性を、この若さで有していることは驚異でもある。
先日のアリス・沙良・オットは、音楽の「楽」を示したが、庄司紗矢香は音楽の持つ高い精神性を表現した。演奏中に見せた、アリス・沙良・オットの、こぼれるような笑顔と、庄司紗矢香の音楽 の伝道者のような、苦渋の表情と、将に対照的であった。
聴衆の熱狂的な拍手に応えて、チャイコフスキー、クライスラー2曲とアンコールが続き、会場の照明がともされても消えない拍手にこたえて、最後に愛らしいエルガーの「愛の挨拶」が演奏された。
ピアノのイタマール・ゴランも、いつもながらの激しい熱演。 |
|
|
|
|
|
|
|
アリス・沙良・オット withオーケストラアンサンブル金沢メンバーズ
2009年1月9日 北国新聞赤羽ホール
ピアノ アリス=沙良・オット
オーケストラアンサンブル金沢
ヴァイオリン アビゲイル・ヤング
ヴィオラ ヤノシュ・フェイエリバリ
チェロ 早川 寛
コントラバス ペーター・シュミット |
|
金沢香林坊の北国新聞社裏に、昨年秋北国新聞赤羽ホールが開館した。以前の古い北国新聞社には、北国講堂があり、学生時代に、サークルのレコードコンサート、映画会、労音の演奏会などで盛んに使用したのを懐かしく思い出す。新聞社社屋が新築され、北国講堂もなくなったが、今回北国新聞赤羽ホールとして立派によみがえったのは嬉しいことである。
ホールは約500席で、シューボックス型で、室内楽を聴くのには適当な規模である。まだ新しいせいか、音響がややデッドな気もするが、残響を適度に抑えた心地よい音楽空間となっている。
このホールで昨年よりOEK赤羽ホール室内楽シリーズが開かれ、今回は2回目。オーケストラ活動以外に、室内楽演奏の拠点としてこのような会場を持てることは、聴衆にとっても、演奏する側にとっても、有意義なことである。今後、意欲的な室内楽活動を続けてほしいものである。たとえば、富山で行っているショスタコーヴィッチの弦楽四重奏全曲演奏なども、金沢での再演があればと期待する。
さて、この日の演奏会、一昨日の定期・ニューイヤーコンサートに続き、アリス・沙良・オットの登場。
前半がアリス・沙良・オットのリサイタル。当初の予定が一部変更され、ベートーヴェンのソナタ14番「月光」、リスト、超絶技巧練習曲集から第9曲「回想」、第10曲、そしてパガニーニによる大練習曲より第3曲「ラ・カンパネラ」。後半がオーケストラアンサンブル金沢メンバーズとのシューベルト、ビアノ五重奏曲「鱒」、というプログラム。
この日の圧巻は何と言ってもリスト。将に超絶的な技巧を駆使しながら、音の絵巻を繰り広げた。弱音での柔らかく暖かい響き、クライマッックスを築く怒涛のような音の洪水、そしてメランコリックな歌。20歳という時点が信じられないというか、いや20歳という時点だからの表現というべきか、このリストには現時点での彼女の美点が最大限表現されていた。演奏中に見せる、輝かしい笑顔、まるでリストを演奏することの喜びにあふれた笑顔。音楽の「楽」を自らに、そして聴衆に与えてくれた演奏。輝かしい技巧、濃厚なロマンチシズム、キラキラときらめくような音色、リストの中にある魅力の総てが表現されていた。
ベートーヴェンは、落ち着いた誠実で、端正な演奏。ベートーヴェンの場合、モーツアルトでも別の意味でそうなのだが、楽譜の中に演奏者自らの音楽観、哲学、人生感のようなものが表わされることが要求される。そう、どのようにその音楽を解釈するかということが、怖いほど赤裸々にあらわれる音楽とでもいえるであろうか。その点、若い彼女ではまだ、食い足りない点があるのは当然で、これは今後、年齢を加えるにつれて、どのように変化していくかの楽しみとして取っておくべきだろう。その意味では、今の時点での等身大の演奏となっていた。
後半のシューベルト。オーケストラアンサンブル金沢のメンバーもアリス=沙良・オットも懸命の演奏ではあるのだが、やはり即席のメンバーという不利な点があった。
意志の統一が見られず、お互いにバラバラに弾いている感じ。室内楽は互いが自らの個性を生かしながらも、統一感のある呼吸というか、阿吽の呼吸というものが要求されるが、この点が欠けていて、シューベルトの音楽の愉悦が聞こえてこなかったのは残念。
今後、室内楽のシリーズが続き、メンバーも固定されていく中で、変化していくことを期待したい。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第253回定期演奏会
ニューイヤーコンサート2009
2009年1月7日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ピアノ アリス=沙良・オット |
|
昨年から、選曲の傾向に変化があった、OEKニューイヤーコンサートだが、今年はがらりと変化し、オール・ベートーヴェンプロ。
ワルツ・ポルカが主流の日本のオーケストラのニューイヤーコンサートで、ベートーヴェンというのは珍しいのではなかろうか。新年だから、ワルツ・ポルカという発想は、ウィーフィルの物まねあたりから始まったのかもしれないが、今年のように暗い年明けに、正月だからと言ってワルツ・ポルカというのも、しらじらしい気もする。それよりも、毅然としたベートーヴェンの音楽で、年の初めを祝うのも良いものである。今後のOEKのニューイヤーコンサートで必ずベートーヴェンというのも、新しい伝統として選択肢かもしれない。
今日のプログラムは、前半が「エグモント序曲」、アリス=沙良・オットのピアノでピアノ協奏曲第5番「皇帝」、後半が交響曲第7番。
ベートーヴェンは、OEKのプログラミングの中でも、中心的な存在。故岩城マエストロの時代から、最も多く演奏されてきたのではなかろうか。そして、昨年の金沢ラフォール・ジュルネでは、ベートーヴェンがテーマ。というわけで、やはり、今年のニューイヤーコンサートにはふさわしい。
最近では、大きい編成で演奏されることの多いベートーヴェンだが、本来はOEKの編成程度を想定して書かれたのであろうから、この程度の編成が最もオリジナルな響きに近いのではなかろうか。この日の、井上道義は、いつもながら、力のこもった筋肉質の、骨格のしっかりとした演奏。最初の「エグモンド序曲」から、峻烈な響きが聞かれた。
ほとんど、弦楽器にはヴィブラートを使わず、管楽器にも鋭い響きを要求し、ティンパニーは乾いた音質のバロックティンパニーを使うなど、徹底したマエストロの姿勢が感じられる演奏。そこから出る響きは、決して暖かいふくよかなものでなく、挑戦するような激烈さ。特に、後半の第7交響曲では、その特徴である、徹底したリズム感の高揚がすさまじい。第一楽章の序奏部の、激しい弦のパートと、やさしい木管の歌の対比に象徴されるように、剛と柔の対比がどの部分でも実に鮮やか。そして、クレッシェンド、ディミヌエンドも滑らかでなく、ゴツゴツとしている。であるが故にこの交響曲の峻烈な革新性が浮かび出てくる。早めのテンポで押しまくる第2楽章、第3楽章中間部の金管の咆哮など、楽曲をいじりまわさない、真摯な演奏。第4楽章も早いテンポながら、総てのパートを鮮明に浮かび上がらせようとする。オケの面々もついていくのが大変だろうと想像するような厳しさ。ここでも。金管は鋭い響き。終結部も決してあおることはせず、厳格な高揚の中で終わる。
ピアノ協奏曲の、アリス=沙良・オット。大曲を鮮やかに、新鮮に表現していた。20歳の若さながら、ごまかさない、丁寧な演奏が、新鮮で好感を与える。第一楽章の第2主題など、温かく気持ちのこもった響き。全体に壮大感よりも、ともかく丁寧にという姿勢が感じられた。今後、更にしたたかさ、良い意味でのアクの強さなどが加われば、更にスケールの大きなピアニストとなるのでなかろうか。
アンコールのリスト、「ラ・カンパネラ」。得意な分野であろうと感じさせる鮮やかな演奏。
キラキラと光り輝くリストで、このピアニストの現在の美点を最大限、聞くことができた。
9日には、北国赤羽ホールで、ソロとOEKのメンバーとの室内楽のリサイタルがあり、これも楽しみである。
今日は、超満員の聴衆。各階の通路のみならず、オルガン前、舞台後方まで補助席が出る盛況。NHK教育の「オーケストラの森」での放映のためのテレピカメラも陣取り、賑やか。新しい年に、幸先の良いニューイヤーコンサートとなったようだ。
アンコールにNHKへのサービスか、「篤姫」のテーマ音楽。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第251回定期演奏会
2008年11月29日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ジョアン・ファレッタ
ヴァイオリン マイケル・ルードヴィッヒ |
|
アメリカの女性指揮者、ジョアン・ファレッタの登場。彼女は機関紙によると、2006年にもOEKを振っているようだ。その際には、東京都響の定期も振っていたようだ。
前半がドヴォルザーク、チェコ組曲、独奏にマイケル・ルードヴィッヒを迎えて、ロマンス、そしてサラサーテ「チゴイネルワイゼン」、後半が現代アメリカの作曲家カーニスの「ムジカ・チェレスティス」、最後がメーデルスゾーン交響曲第4番「イタリア」。
比較的小粒の作品がそろったプログラムだが、各作品の個性をきちんと描き出した、好ましい演奏であった。指揮ぶりも実に明快で大きく、オーケストラから多彩な響きを引き出していた。
最初はドヴォルザーク2曲。チェコ組曲、演奏会で取り上げられるのは珍しい作品ではなかろうか?ドヴォルザークらしい、優美な旋律と躍動感があふれる作品。有名な「スラブ舞曲」と同時代の作品とのことだが、なるほど印象が似通っている。出だしの弦がやや硬い音質であったが、これはオーケストラコンサートでの通常のこと、楽器が温まらない為であろうか。進むにつれて、音質が柔らかくなっていく。べったりと情緒的に流すのでなく、端正に旋律美を歌わせるような、くっきりとした印象の指揮ぶり。フィナーレのリズム感、高揚はこの指揮者の真骨頂。やや、オーケストラをあおり気味にするので、楽団員の真剣さと、指揮者と一緒に突き進んでいく高揚感が迫力を生む。後半最後の「イタリア交響曲」のフィナーレもそうだが、このあたりの迫力はさすがと感じさせる。
独奏者、マイケル・ルードヴィッヒを迎えての2曲。実に、懐かしい音色をもつヴァイオリニスト。最近は硬質で鋭い印象のヴァイオリンが多いが、この方は柔らかく、かつ渋さも感じさせるような暖かい音色を持っている。フィラデルフィア管弦楽団の元コンサートマスターとのことだが、なるほどと感じさせられる。フィラデルフィア管弦楽団はオーマンディーのオーケストラとしての印象で、ど派手な先入観があるが、私はそうではなく、特に弦楽器の響きなど、ウィーンフィルにも通じる、落ち着いた美しい音色を持つオーケトラと感じていた。将に、その音を想起させるようなしっとりとした美感を感じる。
ドヴォルザークは、その音色の特徴がピッタリで、落ち着いたモノトーンのしみじみとした歌が聴くことができた。サラサーテは、もっと派手な演奏が多いが、技巧をひけらかすのでない、サラサーテの憂いに満ちた旋律をたっぷりと聴かせてくれるような演奏。
アンコールに同じサラサーテの「序奏とタランテラ
後半は、最初、カーニス「弦楽のための『天上の音楽』」(「ムジカ・チェレスティス」)
現代アメリカの作曲家だが、この作品は実にオーソドックスな、静謐な美しさに満ち満ちた作品。ワーグナーのパルジファルの「聖金曜日の音楽」を想起させるような、弦楽器のささやくような響きで開始されるが、この部分のOEKの弦楽器のさざなみのような音質は見事。途中、ヴァイオリン、ビオラ、チェロの独奏パッセージが入り、動的な部分が作られ、最後はまた静かに消え入っていく。各部分を明確に描き出した演奏。
最後が、メンデルスゾーン「イタリア交響曲」。ジョアン・ファレッタは祖父母がイタリア人のイタリア系とのことだが、そのDNAが、選曲にも表れているのであろうか。
躍動感と、この作品の生き生きとした推進力が現れた、良い演奏。
第一楽章の展開部のたたみかけるような迫力、第2楽章のしみじみとした木管の歌、フィナーレの圧倒的な迫力。この交響曲の魅力全開の演奏であった。OEKも最終楽章など、疾風怒涛の如くの演奏は見事。アンコールはバッハの「アリア」のしっとりとした歌で締めくくり。 |
|
|
|
|
|
|
|
月田秀子ファド 立山山麓チャペルコンサート
2008年11月6日 立山国際ホテル・スターライト スクエア |
|
富山での月田秀子のコンサートはこれで3回目2年ぶりのコンサート。
2回目は富山駅前のホールだったが、今回は第1回目と同様、立山山麓の国際ホテル、チャペルで行われた。
立山山麓は紅葉も終り、もう初冬。冷たい雨の降る日のコンサートとなった。
暖かいポルトガルの裏町のファドを、冷たい北国の山の麓のチャペルで聞くというのも、不思議な感覚がある。
ポルトガルギターとギターを伴奏に、この日も月田秀子は哀愁ある。心の歌を聞かせてくれた。
丁度スペースも程良いチャペルで、マイクを使用しない歌声も、ギターも、気持よく響いていた。
伴奏を受け持つ、ポルトガルギターの実に切ない響きと、低音部を受け持つギターの刻むリズムが、心地よく溶け合い、微妙な心の襞をえぐるようで、月田秀子の低い朗々とした歌声に実にマッチする。
この日は、途中に休憩を入れることなく、1時間10分あまり、月田は歌い続けた。
ファドは心の叫び。今回もそれを実感した。
シャンソンが小粋に、そして控え目に、詩を語るのに比較し、ファドはもっと泥臭く、激しく、直情的。だから、ストレートに心の内をゆさぶる。音楽の持つ、原始的な力が、率直にあらわれている。
月田は、その歌の内容を、詩の朗読のように、歌う前に語るので、歌の大体の内容は理解できるが、やはり歌詞と結びついた音楽なので、言葉のわからないもどかしさは感じる。というより、言葉が理解できれば、もっとファドが心の内に入り込んでくるのにというもどかしさ。
更に、裏町の片隅の小さな居酒屋で、ワインなどを傾けながら聴けたら、尚最高なのになとど思ってしまう。ファドとはそんな歌ではなかろうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第248回定期演奏会
2008年10月9日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ドミトリ・キタエンコ
ピアノ 小山 実稚恵 |
|
プリンシバル・ゲスト・コンダクター(首席客演指揮者とでも訳すのだろうか)のドミトリ・キタエンコの久しぶりの登場。2年ぶりか。2006年には、ピアノは小川典子でシュョスタコーヴィッチ、今回はピアノ・小山 実稚恵で、グリーグ。ヴィルトゥオーゾ的なソリストの好みのように見える。
プロク゜ラムは、ヴィラ・ロボス、「ブラジル風のバッハ第9番」、グリーグのピアノ協奏曲、後半がベートーヴェンの交響曲第6番「田園」。
ヴィラ・ロボス、「ブラジル風のバッハ第9番」。コントラバスを舞台中央に配置、低音のどっしりとした響きが印象的。この作品は色々な編成で演奏されるようだが、今回は弦楽合奏。OEKの弦のしっとりとした厚い響きが効果的。2曲目のフーガの早いパッセージと、遅いパッセージの絡み合いは見事。
グリーグのピアノ協奏曲。ここでは、小山 実稚恵のスケールの大きい音楽が展開された。1楽章出だしの有名な豪快なパッセージ、展開部の広大なテーマの堂々たる歌わせ方など、この作品の堂々とした部分の見事さと、歌う部分のしっとりとした情感を併せ持った演奏。
しっとりとした静かな部分にも、全体を覆う大きなスケール感が、音の空間に描き出され、統一感のある世界が描き出されていた。キタエンコの指揮も、ピアノを巧みにサポートとし好感がもてる。オーケストラをあおるのではなく、ピアノの表情にぴったりと寄り添うような演奏。
3楽章のエンディングでは、ピアノとともに高らかに民族の歌を歌いあげ、しつかりと全曲が閉じられる。この作品の魅力をたっぷりと描き出した演奏。
アンコールに珍しい左手のための作品。スクリャーピンの「ノクターン、左手のために」という作品とのこと。ここでも、左手一本で、まるで両手のようなピアノの世界が展開され、このピアニストの技巧の確かさに感嘆。
後半は、ベートーヴェン。2年前は、8番だったが、今回は6番。いずれも偶数番号て゜、この指揮者の好みの一端を知る感じ。
スコアの隅々まで、詳細に響かせるような、丁寧な演奏。あいまいさを嫌い、楽譜から忠実に音楽の内容を引き出そうとするような演奏。それだけに、オーケストラは正確性が要求される。今回は指揮者の要求とオーケストラの反応にややズレがみられたのが残念。このようなタイプの指揮者とは、事前に十分な時間が要求されるのではなかろうか。
音楽の構成は堅固。5楽章に頂点を築いていくのは明確だが、1楽章、2楽章はむしろ淡々と進む。4楽章の嵐の部分から劇的緊張度が高まり、5楽章の賛歌はゆつたりとしたテンポで朗々と歌いあげられる。非常に劇的な解釈。コーダぱそれまでの淡々とした進行と異なり、テンポをグット落とし、スケール大きく終了する。
アンコールはシベリウスの「悲しいワルツ」。しっとりとした弦と、中間部の管楽器の歌が印象的。テンポのゆったりとした雰囲気の濃い演奏。
来年早々、キタエンコの再演がある。得意のR・コルサコフ等の演奏で楽しみだ。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第247回定期演奏会
2008年9月18日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ヴァイオリン ギドン・クレーメル
ゲスト・オーケストラ クレメラータ・バルティカ |
|
9月に入り、ここ1週間余りで、OEKの演奏会がたてつづけに3回。それぞれ、特色の異なるプログラムだけに、オーケストラも大変であろうと想像。
今日は、今期のフィルハーモニーシリーズの第一回。今期から席替えとなり、3階の最前列を指定したが、ここの席は見通しもよく、音の抜けも大変良いようで快適。
この日は、先日の第9演奏会と同様、ギドン・クレーメルとクレメラータ・バルティカをゲストに迎えての演奏会。
プログラムは総て北欧もので、シベリウスの組曲「カレリア」(OEK演奏)、ヴァイオリン協奏曲、後半がグリーグの組曲「ホルベアの時代から」(クレメラータ・バルティカ演奏)
、ペールギュント組曲(OEK・クレメラータ・バルティカ)というもの。
2つの個性の異なるオーケストラの組み合わせで、オケの個性の違いが明確で、面白いコンサート。
プレコンサートで、OEKとクレメラータ・バルティカのそれぞれ団員による、室内楽か
演奏され、その際も、個性の際立った違いに驚いたが、本演奏会でもそのあたりが非常に面白い。クレメラータ・バルティカがどちらかというとくすんだ重い音色なのに比較し、OEKは明るい明確な音色。これは、井上マエストロの影響もあるのであろうか。それとも、北ヨーロッパの風土と日本の風土の違いだろうか。
最初の組曲「カレリア」。この作品のうきうきとした躍動感があふれた楽しい演奏。終局の行進曲のはじけるような打楽器と管楽器の響きは痛快。
この日の本命、クレーメルのヴァイオリン協奏曲。この演奏では、クレメラータ・バルティカを各パートとも前に出し、OEKは後方。クレーメルのヴァイオリンの響きとの統一性がとれた演奏。出だしの超弱音の緊張感ある響きから、クレーメルの世界。クレーメルのヴァイオリンが、ゆとりをもって、朗々と歌うのには驚く。緊張感には満ちているが、どこかどっしりとした安定感に満ち満ちている。自信がみなぎつているというか、自らの解釈によるシベリウスはこういうものという堂々とした安定感を感ずる。若い奏者のスリリングな演奏と異なり、完成された巨匠の音楽。一時期のクレーメルよりも更に音色も渋くなり、激しさよりも、風格を感じさせる演奏。第3楽章では、技巧にまかせてギラギラと弾くのでない、独特の印象的なリズム感が強調され、個性的。
井上道義の指揮は、骨格がしっかりと、響きを重厚に、クレーメルの個性と又異なる個性で、協奏曲のからみあいの面白さを感じた。
アンコールにオーケストラをバックにヘンツェンの「ロマンス」という作品。
クレーメル独特の叙情的な、静謐な演奏。
後半は最初がクレメラータ・バルティカの指揮者無しの演奏で、グリークの組曲「ホルベアの時代から。」
弦楽合奏による演奏だが、落ち着いたしつとりとした弦の響き。古典的な手法を用いながら、ノルウェイの民謡も感じさせるユニークな作品。
最後は合同演奏によるグリーク゛「ペールギュント組曲」。第一、第2組曲からの抜粋による組曲。有名な作品でありながら、生で聞くことが珍しい作品でもある。
最初の「花嫁の略奪と嘆き」の出だしの、低音弦の慟哭のような響きは劇的効果十分。
総ての曲が色彩感に満ち、激しい動の部分と静の部分のコントラストのはっきりとした、劇的効果十分の演奏。クレメラータ・バルティカの加わった弦の厚みのある響き、管楽器の冴えわたる歌、パーカッションの迫力と、色彩感も満載。最後のソルベーグの歌の消え入るような柔らかい弦の響き。印象的な終結であった。
これで終わるかと思うと、そうはいかないのが井上マエストロ。
「静かに今日は終わろうと思ったのですが-----」という言葉の後に、アンコールは何と、スーザのマーチの一部分。最初は第一ヴァイオリンのパートのみの演奏でゆっくりと始まり、途中クレメラータ・バルティカのメンバーを立たせ、最後は管楽器とパーカッションの爆発。賑やかなマエストロである。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢設立20周年記念公演
2008年9月15日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
オーケストラ クレメラータ・バルティカ
ヴァイオリン ギドン・クレーメル
ソプラノ 澤畑 恵美 アルト 管 有実子
テノール 中鉢 聡 バリトン 直野 資
合唱 オーケストラ・アンサンブル・金沢合唱団&20周年記念合唱団
合唱指揮 佐々木 正利 |
|
今年で、OEKも創立20周年とのこと。オケとしてはまだまだ歴史は浅いが、この短期間にこれだけ特徴あるオーケストラに飛躍したことは素晴らしい。次の時代は、いよいよ飛躍の基礎を築き上げる時期か。岩城マエスストロが創設し、井上道義がバトンを受け継ぎ、いよいよ好調のOEKではある。
今日の演奏会は記念演奏会で、ベートーヴェンの第9。毎年暮れに日本各地で第9が演奏されるが、OEKだけは頑として、岩城マエストロの意志も固く、暮れには第9の演奏は行わないできている。これは、見識で、第9のような大曲、難曲を、恒例的に演奏するべきでないというのは、本当にその通りで、この名作が惰性的に演奏されるのは、聴衆にとっても良い状況ではない。
というわけで、OEKとしては久しぶりの第9。期待も大きい。
今日は、OEKと関係の深い、クレーメルひきいるクレメラータ・バルティカが演奏に加わり、大編成のオケとなった。20周年にふさわしい豪華なオーケストラ。
第9の前は、ベートーヴェンの序曲が演奏されることが多いが、今日は序曲「レオノーレ第3番」。そして、うれしいことに、ギドン・クレーメルが突如出演、現代グルジアの作曲家カンチェーリの「ロンサム(孤軍)~偉大なスラヴァ2(に)、2人のGKから」という作品が演奏された。
序曲「レオノーレ第3番」。沈痛な序奏から緊張感がみなぎる。闘争的な第一主題、やさしい第2主題と、オペラを彷彿とさせる演奏。劇的な緊張感があふれる。ファンファーレは、舞台裏から。1回目と、2回目と遠近感をきっちりと描き出し、ドラマティツクな世界。やがて、英雄的な勝利の行進曲、堂々たるエンディング。隙のない演奏。
さて、急遽追加となった、カンチェーリの「ロンサム(孤軍)~偉大なスラヴァ2(に)、2人のGKから」。ギドン・クレーメルの独特な音の世界が繰り広げられる。4年前、ベルト「フラトレス」という作品が金沢と富山で演奏されたが、この作品も曲想が非常に似ている。
というより、クレーメルの個性的なヴァイオリンの為に作られた作品であるが故に似てくるのであろうか。緊張感にあふれた静謐な部分では、すすり泣くようなヴァイオリンの音色に、オーケストラが超弱音で寄り添う。そして、超フォルテシモの怒涛のような部分、これが繰り返され、悲しみに満ちた曲想が進んでいく。第9の後に、井上マエストロが、クレーメルの言葉として、「グルジアという困難な祖国を持つカンチェーリの平和への祈り」と付け加えていたが、将にその言葉通りの作品。曲想は複雑でないが、籠められた祈りは複雑。音楽の持つ力の大きさを感じる。第9の前にふさわしい作品であった。
さて、本命の第9。久しぶりに聴く生の第9。富山でも毎年演奏されるが、お祭り騒ぎの第9は厭なのと、アンコールに恒例のように演奏される「聖しこの夜」「ほたるの光」に嫌気がさして、最近は行ったことがない。
この日の井上マエストロは気合いが入っていた。
1楽章は、むしろ淡々と進む。ここで、頑張ってしまうと4楽章まで、ドラマがもたないというような慎重な演奏。出だしの霧の向こうから主題が現れる部分も、衒いのない率直な演奏。展開部の怒涛のような部分も、やや控え目。
2楽章のスケルツォ。ここでは、ティンパニーが遠慮なく炸裂。すさまじい暴力的ともいえる演奏。ベートーヴェンの怒りのすさまじさか。時にはシニカルにも思えるこの楽章が、荒れ狂う嵐に聞こえる。
第3楽章は、この交響曲の一番難しい部分と思う。この楽章で納得した演奏というのは数少ない。第一主題の好ましいテンポ、そして優美な第2主題と、心地よい流れが続く。中間部の転調に次ぐ転調で、音楽は複雑な様相を帯びる。ここでの弦のピチカート、そして木管の響き、よく言われる「天国的な」不思議さが描かれていた。2回のファンファーレに続く終結部はややテンポを早めて、終結部に進む。この部分のテンポはやや急ぎすぎのように感じたが、楽譜の指示はどうなのだろうか?
そしてフィナーレ。序奏部と有名な歓喜の主題の演奏は、淡々と進む。そして、テノールの独唱に続く「歓喜の合唱」で、喜びが爆発する。この部分に到達するために、1.2・3楽章があったのだという構成感がはっきり認識できる演奏。合唱の喜びにあふれた躍動感が素晴らしい。
中間部のマエストーゾの部分も、宗教的な荘厳さに満ち溢れている。
そして、コーダの部分、ここでは満を持したように、テンポを思い切り落し、そして終結部のプレストになだれ込み、最後の和音をたたきつける。最後まで、崩れの無い演奏。
各独唱も名唱、そして合唱団、100名あまりだが、その生々しい歌声は、この作品にぴったり。躍動感に満ち溢れた合唱。
井上マエストロの全楽章を見通した、熱情にあふれながらも、冷静さを失わない、堅固な演奏という印象。この作品、長大なだけに、どこかの部分で妙な色気を起こすと、収拾のつかない演奏となりがちだが、この日の演奏は統一感のある堅固な演奏と感じた。
当然アンコールはなし。
OEKの明日への挑戦を感じさせる新鮮な第9の演奏会だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第246回定期演奏会 岩城宏之メモリアルコンサート
2008年9月10日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ピアノ 木村かおり
チェロ 荒井結子
朗読 薮内 俊弥 |
|
今年のOEKのシリース゛、マイスターシリーズに、金聖響、神尾真由子等、魅力的な演奏会が多く、今年初めてマイスターとフィルハーモニー双方の会員となった。
そのマイスターシリーズの第一回定期、そして今季のOEKの初定期。ということで、暫くぶりの期待。
今回は、岩城宏之メモリアルコンサート、没後毎年9月に開催され、その年の岩城宏之音楽賞の受賞者のお披露目コンサートでもある。そして、今年のコンポーザー・イン・レジデンスの三枝成彰の新作発表と盛りだくさんな内容。
演奏会に先立ち、今年の岩城宏之音楽賞受賞のチェロの荒井結子さんの授賞式が行われた。
演奏曲目は、三枝成彰の新作、ピアノ協奏曲「イカの哲学」、ハイドン、チェロ協奏曲(チェロ・荒井結子)、休憩を挟んで、ベートーヴェン交響曲第一番。
今年のコンポーザー・イン・レジデンス、三枝成彰の新作。
最初、広告のコピーを見たとき、「イカの哲学」という不思議な題名が気になっていたが、「イカ」とは「烏賊」のこと。波多野一郎という哲学者の「烏賊の哲学」という著に、中沢新一が共感し、台本を作り、三枝成彰がその台本を基とし、ピアノと管弦楽のための協奏曲を作り上げたということ。
朗読の部分(といっても単なる朗読でなく、途中朗詠のような部分もあるが。)とピアノ独奏の部分が管弦楽とからみあう複雑な構成。オーケストラもパーカッションの部分は多彩で、ドラ、ゴング、小太鼓、バチ、更には歌舞伎で使用する床を叩く拍子木のようなもの、更には、一部奏者による足踏みなども楽器として用いるという多彩な技巧を駆使している。
その多彩な音色は、さすがに三枝成彰というところだが、どうもこの非常に深い内容のテキストの部分が、わかりにくい。声がオーケストラに埋没してしまって、手元に台本があれば理解できるが、なければさっぱり理解不可能。非常に深い内容、反戦、ヒューマニズム、生物の共存というような内容が盛られているはずなのだが、それが、残念ながら音楽として訴えかけてこない。言いたいことが沢山ありすぎて、オーケストラも饒舌過ぎて、全体像が見えてこない感じ。オーケストラもピアノも、朗読も各々勝手に歌っていて、言いたいことは言っているはずなのだが、聞いている方にとっては、さっぱり理解不可能。というわけで、期待はしていたのだが、どうもさっぱり私には、理解でき難い作品。
音楽にもつと雄弁に語らすべきと思うのだが。
ハイドンのチェロの荒井結子。テクニックは確か、高音部の艶やかさなど魅力的ではある。ただ、まだ全体に平板。懸命に弾いているが、音楽のメリハリというか、訴えかける力というのは、これからの課題であろうか。
後半のベートーヴェンが圧倒的な演奏。とかく、おとなしく、ハイドン、モーツァルトの延長線上の交響曲としてとらえられがちなこの交響曲が、実際は全く新しい時代を切り開く革命的な音楽であることを、しっかりと捉えた演奏。
骨格がしっかりとしていながら、内容は自由闊達。鋭い鋭角的な演奏、特に金管のシャープな響き、バロックティンパニーの切り裂くような乾いた響きが、野性的な生々しさを感じさせる。青年ベートーヴェンの時代への挑戦の雄たけびが聞こえるような演奏。
OEKも指揮者の要求に鋭く反応し、熱気みなぎった演奏。
第1楽章は、ややテンポを抑えながら進むが、それがかえって推進力を感じさせる。細部まで彫琢の刻み込まれた演奏。第2楽章は粛然とした格調の高さを感じさせる。第3楽章は、メヌエツトというより叩きつけるようなスケルツォ、中間部の木管の優美なアンサンブルが印象的。第4楽章は、1楽章と同様、オケが走り出そうとするのを、ギュッと手綱を引き締める騎手の様。しっかりと決然と進む。井上マエストロの演奏は、ロマン的というより、いわゆる古楽演奏に近いスタイルを持っているように思える。ヴィブラートはかけているが、むしろ抑え気味。弱音から強音への移行も、滑らかさよりも、荒々しさを求めている。それらが、この交響曲の魅力の総てを明らかにしている。際立った名演。
ここのところ、昨年の金聖響、6月の沼尻竜介等OEKのベートーヴェンの名演が印象的だ。15日には第9の演奏、来年は金聖響の7番、8番と、非常に楽しみである。
アンコールはNHKの大河ドラマ「篤姫」のテーマ音楽(井上道義編曲か?)。井上マエストロらしい、ひとひねりあるアンコール。 |
|
|
|
|
|
|
|
D.ショスタコーヴィッチ 弦楽四重奏曲全曲連続演奏会 第三夜
大澤 明 弦楽四重奏団
2008年8月28日 北日本新聞ホール |
|
音楽会の夏枯れではないが、ここ2ヶ月間更新もご無沙汰していた。7月のOEK定期は、尾瀬行と重なりキャンセル、8月神尾真由美の演奏会も、孫たちのつきあいでキャンセルと、ここ2ヶ月間音楽会とはご無沙汰であった。この様なことも珍しい。
というわけで、音楽会への飢餓状況。そんなことで、久しぶりの音楽界は、餓えを癒すチャンスと期待していた。
とはいうものの、ショスタコーヴィッチの弦楽四重奏曲ばかりの演奏会。そう、柔なものではない。演奏する方は勿論、聴く方にとってもかなりの緊張感を強いられる演奏会。心の準備をしながら、会場に向かう。
それにしても、地方でこのような濃い内容の演奏会が開かれることは素晴らしい。主催した岩瀬の方たちの尽力に敬意である。
今回の演奏会第3回目であるが、諸事情で延び延びとなっていた。昨年の4月に第2回が開かれ、その年の内に全曲演奏が終了すると思っていたが、開催の報を聞かなかった。
第一ヴァイオリンのOEKコンサートマスター、サイモン・ブレンデスが本国での事情により、来日の機会が減り、演奏会が開けない状況だったようだ。今回、同じく、OEKのコンサートマスター、松井直を第一ヴァイオリンに迎え、呼称も「大澤 明 弦楽四重奏団」と改称し、新たな出発となったようだ。チェロの大澤明が中心の弦楽四重奏団であることは、以前のQuadrifoglio(《四葉のクローバー》の時と同様であるが、自らの名前を四重奏団に冠したことで、大澤明の並々ならぬ意欲を感じる。四重奏団に個人の名前を冠することは、珍しく、記憶ではかなり前、巌本真理がつけていた位である。
とういうわけで、今日の演奏会は、新発足のこの四重奏団への大澤明の強い意欲が感じられる演奏会だった。
プログラムは、4番、10番、休憩をはさんで14番。今日は作品年代順に演奏された。
非常に完成度の高い演奏というのが、一番の印象。
各奏者の技術が非常に安定していることと、各奏者の表現意欲が強いこと、そしてアンサンブルとしての水準が高いこと。
各パートが総て明確に響いている。そしてそれが時には反発しあい、時には調和し、四重奏団としての1つの個性を描き出している。
ショスタコーヴィツチの弦楽四重奏曲の面白さ、シニカル、抒情性、コケティッシユ、狂らん、ユーモア、躁鬱。それらを存分に味あわせてくれた。
4番、第4楽章のユダヤ的とも表される舞曲のリズムの巧みな表現、そして静かに舞曲が遠ざかっていく終結部。舞曲の余韻が演奏が消えた後も残像となっている。
第10番では第2楽章の激しい表現。ショスタコーヴィッチの持っていきようのない、怒りだろうか。そして、第3楽章のパッサカリア、ショスタコーヴィッチ独特の強い静かな意志の世界。怒りの後の決意を感じる。
14番も不思議な世界である。最後の交響曲、15番と前後されて作曲された作品だが、第一楽章はその交響曲を想起させる。しかし、シニカルな皮肉の後ろに、深刻なモノローグが聴ける点など、交響曲より、尚率直な自己告白が聴くことができる。第2楽章のチェロとヴァイオリンの対話、大澤明のチェロと松井直のヴァイオリンが、他の楽器のピチカートに支えられ朗々と歌う部分、印象が深い。全曲が静かに消えていく部分など、諦観と祈りを聴くよう。
ショスタコーヴィツチの弦楽四重奏曲の場合、アンサンブルの重要さは当然として、個々の楽器の独奏的な扱いが非常に巧みで、であるからして各奏者の力量が試されるようなところがあるが、この日の各奏者の演奏の確かさは見事なもの。特に、大切な低音部のビオラとチェロの熱演は聞きごたえがあった。
最近のOEKのオケとしての充実度が、なるほどこのようなアンサンブルで支えられているのだと納得した次第。
まだ2回、全曲を完了するまでには演奏会が必要だが、是非完遂してほしいと願うとともに、北陸の数少ないプロの弦楽四重奏団としての大澤明弦楽四重奏団の今後の演奏に大いに期待したい。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第243回定期演奏会 群馬交響楽団&OEK合同演奏会
2008年6月20日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ピアノ リリヤ・ジルベルシュタイン |
|
数年に1回行われる、他の交響楽団との合同演奏会。先述したが、このような試みは恐らくOEKのみがとりあげていることで、非常にユニークで、聴取にとっても他の地方オーケストラを聴くことができる稀なチャンスでありがたい。是非今後も継続してほしい試み。
この日の期待は2つ。1つは、群馬交響楽団。2つは、ピアノのジルベルシュタイン。
群馬交響楽団は日本の地方オーケストラの草分けであり、私たちの世代のファンにとっては、今井正監督の映画「ここに泉あり」でその存在を知り感銘を受けたオーケストラ。大学時代にサークルの映画界でこの映画を上映したのを懐かしく思い出す。一度聴きたいと思いながら、その機会がなく、今回40数年ぶりにその思いを果たすことができる感慨があった。
ピアノのジルベルシュタインは、アルゲリッチとデュオを組むなど活発な活動を行っているにもかかわらず、日本での知名度は何故か低く、しかし、是非一度聴きたいと念願していたピアニスト。
プレトークでは、今年のコンポーザー・イン・レジデンスの三枝成彰氏が、チャスコフスキーにまつわる興味ある話題を披露。
プログラムはオール・チャイコフスキーで、前半OEKが「ゆううつなセレナーデ」、ジルベルシュタインのピアノ、群響でピアノ協奏曲、後半が群響・OEKの合同演奏で交響曲第4番。指揮はいずれも井上道義。
最初のOEKによる、「ゆううつなセレナーデ」。ヴァイオリンがOEKコンサートマスターのアビゲイル・ヤング。ヤングのヴァイオリンは安定感があり、特に低音の美しさが際立つ。オケは第一曲目のせいか、やや不安定。大切な弱音での乱れがあったのが残念。
さて、ジルベルシュタインのピアノによる協奏曲。期待にたがわない、しっかりとした、ごまかしのない、スケールの大きなピアニスト。第一楽章有名な出だし、実に悠然としたテンポ、乱れのない打鍵、いきなりこの作品の面白さに引き込まれる。主部の早いパッセージにおけるしつかりとしたリズム感、ゆっくりとしたテンポでの歌謡性、いずれも魅力タップリ。群響の響きは、OEKに比較するとやや硬質。しかし、歴史のあるオーケストラを感じさせる響きである。
オケとの火花の散るような1楽章のフィナーレ。オケの強奏の中にも埋もれない頑強な響きのピアノ、見事なエンディング。
第2楽章は、カンタービレではあるが、ピアノは甘さに陥ることなく、清潔に歌を歌いあげる。
第3楽章は、そのリズム感に、なるほどロシアのピアニストと感じさせられる、民俗の香りというものを感じさせる。実に個性的なリズム感。オケと調和しているかと思うと、挑発するようなピアニズムも聴かせる。ピアノに挑発されるようにオケも独特のリズムを刻んでいく。スリリングな演奏、そしてエンディング。
あまりにも有名な作品であるが故の、「またか!?」という感もいだかせる作品が、実に新鮮に聞こえるのは、やはりこのビアニストの音楽に対する姿勢の真剣さによるところであろう。
後半の交響曲4番。合同のオケで舞台はあふれんばかり。弦は16型か。木管は倍管。大きい規模のオケ。1楽章の出だしの金管のファンファーレ。突き刺すような激しい金管の叫びに、度肝を抜かれる。第4楽章の出だしもそうだが、井上マエストロは、容赦なくオケを鳴らす。これは、聴く方にとっても、大きな快感であり。フルオーケストラを聴く魅力でもある。
テンポはゆっくりとしているが、決して弛緩しない緊張感がある。ロシア的な野暮くささは全くなく、テンポが遅い割には、もたれない。このあたりが井上道義の真骨頂なのだろう。
第2楽章と第3楽章の間に、オケの配置の裏と表を入れ替え、1.2楽章では群響が表に、3.4楽章ではOEKが表に。井上マエストロらしい、変わった趣向ではある。確かに、響きが変わるのを体感できる。それぞれのオケに、やはり独特の個性的な響きがあるということか。
第2楽章も妙な色付けはすることなく、美しい歌が淡々と響く。第3楽章のピチカートの合奏は、両オケの技巧の冴えを聞かせた。
第4楽章は、早いパッセージと、ゆっくりとした歌わせる部分との対比が鮮やか。
エンディングは、たたきつけるような迫力と最後になだれ込むような迫力。しつかりとした結尾。2つのオケの最高の能力を引き出した演奏といえよえ。
アンコールに、作曲家としての井上道義をきかせる自作からの一部を演奏。指揮ぶりと同様のパフォーマンス豊かな作品と演奏。それにしても、アルコールは駄目というマエストロが、アルコールにこだわるわけは?
高崎市と金沢市の友好交流都市締結の祝いとも重なり、会場内外には高崎ダルマか溢れていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第242回定期演奏会 2008年6月20日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 沼尻 竜典
クラリネット ヴェンツェル・フックス |
|
クラリネットに元ベルリンフィルの首席クラリネット奏者、ヴェンツェル・フックスを迎え、指揮にOEK初登場の沼尻竜典を迎えての注目のコンサート。
前半がウェーバー、クラリネット協奏曲第2番、モーツァルトのクラリネット協奏曲、後半がベートーヴェンの交響曲第2番。
前半に協奏曲2曲を並べた、独奏者にとっては過酷とも思える、変則的なプロ。
クラリネットのフックス、輝かしい高音から、豊かな低音まで、表情豊かに、まるでオペラ歌手のアリアの如く、歌い上げる充実の演奏。大変なテクニックだが、それを感じさせず、音楽の愉悦をクラリネットで存分に味あわせてくれる様は、将に名人芸。
ウェーバーでは特にフックスの美点が存分にあらわれ、爽快で、充実した演奏。第一楽章出だしの高温のトゥッティーの様な高らかな輝かしい音色、第2楽章のアダージョの、柔らかく深い弱音の音色など、将に同じ楽器とは思えない表情の多彩さ。
オペラアリアを彷彿とさせるような歌が満ち溢れた作品の美しさ、楽しさを存分に味あわせてくれた。
モーツァルトは、気品のある落ち着いた演奏。ここでも第2楽章の弱音の柔らかくありながら、緊張に満ちた演奏が印象的。暖かく、明るい暖色系の音色のため、モーツァルトの陰影とは若干の違和感を感じたが、それも個性か。
沼尻竜典のサポートは、やや厚ぼったい響きで、モーツァルトの繊細さにやや違和感もあったが、落ち着いた、衒いのない伴奏。
さて、後半のベートーヴェン。実に雄渾な、スケールの大きいベートーヴェン。第一楽章の展開部から終結部に至る音楽の高揚は、指揮者のストレートな気持ちの高揚が音楽に息づき、白熱のコーダ。主題がうねりのようになって展開していく。第2楽章はややそっけなさも感じたが、このあたりは若さ故か。
スケルツォの激しさ、そして第4楽章のエンディングのエキサイトしていくオーケストラの様子、特にティンパニーの乱打、金管の強奏などは、ベートーヴェンのこの交響曲の本来の激しさ、革新性を、見事に表現していた。
金聖響がOEKを振った第3交響曲を初めて聴き、「すごい指揮者」がと衝撃をうけたのと、同様の驚きがあった。
指揮ぶりも実に激しい、若いころの岩城マエストロを彷彿とさせるような感も。
アンコールにモーツァルト歌劇「フィガロの結婚」序曲。これも、歌劇の始まりのわくわくとした感情をかきたてるような、昂揚感に満ち満ちた演奏。
沼尻竜典、再登場を是非期待したい指揮者。
|
|
|
|
|
|
|
|
樫本大進・コンスタンティン・リフシッツ デュオ・リサイタル
2008年6月11日 石川県立音楽堂コンサートホール |
|
樫本大進・コンスタンティン・リフシッツ デュオ・リサイタル
2008年6月11日 石川県立音楽堂コンサートホール
2005年に入善コスモホールで聴いて以来、3年ぶりのリサイタル。樫本大進の変化を聴いてみたくて出かけた。
今日のコンサートホールは、私がこのコンサートホールを訪ねるようになって初めての聴衆の少なさ。400人程か、空席の多いことは、大きいホールにとって何か淋しさを感じる。室内楽の場合、隣の邦楽ホールという選択もあってよいと思う。それにしても、何故ここまで少なかったのか?
3年前とピアニストが、イタマール・ゴランから、コンスタンティン・リフシッツに変わっている。どちらも、独奏者としても充実した活動を行っている実力ピアニスト。ピアニストの選択に、リサイタルの成否をかける樫本の姿勢が表れているよう。
今日のプログラムは、ある意味大きい、凝ったプログラム。前半が、ショスタコーヴィッチのピアノソナタ第2番、ヴァイオリンソナタ、後半がベートーヴェンのソナタ9番「クロイツェル」。
最初のショスタコーヴィッチのピアノソナタ第2番。ショスタコーヴィッチらしい、緊張感と、深い思索、そして大きな構成感のある作品。ここでは、コンスタンティン・リフシッツの、一つ一つの音に思いを込めたような、強い意志の力を感ずるピアノの音が印象的。
第2、3楽章は特に単音の使い方に、ショスタコーヴィッチのこめられた思想があるので、表現が大変難しいと思われるが、実に深く、豊かなピアニズムである。叩きつけるような慟哭と、祈りのような静けさの交錯が巧みに表現されていた。
次のヴァイオリンソナタ。これも大変な難曲。入善での庄司紗矢香の集中力のみなぎった名演を思い起こす。樫本は、庄司のような直線的な作品へののめりこみよりも、全体の形式感を重視し、極力、激情の渦の中に入り込むのを避け、冷静に、客観的にこの作品を分析しながらの演奏のように聞こえた。劇的緊張感を重視した演奏といえる。
この傾向は、後半のベートーヴェンでも通じるものがあり、非常に考え抜かれた、苦労の跡の理解できる演奏。
しかし、それ故に、かつて樫本が持っていた、伸びやかな抒情性が薄れ、率直さよりも、「何を伝えたいのか」という点が、なかなか聴衆に伝わってこないもどかしさも感じた。
樫本も30歳近くなり、今までの自分のスタイルに壁を感じ始めていたのかもしれない。どうして表現しようかという、悩み。困惑を感じた。
ショスタコーヴィッチでは考え抜かれた構成感が、この作品のある面に合致し、ドラマ的な緊張感を持った演奏となっていたが、ベートーヴェンでは、考えすぎの点が、表現のあいまいさにつながったようで、ベートーヴェンの英雄的な雄大な人間ドラマが残念なことに卑小な世界の表現に終わってしまっていたようで、残念であった。
ベートーヴェンの音楽は、やはり、率直な音楽への傾倒が、がむしゃらなひたむきさが必要であり、解釈をする性質のものでないと思うのだが。
しかし、これは現時点の話。これだけ樫本が変化してきているということは、将来への大きな布石かもしれないし、ここから更にスケールの大きい演奏家への変貌の期待ももてるともいえる。2~3年後の演奏をまた楽しみにしたい。
長い時間のコンサートデ、時間の関係でアンコールを聞けなかったが、考えられたアンコール、ショスタコーヴイッチの「クロイツェルソナタ」という作品が演奏されたようだ。
|
|
|
|
|
|
|
|
ブルーノ・レオナルド・ゲルバー ピアノリサイタル2008
2008年6月2日 石川県立音楽堂コンサートホール |
|
私たちの世代にとって懐かしいピアニスト、ゲルバーのリサイタルが、ベートーヴェンのピアノソナタの名曲集をひっさげて登場した。かつて、若いころの豪壮な演奏を懐かしく思うと同時に、60を過ぎたであろうゲルバーが、どのように変貌しているかを楽しみに、リサイタルに向かった。
プログラムは前半が14番「月光」、21番「ワルトシュタイン」、後半が8番「悲愴」、23番「熱情」という、初期から中期の傑作をズラリと並べたプロ。こんなプログラミングのリサイタルも最近は珍しいだろう。ゲルバーが何故このようなプログラミングをしたのか、聞いてみたい思いもある。
この日の演奏、少しも老いていない、ゲルバーを再発見。
ステージに出てくる姿、不自由な足を引きずりながら出てくる姿に、かつてのゲルバーを再発見した。そして、容貌も昔と少しも変わらないと、遠目からは見えた。
最近、とみに少なくなった、ビィルトゥオーゾ的なピアニスト。ベートーヴェンの解釈も、実に柄が大きく、最近のピアニストの解釈のスケールの小ささが、再認識されるような豪壮なベートーヴェン。ベートーヴェンの巨人性がホールいっぱいに響き渡っていた。
月光ソナタの第一楽章、悲愴ソナタの第2楽章など、アダージョの楽章の、遅いテンポの、一つ一つ確かめていくような足取りの演奏は、感傷におちいりがちなベートーヴェンの演奏と一線を画し、巨大な宇宙を感じさせる演奏。そして、熱情ソナタ、ワルトシュタインの中期の激情も、大きな形式の中におさまり激しくはあるが、、決して破たんしない。弱音自体が、大きな弱音なので、強弱のコントラストも実に壮大。テクニツクも一つも衰えを見せない。ワルトシュタイン、熱情のフィナーレの築き上げ方など、まるで歌舞伎18番の見栄をみるような、壮大さ。
卑小化している最近のベートーヴェンの演奏に、「ベートーヴェンの真の姿は、そんなものでない。」と、このプログラムで挑戦をしてみたかったようにも感じた。
リサイタルで珍しいアンコール無し。これ以上付け加えることは無駄と考えたのだろう。
後期のソナタも次回は是非取り上げてほしいものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
アルバン・ベルク弦楽四重奏団 フェアウエルコンサート・イン・ジャパン
2008年5月22日 入善コスモホール |
|
アルバン・ベルク弦楽四重奏団が、遂に本年中で解散することが決定された。
解散コンサートを1月より、アメリカ、ヨーロッパ、日本で行い、今回の入善でのコンサートもその日本ツァーの中での実現となった。
入善では、私の記憶では過去3回演奏会を行っているが、そのいずれも記憶に残る名演奏だったが、今回は解散コンサートとあって、その集中力はすさまじいものを感じた。
プログラムはハイドン、ベルク、シューベルトというもので、ベートーヴェンが無いのが残念であったが、シューベルトでの激しくかつ厳しい、そそり立つような演奏は記憶に長く残るであろう。
前半がハイドン「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」より序奏、ベルク「抒情組曲」、後半がシューベルト「弦楽四重奏曲第15番」、というプログラム。非常に地味な、聴く方にとっても集中力が要求されるプログラム。
ハイドンは珍しい作品で、全7楽章、1時間近い時間を要する大曲とのことだが、今回は序奏のみの演奏。静かな、荘厳な世界が支配する音楽。緊張に満ちた各楽器の広々とした歌が印象的。
次がベルク。この四重奏団の命名の基となった作曲家の作品だけに、最後のコンサートには、どうしても入れたかった作品なのであろう。今回、2つのプロを日本に持ってきているが、他のプロでは、ベルクの弦楽四重奏曲が入っている。
2年前の金沢の演奏会では、バルトークの最後の弦楽四重奏曲が演奏され、難解な音楽ながら、内面に凝縮されたバルトークの苦悩を濃密に描き出した演奏に感銘した記憶がある。今回はベルク。全部で6つの楽章からなり、緩急が入れ替わる構成となっている。前回のバルトークと比較し、真情の吐露が直線的であるより、機能的であるがため、すさましい緊張感に満ちた演奏でありながら、ストレートに心の内に入ってこないもどかしさを感じる。これは、バルトークとベルクの作品の質の差であろうか。
後半のシューヘルト。これは、将に直球・ストレート勝負の演奏。4つの奏者のパートが総てクリアーに響き、各奏者が自らの深い自信に裏付けられた解釈を打ち出し、それがさらに4つ合わさり、一つの巨大なシューベルト像が描き出される。
第2楽章の悲哀、絶望の深さ、衝撃。絶え絶えな息の中からも、再生を模索するような慟哭。シューベルトが楽譜の中に記した意味を、これほど明確に描き出した演奏は絶後であろう。
この四重奏団のすさまじさは、個々の奏者が完璧な技術を有しているのは当然ながら、各パートがそれぞれ意味をもちながら、有機的に演奏されていることが、聞く者にとって明確に理解できる点。各パートがはっきりと聞こえながら、全体の主張が一つとなって押し寄せてくること。リハーサル時における、互いの相当な相克があつたと、想像させる厳格な演奏である。
お互いが妥協を許さない音楽づくりがある、このような四重奏団は稀である。
であるから、いつかは、解散という時期が訪れるとはいえ、今の時期での解散は、本当に残念である。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第241回定期演奏会 2008年5月10日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ジャン=ルイ・フォレスティエ
ピアノ 鶴見 彩 |
|
当初予定されていた、伝説のピアニスト・ベネディッテイ・ミケランジェリの息子、ウンベルト・ベネディッテイ・ミケランジェリが急病により、指揮者が、OEKでは馴染みの、ジャン=ルイ・フォレスティエに変更となった。ウンベルト・ベネディッテイ・ミケランジェリがどのような音楽づくりをするのか楽しみだっただけに、残念。
しかし、ジャン=ルイ・フォレスティエは手堅い演奏を聞かせてくれ、OEKも安定した響きを出していた。
プログラムは3月に続いて、フランス系の作品が中心。このあたり、井上色が出ているといえるだろう。
ロッシーニの歌劇「絹のはしご」序曲、鶴見彩のピアノでサンサーンスのピアノ協奏曲第2番、後半が、ラベル、組曲「クープランの墓」、組曲「マ・メール・ロア」という、色彩的な作品が並べられたプロ。フランスは管の国だけあって、管楽器の活躍する作品が中心ともいえる。
最初のロッシーニ、弦の透明な響き、管の明るい響きなど、従来のOEKのドイツ的な響きとは異なる響き。これは、指揮のジャン=ルイ・フォレスティエの個性ではあるが、指揮者の要求に応えられる安定したオーケストラとしての実力を、最近のOEKは身につけてきた証といえる。ロッシーニ独特のクレッシェンドの迫力も十分。
次のサン・サーンス。ここでは、鶴見彩というピアニストの鮮やかさにびっくり。金沢出身で、石川県の新人登竜門コンサートでデビューしたピアニストということだが、私にとっては未知のピアニスト。テクニックも無論だが、表現力の強さが目立つ。サン・サーンス独特の派手なロマンチィシズムを十分にまきちらし、技巧的な部分と、濃厚な歌とが、随所に聞かれた。派手な管弦楽伴奏に負けることなく、堂々と鳴らす音は見事。
アンコールにプーランクを演奏。ショパンかと考えたほど、ロマンティックな作品であり、演奏だったが、休憩時間に掲示を見ると、「プーランク、15の即興曲より、エディト・ピアフの思い出に捧ぐ」とあった。今後、注目していきたいピアニスト。菊池洋子もそうだが、OEKはなかなか優れた新鋭ビアニストを紹介してきているようだ。
休憩をはさんで、ラベル2曲。小編成のオーケストラ向けの作品だが、その中で管楽器、打楽器は豊富に使用され、ラベル独特の色彩的な管弦楽法が光る作品。
組曲「クープランの墓」は、宮廷音楽へのオマージュのような作品。ラベル独特のたゆたいとも形容できるような世界に、不思議に宮廷音楽のリズムが浮かび出る。ここでは、打楽器は一切使用されないで、静謐な舞曲が奏でられる。雰囲気のよく出た演奏。
最後は組曲「マ・メール・ロア」
これも、幻想的な世界が描かれるが、管楽器と打楽器の巧みな管弦楽法が見事。
特にここでの管楽器の演奏は特筆。オーボエ、フルート、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペットと、各々雰囲気の豊かな音を作り上げていた。
アンコールに再び、クープランの墓からリゴードン。 |
|
|
|
|
|
|
|
ラ・フォル・ジュルネ金沢 5月4日のコンサートより。
|
|
東京で注目を浴びていた「ラ・フォル・ジュルネ」が、信じられないことに金沢にやってきた。フランス・ナントで開催され、そのユニークな音楽会づくりで、世界的に注目を浴び、東京でも数年前から開催、昨年は100万人の動員数があったという驚異的な音楽祭。
果たして、いくら文化都市といえども、人口40万人あまりの金沢で成功するだろうかという危惧は誰も持っていたと思うが、昨日の一連の演奏会は総て満席、当日券が買えないコンサートがほとんどという盛況。すべてのコンサートで会場待ちの長い行列が続き、音楽堂コンサートホールの音楽会は、舞台にまで客席をしつらえ、それでも入りきれない聴衆は、立ち見と通路に溢れるという状況。目を疑う盛況であった。最終的な動員数はおそらく5万人は超えるのでなかろうか?
人口比からすると、東京の100万人と並ぶ数字といえるだろう。富山で一回のコンサートか満席になることすら珍しい状況の中で、これは信じがたい、、驚きである。これだけの潜在的な音楽ファンが金沢を中心とする北陸圏には存在するのであり、それを掘り起こした、アンサンブル金沢のこれまでの活動は、地方の音楽文化の灯台のようなものであろう。
真っ赤な、シンボルティーシャツを着ていた、大学時代の友人、音楽堂の山腰館長に、「大成功だね。おめでとう。」と声をかけると、「これだけ詰めかけるとは。人をさばくのが大変。来年からはコンサート数を増やさないと。」と嬉しい悲鳴をあげていた。
チケットフォーという4回公演が聴くことのできるチケット(5,000円)を事前に購入しておいたが、全てフリーのマルチチケット(10,000円)とともに、早い段階で予定数を完売していたようだ。
この日も、他にも2~3、聴きたいコンサートがあったのだが、総て完売ということで、駄目。来年からはこのあたりの改善が課題だろう。この音楽祭の特長に、ぶらっと行ってもコンサートのハシゴができることがあるのだから、それが不可能なのは、やはり困る。
今年のテーマは「ベートーヴェンと仲間たち」。約1000名の世界の音楽家が、膨大なベートーヴェンの作品の中から、交響曲、協奏曲、弦楽四重奏曲、ピアノトリオ、ピアノソナタ、ヴァイオリンソナタ等、名曲を中心に80のコンサートで演奏するというもの。膨大な作品数のベートーヴェンであるから、極く一部の作品のみとなるが、それでも次々とジャンルの異なるベートーヴェンの作品を続けて聴くことのできる機会はないことを考えると、貴重な体験であった。
以下の音楽会はいずれも5月4日開催
212番演奏会
午後1時 県立音楽堂コンサートホール
ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58
ピアノと指揮 ジャン・フランソワ・エッセール
管弦楽 ポワトゥ・シャラント管弦楽団
ピアノと、指揮のジャン・フランソワ・エッセールは、ウラド・ペルルミュテ-ルの門下生とのこと。フランスのピアニストらしい、デリケートなロマンティシズムを感じさせるピアニスト。音楽のつくりは、かなり自由で、テンポの揺れを多用し、古典性よりも、ロマンティシズムを強く印象付けるような演奏。これは、やはりフランスのピアノの伝統なのかな、と思わせる。音質は華やか。特にグリッサンドなどのパッセージは独特の魅力がある。
管弦楽はやや硬質な音ながら、しつかりとまとまった室内楽団の印象。特に個性はないが、手堅いオーケストラという感じ。ジャン・フランソワ・エッセールがかなり自由な音楽づくりをするので、乗っていくのが大変と感ずるが、さすがに長年一緒に活動しているだけあって、息のあったアンサンブルであった。
222番演奏会
午後2時 音楽堂邦楽ホール
弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 Op.131
イザイ弦楽四重奏団
中期の傑作の世界から、いきなり後期の深遠な世界へ。
ここでのイザイ弦楽四重奏団は、繊細なアンサンブルで、ドイツ圏の四重奏団とは異なった作品へのアプローチを聴かせてくれた。それは、デリケートな息遣い、哲学よりも、感性の音楽。第一楽章の深遠な世界は、深い思索よりも詩的なやさしい響き。
全曲40分を超す大曲であるが、一貫して内省的な、心の中の響きを聞かせてくれた。堅固なスケルツォやソナタ形式も、この四重奏団では、力の抜けた柔らかい音楽。
231番演奏会
午後4時30分 県立音楽堂コンサートホール
交響曲第3番 変ホ長調Op.55 「英雄」
指揮 井上 道義
管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢
夜の庄司紗矢香とともに、今回の音楽祭の注目の演奏会とあって、舞台上からオルガン席まで客席を臨時に設け、それでも入れない人が、立ち見で見ているという盛況。1500弱の収容のコンサートホールに1800名位は入っていたのでなかろうか。
コンサートの前に井上マエストロが簡単な挨拶。その中で、「この日のことを、2年前に亡くなった岩城宏之マエストロが夢見ていた」という言葉が印象的。
実に力の入った、将に入魂の演奏。
第一楽章は淡々と進んでいる印象だったが、第2楽章からガラっと雰囲気が変わった。
葬送行進曲のテーマが実に遅い。そして、井上マエストロにしては、珍しく引きずるような重い足取り。
ここで、井上マエストロとOEKは何を表現したかったのだろうか。やはり岩城マエストロに対する鎮魂と考えるのは考えすぎだろうか。
第3楽章はベートーヴェンらしい、荒々しい演奏。中間部のホルンは実に猛々しく勇壮。
第4楽章の変奏曲も、勢いと、潤いの両極を備えた、堅固で壮麗なベートーヴェン像。
ティンパニーの壮絶な響きと、金管の咆哮で、エンディング。
OEKは得意のベートーヴェンで、この音楽祭のレジデンスオーケストラとしての実力を存分に発揮した。
214番演奏会
午後8時15分 県立音楽堂コンサートホール
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ヴァイオリン 庄司紗矢香
指揮 井上 道義
管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢
今回の音楽祭の白眉とでも形容できるコンサート。
今回は舞台上での鑑賞という、貴重な体験をすることができた。
コントラバスの後の席、井上マエストロの指揮ぶりと、 庄司紗矢香の息遣いが感じられる距離での鑑賞。オーケストラの中で聴いていると、実にアンサンブルが見事なことが、客席で聴くよりも実感できる。オケの団員が各々のパートを耳を澄ませて聞きながら、合していく様が目の前で展開していくのは、実にスリリング。
庄司紗矢香のヴァイオリンは、一昨年のノリントン・N響で、その年のベストソリストに選ばれたのを記憶しているが、その際はノリントンの要請でノン・ヴィブラート奏法で全曲を通すという離れ業をやってのけたが、この日は本来のヴィブラートを駆使した演奏で、実にのびのびと、よく歌い、よく弾む演奏を聴かせてくれた。特に、全曲に歌があふれていることは特筆。
全曲をすみずみまで弾きこみ、その上で自らの色合いを添えて行く演奏は、若さを超越した円熟の演奏。
音色ののびやかな美しさ。そして濃厚なカンタービレ。
ベートーヴェンのこの協奏曲の気宇壮大な美しさを、これほど見事に表現した演奏は、なかなか聴けるものでない。庄司独特のオーケストラに、身体をゆだねていく、恍惚とした表情も印象的。1楽章のカディンツァは自作のものと思われるが、主題を様々に変奏、鮮やかなテクニックで展開していく様子は、スリリング。
第3楽章の弾むようなリズムと、オケの弦楽器や木管との競演。ひとりよがりの演奏でなく、オケとの掛け合いの中で音楽を作り上げていく様は、この作品の協奏曲としての面白さを改めて知らしめてくれた。
終了後、嵐のような拍手と、ブラボーの叫びに、うれしそうな笑顔でこたえていく様子は、演奏途中と異なる少女のような初々しさに戻っていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第240回定期演奏会 2008年4月26日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮・ピアノ ラルフ・ゴトーニ
|
|
3月のフィルハーモニーシリーズに所用で行けなかったので、振替で本公演を聴くこととなった。定期会員の振替制度はこんな時ありがたい。
29日からの「ラ・フォール・ジュルネ金沢」を前にして、音楽堂周辺はすでに祝祭気分に満ち満ちている。地方都市での大きな音楽イベント、一回きりでなく、例年、根付いてほしいものである。
さて、今日の演奏会、北欧フィンランドの指揮者、ラルフ・ゴトーニによる。ピアノの弾き振りを交えたコンサート。
ゴトーニは2006年メルボルンでのOEKのコンサートで、亡くなった岩城マエストロの代演を果たした指揮者とのこと。主にイギリスでの活躍が多いようだか、イギリスと北欧はかつてより音楽的には近似感が強いように思える。イギリスの指揮者がシベリウスを得意にしているとか、音楽的に似通った雰囲気があるのだろうか。
この日のプロは、前半がエルガーの「弦楽のためのセレナード」、モーツアルトのピアノ協奏曲第14番、後半が、シュニトケ「ピアノと弦楽のための協奏曲」、モーツアルトの35番のハフナー交響曲と、モーツアルト2曲に、現代作品を配置し、前半と後半に弾き振りを配した面白いプログラミング。
ゴトーニという指揮者、安定感のある、バランスのよく取れた指揮者という印象。特にアンサンブルに気を使い、重厚で、しかし生彩のある響きを作り出していた。
最初のエルガーの弦楽合奏のアンサンブルはその典型で、各声部をしっかりとうたわせ、そこで生まれる弦のアンサンブルは艶やかで重厚。エルガー音楽の特色である、気品ある重厚さを、しっかりと描き出していた。OEKの弦も指揮者の要求に応え、しっかりとしたハーモニーを生み出していた。
モーツアルトのピアノも、その指揮ぶりと同様、誠実で、温かい演奏。
後半のシュニトケ、弦楽合奏のみを伴奏とする、協奏曲であるが、室内楽的というより、かなり激しい嵐のようなリズムを中心として、ピアノの打楽器的な激しさが印象的な協奏曲。かなり、はっきりとした数種類のテーマ、それも独特なリズムをもったテーマが中心となり展開されていくのだが、シュニトケの激情をぶつけたような感。特に、ベートーヴェンの月光ソナタを想像させるようなテーマは印象的だが、そのテーマの中に抒情性はなく、ただリズムのみが強調されるような不思議な展開となる。終結部は激情もおさまり、祈りのように静かに、静かに終わっていく。
ゴトーニのピアノも激しく、その激しさを弦楽器にも求めるため、壮絶。
指揮者がピアノに集中する必要があるため。オーケストラもかなり困難な作業となっただろうが、この難曲をしつかりと弾きこなしていた。
大きな拍手にこたえて、ゴトーニは小曲をアンコールに演奏。曲目は不明だが、ラベルで
あろうか?
最後の「ハフナー交響曲」。この作品の祝祭的な華やかさと生気を溌剌と表現した演奏。特に第一楽章の飛び跳ねるようなテーマの表現は見事。全体を一気呵成に、駆け抜けるように演奏、この作品の持つわくわくとした気分をよく表現していた。OEKも弦、木管を中心として心地よいアンサンブルを響かせていた。ホルンが少し不安定だったのが残念。
アンコールに小品が一曲。これも曲名不明。弦のピチカートと、途中にピアノの調律用の音叉のような楽器を打楽器奏者が叩き、散りばめるユーモラスな作品。
この日のOEKの演奏も、実に安定した演奏で、種々のタイプの指揮者に適応できる安定したオケに成長してきたことを証明したような演奏だった。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第239回定期演奏会 2008年4月20日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
ピアノ 小曽根 真 |
|
ファンタジーシリーズの定期だが、今回は純クラシックプロ。小曽根のピアノと井上道義のショスタコーヴィッチということで、マイスターシリーズでもふさわしいような内容。
モーツァルトのピアノ協奏曲第27番K595、ショスタコーヴィッチ、「ステージオーケストラのための組曲」(旧称「ジャズ組曲第2番」)から5曲、そしてガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」という魅力あふれるプログラム。
ジャズピアニストがバッハやモーツァルトに挑戦する例は、過去から相当数にのぼると記憶する。それだけ、バッハやモーツァルトはジャズマンにとっても魅力ある素材であり、音楽がシンプルな(内容は、実にシンプルでないが。)だけに、その中で自己主張を行いやすい素材ともいえるのだろう。
小曽根真のモーツァルトへのアプローチも、そのような意味で興味津津たるものがあった。
第1楽章、第3楽章では、各々のカディンツァのジャズ的なアドリブは別として、以外にいじくりまわさない素直な演奏という印象。古典的なアプローチの中に、装飾音などで、時折ジャズ的な雰囲気を感じさせてはいたし、リズム感の中に独特のノリのようなものは感じられたが。
カディンツァは完全に小曽根ワールド。テーマをアドリブしていく様は実に爽快。しかし、ジャズの世界が突然協奏曲の中に現れるのに、違和感はない。これは、モーツァルトの音楽の懐の深さといえようか。
第2楽章は、1.3楽章と異なり、独特の粘っこい音楽。ジャズには疎い私だが、なるほどジャズ、特にモダンジャズの世界とはこのような深い思索と沈潜に支えられているのだと納得させられる演奏。そして音楽の表現とは、一つではなく、実に多様性をもつているものだと、改めてモーツァルトの世界の別の面を見た思い。
後半のショスタコーヴィツチ。ショスタコーヴィツチは実に様々な表現の仕方をする作曲家であるが、その深い思索性の対極にあるのが、シニカルな笑いと馬鹿騒ぎ。今日の作品はその後者の典型。1曲目の「行進曲」など、まさに正真正銘のスーザばりのマーチ。そこに天才的な管弦楽法が加わっているのだから、特級のマーチである。
編成もチューバ、サクソフォーン、ピアノ、ハープ、チェレスタ、アコーディオンを入れるなど多彩。
井上道義の指揮も実に生き生きとして、パフォーマンス豊か。時に足をけり上げ、時に手をすり合わせ、音楽の表現力を身体で引き出そうとする様子は、この指揮者独特のもの。
第5曲、7曲のワルツは、下町のうら哀しさ、サーカスのジンタなど、野卑な魅力を感じさせる。あの時代のソヴィエトにおいてのショスタコーヴイッチの権力への皮肉も感じさせる音楽。
OEKも絶好調。チューバ、トロンボーン、サクソフォーンなど独奏を受け持つエキストラ団員も一体となり、渾身の演奏。
最後のガーシュイン、「ラプソデ・イン・ブルー」
小曽根のかなり長いアドリブを加えての快演。
出だしのクラリネットのソロが、高らかに曲の開始を告げるが、このクラリネツトのジャズ的なノリは見事で、この演奏全体のOEKのノリを十分に予感させていた。
ジャズの手法を華やかな管弦楽法の中に展開させ、その中にピアノがラプソディー風にからみあつていく、その面白さを存分に聞かせてくれた。
時にブラスを中心にしたオーケストラが激しく昂揚すると、一転してピアノが憂鬱な旋律を奏する。そして、完全に奏者の創意と思われる、長いピアノのアドリブ。クラシックのピアノが知的であるのに比較し、ジャズビアノは実に感覚的、しかし底には深い思索も秘められている。アドリブの中で、コントラバスやサクソフォーンとの掛け合いがき聴けたが、将にモダンジャズのアドリブの世界。
既に述べたが、オーケストラの、リズムと雰囲気へのノリも抜群。クラシツクのオケが、この様な楽譜に現れない、魂のようなものを表現するのは困難な作業と思われるが、この日のOEKの演奏は実に自発性に満ち満ちていて、精彩活発。オケとしての成熟度を感じさせる演奏。勿論、指揮者のノセ方も巧みなのだろうが。
フィナーレの激しい高揚が終わると、ブラホーの大きな拍手。
アンコールに小曽根は井上の要望で、何と「DSCH」(ショスタコーヴィツチの名前の頭文字「D」(レ)「(e)S」(ミ♭)「C」(ド)「H」(シ))を音符化したテーマでのアトリブを披露。これは、ショスタコーヴィツチ自身が自らの作品の中で試みていることで、井上道義はそれを意識していての要望だったのだろうが、小曽根はピアノの前でしばし沈黙の後、テーマを弾き始めた。随所に現れる4つの音のテーマを、様々に展開していくバリエーションは、ジャズのアドリブの豊かさと、深さを存分に聞かせてくれた。
音楽の「楽」を十分に聞かせてくれ、井上道義の世界が、OEKに根付きつつあることを証明してくれた定期演奏会。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第238回定期演奏会 2008年3月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
ヴァイオリン ネマニャ・ラドゥロヴィッチ
|
|
今月の定期は、井上道義による。フランス音楽の特集。
ビゼー、小組曲「こどもの遊び」、サン・サーンス、序奏とロンド・カプリチョーソ(ヴァイオリン ネマニャ・ラドゥロヴィッチ)、ドヴュッシー、小組曲よりバレー、サラサーテ「ツィゴイネルワイゼン」(ヴァイオリン ネマニャ・ラドゥロヴィッチ)、後半が井上道義のパフォーマンス溢れる語り付のドヴュッシー、バレエ音楽「おもちゃ箱」、という定期にしては珍しい小品を組み合わせたようなプログラム。
ビゼー小組曲「こどもの遊び」は、アンコールピース等で部分的に演奏されることはあるが全曲演奏されることはめずらしいのではなかろうか。メリハリの効いた、井上道義らしい小気味の良い演奏。第2曲、第4曲のしっとりとした部分のOEKの弦の柔らかい響きは、最近のOEKの好調さを示していた。
ヴァイオリンのネマニャ・ラドゥロヴィッチを迎えてのサンサーンスとサラサーテ。実に鮮やかなヴァイオリン。驚異的なテクニックの持ち主だが、音楽が実に力強く、輪郭をくつきりと描き出す。それでいて、曲想のジプシー的な雰囲気も濃厚に描く。日本ではあまり知られていないヴァイオリニストだが、世界は広いと考えさせてくれた。
両作品とも、前半の憂愁に満ちた部分と、後半の華麗な部分の対比が実に鮮明。
アンコールに「タイスの瞑想曲」。しつとりとしたカンタービレを十分に効かせた、それでいて甘さには陥らない。
後半のドヴュッシー、バレエ音楽」「おもちゃ箱」。井上道義の豊かなパフォーマンス。語りながらの指揮という離れ業だが、実に楽しそう。 (演奏している方はそれどころでないかもしれないが。)
語はりあるのだが、全体の明確な筋はなく、「くるみ割り人形」と同様に、一夜の夢物語というところだろうか。ドヴュッシーらしい、夢幻的な曲想に満ちた作品だが、あまりにパフォーマンスが豊かで、肝心の音楽が、聴く方にとって心に入ってこないうらみはある。
アンコールは映画「シェルブールの雨傘」のテーマ音楽。オーケストラによるゴージャスな映画音楽。OEKはこの様な演奏でも、雰囲気を実によく出す。
井上道義の個性あふれる定期だったが、定期演奏会としてはやや物足りなさを感じたのも事実。好みの問題か。
|
|
|
|
|
|
|
|
金聖響 ブラームスシリーズ公開録音 2008年3月1日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響
オーケストラ・アンサンブル金沢 |
|
金聖響のブラームスシリーズの金沢における最後の交響曲、4番の演奏会がCD録音を、定期会員に無料で公開するという形で行われた。1番、3番が定期演奏会で、2番が能登地震復興支援のチャリティーコンサートで演奏され、4番だけが予定になく、残念に思っていただけに、このような形で実現されたことは幸せ。特に4番は、金聖響で是非聞きたいと思っていただけにうれしかった。
ライブ録音は聴衆の熱気が演奏に反映されるという面白さがあるので、この様な試みは今後も続けてほしいものである。
CD録音のためのコンサートということで、いつもの演奏会とは異なった雰囲気。指揮台の後ろに2本の巨大なマイクが設置され、モニターも舞台上に置かれ、指揮者も楽員も平服での演奏という、珍しい光景。客席も前部の客席は使用禁止となっていた。
配置はいつもの金聖響独特の対向配置。正面にコントラバス、右側にトランペット、トロンボーン。ティンパニーがトランペット、トロンボーンの前。ホルンは左手奥。コントラバスは4本に増強されていた。ティンパニーはバロックティンパニーを使用。炸裂するような響きが、実に効果を挙げていた。
プログラムは4番の前にハンガリー舞曲の1番、3番、10番が演奏された。
ハンガリー舞曲3曲とも、実に堅実な演奏。オーケストラを十分に響かせ、この作品の聞かせどころでもある管楽器の独奏もくっきりと浮かび上がらせ、厚い響きを聞かせてくれた。
テンポも中庸、どっしりと構えながら、舞曲特有のテンポの変化も自然にコントロールし、気持よく聞くことができる。
さて、メーンの交響曲第4番。
キリリと引き締まった筋肉質の演奏といったらよいだろうか。ピリオド演奏であるので、弦楽器にはほとんどノンヴィブラートを要求しているため、甘さの無い、またあいまいさのない強い響き。
そして、テンポも落ち着き、ブラームスのこの作品のギリシャ彫刻のような古典的な端正さを、力強く描きだしていた。
40名あまりのオーケストラなのに、聞こえてくる音は実に大きく、まるでフルオーケストラのような迫力を感じる。特に、ティンパニーを遠慮なくたたかせる爽快さは、若さの賜物か。
1楽章の憂いに満ちた出だしの主題は、妙な演出をすることなく、自然に始まり、その後の主題の展開がまるで変奏曲の様に高揚していく。このあたり、自然な心の高揚感が、それはブラームスのものであり、金聖響のブラームスに対する真摯な思いでもあることを強く感じた。
同じピリオド演奏でありながら、先日のノリントンのブラームスとの音楽の質の相違を聞いたような思い。音楽をいじくりまわすか、素直に向かい合うか、そのあたりの質の相違だろうか。
1楽章の終結部の嵐のような高揚感、そこではテンポを若干上げながら、あおっていくのだが、それも金聖響の心の高揚となり、聞くものに迫ってくる。
第2楽章も落ち着いた演奏。もう少し色気を出してもよいのではないかと思わせるくらい、淡々とした出だし。「今の自分のブラームスへの理解は、この程度です。」とでも言いたげな等身大の演奏といつたらよいのだろうか。誠実な演奏である。
怒涛のような3楽章。ここでも、ティンパニーの炸裂、金管の咆哮のすごさ。遠慮のない響かせ方。
バロックティンパニーは調律が非常に難しいようで、楽章間で相当長い間のチューニングを行う。そのため、怒涛のような3楽章の高揚感を持ったまま、4楽章になだれ込みたいところだろうが、それができない、少々、もどかしいところではある。しかし、金聖響は、じっとその間辛抱して待っている。
4楽章のパッサカーリア。一つ一つの主題の展開を丁寧に行いながら、エンディングの堂々たる建築へと到達していく様は見事。ここでは、木管、金管など管楽器の活躍が多いが、どの奏者も丁寧な落ち着いた演奏。弦楽器も力のこもった渾身の演奏。
エンディングも下手にテンポをいじらず、自然な高揚感の内に全曲を閉じる。
若々しい音楽でありながら、ブラームスのこの作品の本質、精巧なモザイクのように組み合わされた音楽の面白さ、をくっきりと浮かび上がらせた、名演といってよいだろう。
このCDは今年秋発売予定とのこと。もう一度じっくりと聴けるのは楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
シュトゥットガルト放送交響楽団演奏会 2008年2月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ロジャー・ノリントン
ピアノ 小菅 優 |
|
今年最初の外国オーケストラを聴くはずだった、シャイー・ゲヴァントハウス管弦楽団が、シャイーの病気とのことで中止となったので、この演奏会が今年初の外国オケを聴く機会となった。
ロジャー・ノリントンという、ピリオド演奏の旗手と、新鋭小菅優のピアノが聴けるということで、興味津津の音楽界。
プログラムは、ヴォーン・ウィリアムスの「すずめばち・むずかし屋」序曲という珍しい作品で始まり、ベートーヴェン、ピアノ協奏曲第4番、後半がブラームス交響曲第1番というもの。
ロジャー・ノリントンという指揮者、かなり個性的な音楽づくりをする指揮者。
私の音楽観の中で、このような音楽をどう位置づけるかということに、正直とまどう。
ピリオド奏法については、ここ十数年、非常に広まり、ホグウッド、アーノンクール、ガーディナー、そしてこのノリントン等大変な人気を呼んでいると聞く。ラトル、ハーディング等もこの傾向に近いし、日本でも鈴木秀美は著名で、若手でも金聖響などが影響を受けているといえる。
しかし、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンあたりまでは、この奏法での演奏はよく耳にするが、後記ロマン派、あるいは国民楽派まで、この奏法を用い演奏しているのがノリントンの特徴ではなかろうか。
ノリントンの個性的なアプローチは、単にノンヴィブラートで全曲を貫くということでなしに、必要と考える場合には、例えばブラームスの1番の第二楽章など、ヴィブラートも使用している点。だから、史学的な観点からピリオト奏法を取り入れているというよりも、その時代にその音楽がどのように鳴り響いていたかを再現するための史実の検証ということになるかもしれない。
どのような検証に基づいて音楽づくりがなされているか、勉強不足で理解していないが、生まれてくる音楽は実にユニーク。悪く言えば、恣意的にも聴こえる。
楽器配置も実に独特、正面奥にコントラバスをずらりと並べ、第一ヴァイオリン、第二ヴァイオリンが対向配置、チェロの後ろにヴィオラ、金管は、ホルンが左、右側にその他の金管というもの。ブラームスでは8本のコントラバス、木管も倍管という大きな編成。
晩年の岩城宏之がブラームスの演奏で、コントラバスを正面に置く配置をしていたが、ブラームスの初演当時はブラームスの指示がこのようだったと聞く。
ノンヴィブラートを基調としているので、音程等のあいまいさは許されず、総ての音が正確に明快に鳴り響く。ノリントンの最大の特徴は、このドライとも感ずる程の明確さ。
しかし、テンポはかなり自由に動かし(ノリントンは楽譜の指示通りというだろうが。)
音楽の推進性を強調しようとする。たとえば、ブラームスの1番の序奏部、非常に速いテンポで始まる、しかし主部に入るとテンポは落ち着く。
ノリントンの音楽づくりがユニークなため、どうも指揮者の音楽が前面に出て、音楽家の顔が見えにくくも感ずる。
個性的な演奏をする指揮者は数多いが、その作品を自らの中でどのように消化し、再現するかという点での個性の違いが音楽にあらわれ、その点が感動を呼ぶ場合が多いのだが、ノリントンの場合そのようなケースとも異なる。やはり、ロマン性の排除という言葉が適当なのか、音楽のぬくもりというか、温かさが排除されているのだ。
このあたりが、史実に基づいた演奏といいながら、実に現代的な印象を与え、好き嫌いの分かれるところとなるのかもしれない。
最初のヴォーン・ウィリアムス序曲は、ノリントンのこのような音楽がプラスに作用され、非常に生き生きとした躍動感に溢れた演奏。
ベートーヴェンでは、小菅優が素晴らしい音楽性を聴かせてくれた。上品で、風格に満ちた音色、特に高温でのトレモロなど均質なビロードの様な肌触りを感じさせてくれる温かい響き。
ノリントンの伴奏は、小菅優の古典的な均整美を打ち壊すように、荒々しい。ノリントンの演奏には、やはりかつてのピアノフォルテの様な楽器がふさわしいのかもしれない。この演奏でも、配置は極端。ピアノを縦に置き、奏者は客席に背を向ける形、指揮者はピアノの先、チェロの横に客席に向くように座り指揮をする。極端に言えば、客席に向かって指揮をしているよう。であるから、管、打楽器に指示を与えるには、振り向く形となる。これも、考証の結果なのだろうか。
小菅優のアンコールはショパン。これは実に清潔で感傷におちいらない詩情豊かな演奏。この年で、既に大家の雰囲気を漂わせるあたり、並みのピアニストでない。最近の若い演奏家は、テクニックの確かさのみでなく、音楽のとらえ方に実に老生したものを感ずることが多い。
さて、先にも述べたブラームス。音の塊のぶつかり合いのような感のある演奏。どうも、ブラームスのくぐもった情熱が聞こえてこない。現在の私には、理解しがたい演奏。この様な演奏だと、いつもノリントンを聴きにいくということになり、ノリントンの解釈するベートーヴェンやブラームスを聴くということにはならないのではなかろうか、などと、ぶつぶつ言いながら帰途に就いた。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第234回定期演奏会 2008年1月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上 道義
ソプラノ 森 麻季 |
|
2008年のOEKのニューイヤーコンサート。例年、華やかなニューイヤーコンサートだが、OEK演奏会の観客数が累計で200万人を今日突破するということで、記念セレモニーが予定されているため、一層賑やか。
今年でOEKは創立20周年、20年で200万人ということは、1年で10万人、1月で8,000人強の聴衆が演奏会に駆けつけたということ。金沢のみの演奏会の数字では無いだろうが、とてつもなく誇らしい数字ではある。地方オケとしては、池辺晋一郎さんの語っている通り、驚異的な数字であろう。200万人目は、午後6時35分ごろ達成され、ホワイエ中央のくす玉が割られ、200万人目の方、又その前後数名の方に記念品が贈られた。
セレモニーの途中、新年らしく、シュランメルスタイルで、ワルツ、ポルカが演奏され、ホワイエは華やかなムードに包まれていた。
さて、今日のニューイヤーコンサート、例年になく力の入ったニューイヤーコンサートとなった。
数年前のニューイヤーコンサートの際、当ホームページで、「ニューイヤーコンサートのありかたも、選曲を含めて一考の余地があるのでないだろうか。別に、本家のニューイヤーコンサートに右倣えをする必要もないと思うが、いかがなものであろうか。」と、生意気なことを書いたが、今年は「J・シュトラウスだけじゃない。」と銘打って、多彩な企画となっていたのは嬉しい限りである。
第1曲目、「青きドナウ」はまるで「本場のワルツなど、日本人に真似られるわけがない。」というような、井上マエストロの開き直りを聴くような、小気味の良い演奏。ウィーン風なメランコリーは一つも無いが、アルコールの抜けたビールを飲まされるような、おざなりのウィーン風ワルツより余程気持ちよい。それでいて、J・シュトラウスの美しさと華やかさは十分に表現されているのだから。
この日のプログラミングは実に雑多だが、まるで音楽の楽しさをバケツでぶちまけたような痛快さがある。このあたりが、井上マエストロの個性。
2曲目が、「届いた楽譜を見て面白くなかった」との理由で、「芸術家のカドリーユ」に変更。確か数年前の本家ニューイヤーコンサートで、ヤンソンスが演奏していたのを思い出した。井上流エンターティーメント躍如の演奏。
森麻季さんの登場で、2曲。プッチーニのボエームから「ムゼッタのワルツ」、フランクの「天使の糧」。透徹した、クリスタルガラスの様な声は、やはり素晴らしい。特にフランクのボーイソプラノのような清潔な歌声は、宗教曲に誠ふさわしい音楽性の持ち主と感じた。
第一部の最後、ニコライの「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲、第2部のブラームス、ハンガリー舞曲第6番は、井上ワールド全開。時にしっとりと、時にアップテンポでオケをドライブしていく様、メリハリの効いた表現、は実に爽快。OEKの音も、実にクリアで明るい。以前聴けなかった響きがある。
後半、武満徹、そして一柳慧の新曲が入ったのは、OEKのニューイヤーコンサートにふさわしい個性的な選曲。
武満徹は、3つの映画音楽より「ワルツ」(他人の顔)。難解な音楽というイメージの武満徹だが、映画音楽やテレビ音楽は実に美しい。岩城宏之追悼コンサートの際演奏された「波の盆」でも感じたが、感傷と寂しさが、この人の音楽の本質と思わせるような作品。
ショスタコーヴイッチの持つアイロニー、クルト・ワイルの「三文オペラ」を想起させるようなうら悲しさがある。井上マエストロの、「武満は若いころ、シャンソンに傾倒していた。」という話が、納得できる作品。
さて、井上マエストロが「本日のメイン」と紹介の、一柳慧のOEK委嘱新作品。ニューイヤーコンサートに世界初演を持ってくるとは、さすがに現代音楽のエキスパートオケと納得させる選曲。
一柳慧というと、イメージでは、鋭い前衛の旗手というイメージを持っていたが、プレトークでの印象、そしてこの作品と、イメージと異なる誠実そうで、暖かそうな人柄に、イメージとの落差にとまどった。
「交響曲第7番-イシカワ パラフレーズ―岩城宏之の追憶に-」と名付けられた、この作品、イメージを様々に膨らませてくれる、詩情豊かな作品と受け取った。
ゆっくりと、重苦しく始まる部分、やはり岩城宏之へのレクイエムか、あるいは能登地震への祈りか、しかし時に金沢らしい伝統文化の香りもただよう、ヴァイオリンの技巧的な独奏のブリッジで繋げられる次の部分、ここでは激しいリズムがパーカッションを中心に打ち出され、石川の山里の土の香りのようなものを感じる、再び静まった音楽は石川の海を思わせるよう。祈りか? チェロの独奏のブリッジで、再び高揚が訪れ、石川の豊かな文化、そしてアンサンブル金沢の躍進を称えるかのように激しく終わる。
石川の民謡が随所に聴かれ、時には能管のような響きも聞こえ、石川の風土と文化の香りを存分にふりまいている。しかし、それが洋楽と一体となり、多彩な管弦楽法で彩られている。一柳慧というイメージにつきまとう難解さを払しょくするような、主張の理解しやすい作品となっていた。
最後は、森麻季が再び登場、「からたちの花」、J・シュトラウス「春の声」で、華やかに閉幕。「からたちの花」の素朴な、しかし情感のこもった歌、「春の声」の輝かしいコロラトゥーラは、ブラボーの声のかかる熱演。アンコールを是非聴きたかった方も多いだろうが、残念。
オーケストラのアンコールでショスタコーヴィツチのバレー組曲から「ポルカ」。井上道義のショスタコーヴィチに寄せる熱い想いを感じさせる演奏。
最後は、恒例の「ラディツキーマーチ」で閉め。飲めないマエストロが、一升瓶をかかえてきて。酔っ払ったギャグに会場はおおいに沸いた。
充実した、ニイヤーコンサート。今年のOEKは、一層色々とやってくれそうな予感。
そういえば、5月には、ラ・フォル・ジュルネが金沢で開かれ、ベートーヴェンがテーマとのこと。熱いシーズンになりそう。 |
|
|
|
|
|
|
|
2008年最初のコンサート ユンディ・リ ピアノリサイタル
2008年1月7日 富山市オーバードホール |
|
今年初めての、そして暫くぶりの音楽会。11月のOEKの楽しみにしていた、金聖響のブラームスも、ナチュラリストの会合と重なり聴くことができず残念な思いをした。そんなわけで。久しぶりに期待に胸ふくらませたリサイタル。
そういえば、1月4日、5日と、例の「のだめカンタービレ」が新春スベシャル「パリ編」として放映された。あいかわらずの過剰な演出に辟易とする場面もあったが、音楽の本質を的確に捉えた、原作者の二宮知子の音楽への深い慧眼と、愛情に感心した。
「のだめ」が初のヨーロッパリサイタルに、モーツァルトの最後のピアノソナタを弾くこととなり、悪戦苦闘しているとき、先生から、「君は音楽から色々な表情を引き出すのが巧みなのに、何故モーツァルトの楽譜に書かれた様々な意味を読み取ろうとしないのだ。」と忠告された場面など、なるほどと納得させるものがある。
この日のリサイタル、当初のプログラムが大幅に変更され、最初にモーツァルトのピアノソナタ10番が演奏された。その一音が響いた時、「のだめ」のこの場面を思い出した。モーツアルトの嬉々とした、飛び跳ねるような喜びを、 まるでモーツアルトがそこで演奏しているように、ユンディ・リは、若い感性で弾いていた。素直で、喜びに満ちている。ユンディ・リの天才的な音楽の捉え方を確かに示してくれていた。
第一部は、ショパンのマズルカ、22番~25番の4曲、ノクターン第2番、シューマン・リスト編曲「献呈」、ショパン「アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ」と続く。
何故当初の、リスト、ベルク、ヒナステラが外されたのかはわからないが、自分の現在最も得意とするもので、勝負したかったのだろうか。
ショパンは、さすがに堂にいったもの。マズルカの複雑なリズム、歌わせ方など、ポーランドの土の香りさえ感じさせる。ただ、この日は絶好調とはいえないようで、マズルカ23番、、「アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ」のポロネーズの部分など華麗な部分に、やや緊張感が散漫となり、流れが止まってしまうような違和感を感じたのは残念。
とはいうものの、ノクターンの過度の感傷を排した歌わせ方、シューマン「献呈」の堂々とした静謐さなど、音楽の捉え方と表現に天才的なひらめきを感じた。
第2部はムソルグスキー「展覧会の絵」
最初のプロムナードは率直に淡々と始まる。だが、2曲目の「小人」に移ると、まるでそこに絵を見ているような色彩的な世界が開かれる。この作品のプロムナードと次の絵との関連が、こんなに気分として鮮やかに描かれているということを改めて、知らしめてくれた。絵をみた感慨が、プロムナードの音楽として、歩みとして描かれ、そして次の絵を見る驚きとして、聴く者にも伝わってくる。「古城」の裏さみしい歌わせ方。「牛車」はこれまで聴いたどの「牛車」とも違う、ポーランドの草の香りを感じさせるような「牛車」。(これまで聴いてきた多くは、重戦車)
「サムエル・ゴールデンベルクとシュムイル」では、滑稽なカリカチュアを感じさせるものが多かったが、ユンディ・リは、絵の中の悲哀を表現しようとしているようだった。「リモージュの市場」の超絶的な速さの表現、カタコンブの不気味な雰囲気の中に聴こえてくる賛美歌、どれも将に絵画的な音楽の表現。最後の「キェフの大門」では、力みすぎで、音を外する部分もあつたが、豪壮に締めくくってくれた。
この「展覧会の絵」は、今まさに旬のピアニストにぴたりの名演であった。
アンコールは中国の作品と思われる、軽快で、草原のさわやかさを感じさせる作品。 |
|
|
|
|
|
|
|
のだめカンタービレの音楽会 2007年11月9日 石川県立音楽堂コンサートホール
企画・指揮・おはなし 茂木大輔
ビアノデュオ プリムローズマジック(石岡久乃・安宅薫)
パーカッション 竹島悟史
管弦楽 オーケストラアンサンブル金沢 |
|
久しぶりの更新だ。パソコンがパンクして、一時は更新が難しいのではと諦めかけたが、不思議なことに(原因は今でもわからない!?)元の環境が復活して、めでたく更新できることとなった。
ホームページ作成ソフトを使っていると、バックアップしていない場合、HTML言語が取り扱えないものにとっては、お手上げとなってしまう。少し、勉強しないと。
さて、パソコンのパンクが原因でもなく、9月のOEKの定期以後、事情があり次の定期にも行けないこととなり、暫く音楽会と遠ざかっていたことも、更新ができなかった理由。
久しぶりの音楽会は、異色の「のだめカンタービレの音楽会」と銘打った企画。
「のだめカンタービレ」は、「のだめ現象というブームを巻き起こした二宮知子のアニメ。アニメは読んだことがないが、ドラマ化されたテレビは何度か見ていた。クラシックブームを若い世代に巻き起こしたアニメだ。特に、ベートーヴェンの7番や、ガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」などは、このアニメとドラマによって、あまねく人気曲となった。ドラマを見ていても、誇張される部分があるとはいえ、非常に音楽の本質をとらえた描写に、なるほどと思った記憶がある。
とはいえ、この音楽会に足を運ぶ勇気はなかったが、富山へ10年ぶりに戻ってきた息子夫婦が、この音楽界に是非行きたいというので、渋々同行したというわけ。
しかしながら、聴いてみて、非常にしっかりした企画と納得した。
会場はさすがに若い二人連れや、ファミリーが多く、いつものコンサートとは雰囲気が異なり、私たち老人の姿は少なく、ちょっと気恥ずかしい。
舞台正面には、2台のピアノと、パーカッションが置かれ、その奥にオーケストラが配置されている。正面オルガンの上からスクリーンが下され、そこに原作のアニメ、作品の解説等が映し出される。
企画、指揮、お話はN響オーボエ奏者の茂木大輔氏。
前半が、ベートーウーエン「悲愴ソナタ、第2楽章」、ハイドンの82番の交響曲「熊」から第一楽章、ジョリヴェ「打楽器とオーケストラの協奏曲、第一、二、四楽章」、モーツアルト「二台のピアノのためのソナタから、第一楽章」、ガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」、後半がベートーヴェンの交響曲第七番全曲、というもので、総て原作アニメにちなんだもの。
前半のプログラムでは、作品が登場するアニメ部分が投影され、アニメ、ドラマを知っている者にとっては、非常に興味あるものとなっていた。アニメでは、音楽の雰囲気は表現されていても、聴くことはできないので、アニメの愛好者にとってはクラシックを身近に感じられる、良い企画と思えた。特に、ジョリヴェなどは、ドラマでも演奏されなかったということで、貴重な演奏である。このジョリヴェとガーシュインが前半の演奏で出色。ジョリヴェでは、竹島悟史のパーカッションを渡り歩く熱演に、目と耳がくぎ付けとなった。右側がティンパニーを中心とした配置、中央部にビブラフォン、左側にドラムセットが置かれ、それぞれの楽器の間を泳ぐように移動し演奏するのだが、大変な難局であろう。曲調は、ストラヴィンスキーの「春の祭典」を想起させるような複雑なリズムと爆発、二楽章の深い静謐さなど魅力ある作品。
ガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」は、倉田典明編曲とあるが、茂木さんの解説によると、初演時に近いアレンジとのこと。普段聴くものより、ジャズの雰囲気が濃い、メリハリがきいた、パンチのある演奏。ピアノ独奏に代わり、プリムローズマジック(石岡久乃・安宅薫)のピアノデュオが加わり、響きも更に多彩。更に竹島悟史がドラムセクションで加わり、ジヤズ的なドラマをしっかり聴かせてくれた。アンサンブル金沢も、クラシックオケとしては、非常に難しいと思われる、リズムのノリがあり、弾むような演奏を聴かせてくれた。身体を揺すりたくなるような愉悦。
前半も、後半のベートーヴェンもそうだったが、スクリーンにアニメとともに、作品の解説が詳細に映し出される。これは、ある意味非常に親切たが、別の意味でうるさい場合もある。
特に、後半は、茂木大輔の独断的な解釈がほどこされ、それはそれで面白いのだが、作品の内容を聴衆に固定させてしまう危惧も感じた。ナポレオン軍の進軍とか、それを迎え撃つオーストリア軍とか、具体的なイメージを作品にあてはめてしまうと、そういうものと固定的に考える若い人たちが出てはこないだろうか?
とはいえ、ソナタ形式など、各楽章の詳細な楽譜に沿った解説など、今まで有り得なかった試みをしており、非常に意欲的であったことは確か。
後半のヘートーヴェンはアンサンブル金沢の最も得意な作品。茂木大輔の細かい部分まで気配りのある、彫の深い、「リズムの権化」と称されるこの作品の特徴をよくとらえた演奏。
非常にユニークな、クラシック音楽をいかにわかりやすく聴かせるかという、今後の貴重な指針となる音楽会と思えた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第229回定期演奏会 2007年10月3日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 大山 平一郎 |
|
10月に入り、県立音楽堂は、ペーター・シュライヤーの監修によるシューベルトフェスティバルが開催され、交流ホールを中心に、一週間にわたり毎日シューベルトの歌曲、室内楽の演奏会が催されている。近くに居れば、毎日でも通いたいくらいである。
この日の定期は、このフェスティバルの中心の演奏会で、オールシューベルトプロ。OEKの定期でも、過去、オールシューマン、オールブラームスなどが行われたことがあるが、定期演奏会ならではの、個性的なプログラムである。この日は当初ペーター・シュライヤーの指揮と発表されていたが、病気で来日不可能とのことで、大山平一郎に変更となった。
大山平一郎は、九州交響楽団で、その個性的な演奏が注目されている指揮者で、以前より興味を持っていた指揮者。
この日のプログラム、前半が序曲「アルフォンゾとエストラレル」という珍しい作品で始まり、交響曲第7番「未完成」、後半が交響曲第8番ハ長調というプログラム。
大山平一郎という指揮者、勝手に室内楽的な穏やかな音楽を作る指揮者と想像していたが、その印象と異なる、ゴツゴツとした個性的な表現をする指揮者。
最初の序曲「アルフォンゾとエストラレル」の、序奏部の低音部の極端な響かせ方に、まずびっくり。かなり、オーケストラを、悪く言えば乱暴にコントロールしていく印象。
であるからして、未完成交響曲も、優美で柔いシューベルトでなく、特に第一楽章など豪壮な展開を聴かせてくれる。確かにこの交響曲、一般的にはシューベルトらしい歌に溢れた、優美なシンフォニーという印象が強いが、第1楽章のデモーニッシュな展開は、それよりも、やはりベートーヴェンを強く意識した作品ということもできる。この演奏を聴くと、そのあたりがよく理解できる。ただし、第2楽章となると、ややそっけなさすぎる印象があり、むもう少しデリケートに歌わせてもよいのではないかとも感じた。この点はこのシンフオニーの難しいところでもある。シューベルト自身の、交響曲を作っていく上での迷いというものも感じさせてくれるのである。
この大山平一郎の特徴は次の第8交響曲となると、、長所となり、シューベルトのベートヴェン的なものへの憧れの強さが、明瞭に聴こえる。
第1楽章の序奏の雄大さ、そして主部の展開の力強さ、一気呵成に終わるコーダの部分など、熱い感情を感じさせてくれた。第2楽章も素朴な歌、変に色気をつけず、淡々と歌っていく。第3楽章のスケルツォは将に豪壮な点、ベートーヴェン的。第4楽章の、ドン・ジョバンニの石像のモチーフという動機も、何回も叩きつけるように響きで特長づけ、全体的に疾風怒濤の如くという趣。
優しいシューベルトではない。ウィーン的というよりも、むしろドイツ的な頑固な印象の演奏。
この日のOEKも木管楽器の、オーボエ、クラリネット、フルートなど絶好調。大山平一郎のやや強引とも感ずるドライブに、ややとまどう点も感じられたが、全体的には緻密なアンサンブルを聴かせてくれた。
アンコールは無し。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第228回定期演奏会 2007年9月14日 石川県立音楽堂コンサートホール
ヴァイオリン チョーリャン・リン
指揮 井上 道義 |
|
マイスターシリーズの定期だが、今年の幕開けにふさわしい内容だったので、是非聴きたく出かける。音楽監督となつて、初のシーズンの開幕だけに、フィルハーモニーシリーズでも、幕開けには新音楽監督での演奏を期待したかった。
この日は、マエストロ井上のたっての希望ということで、オルガン席の前の手すりから朝顔が一面に垂れ下がっているのが目をひいた。金沢21世紀美術館の今年の夏の目玉が、全館周囲を朝顔で覆うということで、それに呼応した企画のようで、「お祭りが好き」というマエストロの意気込みを感じさせる装飾ではある。
さて、この日のプロは、ハイドンとベートーヴェンという、古典の王道をいくプロ。故岩城宏之音楽監督の下で、最も中心となったプログラムを、マエストロ井上が、自ら音楽監督での最初の定期で演奏するという、気合いの入ったプログラムと感じた。ヘートーヴェンもヴァイオリン協奏曲と交響曲第5番という、スケールの大きなプログラムで、期待おおいなるものがあった。
最初のハイドンの交響曲第30番「ハレルヤ」は、初めて聞く作品。3楽章のメヌエットで終わるという、少々中途半端な感じのする作品。しかし、第2楽章のハイドンらしいアンダンテは、後期の時計交響曲を想起させるものもあり、小気味の良い音楽。ここでは、井上道義らしい、キリットと引きしまった躍動感にあふれた演奏となっており、独特の踊るような指揮ぶりが鮮やか。
ベートーヴェンの協奏曲のチョーリャン・リン、この協奏曲の魅力を存分に味あわせてくれた。
有名な協奏曲でありながら、その長大さから、えてして凡演が多いような気がするこの作品、チョーリャン・リンは、全く長さを感じさせない緊張感ある演奏。
この人の音の美しさは驚異的だが、この作品ではその美点が最大限に生かされていた。優美で、高貴といえるような輝きが、この作品の本質を明らかにしてくれた。「ヴァイオリン独奏つきのシンフォニー」とも形容されるこの協奏曲の特長を、なるほどと納得させてくれる演奏はそんなにあるまい。
独奏ヴァイオリンがヴィルトゥオーゾ的に鳴り響かせるのでなく、いかにオーケストラと調和していくか、その点が明確な演奏。特に随所で現れる、管楽器をオブリガートするようなヴァイオリンの部分、管楽器の歌わせ方にピッタリ寄り添うヴァイオリンの歌は、ベートーヴェンの意図をはつきりと聞かせてくれた気がした。1楽章のオーケストラの提示部で、チョーリャン・リンはオケの第一ヴァイオリンの部分を自らも一緒に弾いていたが、ここにオーケストラといかに同化していくかという真剣さを感じた。井上道義の指揮も、そのリンの意図を忠実にくみ取り、繊細な神経の行き届いた演奏。
後半はベートーヴェンの5番。白熱した5番。第1楽章は、一気呵成の一筆書きだが、テンポはそんなにいじらない。再現部からコーダにかけてのたたみかけていくようなベートーヴェンの本質を分厚い響きで再現していくところは見事。第2楽章の堂々とした気品、第3楽章の緊張感、そして緊張のブリッジを経て4楽章の高らかな賛歌。最近は、4楽章提示部を繰り返す演奏が多いが、井上は繰り返さず展開部になだれ込んでいく。劇的緊張感はこの方がある。
4楽章もベートーヴェン独特のしつこいくらいのテーマの繰返しかあるのだが、繰り返されるたびに、緊張が高まり、ついにコーダで爆発する、その緊張感を徐々に高めていく様を見事に表現していた。所々で、やや誇張した響かせ方もあるが、全体としては正統的な演奏。ハイドンやモーツァルトいで見せる優美な指揮ぶりとは一転した鋭い指揮ぶりは、各々作品の本質を的確に表現しようとする、マエストロ井上のしたたかさを聴く気がした。
オーケストラも力のこもった、気合いの入った演奏。終わった後の指揮者の、「このオーケストラはすごい。」というような身振りが、この日の演奏の総てを語っていたような気がする。
アンコールにグリーグの「ソルベーグの歌」。これも、OEKの弦の響きの厚さを感じさせる演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上原彩子ピアノリサイタル 2007年9月19日 入善コスモホール |
|
数年ぶりで聴く上原彩子は、スケールが大きくなり、自らの音楽を雄弁に語っていた。
この日のプログラムは前半がベートーヴェンの5番、31番の2曲のソナタ、後半がプロコフィエフの「束の間の幻影」、ピアノソナタ7番という、緊張感に満ちたもの。
最初のベートーヴェンの5番のソナタの第一音がホールに響いた瞬間、「え、これが初期のベートーヴェンのソナタ」、という驚きがあった。音の大きさと、悪く言えば濁音じみた響き、しかし非常に意思に満ちた堂々たるスケール。上原彩子のベートーヴェンへの挑戦状とでもいえる出だし。
ハイドンやモーツアルトの古典的端正さから、ベートーヴェンがいかにはみ出していったかが確かに理解できる解釈。
最晩年の31番は、ベートーヴェンの澄み切った諦念とでもいえる境地が聞ける作品だが、ここでも上原は、現在の自分の身の丈としてのこのソナタの解釈を聞かせてくれた。やや、遅めのテンボで、むしろどろどろとした情念の様な歌、そして2楽章のたたきつけるような激しいスケルツォ、そして3楽章のフーガの堂々たる歩み。ここでは、巨人としてのベートーヴェン像を描き出したかっqような感さえした。後期のソナタでは、内へ内へと入り込んでいく迷路のような緊張感が全体を支配しているので、演奏者はいかにその内的緊張感を表現するかに苦慮するものだが、上原の今の演奏は、「私は今はこのようにしか理解できない。」というような、開き直った面白さを感じた。
これから先の上原のベートーヴェンか゜、どのように自らの人生経験とともに、変化し成長していくか、大いに期待を持たせる演奏だった。
後半はプロコフィエフ。
「束の間の幻影」は初期のプロコフィエフの作品だが、色彩鮮やかな小品の集まりで、ロシア的でありながら、フランス印象派の影響もうかがわせる、独特の作品集。ここでは、実に色彩的なピアニズムが見事。強靭なだけでなく、キラキラとした輝き、ゆったりとした情緒も、あわせもったピアニストということを証明してくれた。この人がムソルグスキーの「展覧会の絵」を演奏したら、壮絶だろうと思わず想像してしまうような演奏。
最後は、ソナタの7番。強靭なピアニズムを要求する難曲。そのダイナミックさ、そして粘っこい歌、感情を叩きつけるような激しさは、上原のピアノにぴったり。ホールの響きの良さを最大限に生かし、圧倒的な迫力に満ちた演奏を聞かせてくれた。
女性とは感じさせない、腕っ節の強さと、鋼鉄のような響きがあるかと思うと、一転して弱音のデリケートな輝くような音色。幅の広いピアニストである。
アンコールに3曲。後2曲はプロコフィエフと思えるが、最初はチャイコフスキーか? |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第226回定期演奏会 コンサートオペラ「椿姫」
2007年9月14日 石川県立音楽堂コンサートホール
ヴィオレッタ 森 麻季
アルフレ-ド 佐野 成宏
ジェルモン 直野 資
演出・構成 わたべ さちよ
合唱 オーケストラアンサンブル金沢 合唱団 大阪音楽大学オペラ研究室
児童合唱 OEKエンジェルコーラス
バレエ 横倉明子バレエ教室
指揮 大勝 秀也 |
|
コンサートオペラ形式での「椿姫」
今年1月、定期でのモーツァルト「コジ・ファン・トゥッテ」がやはりコンサートオペラとうたっていたが、今回はその時よりもよりオ本格的なペラに近い舞台構成、衣装、であり、演出もオペラとほぼ同様の本格的な舞台となっていた。
ホールの構造上、舞台奥にオーケストラを配置、その上に映像用のスクリーン、舞台前面両側に重厚なアーチ風の柱。
映像で舞台上の足りない部分のイマジネーションを補完するような演出だが、違和感なくオペラに入り込むことができる。このような演出だと、なかなか接することが地方では難しいオペラも、もっと身近に触れる機会が出来そうで、今後もこのようなスタイルでのオペラをどんどん上演してほしいと思う。
さて、この日は、歌手、合唱、指揮者、オーケストラ、それぞれ気合いが入り、素晴らしく充実した舞台となっていた。公演が2回だけという緊張感も作用したのだろうが、真剣勝負のオペラの醍醐味を十分に味あわせてくれた。
タイトルロールの森麻季、初めての「椿姫」ということだが、その清楚な可憐さと、クリスタルな歌唱で、この役柄の別の面に光をあてられた気がした。「高級娼婦」という概念から、えてして外面的には派手な役柄として演じられることが多いが、森麻季は、実に気高い女性としての「椿姫」を描きだし、このオペラの主題の「純愛」を彫り深く描き出していた。
アルフレードの佐野成宏は昨年の4月の定期でも、アルフレードを歌ったが、この日も絶好調、輝かしい若々しい青年を歌い上げた。ジェルモンの直野資、有名な「プロバァンスの海と陸」、堂々とした歌唱。この有名なアリア、有名なだけに、表現の難しいアリアと思うが、せつせつと息子に言い聞かす、親の心の苦しさを見事に演じきっていた。
ホールも中ホールで、1500名弱の響きのよいホールということもあって、各歌手は気持ちよさそうにホールの隅々まで歌唱を響かせていた。
指揮の大勝秀也とオーケストラアンサンブル金沢。オペラオーケストラとして、ドラマティックに、そして美しく歌手を彩り、オペラの伴奏オケとしても、優秀なオーケストラであることを実証してくれた。第一幕への前奏曲の出だしの弦の弱音の柔らかな緊張感、第3幕への前奏曲の悲劇的な響き、随所で歌を彩る木管楽器の表情豊かな歌、そしてエンディングのドラマティックな管楽器の咆哮など、実に表情豊かなオーケストラであることを聞かせてくれた。これは、オペラ指揮者としての経験の深い大勝秀也の力量のなせるところも大きいのだろう。
演出は少々変わっていて、医者のグランヴィールがヴィオレッタの悲劇を語るという狂言回しの役割を担っていた。これは視覚に訴えるところが弱いというコンサートオペラの弱点を補うことと推察したが、特に必要な演出だったか、疑問の残るところでもある。
又、第2幕第2場の宴会の場面で、「金沢からのお客様です。」という趣向で、OEKエンジェルコーラスが出演、「ドレミの歌」「エーデルワイス」を歌ったが、唐突な印象で、オペラの流れを中断してしまったような違和感を覚えた。J・シュトラウスの「こうもり」の祝宴の場面で、こうした演出が行われる例は聞いたことがあるが、「椿姫」のようなシリアスなオペラでのこのような演出はいかがなものであろうか?
とはいうものの、名アリアが多く、美しい旋律に溢れた「椿姫」を全体として十分に堪能させてくれた素晴らしい舞台であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢 岩城宏之メモリアルコンサート
2007年8月31日 富山県民会館
指揮 井上道義
ピアノ 木村 かおり
ヴァイオリン 吉本 奈津子 |
|
このコンサートは、当初金沢でのみ予定されていたが、北陸銀行の協賛により、富山での演奏会が実現したとのことで、富山の聴衆にとってはありがたいこと。そして何よりも北陸を代表するオーケストラを富山で聴く機会が出来ることは、富山の音楽ファンにとって何よりのプレゼントである。企業メセナの重要さが、文化の発展にとってどれだけ大切かということを考えると、北陸銀行の英断に敬意を表したい。ただし、最初の頭取の挨拶はいかがなものか。北陸銀行の協賛ということは、ポスターでも、チラシでもアナウンスでも十分に知れ渡っていること、あえて頭取が挨拶して、音楽会の開始をしらけさせてしまうのは、逆効果のような気がするが。
さて、岩城マエストロが亡くなって、早1年あまりが過ぎた。この日の演奏会は岩城マエストロの功績の大きさをあらためて思うと同時に、井上道義という新しいマエストロを音楽監督に迎えたアンサンブル金沢が、新しい一歩を踏み出しつつあるということを鮮烈に感じさせてくれる音楽会となった。それは、何よりも井上道義という、岩城マエストロと全く異なる個性を感じさせる指揮者を音楽監督に据えたことにより、「何か、とんでもないことをしでかしてくれれるのでないか」という期待を、聴衆に与えてくれつつあるということでもある。
さて、この日の演奏会のプログラム、前半が新見徳英の協奏的交響曲「エランヴィタール」(2006年9月初演)の再演、モーツァルト交響曲第35番K.385「ハフナー」、後半がベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(ヴァイオリン 吉本 奈津子)というプロ。メーンが、大曲とはいえ、、協奏曲というプログラムも珍しい。
新見徳英の協奏的交響曲「エランヴィタール」。初演の際に、「再演を期待したい」と記したが、このように早い機会に再演されてうれしい。初演は外山雄三の指揮だったが、この日の井上道義の指揮も、非常に繊細且つドラマティックで、この作品のコンセプトを明確に描きだし、初演の際よりも一層面白く、素晴らしい作品と感じることが出来た。新見徳英という作曲家、現代音楽に珍しい、ロマンティックな作曲家と感じた。最初、続いて描き出されるピアノの主題が、様々に変形され、弦、管、打楽器の痛切な奔流となって逆巻くさまは、作者の生に対する痛烈な思いを聴くよう。そして、最後の木管で描き出される抒情的な旋律が、いかにも哀切でいとしげで、作者の亡きものに対する心からのレクイエムと感じた。木村かおりのピアノの痛烈な響きも見事。
井上監督は、初演よりも、このオーケストラのもつ財産の再演に重きをおくような意向と感じるが、それは聴衆にとってもありがたいこと、どんどん再演してほしい。
2曲目はモーツァルトのハフナー交響曲。ここでは一転して、井上道義独特の、弾むような音楽の愉悦を存分に聴かせてくれた。「楽しくなければ音楽でない」が井上道義のコンセプトと聞くが、将にその通りの演奏。指揮ぶりを見ていると、こんなに指揮が饒舌な指揮者も珍しい。表現したい音を、身体で引き出そうとする指揮ぶり。そういう意味では、タイプは異なるがカルロス・クライバーの指揮ぶりを想起させる。
この日のアンサンブル金沢は2本のコントラバスという、このオケの基本形だったが、良くまとまり、「アンサンブル金沢」の音ということを感じさせ、このオけの成熟を感じさせてくれた。
後半のベートーヴェン。ここでは、独奏者に岩城宏之音楽賞の第一回受賞者の吉本奈津子を迎え、メモリアルにふさわしい企画としてあった。
井上道義でのアンサンブル金沢はまだ発足したばかり、聴く方にとっても、エキサイティングな面もあるのだが、やはり岩城マエストロが中心に据えていたドイツ古典派の音楽、特にベートーヴェンをどのように聴かせてくれるのかというのは、一番の関心事である。
この日もそのあたりを楽しみにしたが、この日の演奏は独奏者が新人ということもあり、やや独奏者のサポートに中心が移り、井上色が希薄だったのは残念。このあたりは、来月のチョーリャン・リンを迎えての同じ協奏曲と、交響曲5番に期待したい。
独奏の吉本奈津子、大変美しい高音を響かせる、正統的な奏者と感じたが、個性には乏しく、聴衆を自分のペースで引きこむという、プロに大切な面がまだ乏しい。テクニックもあり、音も美しいので、今後どのように音楽を解釈し、聴衆に納得させるかということが加わってくれば、もっと大きな音楽を聴かせてくれると思うが。
アンコール、バッハの無伴奏もやや音程が不安定。
オーケストラのアンコールはベートーヴェンのメヌエットだが、「楽しく、やりましょう」と掛け声をかけ、踊りながらの指揮ぶりは、井上色満載。
県民会館ホールでの演奏会は久しぶりだが、石川県立音楽堂と比較するのも無理だが、音が全くドライで響かず、オケも可哀そう。おまけに、舞台の上は灼熱地獄とのことで、井上道義もアンコールの前に、「このホールもそろそろ手を入れた方がいい。」と発言。思わず、同感の拍手をしてしまった。富山県にも、良いシンフォニーホールが是非ほしい。 |
|
|
|
|
|
|
|
アジアフィルハーモニー管弦楽団2007 2007年8月6日 オーバードホール
指揮 チョン・ミョンフン |
|
アジアフィルハーモニー管弦楽団は、、世界各国の主要オーケストラで活躍しているアジアのプレーヤーが、活動時に集まり演奏するスタイルを持つ、非常設のオーケストラ。チョン・ミョンフンが主宰し、東京で1997年に産声をあげたそうだが、その後活動休止期間があり、2006年に韓国インチョン市がスポンサーとなり、活動を再開したとのこと。オーケストラ・アンサンブル金沢よりも、数名のプレーヤーが参加している。今回は、日本では東京と富山、韓国ではソウルとインチョンで演奏会が開催されるとのこと。なぜ富山での開催となったかは不明だが、チョン・ミョンフンと富山との密接な関係が、公演の実現に関係しているのだろうと推察される。
さて、この日の演奏会、大きなプログラムの変更があった。前半のドヴォルザークの交響曲第6番が、第8番に変更された。理由は不明だが、これにより、メーンディッシュが2つ並んだような、重たいプログラムという印象となった。勿論、6番より、8番の方が有名であり、又大変な名曲でもあるので、聴く方としては面白みはあるのだが、こう2つ大曲が並ぶ演奏会も珍しい。
又、この日のオーケストラの編成はコントラバスを10本並べるという、ブラームス、ドヴォルザークにしては考えられないような18型の編成で、これも又びっくり。広いオーバードホールの舞台も、狭く感じるほどの人数。そして、配置もビオラを右端に置くという変わった配置。低音部の厚みを出そうとした配置か。
チョン・ミョンフンは、私も好きな部類の指揮者で、その熱い感情表現は、時にものすごい熱気をはらんだ音楽空間を創造する大きなスケールの指揮者で、その意味で今回は期待していた。
しかし、どうしたことか、この日の演奏では、やたら演出色が鮮明に出て、音ばかり大きな、やや空虚な、指揮者の空回りのような、つまらなさを感じたのは何故であろうか?
プログラムの編成はいうまでもなく重要なことで、交響曲2曲というプログラミングに無理があったのではなかろうか。小曲から徐々に音楽的感興を高め、フィナーレにそれにふさわしい大曲を持ってくるというプログラミングは、それなりに意味を持っていると思うのだが。
最初のドヴォルザークでは、非常に遅い出だしからして、意図的な演出を感じ、やたらテンポを動かすので、この交響曲の持つ自然な美しさが損なわれ、ギスギスした音の大きさだけが鼻につくような、いじりすぎの演奏となってしまっているような気がした。部分的には美しい箇所も多く、、盛り上がりもある演奏なのだが、全体として印象は希薄。
後半のブラームスは、ドウ゛ォルザークよりも、面白く聴けた。1楽章の序奏部の、これもテンポの遅い出だし。ティンパニーを思い切り鳴らし、劇的緊張感を高める。主部でもテンポは遅め、チョン・ミョンフン独特の粘り気のある歌わせ方が印象的。第2楽章の古典的な静謐さ、ヴァイオリン独奏と管楽器のコラボレーションなど、聴かせどころはきちんと押さえている。全楽章を通じて、この作品では極端な演出は控え、重厚さを失わないような配慮のある演奏と感じた。しかし、全体的な印象としては、やはり、熱気の感じられない、やや厚化粧的な演奏という感じ。
チョン。ミョンフンのようなタイプの指揮者は、やはりムラが多い指揮者なのだろうか?
オーケストラも臨時編成のオケという印象で、個々の奏者の技量は相当なものと感じるが。オケ全体としての個性は希薄。このオーケストラの色というものが感じられない。
というわけで、やや期待外れの演奏会ではあった。
来年、このメンバーを中心として、富山市民オペラ事業の第2弾、「ラ・ボエーム」の公演があるとのこと。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第225回定期演奏会 2007年7月21日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 安永 徹
ピアノ 市野 あゆみ |
|
安永・市野のOEKへの登場は、今回で4度目とのことで、息のあった共演者といえるだろう。
ということで、今日は実に安定した音楽が聴けたという印象。
前半がモーツァルトのピアノ協奏曲第22番K482、後半がバッハのヴァイオリン協奏曲第1番、最後がシューベルトの交響曲第3番D.200。最初にモーツァルトのピアノ協奏曲から始まるというプログラムも珍しいが、バッハ以外、取り上げられるのが珍しい作品を中心としたというのも、面白いプログラミング。「大作曲家の隠れた名作」とでもいえようか。
最初のモーツアルト、後期のモーツァルトの協奏曲の中では地味な存在の作品だが、堂々とした劇的な開始、最終楽章の魅力的なロンドの旋律など、聴きどころの多彩な協奏曲。市野は実に安定したスタイルで、尚且つモーツァルトの表現に最も適した泡立ちの良い音色を聴かせてくれた。
全体は落ち着いた色彩に彩られるが、時にちょっとしたテンポのゆらめきでモーツァルトの心情の複雑さを表すところなど、心をゆさぶる趣がある。
休憩後のバッハ、ここでは何といっても安永徹の美音につきる。これほどストラディバリウスを、その楽器にふさわしい華やかさで鳴らせることができる奏者はそんなにいないだろう。であるからして、バッハが゜実に壮麗に響く。伴奏のOEKも安永につられて、弦の華やかな合奏を聴かせてくれた。
最後は、これも珍しいシューベルトの3番の交響曲。この頃の交響曲としては。第2番が比較的多く演奏されるようで、私も大好きな作品だが、この3番も実にのびのびとした、新鮮な交響曲。後のシューベルトの交響曲のように、かなり無理をしたなと思わせるところが無く、一筆書きのような、情感のほとばしりがある。ハイドンでも、モーツァルトでも、もちろんベートーヴェンでもない、みずみずしい息吹が感じられる交響曲。
ここでも安永は指揮台に立つことなく、コンサートマスターの席で、ヴァイオリンを弾きながらの
指揮。というよりも、室内オーケストラのリーダーの様な存在か。
アンサンブル金沢の合奏能力の高さを聴かせてくれた演奏。細かいパッセージのやりとりなど、指揮者がいないと難しいと思われるような箇所も、難なく演奏していく様は、このオけの完成度の高さがうかがわれる。その反面、音楽の微妙な呼吸のようなものは、やはり指揮者がいないと、難しいようで、巧みではあるが、色彩感はやや乏しいとも感じた。これは、他の指揮者のいない室内オーケストラ、例えばオルフェウスなどにも、共通して感じる部分でもある。やはり、指揮者というのは大切な存在なのだろう。
アンコールにグリーグの「ホルペアの時代から」第1曲。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラと遊ぼう 2007年7月13日 オーバードホール
指揮 井上 道義
新日本フィルハーモニー管弦楽団
AUBADEジュニアコーラス
チームmao 藤井雅子 廣川奈美子 |
|
「井上道義と新日本フィルによる、おとなとこどものためのコンサート」と副題がつけられ、「楽しくなけりゃ音楽じゃない!」というテーマの基に開かれたユニークなコンサート。
一部に、山本直純作曲、阪田寛夫作詞による、管弦楽と合唱のための組曲「遠足」、第二部にストラビンスキー「火の鳥」組曲(パペット、映像、ダンスでおくる「音楽の絵本」)をメーンとしたプログラム。
コンサートの名前通り、この日のオーバードホールは親子連れで賑やか。クラシックのコンサートにあまり縁のない子供たちに、このように魅力的な構成で、音楽の楽しさに触れる機会を与えることは、とても大切で、この日は多くのオーケストラファンの卵たちを育てたのではないかと思う。
内容も、妙に子供に媚びたものでなく、素晴らしい音楽であれば、素直に子供たちは楽しみ、感動するだろうという、井上道義の姿勢が表れているものだった。
一部はJ・シュトラウスⅡの「常動曲」で始まり、ベートーヴェンの序曲「レオノーレ第3番」、そして山本直純作曲、阪田寛夫作詞にる、管弦楽と合唱のための組曲「遠足」、第二部が井上道義と司会の廣川奈美子のお話に続いてパペット、映像、ダンスでおくる「音楽の絵本」ストラビンスキー「火の鳥」組曲(1945年版)。
前半が舞台上で、後半がオーケストラピットにオーケストラが入るという、かつて見たことのないような構成。最初から、舞台上とオーケストラピットにオケ用の配置がなされており、更になんと休憩時間に舞台上の大転換、オケ用反響板を取り除き、舞台に転換する様をショーとして観客に見せるという前代未聞の試みがなされた。このため、休憩時間は約30分ほどの長さとなった。
J・シュトラウスⅡの「常動曲」では、オレンジ色のTシャツを着ての登場、独特の飛び跳ねるような指揮ぶりに音楽も弾む。来年のアンサンブル金沢でのニューイヤーコンサートで「シュトラウスばかりがニューイヤーコンサート゜でない」といいながら、シュトラウス一家の音楽が一部組み込まれているが、それが楽しみになるような、痛快な演奏。井上の面目躍如という演奏。
次のベートーヴェン序曲「レオノーレ第3番」では、一転して黒の燕尾服で登場。音楽に対する向き方を服装で示すというユニークさ。ここでのベートーヴェンは緊張感に溢れた、鋭い演奏。壮大というより、鋭角的なシャープな演奏。有名なファンファーレのトランペットは舞台裏でなく、3階席左手前方の方から聴こえてきた。これも、立体的な演出。
子供たちには、少し難解な音楽かも知れないが、約15分ほどの長さ、集中して聴いている子供が多いことは、子供たちは素直な感受性を持っているものという感慨をもつ。
一部最後は、大変演奏されることが珍しいため、「山本直純の幻の名曲」とも言われるという、山本直純作曲、阪田寛夫作詞にる、管弦楽と合唱のための組曲「遠足」。遠足の一日を、山本直純らしい、素朴さと、懐かしさと、溌剌とした音楽に載せて描きだした楽しい組曲。ここでは、公募で集まった富山県の小学生から高校生までの合唱団が、見事なハーモニーを歌い上げていた。富山県の子供の合唱団の水準の高さを示していた。途中入る、ボーイソプラノ、ソプラノのソロも澄み切った子供の声を聴かせてくれた。
休憩時間の舞台の大転換。オーバード゙ホールの3面半舞台の広さを実感。音響反射板がするすると動き、舞台裏に収まる様は圧巻。又、オーケストラピット全体が下がり、沈んでいく様子も珍しい見もの。井上道義の発案でないかと思わせる、何でもショーにしてしまえというえ意図が面白い。子供たちも初めて見るオーケストラピットの中を興味深そうにのぞきこみ、沈む様を目の前で見て、興味津津の様子。
第2部は井上道義のお話で開始。司会が「曲によって指揮する顔を変えるのですか? 」という質問に、「変えるのではなく、変わるんです。変える、と、変わるでは、全く違いますよ」という答えに、音楽に対する井上の姿勢がわかるようで納得。
さて最後は、パペット、映像、ダンスでおくる「音楽の絵本」ストラビンスキー「火の鳥」組曲(1945年版)。1919年版の組曲でなく、やや曲数の多い1945年版を使っているのが珍しい。
舞台上にスクリーンが組まれ、そこにコンピューターによる映像と影絵、更に王子と王女のダンス、パペットというのか、一種の人形劇による魔王を躍らせるという、抽象と具象を組み合わせたようか舞台。ここでも、井上の引き締まった、ややドライとでもいえるような音楽作りが印象的。ロンドや子守唄の冷たい叙情性、カスチェイの凶暴な踊りの引き裂くような鋭さ、エンディングの鋭い盛り上げ、井上の特長がよく表れた演奏。魔王カスチェイは大きな人形を2人で操っていたようだが、映像・影絵の効果と相乗し、面白い世界が表れていた。子供たちも、映像と生のオーケストラのコラボレーションにくぎ付けになっているよう。
アンコールにストラビンスキーの「サーカスポルカ」、後半に例の魔王の人形が登場、ユーモラスな踊りを披露してくれた。
ユニークで面白い企画。子供たちにとっては、「楽しい」音楽に触れられる貴重な体験となったのではなかろうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢 能登半島復興支援 チャリティーコンサート
2007年6月7日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響
ピアノ 菊池 洋子 |
|
金聖響のブラームスシリーズ、大阪では全4曲の交響曲が演奏されることとなっているが、金沢では定期に組まれているのが、先日の1番と11月の3番のみ。今回能登半島復興支援 チャリティーコンサートとして、2番が演奏されることとなった。そして、菊池洋子をソリストに迎えての、ピアノ協奏曲第1番というプログラム。8日の大阪では「悲劇的序曲」が演奏されるが、金沢では割愛されているのが残念。
金聖響のブラームス、先日の第1番で堂々たるスケールの演奏が聴けたので、今回も非常に楽しみ。
ピアノ協奏曲第1番では、菊池洋子が、女性と思えない壮大なスケールのブラームスを聴かせてくれた。長大な1楽章、ドラマティックな出だしから金聖響は、炸裂するような、しかし厚みのある弦の響きを引き出している。ビアノはオーケストラの提示の後、静かに入ってくるが、この部分の沈潜した響きは、ブラームス独特の「ぶつぶつ」とつぶやいているような雰囲気をよく表現している。
オーケストラとピアノの掛け合いも絶妙。金の協奏曲は、常にやや挑戦的な姿勢を見せるが、今回もかなり挑戦的。しかし、ピアノも全く退くことなく、そのオケに挑むよう。第1主題をピアノが再現する部分など、テクニックの見事さは無論だが、精神的な緊張感がみなぎり、壮絶とでも形容したいような迫力を感じる。
第2楽章では、1楽章と対照的な沈潜した静けさが楽章を支配するが、ここでのピアノも実にしっとりとした、落ち着いた響きを出している。ブラームス独特のいぶし銀のような響きとでもいえようか。オーケストラの響きも厚みと、管楽器のしみじみとした歌が印象的。
第3楽章では、舞曲的な激しさの交錯の中での、ピアノの分厚いテクニックが印象的。菊池洋子は、激しいが、きちっとした構成感を保ち、重厚な緊張感を失うことなく、最後まで見事に弾ききった。金聖響も中庸のテンポながら、、最後はややアップ気味な高揚感をもって全曲を閉じた。
極めて大きなスケールを感じる演奏であった。
この見事な演奏に客席のあちらこちらから、ブラボーの大きな声が飛び交った。
アンコールにブラームスの有名な「ワルツ」。これも、落ち着いた気品のある演奏。
休憩を挟み、後半は交響曲第2番。以前も書いたが、最近はブラームスの交響曲の中で最も演奏頻度が高い作品ではなかろうか。その割に、なかなか良い演奏に巡り合えない作品でもある。
これも、金聖響の特徴がよく表れた演奏。細部まで神経が行き届いていながら、全体のがっちりとした構成感を失うことなく、指揮者の息遣いまで気くことが出来るような、生々しさを感じる演奏である。
第1楽章の出だしの3音が、この楽章全体を支配し、時に沈潜し、時に高揚するのだが、全体にこの3音のうねりのようなものが、この楽章のテーマであると思うのだが、今日の演奏では、そのうねりが実に重厚に出ていて、気持ちを高揚させる。その意味で実に統一感のある演奏である。かなり、細部にこだわるのだが、細部が全体を作っているということが、聴いていてよくわかる演奏。ただ、この楽章全体の牧歌的な雰囲気は、やや失われ、鋭さのようなものを感じる演奏ではあった。
第2楽章も、実に丁寧な演奏。ブラームスの歌が綿々と響く。管と弦の調和も見事。
第3楽章はかわいらしい楽想だが、ここでは木管が実によい響き。
フィナーレの第4楽章、決してあわてずしっかりとした足取りで進み、エンディングも、ややテンポを上げながら、金管を壮大に響かせる。1楽章の出だしから、4楽章のエンディングまで、劇的とさえいえるような構成を感じさせる、見通しの良い演奏であった。やはり、金聖響という指揮者、音楽を作り上げていく上で、直観的な鋭さを身につけている指揮者という印象を聴くたびに強くする。
アンコールは無し。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第223回定期演奏会 2007年6月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 アヴィップ・プリアトナ
クラリネット 遠藤 文江
合唱 バターヴィア・マドリガル・シンガーズ |
|
今日は、プログラム、演奏者とも独特なもの。プログラムがオール・ウェーバー、そして指揮者と合唱団がインドネシアという異色の組み合わせ。
当初、故岩城マエストロの指揮が予定されていたと記憶するので、死去にともない、バターヴィア・マドリガル・シンガーズの主宰者、アヴィップ・プリアトナがそのまま全体の指揮をとることとなったようだ。想像するに、この合唱団の素晴らしさにほれ込んだ岩城マエストロの置き土産のコンサートかもしれない。
プログラムはオール・ウェーバーで、歌劇「魔弾の射手」序曲、舞踏への勧誘、クラリネット協奏曲第一番、後半が「魔弾の射手ミサ」というもの。プレトークで池辺晋一郎氏が語っていたように、オールウェーバーというプロは非常に珍しい。
さて、前半のウェーバーの2曲。無難な演奏ではあったが、音楽的感興には乏しい演奏。
歌劇「魔弾の射手」序曲は、遅いテンボをとり、全体をがっちりとまとめようという意図は聴けたが、ウェーバー独特の、わくわくするような音楽の進み方がなく、各駅停車をしてしまっているような印象。「舞踏への勧誘」も、同様に楽しく踊っていない。手堅さのみでない、面白く音楽を表現する術が聴きたかった。
クラリネット協奏曲第一番の独奏者の遠藤文江。以前から、OEKの木管パートの巧みさに注目していたが、このクラリネット、技巧的にも完璧、そして生き生きしたフレーズの表現力など、見事な演奏だった。このコンチェルトのロマン派らしい華々しさと、感傷を、実におおらかに気持ちよく聴かせてくれた。第2楽章では、非常に珍しいホルンとのかけあいがあるが、この部分でのホルンとクラリネットの対話も、面白く聴くことができた。今日は最初の序曲からホルンの活躍する場が多いが、すべて無難にこなしていた。第3楽章の軽妙なフレーズの技巧の鮮やかさも特筆。
アンコールに、この協奏曲の献呈者、ベールマンのしみじみとした「アダージョ」。美しい感傷的な旋律が、朗々と歌われ、クラリネットの持つ、「歌う楽器」という特色が最大限発揮されていた。この遠藤文江、タフな方のようで、後半のミサ曲にも、団員として再び登場していた。
後半は非常に珍しい、聖なるミサ第一番「魔弾の射手」ミサ。解説書によると、ヨーロッパでは、比較的多く演奏されるということだが、日本では演奏される機会はほとんどなかろう。全体は、典礼ミサの常道に従って作られているが、諸所に歌劇「魔弾の射手」の動機が聞かれるので、このように名付けられたとのこと。
ここでは、合唱団バターヴィア・マドリガル・シンガーズの素晴らしさに尽きるといえよう。独唱も、合唱団員が受け持っているが、ソリスト級の実力を聴かせてくれた。
指揮者アヴィップ・プリアトナは、前半と異なりここでは、水を得た魚のように、生き生きとした音楽を聴かせてくれた。やはり、本来の合唱指揮で、自らの個性を主張できたよう。
30名弱の合唱団だが、かなりの声量で、弱音部の繊細さから、強音部の輝かしさまで、幅広い。そして、ハーモニーの美しさは抜群で、各パートがくっきりと浮かび上がる。
ミサという宗教典礼用の作品だが、その意味を超えてドラマティックな世界を現出させていた。
ウェーバーのオペラ作曲家としてのドラマティックな側面がよく表れた作品と思えるが、この合唱団はその劇的側面を生々しく表していたように思える。
アンコールにインドネシア民謡と思われる、日本の唱歌にも似た素朴な作品が、無伴奏で歌われた。プレトークでも、インドネシアの民謡を同じく無伴奏で、踊りながら歌ってくれたが、無伴奏でのハーモニーの美しさは尚輝いていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第222回定期演奏会 2007年5月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ディヴイット・スターン
ヴァイオリン 庄司 紗矢香 |
|
今日は、何と言ってもチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の庄司 紗矢香への期待。
プログラムはコダーイ「ガランタ舞曲」、チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲」、後半がメンデルスゾーン交響曲3番「スコットランド」。
ある意味、多彩な民族色を感じさせるプログラム。
指揮はディヴイット・スターン。紹介記事には記載されていないが、名ヴァイオリニスト、アイザック・スターンのご子息とのこと。
プレトークで池辺晋一郎氏がそのことに触れ、妙な縁という風なことを言われた。
つまり、今日の庄司 紗矢香の使用のヴァイオリンが19世紀の名ヴァイオリニスト、ヨアヒムが使用していたストラディヴァリウス、そしてチャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲」は同じ19世紀の名ヴァイオリニスト、アウアーに捧げられている、そして指揮のスターンは20世紀の名ヴァイオリニスト、アイザク・スターンの息子、そして庄司 紗矢香は21世紀のヴァイオリニストのホープ、と3世紀にわたるヴァイオリニストの系譜が示されるというわけ。なるほど、そのように考えると感慨深い演奏となる。
最初はコダーイの「ガランタ舞曲」。調べてみると2004年9月の166回定期で岩城マエストロが同じ作品の演奏を行っている。その時の演奏は、かなり良い意味での泥臭さを感じる演奏だったことを思い出す。今日の演奏はむしろコダーイの野暮ったさを排除し、すっきりとした舞曲の面白さを浮き出せたような演奏。この後のチャイコフスキーでも感じたが、スターンという指揮者、民族的な作品も、民族色よりも、すつきりとした構成感、てきぱきとしたメリハリを押し出そうとするような演奏。ある意味、物足りなさも感ずるところもある。もう少し、粘り気のある面もほしい気もするのだが。
さて、チャイコフスキーの庄司 紗矢香。5月初めの東京での「熱狂の日」のウラルフィルとの共演に続いての演奏。その時の演奏もFMでオン・エアーされていたので聴いてびっくりしたが、今日も全く完璧な演奏。このテクニックの難しい協奏曲を完全に消化し、自分の音楽として再現している。この年齢で、過去の名ヴァイオリニストを凌駕する演奏を行うのにはびっくり。
カンタービレでの、のびのびとした歌、早いパッセージでの唖然とするような技巧、そして全体の構成をきちんと見極めた冷静さ。この協奏曲の面白さは、このような演奏でこそ再現されると、改めて納得させられた。オケに合わすというより。挑戦し、挑発するような即興性。
第3楽章でも全く急がずどのように早い部分でも、ごまかすことなくすべての音が聴こえてくる。
オケもこの楽章、管楽器群のヴァイオリンとのかけあいなど見事。お互いに触発し合っている瞬間が聴こえてくる。コーダの部分の前、庄司はグット上を向き、上部の客席に鋭い視線を向けけ、最後の爆発に向かっていく様は、このヴァイオリニストのギリキ゜リの緊張感を感じた。
アンコールにバッハ。これも、一週間前の諏訪内の流麗なバッハと対局をなすような個性的な演奏。
きっちりとした古典的な構成感と素朴さを打ち出し、バッハの舞曲のスケールの大きさを示すような演奏。
後半はメンデルスゾーン交響曲3番「スコットランド」。魅力的な作品なのだが4番のイタリアなどに比べると、演奏される機会がそんなに多くないのではないだろうか。私も、ライブで聴いた記憶がない。
スターンはこの作品の古典的な端正さをすっきりと描き出していた。もう少し、メンデルスゾーン独特の感傷的な旋律の歌わせ方があっても良いような気もするが、これがこの指揮者の特質なのだろう。クリヴィヌなどもそうだが、室内オーケストラの指揮者にはこのような淡白なタイプが多いのかもしれない。フルオ-ケストラと異なる、クリアーさと丁寧さが室内オケには要求されるということか。
OEKは弦楽器、管楽器とも好調。最近のこのオーケストラの好調さを感じさせてくれた。
思ったより長い時間の演奏会となり、バス時間に追われ、急いでホールを後にしたので、アンコールがあったのか不明。 |
|
|
|
|
|
|
|
ハンブルグ北ドイツ放送交響楽団演奏会 2007年5月14日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 クリストフ・フォン・ドボナーニ
ヴァイオリン 諏訪内 晶子 |
|
昨夜に続いての石川県立音楽堂。続けて通うのも初めてだが、それだけ聴きたいコンサートが連続していたわけ。
まず、ドボナーニという指揮者、名前は良く知っているのだが、生は勿論のこと、放送、CDでもじっくりと聴いたことがないので、非常に興味があったこと、ヴァント時代の北ドイツ放送響の素晴らしい演奏を知っているので、是非そのオケを耳にしたかったこと、等が理由である。
結論からいうと、本当に面白く、興奮させてくれたコンサート。
プログラムはメンデルスゾーン、「ルイブラス序曲」、「ヴァイオリン協奏曲(ヴァイオリン 諏訪内 晶子)、後半がチャイコフスー交響曲第6番「悲愴」、というオーソドックスなもの。
まず、このオーケストラの並はずれたパワーとその音の重量感。さすがに、ドイツのオケ。ベルリンフィルあたりの垢ぬけた軽さと比較すると、なるほどこれが本来のドイツのオケと納得してしまう。
最初の序曲は手慣れたもの。安定感のある響き、ブラスの重厚な響きなど、このオケの特質をあますところなく披露し、なによりも自信に満ちている安定感を感じる。
諏訪内晶子の独奏による協奏曲。ここでも、オケは決して感傷におちいらない、古典的な端正美と、深い響きを聴かせてくれる。今日の諏訪内は非常にのっている演奏。特に第一楽章は、彼女独特の高音ののびやかで艶やかな音色、そして堂に入った歌わせ方など聴かせどころ満載の演奏。今まで、何かもどかしさを感じることが多かった彼女の演奏だが、今日はそれを突き破り、自分の持っている美点を最大限生かそうという音楽が聴かれ、一皮むけたなという印象を持った。楽章終りの、アッチェランドで追い込んでいくところなど、今までの彼女の演奏になかった迫力と爽快感を感じた。第二楽章中間からやや音程に揺れが見られたこと、第三楽章がやや、性急過ぎたのでないかなどの気になる点もあったが、目指す演奏スタイルがよく聴こえた演奏となっていた。
そして、なによりも個性的だったのはアンコールのバッハ。これほど艶やかでなまめかしいバッハは初めての経験。なるほど諏訪内というヴァイオリニストの個性はこれだっのだと、納得させられ、バッハの別の面を認識させられるような演奏。是非、全曲を聴きたいものである。
後半はチャイコフスキーの6番。ここでは、2楽章の途中から、終楽章までが圧巻。
2楽章の始まりから、なにかもたもたした鈍重さを感じたが、それが実に後の楽章を予感させる伏線であることに途中から気付く。この楽章はワルツであるが、その特異なリズムからも、単純なワルツでなく、チャイコフスキーの屈折した鬱の感情を色濃く描き出したものであることが、ドボナーニの演奏からは浮き上がってくる。だから、もたもたと漂っているのである。そして、第3楽章の躁状態の興奮から、4楽章の絶望への段差のすごさ。3楽章のコーダの金管、ティンパニー、大太鼓のすさまじい進行。そして、最終楽章の弦の低音の、将に地の底から響いてくるような呻き。ここでは、このオケの個性的な響きが、実に効果を上げている。ワーグーナーの音楽はこんなオケを想定して作られたのかと納得してしまうような、分厚い響きである。
4楽章はこの重い響きが全楽章を支配する。コーダの部分のミュートをつけた、ホルンの絶望感に満ちた叫び゛。そして、暗く重いファゴットの響き。
この交響曲の面白さを、徹底的に掘り出したドボナーニという指揮者。やはり、実力者というほかない。
アンコールは無し。このような「悲愴」の演奏の後では、アンコールは無理であろう。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第221回定期演奏会 2007年5月13日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 下野 竜也
ピアノ フィリップ・アントルモン |
|
故岩城浩之マエストロが振る予定だったプログラム。下野竜也が代演となった。
このプログラムが組まれたころ、マエストロはかなり体力的に参っていた時期と考えられるが、それでもこのシ-ズンには晩年のライフワークであったベートーヴェンのみのプログラム、それも大曲ばかりのプログラムを組むというすごさ。執念を感じる。そういう意味で、この日のプログラムは単なる名曲コンサートとは、意味合いが異なる。
そのプログラムを、若手、いやもう中堅か、の下野竜也が振るという興味。
プログラムは「エグモント序曲」、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、交響曲第3番「英雄」。体力と集中力が指揮者にも、聴衆にも要求されるプロ。
下野竜也は、この大きなプログラムに臆することなく、等身大の演奏を聞かせてくれた。
オーケストラの配置も通常のもの、最近流行の古楽スタイルをとることもなく、正面からベートーヴェンと取り組もうとする誠実な演奏と思えた。
最初の「エグモント序曲」が、素晴らしい演奏。ベートーヴェンの激しい、劇的な構成をきっちりと明確に打ち出していた。テンポも中庸、すべてのパートをくっきりと浮かび上がらせながら、主題の展開を明瞭にしながら、誠実に進んでいく演奏。小細工は一つもなく、楽譜の指定どおり進めることにより、ベートーヴェンの巨大な世界を展開させる。
5番の協奏曲はフイリップ・アントルモンを独奏に迎えた。
アントルモンは2004年の定期で、同じ5番を弾き振りしたのを思い出す。あの時は、指揮をしながらのピアノという、この大曲では、考えられないような演奏だったが、それ故に、より調和を重視したような、ややおとなしい演奏と感じたが、この日はピアノに集中できるということで、かなり自由な、ファンタジックな世界を感じさせてくれた。それでも、指揮者としての本能がうずくのか、オーケストラの演奏場面では、いかにも自分が指揮をしたいような素振が見えたのも、面白かった。音は明るく、この協奏曲のある面、アポロン的な明るさというか、豪壮さのみでない、キメの細かい演奏、。音の粒の立ち上がりの輝かしさなど、このピアニスト独特の世界。
独特なリズム感も印象的。第2楽章に、こんなリズム感があったのだということを、再認識させられた。下野竜也の演奏も誠実。ピアノと調和しようという意識が見られ、アントルモンも演奏しやすそう。オケも響きが充実し、あいまいさのない好演。第2楽章から3楽章へのブリッジの部分の、ホルンの同一音の弱音での気の遠くなるような持続など、破たんなく演奏していた。
アントルモンはアンコールにショパンのポロネーズ。フランスの伝統的なショパンといってよいか。洒落ていながら、ポロネーズ独特のリズム感を強調した、魅力的な演奏。
後半は3番「英雄」。最初に「等身大の演奏」と書いたが、この交響曲では特にそれを感じた。
決して背伸びをしない、つまりいじらない、楽譜のありようを忠実に再現しようとした演奏と感じた。であるから、オケにも相当な要求をしたであろうことが感じられ、各細部までよく聞こえる見通しの良い演奏。欲をいえば、この大曲を感情移入のある、下野竜也ならではという演奏にしてほしかったが、それは今後の楽しみか。演奏とは難しいもので、聴衆は、やはり音楽に酔いたいから通っているのであり、良い意味での「アクの強さ」、もその要素の一つではなかろうかと思うのだが。
歌劇「フィデリオ」から、ロッコの入場の際の行進曲、という珍しいアンコール。
下野竜也、初めてその指揮に接したが、どんどん若手から中堅に力のある指揮者が続いているという印象を更に強く持った。 |
|
|
|
|
|
|
|
ショスタコーヴィッチ弦楽四重奏曲全曲連続演奏会第2夜 2006年4月23日 北日本新聞社ホール
Quadrifoglio(《四葉のクローバー》
第一バイオリン サイモン・ブレンディス
第二バイオリン 竹中のり子
ビオラ 石黒靖典
チェロ 大澤明 |
|
前回、実に広く、深い世界を聴かせてくれた、ショスタコーヴィッチ弦楽四重奏曲全曲連続演奏会の第2回目。今回も、実に力のこもった、深い世界をQuadrifoglioは聴かせてくれた。
今回は7番、12番、3番というプログラム。演奏順番が制作順でないのは、演奏効果上の問題を考えてのことだと思われるが、今回の場合3番、7番、12番でもよかったような気もする。3番が実に重い内容で、フィナーレにふさわしいという意図があったのだろうと推察するが。
今回の全作品は、すべて戦後の作品。7番、12番などは、ついこの間の作品である。その時代をつい先ほど過ごしてきた人間にとって、これらの作品の持つ意味が、実感として体感できるという面白さがあった。それとともに、この時代の日本の作曲家と比較し、ショスタコーヴィッチが、いかにヒューマンな意識をしっかりと持った、スケールの大きな作曲家であったか、ということを改めて知らしめてくれた。現代のベートーヴェン、なるほどショスタコーヴィッチはそういう作曲家であったと実感できた。そして、ベートーヴェンが交響曲において描いた世界と弦楽四重奏曲で描いた世界が、異なるように、ショスタコーヴィッチも弦楽四重奏曲iおいては、心の内面を率直に吐露しているように思える。
7番は、小ぶりの作品であるが、第1楽章のやや軽めの世界、第2楽章の重い雰囲気、第3楽章の激しさと対比が印象的。「妻ニーナの思い出に捧げる」というプログラムの解説だが、妻との懐かしい思い出、そしてしみじみとした愛情、亡くなったことに対する激しい憤り。そんな風に聴いたら、あまりにも詩的すぎるだろうか?
第12番は日本でいえば昭和43年、ショスタコーヴィッチ61歳のときの作品。この頃は、私は大学生、ベトナム戦争が拡大しつつあった頃。序奏部の主題は12音技法て゜不安定な開始。しかし、徐々に旋律的に安定してくるのは、ショスタコーヴィチの前衛に対するアンチテーゼのようにも聴こえる。第2楽章は全体が一つの作品のように4つの楽章とも思える部分で構成されている。ここでは、激しさ、深い瞑想が、実に巧みな作曲技法によって展開される。第2部のチェロのうなるような深い響き、それが他の楽器に引き継がれてとうとうと流れる様。そして最終部の堂々とした展開。
第3番は、1946年の作品。交響曲でいえば、9番の後に位置する。第1楽章は明るい雰囲気で始まるが(しかし、その明るさのなかには何か空虚さも感じる。このあたりが、ショスタコーヴィッチの一筋縄でいかないところか。)、2楽章以降はが゜らっと変化し、激しさと、痛烈な慟哭、怒り、そして明日への希望を思わせるような透明なヴァイオリンの響きが消え去っていき、全曲が終わる。プログラムの説明によると、各楽章には当初各々表題がつけられていたとのこと。第2次世界大戦が終わり、世界は解放されると思いきや、冷戦の時代に入っていく、この作品には、その暗い時代の影が、ショスタコーヴィッチの言葉によって、如実に語られているように思える。絶望しながらも、希望をもちたいという複雑な心情。
あらゆる作曲技巧が駆使され、、めくるめくような世界を現出させながら、その技法がショスタコーヴイッチ自身必然であったと納得させられる凄さ。そこに、シヨスタコーヴイッチの音楽の誠実さを見る。そして、弦楽四重奏曲の中には、そのようなショスタコーヴイッチの音楽の凄さのエッサンスがつまっているように思える。
今日の、Quadrifoglioの演奏は第一回と同様、あるいはそれ以上の表現力を聴かせてくれた。第一ヴァイオリンのサイモン・ブランディスの鋭い、つきさすようなヴァイオリン、チェロの大澤明のうなるようなチェロ、竹中のり子の第2ヴァイオリン、ヴィオラの石黒靖典が内声部をがっちりと固めるなど、あいまいさのない、各々の奏者の声と息遣いが聴こえるような、迫力ある四重奏。
今後の展開が益々楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第219回定期演奏会 2007年4月21日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響
ヴァイオリン シュロモ・ミンツ |
|
先月の定期は、町内会の仕事の関係で残念ながら聴くことができなかったので、久しぶりの音楽堂である。
今月の定期は、期待の金聖響のブラームス。今年はブラームスの交響曲全曲に挑戦するとのことで、大いに楽しみである。というものの、第4番は金沢では予定されていないのが残念。大阪では全曲演奏が予定されているので、早い機会に金沢でも4番の演奏を実現してほしいものである。今日は更にシュロモ・ミンツという、ヴアイオリンの名手をソリストに迎えているので、それも楽しみ。
金聖響の人気か、今日の音楽堂は補助席まで完売、立ち見席まで販売されるほどの超満員。先日の井上道義の監督就任演奏会の時と同様の盛況である。やはり、クラシック音楽への人気が盛り上がってきているのだろうか、うれしい状況である。
プログラムはオールブラームス、「大学祝典序曲」、ヴァイオリン協奏曲、交響曲第1番。
オーケストラの配置は金聖響独特の配置。両翼配置とコントラバスの左側への配置は、古典的配置だが、トランペット、トロンボーン等を右側に一列にやや離して配置するのが、独特。今日はこの配置の効果がよくあらわれ、金管が埋没せずよく響いていた。ティンパニーもバロックティンパニー使用なので、歯切れのよい、インパクトの強い響きが効果的。
最初の「大学祝典序曲」では、金の衒いの無い、率直な、一筆書きのような演奏が印象的。オケは最初の曲でもあり、やや硬さが見られ、金管が音を外すなど、普段のOEKに見られないミスがあったのが残念。このあたり、最初の序曲とはいえ、もう少し練りこんだ演奏を要求したい。
ウァイオリン協奏曲での、シュロモン・ミンツ。テクニックと音の輝き、美しさは勿論のこと、全体の構成をがっちりとおさえ、さらに細部まで磨きこまれた、巨匠の演奏。第一楽章のブラームスらしい、しみじみとした楽想と、怒涛のような情熱、この二つの対比が見事に浮き上がっていた。
自分の独奏の際も、オケの響きに耳を澄まし、協調しようとする姿勢は、協奏曲の面白さ、独奏楽器とオーケストラのからみあいの面白さを、存分に聞かせてくれた。第2楽章では、オーボエなど木管楽器とヴァイオリンの対話が素晴らしい。オーボエの素晴らしい音色は秀逸。
第3楽章は生き生きと、しかし重量感に満ちた演奏。全体に、主張がはっきりしとし、個性的でありながら、それが独りよかりにならず、、ブラームスのこの協奏曲の魅力をたっぷりと表現するあたり、やはり円熟の演奏である。
アンコールにバッハ。これは、もう名人芸の極地のような演奏。やや早いテンボをとり、旋律の絡み合いを、実に巧みに面白く、ある意味万華鏡の如く聞かせてくれた。
さて、後半はブラームスの1番。OEKのブラームスとしては、おそらく最高の演奏と思われるほどの名演。太い骨格、うねるような展開、沈潜と高揚、そして爆発。ベートーヴェンでの金聖響と異なり、テンポも中庸、決してあせらず、インテンポを持続させながら、音楽に力強さを与えていく。重厚でありながら、重くなりすぎす、生き生きとしている。細部まで、神経が行き届いている。
1楽章序奏部の堂々とした開始、ティンパニーの炸裂、主部に入ってからの展開の面白さ。
提示部の繰返しを省略せず演奏するなど、極めてブラームスの意図に忠実な演奏でありながら、金聖響の熱い思いが聞こえてくる。2楽章では、丁寧に旋律を描きながら、甘くならず、ブラームスらしい秘めた情熱を聞かせてくれた。金管、木管、ヴァイオリンの独奏の絡み合いも絶妙。4楽章では、序奏部でホルンを堂々と鳴らす。全く躊躇することのない率直さを感じる。
有名な第一主題も滔々と響かせ、どんどんと高揚していく様は、この交響曲の真髄を示してくれた。50分以上の演奏時間の中での緊張の持続。4楽章のコーダが堂々と終わり、金聖響は、ぐったりと、しかし満足の笑みをたたえていた、オーケストラも精根尽きはてたという様子ではあったが、満足の輝きがあった。
プログラムの中で「自分が描くブラームスを皆様と天国の岩城先生に来く聴いていただきたい」と語っているが、天国の岩城マエストロも、「俺を超すなよ。」と苦笑しているかもしれない。
今まさに旬。そんな金聖響を聴けた一夜。
今後の金聖響-OEKに益々の期待が募る。 |
|
|
|
|
|
|
|
諏訪内晶子・ニコラ・アンゲリツシュ デュオリサイタル 2007年3月4日 入善コスモホール
ヴァイオリン 諏訪内晶子
ピアノ ニコラ・アンゲリツシュ |
|
クラシックの演奏会の入場者が段々減りつつあるようで、年間の公演回数も減りつつあり、寂びしい感じのするコスモホールだが、今日は久しぶりの満席。諏訪内人気をうかがわせる。
伝統のあるホールなので、灯をたやさないでほしいと切に思う。
さて、昨年ファジル・サイとのデュオが予定されていたが、芸術上の理由とかで、延期となり、共演者をニコラ・アンゲリッシュに変更し、時期をずらして実現された演奏会。
諏訪内とサイと聞いた時、アンバランスも感じたが、反面新しい諏訪内の境地も聞けるかもという期待もあったが、延期と聞き、やはりという感じではあった。
ニコラ・アンゲリッシュはサイに比べれば、正統的なビアニスト。諏訪内とは相性もよいのだろう。
今日のプログラムは、ソナタ3曲というどっしりとしたもの。
モーツァルトの40番KV.454、ドヴュッシーのソナタ、そしてベートーヴェンの9番「クロイツェル」
全体の印象としては、やはり冒険をしない、安全運転のヴァイオリンということ。テクニックは素晴らしい、音色も美しく響きも大きい。全く優秀なヴァイオリンなのだが、印象としては平板。時には、退屈さも感じてしまう。ドラマと情熱を感じさせない、優等生的な面を感じてしまう。
中では、ドヴュッシーが面白かった。人工的な美しさが極まっていて、緻密なクリスタルのガラス細工のような旋律の重なりが見事。テクニックの栄えと、美音ががこのソナタにぴったりとしている。
モーツルトは整ってはいるが、モーツァルト独特の愉悦と憂愁が聞こえてこない。
ベートーヴェンも見かけとしては雄大なスケールで、細部まで彫琢の凝らされた演奏ではあるが、求心力というか、説得力というか、聴衆へのアピールを感じさせない演奏。このヴァイオリニスト、このもどかしさを、いつ突き崩してくれるかと、聞くたびに期待するのだが、なかなかである。別の意味での円熟が出来てくるのか?
ピアノのニコラ・アンゲリッシュは、さすがという演奏。この日は、自己主張を極力抑えて、デュオとしての調和を重視しているようてあったが、随所に聞かれる作品へのアプローチはしっかりとしたものを感じた。独奏者として聞いてみたいピアニスト。
アンコールは何番のソナタか思い出さないが、ベートーヴェンのソナタの2、3楽章のよう。今後、ベートーヴェンへのアプローチをしていくという諏訪内の意思表明か? |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢 井上道義 音楽監督就任記念公演
「雅楽・声明との出遭い。」
2007年2月25日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 井上道義
雅楽 東京楽所 声明 比叡山延暦寺法儀音律研究部 天台聲明音律研究会 |
|
いよいよ、井上道義のアンサンブル金沢での挑戦が始まったことを印象付ける刺激的な演奏会。
前半に、石井真木の大作、後半にモーツァルトというプログラミングの大胆さもさることながら、モーツァルトにおける、挑発的な演奏は、井上道義がどんな世界を今後金沢で展開させていくのかという、期待と興味を大いに抱かせてくれた。
音楽堂は、井上人気か、雅楽、声明への大いなる期待か、補助席も完売、立ち見まで出る盛況。外のポスターには、「SOLD OUT 完売」のお知らせが踊り、大変な盛況の幕開けとなった。
プロク゜ラムは前半が、舞楽「萬歳楽」、石井真木「聲明交響Ⅱ」(オーケストラ金沢バージョン)、後半がモーツアルト交響曲第39番。
演奏前に、池辺晋一郎が井上新監督の簡単な紹介、そして井上自身のトークと続く。井上の、「金沢のいたるところを舞台としたい。」、「僕は楽しいことが大好き、明日楽しいことがあるかな?というのでなく、今を楽しみたい。」という言葉が印象的。
オーケストラコンサートでは例が無いと思われる、舞楽「萬歳楽」で開幕。舞台中央に朱塗りの欄干を形どった舞台を特設、雅楽の管方は右側に、左側にオーケストラ、舞台奥に声明の僧たちのひな壇という配置。舞楽「萬歳楽」は東京楽所(宮内庁式部雅楽部のメンバーが中心となり結成された、プロの雅楽団とのこと。)のメンバーにより演奏される。
舞楽を実演で見るのは初めての経験。実にゆったりとした、しかし力強い悠然とした世界が繰り広げられる。笙、篳篥、龍笛ののびのびとした音律、鼓、太鼓の独特な間延びしたリズムが印象的。素朴、単純ではあるが、実に雄大な、おおらかな世界を感じる。
次は、石井真木の「聲明交響Ⅱ」(オーケストラ金沢バージョン)。
雅楽と、声明、オーケストラ、更に舞方を要するので、演奏されるのは非常に珍しいだろう。
オーケストラは左側、編成は小さいが、特筆すべきは打楽器の多様さ。大太鼓、テインパニはもちろん、ベル、鈴、木琴、ヴィブラフォン、更にはティンパニの皮の上に小さなおりんのようなものが数個置かれ、ティンパニー奏者が叩く。さらにハープも入り、多彩な音色が交錯する。雅楽の、笙、篳篥、龍笛の3人が、管方とは別にオーケストラの中に入り木管奏者のような役割を担っている。
真っ暗なホールのオーケストラ部分にランタンの様な照明が、フロア数か所に置かれ、幽玄とでも形容できるような世界を現出。更に正面のオルガンのバイプに、赤銅色の照明があてられ、ホール全体に宗教儀式のような雰囲気が漂う。
その中を、客席の通路から、声明の僧たちが声明を奏しながら登場。これは列讃といわれる部分のようだが、声明の宗教儀式に沿った展開となっているよう。昨年富山能楽堂で富山の声明研究会の僧たちによる、珍しい会があり、そこで初めて声明に接したが、宗教儀式としての声明には細かい約束事があるようで、この日の演奏にもそれは忠実に再現されているようだ。
石井真木は、この声明の儀式と、全く別の世界の雅楽を融合し、統一した新しい音楽世界を現出させている。声明が進むにつれ、雅楽が入り込み、そこにオーケストラの多彩な響きが混ざりこみ、不思議な世界を現出させている。更に、後半には「鳥」を象徴した舞方が入り踊る。
声明と雅楽、オーケストラの渾然一体となった響きは、一種異様でもある。
声明はグレゴリア聖歌のような響きも感じる。
終結部は、オーケストラのパーカッション群のすさまじい咆哮。一種の宗教的恍惚の世界か。
後半はがらっと変わり、モーツァルト。休憩の間に、舞台はすっかり変換され、通常のコンサートホールに変身。裏方の苦労を思う。
モーツァルト39番第一楽章の序奏が始まったとたん、「え、こんな響きだった」という驚きを感じる。今まで聴いてきた39番と全く異なる響き。トランペットの突出した響き、一種の不調和のような異様な響き。「ロマンティックなモーツァルトを期待すると、裏切られるぞ」とでもいいたげな、挑戦的な開始である。
オケの配置は、対向配置、ただしコントラバスは右側、ティンパニーはバロックティンパニを使用。なるほど、徹底した古楽指向の配置。そして、弦もノンビブラートを要求しているよう。
であるからして、非常に鋭いモーツァルトの演奏となっている。各パートを明確に響かせ、あいまいさは許されない。テンポはかなり、早め。これはオーケストラにとっては、かなり過酷な演奏である。
第2楽章も、実に淡々とした流れ。いわゆるカンタービレがないので、古典的端正さが際立つ。
第3楽章メヌエットの有名な中間部での指揮ぶりは、見ていて思わず笑いを誘うよう。腰をくねらせながら、手は泳ぎダンスをしている。「こういう風に、演奏してね」と姿で示しているよう。かつてダンスをしていたという、面目躍如。
最終楽章も、さっそうとしたテンポて゜かけぬける。アクセントをつけるときのアクションも実に独特。
アクセントとリズムの強調など、井上道義のモーツァルトに対する独特なアプローチを聴くようで、今後どのような世界を聴かせてくれるか、良しあしを別として、期待させ、予感させてくれるような39番だった。
アンコールに「フィガロの結婚」序曲。客席の岩城マエストロ夫人、木村かおりさんに対し、「今日も岩城さんにです。木村かおりさん、あなたたちの結婚はどうでしたか?」と問いかけてのアンコール。
もともとテンポの早い序曲だが、更にスピードアップ。オーケストラは大変!!
ここでも、「あれ、こんな旋律が鳴っていたのだ。」と気づかされる、各部分が明瞭に浮き出された演奏。
9月からの新シーズンに井上道義監督がどのようなアプローチを見せてくれるのか、非常に楽しみとなってきた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第216回定期演奏会 2007年2月9日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮とヴァイオリン マイケル・ダウス |
|
ヴィヴァルディーの「四季」とピアソラの「ブェノスアイレスの四季」を組み合わせたユニークなプログラム。
以前入善コスモホールで、クレメルとクレメラータ・バルティカで同様のプログラムを聴いた。
最近、この組み合わせのプログラムがしばしば演奏されているようだ。
前半がピアソラの作品、有名なりベル・タンゴを含め5曲が演奏され、後半が2つの四季。
編成はこれらの作品の編成としては大きいと思われる弦楽合奏。第1ヴァイオリン7人、第2ヴァイオリンが6人、ヴィオラ、チェロが4人、コントラバスが2人、それにチェンバロ(後半)という変則的な編成。
これだけの編成でピアソラを演奏するのは、合わすという点で大変難しいと思われるが、アンサンブルは精緻で、調和していた。ただし、やはりピアソラ独特のテンポ・リズム感という点では、これだけの編成では難しい点があるという印象。少々厚ぼったくなりすぎ、切れ味が鈍い感じ。マイケル・ダウスはバンド・ネオンを思わせるような奏法で、ビアソラの哀愁を醸し出していた。「二調のミロンガ」では、チェロのカンタの独奏が独特の効果を与えていた。
後半は、1時間10分程の熱演。
ヴィバルデイーは「春」から、ピアソラは「夏」からという順序で、ヴィバルディーの後にピアソラが入るという、演奏順はクレメルと同様。ただクレメルの場合はピアソラも「春」から入っていたような記憶があるが。ピアソラの中にもヴィバルディーが顔を出し、特に最後のピアソラの「春」では、終結部にヴィヴァルディーの春の旋律がチェンパロで回想されるように静かに奏でられ終わるので、効果的な順序であろう。
バロックと現代という対照的な組み合わせだが、違和感はなく、むしろコントラストの鮮やかさが面白い。
ダウスは特に奇をてらった演奏でなく、各曲の特徴を明確に描き出すような、オーソドックスな演奏。
ヴィバルディーでの独奏ヴァイオリンも鮮やか。ピアソラは前半に比較し、作品の性格の違いもあるだろうが、情熱を感じさせてくれた。
こうして、弦楽合奏のみで、OEKを聴いてみると、最近の演奏の充実ぶりがよりはっきりと聴こえ、室内オケとしてのアンサンブルのまとまりの良さをしっかりと聴くことができた。オケとしての基礎的な能力の高さを示したといえる。
アンコールに珍しい作品。出口の掲示を見ると、ペレチス「歴史の如く」とあった。岩城マエストロへの、ダウスの哀悼の意のようだが、痛切に独奏ヴァイオリンが歌い、しみじみと心を打つ。 |
|
|
|
|
|
|
|
フィンランド放送交響楽団演奏会 2007年2月7日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 サカリ・オラモ
チェロ ミッシャ・マイスキー |
|
フィンランド放送交響楽団は、20年程前に、旧の富山公会堂で、サラステの指揮で聴いた。その頃は、富山では演奏されるのが珍しい、マーラーの第5交響曲が演奏されたのを覚えている。パワフルなオケという印象が鮮やかに残っている。
又、ついこの間NHKのベストオブクラシックで、1週間にわたり、オラモの指揮でシベリウスの全交響曲(クレルヴォも含み)が放送され、改めてシベリウスの素晴らしさに開眼したような気がしたものだ。
そんなわけで、今日の演奏会は大いに楽しみにしていた。
プログラムはシベリウスの交響詩「タピオラ」、ドヴォルザークのチェロ協奏曲(チェロ:ミッシャ・マイスキー)、ブラームスの交響曲第2番。シベリウスの交響曲が聞けないのが残念だが、堂々たるプロである。最近はブラームスでは、2番が盛んに演奏されるようで、面白い現象でもある。一時代前であれば、1番、4番が指定席だったような気がするが。
オラモという指揮者、実にスケールの大きな音楽を創り上げる指揮者。最近の指揮者に珍しい、ロマン的な音楽を聞かせてくれる。最近は、古楽ブームということもあり、どうも小手先器用な指揮者が多く、面白くはあるが、どこかその音楽の本質とは違うのではないかという、細部をひねくりまわしすぎの様な音楽を聞かせる指揮者が多いように感ずるが、オラモは異なり、全体の構築がしっかりとたてられ、その構築の中で細部に神経が行き届いているので、実に全体的なまとまりがよく、音楽の全体像が示される。
オーケストラの配置は対向型だが、コントラバスは右側。16型の大きな編成で、舞台一杯にオーケストラが広がっている。
最初のシベリウスの「タピオラ」。出だしのティンパニーの音、ヴァイオリンの細かいパッセージから、見たことの無い、フィンランドの深い森と湖が、浮かび上がってくる。最初の主題が、シベリウスらしく、点滅しながら、ある時は盛り上がり、そして鎮まる。晦渋という印象の強い、後期のシベリウスの作品であるが、こうしてフィンランドのオーケストラと指揮者で生で聴くと、実に魅力的な作品であることが実感できる。終結部近く、すさましい弦楽器のざわめきがあるが、森を吹き抜ける鋭い風の音を感じる。フィンランドの自然の中にたたずむ、シベリウスの孤高の姿が強く印象付けられる。晩年のシベリウスの、、自然に対する畏敬の念と、自らの人生への率直な回顧の気持ちが、淡々と語られているという印象(といっても、亡くなるまでの20年間の創作の空白はあるのだが)
マイスキーはリサイタルを含め何度聞いただろうか。ドヴ゛ォルザークも、3年ほど前に、高岡でラトヴィア交響楽団との演奏を聴いた。その時は、何か一つ乗り切れないもどかしさを感じた。
今日、改めて聴いてみて、なるほどマイスキーの本質は、外面的な派手さを求めるのではなく、その作品を自らがどう読み解くかを誠実に追及しているのだということが、強く感じられた。
外に対する見せびらかしでない、実に誠実な、彼自身の作品との対話のような演奏。
であるからして、気持ちがシックリいかないときの演奏は、つまらなくなることがあるのたろう。
今日の演奏は、オラモに触発されたこともあるのだろうが、実に説得力のある演奏。ドヴォルザークの懐かしい旋律を、表面的でなく、共感をもって再現していた。オラモは、ここでも滔々たる流れのある。スケールの大きさを感じる演奏。マイスキーは虚飾の少ない原典版を使用とのことだが、そこにもマイスキーの誠実さを感じる。
アンコールにバッハ。マイスキーのバツハは、極めて詩的な演奏。ここでも、バロックの壮大な構築を聴かせるのでなく、バッハと自らが確かめ合い、対話をしているような演奏。
後半はブラームスの第2交響曲。生で幾度となく聞いてきた作品だが、満足いく演奏に出会ったことがない。それだけ、ブラームスは奥が深いということか。今日の演奏は、ベストに近い演奏。
全体の構成ががっちりしていて、がっちりした構成の中で各細部を緻密に再現していく。各主題の歌わせ方もロマンティックで、かつ率直。ブラームスのこのシンフォニーの喜ばしい感情と、やさしい感情が、率直に訴えかけてくる。静かな部分から、盛り上がりまで、自然に音楽がうねっていく様は、音楽を聴く興奮をかきたててくれる。ブラームスはやはりロマン派の音楽家であることを再認識させてくれた。
オーケストラも、やや硬質の音ではあるが、分厚い響き。弦、木管、金管それぞれバランスがとれ、個性のある音を持つ、優秀なオーケストラである。
第4楽章の終結部も、ゆっくりとしたテンポで、あせらず堂々とオケが鳴り響く。充実したエンディング。
アンコールはブラームス「ハンガリー舞曲第一番」とシベリウスの「悲しきワルツ」
ブラームスのやや遅めのテンポで、舞曲が分厚く展開していく様、シベリウスの繊細な弦の響き。対照的な、見事な2曲のアンコール。
終演が9時30分を回った長い演奏会だったが、充実した気持ちでホールを後にした。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第215回定期演奏会
モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
(コンサートホールオペラ形式)
2007年1月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
フィオルデリージ 尾崎 比佐子 ドラペッラ 福住 恭子 フェランド 谷 浩一郎
グリエルモ 迎 肇聡 デスピーナ 田邉 織恵 ドン・アルフォンゾ 安藤 常光
語り 竹崎 利信
合唱 オーケストラ・アンサンブル金沢合唱団
指揮 金 聖響 |
|
マイスターシリーズとファンタジーシリーズの2回公演の内、今日はファンダジーシリーズでの公演。
恐らく、金聖響、国内で初めてのオペラ挑戦でなかろうか。
今日の公演は、制作の中心が大阪音楽大学のオペラ研究室とのことで、出演歌手も大阪音大の出身者が中心となっている。
コンサート形式のオペラで、舞台装置らしきものは、ステージ奥のひな壇の両側の西洋風な柱とワインを乗せるテーブルのみ。但し、出演者は衣装は着けているので、オペラの雰囲気は味わえる。そして、注目すべきは、同時通訳の電子掲示が無いこと。ドン・アルフォンゾの使用人という、原作には登場しない人物を狂言回しの語りとして登場させ、物語の進行をわかりやすくしている。
同時通訳無しという事で、原語のわからない私のような聴衆は、ややとまどうが、しかしその分音楽に集中でき、感覚が分散されない効果がある。ミラノスカラ座の日本公演の際、スカラ座の強い要請で、やはり電光掲示をやめたというニュースを聴いたが、こうして実際に接してみると、とまどいはあるものの、音楽の全体の流れに集中できるという実感を体験し、なるほど面白い試みと感じた。又、語りの竹崎 利信が実に巧妙で、大阪弁での語りが、モーツァルトと全く一体化し、ドラマの進行を面白くしている。この竹崎 利信、舞台、客席、オルガン席、2階席と神出鬼没の大活躍。
歌手達も好演。重唱が多く、重唱の魅力たっぷりのオペラであるので、特に注目したが、ハーモニーも、個性もきっちりと決まり、愉悦感の溢れる舞台となっていた。特に、フィオルデリージ 尾崎 比佐子 、ドラペッラ 福住 恭子、ドン・アルフォンゾ 安藤 常光の演技力と歌唱力が光っていた。
オケはひな壇の前に位置し、コントラバスを左に配置した両翼配置の古典スタイル。ティンパニーもバロックティンパニーを使用しているようで、キリリと引き締まった響きとなっていた。
金聖響の指揮は、独特の早いリズム感とたたみかける様なスピード感が特長。1幕の最後の終曲など、歌手達もついていくことが大変と思わせるアップテンポで興奮をかきたてながらの終幕。若々しいモーツァルトを聴かせてくれた。
旬の指揮者と、若々しい歌手達による、新鮮で、心ときめくモーツァルトだった。 |
|
|
|
|
|
|
|
ショスタコーヴィッチ弦楽四重奏曲全曲連続演奏会第1夜 2006年1月10日 北日本新聞社ホール
Quadrifoglio(《四葉のクローバー》
第一バイオリン サイモン・ブレンディス
第二バイオリン 竹中のり子
ビオラ 石黒靖典
チェロ 大澤明 |
|
一昨年、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲演奏を成し遂げた、オーケストラアンサンブル金沢のメーンバーによる弦楽四重奏団、Quadrifoglio(《四葉のクローバー》が、メンバーを一新し、ショスタコーヴィッチの弦楽四重奏曲全曲演奏という、地方レベルでは考えられないようなコンサートに挑戦することとなった。今回も、主催は富山市岩瀬地区の有志による実行委員会。興行レベルでは、考えられないようなこの企画を実行されたのが、素人の実行委員会であるのに驚く。音楽を興行として捉えない熱意あるメンバーだからこそ実現した企画といえるだろう。そして、アンサンブル金沢という土壌があってこその企画ともいえる。日本、いや世界でも稀なコンサートといえるだろう。そして、地方の一都市で、このような贅沢なコンサートを聴けることの幸せも、実行委員会の方々のご苦労があってこそと感謝。
当日のプログラムも、富山在住の音楽学者谷口昭弘氏による丁寧な楽曲解説、実行委員会代表、参納純三氏による富山の音楽史、犬島肇氏によるショスタコーヴィッチ論と、充実した内容。音楽に解説は不要という論もあるが、やはり構成、背景などを知ることは、聴く上での作品の理解を大いに助けることとなるので、このようなブログラムは有り難い。
今回は、第1ヴァイオリンにOEKコンサートマスターのサイモン・ブレンディス、第2ヴァイオリンにOEKの新人竹中のり子を迎え、一層アンサンブルに磨きのかかった演奏を聴かせてくれた。
この四重奏団、アンサンブルが見事。各パートがクリアーに響くと同時に、アンサンブルとしての調和がとれ、そしてなによりもシュスタコーヴィツチの楽譜を自らのものとしている自信に満ちた演奏となっていた。
プログラムは当初、モーツアルトの「狩り」の四重奏曲が入っていたが、変更され、オールショスタコーヴィッチプログラムに変更された。ショスタコーヴィッチの弦楽四重奏曲全曲演奏という企画意図からして、当然の変更といえる。
前半に1番と11番、後半にエレジー、ポルカという小品に、8番という構成。
ショスタコーヴィツチの面白さに、あらためて目を開かされた一夜。
最初の1番は、4楽章形式の古典的な形にのっとているが、8番、11番では構成は自由となり、ショスタコーヴィツチの内面世界が自由に展開される。
1番は古典的な形式にのっとっているとはいえ、内容は既にショスタコーヴィツチ独特の魅力に溢れている。第1楽章出だしの不安定な主題の提示、2楽章の民謡風の沈潜など、独特の世界を感じさせる。次の11番に至っては、後期のショスタコーヴィッチのモノローグを聴くよう。ここでは、特に重要と感じられる第2楽章での、各楽器の独奏の受け渡しなど、見事な効果を表し、演奏も極めて説得的。作曲者の暗い深淵に触れるようであった。第6楽章の低音楽器と、高音楽器の分厚いユニゾン、そして第7楽章では、再び回想、深い沈黙の中に曲は終了する。
後半の傑作第8番は将にすさまじい演奏。この作品のテーマが、“DSCH”、すなわち作曲者自身であることが、強烈に印象づけられる。「ファシズムの戦争の犠牲者の思い出に捧げる。」と記されているが、後にショスタコーヴィッチ自信は、「戦争を直接的に描いたものではない」と否定したという話も伝わる、謎に満ちた作品。しかし、その第2楽章の強烈なたたきつけるような怒り、第4楽章の静かな祈り、そして5楽章の深い悲しみの表出など、やはりその戦争の時代に生きた、ショスタコーヴィッチ自身の深い憤りと祈りが、この作品に込められていると、改めて感じさせられた。
政治的に利用されることを嫌い、しかし、あの時代に生きるためには、政治といかにかかわっていくか真剣に考えざるをえなかったショスタコーヴィッチ。その複雑な心情の吐露が、弦楽四重奏曲には溢れている。そう、強く感じさせられる名演であった。
そして、シヨスタコーヴィツチの世界は、色々な色彩が混在する、目くるめくような面白さがあると。知らしめてくれた。
後半の最初には、小品二曲、「エレジー」、「ポルカ」が演奏された。ショスタコーヴィチの両極端、沈潜とバカ騒ぎ、を象徴するような作品配置で、これも面白かった。ポルカはアンコールでも演奏され、昨日のOEK定期演奏会のブレコンサートでも演奏されたので、3回聴くこととなったが、皮肉と諧謔という、ショスタコーヴィッチのある面の特色を顕著に表した面白い作品。
これから、恐らく4回ほどであろうか、続く演奏会への大いなる期待を抱かせる、そして富山でショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲全曲を、生で聴くことが出来るという至福の一夜であった。是非最後まで、完結して欲しい。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第213回定期演奏会 2007年1月9日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ルドヴィーク・モルロー
チェロ 遠藤 真理
ソプラノ ジョアナ・ゲドミンタイテ |
|
今年初めて聴くコンサート、そしてOEKのニューイヤーコンサート。
音楽堂はエントランスから華やかな飾りに包まれ、職員も正装、一部女子職員は着物を着て、新年らしい華やかさ。舞台にも、簡素だが、美しい花が飾られ、金沢らしく、客席にも着物姿の女性が見受けられる。古都の正月の音楽会を感じる、気持ちの良い雰囲気につつまれていた。
今日の指揮は、ルドヴィーク・モルロー。2005年4月にもOEKを振っているようだが、その時はマイスターシリーズだったので聴いていない。
今年のニューイヤーコンサートは、前半がオッフェンバック、サンサーンス、後半がシュトラウス一家の音楽という構成。3年前2004年のニューイヤーコンサートで、ウィンナワルツばかりのニューイヤーコンサートとは、いかがなものかと苦言を書いたことがあるが、今年はその意味で若干改善されているようだ。特に、前半の演奏が素敵だったのは、この指揮者の個性と選曲がピッタリだったからだろう。新年だからといって、定番がウィーンナワルツ・ポルカである必要は全然ない。聴衆を楽しませる工夫があって然るべき。
さて、前半はサンサーンスのチェロ協奏曲(遠藤真理のチェロ)を挟んで、オッフェンバックの序曲と小曲という構成。
最初のオッフェンバック「天国と地獄」序曲。独奏楽器の歌と、後半のカンカンが魅力的に演奏され、明るいきらめきに満ちた演奏。クラリネット、チェロの独奏など、伸びやかに歌っていた。後半のカンカンは快適なスピードで、野暮ったくならず、さすがフランスの指揮者と思わせる洒落た演奏。
サンサーンスのチェロ協奏曲。サンサーンスらしい華麗さと、情熱に溢れた作品。チェロの遠藤真理は、ゆっくりとした部分は伸びやかに歌い、激しい部分は情熱的にと、くっきりと描き分けた巧みな演奏。これに、なんらかの“個性”が加われば一層面白くなるのだろうが、それは今後の楽しみか。
一部最後はオッフェンバックの「ジャクリーヌの涙(チェロとオーケストラのための)」とう、珍しい作品。チェロがしっとりと歌い、オーケストラが寄り添う、心地良い一品。OEKの弦の優しい美しさが印象的。
後半はヨハン・シュトラウスのオペレッタ「こうもり」を中心とした組み立て。ソプラノにリトアニアのソプラノの新鋭ジョアナ・ゲドミンタイテが加わる。
最初はヨハン・シュトラウスのワルツ「朝の新聞」。アンコールの「青きドナウ」とワルツは2曲。
ウインナワルツ独特の官能的な魅力は感じられない、良く言えは゛若々しい、しかしそっけない演奏。ウィンナワルツほど、演奏する側にとって難曲はないと思う。良く言われる、ワルツの独特の刻み方など、真似してできるものではない。もう、そのあたりは“血”としか言いようの無いものがある。各パートの演奏者が、その独特の節回しを自らのものとして、更に合奏としてまとまらないと、全くつまらない。これは、ウィーンの完全な民俗音楽であって、インターナショナルなものではないと思うのだが。アルゼンチンタンゴや、ディキシーランドジャスのような、ノリを必要とする。だから、やたらと演奏するものでないと思うのだが。
「こうもり」の序曲と数曲のアリア。ワルツやポルカと違って、このような作品は楽しめる。序曲も、曲想がめまぐるしく変化する難しい作品と思うが、モルローは各部分をキチット描きわけ、面白く聴かせてくれた。ソプラノのジョアナ・ゲドミンタイテは、やや硬質の声で、温かみが欲しいと感じたが、巧みな歌い方ではあった。アンコールにレハールのメリーウイドウから。これは、なかなか素敵な歌だった。
最後の「芸術家のカドリーユ」。過去の作曲家の作品をごったまぜにした、機智に富んだ作品。ウィーンフィルの数年前のニューイヤーコンサートでも演奏されていた。モルローは、このような作品は最も好きらしく、バカ騒ぎの面白さを楽しませてくれた。
アンコールの「青きドナウ」は前述の如く。急流のドナウ川であった。
最後は定番の「ラデツキー行進曲」。モルローは手拍子まで、細かい指示をする入念振り。細部を大切にする指揮者らしい。 |
|
|
|
|
|
|
|
新日本フィルハーモニー交響楽団演奏会 2006年12月26日 オーバードホール
指揮 小澤 征爾
ピアノ ユンディ・リ |
|
オーバードホール開館10周年記念演奏会
さすがに、小澤人気は凄く、チケットは早々と完売となったようだ。クラシックでも、スタープレーヤーは入るということか。それにしても、これだけのクラシックの底辺人口があるなら、他の音楽会ももっと盛況であって然るべきと思うが、どこに原因があるのだろう。不思議な思いだ。この音楽会の質に匹敵する、あるいは以上の質の音楽会も多く開催されていると思うが。
さて、今日の拾い物は、ユンディ・リ。当初予定の、ルトスワフスキーの「管弦楽のための協奏曲」が、どんな理由によるのか、ラベルのピアノ協奏曲に変更となり、ユンディ・リが組み込まれた形。これは、有り難い変更。旬のピアニストを聴く機会ができたわけだから。
そのユンディ・リ、期待に違わぬピアニスト。そのみずみずしい叙情性、歌、そしてきらめくようなピアニズム。鮮やかなラベルだった。中国人としての特色か、その歌が、この作品の東洋的な叙情性にピタリ。そして、ラベル特有のキラキラと輝くようなパッセージはフランスのピアニストを想起させるほど。ここでは、小澤の水際立った伴奏も見事。
小澤を聴くのは2回目。最初は、もう40年近く前となるだろうか、小澤がN響とのトラブルで失意のどん底にあった頃、励ます演奏会が開かれ、旧日本フィルと演奏したのを聴いたこと(日比谷公会堂だったか?)。その後は、20年ほど前か、旧富山公会堂での演奏会。オケは忘れたが、メンデルスゾーンのイタリア交響曲のつまらなかったことと、休憩後のラベルの「ダフニスとクロエの第2組曲」が、対照的に素晴らしい演奏だったことを鮮明に思い出す。
今日の演奏を聴きながら、小澤の長い遍歴と、その間に培ったであろう磨かれた、オーケストラドライブのテクニックに歴史を感じた。ラベルでの、隅々まで磨きこまれた響き、そしてピアノを引き立てる管弦楽法の巧みさを鮮やかに浮き上がらせる手法、これは小澤の美学の真骨頂であろう。第2楽章の静かなピアノの歌に添いながら、木管とホルンがからみあい、低域の弦が優しく支える箇所のヴアイオリンの響きなど、ぞっとするような静謐な美を感じる。そして、消え入るような2楽章の最後。
ユンディ・リのアンコールが2曲。得意のショパン、ノクターン、中国の作品。ノクターンは意外とさっぱりとした演奏。
休憩後はチャイコフスキー。演奏されるのが珍しい交響曲第一番「冬の日の幻想」。
ここでも、ラベルと同様、細部まで磨きこまれた演奏。言ってみれば、計算しつくされた演奏。それはそれで、美しく華やかではあるのだが、果たして?と考えてしまう演奏でもあった。私の肌にはぴったりこない。音楽に一番必要な何かが欠けていると感じてしまう。お酒で言えば「淡麗」なのか、コクが無い、あっさりとしすぎている。ここまで、完璧な演奏であるのだが・・・・・・・
私が音楽に求めるのは、その作曲家の人生ドラマであり、又再現する演奏家の熱い思い。この演奏にはそれが感じられない。こういうスタイルの演奏も確かにあるのだろうが。
昔から小澤征爾という音楽家に抱いていた「偏見」がそう聴かせるのだろうか。残念ながら、その「偏見」は、今回も氷解しなかった。
アンコールにチャイコフスキー弦楽セレナーデ第三楽章から。 |
|
|
|
|
|
|
|
桐朋アカデミー・オーケストラ 特別演奏会 2006年11月24日 オーバードホール
指揮 高関 健 |
|
桐朋学園の学生、卒業生を中心としたメンバーによる演奏会。桐朋学園富山キャンパスがあるため、年間に相当数の桐朋の学生による演奏会が開かれており、定期演奏会も既に30数回開かれているようだが、今回は年一回のフル編成による特別演奏会。
前半にハイドンの交響曲第90番、後半にマーラーの交響曲第1番「巨人」。指揮は高関健。
日本の音楽学校の頂点をいく桐朋だけに、プロの卒業生を含めた楽団員の技量はたいしたもの。
前半のハイドンが特に充実した演奏。配置は古典的な両翼配置で、コントラバスも左側に位置している。ハイドンは小型編成での演奏かと思ったが、実際は弦楽器は14型の大編成。管楽器は通常の2管編成。故にかなり、大音響のハイドン。しかし、キリリとした、古典的なダイナミズムを感じさせる演奏で、ハイドンの交響曲の醍醐味を満喫せてくれた。高関健の指揮は、ティクスチュアをごまかすことなく、細部まできちんと描くため、ハイドンの音楽の巧みな構成が鮮やかに浮き出て、充実した演奏となっていた。第4楽章コーダの終結かと思わせる機智に富んだ部分では、意図通り拍手が起き、高関健は、「まだ終わりませんよ」というような身振りで、更に音楽を続ける。この面白さは、ハイドンの時代そのままであろう。
休憩の後、後半はマーラーの大曲。さすがに、このような作品では、学生のオケには限界があるのは、しかたあるまい。テクニックだけで、片付けられるほど、マーラーは甘くないということか。
健闘はたたえるが、音楽的感興の高まりを感じるまでには、残念ながらいたらない。厳しく言えば、バラパ゛ラの演奏で、音の大きさだけでは、音楽は作り得ないということか。再現芸術としての、音楽の難しさを再認識した演奏となった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第211回定期演奏会 2006年11月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ギュンター・ピヒラー
ピアノ スタニスラフ・ブーニン |
|
今年は、9月、10月の定期に用事で参加出来なかったので、定期としては初めてのコンサート。
今日は、ブーニンのピアノがメインのプロ。ブーニンは2002年にOEKと共演しているそうだが、その際は残念ながら聴いていない。
初めにブーニンのショパンのワルツ2曲で始まるという、オケの定期としては珍しいプログラム。
次にモーツァルトのピアノ協奏曲第23番イ長調K.488、後半がシューベルトの交響曲第6番ハ長調D.589という、簡素なプロ。
さて、ブーニン。天才として、かつて大ブームを起こしたピアニストだが、その頃の印象というものが、私にはあまりない。そのブーニンも、もう40歳。どんな演奏を聴かせてくれるのか楽しみである。
最初のお得意のショパンのワルツ(6番小犬、7番嬰ハ短調)。繊細さよりも、ゴージャスな感じとスピード感を感じさせる演奏。もう少し、ショパンらしい繊細さと、音色のデリケートさが欲しい気もした。しかし、さすがに堂に入った演奏ではある。このあたりが、この人の個性か。
次のモーツァルト。これも、かなりドラマ性を求めたような演奏。音も大きく、時々ペタルを強く踏む音も聞こえるほど。全体的には、構築のしっかりとした、古典的な演奏。ただ、その中に微妙なテンポの揺らぎや、時には思い切ったテンポの揺らし方もある。今、ブーニンが追い求めているものと、かつてのブーニンと、丁度その端境期なのだろうか。第三楽章の、例の転がるようなフレーズなど、見事。又、がっちりとした古典的な枠組みを崩さない、言ってみればドイツ的なモーツァルトか。これから、このような面が強く求められれば、求心性の強い演奏を聴かせてくれるのではなかろうか。
アンコールにシューベルトの即興曲から。これも、かなりドラマティックな構成感を感じさせる演奏。ベートーヴェンも聴いてみたいなと、感じた。
ピヒラーのOEKの今日の演奏は緻密なアンサンブル。かつて、2度聴いたが、今回が一番の出来。全体のアンサンブルが素晴らしい。かつては、強奏の部分で、妙に金管や打楽器の突出が目立ったりし、ピヒラーの意図にオケが応えられないような瞬間があったりしたが、今日の演奏では、総ての部分にアンサンブルとしての磨きがかかり、ピヒラーとオケの呼吸の見事な一致があり、音楽が自然に息づいていた。
後半のシューベルト6番も同様の感。古典的な鋭さを要求するピヒラーにオケは十分に反応していた。弦楽器群の柔らかい響き、管楽器のアンサンブル、どれも調和がとれていた。全体は、ピヒラー独特のキリリとしまった、硬質な印象をもつ、引き締まった演奏で、その中にシューベルト独特の歌と踊りが乱舞する様は見事。この交響曲あまり演奏される機会が無いと思うが、シューベルトのシンフォニーへの執着を見るような面白い曲。苦労しても、苦労しても、なかなかシンフォニーとしてまとまらないそんなシューベルトの姿を見るようで、面白い。
第三楽章など、明らかにベートーヴェンへのオマージュ。7番のスケルツォをこんなに意識させるところも、面白い。
アンコールにロザムンデから間奏曲。ここでも、弦楽器と管楽器の優しい歌が印象的。
それにしても、最近のOEKの管楽器群の充実は見事。 |
|
|
|
|
|
|
|
ワディム・レーピン ヴァイオリンリサイタル 2006年11月18日 入善コスモホール
ピアノ イタマール・ゴラン |
|
昨年末の庄司紗矢香、そして今年のワディム・レーピンと、期待のヴァイオリニストを富山で聴くことが出来る貴重な機会。そういえば、ここのホールでは、ヴァイオリンだけでも、クレメルもベンゲーロフも、樫本大進も、竹澤恭子、諏訪内晶子も聴かせてくれた。地方の小さい町で、これだけ充実したリサイタルを開いているのは珍しいのでは無かろうか。それだけに、ここ2~3年の聴衆の減少が心配である。好楽家の層は富山でももっと厚いはずなので、何とか聴衆増の方策をとってほしいものだ。
今日の聴衆も200名余り。勿体ないというか、贅沢というか、複雑な気持ちである。しかし、レーピンとゴランは、少しも手を抜くことなく、圧巻ともいえる音楽世界を聴かせてくれ、ホールは熱狂的な盛り上がりを見せた。
レーピンは、数年前にここコスモホールで聴いたベンゲーロフと同じ旧ソ連出身のヴァイオリニストで、師も同じブロンだが、傾向はかなり異なる印象。
ベンケーロフが陶酔型とすれば、レーピンは堅固な構造型とでもいえようか。
この日のプロは、前半がヤナーチェックのソナタ、ブラームスのソナタ3番、後半がグリークのソナタ3番、ショーソンの詩曲、ワックスマン「カルメン幻想曲」という、それぞれ個性の異なる作品を組んだプロだが、それぞれの作品の個性、聴かせどころを際だたせた演奏。ピアノはイタマール・ゴラン。樫本大進、庄司紗矢香の伴奏でも聴いたが、伴奏という域を超越した、個性的なピアノ。
最初のヤナーチェック。ここでは、ヤナーチェックの、民俗的な面よりも、現代的なバーバリズムのようなものを押し出した演奏。音は極端なほど、くすんでおり激しい。かつて聴いたヤナーチェックの民俗的な側面とはかなり異なる、現代的な激しさを強く打ち出した演奏となっていた。これは、ゴランのピアノによるところも大きい。勿論第2楽章のバラードのカンタービレの際立った優しさなど、素朴な柔らかさももちあわせているのだが、全体の構成としては、ヤナーチェックの苦悩の様なものが強く印象付けられる演奏となっていた。
ブラームス。出だしのうつうつとした主題が次第に高揚し、大きな感情のうねりとなる様はすさましい。高揚するときのピアノとの競い合うようなうねり。ブラームスの後期ロマン派的な内に秘めた感情の表出と、ベートーヴェン的な激しさがからみあう凄さを感じさせる演奏だった。第4楽章は、「アジタート」の指示そのままの激情的な高まりをみせて終結する。構成感を崩さず、しかしながらその枠の中で豊かな感情を表現する、雄大で、逞しいブラームスだった。
後半のプロは一転して、優しい詩的な世界が展開する。このあたりのプログラミンクの妙のようなものも、レーピンの才能の証かもしれない。一つの世界に固執するのでなく、様々な音楽世界を、個性的に演じ分けられる才能。
最初のグリーグのソナタ3番。グリーグらしい、親しみやすい主題が次々と展開する。しかし、ここでも単に優しいのでなく、きちんとした構成を崩していない。だから、音楽は恣意的にはならず、その音楽が本来持つ魅力が輝く。グリーグの北欧独特のクリスタルな透明感が損なわれることは無い。
ショーソンでも、「詩曲」という表題そのままに、ヴァイオリンの浪々たる響きが、全体を纏綿たる情緒で覆い尽くす。ここでのヴァイオリンの厚い響きは、この作品の持つ瞑想的な雰囲気にぴったり。
プログラムの最後は、技巧の粋を極めたような、ワックスマン「カルメン幻想曲」。いかにも、リラックスしたレーピンの技巧の映えが素晴らしい。
アンコールは3曲(パカーニーニ、グラナドス、サラサーテ)演奏され、ホールの興奮は最高潮に達したが、最後に「チゴイネルワイゼン」という大曲を持ってきたのにはびっくり。最初の音が響くと、ホールではざわつきが聞こえた程だった。ここでは、レーピンとゴランはのりまくり。。前半のたっぷりとしたジプシーの歌がゆったりと情感をこめて歌われ、後半の激しさと技巧の見事さ、スピード感。身体を揺すられるような感覚を感じるほどの演奏。
客席の照明が点けられなければ、拍手はいつまでも絶えるこがなかったろう。
一昨年、ルガンスキーと組んだ演奏をビデオで見たが、ピアニストの違いが、やはりレーピンの演奏にも微妙にニュアンスの違いを生んでいることが面白かった。ルガンスキーは繊細な世界を内に持ち、調和していくようなピアニスト。ゴランは、調和するよりも挑発するようなピアニスト。
やはり伴奏者というのも大事な選択肢なのだと、改めて思う。どちらが良いということではなく、生れてくる音楽の世界が異なってくる。面白い経験であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村治 佳織 ギターリサイタル 2006年11月7日 入善コスモホール |
|
久しぶりのコスモホールでの演奏会。今月は、この後、18日にレーピンという大物がコスモホールに控えている。しかし、このコスモホールでの演奏会、内容と正反対に天候には恵まれていない事が多い。今日も、寒冷前線の通過で、朝から20m近い強風に、冷たい雨が横殴りという悪コンデイション。
しかし、そんな天候にもかかわらずホールはほぼ満員。村治佳織に対するファンの多さを物語っている。その期待にたがわず、ギターのあらゆる可能性を村治佳織は披露してくれた。
プログラムは前半がギターの名曲。後半がフランス、日本、ブラジル等のギター曲。
最初のソルの「モーツァルトの<魔笛>の主題による変奏曲」、そして次のタレガ「アルハンブラの思い出」「アラビア風奇想曲」、共にギターの定番名曲だが、村治は新鮮な息吹をこの名作に感じさせてくれた。伴奏と主旋律の対比の鮮やかさ、独特な節回し、多彩な音色、強弱の見事な対比など、ギター一つで奏でられているとは思えない、音楽世界が現出していた。ギターという楽器、両手と指先にのみ頼る最も原始的な楽器であると思うが、それ故に技術的には、ミスがすぐ露呈してしまう難しい楽器であるが、村治はそんなことを一つも感じさせない完璧なテクニックで作品を表現する。
「アルハンブラ」の有名なトレモロなど、これほど詩的で憂いに満ちた表現は聴いたことがない。
繊細で多彩な音色。
次は武満徹編曲のビートルズナンバー、マイヤーズの映画音楽と続く。
ここでも、各曲の個性を際立たせた表現を聴く事が出来た。
後半のフランス印象派、ドビュツシー、ラペ゛ルの小品も、独特のけだるい雰囲気を巧みに出しながら、淡い色彩感を漂わせた雰囲気ある演奏。
完璧なテクニックがあるからこそ、各々の作品の持つ性格をきちんととらえ再現することが可能となっていることを、まざまざと聴かせてくれる。そして、作品に対する深い読み込みと、愛着があるからこそ、聴くものにもその作品の持つ魅力を十分に感じさせてくれる。やはり、類稀な才能である。
吉松隆の「水色のスカラー」よりでも、特殊なテクニックを使いながら、吉松独特の浮き立つような洒落た個性を巧みに現出。
最後は、南米の雰囲気を濃厚に感じさせる、ディアンス、ヴィラロボスの作品を、自らのコスタリカ訪問のトークを交えながら、情熱的に演奏。
決して外面的な派手さは無いが、、作品に対する凝縮された集中度の凄さを感じる演奏家である。
アンコールに2曲。カタロニア民謡「盗賊の歌」、ディアンス「タンゴ・アン・スカイ」
「タンゴ・アン・スカイ」は締めくくりにふさわしい、タンゴのリズムが弾む快演。
得意なロドリーゴが組まれていなかったのは残念だった。 |
|
|
|
|
|
|
|
大阪センチュリー交響楽団・オーケストラ・アンサンブル金沢合同公演
ショスタコーヴィッチ オラトリオ「森の歌」演奏会 2006年11月5日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮:井上 道義 テノール 志田 雄啓 バス 安藤 常光
合唱 「森の歌」特別合唱団 OEKエンジェルコーラス
ピアノ アリス=沙良・オットー |
|
石川県立音楽堂開館5周年記念演奏会。前半にショスタコーヴィッチ「祝典序曲」、ラフマニノフ、ピアノ協奏曲第2番(ピアノ アリス=沙良・オットー)、後半がメーンのショスタコーヴィッチ「森の歌」。
開始は、ショスタコーヴィッチの「祝典序曲」。記念演奏会にふさわしい華やかなファンファーレで開始。勇壮で華麗な中にも、ショスタコーヴィッチ独特のリズム感と旋律を持った作品を、井上道義はくっきりと、メリハリをつけて演奏していた。途中からは、オルガン席前に、トランペット、トロンボーン12本からなるバンダも加わり、ホールが割れんばかりの音響で締めくくられた。
次はラフマニノフ。アリス=沙良・オットー、実に18歳の女性だが、その可憐な容姿にふさわしい、巧みな技巧と、新鮮な感覚でラフマニノフを聴かせてくれた。ラフマニノフとしては、実に爽やかな演奏で、やや物足りないと感ずるでもないが、特にケレンミをひけらかすでもなく、18歳にふさわしい初々しい叙情性を感じた。それに対して、井上道義は、円熟の棒。出だしからとうとうと、遅いテンポで、ラフマニノフ独特の粘っこい歌を、たっぷりと聴かせてくれた。ピアノに遠慮することなく、自らの音楽を展開するあたりは、さすが。こうでなけば、コンチェルトは面白くない。ピアノもそのペースに巻き込まれること無く、自らを主張していたのは、たいしたもの。この若さの身の丈にふさわしい演奏と感じた。アンコールにリストの「ラ・カンパネラ」。超絶技巧の作品だが、ここでも、ガンガン弾きまくるのでなく、丁寧に誠実に楽譜を再現していたのが印象的。それだけに、技巧の映えが際立っていた。
さて、後半のショスタコーヴィッチ オラトリオ「森の歌」。130名余りの合唱団、80名余りの児童合唱、それにフル編成のオケ、更にバンダと、記念演奏会にあさわしい規模で、舞台も、オルガン席のベランダも一杯。客席も満席で、補助席が出るほどで、開館5周年にふさわしい華やかなホールとなっていた。
「森の歌」、私たちの世代の若い頃、日本の民主運動の旗手の如く、もてはやされ、各地で演奏会が開かれたことを思い出す。あの時代は、日本の行く手にまだ未来の明るさを求める新鮮さが、充満しており、ソヴィエトという国家に対する、現在と異なる憧れのようなものが若者の中にあり、それが、この「森の歌」が盛んに演奏された要因となっていた。
ソヴイェトが崩壊し、ソヴィエトのコミュニズムの欺瞞性が明らかにされようになり、その反動としての絶望感、更に日本の社会の閉塞性も進み、この作品は急速に忘れ去られ、演奏されることが゜無くなっていくようになった。それだけに、現在あらためてこの作品をこうして聴く機会を得ると、やはり、ある種のアナクロニズムを感じると同時に、音楽と社会の関わりの難しさ、恐ろしさも感じる。
作品自体は、他のショスタコーヴィッチの作品とは色合いが異なる。「こんな曲なら、簡単に出来るさ」というような、開き直りさえ感じさせられる。極めて簡明、オーソドックスであり、聴きやすく、親しみやすい。ショスタコーヴイッチ独特のアイロニーのかけらさえも無く、創られた明るさのようなものすら感じる。逆説的に考えれば、ショスタコーヴイッチの天才性の証かもしれない。
演奏は、井上道義の明快で、輪郭のくっきりとした演奏が、この作品の面白さを際立たせていた。オケも2つのオーケストラの合同ということを感じさせない統一した響きがあり、アンサンブルは見事に安定していた。男性合唱と児童合唱も立派、ロシア民謡を思わせる部分の両合唱は、この作品の民俗的な特長を良く表現していた。
最終楽章「賛歌」のフィナーレでは、テノール、バスの高らかな独唱に、合唱が加わり、更にバンダのブラスの響き、全オーケストラの合奏が高らかに響き、祝典的な雰囲気をホールに響きわたらせて終わった。
アンコールに、この演奏会を企画し、自ら指揮をする予定だった岩城宏之マエストロを追悼し、バッハの「G線上のアリア」がしっとりと演奏された。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
月田秀子ファドコンサート 2006年10月22日 明治安田生命ホール |
|
昨年11月に立山国際ホテルチャペルにて開かれたのに続き、2回目の月田秀子の富山でのコンサート。
コンサートの内容と関係ないが、こうして同様のコンサートを1年ぶりに聴くと、「もう1年経ったのか」と言う、移ろいの速さにとまどってしまう。それだけ、年をとったということか。
今回は残念なことに聴衆が少なく、主催者の村田さんに言わせれば、「少数精鋭の聴衆」とのことだったが、それだけにじっくりと、しっとりと月田秀子の世界を楽しむことができた。
昨年に比較し、落ち着いたのびのびとした雰囲気が唄に漂っていた気がする。昨年は、初めての富山ということで、気負いと緊張があったのかもしれない。
今回は伴奏が、昨年と異なり、チェロとギター。この伴奏が実に素晴らしかった。ファドにチェロという組み合わせが通常あるのか知らないが、チェロの太く、艶やかな音色は月田秀子の声とフィットして、独特のムードを漂わせていた。(ギター:蓮見昭夫 チェロ:竹花加奈子 伴奏者の名前、紹介程度はチラシに印刷してほしかった。 )
18曲とアンコールで合計19曲の演奏だが、あっという間の2時間弱であった。歌う側にとって見れば、歌い続けの2時間弱というのは、相当過酷なはずだが、全くそれを感じさせない、熱唱だった。
ファドは「心の唄」、今回もそれを強く感じた。音楽は総て心から発しているはずだが、このように率直に、ストレートに心に響いてくることはそんなに多く体験できることではない。唄の内容よりも、その声、旋律自体が、素直に自分の心を揺り動かす。確かに、恋愛の唄、運命の悲劇の唄、抵抗と愛国の唄など、内容も豊かなのだろうし、その内容を表現する歌唱力があるからこそなのだろうが、なによりも原始的な唄の旋律が心を揺り動かす、第一声がホールに響いた時から、その虜にさせられる。ファドという唄の特長は、このような人間の根源的な、率直な、心の叫びとつぶやきのようなものを、ごく端的に表現しているというということを、再認識させられた。
それにしても月田秀子の歌唱力の凄さに、今回も圧倒させられた。
ポルトガルワインでなく、「みゃあらくもん」を時々口にしながらのステージだったが、ファドはやはり、ゆったりと酒をたしなみながら、涙を流して聴くのが、ふさわしい唄なのかもしれない。 |
|
|
|
|
|
|
|
シモン・ゴールドベルクメモリアル こしのくに音楽祭 メモリアルコンサート in富山
2006年10月1日 富山県民会館
ヴァイオリン ヴェスナ・スタンコヴィッチ
チェロ サンドラ・ベリッチ
ピアノ 寺嶋 陸也 |
|
こしのくに音楽祭の第2回目のホールコンサート。
この日は、ジュリアード音楽院でゴールドベルクに師事したヴェスナ・スタンコヴィッチのヴァイオリン、アンドレ・ナヴァラに師事したという、スタンコヴィッチと同じ旧ユーゴスラヴィア出身のサンドラ・ベリッチのチェロのリサイタル。ピアノはゴールドベルク夫人山根美代子の予定が急病で、寺嶋陸也に変更。
プログラムはハイドン「ピアノ三重奏曲第45番」、J・Sバッハの「無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番」
、コダーイ「ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲」、ブラームス「ヴァイオリンソナタ第3番」
非常に多彩な、充実したプロ。
ピアノが残念ながら山根さんから変更となったが、寺嶋陸也さん、堅実な演奏を聴かせてくれた。
ハイドンは演奏されるのが珍しい作品だが、古典的な典雅さと優美さを備えた佳品だ。ここでは、スタンコヴィッチのヴァイオリンが全体をリードしている様で、ピアノ、チェロとも、控えめで室内楽的な調和を整えているよう。
スタンコヴィッチのヴァイオリンは実に誠実な演奏。
キッチンの演奏の時にも感じたが、やはりゴールドベルクの音楽性が、弟子達に忠実に受け継がれているよう。
J・Sバッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番で、その印象は更に強くなった。
もっとケレン味のある、あるいは大伽藍のような演奏もバッハにはあるが、ここではむしろ作品の中身をしみじみと解きほぐし、あるいは音のつながりの意味を確かめていくようなスタイルの演奏。
休憩後のコダーイ。チェロもヴァイオリンも実にやさしい。この作品の野性的な荒々しさの側面よりも、唄のような独特な旋律を浮き出させた演奏。ハンガリーの鄙びた民謡があちらこちらから響いてくる。
最後のブラームス。がっちりとしたブラームスらしい構成感を基本としながら、優しいロマン的な響きが聴こえる。ブラームスのソナタにマッチした演奏。ゴールドベルクが立山国際ホテルの一室で最後に響かせた曲とのことだが、師ゴールドベルクのこの作品に対する姿勢をうかがわせる演奏。
アンコールの2曲目に、この音楽祭でスタンコヴィッチとサンドラ・ベリッチのセミナーを受けた生徒達を加えて、ヨハン・シュトラウスのワルツが演奏されたが、これが実に楽しい。いわゆる、シュランメルのスタイルで、のひのびと楽しそうな合奏が展開された。富山のセミナーで、技術的な側面のみでなく、このような音楽の生き生きとした面の教えを受けた生徒達がいたということは、実に嬉しいことである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ウェスト・サイド・ストーリー ブロードウェイミュージカル 2006年9月10日 オーバードホール |
|
考えてみたら、ミュージカルを見るのは、記憶にある限りでは初めて。「サウンドオブミュージック」など、映画化されたものは、勿論見たことはあるが。興味が無かったこともあるが、それ以上に機会が無かったのもある。
しかし、このウェスト・サイド・ストーリーは別。青春の頃、繰り返しLPを聴き、「マリア」「トゥナイト」、「アメリカ」など、そのナンバーに心躍らせたことを覚えている。
今回、初めて貴重な生の舞台を富山で見る機会が出来るので、楽しみにしていた。
「ブロードウェイ・ミュージカル」と謳っているが、このバージョンが最近ブロードウェイで上演されたものであるのかどうか、そのあたりがプログラムを見てもわからない。恐らく、日本公演のためにスタッフが集められたものと考えた方がよさそうだ。
演出、振り付け、歌手、踊り手、舞台美術、指揮者、オーケストラ、総て充実した緊迫感溢れる舞台が展開されていた。
指揮はドナルド・ウィング・チャンという、「ウエスト・サイド・ストーリー」を2000回以上も指揮したというベテラン。オケは日本人を中心とした、管楽器中心の25名程度の小編成だが、その馬力はたいしたもの。出だしから、鋭い響きが充満する。バーンスタインの音楽独特の跳ねるような高揚感とリズムをよく描く出している。
舞台は、左右に無機質のパイプが乱立し、奥のスクリーンにニューヨークの下町の風景が映し出される。左右のパイプの乱立が、ビルの片隅、広場、小路、高速道路等、その場面に応じて想像させる効果を持っている。単純だが、照明の効果とあいまって、音楽の想像性を高める。
さすがに、ダンスの迫力が凄い。ミュージカルの内容が、チンピラの対立を基本としているので、激しい闘争の場面が多くなるのだが、鬱積した若者の不安の爆発を、音楽と共に激しく表現し、心に迫るものがある。
トニーとマリアの主役二人、踊りと歌唱という大変な役柄だが、共に声量、表情、踊りとも申し分ない。聞かせどころの「トゥナイト」も、やや早めのテンポ設定ではあつたが、愛の二重唱を高らかに歌い上げていた。
アメリカの中の移民の立場を、皮肉たっぷりに、そして激しく歌い踊る「アメリカ」。群舞と合唱が激しく高揚する。
トニーが撃たれ、マリアが「貴方達がトニーを殺した。私は初めて貴方達総てを殺したいほど憎いと思う。」という、幕切れ。バーンスタインがミュージカルのハッピーエンドを排除し、シリアスな現実をつきつけた、このミュージカルの本質が鮮やかに描き出された。このあたり、バーンスタインはやはり、オペラの流れの先でのミュージカルというものを意識して作っていたことが明らかにわかる。
この作品では、「オペラ」と「ミュージカル」という区分はあまり意味が無く、バーンスタインが「現代のオペラ」としてこの作品を位置づけたかったのだろうと、理解できる。
力のこもった舞台であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
シモン・ゴールドベルクメモリアル こしのくに音楽祭 町中コンサート
2006年9月10日 富山県立近代美術館
ヴァイオリン ニコラス・キッチン
ボロメーオ弦楽四重奏団 |
|
昨日の開幕コンサートに続いて、町中コンサートと題して、「現代ロシアの美術」展が開催されている近代美術館の企画展示室で小コンサートが開かれた。美術館の入場料以外は無料という有り難い企画で、相当数の聴衆(300名程はいただろうか)が集まっていた。
この日はなんといっても、グァルネリ、アマティー、ストラディバリウスという3つのヴァイオリン名器の競演が聴きもの。こんな機会も本当に珍しく、生涯に一度の機会かもしれない。
最初にキッチンのヴァイオリンでバッハのシャコンヌが演奏されたが、3つの部分に分け、アマティー、ストラディバリウス、グァルネリの順序で演奏された。アマティーの艶やかな音色、ストラディバリウスの高貴な音色、グァルネリの豊潤な音色と、楽器によりこんなに個性が異なるものとびっくり、名演奏家が楽器にこだわる理由が感覚として理解できる。
次にベートーヴェンの16番の弦楽四重奏曲の第3楽章の一部を、ビオラをヴァイオリンに変えて、3つのヴァイオリンで各パートを交代して3通り弾くという試み。つまり、各パートを3通りの楽器で弾くという試み。ここでは、各楽器のソロ楽器としての響きの特長と、その特長の重なり合った時の響きの素晴らしさを堪能。全く至福の瞬間であった。
最後に、ボロメーオ弦楽四重奏団でショスタコーヴィッチの弦楽四重奏曲第8番が演奏された。
司会者の作品紹介の通り、反ナチと反戦、平和への祈りをこめたこの作品が、現代のロシアの反戦をテーマとした大きな絵の前で演奏され、一層感動深く聴くことが出来た。
全体が緊張感に満ちた作品だが、1楽章の初めの祈りにも似たテーマ、第2楽章の暴力的な激しさ、第4楽章の特徴的な主題での終結部など、作品の内面を深くえぐりとった名演であった。
ヴァイオリンも勿論だが、ビオラ、チェロがショスタコーヴイチ独特の激しい情感を的確に表現していた。前半のヴァイオリン3名器の競演と後半のショスタコーヴィチの演奏の現代へのメッセージと、内容の濃いコンサートだった。座席が無く、立ったままの1時間余りのコンサートだが、そんなことを忘れ、終わって初めて心地よい足の疲れを感じた。 |
|
|
|
|
|
|
|
シモン・ゴールドベルクメモリアル こしのくに音楽祭 里帰りコンサート
2006年9月9日 富山市民プラサ゜アンサンブルホール
ヴァイオリン ニコラス・キッチン
ピアノ 山根 美代子 |
|
晩年を立山山麓で過ごしたシモン・ゴールドベルクの足跡を偲び、新しい音楽のメッセージを富山の地から発していこうという趣旨で、「こしのくに音楽祭」が開催された。富山では非常に珍しく、企業メセナ事業で、地元の多くの企業と個人の寄付により音楽祭が運営されている。
このような音楽祭は、別府アルゲリッチ音楽祭、倉敷音楽祭、宮崎国際音楽祭、草津音楽祭等等、各地で開かれているが、富山ではこのようなことは今まで無かったと思われる。官製の押しつけの文化でなく、自らの手で文化の発信を行っていこうとする試み、関係者は大変なご苦労であったと想像するが、この芽を大切に育てていただきたいと思うし、輪を更に広げて県民的な運動に盛り上がれば富山の文化事情も随分と変化してくるのでないかと思う。
さて、シモン・ゴールドベルクは晩年の僅かな時間を富山の立山山麓の立山国際ホテルで過ごし、そこで亡くなり、最後のコンサートを市民プラザで行ったということは記憶しており、そのコンサートのチケットが手に入らず残念に思った記憶もある。それが、15年前の1991年だったそうだ。亡くなったのは1993年。奥様のピアニスト山根美代子さんは、現在も富山に住んでいらっしゃる。
今回の音楽祭では、ゴールトベルク山根さんが音楽監督となり、ゴールドベルクにゆかりの音楽家を中心に、メモリアルコンサート、町中コンサート、セミナー、文化塾。学校を回るコミュニティーキャラバンなど多くの行事が計画された。
本日のコンサートは、その前夜祭(立山山麓、立山博物館遙望館で開催)に続く最初のコンサートである。
今日のヴァイオリニストはカーティス音楽院でゴールトベルクに師事したというニコラス・キッチン。
プログラムはベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第5番ヘ長調Op24「春」、ドビュッシー:「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ、ヒンデミット:無伴奏ヴァイオリンソナタOp31-1、ブラームス:ヴァイオリンソナタ第3番ニ短調Op24。総てゴールドベルクゆかりの作品。
この日の注目は、ゴールドベルクが晩年使用していた名器「グァルネリ・デル・ジュス・バロン・ヴィッタ」が富山へ里帰りし、キッチンによって演奏されること。この名器はゴールドベルクの死後、アメリカのスミソニアン博物館に展示されていたとのことだが、今回の音楽祭にあたり、故郷富山へ里帰りとのこと。15年前、ゴールドベルクが響かせたと同じホールで15年ぶりにこの名器が響くこととなった。
コンサートが始まる前に、、この楽器のメンテナンスを担当した楽器製作者、マルコ・コッピアルディー氏と㈱日本弦楽器の社長が楽器についてプレ・レクチャー。1600年代から1700年代のイタリアクレモナ地方の楽器の特色について詳しく説明され、楽器に疎いものも興味深く聞くことができた。そして、グァルネリだけでなく、ストラディヴァリウスとアマティーも持ち込まれ、3大名器が紹介された。ニスの色の違い、アマティーの黄金の黄色、ストラディヴァリウスの深い飴色など、現物を目にして初めてわかることであり、。非常に稀な貴重な機会であった。翌日には、近代美術館の町中コンサートでこの3台の名器の音色の比較が行われるという、贅沢な企画もある。
そのグァルネリによるコンサート。ベートーヴェンのスプリングソナタによって開演。
このベートーヴェン、そして最後のブラームス、最近耳にすることの少ない、作品に誠実な演奏だった。形式感を重視し、細部まで神経が行き届き、なおかつ決して崩すことの無い、言ってみれば楷書型の演奏。ベートーヴェンの古典的な端正さ、ブラームスのほの暗いロマンティシズムがくっきりと浮かび上がってくる。演奏者の主観を押し付けるのでなく、楽譜の中から作品の本来の美しさと、雄弁さを語らせようとする演奏。これは、やはりゴールドベルクの音楽の本質的な特徴であるのだろう、それを弟子が忠実に再現している。ピアノ゜のゴールドベルク山根美代子さんも、かなりの高齢と見受けたが、堂々たるピアノであった。夫君シモン・ゴールドベルクの演奏スタイルを知り尽くした演奏と思える。グァルネリの響きは豊潤、驚くほど豊かな響き。響きがデッドなこのホールでも一杯に響き渡っていた。キツチンも師の名器を手にして大変な熱演。
ドヴュッシーとヒンデミットもゴールドベルクが同時代の音楽家として暫し取り上げていた作曲家とのこと。ドヴュッシーでも、印象派的な側面よりも、形式感をきっちりと表出しようとした演奏と思えた。ヒンデミットは無伴奏の大変な技巧を要する作品と思えたが、各部分の特長がきっちりと表現されていた。
プログラムが終了すると、二人が舞台袖のゴールドベルクの写真に深々と礼をしていたのが印象的。
アンコールにクライラー。作品名が不明だが、クライスラーのイメージの感傷的な小品でなく、古典的ながっちりとした作品。ここでは、キッチンは弓が切れるほどグァルネリを思い切り鳴らしていたので、圧倒的な音量となっていた。そうえば、プログラムの説明によるとクライスラーが使用していたグァルネリは今日のグァルネリと同じ木で作られた、姉妹楽器とのこと。クライスラーの作品は、繊細に又華麗に演奏されることが多いが、実際はこのような豊潤な楽器での演奏をイメージしていたとすると、印象も変ってくる。
当日のプログラム、1000円の有料販売だが、「ゴールドベルク略伝」を初め、楽器のこと、楽曲のことなど豊富な内容で貴重な資料となる。作成者の熱意を感じた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第206回定期演奏会 2006年9月7日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 外山雄三
ドラム ディヴィッド ジョーンズ
ヴァイオリン エリック シューマン
ピアノ 木村 かおり |
|
OEKの新シーズン幕開けのコンサート。
OEKの会員となり、4年経つが、新シーズンの開幕はわくわくするものがある。8月は音楽会の夏休みの時期で、久しぶりのコンサートということもある。
今回はマイスターシリーズで開幕。18日のフィルハーモニーシリーズは、ナチュラリスト活動と重なってしまい、昼間のコンサートでもあり参加出来ないのが残念。
さて、今日のコンサートは世界初演が2つ(渡辺俊幸、新実徳英)という、オケにとっても大変なプログラム。指揮は初演魔、故岩城マエストロの予定だったが、残念なことに死去。代演に外山雄三。岩城マエストロの影をまだ色濃く残した演奏会となったが、この代演は的を得た人選。外山雄三の明確で堅固な演奏が、初演作品2つという過酷なプログラムを、興味深く聴かせてくれた。
この日は、各新作の演奏の前に、指揮の外山雄三と各々の作曲者の作品にまつわる対談があり、面白く聴かせてくれた。作曲者によっては、このようなことを嫌う人もいるだろうが、聴く方にとっては、作品に対する作曲者の思いの一端を知ることは、作品の理解に大いに役立つことで、このような試みは続けて欲しいと思う。
最初は渡辺俊幸の「Essay for Drums and Orchestra」(ドラム:デヴィット ジョーンズ)
当初、「ドラム・コンチェルト」とされていたが、当日のプログラムの正式名称は上記の通り。
渡辺俊幸という名前は、NHKの大河ドラマ「利家と松」の音楽で馴染み。ファンタジーシリーズでは、指揮者としてしばしば登場しているようだが、私は初めて。元フォークグループ「赤い鳥」のドラマーという異色の作曲家であるが、アレンジャーとしてはさだまさしのアレンジャーとして著名とのことで、なるほど手馴れた感じの作品である。基本的には、かなりジャス゛っぽい雰囲気が濃いが、面白いのは、なにか土俗的な、言ってみれば、田舎の盆踊りのような雰囲気も感じさせるところ。楽器の並べ方も、作曲者の指定であるのだろうが、通常のオケの並べ方とは全く異なる。弦楽器群を左に、管楽器群を右に置き、中央に独奏ドラム、その奥にパーカッション群という配置。
ドラムのデヴィット ジョーンズ、登場の仕方がユニーク。何という楽器なのかわからないが、日本の「おりん」のような楽器を掲げ、それを撫でるようにしながら(ウォーンというような響きがする)、舞台袖から登場。演奏前の作曲者の言葉によると、「信仰の深い方なので」、このような登場の仕方をするということ、「ここから既に音楽が始まっていると思ってください。」とのことだった。それにしても、このドラマー、巧みである。ドラムセット以外に、鈴やら、小物のパーカッション類、更には私の位置からは確認できなかったが、ビブラフォーンのような音のするものも前に置き、それらを2本の腕と手、足で駆使する。時にはバチを置き、手先で打楽器を駆使する。視覚的にも非常に見ごたえのあるもの。終わり近くには、ドラムソロ(クラシックでいえばカディンツァだろうが、ここではアドリブのようなもの)がかなり長時間続き、迫力がある。
OEKも懸命な演奏だったが、弦楽器群など、もうひとつ、ノリが欲しかった。このあたりの作品になると、やはり「ノリ」が命、のようなところがあると思うが、クラシックのオケには一番難しい部分でもあろう。金管、打楽器はその点、非常によくスイングしていたように感じた。
次はプロコフィエフ「ヴァイオリン協奏曲第2番」。ヴァイオリン独奏はドイツの若手「エリック・シューマン」
平明な旋律の美しさと、プロコフィエフらしい諧謔に富んだ魅力ある作品。
エリツク・シューマンは実に真面目なソリストと感じた。誠実に正面から作品に取り組んでいるのだが、故にやや平板となってしまう。プロコフィエフとアンコールのバッハと、全く性格の異なる作品が、同じような色彩で弾かれてしまうと、各作品のもつ面白さが消去されてしまう。良い意味での「ハッタリ」も、プロの独奏者には必要なものと思うが。
オケの伴奏は良く鳴っており、細部まで呼吸が行き届いた演奏で、外山雄三の堅実さと作品への読みの深さが光っていた。
ここまてで、既に8時を過ぎており、今日も長い演奏会となりそうな予感。
後半は、今年のコンポーザー・イン・レジデンス、新実徳英の「協奏的交響曲 エラン・ヴィタール」 ピアノ独奏が岩城マエストロの奥様、木村かおり。
「協奏的」とは、ピアノとの協奏をさすのだろうが、各楽器群もかなり独立した扱いを受けているようで、「オーケストラのための協奏曲」的な色彩か。「エラン・ヴィタール」とは「生命の奔流」というような意味とのこと。
音と音のぶつかり合いに、作曲者の人間の生に対するドラマティックな思いを感じさせる作品となっている。終結部は作曲者が述べたとおり、静かな祈りで終わるが、これはやはりレクイエムであろうか。マエストロ岩城への熱いメッセージを感じさせる音楽であった。
ところで、コンポーザー・イン・レジデンスも新実氏で数えてみると18人目。この間の作品の再演も何度かあったようだが、是非再演を、又再々演をしてほしい。作品が聴衆に根付くには、そして評価が固まるには、やはり繰り返しが必要ではなかろうか。一度だけの演奏では、もったいない。出来れば、特集のような形で実現できればとも思うが。
最後はメンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」。実に溌剌とした、刺激的なメンデルスゾーン。第一楽章展開部のたたみかける部分など、心を沸き立たせるような刺激。第二楽章のしっとりとした情感、4楽章の颯爽としたスピード感。気持ちの良いメンデルスゾーンであった。
70歳を過ぎても、益々若い外山雄三の情熱を感じた。
拍手に応えて、「もう時計は9時半を回っています。このように長いコンサートとなったのは、このプログラムを計画した岩城の責任です。」と聴衆にユーモアたっぷりに語った外山雄三はアンコールに岩城宏之だったらきっと好きな曲だろうと、プッチーニの「菊」という珍しい作品をアンコールとして演奏。しっとりとした情感溢れる演奏。旧友への思いの籠った演奏。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第205回定期演奏会 2006年7月20日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮とピアノ 天沼 裕子
ピアノ 児玉 麻里 児玉 桃 |
|
今回の定期は「モーツァルト」がテーマだが、一風変ったプログラミング。
「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」に始まり、シュニトケ「モーツ・アルト・アラ・ハイドン」、「2台のピアノのための協奏曲」、シルヴェストロフ「ザ・メッセンジャー」、「3台のピアノのための協奏曲」、というプロ。モーツァルトを主題にした、変奏曲のような構成のプロである。
更に、2台のピアノはよく演奏されるが、3台のピアノは演奏会では珍しいのではないだろうか。そんな意味で、とても興味の募るプロである。
最初の「アイネ・クライネ」、出だしこそやや硬さが見られたが、一楽章の提示部の繰り返しあたりから俄然オケものりだし、非常に小気味の良い演奏が聴かれた。天沼は、ごく手堅い造りで、真面目な音楽。適当にアクセントもつけながら、オケ全体のバランスをきちんと整え、細部まで神経が行き届いた演奏であった。オケはアンサンブルが見事。各奏者の自発性がはっきりとしながら、全体の調和がとれたバランスの良い演奏。
次のシュニトケ。機智に富んだ、シュニトケらしい響きの充満する作品。モーツァルトの旋律の断片が飛び交う中、現代の混沌が浮き出てくる。楽器配置も独特。コントラバスを中心に、チェロ、ビオラ、第2ヴァイオリン、第1ヴァイオリンと左右対称扇型に弦楽器が並ぶ。扇の先の左右に、ソロバイオリン。真っ暗になった舞台に静かに指揮者と奏者が現れ、静かに始まる。左右の楽器群は、ある時は対立的に、ある時は調和的に響く。曲の頂点になると、舞台の明かりが照らされる。そして、いっせいに奏者が中央に集まり音楽は高まる。その後、再び奏者は扇型に広がり、舞台は再び暗転し、奏者が一人一人立ち去る。最後はコントラバスと指揮者のみが、舞台に残る。指揮者はいない奏者を前に、懸命にタクトをふり、静かに音楽は終わる。ハイドンの「告別」交響曲を想起させるが、「アラ・ハイドン」というのは、ここから名づけられたのだろうか。
この作品も、後のシルヴェストロフの「ザ・メッセンジャーズ」も、クレメルによって紹介された作品のようだ゛が、一昨年の定期のベルトといえ、クレメルの現代音楽への傾倒-特に旧ソ連の現代作曲家-は興味あるものがある。
今日は舞台の転換が忙しいが、係りの方たちが5人ほどで見事に舞台転換していく様子は見ていて楽しい。(やっている方は大変であろうが。) よく混乱しないで短時間で的確に配置していけるものである。
次が今日のメーン、児玉麻里・桃 姉妹による「2台のビアノのための協奏曲」
ここでは、第一ピアノが児玉桃、第2ピアノが児玉麻里、「3台のビアノのための協奏曲」では逆となっていたが、見ているといずれも姉の麻里が大きな身振りでリードしているようで、面白かった。麻里が大柄でくっきりとしたビアノであるのに対し、桃はもう少ししっとりとしたピアノであるような感じ。非常に躍動感があり、モーツァルトの飛び跳ねるような音楽をピッタリと息の合った演奏で聞かせてくれた。オケの伴奏もピアノとのバランスがよく、突出することなく、しかしピアノの息遣いを微妙にサポートした好演。天沼のしつかりとした音楽作りの賜物であろう。管楽器、特にオーボエの響きが美しい。
休憩後はシルヴェストロフの「ザ・メッセンジャーズ」で始まる。シルヴェストロフはウクライナの作曲家とのこと。シュニトケとは異なり、激しさでなく、叙情性を感じさせる作品。風の響き(シンセサイザー?)で始まり、モーツァルトの歌が静かに聞こえてくる。ピアノの静かな響き。全体はあくまでも静謐である。同じモーツァルトをテーマに取り上げながら、二人の作曲家がこんなに異なる作品を作り上げているのが面白い。それだけ、モーツァルトの音楽に多面性があるということか?音楽は再び風の響きの中に消えていく。
最後は豪華に「3台のピアノのための協奏曲」。ここでは指揮者の天沼裕子が第3ピアノと指揮ということで、大忙しである。ゴージャスな響き。モーツァルトの華麗さがきらめいている。ここでも、オケのアンサンブルは見事。響きのバランスが実に良い。
長いプロであったが、アンコールに児玉姉妹で野平一郎の「森の中のこだま」
静かな雰囲気で始まるが、中間部から俄然もりあがり、ショパン風なビルトゥオーゾ的なピアノがダイナミックに繰り広げられる。「森の中のこだま」というより、嵐のような激しさを感じる。面白い作品である。
「定期」ならではの、凝ったプログラム。「定期」はオケにとっても、聴衆にとってもある意味「挑戦」の場でもあるので、このような方向は今後も継続してほしい。 |
|
|
|
|
|
|
|
岩城宏之 追悼演奏会 2006年7月16日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ジャン・ピエール・バレーズ 外山 雄三 天沼 裕子 池辺 晋一郎
独奏 ジェフリー・ペイン(トランペット) ルドヴィート・カンタ(チェロ) 鳥木 弥生(メゾ・ソプラノ)
鶴見 彩(ピアノ)
オーケストラ・アンサンブル金沢、オーケストラ・アンサンブル金沢合唱団 |
|
岩城マエストロが亡くなって、早1ヶ月が過ぎていった。石川県と金沢市が主催で、追悼式と演奏会が石川県立音楽堂で行われた。幸いに、参加することが出来た。会員対象だが、殆どの会員が参加希望だったとのことで、苦肉の策として抽選となったようである。マエストロが本当に多くの人から愛されていた音楽家であったことの現れであろう。
音楽堂正面には献花台が設けられ、白、黄、青のカーネーションが捧げら、2階ホワイエには、在りし日の指揮ぶりの写真、各界の方々の弔辞が掲げられていた。
補助席まで満席の中、第一部の追悼式。石川県知事、金沢市長の追悼の言葉が続く。石川県で、金沢市でのマエストロの音楽への熱い情熱が浮き彫りにされ、改めて失ったことの大きさを痛感。その後、オーケイトラ・アンサンブル金沢永久名誉音楽監督の称号の贈呈、金沢市の功労者名簿への掲載の表彰があり、奥様の木村かおりさん、娘さんへ授与、奥様の感謝の言葉と続いた。オルガンの前には大きなマエストロの微笑みかけている遺影、その両脇にも指揮ぶりの遺影が飾られていた。
第2部の追悼演奏会は池辺晋一郎氏の司会で進行。
ここでは、単に哀悼の悲しみのみでなく、マエストロの多彩な音楽活動が、様々な側面から明らかにされ、非常に充実した内容となっていた。
1つは、何といってもオーケストラ・アンサンブル金沢の創設と県立音楽堂の建設。外山雄三氏が語っていたが、「とてつもないことを、公言し、そして実現してしまう男」
地方都市でオーケストラを創設し、そのオケを世界的にし、地方都市から音楽文化を発信しようという構想など、その当時は暴挙に等しい、夢みたいな話であったろう。それを、18年かけて、マエストロの言葉を借りれば、「急速なスピード」で実現させてしまった男。更には、そのオケを活動させるためのホールまで作らせてしまった。ロマンの実現を、ここまで見事に具現することは、現代のおとぎ話の様な感さえする。そのお陰で、私達聴衆は、素晴らしいホールとオーケストラに身近に接する恩恵を授与されることとなった。オーケストラ活動はとてつもなく金のかかる仕事、県や市のみでなく、マエストロが民間に応援団を個人的に持ち、そこからの莫大な援助があつて今日のOEKの活動があることが、関係者の証言によって明らかにされた。大阪フィルの朝比奈隆の場合も同様の話があるが、カリスマ的な影響力を持つ人の出来る業である。次期の音楽監督の選定に当たっては、このマエストロの意志を継ぎ、更に発展させる力をあらゆる面で持った指導者の実現が、マエストロの意志に応えることとなるのではないだろうか。
1部の最後にベートーヴェンの7番の4楽章が指揮者無しで演奏された。すさましい演奏であった。まるで、岩城マエストロが誰もいない指揮台の上からタクトを振っているのでないかと錯覚するような。
2つ目は日本の現代作曲家の紹介。初演魔といわれているくらい多くの、自分でも数えていないと言うほどの作品の紹介。コンポーザー・イン・レジデンスという日本のオケでは初めての試み。「ベートーヴェンだって、生きていた頃は現代音楽だった。」というマエストロの言葉。発表する場、聴く事が出来る場、が無ければ、知ることも評価することもできない。場の提供と言う、言うはやさしいが、行なうは大変なこのことをマエストロは長年かけてやりとおして来た。
今日も、武満徹、外山雄三、池辺晋一郎という3曲が演奏されたが、いずれも名演。日本の現代作品をこんなに巧く演奏するオケはアンサンブル金沢が一番ではないだろうか。
武満徹の「波の盆」と言う作品。TVのバックミュージックということだが、こんなにメロディックな作品を武満が作っていたのかと思うようなロマンティックな佳品。マエストロの好きだった作品といことであったが、好みの一端を知った気がした。
3つ目は、地方の新進演奏家の発掘。毎年、新人登竜門コンクールを行い、優秀者がOEKと共演するという試み。今日もそこから巣立った二人の演奏家が出演。特に、モーツァルトの20番の協奏曲の2楽章を演奏した鶴見さんの、しっとりとした情感に満ちた演奏が印象的。オケと対話をしながら、実に自然に音楽が流れていた。ここにも、マエストロの影を見た気がした。
本日の指揮の天沼裕子氏もマエストロが見つけた才能。
4つ目は、金沢に世界的な奏者を多く招聘したこと。OEKとの共演でも多く聴く事が出来たが、ソリストのみでなく実力派の奏者をOEKに招き、オケとしての実力の向上を図ってきた。この日は、ジェフリー・ペイン、ルドヴィート・カンタが、それぞれ独奏者として登場。ペインのトランペットはマエストロが「世界で一番巧いトランペット」と評していたということだが、ハイドンのトランペット協奏曲の2楽章を、これもしみじみと演奏してくれた。カンタはカザルスの「鳥の歌」。追悼にふさわしい深々とした音色、アンサンブル金沢の絶妙な弦の弱音。「カタロニアの鳥は、ピース、ピースと鳴くのです」というカザルスの言葉が満ち満ちている演奏てあった。
最後に合唱団の取り組み。マエストロは東京混声合唱団の育成に多大な情熱を捧げてきたことはよく知られるところだが、金沢でもオーケストラ・アンサンブル金沢合唱団、エンジェルコーラスを創設、オーケストラと共演を重ねてきた。私が会員にななった3年間でも、毎年2月には合唱団との共演の定期演奏会が開かれバッハのマニフィカートやモーツァルトの戴冠ミサ曲、そして忘れられないペーター・シュライヤーの「マタイ受難曲」など、滅多にオーケストラの定期演奏会で聴く事が出来ない作品を紹介してくれてきた。オーケストラが合唱団を持っているというのは非常に珍しい例ではなかろうか。この演奏会の最後に得意のモーツァルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」とマエストロが大好きだったと言う中田喜直の「夏の思い出」が出演者全員と会場の聴衆と共に歌われ、演奏会は締めくくられた。
池辺晋一郎氏の司会も、感情を表に出さず、冷静に、そしてマエストロの様々な側面をインタビューアーとしても関係する人々から聞き出し、マエストロの多面にわたる功績を浮きだしにしていた。
単に哀悼の意味のコンサートでなく、今後のオーケストラ・アンサンブル金沢がどうしたらマエストロの意志を受け継ぎ、更なる発展をとけられるか、そのあたりを考えさせられる、よく考えられた構成となっていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第204回定期演奏会 2006年6月29日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 広上 淳一
ヴァイオリン 内藤 淳子 |
|
マエストロ岩城が亡くなって初めての定期。音楽堂の入り口正面には遺影と花が飾られ、多くの方が足を止め、黙礼をしていた。ぽっかりと穴が空いた様な空虚感を感じる定期である。
最初に山腰音楽堂館長より、マエストロの逝去の報告があり、一同黙祷。その後本日の指揮者広上淳一氏のマエストロ岩城への追悼の言葉。その中で、「このオーケストラ・アンサンブル金沢は世界水準に達している。この短期間にここまでオケの水準を上げてきたマエストロの功績は言葉に尽くせないほど。」と語っていたのが印象的。本当に凄いスピードで進み、それはまるで自らの死を予測し、急いでいたような気もする。あらゆる意味で大切な指導者を失ってしまったと痛切に思う。山腰館長が「マエストロの意志を受け継ぎ、今後もアンサンブル金沢は前進していくので、変わらないご支援を」と呼びかけていた。
追悼の音楽としてグリーグの「2つの悲しい旋律」から「過ぎ去った春」が広上淳一によって演奏された。マエストロが好きだったと言うこの曲、アンサンブル金沢の弦は痛切に響いていた。
気を取り直すかのような暫しの休止の後、本日のプログラムの開始。広上淳一は「マエストロ岩城の死を意識していたら、滅茶苦茶になってしまうので、この一週間その事は考えないようにして練習をしてきた。」と語っていたが、その通りであろう。今日の演奏は、いつにもまして団員の音楽に対する目つきの違いのような、凄さを感じた。
プログラムはオールモーツァルト。交響曲代32番ト長調k.318、ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調k.219「トルコ風」、後半が大曲゛グラン・パルティータ」変ホ長調k.361というもの。
最初の交響曲第32番、ごく短い作品でありなから゛、モーツァルトらしい響きの豪華な作品。広上はメリハリの効いた指揮ながら、非常にコクがあるある演奏。旋律線を豊かに歌わせながら、リズム感も明快。芳醇な香りをただよわせた名演。
ヴァイオリン協奏曲第5番では、地元石川県出身の新進、内藤淳子が熱演。岩城が提唱して始めた石川県新人登竜門コンサートで優秀賞に選ばれた新進。
技巧も確か、響きも美しく、大柄なスケールを感じさせる新進。ただ、まだおとなしい。今後、自らの主張がもっと明確に出てくれば、ソリストとしての期待も高まるであろう。
後半は生で聴く事が珍しい、「グラン・パルティータ」。12の管楽器とコントラバスという変った編成の大曲。管も、オーボエ2本、クラリネット2本、バセットホルン2本、ファゴット2本、ホルン4本という独特の編成。バセットホルンも珍しいが、フルートが使われていないのも珍しい。全曲は7楽章からなるセレナード。楽器が少ないことで、演奏者の質が問われる難曲と思われる。
ここでは、アンサンブル金沢の管楽器群の素晴らしさを改めて感じさせてくれた。個々の奏者の自発性の高さ、そしてアンサンブルとしてのまとまり、隙の無い、それでいて充実感に満ちた演奏。これは、偏に広上淳一の凄さ。指揮者の明確な意志があるのだが、それを見事に解釈し音として出す奏者。見ていてこれほど痛快に感じた演奏も稀。優れた指揮者と、優れた奏者が、これでもかと演奏するのであるから、こんなに楽しい愉悦に満ちた音楽は無い。モーツァルトの弾けるような旋律、アダーージョの浪々とした歌、どこをとっても、今音楽が生れたというような新鮮さを感じた。広上は楽章毎に指揮台から下り、じっと集中を高めている。時には、次の楽章の空振りも試している。この集中力に、音楽に対する広上の対し方の真剣さを感じる。
50分近い大曲であるが、長さを感じない、音楽の愉悦の極地を聴いた感がした。 |
|
|
|
|
|
|
|
マエストロ 岩城宏之逝去 2006年6月13日午前0時20分
2006年6月14日 |
|
いつかは、この日が訪れるのではないかと怖れていた日が、ついにやってきた。
昨年夏手術、9月オーケストラ・アンサンブル・金沢の定期が欠演となり心配したが11月に復帰、、12月には東京でその前年に引き続き、ベートーヴエンの全交響曲を1日で゜演奏すると言う暴挙を病身を押して実行した。今年に入り、検査のため再入院という報に不安が募ったが、4月定期に再びカンバック、車椅子での指揮が結局最後の指揮姿となってしまった。
考えてみると、私にとっての岩城マエストロは青春からのシンボル的な音楽家であり、最も親近感を感じてきた音楽家であった。その最晩年となるこの4年間、オーケストラ・アンサンブル・金沢定期会員としてその指揮ぶりをつぶさに聴く事が出来たのは自分の音楽体験の歴史の中で幸せなことであったのかもしれない。
19歳の青春の年にその当時30代前半であったエネルギー溢れる演奏ぶりをN響の指揮で聴いた。確か東京オリンピックの記念演奏会であったが、レオノーレ序曲第3番の途中で子供の声が入り、演奏を中断したことを鮮明に覚えている。その後、ヨーロッパやオーストラリアなどでの活躍が多く、日本で接することが暫く出来なかったが、コンサートホールソサェティーという、その当時クラシックファンに馴染みのレコード頒布会で、日本人で初めて録音され、購入したリストのハンガリー狂詩曲集で、「火山の爆発」とも形容される演奏に、心ときめかした。そのレコードは今も手元に残っている。
合唱指揮でも東京混声合唱団とともに金沢に来演した時の演奏会が印象的だった。何と曲目の中に、荒木栄の「沖縄を返せ」が入っていたのである。「沖縄返還運動」が盛んだった頃なのだろうが、音楽家として社会に発言していく姿勢を鮮明に表明したこととして印象深い。
今日の朝日新聞の追悼の記事の中で、4月の東京混声合唱団の50周年記念演奏会でプログラムに軍歌「戦友」を10分間にわたり演奏、「誤った時代が日本にあったことを、忘れてはいけないということを訴えたかった」と述べていたことを知り、姿勢が一貫して変らない信念のマエストロの姿を印象づけられた。
日本の現代音楽を身近に聴かせてくれたのもマエストロ岩城だった。「金沢の聴衆は、私が変な曲をプログラムにいれるので、そんな作品を聴くことに慣れているんです。」とユーモアを交えて語っていたが、現代音楽がスリリングで、古典音楽と異なる面白さがあるということを示してくれた。コンポーザー・イン・レジデンス(座付き作曲家)という、日本のオーケストラで初めての試みを続け、作曲家と聴衆に、創ることと聴くことの場所を提供してくれた。この4年間でも、どれだけの面白い作品を聴かせてくれたことか。こんな指揮者はもう、現れないだろう。
アンサンブル金沢も、いずれはと予測はしていたことだろうが、支えを失ったショックは大きいだろう。聴衆とても同じである。来期はアンサンブル金沢での、ベートーヴェンへの再挑戦が予定されていた。又、県立音楽堂の創立5周年記念のショスタコーヴィッチのオラトリオ「森の歌」の演奏、9月にはN響での久しぶりの定期演奏会への登場の予定、又第2の故郷オーストラリアへのオーケストラ・アンサンブル・金沢との演奏旅行等など、まだまだ意欲満々であった途上での逝去。残念で仕方ない。
今は、天上で、先に逝った黛敏郎、石井真木、武満徹等とまた喧々諤々とやっているのだろうか。ご冥福を祈りたい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
クリスチャン・ツィメルマン ピアノリサイタル 2006年6月6日 オーバードホール |
|
前半がモーツァルト、「ピアノソナタ10番K330」、ベートーヴェン、「ピアノソナタ第8番<悲愴>」、後半がラベル、「高雅で感傷的なワルツ」、ガーシュイン「3つのプレリュード」、グラジナ・バツェヴィッチ「ピアノソナタ2番」というプログラム。個性的なプロと言えるだろう。
個性的なプログラムと同様に、非常に個性的な、独特のアプローチをもつピアニスト。
最初のモーツアルトからして、大胆なテンポの動かし方、テンポルバート、休止の間のぺタルを多用した独特の間、等、驚くような仕掛けが随所に聴ける。音色もどちらかというと、くすんだ、うつうつとした感じである。しかし、全体の構成はがっちりとしていて、個々の恣意的な色づけが全体の構成を崩すことなく調和している。これは、言い方は悪いが、相当計算しつくされた、したたかな演奏といえるだろう。
ベートーヴェンになると、尚その傾向は強くなる。この作品の革新的な響きを極度に増幅した感じ。であるから、初期の後半、中期にさしかかろうとしているこの作品が、もう既に中期の傑作群と同様の革新性を持っていることを知らしめてくれた演奏だった。かなり、ディフオルメされた感もあるが、ベートーヴェンの凄さを、ツィメルマンが具現してくれた演奏ともいえる。
1楽章出だしの序奏の和音の激しさ、その後に続く主部の疾走、独特のテーマの歌わせ方。時にテンポを落とし、止りそうになったり、とてつもなく長い休止をおいたり、かなりやりたいことをやっている。しかし、全体の構成はがっちりとしており、破綻した感じが無い。やはり、したたかな演奏である。3楽章の終結部も、これで全編の終わりというように、念をおすようなエンディング。劇的な作り方である。
後半は販売プログラムと当日の演奏順が異なっていた。先日のベルク四重奏団の場合もあったが、今日もやはり事前にプログラムと演奏順が異なることを事前にアナウンスすべき。特にこの日は、ラベルとガーシュインが切れ目無く演奏されたので、とまどった聴衆も多かったと思える。当日のプログラムとして掲示はあったが、事前の聴衆に対するアナウンスはあってしかるべきである。きめの細かい主催者側の配慮がほしい。
ラベルは、キラキラとした輝きでなく、くすんだ落ち着きのある音色、そしてなによりもここでも独特の歌わせ方が印象的。ラベルが後期ロマン派の作曲家であることを思い起こさせてくれた。
切れ目無く演奏されたガーシュイン。ジャズ、ブルースの世界であるが、ここでもツィメルマンは作品の個性を際だたせるような演奏を聴かせてくれた。
最後はポーランドの現代作曲家、グラジナ・バツェヴィッチ「ピアノソナタ2番」。勿論初めて聴く作品。全体的には現代作品としては聴きやすい感じ。形式も明確な3楽章形式をとり、ポーランドの香りを撒き散らしている。各楽章の性格の対比が鮮やかで、特に3楽章は技巧の限りをつくしたような盛り上がりがあり、ツィメルマンがプロの最後においた意図がわかる。
アンコールに、ショパンのピアノソナタ3番の3楽章「ラルゴ」。得意なショパンが無かったプロだけに、ショパンのアンコールは有り難い。これも、感傷に傾かない、思索的な沈潜するようなショパン。全く甘くない。音は暖かくふくよかである。
この日は1000名程度の聴衆か。オーバードホールような多目的ホールでは、やはり器が大きすぎる。ツィメルマンの音は、さすがに音響を大切にするピアニストらしく、この大きなホールにまけない響きを出していたが、ホールの器が大きいと集中度もそこなわれる。コンサート専門の中ホールが富山にも欲しいと痛切に思う。
それにしても、3年前のキーシンの時は超満員であったが、この違いは何なのであろうか? |
|
|
|
|
|
|
|
チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団 2006年6月4日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ディヴィツト・ジンマン
チェロ ヨーヨー・マ |
|
今月は期待のコンサートが2つ。今日のチューリッヒ・トーンハレと、明日の富山でのツィメルマンのピアノリサイタル。月末には広上淳一がOEKに登場する楽しみもある。
さて、数年に一回出会うかというような、素晴らしいコンサートであった。
スイスのオーケストラを聴くのは初めてだが、各奏者の技量の高さ、オケとしての品位のある風格、さすがに伝統の長さを(140年近いということである。)実感させてくれるオケ。
そこに、ジンマンという、実にきめの細かい名匠を得て、稀にしか聴けないような名演を繰り広げてくれた。
今日の石川県立音楽堂コンサートホールは、ヨーヨー・マの人気もあるのか超満員。2階のオルガンの前のバルコニーにまで、補助席を出す盛況。
ヨーヨー・マのチェロを生で聴くのは初めて。数年前岩城宏之・OEKと富山県民会館ホールでシューマンを演奏したが、高い価格(確か一番安い席で2万円程だった)に嫌気がさし聴く機会を逃した。今日聞いてみて、たとえどんなことがあっても聴くチャンスを逃すべきでないチェリストと実感した。
今日もシューマンのコンチェルト。出だしのテーマをチェロが弾き始めるとともに。その音色にぞっとする。柔らかい、そして艶やかでふくよか。チェロという楽器のイメージは、素朴・剛毅・豪快というものがあるが、ヨーヨー・マのチェロは全く異なる。肩の力が抜けた、飄々とした、天空を爽やかに泳いでいくようなチェロである。総てのパートをごまかすことなく明瞭に響かせる。そして、総てのフレーズが実に意味あるものとして聴こえてくる。だから、少々難渋とも思えるこの作品が、わかりやすく心に入ってくる。
ジンマンの伴奏も、そのヨーヨー・マを邪魔することなく、しかしやはり明晰に響かせる。個々の独奏楽器とチェロのかけあいなど、このオケの各奏者の音楽性の豊かさを如実に聴かせてくれる。後半のマーラーで強く再確認したが、このシューマンでのオケの伴奏のごまかしのない細部まで磨きがかけられた音楽こそジンマンの音楽の大きな特色である。
第2楽章のチェロの深々とした、豊かな低音の歌、こんな音は聴いた経験が無い。そして、第3楽章の溌剌とした情感。終結部のカディンツア風のパッセージでの、見栄を切るような盛り上げ方。堂々としながら、音楽の愉悦を聴かせてくれたチェロだった。
アンコールに無伴奏でシルクロードを思わせるような一品を聴かせてくれた。トルコの現代作曲家の無伴奏チェロソナタからとのこと。シルクロードにこだわるヨーヨー・マらしいアンコール。
これも、「天馬、空を行く」ような演奏
後半は、マーラーの交響曲第一番「巨人」
マーラーとなると、さすがに大オーケストラ、舞台から溢れそうでさえある。配置は古典的な両翼配置だが、コントラバスは右側後に配置。
総てのパート、テクスチュアを響かせた、精緻な工芸品のような演奏。
妙な言い方たが、ここまで冷静に客観的に分析して演奏すると、そこに「客観的」でも、冷たくもない、凄い熱い音楽が浮かび上がってくるということを、初体験した演奏であった。
音楽の力というのは、その作曲家の意図をどのように再現するか、聴衆に追体験させるかということであるのだから、客観的、冷静に演奏することがある一面重要なことであるだろうが、そこだけにとどまった場合、何か燃えないもどかしさを今までは感じできた。しかし、今日の演奏のように完璧に演奏された時に初めて、作曲者マーラーがこんなに凄い音楽を作っていたのだということを知らしめてくれるのだということを、強く体験した演奏であった。
1楽章の出だしのチェロの響きに、様々な楽器がからみ、夜明けの森のように高揚していくさま、ここではトランペットを舞台裏から響かせるという演出により、実に立体的な音楽構造を体験させてくれた。細かいテクスチュアから、徐々に音楽が作り上げられ、大きなテーマに向かっていくことが、良く理解できる鮮やかさ。そして、個々のフレーズの独特の強調による、あざといでも感じてしまうようなマーラー音楽の面白さ。将に万華鏡である。
2楽章の荒々しい低音のスケッルツォと中間部の優しい歌わせ方の対比、3楽章の木管のコケットな強調、時に聴こえるジンタ風の野卑な旋律、ウィーンの世紀末を明瞭に感じさせてくれる。
4楽章は将に爆発。高揚し、収束していくなかで最後の大興奮に音楽は突入する。この楽章でも、実にジンマンは冷静。高揚から沈静、沈静から高揚への流れが必然的で自然。このように音楽が流れていくと言う期待を裏切らない。だから、聴くものは安心してその流れに身を委ねる。コーダは白熱、マーラーの指示通り、ホルン奏者を起立させ、終結に堂々と進む。最後まで、しっかりとオケの手綱を締め、堂々たるエンディンク。最後まで鮮やかで、乱れないオケ。
全曲を通じて、チューリッヒ・トーンハレ管の実力にも脱帽。弦のしなやかさ、管の透明感と輝かしさ。、ドイツでもフランスでもイタリアでもない、将にこのオケ独特のトーンは伝統の力か。
聴衆も熱狂、爆発的な拍手が続いた。アンコールは残念ながら無し。
オケが退場を始めたが、聴衆の拍手は続く、照明を明るくしてしまったので、残念ながら終了。
拍手が続いている間は、せめて照明はそのままにしておいてほしかった。オケが退場しても、指揮者を呼び出したい聴衆も多かっただろうから。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
アルバンベルク四重奏団演奏会 2006年5月22日 石川県立音楽堂コンサートホール |
|
アルバンベルク四重奏団を聴くのは4回目。前回の感想でも書いたが、聴く度に新鮮な喜びを感じさせてくれる、将に至高の四重奏団である。
今までは、入善のコスモホールという、400名程度の小ホール。今回は1400名を越す大ホール。響きの点でもニュアンスが異なり、興味深かった。
今回は、モーツァルトイャーを意識して、モーツァルトが2曲、そしてバルトークという、地味なプロ。
全国公演を見ても、プログラミングはモーツァルトとバルトークと共通している。モーツアルトは、14、15、18、19(以上ハイドンセット)、20、23番、バルトークが2、4、6番を取り上げている。
金沢は日本ツァー最初の公演地で、モーツァルトの15番、20番、バルトークの6番が組まれた。
販売プロク゜ラムでは演奏順がバルトークを真ん中に挟み、前後がモーツアルトとなつていたが、当日変更で前半がモーツアルト15番ニ短調K421、20番ニ長調K499、後半がバルトーク6番と変更となっていた。当日の配布プロでは変更が明記されていたが、販売プロを見ていた私は2番目がバルトークと思い込んでいたため、又後記するが、2曲目で大きなハップニングが発生したため、残念ながら第2曲目に集中できなかった。こんな場合、事前に館内放送で案内してほしいものである。
しかし、この変更は正解で、この演奏順が妥当であろう。恐らくベルク四重奏団も演奏順については迷ったのであろう。
さて、前半のモーツァルト。15番の出だしの短調の旋律の何と高貴で、典雅なこと。感傷におぼれることなく、淡々と演奏されながら、心に染入ってくる深さ。4人の奏者がそれぞれ主張を持ちながら、四重奏団としての一つの楽器にまとまり奏でるその様子は、室内楽の理想的な完成された姿を見る。前回の入善コスモでは、シューベルトが演奏され、特に「死と乙女」の壮絶なドラマに接したが、今回は響きとしてはむしろ柔らかい。これはホールの個性の相違か、あるいはモーツァルトとシューベルトという個性の相違か。古典的な品位を厳格に保ちながら、個々のテーマには深い思索をこめて演奏する、これは相当な練り上げられた楽団でないと出来ない演奏である。残念だったのは、聴衆の拍手。消え入るかのように終わる最終楽章、音楽が消え入らない内の性急な拍手。最近、このようなぶち壊しの例が多く見られる。聴くほうも、もっと音楽を聴くことを大切にしたいと思う。余談だが、富山入善コスモでの演奏会では今までこんなことは皆無。今回の3分の一位の聴衆であるが、その聴くことへの集中力は凄い。終了してからの内容のある暖かい拍手。であるから、演奏する側ももの凄い集中力で応えてくれる。
さて、問題の2曲目、モーツアルトの20番ニ長調K499。バルトークとばかり考えていたので、モーツアルトが鳴り始めた時はびっくりしたが、その後急に演奏が中止され、ピヒラーが最前列の客に対し、弓で出て行くようにと指示している様子。その客が移動すると、それでもピヒラーはホールから出て行くようにと指示している。その客がドアから、出ていくと、何も無かった様に演奏は初めから再開された。
後から聴いたところでは、なんとカメラマンが最前列でカメラを向けていたとのこと。恐らく、主催のH新聞の記者であろうとのことだった。今まで見たことも無いようなハップニング。こんな記者がいるような新聞社は、どんな教育を記者にしているのか、信じられない光景であった。録音、撮影は厳禁ということは、常識であり、主催者側が最も気を使うべきことである。それがこともあろうに、主催者側のカメラマンであったとしたら、全く想定外の珍事である。たとえ、許可された撮影でも、遠くから望遠レンズでも使って撮影するのが礼儀であろう。
以前、富山でも主催者側の新聞社が、翌日の記事で演奏された曲順を間違って紹介した事例を見たことがあったが、どうも地方新聞はお粗末過ぎる。もう少し、記者教育を徹底して欲しいものである。
そんなことがあって、2曲目は実に音楽に集中できなかつた。聴衆にとって、そしてなによりも演奏者にとって気の毒な事件てあった。それでも、なんとか集中して演奏しようとしたベルク四重奏団は立派であったが、残念である。
休憩を挟んで後半。気を取り直して音楽と向かう。
バルトークの6番、バルトーク最後の四重奏曲。全曲に痛切な哀歌が鳴り響く。
ここでのベルク四重奏団は、音楽を無機的に響かせるのでなく、複雑で難解なこの曲を、実に暖かく、人間の叫びとして表現していた。これにより、難解とも思われる作品が、実に解りやすく端的に心に響いてくる。これが、音楽の解釈と言うことなのであろうが、このいわば抽象化、単純化は容易なことではないだろう。楽譜にこめられたバルトークの思いを、4人が丁寧に解き明かし、表現していく。個々の技術のレベルを超えた、四重奏団としての表現の凄さを感じるのである。各楽章が、別れ、望郷、怒り、絶望、そして希望に彩られていることが痛切に感じられた表現であった。
アンコールが2曲。バルトークとハイドンの四重奏曲のそれぞれ中間楽章。
特にハイドンのラルゴの静謐な響きと、深い沈潜。ハイドンにこんな深淵があったのかと思わせる深い響き。
ハップニングもあり、素晴らしい演奏会てあったと同時に、色々考えさせられた演奏会。室内楽には、やはり1500名近いホールは大きすぎるのでは無いかとも思わせられた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第202回定期演奏会
2006年5月17日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ドミトリー・キタエンコ
ビアノ 小川典子
トランペット ジェフリー・ペーン |
|
キタエンコのプリンシパル・ゲストコンダクター(主席客演指揮者)への就任後初の定期公演。キタエンコはベテランのロシア指揮者と聴いており、楽しみにしていた演奏会。
しかし、来年の定期には登場の機会が無いようで、主席客演というからには、もう少し登場の機会を多くして欲しいものである。
プログラムはユニークで、前半がベートーヴェン交響曲第8番、後半が今年生誕100年のショスタコーヴイッチのピアノ協奏曲第一番とバレー組曲第3番。スケールの大きなというより、小粒でピリッとした感じの、巧者キタエンコというプログラムである。
オケは対向配置。古典的なスタイルだろう。
前半のベートーヴェン、リズム感が明確で、彫の深い、それでいてしっとりとした弦の響きなどを聴かせる、引き締まった演奏ではあった。しかし、やはりベートーヴェンには粗野な面と、ワイルドな面、そしてなによりものめり込むような激しさが欲しく、試合巧者だけでは表現しきれないもどかしさと、難しさも感じた。オケも1楽章と4楽章に指揮者の要求とのズレが感じられ、ややとまどいがあったようだ。第2、第3楽章はキタエンコの要求するしっとりした、デリケートな響きの呼吸とピタリ合った演奏を聴かせてくれたが。
昨日のマイスターシリーズのモーツァルトは聴かなかったが、この方がキタエンコには合っていたのではなかろうか。
後半のショスタコービッチは、将にキタエンコ独壇場の演奏。
ピアノ協奏曲の小川典子、激しさ、乾いた叙情、アイロニー、ブルースのような悲哀など、この曲に込められたショスタコーヴィッチの思いのたけを存分に表現し聴かせてくれた。この人の、粗野とでもいえるようなピアニズムがショスタコーヴィッチにピタリとはまっている。トランペットのジェフリー・ペーンも見事。2楽章のミュートを使用した、場末の悲哀のような歌の響かせ方、この作品など当時のソヴィエトでは到底評価されなかったであろうとうことを、如実に解らせてくれた。OEKの伴奏も、弦楽器を中心としたしっとりとした分厚い響きにはっとさせられ、キタエンコの棒の巧みさが強く感じられた。この弦楽合奏の美しさは特筆。
最後の「バレー組曲第3番」。勿論始めて耳にする作品。ショスタコーヴィッチのある一面の、馬鹿騒ぎが乱舞するような作品である。バレー音楽「明るい小川」が、痛烈な批判にあったという史実を知っていたが、その作品を耳にするのは始めて。なるほど、当時のソヴィエトで「軽佻浮薄」と批判されたのが理解できる。このような作品を理解する度量の豊かさは、当時の官僚にはさても有り得なかったのであろう。それにしても、当時このような作品を作曲したショスタコーヴィッチの抵抗精神に、驚きと、芸術家としての信念を改めて感じた。
キタエンコはこの作曲家独特の鋭さと、管弦楽の巧みさを自在にあやつりながら、馬鹿騒ぎの背後のアイロニーのようなものも巧みにあぶりだしていた。ここでも、トランペットのジェフリー・ペーンの巧みさが際立っていた。ハープ、ピアノ、チェレスタ、木琴、ビブラフォーン、トロンボーン、チューバなどショスタコーヴィッチらしい際立った管弦楽法を、OEKはキタエンコの棒の下、見事に演奏しきっていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第200回定期演奏会
2006年4月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城 宏之
Sop.サイ・イェングアン
Ten.佐野 成宏 |
|
節目となる200回定期。17年間で200回、岩城監督に言わせると、世界のオケの中でも驚異的なスピードで成長してきたとのこと。そのマエストロ、今回は車椅子での指揮となった。4月初め、内臓疾患で検査入院との報があり心配されたが、今回の定期には並々ならない執念を感じる。
200回定期を楽しくとの狙いか、ポピュラーな作品のコンサートであったが、音楽の内容はずっしりと重い、存在感が溢れた演奏となっていた。
プログラムは前半が、ソプラノ-サイ・イェングアン、テノール-佐野成宏をゲストに、ベルディー「椿姫」のコンサート形式でのセレクション(ハイライトというには、曲目が少なすぎた)、後半がR・コルサコフの交響組曲「シェヘラザード」
「椿姫」、静かな第一幕への前奏曲では、出だしの弦の緊張感が印象的。ただ、やや弦の音が硬い。ふくよかな柔らかさが欲しかった。
サイ・イェングアンは以前富山での「魔笛」の夜の女王のアリアの見事な歌いっぷりが印象に残っているが、今日のヴィオレッタも見事。可憐でありながら、芯の太い女性を見事に演じきっていた。コロラトゥーラでありながら、ドラマティックな歌唱で、「ああ、そはかの人か、花から花へ」では可憐さと奔放さを巧みに演じ分ける。澄み切った高音の輝かしさ、それでいて骨太な声量に魅了される。。
テノールの佐野成宏のアルフレードも凄い。日本人離れした、張りのある輝かしいテナーである。
有名な「乾杯の歌」は、合唱が無いのがやはり寂しいが、二人の歌唱はそれを忘れさせるほどであった。
疑問は最後、二重唱「パリを離れて」で終わるのだが、やはりヴィオレッタの絶命まで聴かせて欲しかった。非常に中途半端なもどかしさを感じた。この日の最初の演奏順では、「乾杯の歌」を最後に持ってくるという改悪をしていたようだが、変更されたのは正解だが、やはりエンディングまで演奏すべきだったのではないか。アンコールに再度「乾杯の歌」
後半はR・コルサコフ「シェヘラザード」。ポピュラーな曲であるが、生で聴くのは初めての経験。やはり、演奏頻度は少ないのであろう。
編成も客演奏者を入れて、いつものOEKよりも大きい。ファゴット、トロンボーン、チューバ、パーカッション、ハープ、低音弦等が補強されているようだ。
岩城マエストロは、テンポを相当おとし、とうとうと流れるような雄大な音楽を創っていた。
この作品、ヴァイオリンの独奏を初めとして、管楽器等独奏が活躍する部分が多く、それだけオケにとっては聴かせどころが多い反面、粗も目立ちやすい、難しい作品と思われるが、この日のOEKは細部に若干の乱れはあったが、非常に充実した演奏を聴かせてくれた。
細部まで相当練り上げているようで、全体の印象は巨大なカンパス画を見るような印象が有り、オケ全体が一つの大きな波に向かって進んでいくようなノリとスケール感があった。最終楽章の「岩での難破」でのオケの咆哮のすさましさ。かつての岩城節を聴くようであった。しかし、あの頃は若さにゆだねた情熱、今はもっと底の深い充足感。どっしりとした重さを感じる演奏である。
ヴァイオリンのヤングさんの独奏は、これも美しかった。
力のこもった「シェヘラザード」を聴かせてもらった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第198回定期演奏会
2006年3月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城 宏之
チェロ 堤 剛 |
|
プログラムは次の通り
武満徹 「地平線のドーリア」
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104
ブラームス 交響曲第三番 ヘ長調 Op.90
武満徹 「地平線のドーリア」は武満の代表作であり、かつて幾度と無く耳にしたことがあるはずだが、生で聴くのは今回が初めて。音楽が始まると同時に、ああ武満の音ということが聴こえてくる。
あらためて集中して聴いてみると、なんと日本的な音楽であることか。竹林のざわめき、笙のような響き、色彩が鮮やかなのだが、それは淡色系である。緊迫した響きの中に、鮮やかな風景が繰り広げられる。これだけの限られた弦楽器群で、これだけ大きな世界が描けるとは、やはり武満の音楽の凄さを感じる。OEKの弦楽器群の緊迫した音色も見事。
堤剛は何年ぶりに聴くことになるのか。若い日の猛々しいチェロの音色を思い出すとともに、自らの経てきた年月も考えてしまう。この世代の演奏家を聞くたびの感慨でもある。
ドウォルザークの懐かしさ、歌心をこれほど見事に歌い上げた演奏も稀である。テンポをやや遅めにとりながら、浪々と歌い上げる。感傷過多と紙一重なのだが、ドヴォルザークはこうでなければ面白くないというほどの感情移入である。醒めたドヴォルザーク程、味気ないものは無いと改めて知らしめてくれた演奏でもある。岩城宏之の指揮も、堤に負けまいと、しっとりと、そしてある時は高らかに歌い上げる。堂々たる熱い演奏であった。
後半のブラームス3番。岩城-OEKのブラームスシリーズの最後となる演奏。このシリーズの特長である楽器編成と配置によるのは今回も同様。(ブラームスが自らの交響曲を演奏する際に、理想的としていた楽器配置とのこと) ヴァイオリンの人数を通常の半分にしぼり、配置もコントラバスを正面に据えた対向配置。この配置により、より重量感が増した音楽となっている。人数をしぼりながらも、音量はかなりのもの。そしてなによりも、てらいのない音楽の創り方が、堂々たるブラームス像を創造していた。テンポもインテンポで動かさない。淡々と進んでいるようでありながらブラームスの古典派的な側面をしっかりと打ち出している。なによりも、芯の太い音楽で、若い演奏家の軽々しいブラームスとは、一味も二味も異なる、心にしみいるブラームスである。
岩城マエストロが巨匠への道を確実に歩んでいることを、再認識させられた。
アンコールに軽やかにブラームスのワルツ。 |
|
|
|
|
|
|
|
大阪フィルハーモニー交響楽団第396回定期演奏会 2006年3月17日 ザ・シンホニーホール
指揮 小林研一郎 |
|
小林研一郎が大フィル定期で、スメタナ「わが祖国」の全曲を演奏するというので、所用のついでに、是非聴きたいということで足を運んだ。
大阪福島のザ・シンホニールで聴くのは初めての経験。変形のボックスシュー型の様なホールだが、1700名余りの収容人員なので、どの座席からも、ステージが近く、オーケストラを身近に感じられるような、雰囲気の良いホールである。反響も程よく、音がこもらず、良く抜けるような感じ。難は、初めてであったせいもあるが、座席にたどりつくまで入り口が非常にわかりづらかったこと。同じ階の席でも、センター席と左右のバルコニー席に段差があることが、その原因のようだ。要するに1階と1.5階、2階と2.5階、3階というような構造になっているようだ。
大フィルの定期は始めてだが、色々と面白いことを発見した。まず、オケのステージへの登場の仕方。最近は団員が揃って入ってくる、それにあわして聴衆が拍手をするというスタイルが多いが、大フィルは三々五々と入り、最後にコンサートマスターが入ってくるというスタイル。私も、40年ほど前にN響の会員だったので、このスタイルがあたりまえと思っていたので、最近のオケの入り方に違和感を感じていたので、なにかほっとしたような感じがした。そしてアンコール無し。
最後に小林研一郎が熱狂的な拍手を抑え、わざわざ、「大フィルの定期はアンコール無しということが伝統となっているのは皆さんご存知の通りとおもいますので、今宵の思い出を心に残してお帰りください」と、わざわざ挨拶したのがおかしかったが、定期ではやはりアンコール無が普通なのだろうか。ちなみにN響定期もアンコールは無い。アンサンブル金沢は必ずアンコールがあるが、他のオケの定期はどうなのだろうか?
さて、コバケンのスメタナ「わが祖国」は3年余り前、アンサンブル金沢の定期で大阪センチュリー交響楽団との合同演奏会で「ボヘミアの森と草原から」までが演奏されたのを聴いた。今日は、オケが大フィル。前回同様、全曲にわたり、指揮者の息遣いがきこえるような、入魂の演奏であった。演奏が始まる前に、指揮台から下り、オーケストラに「よろしくお願いします」とでもいうように、頭を下げる、独特のコバケンの姿勢が印象的。オケと、これから始まる音楽に対する敬虔な祈りのように感じる。
オケは16型の大きな編成。楽器の配置は、モダンの通常型。大フィルは、以前聴いたときは、やや荒削りな感じがあったが、今回はかなり円熟したとでもいえるようなトーンを感じた。
2台のハープで1曲目の「高い城」が全曲の開始を告げるが、コバケンはここでは合図のみを送り独奏に任せているようだ。全体はスケー.ルの大きな、うねりを感ずるような演奏。細部まで神経が行き届いているのだが、それが機能的な磨きでなく、一つ一つの音に感情が籠められているような凄さがある。単に「うまい」という種類の演奏ではない。作品の心を、指揮者が再創造しているかのような。音が美しい、細部まで見通しが良い演奏は、最近多々あるが、このような創造性に満ちた音楽は、最近は聴けなくなった。
「高い城」の神々しさ、「モルダウ」の雄大さ、「シャ-ルカ」、そして後半の「ターボル」から「プラニーク」にいたる激しさ、「ボヘミアの森と草原から」からの広大な広がり、それそ゜れの交響詩が、単に描写でなく、作曲者の「祖国」に対する熱い思いであるということを、再確認させてくれた演奏である。
最終章の「プラニーク」のエンディングでは、金管を中心とし、全オーケストラが高らかに賛歌を歌い上げるが、ここでもしっかりとした音楽の足取りがある。確固としたスメタナの祖国への熱烈な愛情を聞くかの如くであった。
曲が終わると同時にブラボーの連呼の、炎のコバケンらしい、燃え尽きた演奏であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
ロンドン交響楽団演奏会 2006年3月14日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 チョン・ミョンフン ピアノ 横山幸雄 |
|
プログラムは前半がショパン、ピアノ協奏曲第一番(独奏 横山幸雄)、後半がマーラー交響曲第五番。大きなプログラムである。
LSOを聴くのは3度目、最初は高校生の頃だから50年近く前になるか、ケルテスの指揮(東京文化会館)、2度目は1998年コーリン・ディービスの指揮(富山オーバードホール)だった。
いずれも印象深い演奏会。初回は開場直前にドアの隙間から聞こえるゲネプロのショスタコーヴィッチの5番のシンフォニーのフィナーレのラストの部分の音の分厚さに驚愕したのは、今でも鮮烈な記憶として残っている。2度目のディーヴィスのペーーヴェンの3番のシンフォニー、2楽章の揺れ動くようなテンポの微妙さに心動かされた。
今回も、このオーケストラの底力のようなものを感じた。チョンがプロク゜ラム冊子の中で書いているが、このオケは非常に適応性の高いオケで、指揮者次第で色々な色彩に染められるようなオケという気がする。その点では、日本のオケに似ているのだが、それでいてやはりどっしりとした気品というようなものを個性として持っているのはやはり歴史の証であろうか。
まず、前半は横山幸雄の際立ったピアニズムと、チョンの名ピアニストらしい作品の総てを把握している好サポートにより、稀にしか聞けないようなショパンとなっていた。出だしのオケがやや雑な感じがしたが、横山のピアノ独奏が入ってからガラっと雰囲気が変ってしまい、チョンの巧みな指揮にオケが段々のりまくつていく様は見事であった。横山のピアノは、ショパン独特のテンポルバートのようなところを、崩れる直前で止めるような、それが何ともいえないショパンの感傷を醸し出している。しかし、けっして崩れるようにのめり込まないので、気品が高く、下品な感傷とならない。ショパンの切実な青春性というものを、見事に描く出していて、心にしみこむ。決してたかぶらないのだが、精神の高揚は高らかである。チョンの指揮も、細部まで精密に描き出しながら、ピアノと対話をしていく。第二楽章のセンチメンタルに落ち込まない静謐さ、第三楽章の転がるようなピアノの音色など、聞かせどころたっぷりのショパンであった。
さて、後半のマーラー。ここではオケの底力が遺憾なく発揮された。オケの配置は、コントラバスを左側に、チェロを真ん中にした両翼配置で、古典的な配置。編成は大きく、コントラバスが8本だが、第一ヴァイオリンは数えてみたところでは16人なので、変則的な16型か。ホルンは7人という、音楽堂のステージがはちきれそうな編成。この大編成オケが、力一杯奏でるのであるから、その迫力たるや、大変なもの、コンサートホールが壊れんばかりであった。マーラーは、やはりこうであるべきという爆演であった。
チョンの指揮は、いつもの通りかなり深く抉り出すような演奏、テンポもやや遅め、たっぷり歌わせる。しかし、それでいて、泥臭さが無いのはこの指揮者の特長である。細部までおろそかにしないので、複雑なマーラーのオケのテクスチュアの精緻さが浮かび出る。これは、オケの力量の凄さもあろう。大きな音量でありながら、濁らない。第二楽章の高揚、第四楽章の静謐なアンサンブルでの高揚、第四楽章フィナーレでの崩れない堂々たるエンディンクなど、鮮やかとも形容できる熱演。
その反面、マーラー独特のどろどろとした情念のようものは感じられない演奏ではあった。
このあたりはマーラー演奏の難しさか。
大曲2曲のプロで終演が9時30分近くとなっていたが゛、長さを感じさせない迫力であった。
当然ながらアンコールは無し。これでアンコールをやらされたら、オーケストラは怒るだろう。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第195回定期演奏会
2006年2月23日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ロルフ・ベック
So.シモーナ・ホーダ・シャトローヴァ Ar.バーバラ・ロールフルス
Te..ハルトムート・シュレーダー Bs.マティアス・クライン
合唱 オーケストラ・アンサンブル金沢合唱団 合唱指揮 佐々木正利 |
|
今回は、ドイツ・シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン音楽祭監督のロルフ・ベックを客演に迎えてのコンサート。昨年、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン音楽祭のレジデンスオーケストラとしてアンサンブル金沢が招聘され出演したことに対する、返礼の趣旨のコンサートとのこと。
アンサンブル金沢は毎年2月定期には合唱団と共に、宗教曲を演奏することが、ここのところ通例となっているようで、昨年のマタイ受難曲、一昨年のバッハのカンタータ等、印象深い演奏会が思い出される。合唱団を有しているオーケストラは珍しいであろうから、この試みは続けて欲しいものである。中々、宗教曲を聴く機会が少ない北陸では尚更である。
さて、本日のコンサート、プログラムは前半がベートーヴェンの交響曲第4番、モーツアルトの演奏会用の、レチタティーボ「あわれ、ここはいずこ」とアリア「ああ、語るはわれならず」K.369、アリア「はげしい息切れとときめきのうちに」K.88、後半がミサ曲ハ長調「戴冠式」K317
楽器の配置が典型的な両翼配置の古典型。ティンパニーもバロックティンパニーを使用。これは明らかに指揮者ロルフ・ベツクの要求であろう。
演奏スタイルも典型的な古楽スタイル。余計な装飾を廃し、厳しく音素材を追及したような演奏。
ノンビブラートの弦、鋭い管楽器の響き、乾いた激しいティンパニの音色など、独特のベートーヴェンである。フォルテシモやピアニシモも、かなり極端に増幅、減衰をおこなう。
しかしこれが、ベートーヴェンでは逆効果をもたらしたようにも感じた。ベートーヴェンの時代は、なるほどこのような音色のオーケストラであったのだろうが、ベートーヴェンの音楽自体は、その時代を超越してしまった、ロマン的で、感情豊かで人間臭い音楽ではないかと考える。様々な解釈を許容し、その解釈により凄さが発見される、言ってみれば音楽にのめり込むような捉え方を要求される音楽とでも言えようか。アカディミックなスタイルに忠実のみでは、ベートーウ゜ェンの本質を見失ってしまうような気がする。そのような意味で、このスタイルの演奏は、面白さは感じるが、感動の質としては薄いものとなってしまう。とはいうものの、第一楽章、第四楽章の古典的な端正な躍動感など、アンサンブル金沢の美質を引き出した、誠実な演奏とはいえる。
モーツァルトの珍しい演奏会用のレチタティーボとアリア。2曲とも完成年代は異なるが、内容的には非常に似通った、オペラのアリアのような劇的な要素を持った作品。後の魔笛の夜の女王のアリアをも想起させるような、ドラマティックなコロラトゥーラを要求される作品。
ソプラノのシモーナ・ホーダ・シャトローヴァは透き通った流麗で、しかしドラマティックな歌唱で、この作品の本質を歌いきっていた。ヨーロッパのオペラ界の底の厚さを感じさせるソプラノである。
後半は「戴冠式のミサ曲」
ここでは、アンサンブル金沢合唱団の見事な合唱が特筆される。プレトークの際に、合唱指揮の佐々木氏が合唱団をステージに立たせ、丁寧にこの作品の構成について合唱団を歌わせながら解説をしてくれたが、その最初の「キリエ」の冒頭部分が歌われた時、ハーモニーがホールの余韻となって漂うさまにびっくりしたが、良く鍛えられた合唱団である。一昨年のバッハの夕べの際にも、ベックの指揮で合唱団が見事な歌唱を繰り広げたのを記憶しているが、合唱指揮者としてのベックの面目躍如とした演奏である。この作品の場合、古典的な端正なスタイルが見事に作品とマッチし、祝典的な華やかさと、モーツァルト独特の流麗な音楽の流れが心をときめかせた。ドイツからの独唱陣、オーケストラの精緻なアンサンブルともども、聴き応えのある30分であった。
アンコールに合唱曲「まことのお身体(アヴェ・ヴェルム・コルプス」)。静謐な締めくくりであった。
面白かったのはビオラがアンコール演奏で加わり、「戴冠式のミサ曲」ではビオラが無かったのを気づかされたこと。
ロルフ・べックのドイツ正統派の音楽を堪能した一夜。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第194回定期演奏会 2005年1月29日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金 聖響
ソプラノ 森 麻季 |
|
ニューイヤーコンサートには行かなかったので、今年最初のアンサンブル金沢の演奏会。
9月定期の感想の際、金聖響は今期の定期に予定は無いと記したが、間違い。フィルハーモニーシリーズにはないが、マイスターシリーズにありました。訂正です。
さて、そういうことで、楽しみな金聖響の登場。そして、ソプラノに今、旬の森麻季ということで、期待を大いに持たせてくれる定期。
今日の楽器配置も金独特の古典的対向配置。コントラバス、チェロの低音域が左側、第1バイオリンと第2バイオリンがビオラを挟む形で対向、金管のトランペットトロンホーンをを極端に右側に寄せた独特の配置。金はこの配置が定型化しているようである。ティンパニーも小型のバロックティンパニーを使用。このティンパニーが「田園」の4楽章嵐の部分で効果的に使われていた。
前半が森麻季で、モーツアルト「フィガロの結婚序曲」を皮切りに、ヘンデルの歌劇「セルセ」より、「オン・ブラ・マイフ」、バッハ/グノー「アヴェ・マリア」、そしてモーツアルトのモテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」k.165、後半がベートーヴェンの交響曲第6番「田園」、というプログラム。
最初のモーツアルト「フィガロの結婚序曲」が、キリット引き締まった、それでいて生き生きと躍動する秀演。特にコーダの部分の金管を中心に堂々と響かせる盛り上げ方が見事。金の指揮はいつも感じるが、とても彫が深く、そし総てのパートをきつちりと響かせる。あいまいさが無いのでとても気持ちよく響く。この序曲とアンコールのベートーヴェン「プロメテウスの創造物」序曲がその典型ともいえる名演であった。早いスピードで総てのパートをくっきりと鳴らしながら、疾走していく快感は、若い指揮者ならではの爽快感がある。オーケストラもよく鳴っていた。
森麻季は、さすがというべき歌唱。透明でありながら艶やかで、低音から高音まですべるように音が動いていく。今日本のソプラノの中では間違いなくトップクラスて゜あろう。容姿といえ、申し分ない名花である。この日は古典歌唱であったが、きつちりと崩すことなく格調高く歌い上げていた。金の伴奏も古典の枠をきつちりと守り、深い響きを聴かせてくれた。ヘンデルでのオーボエの見事なオブリカート、オルガンの落ち着いた響き、弦の静謐な響き等、アンサンブル金沢も深い響きで森麻季をサポートしていた。
さて後半のベートーヴェンの交響曲第6番「田園」。全体的には金の今までのベートーヴェン演奏のあり方を踏襲したと思える。丁寧に各パートを響かせ、細部まで磨きのかかった演奏である。只、この交響曲は他のベートーヴェンの作品と異なる難しさがある。第5楽章の「神に捧げる感謝の気持ち」に至るまで、自然な感情の高揚感を持続し、盛り上げていかなければ聴く者にとっては、気持ちは良いが、冗長感にとらわれることがある。この作品に求められるのは、作為ではなく、いかにして第5楽章の精神的高揚感に到達するかという、その難しさの解決ではなかろうか。金はやや早目のテンポで、緊張感を持続し、弛緩が無いように、前へ、前へと進めているようだが、それがややこの作品の本来持っている、自然な精神の高揚感を妨げているように感じてしまう。今後の金が、このあたりをどのように変化させていくか、非常に興味があるが、今日の演奏では残念ながらそのあたりの不満が残った。
しかしながら、前述したように第4楽章の盛り上げ方の見事さ、そしてその後の第5楽章のテーマのすがすがしい歌わせ方など、今の金聖響のベストであろうという演奏ではあった。
金聖響とアンサンブル金沢は以前にも書いたが、とても相性が良いようだ。今後継続した関係を持続し、又次の、その又次も聴いてみたいものである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ニューイヤーコンサート2006 ウィーンフォルクスオーパー交響楽団 2006年1月5日 オーバードホール |
|
2006年がいよいよ幕開け。暗い世相の2005年であったようだが、今年はどうか。今年は年頭から久しぶりの大雪。不安の年明けでもある。
さて、昨年の音楽会への訪問は29回、一昨年より若干増えたようだ。昨年の幕開けは及川浩治だったが、今年は華やかにワルツである。そういえば、及川浩治の時は雪は殆ど無く、歩いて市民プラザから帰ってきたことを考えると、今年はやはり異常である。
指揮がユリウス・ルーデルというオーストリア出身で主にアメリカで活動している指揮者。見たところかなりの高齢のようであったが。ソプラノとテノール、地元のバレーも加わって華やかな舞台。
ホール入り口には門松が飾られ、樽酒も振舞われ、舞台も花で彩られ、正月らしい華やぎを演出していた。
さすがに本場のワルツとポルカ、オペレッタという醍醐味があった。
最初の「くるまば草」序曲は、オケにやや硬さが感じられたが、徐々に調子が上がってくるよう。さすがにウィーンフィルの上質な気品とウィットは望めないが、むしろこれがウィーンとでもいえるような濃い雰囲気と、親しみやすさと懐かしさを感じさせてくれるオーケストラである。決して巧いというオケではないが、ワルツ・ポルカのアンサンブルのコツのようなものを知り尽くしている感じである。ルーデルの指揮はかなり表情が濃く、テンポもやや遅め、歌うところはゆったりと歌い、盛り上げるところはたっぷりと堂々と盛り上げていく、ツボを心得た指揮である。指揮ぶりは、お世辞にも優雅とは言えないが、生れてくる音楽はコクのある、雰囲気の豊かなものであった。
テノールはかなりの声量を持っているが、やや生硬。ウィーン少年合唱団出身とのことだが、もう少しリラックスしてのっていって欲しかった。ソプラノもソフトな良い声質だが、やはりノリが薄い。メラニー・ホリデーのような、声は衰えても、芸達者でお客をのせていくという、楽しさに欠けるのはこの種の音楽では物足りない。それとせっかく「春の声」があるのに、ソプラノが歌わないのはどうして? コロラトゥーラの妙技を聴きたかったのだが。
バレーは富山公演のみのサービスで、地元の松岡舞踊が踊っていたが、正直なところ余計と感じた。音楽に集中したいところを妨げられてしまう。バレー音楽を聴きにきているわけではないのだから。
アンコールはお決まりの「青きドナウ」と「ラデツキー行進曲」、それにテノールとソプラノでこうもりから乾杯の歌。「青きドナウ」と「ラデツキー行進曲」、どちらも堂にいった、さすが本場と感じさせる演奏。このあたりは、日本のオケは絶対にかなわないだろう。やはり、シュトラウス一家や、カールマン、レハールあたりの音楽は、ローカルな音楽。ウィーンの音楽家にまかしておけばよいのだろう。
しかし、正月に本場のウィーン音楽を楽しめたのは幸せであった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
庄司紗矢香 ヴァイオリンリサイタル 2005年12月1日 入善コスモホール |
|
今年聴く最後の音楽会となるであろうリサイタルで、将にハイライトとなるようなコンサートを聴いた。
庄司紗矢香とピアノのイタマール・ゴラン、圧倒的なデュオであった。
プログラムはシューマンのヴァイオリンソナタ第一番、ショスタコーヴィチのヴァイオリンソナタ、そしてR・シュトラウスのヴァイオリンソナタという、大曲3曲。
庄司紗矢香とゴランは、各作品の性格を見事に描き分け、「凄い」とでも形容して良いような音楽世界を描き出した。
馴染みの少ない作品を並べた、地味とでもいえるようなプログラミングであるが、各作品の面白さ、醍醐味を聴くものにしっかりと伝えていく、この二人の能力は大変なものである。
シューマンは、出だしの暗い低音から始まり、全体にうつうつとした、しかし歌に満ちた複雑な作品の面白さを、わかりやすく伝えてくれた。この「わかりやすさ」、が庄司の大きな特徴である。相当深く読み込み、自分のものとして表現しているから、聴くものにとっても主張がはっきりと聴こえてくる。シューマンの作品は時に迷路に入り込み、わけのわからない演奏となる場合があるが、庄司は各パートの意味をしっかり捉え表現しているので、聴く者にとって魅力ある作品となって聴こえる。
ショスタコーヴィチは、舞台の照明をやや落として集中力を高める。作品の性格として当然だが、集結の部分で照明を全く落としてしまうことといえ、演出とはいえ、この作品に対する庄司ののめりこみと表現意欲の強さを、見せつけてくれた。。ショスチコーヴイッチの一面の特長である、深い思索と激しいアイロニーの交錯、苦悩の深さ、総てが凝縮され、ヴァイオリンとピアノで表現される。機械的なメカニックなテクニックの凄さとは全く異なる、一つ一つの音、技巧に魂がこもっている演奏である。特に第2楽章の激しさは、単なるアイロニーでない、ショスタコーヴィチの、持っていきようのない慟哭を聴く様であった。第3楽章の深い沈潜と逆らうような高揚、そして最後は祈るような沈黙をもって終わる。ヴァイオリンの最後の音が消えても、庄司は弓をそのままの姿勢で微動だにしない、そして照明が消える。聴衆は最後の音が消えても暫く、まだ音が響いているような感慨にとらわれる。暫くして、怒涛のような拍手。聴衆も素晴らしい聴衆であった。演奏が終わって、震えるような感動を覚える経験はそんなにあるものではない。
もう、ここで終わっても良い、これ以上は弾くほうも大変だろうと思わせるような緊張と弛緩。
しかし、まだ後半のR・シュトラウスがあった。
R・シュトラウスは昨年樫本大進が、ここコスモホールで名演を聴かせてくれた。今日の庄司は又その時とは異なる感慨を与えてくれた。ドラマティツクで骨太なR・シュトラウス。雄大な演奏であった。R・シュトラウスらしい甘美で濃厚な歌が、ト゜ラマティックに展開していく。樫本が青春の歌であれば、庄司はもっと劇的な表現と感じた。
樫本の時もピアノはゴランであったが、このピアニスト大変なピアニストである。自らの主張は明確にもちながら、ヴァイオリン奏者の特色を最大限引き出そうと挑発していく。単なる伴奏者であっては、デュオは面白くならないということをはっきりと解らせてくれる伴奏者である。
アンコールにシューマン(3つのロマンスより)、バルトーク(ルーマニア民俗舞曲)、クライスラー(スラブ舞曲)。シューマンの素朴な歌は、何かドヴォルザークを思わせるほどの素朴な歌、バルトークの激しい民俗性、いずれも見事。最後のクライスラーはさすがに疲れを感じさせた。
庄司紗矢香を聞くのは今回2度目だが、スケールが益々大きくなっていく。テクニックが見せびらかすものでなく、その音楽にとって必然性を持つことが理解できるのは、庄司の成長の証である。
このホールでのコンサートも、相当聴いてきているが、聴衆の質の良さにいつも感動する。そんなに多くない聴衆であるが、演奏者と呼吸をあわせて音楽にのめりこむ、本当に音楽が好きな人達が集まってきていることを感じる。だから、演奏者も乗りまくって演奏する。このホールの長い歴史がそのような雰囲気を作り出しているのだろう。年々聴衆も少なくなり、演奏会の回数も徐々に減りつつあるようで、会館の運営も大変だろうが、この伝統と歴史を絶やさないように、素晴らしいコンサートの開催を続けていってほしいと思う。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
月田秀子 立山山麓チャペルコンサート 2005年11月28日 立山国際ホテル・スターライトスクエア |
|
みゃあらく座、村田さんの主催するコンサート。村田さんは、自らの目で、埋もれているが、輝いている人達を掘り出してきては、色々な機会をつくり紹介してくれる、貴重な方である。
今回も、殆ど知られていないファドというポルトガルの民衆の歌を日本でただ一人歌い続けている、月田秀子というアンダーグラウンドの歌手のコンサートを私達に聴かせてくれた。場所が立山極楽坂という悪条件にもかかわらず、200人近い聴衆が集まっていた。
初めて聴くファド、そして月田秀子だが、歌いはじめの一声から心をつかむ。原語で歌うことが多いため、歌詞が解らないのが残念だが、その暗く、しかし直情的な歌は聴くものの気持ちを瞬間に掴み取ってしまう。人生を、愛を、悲しみを、喜びを歌うと言う意味では、シャンソン、ブルースに近いものであろうが、もっと直情的、本能的である。なりふりかまわない、弱い人間の叫びが歌になっているという感覚。であるからして、このような歌の場合、巧拙よりも、その歌の中に込められた思いを、自分に重ねて表現しつくしたいという意欲が、聴くものの心を捉えるのだろうが、月田秀子は将にそれをやってくれた。音楽、歌が根源的に私達に訴えかける力を、月田秀子はファドというポルトガルの歌で示してくれた。このような本物の歌を聴くと、日本のフォークソングなどが、いかに底が浅く、稚拙なものかということを考えてしまう。
ギターと、珍しいポルトガルギターという楽器のデュオが伴奏であったが、これが又素晴らしい。ピアソラの音楽の原型を聴くようであった。見たことも無い、リスボンの裏町の情景が目に浮かぶよう。
村田さんも再演を恐らく考えているだろうが、出来れば次回は歌詞の概要程度をプリントして貰えると、聴くものにとっては有り難い。 |
|
|
|
|
|
|
|
バイエルン放送交響楽団演奏会 2005年11月26日 オーバードホール
指揮 マリス・ヤンソンス、
ヴァイオリン 五嶋みどり。 |
|
石川、富山へ来演の今年のオーケストラの中でも期待していた演奏会。指揮はマリス・ヤンソンス、ヴァイオリンが五嶋みどり。
ベートーヴェン「レオノーレ序曲第3番」、シベリウス「ヴァイオリン協奏曲」、ワーグナー「楽劇トリスタンとイゾルデより前奏曲と愛の死」、ストラヴィンスキー「火の鳥」、という才人ヤンソンスらしいプログラムであるが、シンフォニーが無いのが寂しい。どうも、富山だけシンフォニーが無かったようだが、残念である。
最初のベートーヴェンはもう一つ調子の出ない演奏であった。ヤンソンスの思いに、オーケストラが乗り切れず、特に木管など不調でもたもたしていた。意図は見えるがオケがついていかずという不完全燃焼であった。その日最初に演奏する曲とはやはり難しいものなのか。
シベリウスの五嶋みどり。出だしのかそけき音にびっくりする。本当に小さい音量、しかし内容はぎっしりとつまったという音色。かつての五嶋みどりはもっとバリバリと弾くという印象があったが。オケの音量が大きいので、時には埋没してしまいそうになる。ヤンソンスも相当緊張し抑えているようではあったが。しかし、この沈潜は何であろうか?深く深く沈んでいくような演奏。激しく高揚する場面でも、わめき散らすことなく、節度を持って高揚していく。弱音は将に消え入るようである。
シベリウスの北欧の暗い叙情はこんなものだったのだと感じさせてくれた。活発な3楽章も、浮かれることなく落ち着いた品位を保っていた。ヤンソンスはさすがにシベリウスの暗い情熱と叙情を、深く深く描き出していた。
後半のワーグナーとストラヴィンスキー。どちらも、作品の性格を明確に描き出した演奏。
「楽劇トリスタンとイゾルデより前奏曲と愛の死」は、暗い官能と愛の世界、高揚と恍惚の死を暗く激しく描き、ワーグナーの壮大な管弦楽世界が描き出されていた。オケの分厚い音の重なりは、ドイツの音を堪能させてくれた。昨年のドレスデン、ベルリンフィルのどちらとも違う個性のオケである。伝統と近代性がうまくマッチングしたオケという感想。
それにしても、指揮者のタクトが下ろされないのに、待ちきれないように拍手が起こるのは、折角の余韻を台無しにしてしまう。もう少し、音楽を大切にする聴衆であってほしい。特にこのような作品では、オケも指揮者も聴衆も、音が消えても残っている感情を大切にしたい時間があるのであるから。
最後はストラヴィンスキー「火の鳥」。情景が目の前に浮かんでくるような名演。「火の鳥の踊り」の弦楽器の飛び跳ねるようなパッセージ、「王女達のロンド」と「子守唄」の木管の叙情的な歌、終局の壮大な盛り上がり、ヤンソンスの面目躍如の演奏であった。細部まで研ぎ澄まされた、オケの緊張した響きは、やはり師のムラビンスキー譲りであるのだろうか。
アンコールにチャイコフスキーの「眠りの森の美女よりアダージョとフィナーレ」。これも凄い演奏
。チャイコフスキーのロシアの冷たい叙情とドラマティツクなエンディングを壮大に描き出していた。
やはりヤンソンス、只者でないという演奏会。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第191回定期演奏会 2005年11月24日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城宏之 |
|
円熟と濃厚。そんなことを感じさせてくれた演奏会。
プログラムは多彩。前半がメシアン「異国の鳥たち」、イブリー・ギトリスのヴァイオリンでパガニーニのヴァイオリン協奏曲第一番、後半が間宮芳生の新作「オーケストラのための2つのタブロー2005」(世界初演)、最後がビゼーの交響曲第一番、アンコールに更に間宮の新作「白峰かんこ」。
間宮の新作は9月の定期初演の予定であったが、の病気により2ヶ月初演が延ばされたもの。当初のプログラムにこの新作が加わったため相当長いプログラムとなった。
メシアンの「異国の鳥たち」。管楽器と打楽器のみによって演奏される。配置も独特で、木管を2群に分けての配置。メシアン独特のリズム感と多彩な管楽器のソロ、そしてピアノ独奏。岩城の指揮は打楽器群の独特なリズム感を強調した演奏。鋭く、クリアな演奏もあるが、むしろ分厚い響きの中にメシアン独特の打楽器のリズムとソロ楽器の名人芸が展開する。OEKはこの作品を得意としいるのか、ピアノの木村かおりを加え、手馴れた演奏と感じた。
楽譜に各鳥(47種とのこと)の名前が明記されているとのことであり、楽譜と対比して聴けば更に面白く聴けるのかもしれない。
次のバガニーニ、これは将に巨匠(あまり簡単に使いたくない言葉ではあるが)同士の音楽の愉悦という趣。ギトリスは舞台に出てくる風貌からして、「魔法使いのおじいさん」の様。あるいは、パガニーニに似ているのかも。ともかく、年輪を感じさせる風貌である。細かいところにこだわらない、将に大柄の風格のヴァイオリン。オケの提示部が終わると、「さあ今度は俺の番」とばかり、オケ伴奏にはこだわらず、浪々と自分のペースで歌いだす。岩城マエストロもその時はじっと合わしているがオーケストラの部分になると、また堂々と元のペースで歌いだす。協奏曲の面白さではある。
超絶技巧を要する作品であるが、ギトリスのヴァイオリンは技巧の中にも、何か枯れた趣を感じてしまう。若いヴァイオリニストの緊張感に満ちた鋭いヴァイオリンと異なり、何かほっとするようなノスタルジィーを感じるヴァイオリンでもある。アンコールに「浜辺の歌」。転調に転調を繰り返すユーモラスな演奏に会場から笑いが漏れる。魔法使いのおじいさんの「魔法のヴァイオリン」であった。
注目の間宮芳生の新作「オーケストラのための2つのタブロー2005」
音響の塊がぶつかりあうようなダイナミックな作品。底には間宮独特の土俗的な響きも聞こえる。アンコールの「白峰かんこ」で明らかだが、間宮は土俗的なもの、民俗的なものを一度分解させ、自らの手法で再構築させるという手法により、より深く日本人ということを感じさせる作曲家である。武満徹の繊細なジャパニズムと異なる、もっと土臭いジャパニズムを感じさせる作曲家。この作品については、何度か聞きなおしてみたい。LIVE録音をしていたようなので是非CDの発売を期待する。
最後はビゼーの「交響曲」。
アンサンブル金沢と岩城の円熟を感じさせる演奏。堂々とオケを鳴らし、歌うところは徹底的に歌うという、この作品の美点をいかんなく発揮していた。最近の岩城マエストロは、細かい演出や、小細工は労せず、作品を正面から見すえた演奏と感じる。テンポは動かさず、妙なアクセントはつけず、楽譜の指示を忠実に生かし演奏しているように思えるが、生れてくる音楽は揺るぎの無い堂々としたものとなっている。やはり円熟というべきであろうか。
この交響曲の古典派的な端正さと、ロマン派的な歌とが、気持ちよく溶け合い響き合った演奏であった。
アンコールに間宮の新作「白峰かんこ」。民謡をテーマとしながら、民謡にとらわれることなく、民衆の息吹とエネルギーをエキスとして仕上げたような作品。アンサンブル金沢の新しいアンコールピースとして定番となるのでなかろうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
チェコフィルハ-モニー管弦楽団演奏会 2005年11月14日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 シャルル・デュトワ |
|
シャルル・デュトワの名人芸を聴けた一夜。
チェコフィルはノイマンの指揮での富山と金沢の公演を続けて聴いたのが、1982年、23年程前になるから、それ以来である。
この日は、デュトワらしいプログラム。プロコフィエフの「ロミオとジュリエット」組曲とチャイコフスキーの交響曲第4番。
何ともゴージャスな音の饗宴であった。チェコフィルがこんなに華やかで艶やかな音を出すオーケストラとは、再認識。以前は、ややくすんだいかにも東欧という銀色の音色に、野暮ったいほどの懐かしさを感じたものだが、この日の演奏はその印象をひっくり返されてしまった。やはり、デュトワ、ただものでないと思わせた。弦のささやくような弱音、ホルンの柔らかい響きなど、随所にチェコフィルの美点を残しながら、全体は分厚く鋭いアンサンブル。
デュトワは、細部まで磨き上げ、オケの総てのパートがくっきりと鳴り響く。
その長所が最大限生かされたのがプロコフィエフ。初めの「モンタギュー家とキャピレット家」の出だしの弦楽器の弱音の分厚い響きにまずびっくり。これは将にチェコフィルの弦の凄さ。
デュトワはそのようなチェコフィルの美点を最大限に生かしながら、更に緊張と鋭さをつけ加えていく。全曲弛緩することなく、緊張した歌に溢れている。6曲目の「ロミオとジュリエット」のカンタービレの美しさ、次の「タイボルトの死」のドラマ。そして、終局の最後分厚い弱音が消えていく部分。計算しつくされた演奏ともいえよう。
後半のチャイコフスキーも同様の演奏。1楽章の出だしから、かなりテンポを遅くとりながら弛緩することが無い。各主題をくっきりと描き出し、さの主題が展開していくさまを丁寧に描き、次にどんな展開が待っているかを常に期待させる。主題が生成し展開し歌いまくるという様が明瞭に聴こえてくる。であるから、テンポの遅い部分、ピアニッシモの部分でも音楽が停滞することが無い。各パートを明確に響かせながら、全体のアンサンブルをきっちりとまとめていく。将に名工の彫刻のようである。
第2,3,4楽章は切れ目無しに演奏されたが、これも流れが断絶することなく継続しているということを明瞭にわからせる演出といえよう。
細部まで神経の行き届いた、深い彫りのある演奏であった。
ただ、完成しつくされた演奏でありながら、熱い感情を感じ得ないのは、この指揮者の特長であり、限界であるのだろうか?欠点のある演奏でも、人間の熱い情熱を感じさせる演奏があるのと正反対のことを感じてしまう。ここでも、又音楽の深さと表現の難しさを思うのは、私の聴き方がひねくれているせいだろうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
館野 泉ピアノリサイタル 2005年10月29日(土) 石川県立音楽堂コンサートホール |
|
脳溢血で演奏中に倒れ、その後後遺症で右半身が不随、ピアニストとしての道を絶たれた館野が、左手で演奏会に復帰という衝撃的なニュースを聴き、是非その演奏に触れたいと念願してきたが、今回運良く聴くことが出来た。
館野泉は私にとっても忘れられないピアニストの一人。34,5年以前に、大学時代にサークルの主催リサイタルに招聘し、その演奏会の成功に心を砕いたことを思い出す。その頃から既に当時は演奏されることが珍しいにフィンランド現代音楽の紹介を盛んに行い、その演奏会でもラウタバーラの作品を演奏されたことを記憶している。又、その時のプロコフィエフのソナタ7番の壮絶な演奏は生々しく印象に残っている。
その後10年前に、北日本新聞ホールで詩的でダイナミックな演奏に再会した。それが彼の元気な演奏を聴いた最後となった。
右足を引きずりながら舞台中央へ歩いてくる姿は、痛々しさを感じたが、左手で鍵盤にふれるや、健在であったときの感性が、より研ぎ澄まされて生み出されているのを感じることが出来た。
プログラムは、バッハ・プラームス編曲「シャコンヌ」、スクリャービン「左手のための2つの小品」、林光「花の図鑑・前奏曲集 ピアノ(左手)のために、館野泉に」、ノルドグレン「小泉八雲の『怪談』によるバラードⅡより゛振袖火事゛゛忠五郎の話゛(館野泉に捧げる)、吉松隆「タピオラ幼景(館野泉に捧げる)。
このプロに見られるように、館野が委嘱した左手のための作品が中心。
館野のような高度なテクニックを有するピアニストだからこそ可能であるのだろうが、左手のみでこれだけ多彩な音楽を繰り広げられることは驚きであると同時に、作曲家にとっても左手のみのピアノ作品という制約が逆に密度の濃い音楽を作り出している事を感じた。
林光の音1つ1つに深く込められたメッセージ、ノルトグレンのドラマティックなバラード、吉松隆の幻想的な世界、それらを集中して表現する館野の凄さ。
両手が使えないことのもどかしさが゛どれ程のものてあったか、その葛藤は想像を絶するが、それを乗り越えて明らかに別の新しい世界を館野は築き上げてきている。
館野は同情や哀れみ、好奇心、そのようなものを乗り越えて「左手のピアノ」という新世界を築き上げている。そして、その世界は、従来の館野のピアにズムを更に深く、研ぎ澄ました世界となっていることを強く感じた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
福田進一の挑戦 福田進一・松原勝也デュオリサイタル 2005年10月28日 富山市民プラザアンサンブルホール |
|
ギターの福田進一・ヴァイオリンの松原勝也による7「福田進一の挑戦」と名づけられたデュオリサイタル。
6月に松原勝也を中心とした室内楽を聴き、松原勝也の熱いヴァイオリンに魅了されたので、今回も大いに期待していた。
前半がバッハ、後半がドビュッシー、ラベル、バルトーク、ファリャ、ピアソラという多彩な、やはりギターの特色を良く生かそうというプログラミングと思えた。
福田進一のギターはさすが。音色の渋い暖かさ、技巧の確かさなどトップギタリストの面目躍如であった。
今回の松原勝也は、その野太いヴァイオリンの音色はそのままであったが、ギターとの共演ということで、前回の印象と異なり、ややおとなしい演奏となっていた。
前半のバッハ。1曲目は無伴奏チェロ組曲第6番から゛プレリュード゛゛ジーク゛のギター編曲版。
チェロ独奏曲の編曲であるが、むしろギター用の作品という印象。古典的な端正さに満ちた演奏。
2曲目は松原勝也の独奏で有名な無伴奏パルティータ第2番からの「シャコンヌ」。朗々と鳴り響く、骨格の太い演奏。
バッハの最後は「ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ」。通奏低音のチェンバロ伴奏の部分をギターが受け持つ演奏。チェンバロをギターに変えたことによる違和感が全く無く、ギターがーまるでチェンバロのように響くことにびっくりする。
後半はドビュッシー「亜麻色の髪の乙女」、ラヴェル「ハバネラ形式の小品」、バルトーク「ルーマニア民族舞曲」、ファリャ「スペイン民謡組曲」、ピアソラ「カフェ1930、ナイトクラブ1960」というプログラム。
ファリャとピアソラが、憂いと哀愁に満ちた好演。ピアソラがファリャと非常に雰囲気が接近した音楽ということを発見し面白かった。やはり、同じラテンの血なのであろうか。
バルトークはヴァイオリンが以外にスマート。もう少し泥臭さがあっても良いように感ずる。ギターの端正さに合わしたのであろうか?
クラシックギターが、古典からラテン、あるいはジプシーに至るまで、幅広い表現力を有する楽器であること、そして福田進一の表現力が各曲の個性をそれぞれ引き出していたことに、さすがと納得した。
アンコールは「アルハンブラの思い出」とパガニーニのカンタービレ。
有名なトレモロのアルハンブラ、見事な演奏であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第188回定期演奏会 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城宏之
共演 ザルツブルグフェスティバルオーケストラ |
|
岩城マエストロの病気後、復活第一回の定期演奏会。
8月に緊急入院、手術とのことで、病身であっただけに心配であったが、早く復帰されて何よりである。この日の演奏会は、そのような意味で、感慨深いものとなった。岩城さんも、「又、復帰したよ」とでもいいたげに、聴衆の熱い拍手にこぶしを振り上げてこたえていたのが印象的。
この日は「モーツァルトフェスティバルin金沢」の最終日でもあり、招聘の「ザルツブルグフェスティバルオーケストラ」との合同演奏会。各パートに数人づつの「ザルツブルグフェスティバルオーケストラ」団員が加わった。
モーツアルトの35番「ハフナー」、41番「ジュピター」の2つの交響曲を挟んで協奏交響曲k297bが演奏された。
「ザルツブルグフェスティバルオーケストラ」との合同ではあったが、それ程普段聴くアンサンブル金沢の音質との違和感は無く、ただやはり伝統なのか、弦楽器を初めとして落ち着きのある、品格のある音色が聴かれたような気がする。
この日の演奏は、最初に書いたとおり岩城マエストロの復帰定期演奏会でもあり、そのようなことを音楽を聴く上に持ち込むことは誤っているのかもしれないが、やはりマエストロの熱い思いが伝わってくるような主張の強い演奏であった。
35番「ハフナー」1楽章の飛び跳ねるような躍動感。4楽章のコーダのティンパニーの強奏、41番ジュピターにおけるトランペットのやや突出したかのような響かせ方、など古典的な形式美を超えた、生命の炎のようなものを感じた演奏であった。
協奏交響曲k297bは以前デュトワのモントリオールの特別小編成オーケストラが入善コスモでおこなった演奏会で、ライブで聴き印象に残っていた作品である。モーツアルトの作品で無いのでないかという疑惑もあるといういわくつきの作品であるが、美しい旋律に溢れた魅力ある作品であり、大好きな作品の1つでもある。オーボエ、ホルンが「ザルツブルグフェスティバルオーケストラ」団員、クラリネット、ファゴットがアンサンブル金沢団員というソロ構成で、いずれの奏者も達者な技術で見事なアンサンブル。
ここでは、出だしからやや遅めの暗い音色で始ったのにやや途惑った。全体的には、前後の交響曲とは異なり、ソロ奏者とのアンサンブルを重視した、落ち着いた演奏となっていた。
プレトークの時と、アンコールにアルペンホルンが登場。その浪々とした柔らかい響きをコンサートホールに響かせ、まるでコンサートホールがアルプスの草原になったかのような雰囲気を醸し出していた。アンコールの2曲目にレオポルド・モーツァルトの「アルペンホルン協奏曲」第3楽章が演奏され、見事なテクニックを聞かせてくれた。アンコール1曲目の「ディベルティメント」1楽章とも、岩城は指揮台から下り、オケに演奏をまかせていた。
岩城宏之マエストロ、いつまでも元気でと、エールを贈りたい様な演奏会であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢 第186回定期演奏会 2005年9月4日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 金聖響
ヴァイオリン 川久保賜紀 |
|
今期初の定期だが、指揮の岩城宏之マエストロが緊急入院とのことで、急遽金聖響に指揮者が交代。
病身であつた岩城氏であるだけに、心配である。10月には復帰予定とのことだが、10月の定期での元気な姿に接することを心待ちにしている。1日も早いご回復を祈るのみ。
プログラムも一部変更があり、間宮芳生の新作発表は11月定期マイスターシリーズに延期、変わりにシューマンの第3交響曲「ライン」が加わった。
金聖響は期待の指揮者。以前のOEKとの共演のベートーヴェンの英雄交響曲の鮮烈な印象があり、再演を期待していたが、地方公演ではOEKを振っていたようだが、定期での指揮は無く、今期の予定にも入っていなかったので、がっかりしていたが、こんな形で゛聴くことが出来たのは複雑な心境である。OEKとの相性も抜群のようなので、もっと取り上げて欲しい指揮者である。
さて、本日は前半がロッシーニの序曲が2曲、ラロのスペイン交響曲(独奏・)、後半がシューマンの交響曲第3番「ライン」。
尚最初に8月11日に59歳の若さで急死されたOEK初代指揮者榊原栄氏を追悼しバッハの「アリア」が演奏された。
オーケストラの配置が独特。オケ全体をステージ左側に寄せ、空いた右側のスペースにややオケ群と離す格好で、トランペット、トロンボーンを配置その後に打楽器。オーケストラは古典的な対向配置でコントラバスが左側、第一、第二が左右に別れ、チェロ、ビオラが真ん中、木管は中央、その後方左側にホルン。対向配置は最近よく目にするが、トランペット、トロンボーン、打楽器を極端に右側に寄せた配置は見たことが無い。明らかに指揮者金聖響の意図なのだろう。聴いた感じでは、ホルンとトランペット、トロンボーン群が離れているために立体的な音の重なりがくっきりとし、メリハリの利いた響きとなっていた。ティンパニーもやや小型のバロックティンパニーを使用していたようで、金聖響の古楽への傾倒を感じる。
ロッシーニは、「ブルスキーノ氏」序曲と「ウィリアムテル」序曲。非常に明快なロッシーニ。独特のロッシーニクレッシェンドが生きている溌剌とした演奏。この指揮者、各パートの音を明快に鳴らし、それでいて全体のオケの音のバランスを崩すことなくまとめあげるていくのは見事。テンポ設定も気持ちよく、ロッシーニの音楽独特の沸き立つような興奮を造り上げていく。
「ウィリアムテル」序曲のチェロ(カンタ氏、大沢氏他)の見事な響き、嵐のドラマティックな盛り上げ、最後の行進曲のクレッシェンド等、聴きどころ満点のロッシーニ。これだけのロッシーニは滅多に聴けないと思わせる名演であった。
川久保賜紀をヴァイオリン独奏に迎えたラロのスペイン交響曲。若い両者が火花を散らすようなスリリングな演奏。川久保賜紀は、小柄な容姿のどこからあのパッションが出てくるのかと思うようなヴァイオリン。音は硬質なため、いわゆる甘ったるさは皆無だが、ピンと張り詰めたような緊張感がラロのこの名作を、すかずしい生気で蘇らせていた。ここでの金聖響は、ヴァイオリンに遠慮することなく、むしろ挑発するかのごとくオケを引っ張っていく、。この二人の丁々発止のやりとりは実に面白い。第4楽章のしみじみとした楽想を甘くなることなく、堂々と深々と響かせていたところなど、年齢を超えた両者の深みを感じた。
休憩後のシューマンがまた素晴らしい演奏。この作品に限らずシューマンの作品というのは、複雑な要素を沢山持っているため、迷路にはまってしまうと、わけのわからない演奏になってしまいがちだが、金聖響は総ての部分を明確に演奏しながら、シューマンの情熱という一本線をしっかりと底に秘めながら表現しているので、聴くものにとって「こんなに面白い曲」ということを体感させてくれる演奏となっている。そういう意味では、相当深く楽譜を読み込んでいるからこその演奏でもあるのだろう。第4楽章が見たことも無い大聖堂が目の前に浮かんでくるようであったこと、第5楽章の堂々たる金管の鳴らせ方など、聴かせどころを見事に抑えた演奏であった。フィナーレはややオケを追い込みがちに、アッチェランドの様なスピード感で全曲を閉じていた。この部分だけがやや性急に感じた。最後の盛り上がりを狙ったのであろうが、それまでそんなにテンポをいじることも無かったので、この部分だけがやや浮き上がった様な感があった。
OEKはこの日、今まで聴いて来た定演の中でも、最高と思われる演奏を聞かせてくれた。弦のしなやかさ、金管の輝かしさ、木管の明快な響きなど統一のとれたアンサンブルてあった。
金聖響との相性が本当に良いのだろう。
アンコールは再びロッシーニ、「セビリアの理髪師」序曲。岩城マエストロの当初のプロク゜ラムに入っていた曲である。ここではややオケに疲れを感じたが、最後のクレッシェンドではやはり興奮を呼び起こしていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
NHK交響楽団演奏会 2005年8月23日 オーバードホール
指揮 クリストファ・ワーレン・グリーン
トランペット アリソン・バルソン |
|
NHK交響楽団の東海・北陸公演。前回N響が富山を訪れたのが2003年9月新川文化ホールだったので。2年ぶりの来富で、比較的短い周期で訪れてくれたこととなる。前回はワルベルクが亡くなる前年の演奏で、ブラームスの4番は円熟さを感じさせてくれた演奏であったことを記憶している。その後まもなくワルベルク死去の報にびっくりした。
今回はクリストファ・ワーレン・グリーンというイギリス出身の指揮者。全く私の知識に無い指揮者であるが、アメリカを中心にしている中堅の識者で、元々フィルハーモニア管弦楽団のコンサートマスターであったとのこと。
プログラムはグリークのペールギュント組曲第一番、フンメルのトランペット協奏曲(独奏・アリソン・バルソム)、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」。
前半のグリーク、フンメルが心地よい演奏であった。
ペールギュント組曲、出たしの「朝」はやや硬い感じの弦であったが、進むにつれて美しいアンサンブルを醸し出していた。特に「オーゼの死」の弦楽器のハーモニーは絶妙。さすがに日本トップのオーケストラのアンサンブルを聴かせてくれた。
フンメルのトランペット協奏曲、独奏のアリソン・バルソン、うら若い美貌の奏者。管の国、パリ音楽院出身だけあって、輝かしくエレガントな演奏を聴かせた。軽々と吹いているようだが、大変な力量て゜ある。オケもオーボエのオブリガートの見事なことを初めとして、弦楽器も好サポート。後半のチャイコフスキー、前半の力の抜けた好演奏と比較し、力が入りすぎの演奏。一向に音楽が流れない。指揮者の力みばかりが目立ち、この交響曲の感情の深遠が見えてこない。
メロディーに感情がこもっていないので、ただただ空虚に音楽が響く。
フォルテの部分ばかりが勇ましく目立つ演奏。音は大きく響いているが、内容が伴わない。
音楽表現とは難しいものということを再認識させられた演奏。全く「何がそうさせるのか」、素人にはわからないが、音楽の表現とは深いものである。
アンコールのチャイコフスキー「弦楽セレナーデ」からワルツ、の演奏も粗っぽい演奏。もう少しデリカシーが欲しい。 |
|
|
|
|
|
|
|
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン祝祭管弦楽団演奏会 2005年7月30日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 クリストフ・エッシェンバッハ
ヴァイオリン エリック・シューマン |
|
ドイツ、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン音楽祭のために編成された特別オーケストラ。指揮はクリストフ・エッシェンバッハ、ヴァイオリン、エリック・シューマン。
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン音楽祭は日本ではあまり知られていないが、ヨーロッパでは、ザルツブルク、ルツェルン音楽祭と並ぶ大規模な音楽祭として知られているとのこと。今年は「日本年」ということで、日本から内田光子、諏訪内晶子、五嶋みどり、今井信子、庄司紗矢香、東京クヲルテット、バッハ・コレギウム・ジャパン等、蒼々たるメンバーが招かれ、オーケストラ・アンサンブル金沢がレジデント・オーケストラとして招聘された。音楽堂山腰館長の話によると、OEKの公演は大成功で、特にジェシー・ノーマンとの共演は感銘深いものであり、オケのメンバーも金縛りに会ったようだったとのこと。オケとしての実力が試される公演であったようだが、OEKは6回の公演を好評のうちに演奏し、このオケの実力を見事に示したようだ。
さて、今日の公演はこの音楽祭のために特別編成され、各国からオーディションで選抜された、若い人たちが集まったオケ。
ブラームスが2曲「ハイドンの主題による変奏曲」、交響曲第4番、中間にエリック・シューマンのヴァイオリンでメンデルスゾーンのヴ゛ァイオリン協奏曲。
エッシェンバッハが、着実に巨匠への歩みを進めていることを印象付けられた。
「ハイドンの主題による変奏曲」では、初めのテーマで濃厚な表情付けを行ったのに始まり、各変奏の表情付けが実に豊かで、飽かず面白く聞けた。最後のフーガの盛り上がりもふくよかで雄大であり、感情豊かな演奏。オケは特に管楽器群が巧い。最初のテーマの出だしから見事なアンサンブルであった。弦楽器群は、やや硬さとアンサンブルの粗さが感じられたが、これは速成のオケとして仕方ないところか。
メンデルスゾーンを弾いた、エリック・シューマン、年はまだ若いが円熟した演奏を聴かせてくれた。
バリバリと弾きまくるのでなく、音の意味を一音一音確かめながら、全体の構成を作っていくような堅実な演奏。音色も暖かい。アンコールにクライスラーの珍しい小品。イザイを思わせるような作品で、何の曲かと思ったが、クライスラーとのこと。多彩な作曲家ではある。
休憩後のブラームスの第4交響曲。実にロマンティックで濃厚な演奏。最近のブラームスの演奏の多くが、淡白に聞こえてしまうような激しい演奏。かつての、フルトヴェングラーを軸とする、ロマン的巨匠の時代のスタイルに近似している。1楽章の出だしの音など、40年ほど以前コンサートホールというLPで聴いた、シューリヒト・バイエルン放送響の演奏を思い出させるような響き。そして、1楽章のコーダ、4楽章のコーダの追い込むような激しさ、第2楽章の音を溜めていくような効果など、白熱したブラームスの面白さを聴くことが出来た。
エッシェンバッハは最近珍しい、感情を音楽に顕に表現する指揮者、現代のクールな指揮者が忘れ去った熱い演奏を思い出させてくれる貴重な指揮者と思えた。
アンコールはブラームスのハンガリー舞曲5番と、スメタナの歌劇「売られた花嫁」から「道化師の踊り」、両曲とも溌剌とした元気の良い演奏、オケも十分に鳴っていた。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第185回定期演奏会 2005年7月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 安永徹
ピアノ 市野あゆみ |
|
ベルリンフィルのコンサートマスター安永徹を迎えてのコンサート。
メンデルスゾーン「ヴァイオリン、ピアノと弦楽のための協奏曲」、ウォーロック「キャブリオル組曲」、モーツアルト交響曲第38番「プラハ」、というプログラム。ピアノは市野あゆみ。
安永徹の弾き振りという形だが、コンサートマスターとしての弾き振りというスタイルで、指揮者というより、室内楽オケのリーダー的存在とみなしたほうが良さそうだ。
モーツアルト以外は珍しい選曲で、初めて聴く作品ばかり。
メーデルスゾーンが、ヴァイオリン、ピアノ、伴奏オーケストラとも素晴らしい出来栄え。
安永の清潔で誠実なヴァイオリンと市野の典雅なビアノ、そしてオケの充実したアンサンブルが、青年メンデルスゾーンの歌の世界を典雅に奏でる。モーツアルトをも想起させるようなピアノの響き、しかし音楽全体は華やかでゴージャスである。
編成は弦楽器のみで、コントラバスを左に、チェロとビオラを中央にした対向配置。
初めて聴く作品だが、30分以上の大曲。第一楽章のヴァイオリンとピアノの活躍は見事なもの。
カディンツアも2箇所に聴かれるなど、堂々たる構成をもった楽章。OEKの弦楽合奏は安永のヴァイオリンと一体化し充実したアンサンブル。最近、OEKの室内オーケストラ的な側面を聴かせる場面が少なかったが、こうして聴いてみると実にアンサンブルが安定していることが聴ける。
第2楽章はしっとりとした叙情的な歌謡楽章。そして、はじけるような、堂々とした第3楽章と、全曲魅力に満ち満ちた作品であった。有名なビアノ三重奏曲のような趣も感じた。興味を持ち、ネットで調べたら1951年にメニュ-ヒンがこの作品を発見したとのこと。もっと取り上げられても良い作品ではある。
後半はこれも初めて耳にする、ウォーロック「キャブリオル組曲」
舞曲的小品を6曲組み合わせた組曲。ウォーロックは1894年~1930年という生涯とのことで、後期ロマン派から現代に至る時代の作曲家であるが、この作品の作風は実に古典的。パーセルを想起させるような世界。ここでも、OEKの弦楽合奏の質の高さを聴くことが出来た。
最後はモーツァルトのプラハ交響曲。ここでは、管楽器とティンパニーが加わり、OEKとしてのフル編成。面白いもので、弦楽合奏の作品から交響曲に移ると、小編成のこの作品ですら、実に大編成に聴こえる。
出だしからかなりこの作品の世界の暗さを表出した解釈。オペラ「ドン・ジョバンニ」の悲劇性を交響曲で現したという、この作品の本質を抉り出そうとするかのような演奏。全体的には、古楽志向も感じられ、ノンビブラートに近い弦、鋭い金管など、おとなしく暖かいモーツァルトの印象ではない、深い悲劇的精神性を表出することを意識している演奏。
ここでも安永は指揮台に立たず、コンサートマスター席でリードする。見ていると時々目で管楽器に合図を送っているのがわかる。ただし、このような複雑な感情表現を有する作品では、指揮者が指揮台に立つ重要性がが逆に感じられた。このようなスタイルでの演奏では、単なるアンサンブルの巧さだけでなく、オーケストラとしての自発性が必要と思われ、それは相当成熟したアンサンブルでないと困難と思われるが、この弱点か感じられた演奏。
安永の意図、オケの巧さはあるのだが、なにか全体にぎくしゃくしたもどかしさを感じたのも事実。このあたりの克服にはOEKにとって、相当長い時間が必要なのであろうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
モスクワ室内歌劇場公演モーツァルト「魔笛」 2005年6月22日 オーバードホール |
|
序曲が始まる前から、妖精のようなフルーティストがザラストラの兵士に守られ、舞台中央でフルートソロを吹く。
このフルートティストは後の随所で活躍、タミーノか゛吹く笛はこのフルーティストが舞台上で吹く。「魔笛」の象徴のような存在か。
舞台は、際めて簡素で象徴的な装置。中央に大きな円が2つ、その円の中を道が続いている。右側には夜の世界の入り口をも思わせる黒く丸い円。「夜の女王」は常にそこから出入りする。
木の茂みを象徴するような網のような装置と鳥かご。舞台奥左手には森の象徴であろうか、メタリックな網のような装置。舞台左手奥にドラが置かれている。(このドラが実際に進行上のポイントで鳴らされる。)
1幕、2幕とも舞台装置は変化せず、照明の変化で転換を図る。照明が美しく、幻想的な雰囲気を盛り上げる。
オーケストラピッチの中に合唱団を配置という変った演出。オケは30人弱、合唱団も30名程度。オケ、合唱団とも密度は高い。
オーケストラピッチの前、客席との間の通路も舞台の1部に使用、客席との一体感を図っているよう。
序曲が始まると、舞台上では既に総ての登場人物が揃い、序曲を盛り上げる。
このように、非常に凝った演出が見られた舞台。室内オペラという、制約を逆に巧みに利用した演出、このあたりにポクロフスキーの奇才ぶりがうかがい知れる。例えば、出だしの大蛇と戦う場面は、「蛇踊り」のような蛇を登場させ、象徴的に示す。
しかし、「魔笛」というオペラ、何度見ても不可解なオペラ。その不可解さを変に解釈しようとすると、無理が生れてしまうのかもしれない。ポクロフスキーは変な解釈を加えずに、不可解さをそのまま表わそうとしているようだ。不可解さがありながら、モーツァルトの素晴らしい音楽に酔いしれれば、それで良いでしょう、というような演出と感じた。その点では文句無く楽しいオペラ。
歌手はタミーノか゜やや苦しげだったことを除けば、好演。特にパミーナの可憐さ、パパゲーノの巧みさが印象に残った。「夜の女王」の例の超絶技巧のアリアも無難。
オーケストラは小編成ながら締まったしっかりとした演奏。そして特筆すべきは合唱団の素晴らしさ。弱音から最強音に至るまで見事なハーモニー。ロシアの合唱団の底力を感じた。
このオペラは、恐らくもっと小さなホール(1000人規模程度か)を想定して作られたものと思う。
2000人を超えるホールで演じられると、観客との緊密間が薄れ、歌手も全体的に苦しそう。
その意味でこのホールの大きさが興趣を削ぐことになっていたようだ。 |
|
|
|
|
|
|
|
松原勝也と仲間達 2005年6月14日 富山市民プラザ・アンサンブルホール
ヴァイオリン・松原勝也、ビオラ・川本嘉子、チェロ・安田健一郎、ピアノ・迫昭嘉 |
|
ヴァイオリン・松原勝也、ビオラ・川本嘉子、チェロ・安田健一郎、ピアノ・迫昭嘉、という実力者を揃えた室内楽。
ビーバー「16のソナタ(ロザリオのソナタ)より16番パッサカリア」、ラヴェル「ヴァイオリンとチェロのためのソナタ」、ドボナーニ「弦楽三重奏曲(セレナード)、ブラームス「ピアノ四重奏曲第3番」という凝ったプログラム。
最初はヴァイオリンソロから始まり、一人づづ奏者が増えてくるという試み。アンサンプルの面白さを追求したプログラミングといえよう。
迫真の演奏。それぞれの奏者の個性的な息遣いが、間近に聴こえてくるような迫力。激情の産物としての音楽というものが、躊躇することなく吐露される。これほど激しい音楽を聴いた覚えが無いほど。
ブラームスを除いては全くなじみの無い作品ばかりだが、直接的に感性に訴えかけてくる。
最初のビーバー、バッハ以前のバロックの作曲家とのことだが、壮麗な世界。ヴァイオリンは太棹三味線の如く、朗々と歌う。バックに森の如くの光のシルエットを浮かび上がらせた前でヴァイオリンが響く。松原勝也の、言ってみれば個性の強い歌い方が、かえって面白くこの作品の魅力を引き出しているよう。それは、言ってみれば粘液質の、演歌的なこぶしといったら言いすぎだろうか。
次のラヴェル。ヴァイオリンもチェロもむき出しの激しさを見せる。4楽章などラヴェルの中にジャズ的なアドリブさえ聴こえてきそうな錯覚を起こさせる。それにしてもこのヴァイオリンとチェロの超絶的な技巧のぶつかりあいは壮絶である。
ドホナーニはビオラが加わり、更に厚みを増す。川本嘉子のビオラの凄さ。こんなビオラは聴いたことが無い。ヴァイオリンとチェロの中間として地味な印象のビオラが、こんなに独特の響きを持っていたとは。第2楽章のビオラ独奏では、楽器が唸っていた。そして、松原と共通する、粘っこい気質。朗々と、良い意味での演歌的な歌い回しが心をゆさぶる。ドホナーニという作曲家、名前は知っていたが初めて耳にして、実に魅力的な作品である。ガッチリとしたドイツ的な構成の中に、多彩な歌が聞こえてくる。やはり、ハンガリーの作曲家である。
休憩を挟んで、最後がブラームス。絶望の響きが最初から聞こえてくる、悲痛な作品であるが、ここで各奏者は激情のおもむくままの如く各楽器を響かせる。各奏者の強い主張がアンサンブルの中から浮かび上がってくる。遠慮することの無い各楽器のぶつかりあい。これが室内楽の醍醐味であろう。ブラームスの個人的告白であるこの作品は、このように演奏されてこそ理解が深まる。ここでもビオラの活躍が著しい。ビアノの迫はやや遠慮していたのか、他の奏者の気迫に押されたのか、ややおとなしいが、がっちりした構成感で全体を支えていた。
松原勝也が「一期一会」とプログラムに記していたように、将に「生」でしか味わえない、聴くほうも、演奏する側も瞬間に生れ出る音楽を十分に堪能した一夜であった。
このメンバーを中心としたクヮルテットなどで恒常的な活動を続けてくれたら、世界的なクヮルテットとなるのではないだろうか?
オーバードホール室内楽シリーズと銘打ったシリーズの第一回であったが、大いに興味ある試み。ただ、市民プラザ・アンサンブルホールは響きが硬く、空調の音が聞こえてくるようなコンディションの悪いホール。入善コスモあたりと比較するとかなり劣悪である。オーバードホールのような多目的ホールと同時に、音響のコンデションの良いオーケストラ用、室内楽用の中、小ホールが富山にも欲しいと改めて感じた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第183回定期演奏会 2005年6月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 モーシェ・アツモン
ピアノ リーズ・ド・ラサール |
|
モーシェ・アツモンを客演に迎えての演奏会。プログラムはメンデルスゾーンが2曲、序曲「フィンガルの洞窟」と劇音楽「夏の世の夢」。
中間に新鋭ピアニスト、リーズ・ド・ラサールを迎えてリスト「ピアノ協奏曲第一番」
アツモンは何故か懐かしい名前である。かつて、日本で良く演奏していたのだろうか?
さて、本日の注目はリーズ・ド・ラサール。全く新鮮なビアニストであるが、なんと17歳の少女。
強靭なタッチを有する、ビルツゥオーゾタイプのピアニスト。この派手な技巧を要する協奏曲を殆どミス無しに弾きまくっていた。アルゲリッチのデビューの頃は、こうではなかったかと想起させるような演奏。
アンコールに演奏されたラフマニノフも濃厚な雰囲気を漂わせた少女とは思えない演奏。現在比較的技巧的な作品を中心に演奏しているようだが、今後の成長が非常に楽しみなピアニストである。
メーンのメンデルスゾーン。序曲「フィンガルの洞窟」と劇音楽「夏の世の夢」共、アツモンの指揮はやや生硬。この作曲家独特の夢幻的な色彩感に乏しく、平板な演奏となっていたのが残念。細部のデリカシー、特に弦楽器の独特のささやきが聴こえて欲しかった。木管は総てに好演。
「夏の世の夢」は響敏也氏の脚本による、珍しいナレーション付(語り 太郎田真理さん)の演奏。脚本が良く出来ていて、語りも名演。音楽に合せての語りは非常に難しいと思うが、指揮者との呼吸も合い、とても面白く聴くことが出来た。女性合唱とソプラノ、メゾソプラノ(女性合唱OEK金沢合唱団女性コーラス、ソプラノ西野薫、メゾソプラノ池田香織)が加わった完全版の演奏であり、その意味では力の入った企画と思える。合唱、独唱とも好演。
今回の定期は前回の定期と10日も経っていなかったが、何か事情があったのだろうか?
聴く側にとっても、演奏する側にとってもやはりもう少し間隔があった方が良いように思ったが。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
アルバン・ベルク四重奏団演奏会 2005年6月4日 入善コスモホール |
|
オールシューベルトプロ。第12番四重奏断章D703、第10番D87、第14番「死と乙女」D810。
当初ベルクの「叙情組曲」の予定が、ビオラのカクシュカが体調不良とのことでイザヘル・カリシウスという弟子に変更となったのに伴い曲目の変更となったようだ。
ビオラの交代というアクシデントはあったが、全く以前と変わらない、鋭く厚いアンサンブルを聴かせてくれた。
ウィーンのカルテットのシューベルトというと、コンツェルトハウス、バリリ等かつての名カルテットの情緒纏綿たる柔らかい演奏様式を思い起こすが、ベルクカルテットは趣の異なる、鋭い切り込みを見せる演奏。
それにしても、凄いの一語に尽きるアンサンブルである。
細部まで磨きぬかれ、一点のあいまいさも許さない。各奏者の音が全部響きながらも、それが一体となりシューヘルトの精神を奏でる。各奏者の自発性が一つのカルテットとしての特徴を形作る様は奇跡的でもある。一人一人の奏者のテクニックというより、やはり30年と言うカルテットとしての年輪がここまでのアンサンブルを築き上げてきたのだろうか?
同じシューベルトの作品でありながら、12番、14番の演奏と10番の演奏は明らかに性格を変えて演奏している。10番はやはり古典的典雅さとやさしさに満ち、12番、14番は悲劇的なドラマに満ちている。14番「死と乙女」はかなり早めのテンポでグイグイと引っ張っていく。出だしの強烈な総奏はこの作品の劇的な性格を端的に現していた。感傷的な面でなく、もっと深い人間のドラマをこの演奏は聞かせてくれた。
アンコールのモーツァルトK465からの第2楽章も、実に深遠なモーツァルト。格調高く深い。
3回目のベルク四重奏団を聴くこととなったが、聴くたびに感動新たではある。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第182回定期演奏会 2005年5月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 アントン・ガブマイアー |
|
ハイドン・アカデミー管弦楽団の創立者、アントン・ガブマイアーを迎えての、ハイドンとモーツァルトの最初と最後の交響曲を演奏するというユニークなプログラム。
ハイドンの104番「ロンドン」、モーツァルトの41番「ジュピター」は超名曲として演奏回数も多いが、両者の1番は殆ど演奏されないのではないか。その意味で興味深い演奏会。
まず、カブマイヤーの指揮。完全に古楽器奏法を取り入れた演奏。楽器はバロックティンパニを用いた以外はモダン楽器だが、スタイルは明らかにピリオド奏法的。ビブラートを完全に排除し、滑らかさより、古典的明快さを表に打ち出した明確な演奏。それが、ハイドンでは見事に生かされていた。104番「ロンドン」では、出だしから乱打されるティンパニーに驚く。弦楽器、管楽器共、ビブラートがかからないので、各音色がくっきりと浮かび上がる。ピアノからフォルテに至る場合も、音が徐々に膨らんでいく様が明快に聴こえる。4楽章の特徴的な、テヌート的な低音主題が気持ちよく興奮を誘う。ハイドンのシンフォニーは、この様に演奏されて、初めて面白さが理解出来るというような演奏。OEKも弦、管、ティンパニー共、濁りの無いくっきりとした輪郭のアンサンブルを聴かせ、最近のこのオーケストラの充実ぶりを証明してくれた。
後半はモーツァルト。モーツァルトの場合、この様な演奏スタイルの好き嫌いははっきり出るのではないだろうか?ハイドンが古典的な、言ってみれば職人芸的な面白さを描き出すのに比較し、モーツァルトは、やはり感情表現がもう少しロマン的な要素を多く持っていると思うが、このスタイルの演奏では、その天才的なモーツルトの感情表現が抑制されて、端正で知的な側面は理解できるが、モーツアルトの率直な喜びゃ悲しみといった感情の側面が犠牲になってしまう気がする。特に41番「ジュピター」の第2楽章など、やはりもっとロマン的な演奏の方に惹かれていく。とはいうものの、41番の4楽章の例の大フーガは、見事な統率のとれた演奏で、重なり合っていく音の絵巻と、そのスピードに大いに興奮を感じた。このカブマイヤーという指揮者、オーケストラをドライブし、細部も磨き上げていく大変な才能の指揮者と感じた。
こうして、二人の古典派大作曲家の最初と最後の交響曲を聴いてみると、この二人の作曲家の個性の相違ということに改めて気づかされて面白かった。
ハイドンの第一交響曲と104番の間には30年余り、モーツアルトの1番と41番にも30年近い年月が隔たっている。もっとも、ハイドンは27歳で、モーツァルトは7~8歳での最初の創作、そして最後はハイドンが58歳、モーツアルトは35歳であるのだが。
ハイドンはこの30年間で、最初の交響曲から、どんと゜んとその作曲技巧を高め、最後の104番では、古典交響曲の最高峰の精緻な技法に満ちた作品を創作した。
それに対し、モーツァルトの第一交響曲には、後のモーツアルトに見られる豊かな感情表現が既に聴かれる。勿論。モーツァルトの41番は1番に比較すれば、技法的にも大変な進化を遂げているのだが、底に流れる音楽の喜悦というものは、モーツアルトが1番から41番に至るまで、一貫して失ってこなかったものという感がする。このあたりがモーツァルトの天才たる由縁であるのか。子供の頃からの瑞瑞しい感情を終生失わなかったモーツァルト。
面白かったのは、1番のシンフォニーの1楽章、2楽章に41番の終楽章のフーガのテーマのモチーフが使われていたこと。41番の最後の交響曲に、モーツァルトは少年時代を甘酸っぱく回顧していたと考えるのは、余りに文学的すぎるだろうか? |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第181回定期演奏会 2005年4月29日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ルドヴィーク・モルロー
ピアノ 若林顕 |
|
4月9日、ロジェ・ブトリーの定期演奏会に都合で参加出来なかったため、今回の演奏会に振り替えてもらう。定期会員に対するこのサービスは大変有り難い。
今回から、ロビーで開演前にOEKメンバーによるアンサンブルの軽いコンサートが開かれた。今回はブラスメンバーによるパンスタイン、ウエストサイドスドリーメドレー。開演前の雰囲気を盛り上げるのに良い試みと思う。
さて、若手指揮者、ルドヴィーク・モルローによる、大変珍しい「名曲コンサート」。珍しいというのは、定期演奏会でこれだけのポピュラーな名曲を並べるのは、最近聴いたことが無いから。
シベリウス交響詩「フィンランディア」、グリーグ「ピアノ協奏曲」、ドヴォルザーク交響曲第9番「新世界より」というプログラム。
国民楽派の名曲をズラリと並べたプログラムは、相当自信がないと、怖い?プログラムともいえる。しかし、この日の指揮者、ルドヴィーク・モルロ-は、堂々とこの名曲を、若さ溢れる熱演で演奏しきった。初めて知った指揮者だが、かなりの実力者である。
最初の「フィンランディア」の出だしのブラスの力強い響きに、「あれ、アンサンブル金沢ってこんなに大きな音を出せるんだ」と感じ入ってしまう。この日の全曲にわたって、オケの力強いアンサンブルと、音楽の愉悦というものが、楽団員の表情と、響きに溢れ、この指揮者、オーケストラと物凄く相性がいいのだと感じる。
グリークのピアノの若林顕、大変な熱演。この良く知られたコンチェルトを、今生れたかのように新鮮に響かせていた。全体の大きな構成感を崩すことなく、それでいて、細かい部分の濃密な歌わせ方、豪快な盛り上げ方、この作品の総ての魅力を示し、「ああ、やっぱり面白い曲なんだ。」と納得させられてしまう。実力者である。最近聴いた梯剛之、及川浩治、テレビで聴いた横山幸雄など、日本の中堅の男性ピアニストの充実ぶりを再認識させられた。
休憩後のドヴォルザークも、率直に謳いあげ、オケも充実、熱い演奏であった。
かなり、細かい部分にこだわりながら、全体を見通して盛り上げていく、そして、常にオケにダイナミズムを要求しているようで、オケにとっても困難な仕事であったろうが、指揮者と一体となり、新鮮で溌剌とした音楽を奏でていた。
アンコールはスラブ舞曲より1曲。
この日のプレトークて゛、この指揮者とアンサンブル金沢が、7月にドイツ「シュレスヴィッヒ・ホルンシュタイン音楽祭2005」で、ジェシー・ノーマンをソリストとしたコンサートを行うということが報告される。ドイツでの反響が楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲連続演奏会第4夜 2005年4月19日 北日本新聞社ホール
Quadrifoglio(《四葉のクローバー》 第一バイオリン坂本久仁雄(オーケストラアンサンブル金沢)、第2バイオリン上保朋子(フリー)、ビオラ石黒靖典(オーケストラアンサンブル金沢)、チェロ大澤明(オーケストラアンサンブル金沢) |
|
オーケストラアンサンブル金沢のメンバーを中心としたQuadrifoglioによるベートーヴェン弦楽四重奏全曲演奏会の第4夜
。第一バイオリン坂本久仁雄(オーケストラアンサンブル金沢)、第2バイオリン上保朋子(フリー)、ビオラ石黒靖典(オーケストラアンサンブル金沢)、チェロ大澤明(オーケストラアンサンブル金沢)
このシリーズもいよいよ第4回。
今回は初期の作品から、第5番(Op18-5)、第13番(Op130)、大フーガ(Op133)が演奏された。
ベートーウーェンの演奏の前に、3月に亡くなられたこの演奏会の実行委員会会長であった、故米田寿吉氏を追悼して、バッハの小曲が4曲演奏された。
前回第4回の演奏会に引き続き、緊張感の溢れた熱演。
ただ、若干音程の不安定さが感じられたのが残念であった。
特に初期の第5番は、古典的様式間感が色濃く残っている作品だが、力が入りすぎ全体のバランスが崩れがち、意気込みのみが先行し、音楽の様式美が犠牲になってしまっていた感があった。全体にもう少しアンサンブルへの神経の細やかさが欲しかった。
後半の13番と続けて演奏された大フーガはスケールが大きく、骨太なベートーヴェン像を描き出し、熱演。特に大フーガは、エキセントリックなベートーヴェンの心情を、共感をもって描き出していた。13番の最終楽章として作曲され、それが理解されずに別の最終楽章を改めて作り作品を完成させたとの事であるが、こうして連続して演奏されるとこの大フーガにこめられたベートーヴェンの壮大な心情がよく理解でき、この作品が13番の最終楽章として真にふさわしいと感じることが出来た。
このあたりの後期の作品になると、常識では理解出来かねるところがあり、演奏方法でも、ごく沈潜して演奏する、言ってみるとわけのわからなくなる演奏が多く感じられるが、この日の演奏はむしろ率直に書かれたことを描き出しているようで、それがかえって理解を素直にしやすくしていた感がした。この連続演奏会で常に感じてきたことは、ベートーヴェンの作品を演奏するということは、そこにのめりこむ様な音楽に対する共感が必要であり、表面的に楽譜を巧く演奏することでは面白くなくなる、という当たり前のことを改めて教えてくれている。
中々生で聴くことが難しい、特に後期の四重奏曲をこの会で纏めて聴くことが出来るのは、大変幸せな経験であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
新交響楽団第189回演奏会 2005年4月17日 東京芸術劇場大ホール
指揮 飯守泰次郎 |
|
東京へ所用のついでに見つけた演奏会。飯守泰次郎指揮による新交響楽団定期。
プログラムは飯守得意のオールドイツプロで、ベートーウ゜ェン「エグモント序曲」、シューマン交響曲第4番、ブラームス交響曲第2番、という堂々たるもの。
新交響楽団は故芥川也寸志が育て上げたアマチュアオーケストラ。邦人作曲家の作品の演奏や、飯守指揮でのワーグナーの「指輪4部作」の演奏会などで注目されているオケだ。そのような意味で非常に興味をもったわけ。
前半の2曲、ベートーヴェンとシューマン。実にオーソドックスな芝居気のない実直な演奏。
テンポはやや遅め、細かい部分の掘り下げが全体の流れと調和し、劇的興奮をもたらす演奏。
シューマンでも、この作曲家独特の暗い情念を底辺にみなぎらせながら、全体の構成感をきちんと保ち、様式感を崩すこと無く(シューマンの作品ではこれが難しい様に思うが)、がっちりと全曲を組み立てていた。新響も良く響き、熱演。
後半のブラームス。前半同様の演奏だが、こちらではややオケに破綻があり、飯守の意図が十分に伝わってこないもとかしさを感じた。やはり、交響曲2曲を一度に取り上げるのは無理があったのではなかろうか。細部の彫たくがオケの破綻により阻害されるため、全体の流れが指揮者の意図通りに流れずよどんでしまう。
それにしても、アマチュアのオケとして50年の歴史を刻んできていることは驚異であり、楽団員の音楽に対する熱情を強く感じた、それにも増してびっくりしたのは、この2000名以上は収容できる大きなホールがほぼ満席の聴衆に埋め尽くされていること。熱烈なファンをこのオケは持っており、聴衆との熱い交歓が生れていることが良くわかった。 |
|
|
|
|
|
|
|
歌劇「カルメン」 2005年3月20日 オーバードホール
指揮 チョン・ミョンフン
管弦楽 桐朋学園音楽部門特別オーケストラ |
|
フランスのオランジュ音楽祭でプレミア公演されたものを、東京、ソウルで公演、更に市民参加型オペラとして富山で公演されるもの。演出はジェローム・サヴァリ。指揮がチョン・ミョンフン
藤原歌劇団とオランジュ音楽祭の共同制作。
主な出演者は次の通り。
キンガ・ドバイ(カルメン) チョン・イグン(ドン・ホセ)チェ・ウンジュ(エスカミーリョ)松田奈緒美(ミカエラ) 合唱 藤原歌劇団合唱団 公募による特別編成のオーバード声楽アンサンブル 児童合唱福野小学校合唱クラブ 地元松岡ジャズバレエ研究所等のバレエ団。
管弦楽 桐朋学園音楽部門特別オーケストラ
演出、装置・美術とも、極めてオーソドックス。偶然に同日の夜NHK教育TVでオランジュ音楽祭のプレミア公演のハイライトが放映され、比較し興味深かった。特に第3幕、4幕の演出・装置に大きな変化があったこと。オランジュでは第3幕が抽象的な装置で、舞台に馬(あるいは牛?)の死体と思われれるものが累々と横たわっていたが、今回は山並みを背景としたリアルな装置。4幕ではオランジュでは、闘牛士の入場の際、骸骨の衣装を着た一群が先頭に入ってきたが、今回はそれは無し。又、背景の闘牛場の模様がオランジュでは赤い炎の様な中に牛のシルエットが浮かび上がっていたのが、今回はリアルな闘牛場の写真に変更されていた。
オランジュでの演出は多分に「死」を抽象的に強調する意図が汲み取れたが、今回はまともで具象的。東京、ソウルではどうだったのだろうか、興味深い。
歌手はチョン・ミョンフンが連れてきたという、若手の歌手ばかり。特に韓国の若手歌手の起用が中心。カルメンはハンガリーの新星、ギガン・ドバイ。カルメンにしてはやや線が細く、こなれない生硬さは感じたが、身体を張って難役にぶつかり、堂々と務め上げていた。ドン・ホセのチョン・イグン、良く声の通るテナー。今回初オペラというミカエラの松田奈緒美が、可憐で初々しい舞台で、声もソフト、ミカエラという役にふさわしい熱演だった。エスカミーリョのチェ・ウンジョは歌い方にやや癖が感じられ、声量も今ひとつ。
管弦楽は桐朋学園の学生中心。コントラバス6台の大型編成。ピットの関係か、コントラバスを左奥に並べ、管楽器を右側に、テインパニーを右奥に配置する変わった配置が面白い。
チョン・ミョンフンはさすがにこのオペラを知り尽くした、丁寧でドラマティックな音楽作り。
管弦楽と歌手、合唱がチョンの手先の様にオペラを進行していく。歌手中心の作りでなく、ドラマとしてのカルメンが演じられ、ビセーの音楽の雄弁さが良く生かされた舞台。
管弦楽は音色に硬さが感じられたが、チョンの要求に良く応え、高い水準の演奏。
合唱団は藤原の他に、公募オーデションで選ばれた地元富山の合唱団。良く鍛えられた合唱。
福野小学校合唱クラブの児童合唱の高い水準にもびっくり。オランジュの児童合唱よりも巧かったのではなかろうか?
バレエ、群集等も地元で公募の参加者で賑やか。大成功の公演といえる。
ところで。
一つ気になったこと。オーケストラが桐朋の学生オケが中心だったが、桐朋音楽アカデミーとの関係でということと想像できるが、中心は東京の本校のオケメンバー。桐朋と富山市のデモンストレーション的な臭いを感じてしまう。
北陸にはプロのオケとしてアンサンブル金沢という立派なオケがある。このオケを使うという選択肢は無かったのだろうか? 地元参加型の市民オペラとしての位置づけがあるならば、北陸という地域性の中でのアンサンブル金沢は最善の選択肢でもあったと思えるが。
富山でのアンサンブル金沢の演奏回数が、隣県であるにもかかわらず少ないことが奇妙である。小杉、高岡には年に数度来ているが、富山市での公演は極めて少ない。変なセクト意識が富山側にあるのでないかと勘ぐってしまう。せっかく立派なプロのオケが北陸にあるのであるから、もっと富山市民にも広く聴かせてほしいと願う。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第178回定期公演 2005年3月19日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城宏之 |
|
今年度のOEKコンポーザー・オブ・レジデンス権代敦彦の世界初演作品「84000×0=0オーケストラのための」、ブルッフの「ヴァイオリン協奏曲第一番」(アン・アキコ・マイヤース)、ブラームスの交響曲第一番、という興味深いプロ。いかにも音楽監督岩城宏之らしい充実したプログラムである。
権代敦彦「84000×0=0オーケストラのための」。打楽器と木管楽器の多彩さが目立つ、大編成のオーケストラ作品。資料を見ると打楽器は何と12種類。木魚、寺の鐘などという珍しいものもある。これを3名の打楽器奏者が演奏するのだから大変。一人当たり4個の楽器をうけもつこととなり、大奮闘。木管もコントラバスクラリネット等という珍しい楽器も使用。
プレ・トークと配布のプログラムの中で、作曲者がこの作品の作曲意図を細かに説明しているので、理解は明快。ちなみに、84000とは煩悩の数、0とは解脱、極楽浄土の世界への到達とのこと。作者は1年半金沢の東の廓街に居を定め、この作品を作り上げたとのこと。朝晩聴こえてくる東山の寺院群の鐘の音に、創作の原点を見出したとのことであった。
その東山の鐘の音を思わせる打楽器のモチーフから始まり、弦楽器の特殊な奏法と木管による、高い、キンキンとするような高まり、打楽器群の咆哮を経て、最後は平安を感じさせる合奏によって曲は閉じられる。楽器の様々な使い方が面白く、音色は極めて多彩。作曲技巧の巧みさと、表現の面白さが光る作品に思えた。OEKは勿論大熱演。
次のブルッフ。ヴァイオリンはアン・アキコ・マイヤース。この様な派手な作品にはぴったりのヴァイオリニストだろう。ただ、想像していたよりおとなしいヴァイオリン(技巧的なおとなしさという意味でなく、けれんみがないというような感じ)。作品へののめりこみが無く、変に崩さず、気品高く演奏していく。それが、逆にやや物足りなさを感じさせるのも事実。オケは実に壮大な作り、堂々と情熱的な高まりを描き出す。
休憩後のブラームス。最近の岩城はブラームスの交響曲で、初演の際の楽器配置というものを採用している。この日も、コントラバスを、テインパニを真ん中にして、正面奥に配置、ヴァイオリンは対向配置という変わった楽器配置。低音を正面から響かせようという意図なのであろうか?それは別として、てらいの無い、正攻法のブラームス。細かい部分は小細工をせず、さらっと流し、全体のテンポは大きく崩さず、堂々と骨太に流れるブラームス。最近の岩城の特徴的な、正面からブラームスの作品をとらえた演奏。ブラームスの交響曲は、細かいところにこだわりすぎ、全体の流れをそこなってしまう演奏が多くみられるが、今日の演奏は全体の流れを見通したスケール感のある演奏で、ブラームスの交響曲の醍醐味を味あわせてくれた。
オケも熱演だったが、金管のアンサンブルに若干の破綻が聴かれたのが残念。
アンコールのハンガリー舞曲第1番も熱演。久しぶりに岩城監督の音楽をドライブするような指揮振りが見られ興味深かった。 |
|
|
|
|
|
|
|
日本フィル第298回名曲コンサート《コバケン・ガラVol.2》 2005年 3月6日 (日) 東京 サントリーホール
指揮 小林研一郎
ピアノ 寺田悦子&渡邉規久雄。
オルガン 長井浩美
|
|
息子の結婚式の打ち合わせで、横浜に行く予定となり、その日前後の音楽会情報を探していたら、このコンサートとミューゼ川崎での金聖響-東京交響楽団の演奏会が目に留まつた。金聖響-東京交響楽団は既に完売となっており、こちらの演奏会を予約。それにしても最近はネットでどこの音楽会でも予約できるので便利になったものだ。
小林研一郎は一昨年アンサンブル金沢と大阪センチュリー交響楽団の合同演奏会でスメタナ「わが祖国より」抜粋とムソルグスキ-「展覧会の絵」で、凄い名演奏を聞かせてくれた、印象に強い指揮者。その後日本フィルの音楽監督として各地で絶賛されているのを耳にし、一度聞いてみたいと思っていた指揮者とオーケストラである。
この日は名曲コンサートということで、楽しい作品が組まれていた。プログラムは次の通り。
モーツァルト:2台のピアノのための協奏曲
ブリテン:青少年のための管弦楽入門
サン=サーンス:動物の謝肉祭
(以上2曲の語り/小林研一郎)
サン=サーンス:交響曲第3番《オルガン・シンフォニー》より第2楽章第2部
ピアノは寺田悦子&渡邉規久雄。
オルガン、長井浩美
ポピュラーで楽しい作品ばかりであるが、中々演奏されることは珍しい作品ではなかろうか。楽器の編成が多種にわたるし、なにより二人のピアニストがサン=サーンス:動物の謝肉祭は必要であるので゛、コンサートで取り上げるのは珍しいと言えるだろう。
そしてこの日は何と指揮者の小林研一郎が語りまで行うというサービス。
小林研一郎という指揮者、いつの演奏会も全力投球という感じ。あれだけ多くの演奏会をこなしながらマンネリに陥ることなく、いつも新鮮な全力投球の音楽作りが、多くの聴衆の心を捉えているといえる。この日もそんなコバケンの姿勢が如実に出た演奏会。
最初のモーツァルト。ピアノの二人は実に率直な、誠実なモーツァルトを聴かせてくれた。コバケンの指揮もメリハリの利いた、しっかりとした演奏。そして第2楽章のしっとりとした叙情、第3楽章の愉悦など、ピアノを巧リードしていく。
ブリテンと休憩を挟んだサン=サーンスはコバケンの語りつき。普通は台本があり、声優などがナレーションをつけていくが、この日は台本も無さそう。まるでリハーサル風景を見るような面白さがあった。ただ、音楽が語りの度に中断されるので、せっかくの音楽の流れがが途切れてしまうような部分もあり、もどかしさも感じる。小林研一郎もちょっとやりにくそう。
ブリティンは各楽器ソロが見事。コバケンが「いやー、素晴らしいクラリネットでしたね」なとどほめまくるのがほほえましい。最後のフーガはコバケンらしい熱い盛り上がりを見せる。
サン=サーンス:動物の謝肉祭は、弦楽器などのパートを相当増員したフルオーケストラに近い編成での珍しい演奏。ここで面白かったのは、この作品の特徴である、他の作品からの引用の原曲をオケで演奏し、サン=サーンスがいかに巧みに、又皮肉たっぷりにその原曲を使っているかを浮かび上がらせた点。こんな試みは初めてであろう。ここにもコバケンのサービス精神が見られる。各小品とも性格がはっきりした名演であり、快演であった。ピアニストの二人もいかにも楽しそうに演奏、有名な「ピアニスト」など、下手さを見事に誇張した怪?演。有名な「白鳥」のチェロも感動的。
最後のサン=サーンス:交響曲第3番《オルガン・シンフォニー》より第2楽章第2部は壮麗なオルガンの演奏で始まるこの交響曲の最後の部分のみの演奏であったが、サントリーホール全体に響き渡る重厚なオルガンの響きと輝かしい管楽器の響きが合わさって鳴り渡る、コバケンらしい熱のこもった演奏。明るく軽やかな面よりも、がっちりとした堂々たる建造物を見るような、コバケン独特の世界を聴くことが出来た。
アンコールにダニーボーイ。弦楽器を中心としたよく歌う、懐かしさに満ち満ちた演奏。
来て良かったと感じさせてくれた演奏会。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第177回定期公演 2005年3月4日 石川県立音楽堂 コンサートホール
指揮 ジャン=ピエール・ヴァレーズ
チェロ 遠藤真理 |
|
今回の定期、当初予定のルドルフ・ヴェルテンが急病のため、ジャン=ピエール・ヴァレーズに変更という珍しいこととなった。プロク゜ラムの変更は無し。ヴェルテンはベルギー、ヴァレーズはフランスと、共に似通った香りを持つ音楽圏の指揮者なので、オーケストラとしてもとまどうことはなかったのではなかろうか。
プログラムは次の通り。
J.S.バッハ/外山雄三:トッカータとフーガ 二短調BWV.565
ボッケリーニ:チェロ協奏曲第9番 変ロ長調 G.482
ブリクシ:オルガン協奏曲第5番 ヘ長調
J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番BWV.1068
オルガンは小林 英之、チェロは遠藤真理。
プレトークに珍しく池辺晋一郎先生。相変わらずの駄洒落を交えての軽妙な解説。
ヴァレーズはフランスの室内楽の指導者だけあって、とても明るく輝きのあるアンサンブルを作り上げる人という印象。パイヤールあたりの音色と非常に似通った音をアンサンブル金沢が出しているのにびっくり。指揮者に順応できるアンサンブルを作り出すのは、指揮者の才能は勿論のこと、オーケストラが優秀でないと出来ないこと。それだけアンサンブル金沢の成熟度が高いということだろう。
最初の「トッカータとフーガ」、出だしに管楽器でチューニングの様な音が出で来て驚いた。有名なトッカータのテーマはその後からオルガンで壮麗に響く。これは、編曲者外山雄三のいたずらであろうか。全体的には、ストコフスキーの編曲を想起させるような華やかな演奏。最後の部分、性急な拍手に中断されたような感じがあったが、どうだったのだろう。
音楽堂のオルガンは初めて聴いたが、曲の性格もあるのだろうが、重厚さよりも、輝かしい明るさを感じた。
さて次のボッケリーニ。どうも古典のチェロ協奏曲はハイドンにしろボッケリーニにしろ、中々演奏が難しいようだ。遠藤真理のチェロはしっかり弾いているのだが、やや荒っぽく、古典的な典雅さに欠けている印象。技術的にも相当難しい作品なのであろうか。音程の不安定さなども感じられ、もう一つのり切れないもどかしさを感じた。
ブリクシという初めて聴く珍しい作曲家。オルガンも重くなく、明るくきらきら輝くような印象。時代としては古典派に属する作曲家なのだろう、ヘンデルをもう少し軽くしたような印象。楽器編成も弦楽器にホルンを加えた珍しい編成。
さて、最後のバッハ管弦楽組曲第3番。バッハの壮麗さと輝かしさが良く出た演奏。アンサンブル金沢の弦楽器群のアンサンブルは見事。有名なアリアのしっとりとした叙情など、見事な弦の響きであった。そして非常に難しいと思われるトランペットも、思い切りのよい、きちっとした音を出していた。ヴァレースの指揮も輪郭がくっきりとし、堂々としたバッハの世界を表出。この日一番の演奏で最後を締めくくった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
樫本大進ヴァイオリン・リサイタル 2005年2月23日 入善コスモホール |
|
日本の若手アヴァイオリニストの底の厚さをみるようなリサイタル。川久保賜紀、庄司紗矢香と聴いてきたが、この樫本大進は将に大物。作品に対する深い洞察に基づく個性的な表現は、聴く者を圧倒させる。
プログラムは次の通り。
シューベルト ソナチネ第2番 イ短調 D.385
ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ第5番 ヘ長調 Op.24「春」
フォーレ 「夢のあとに」
バルトーク 狂詩曲第1番
R・シュトラウス ヴァイオリンソナタ 変ホ長調 Op.18
ピアノはイタマール・ゴラン
シューベルトの素朴で抑えた表現、ベートーヴェンの溌剌とした若さはじける表現、フォーレのしっとりとした叙情、バルトークの粗野な民族性、そしてR・シュトラウスの濃厚なロマンティシズムと、各々の作品の持つ性格を見事に描き分けながら、それでいて、自らの個性をどの作品の中にもしっかりと打ち出していく、これは大変な才能である。相当な作品に対する読み込みと共感があるからこそ、聴き手に明確に伝えることが出来るのだろう。
最初のシューベルト。ソナチネと言いながら4楽章形式の大規模な作品。出だしのゴランのピアノにはっとさせられる。シューベルトの歌と深い沈潜がこめられている。樫本大進のヴァイオリンはここでは、終始押さえ気味に歌っているが、それがシューベルトの特徴である、「心の歌」を的確に再現している
うって変わってベートーヴェンの「スプリングソナタ」は、開放された若々しさ、みずみずしさに満ちている。そして、古典的な端正さも失うことなく、ベートーヴェン初期から中期への移行期の作品の特徴である、端正な激しさと雄渾、を見事に表現。第2楽章の変奏曲など、ゴランのピアノと寄り添うように歌い、静かに謳いあげていく様は、しみじみと心にしみる。短い第3楽章に続く第4楽章は率直に端麗に、そしてみずみずしく歌が続く。ここでのゴランのピアノも見事。
休憩の後の、フォーレ。その題名の通り、「夢のあとに」である。静謐な美しさが支配している演奏。
そして、バルトーク。ここでは一変して激しい、粗野とも言えるヴァイオリンを見せる。前半の「ラッサ」の部分のジプシー風の濃厚な民族的な粘り、後半のフリスカの超絶的な技巧と激しさ。
最後のR・シュトラウス。ここで、樫本大進は、それまでの総結集をするような、濃厚なヴァイオリンを聴かせる。艶やかな伸びのある厚い音色で、R・シュトラウス特有の甘美な歌が綿々と続く。
第2楽章は歌劇「ばらの騎士」を思わせるような甘く切ないカンタービレ。ピアニシモからフォルテシモに至る音色の豊かさも圧倒的。
アンコールは3曲。
ドヴォルザーク-クライスラー編曲 :スラブ舞曲Op72-2
クロール:バンジョーとフィードル
バッハ:G線上のアリア
2曲目は聴いたことの無い作品だが、ホールに問い合わせた結果の返答。
とても。技巧的なウィニャフスキーをも想起させるような作品。
聴衆の熱い拍手に、最後は「もう、これで勘弁してください」とでも言いたげに微笑みを浮かべて終了。2時間30分近い熱演であった。
樫本大進とともに、ピアノのイタマール・ゴラン。総ての作品に樫本をある面では挑発するように、そしてある面ではしっかりとサポートする。そして、しっかりとした作品に対する自らの姿勢を持っている。ヴァイオリンリサイタルはピアニストが単なる伴奏者でないことを実感させてくれた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西本智美バレンタインコンサート 2005年2月21日 石川県立音楽堂コンサートホール |
|
話題の指揮者、西本智美が客演の、オーケストラアンサンブル金沢の特別コンサート。
司会と「白鳥の湖」のナレーションが中井美穂。
「西本智美バレンタインコンサート」と銘打っているが、さてさて、意味不明の名称である。
アンサンブル金沢は客演奏者を加え、コントラバス6本の大型編成。
オールチャイコフスキープロで、バレー音楽「白鳥の湖」抜粋、交響曲第4番というプログラム。
「白鳥の湖」からが、熱演そして秀演。西本智美という指揮者、オーケストラをドライブするのに長けた指揮者という印象。良く鳴らし、細部を磨き、そしてドラマティックな音楽作りをしていく。その特徴がバレー音楽にはピタリとはまっている。音楽がドラマとなり、雄弁に語っている。
アンサンブル金沢も好調。金管、木管、など輝かしい音である。「王子とオデッタのアダージョ」のコンサートマスター、ヤングさんとチェロのカンタさんの独奏、そしてハープの独奏、いずれ良く歌い美しい。最後の情景から、フィナーレの大きなうねりのような高揚も見事。
後半のチャイコフスキーの4番だが、前半の「白鳥の湖」に比較し、やや平板。第3楽章の有名なピチカート、管楽器のかけあい、第4楽章のフィナーレへの盛り上がりなど、聞かせどころは沢山あるのだが、全体の印象として散漫。シンフォニーとは、小曲のつながりであるバレー音楽と異なり、全体を見渡した細部への構築が必要とされると思うが、彼女の場合、細部の構成から全体を組み立てようとしているようで、それが印象を散漫とさせているようだ。最近の中堅指揮者によく感じられる、才気煥発型で、オケを良くドライブし、細かく部分部分を磨き上げていくが、全体として感動が薄いという傾向がこの指揮者にも見られるようである。指揮ぶりも見事、オケも良く鳴らし、ドラマティックな音楽作りをする指揮者なので、今後このあたりがどのように変化していくか楽しみにしたい。
アンサンブル金沢は全体のアンサンブル、そして音量とも申し分ない熱演。この指揮者のドラマティックな音楽作りに良く応えていた。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第175回定期演奏会 2005年2月4日石川県立音楽堂コンサートホール
指揮とバリトン ペーターシュライヤー |
|
今回の定期はペーターシュライヤーの福音史家と指揮によるバッハ「マタイ受難曲」。めったに、というより全曲演奏は北陸初演ではなかろうかと思われる大曲のコンサート。休憩も含め、3時間30分にも及ぼうという大曲である。
指揮と福音史家はペーター・シュライヤー、ソプラノ:クリスティーナ・ランズハーマー、メゾ・ソプラノス:ティフニー・イラニ、テノール:マルティン・ペツォルト、バリトン:ヨッヘン・クプファー、バスバリトン:エグベルト・ユングハウス、OEK金沢合唱団と児童合唱エンジェルコーラス(合唱指揮佐々木正利)という大きな編成。
オーケストラは左に第一オーケストラ、右に第2オーケストラ、オルガンは第一オーケストラ内に配置、正面に独唱陣、奥左に第一コーラス、右に第2コーラス、正面2階オルガンステージに児童合唱団という配置。合唱は約100人ほど、児童合唱も約40人ほど、オーケストラも通常より木管、弦楽器を増員しているようだ。
ペーター・シュライヤーは正面奥に客席に向かって立ちオケを指揮、合唱を指揮する時は振り向くという、そして福音史家も歌うという、大変な熱演。それも、全曲暗譜での演奏。
ペーター・シュライヤーの福音史家は、極めてドラマティック。言葉への感情移入は激しく、時には慟哭に近い。声がこれほど激しい感情を伴って表現されることは驚き。アリアでなく、レシタチーボに近い語りでありながら、歌になっており、バッハの描いた音のドラマ性が見事に描かれている。
言葉の壁があり、ドイツ語にほとんど堪能でない私は、同時通訳の字幕に頼らざるを得ず、もしドイツ語に堪能であったなら、恐らくシュライヤーの言葉と音の密着度の凄さをもっと感じられたのにと思うと残念。
全体の印象は、長大な叙事詩の如くであった。テンポは極端に動かさず、音楽は劇的ではあるが、センチメンタリズムを廃し、淡々と流れながら、大きなドラマの骨格を築いていき、それが一層この受難曲の悲劇的な壮大さを築いていっている。
各独唱陣も立派な演奏、特にユダのバス、ソプラノは、声の質といい、声量といい、格調のある歌唱。オーケストラも熱演。フルート、オーボエ、ファゴット等木管の、オブリガート風な各歌唱へのからむ旋律など、見事な演奏であった。特に第21曲であったか、ファゴットの艶やかな高音域の独奏は印象に強く残る。低音弦、チェロ、コントラバスの活躍もこの作品の特徴であるが、いずれの独奏者も見事。OEKのアンサンブルの質の高さと、シュライヤーの高度な要求とが、マツチングして、質の高い演奏となっていた。
そして、合唱団。群集の叫びなど、劇的な効果を高める要素の多い合唱部分であるが、シュライヤーの激しいドラマ作りに応えた熱演。各声部のバランスも整い、児童合唱も含め見事なアンサンブルて゜あった。
最終曲68曲は、やや早めのテンポで、過度な思い入れを廃し、淡々とこの大曲を閉じていった様に感じたが、それまでの壮大なドラマを閉じるにふさわしい終結であった。
それにしても、この大曲を本当に理解できるのには、まだまだ時間が必要であることも痛感した。あまりにも、多くの要素が詰め込まれている作品であることを、そしてそ無尽蔵の魅力をもっともっと聴き込みたいと思わせる作品である。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ペーター・シュライヤーリサイタル シューベルト「冬の旅」 2005年1月30日 石川県立音楽堂コンサートホール |
|
「冬の旅」全曲の最後「辻音楽師」(最近「ライアー回し」と訳されるようだが、「辻音楽師」の訳こそ、名訳だと思うが。))が、消え入るように終わり、暫くの静寂の後に、湧き上がるような拍手が起こる。ペーター・シュライヤーの名唱で、青年の絶望の心象風景に深く分け入っていた聴衆の一人である私も、全曲の閉ざされた後に、心の熱くなる感動がこみあげてきた。稀有な体験である。
70歳近いといえば、円熟という言葉で片付けられそうなものであるが、今日の歌唱はそんなものでなく、永遠の青年の歌であった。゜
かつて、フイッシャー・ディスカウ、ヘルマン・プライ、ハンス・ホッター、古くはゲルハルト・ヒュッシュ等の「冬の旅」の名唱をLPやCDで聞いてきたが、そのどれとも異なる、リードというよりむしろモノオペラの世界のような歌唱。ペーター・シュライヤーの「冬の旅」は、ドラマティックな、しかし表面的なドラマでなく、言葉と音符が最奥まで読み込まれ、、一人の青年の絶望的な心の葛藤が、リアリティーをもって表現しつくされていた。この作品は、立派な風格をもって演奏されるよりも、今日の演奏のように、生々しく、青年の独白のように演奏されるべき作品であることを、シュライヤーは証明してくれた。
普通はバリトンて゜歌われることが多いと思うが、テナーという音域は、一層良くこの「冬の旅」に合っている。そして、艶やかで伸びのあるシュライヤーの声は、青年の独白にぴったりである。
それにしても全24曲総てに心のドラマが刻み込まれた、何とも生々しい「冬の旅」であった。
ピアノは、カミロ・ラディケ。良くサポートしていたが、シュライヤーの絶唱ばかりが目立ち、ピアノの個性がやや沈んでしまっていたことは残念であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
及川浩治ピアノノリサイタル 情熱のベートーヴェン 2005年1月14日 富山市民プラザアンサンブルホール |
|
冬場は音楽会も少なく、久方ぶりの、そして今年初めての音楽会。
本来なら1月8日のアンサンブル金沢のニューイヤーコンサートに行く予定だったが、娘一家が来ていたためキャンセル、今年初めてのコンサートがこの日となった。一昨年から、このホームページを開設したので、昨年の音楽会へ足を運んだ回数をカウントすると26回であった。1月平均2回、こんなものかな。
さて、今年初の演奏会。なかなか、エキサイティングなものであった。
名前は聴いていたが、初めて聴くピアニスト。日本の演奏家に珍しい、派手なピアニストである。
というのは、日本の演奏家の印象は、きめが細かく、むしろ求心的で、内面に沈潜していくタイプでが多いように思えるが、彼の演奏はむしろ外へアピールしようとする意欲が強く、悪く言えば大向こう受けを狙うような演奏家。ロマン派後期の大ピアニストに見られたような濃厚なロマンチシズムを醸し出そうとするタイプのピアニストと思える。
「情熱のベートーヴェン」と銘打った演奏会のプログラムは、ソナタ第8番「悲愴」、第14番「月光」、バガテル「エリーゼのために」、ソナタ第17番「テンペスト」、第23番「熱情」という、ベートーヴェンの初期から中期の傑作をずらりと並べたもの。プログラミングからして、悪く言えば聴衆受けを狙ったようなものとも思える。このあたりが、このピアニストのてらいの無い面白さかもしれない。
前半のソナタの8番、14番は、彼の表現しようとする世界と、作品の有する性格に乖離が見られ、熱演ではあるが、表面的な派手さだけが聞こえてくる退屈な演奏となってしまった。
初期のベートーヴェンの作品は、独自のベートーヴェンの世界が開きつつはあるが、まだハイドン時代の古典的な格調も作品に色濃く残っていると思われるが、彼の演奏はベートーヴェンの中期の作品に充満する破壊的な情念を、初期の作品にも求めたため全体的にまとまりのつかない演奏となってしまったように思える。第8番の3楽章の異常な激しさ、第14番の1楽章の非常に遅いテンポのとりかた、そしてぺタルの多用など、彼の意識的な挑戦は理解できるが、作品全体の構成を歪めてしまっているような印象を受けた。
しかし、後半「エリーゼのために」に続いて切れめ無く始まる17番「テンペスト」の異様な開始から様相が異なってきた。ベートーヴェンの中期の作品の持つ、ワイルドな情念が見事に描かれ、
音楽は吼えまくった。面白かったのは17番、23番の第2楽章の緩やかな楽章。音楽は沈潜し、メロディーは歌わず、むしろ点描的な、一つ一つの音を確かめるような足取りの音楽。決して流れるようには弾かず、むしろベートーウ゜ェンの足取りを確かめるように弾いていく。アンコールのリスト「愛の夢」、ショパン「ノクターン」でも感じたが、彼の緩やかな旋律に対するアプローチは独特の節があり、テンポのとりかたも独特である。こんなところが、かつてのロマン派後期の爛熟した世界をも彷彿とさせる趣を感じた。
23番「熱情」、第一楽章の有名な「運命」の動機の劇的な展開、第3楽章終結部のテンポの激烈な追い込み方など、聴いているものを興奮に追い込む凄さがある。
ベートーヴェンの中期の傑作群に挑戦するには、この位の気合が必要であり、その気合が聴くものをベートーヴェンの音楽の持つ凄さに引きずり込んでくれる。そんなことを感じさせてくれた熱演であった。
新年早々、エキサイティングな音楽を聴き、今年の音楽会へ足を運ぶわくわくする期待感を予感させてくれた演奏会であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第171回定期演奏会 2004年11月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城宏之
バリトン フローリアン・プライ |
|
岩城宏之氏の指揮、フローリアン・プライのバリトンによるシューベルト管弦楽伴奏版「冬の旅」をメーンとし、前半に未完成交響曲が演奏される。当初の予定曲目に「未完成」は無かったので、追加となったようだ。「冬の旅」に入る、雰囲気を醸し出すためには、適切な選曲と感じた。
岩城氏の「未完成」はもう定番なのだろうが、実に手馴れた指揮で、変にセンチメンタルに歌わない、風格のある演奏。やや早めのテンポをとり、さらっと流しているようで、細かい部分はよく歌い、メリハリの利いた好演。アンサンブル金沢のクラリネット、オーボエ、フルート等木管のソロは実に巧いものであった。
さて、メーンの「冬の旅」 バリトンのフローリアン・プライは大歌手ヘルマン・プライの息子とのこと。この管弦楽伴奏版の初演は、亡くなる直前のヘルマン・プライが行っているので、その意味で感慨深い演奏会でもある。管弦楽版の編曲は鈴木行一氏。
ピアノ伴奏部分を管弦楽に編曲してあるのだが、ピアノ版とはかなり雰囲気が異なり、伴奏部分の音色の多彩さと、饒舌さが、功罪相半ばしているような気がする。良く語られるように、このピアノ伴奏は歌と同等、あるいはそれ以上に重要で、ピアノ部分の語っている内容が実に深い。それは、ピアノという楽器の音色に依存するところが多く、シューベルトは実に巧みにピアノに語らせているわけだが、管弦楽に翻訳すると、意味合いが違って聴こえてくる。繊細さと、熱い感情より、ドラマ的な要素が強く出てくる。饒舌なのだが、やや皮相的に聴こえもする。このあたりが、非常に難しいところであろう。ヘルマン・プライが初演でどのように歌ったのか、聴いていないので、なんとも言えないが、管弦楽版で歌う場合にはかなりのオペラ的なドラマ性が要求されるように思う。
この日のフローリアン・プライは、実に良い声の質をしており、リード歌手としてふさわしい声の持ち主と感じたが、作品の捉えかたとしては、やや平板であった。一つ一つの歌の質が、総て同じに聞こえて、1曲目から24曲目までにいたる、ドラマが感じられない。これは、やはりまだ若いということのなせる業であろう。「冬の旅」という作品は、それほど恐ろしい作品でもある。現在のフローリアン・プライでは、むしろ「美しき水車小屋の娘」の初々しい叙情性がふさわしいのではないかという気がする。
しかし、これだけの美声とテクニックの持ち主、将来が楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
ウィーンフィルハーモニー管弦楽団演奏会 2004年11月11日 オーバードホール
指揮 ワレリー・ゲルギエフ |
|
ワレリー・ゲルギエフ指揮によるウィーフィルの2004年日本開幕公演。J・シュトラウス2世のワルツ・ポルカ集とチャイコフスキー「悲愴交響曲」という、ユニークなプログラム。
他のオケがこのようなプロを組むと、「名曲特集」のようになってしまうが、さすがにゲルギエフ・ウィーンフィルは、きちんとした意図のもとにこのプログラミングをしていることをプロク゜ラムの記載記事で知った。ロシアゆかりのプログラムとのことで、昨年モスクワとサンクト・ペテルブルクでも同様の曲目で公演を行っているとのこと。
それにしても、富山でウィーンフィルのワルツ・ポルカを聴くことが出来るとは、感慨ひとしおである。
40数年前、青春の頃、ボスコフスキーがウィーンフィルを率いて日本でワルツ・ポルカの演奏会を開いたことがあり、その頃LPでクレメンス・クラウスのワルツ・ポルカに心酔していた私は、胸をときめかして聴きに行ったものである。ところが会場が日本武道館!?。悲しいかな、音が全部逃げていき、がっかりして帰ってきたことを思い出す。それ以来、生でウィーフィルのワルツ・ポルカを聴きたいとおもい続けて来たが、そのチャンスは中々訪れなかった。ウィーンを訪れた際、トンキュンストラー管弦楽団のワルツ・ポルカをムジークフェラインザールで聴いたが、やはりウィーンフィルを聴きたいという思いはつのっていった。
その思いがようやくかなった富山での公演。指揮は、ゲルギエフである。
最初のワルツ「戴冠式の歌」。出だしこそ、疲れと緊張からか、ややもたもたしたアンサンブルが聴かれたが、これもウィーフィルの特長か。ベルリンフィルのように決してピタッとそろわないで、もやもやっとしているが、それが又人間的に感じ、魅力でもある。曲が進むにつれ、オケもゲルギエフも次第にのってくるのが感じられる。これはもうやはり、良く言われるように、民族の血であろうか。上品で、歯切れがよく、優雅で、柔らかい。ベルフィンフィルと大きく異なるのは、オケの音色が弦にしろ、管楽器にしろ、打楽器でさえも同一の音色をしているので、渾然としたハーモニーを奏でていること。ベルリンフィルは個々の奏者の個性と力量がストレートに聞けたが、ウィーフィルはオケとしての一つの個性に各奏者が同一化している。将にウィーフィル・トーンという音が、世界にこのオケだけという個性を際だたせている。
「ニコ・ポルカ」、「皇帝円舞曲」、「ペルシャ行進曲」と続き、プログラム最後はワルツ「ウィーン気質」。ヴァイオリンの独奏、チェロの独奏とも絶妙。将にウィーン節である。旋律の歌わせ方、リズムの刻み方など、「俺達の音楽」という自信と誇りに満ちている。ゲルギエフはかなり細かい指示を与えているようだが、全体の構成をきちっとすることで、情緒だけに流れるのを抑えるように工夫しているだけで、細かいところはウィーンフィルに任せているようだ。
アンコールにポルカが一曲。CDや正月のニューイヤーコンサートの中継で、電波を通じて聴いてきたが、生の音はやはり違う。ウィーンフィルの暖色系の、ビロードのような音の魅力は格別であり、やはり世界の宝であることを、改めて認識させてくれた。
後半は、チャイコフスキーの「悲愴」
出だしのコントラバスの低音にファゴットがぶつぶつと歌いだす冒頭部分で既に音楽に引き込まれる。柔らかく、それでいて太く深い音色である。ゲルギエフのタクトはウィーンフィルを自在にコントロールする。がっちりとした、起伏に満ちた音楽。全体の構成感をがっちりと固めながら、細部はかなり細かく彫りこんでいく。ウィーンフィルも真剣である。よく、ウィ-ンフィルはコントロールするのが難しい、わがままなオーケストラと言われるが、指揮者に納得すれば実に見事なノリを見せるオーケストラである。ゲルギエフの呼吸がオケにのり移り、深くオーケストラ全体が呼吸している。弱音から、最強音までの自然な盛り上がり。弱音の美しさ、最強音の輝かしさ。
ゲルギエフのチャイコフスキーは、決してセンチメンタルに陥らない。ギリギリのところで、格調の高い美しさと、深いい思索を秘めている。第二楽章のワルツ、第三楽章のマーチとも息をのむような美しさと、激しさに満ちていたが、特に最終楽章の低音の凄さは特筆。この様にこの楽章が、深い祈りにも感じられる思索性に満ち満ちて格調高く演奏された例は聴いたことが無い。
今年は、ハイティンク・ドレスデン、ラトル・ベルリンフィル、ゲルギエフ・ウィーンフィルと、一生にそんなに出会えない超名演に、北陸に居て接することができた大変な年であった。
2004年は外ではイラク戦争、内では台風、地震と暗い記録に残る年となったが、私の人生にとっても、凄いオーケストラを聴いた年として、記憶に深く残る年となりそうだ。 |
|
|
|
|
|
|
|
ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会 第3夜 2004年11月9日 婦中町ふれあい館ホール
Quadrifoglio(《四葉のクローバー》 第一バイオリン坂本久仁雄(オーケストラアンサンブル金沢)、第2バイオリン上保朋子(フリー)、ビオラ石黒靖典(オーケストラアンサンブル金沢)、チェロ大澤明(オーケストラアンサンブル金沢) |
|
オーケストラアンサンブル金沢のメンバーを中心としたQuadrifoglioによるベートーヴェン弦楽四重奏全曲演奏会の第3夜
。第一バイオリン坂本久仁雄(オーケストラアンサンブル金沢)、第2バイオリン上保朋子(フリー)、ビオラ石黒靖典(オーケストラアンサンブル金沢)、チェロ大澤明(オーケストラアンサンブル金沢)
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第1番ヘ長調、第9番ハ長調「ラズモフスキー第3番」、第15番イ短調というプログラム。
前回7月の演奏会に続く第3夜。6回連続公演の丁度真ん中ということになる。
この夜も、充実した演奏会。前回に比較し、総ての楽器が良く鳴っていた。特に第一ヴァイオリンは、積極性が増し、主張もはっきりとし、全体のリード役としてグイグイと引っ張っていく意気込みが感じられた。
大変な大曲が並んでおり、演奏する側は勿論、聴くほうにも集中力を要求する演奏会であったが、終始張り詰めた緊張感に満ちていた。
こうして、ベートーヴェンの初期、中期、後期の弦楽四重奏曲の代表作を一度に聴いてみると、あらためて最後にベートーヴェンか゜到達した世界が、いかにはるかな旅路を辿ってきたかが体験でき、ベ-トーヴェンの音楽の世界の巨大さを改めて知ることとなる。それは、また交響曲の世界とは異なるベートーヴェンの内なる精神の遍歴の跡でもある。
15番の作品では、初期にみられた若々しい挑戦、中期の激しい格闘から、総てを渾然と統一し、さらに形式は単純化し、音楽は純化され、内なる澄み切った世界に到達した祈りのようなものが聴こえてくる。特に15番の第3楽章「病の癒えた者の、神への感謝の祈り」では、第9交響曲の第3楽章と同様の、極限のベートーヴェンの、ある意味では病的ともいえるような複雑な静けさが満ち満ちている。
「ラズモフスキー第3番」の第2楽章のテンポの取り方のやや急ぎすぎと感じたこと、15番の第3楽章の歌わせ方などに、若さゆえのやや性急さを感じたが、全体に正面から大曲にぶつかり、格闘した演奏てあり、熱演であった。回を増すごとに、アンサンブルも良くなり、各奏者の作品に対する傾倒と主張が感じられるようになり、この先の演奏会がが大いに楽しみである。
主催は、岩瀬地区の方々が中心となった実行委員会であるが、こんな大変な演奏会を企画する岩瀬の町とは、不思議な町である。
|
|
|
|
|
|
|
|
ベルリンフィルハーモニー管弦楽団演奏会 2004年11月6日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 サイモン・ラトル |
|
サイモン・ラトル指揮。ハイドン交響曲第86番、ワーグナー楽劇「トリスタンとイゾルデ 前奏曲と愛の死」、ブラームス交響曲第2番というプログラム。
S席4万円という高額の入場料にもかかわらず、補助席まで出る盛況。さすがに、ベルリンフィル・ラトルの人気だ。
それにしても、この1週間の内にラトル・ベルリンフィルとゲルギエフ・ウィーンフィルと立て続けに北陸で公演という(10月にはニューヨークフィルも福井に来ていたそうだ。)、前代未聞の珍事?である。ヨーロッパ、あるいは東京に行って聴くより安いというものの、一人7~8万円の出費は大変である。それでも、なんとか聴こうとする。いじましさである。
さて、ラトルとの4年ぶりの再会。前回はウィーフィルとのベートーヴェンで鮮烈な印象を与えてくれたので、胸をときめかせながら開演を待つ。
ベルリンフィルは生で聴くのは初めて。大学時代にカラヤンと金沢での演奏会があったが、チケットの高額さと、カラヤンというキャラクターに嫌気がさし、聴きに行かなかった思い出がある。
出だしの音から、「え、これがドイツのオケ」という驚きがある。明るく、クリアで、ゴーシャスな音。先日のドレスデンの暗く、重い響きとは根本的に異なる。
しかし、うまい、機能的である。こんなに、オーケストラとしての完成度が高いオケは聴いた経験が無い。個々の奏者の技量の高さは勿論なのだろうが、オケとしての完成度というか、合奏能力の高さというか、凄ささえ感じる巧さである。総ての楽器が贅沢に響き、音が輝いている。これはやはり、功罪は別として、又好き嫌いは別として、カラヤンの残した大きな遺産であるのか。なるほど、録音で聴くフルトヴェングラー時代のベルリンフィルの音とは根本的に異なる。
ラトルのハイドン。小型の編成、そしてコントラバスを左側に配置するという古典的な配置。ティンパニーも小型の、バロックティンパニーのようなものを使用し、ラトルの古楽への傾斜を見る。
リズム感、フレーズの歌わせ方の巧みさ、細部まで息のかかった、躍動するハイドン。ハイドンの音楽のもつ、飛び跳ねるような生き生きとした息吹。音楽が生きているというのは将にこのような演奏であろう。
さて、次のワーグナー。明るい、余りにも明るい。健康的なワーグナー。
「トリスタンとイゾルデ」の絶望的、かつ究極的な性愛よりも、「ロミオとジュリエット」の世界を見るような、純愛の世界。無限旋律の連続による音楽の高まりというより、瞬時の音の輝きと、重なりによる高揚。。ホールが割れんばかりに響く音の饗宴。現代的なワーグナーである。
休憩を挟み、ブラームス。フレーズの細部まで磨きのかかった、構築がしっかりとしたブラームス。しかし、ブラームスはやはり難しい。興奮が欲しい、耽溺が欲しい。巧さだけでは処理しきれないブラームスの難しさ。共感と熱い思いが欲しい。
オケが巧く、指揮者が巧みでも、熱い感動を生まない場合もある。音楽の表現とは難しいものである。
アンコールが無しは、少々寂しい思い。
さて、先日のドレスデンに比較し倍以上の入場料。恐らくギャラが法外なのだろうが、どうしてという疑問がわく。ラトルとハイティンク、ベルリンフィルとドレスデン・シュターツカペレ、この比較に倍以上の音楽的な質の違いがあるとはとても思えない。音楽市場とは私達には理解出来ない面があるようだ。勝手にギャラを吊り上げているのは、私達聴衆にも責任があるのかもしれない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ギドン・クレ-メル&クレメラータ・バルティカ演奏会 2004年10月18日 オーバードホール |
|
ギドン・クレ-メル&クレメラータ・バルティカは金沢石川県立音楽堂にて、2年に1回程度の合宿を行うこととなったそうで、今年はその第一回目。この後世界に演奏旅行に旅立つとのことで、その関係でOEKの定期演奏会以外に石川県立音楽堂と富山市オーバードホールにて演奏会がもたれることとなった。
富山の演奏会は、ベルト「フラトレス」、モーツァルト「協奏交響曲k364」、ショスタコーヴィチ「ヴアイオリンソナタOP134(オーケストラ版)」、「室内交響曲OP110a」というプログラム。当初の予定曲目にベルト「フラトレス」は無かったので追加されたようだ。
非常に凝った、集中力を要するプログラミングでもあり、クレーメル好みのプロともいえよう。
ちなみに金沢は、ブランデンブルグ協奏曲3,6番、シュニトケ合奏協奏曲1.3番というプロ。これも聴きたかった。
さて、ベルト「フラトレス」はOEK定期に続いて2回聴くこととなった。OEK定期の時の演奏に比較すると、最初の部分にやや集中が欠けたようなところがあったが、進むにつれて凝縮されていった。
2回聴いてみると、構成も理解でき、非常に緻密に描かれた音楽であることを再認識する。
繰り返しの中に、高揚する感情と、それを抑えようとする感情、そして点描のように響くパーカッション。最後はヴァイオリンのすすり泣くような繊細なトーンで締めくくられる。テーマは祈りであろうか。最後の部分のヴァイオリンの消え入るようなデリケートさが印象的。
モーツァルト「協奏交響曲」はバルティカのビオラ奏者とクレーメルが競演、管楽器にOEKのメンバーが賛助出演。典雅なモーツァルトの世界が広がるが、バルティカの演奏にやや粗さが見られる。管楽器はホルンを初め好演。クレーメルのヴァイオリンはむ自由闊達、遊び心に満ちた演奏。ビオラも好演だが、クレメルとそっくりな歌い方をするのはやむをえないところだろう。
後半はショスタコーヴイチが2曲。緊張と優しさ、ショスタコーヴイチ独特の深い思索性、それら総てが表現し尽くされた後半の凄演であった。
ヴァイオリンソナタは比較的演奏される機会の少ない作品と思うが、このオーケストラ版ということになると尚更珍しいのではないだろうか。プログラムを見ると編曲はショスタコーヴイチではなく、2名の名前が書かれていた。(Michail Zinman and Andrei Pushkarev)
オケの部分もパーカッションが効果的に使われていたり、ピアノでは表現できないと思われる表現もあり、多彩な表現力を感じる。ヴァイオリン、オーケストラとも熱い感情をみなぎらせ、この作品の核でもある、1、3楽章の心の深淵を覗き込むような集中した静寂、2楽章のショスタコーヴイチ独特のアイロニーのような感情等、表現しつくした名演。バルティカは音色からして、クレメールと一体化している。
室内交響曲は弦楽四重奏曲第8番のオーケストラ版とのことであるが、これも演奏されることは珍しいのではないだろうか。この作品も編曲はA・Stasevichとあり、ショスタコーヴイチではないが、まるでショスタコーヴイチ自身の作曲のように響く。むしろ弦楽四重奏版より、雄弁であり、面白い。全体は5つの部分からなっているが、続けて演奏される。ショスタコーヴイチのエッセンスのような作品で、過去の交響曲の中で使われたものに似た旋律も見え隠れする。
ショスタコーヴィッチの苦悩に満ちた内面の世界が語られる。
ここでは、クレーメルはコンサートマスター席に座り、オケをリードする。指揮者なしの形だが、オケは全く乱れない。
見事な集中力に満ちた演奏。バルティカの弦楽器の美しさが際立つ。パーカッションも大活躍。
アンコールはピアソラ。クレーメルとバルティカの得意曲目だけに、のりまくった演奏。マリンバをヴァイオリンの横に置き、パーカッション奏者との掛け合いも熱く燃え、将にクレーメル節。
改めて、クレーメルの凄さを認識するとともに、バルティカをここまで育て上げてきた情熱に感動した一夜。
外へ出、秋の冷たい外気に、上気とほてりを気持ちよくさます。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢 第169回定期演奏会 2004年10月15日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城宏之
ヴァオリン ギドン・クレ-メル
共演 クレメラータ・バルティカ |
|
ギドン・クレ-メルとクレメラータ・バルティカをゲストに迎えての定期演奏会。指揮は岩城宏之。
前半が、ベルト「フラトレス」、スメラ「弦楽と打楽器のためのシンフォーネー」(以上クレメラータ・バルティカ)池辺晋一郎「悲しみの森」(オーケストラアンサンブル金沢)、後半がベートーヴェン、ヴァイオリン協奏曲(Vn.クレメル、アンサンブル金沢とバルティカの合同演奏)というプログラム。非常に意欲的なプログラムで期待が大。
最初のエストニアの現代作曲家、ベルトとスメラの作品。旧ソ連の作曲家としては、先月のアウエルバッハと今月のこの二人と続けて聴くことになったが、共通するのはその作風の平明さだと感じる。勿論音楽技法は極めて複雑なものであるのだろうが、表現意欲の強さが技法の必然性を伴っているので、聴くものにとって複雑でなく直接的に訴えかけてくるものがある。
ベルト「フラトレス」はクレメルの独奏ヴァイオリンをヴァルティカが伴奏するという構図。同じ楽句が繰り返し奏され、時に高揚し、時に静まる。しみじみとした、簡素な感じさえ与えるが、弦楽器、打楽器の巧妙な使用法など巧みさも感じられる。心やすらぐ音楽となっている。
スメラ「弦楽と打楽器のためのシンフォーネー」はバルティカのみの演奏。最初の打楽器の鋭い一撃にびっくりさせられるが、中間部では弦のさざなみの中でパーカッションの不思議な繰り返しの響きが印象的。後半では民謡を思わせるような分厚い旋律も聴かれる。短い時間の中に、静と動、リズムの面白さ、旋律製の豊かさなど、様々な要素を詰め合わたような作品。解説によるとスメラは50歳でなくなるまで、5曲の交響曲を書いているとのことだが、聴いてみたいものて゛ある。クレメラータ・バルティカの演奏は切れ味鋭く、若々しい。
池辺晋一郎「悲しみの森」。エストニアの2曲に比較し、オーケストラの規模も大きく、管楽器、打楽器を巧みに使い、書法は色彩的で多彩。音楽の基調は重く、レクイエムのような祈りを感じるが、楽器の使い方が多彩なので、出てくる音は華やかでさえある。表現しようとするテーマの重さと、表現される音楽の質の華やかさとの相違に、ややとまどうところがある。
アンサンブル金沢は現代音楽を演奏すると、将に「水を得た魚」のようになり、自信にみちて、安定感がある。
後半のベートーヴェン。クレメルが現代音楽にささげる情熱をベートーヴェンの中に再現したような演奏。実に斬新で生き生きとしたベートーヴェンである。これがベートーヴェンという気負いも無い、またヴァイオリン協奏曲というので、ヴァイオリンの美音をひけらかすこともない。淡々と、しかし嬉々とベートーヴェンの音楽が弾む。ひけらかすことが無いのに、旋律は歌い、ベートーヴェンの凄さが浮かび上がってくる。クレメルの円熟であろうか。
有名なシュニトケのカディンツア。1楽章のカディンツアは、シュニトケらしい熱い荒々しさを感じさせるカディンツァであるが、カディンツァが終わり管弦楽の主部が戻ってくるところで、ああやはりベートーヴェンは凄いと感じてしまう。これも、シュニトケとクレメルの計算なのであろうか。
岩城氏の堂々とした指揮と、アンサンブル金沢の分厚い響きは、尚一層クレメルを引き立てていた。充実したベートーヴェンを久しぶりに聴いたという、充足感に浸った。
アンコールはなんと「ラブミー・テンダー」。誰の編曲か知らないが(クレメルか?)、クレメルのノリが感じられ、ヴィブラホンの響きが印象的なオーケストラとともに、当日をしめくくるにふさわしい印象的なアンコール。
バルティカは今後石川県立音楽堂を合宿の場とし、そこから世界にはばたくとのことで、数年に一度は今日のような演奏会が聞けそうで、楽しみである。 |
|
|
|
|
|
|
|
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団演奏会 2004年9月30日 オーバードホール
指揮 アラン・ギルバード
ピアノ 梯剛之 |
|
アメリカの中堅指揮者アラン・ギルバードによるストックホルムフィルの演奏会。ベルワルド、オペラ「ソリアのエストレルラ」序曲、梯剛之のピアノでモーツァルト、ピアノ協奏曲第23番K.488、ブラームス交響曲第2番というプログラム。
さすがに100年以上の歴史をもつオケだけあって、個々の奏者の力量、オケとしての風格も感じられ、ドイツ・オーストリア圏のオケと比較しても劣らない実力のあるオーケストラと感じた。全体的には、シャープさのあるオケで、音色も硬めである。
この日の出色は何といっても梯剛之のモーツァルト。以前高岡のリサイタルでも同様の感慨をもったが、実に誠実、けれんみの無い、それでいて十分に音は鳴り、よく歌う演奏。盲目というせいもあるのだろうが、鍵盤に指を置くと、身体はほとんど動かさず、腕と指だけが鍵盤を走り回るのであるが、出てくる音楽は実に表情豊か。感情移入が激しいピアニストだと、身体中激しく動かし、表情も激しく変化するタイプが多いが、梯にはそんなところはみじんもない。凄い集中力が、暗いサングラスの奥に潜んでいる。1楽章の第2主題の歌わせ方などに、独特のものを感じたが、総じていじらない、それでいて完全にモーツァルトの悲しい喜悦が浮かび上がってくる。3楽章の、特徴のある何度も繰り返される旋律など、リズム感が豊か、しっかりとした流れの感じられる、弾けるようなモーツァルトて゜あった。ギルバートもしっかりとした伴奏で、ピアノの好演をサポート、オケの木管などの見事さもあって、聴き応えのある演奏であった。
1曲目のベルワルドという作曲家は初めて耳にした。解説書によるとロマン派初期のドイツからスウェーデンに移住した作曲家とのこと。生気に溢れた、旋律も魅力のある序曲であった。堂々とした序曲で、こんな作品が埋もれているということも面白い。
ブラームスの2番。今年はこの作品を聴く機会が多い。先日の岩城宏之-アンサンブル金沢、11月のラトル-ベルリンフィル。岩城宏之-アンサンブル金沢の楽器配置がコントラバスを正面に置いた両翼配置という変わった配置で、岩城氏の解説によるとブラームスが指示した配置とのことであったが、今日の演奏会では近代オケの通常の配置による演奏。
ギルバートの指揮は、丁寧であり、ごまかしがなく、細部まで輪郭をくっきりと浮かび上がらせるようなスタイルの演奏。
しかしながら、それだけて゛は面白くないのがブラームスの難しいところ。旋律を歌わせ、盛り上げようと努力すればするほど、音楽は停滞し、流れず、音だけが盛り上がっても、裏づけが無いものだから、薄っぺらになってしまう。アンサンブル金沢の倍以上の人数のオケなのだが、出てくる音楽はスケール感がずっと小さい。ブラームスには、音楽に一度のめる込むような情熱と、そこを抜け出て過去を振り返るようになるか、どちらかしかないのではないのだろうか?
中途半端では、ブラームスの音楽は語れない気がする。11月、ラトル-ベルリンフィルはどんな演奏を聴かせてくれるのだろうか。
アンコールは全く耳にしたことの無いもの。弦の厚い響きと、金管のコラールを想起させるような分厚い響きが印象的であった。ギルバートは非常に巧みな、器用な指揮者という感じだが、そこから一皮むけ、スケール感と、熱い響きを聴かせてほしい。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第167回定期演奏会 2004年9月21日石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城宏之
ヴァオリン 諏訪内晶子 |
|
今期マイスシリーズの第一回定期。マイスターシリーズも興味ある演奏会があり、PH会員であるのだが、単発的に聴きたくなるものが多い。今回は岩城宏之、ヴァオリン諏訪内晶子による演奏会。ベート゜ヴェン「プロメテウスの創造物」序曲、サンサーンス「序奏とロンドカプリチオーソ」、アウエルバッハ「ヴァイオリン協奏曲第2番」(世界初演)、同じくアウエルバッハの「ヴァイオリンとピアノと室内オーケストラのための組曲」、最後にブラームスの交響曲第2番というプログラム。
注目はアウエルバッハの新作。当初のプログラムに旧作の改編「ヴァイオリンとピアノと室内オーケストラのための組曲」が追加された。出来上がった新作が時間的に短かった為、追加されたとの当日発表であったが、有り難い変更である。
北陸というローカルな地で、世界初演の作品を聴けるということは、かつては考えられないことで、その演奏会にほぼ満員に近い聴衆が聴きにくるということも、特筆すべきことである。岩城宏之とアンサンブル金沢の大変な足跡である。
ベートーヴェン「プロメテウスの創造物」序曲は堅実な演奏で、OEKの安定した実力を示していた。
続くサンサーンス「序奏とロンドカプリチオーソ」。出だしの弦のデリケートでソフトな弱音にぞくっとする。この様な柔らかい音色は最近のOEKの特色であり、円熟を感じさせる。諏訪内晶子のヴァイオリン、全くそつがなく安定した演奏。クリスタルな響きは彼女の特徴であり、崩さずにきちんと弾ききるのは見事である。ただ、その反面音楽が醒めていて、熱さを感じさせてくれない。このような超名曲をただあっさりと弾いてみてくれると、何か物足りない。聴衆を引きずり込むような、熱さが、彼女の演奏には欲しいと感じるのは、無いものねだりであろうか。
当日の注目、アウエルバッハ。ロシア出身でアメリカ在住の新進女性作曲家。文学でもノーベル賞候補となるという多彩な才能の持ち主とのこと。
新作のヴァイオリン協奏曲、非常に魅力的な旋律に溢れた作品。構成も明快であるようで、主題である旋律が変化し高揚し、多彩な楽器に彩られ、最後は祈りにも似た感情で終結する。
主題は日本のわらべ歌をも想起させるような、優しい旋律。女性らしい、優しさを感じる。
使われている楽器はパーカッションを中心に多彩。リズムも複雑であるが、難解さを感じさせない。チェレスタやヴィブラフォンの響きの多用が、独特な効果を生むのは、ショスタコーヴイッタなどの伝統を感じさせる。
「ヴァイオリンとピアノと室内オーケストラのための組曲」はクレメルのために書かれた作品を今回縮小して改編した作品とのこと。四つの部分からなる組曲だが、いずれも魅力的な小品。メロディーの魅力が満ちている作品だが、全体的には暗く、作曲者の現代のアメリカ社会における祈りを聴くような作品と感じた。リズムにも特色があり、ピアソラをも想起させるような部分もある。彼女は、いわゆる前衛とは距離を置いたところに自らを置いているようだが、しかしながら実に個性的。ピアノはアウエルバッハ自信。ヴァイオリン諏訪内晶子も、よく弾きこみ、再創造の意欲に満ちた演奏であった。OEKのバックともども充実した演奏。是非CD化してほしいものである。
最後のブラームス。岩城氏の円熟を聴くような演奏。ブラームスの作品、特に2番、3番は、うっかりすると、とてもつまらない演奏となってしまう。細部にこだわりすぎ、全体の流れをつかみ損ねると、実に散漫となり、ブラームスってこんなにつまらない曲?、ということになりやすい気がする。この日の演奏は、全体のブラームス独特のうねりというか、テーマの連結がきちんと聴くものに伝わり、ブラームスの意図する秘めたる情熱が伝わってくる演奏。テンポはインテンポ。昔の岩城氏であったら、もっとオケを煽り立てるような演奏をしたであろうが、最近は実に落ち着いた演奏。作品の細部をくっきりと描き出すことにより、全体を構成していくようなガッチリした演奏であった。4楽章のエンディングも、決して煽り立てることなく、総ての楽器をきっちりと鳴らすことによって、ブラームスの意図した盛り上がりの効果を作り出していく。OEKは、一部金管の細部のアンサンブルに気になるところがあったが、とても大きな音を作り出し、オケとしてのスケールが段々大きくなっていくことを感じさせてくれた。
演奏会の時間がいつもより長くなり、バス時間の関係で最後まで席に座っていられなかったことが、残念。アンコールはあったのだろうか?
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第166回定期公演 2004年9月4日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城宏之 |
|
今期もいよいよアンサンブル金沢の新定期シリーズが始まった。興味あるラインアップが色々。
フィルハーモニーシリーズ第一回は音楽監督の岩城宏之氏の登場。
コダーイ「ガランタ舞曲」、西村朗「オーボエ協奏曲 迦楼羅<カルラ>」、フィオリロ「2本のオーボエと管弦楽のための協奏交響曲」、ムソルグスキ(ジュリアン・ユー編曲)「展覧会の絵」という、岩城氏らしい凝ったプログラムで、知的興味と興奮を呼ぶプログラミング。
コダーイの「ガランタ舞曲」は、有名な曲である割には聴く機会が少ない作品。勿論生で聴くのは初めて。ハンガリーのジプシー音楽を根底に置いた民族色豊かな音楽。独特のゆったりとした部分と、早い部分の舞曲が交互する。クラリネットが秀演。ジプシー独特の節を朗々と謳いあげる。
アンサンブル金沢のアンサンブルも見事。岩城氏独特の粘っこい節回しによくついていき、フィナーレの激しい盛り上がりまで見事にコントロール。今回の演奏会での特色はパーカッション群の大活躍だが、この曲でも乗りに乗った活躍。思い起こすのは、40年近い前だったか、コンサートホールという通信販売のレコードラベル(CDではなく、LPレコードの時代)で、岩城氏の指揮で(オーケストラはドイツのオーケストラと記憶しているが定かでない)リストのハンガリー狂詩曲集の演奏を愛聴したこと。あの当時と情熱的な音楽作りは変化していないのを、懐かしく思った。
2曲目は西村朗「オーボエ協奏曲 迦楼羅<カルラ>。西村氏らしい、多彩な管弦楽のパレットの中から、オーボエの技巧をこらした旋律が立ち上がる。奈良興福寺の迦楼羅像をモチーフとした作品とのことだが、よく雰囲気を感じさせる作品。 独奏オーボエはトーマス・インデアミューレ氏。大変なテクニックと感性の持ち主。西村氏の作品は、日本人の作曲家に珍しい厚ぼったいものを感じる。繊細さよりも華麗、豪華な管弦楽の響き。アンサンプル金沢が現代音楽を演奏するとき、堂々とした風格さえ感じさせる。現代音楽のスベシャリストオーケストラといってよいだろう。アンサンブル金沢の誇るべき個性である。
フィオリロの「2本のオーボエと管弦楽のための協奏交響曲」。初めて耳にする作曲家と作品。
古典派の時代には、多くの埋もれた作曲家がいたことを改めて感じる。あの悪名高いサリエリの作品も最近復権しているようだし、この時代の作曲家と作品にもっと陽の目があてられても面白いのではないだろうか。オーボエはトーマス・インデアミューレ氏と加納律子氏。古典派らしい端正な旋律と愉悦にあふれた佳品。2本のオーボエのかけあいも見事だが、オーケストラもホルンを初めとして緻密なアンサンブルを聴かせた。アンサンプル金沢の円熟を聴いた。
さて、最後のジュリアン・ユー編曲「展覧会の絵」。何と15名程の演奏。室内楽版とは聴いていたが、実際に舞台で演奏されるのを見て、小さいアンサンブルにびっくりする。バイオリンが二人、ビオラ、チェロ、コントラバスが一人、管楽器も一人づつ(木管は一部持ち代えによる)、パーカッションが二人。編曲者の指示による編成だろうが、何を意図したものだろうか興味がある。
作品は編曲というより、ムソルグスキ-「展覧会の絵」を土台にした変奏曲という趣。編曲者のジュリアン・ユーがおもちゃ箱をひっくり返し、楽しんでいるような感じ。プロムナードはビオラが活躍、一部分は明らかに編曲者の作曲した中国風の旋律が聴こえる。総ての絵の表現が独奏的であるが、特に「サミュエル・ゴールデンベルクとシュミーレ」などは、打楽器とコントラバスを強調、原曲とは全く異なる方法でこの絵の雰囲気を巧みに表出。最後の「キェフの大門」も、管弦楽版の壮大さと異なる音の重なりでの盛り上げを見せていた。特筆はマリンバ、ゴング、ベル、ドラなど多彩な楽器を駆使したパーカッションの活躍。二人でいくつの楽器を持ち替えたのか、ある時はマリンバを前にして後の大太鼓をたたくという忙しさ。しかし、いかにも楽しそうに演奏している女性パーカッション奏者が印象的。これだけ。小さい編成だとメンバーに大変な緊張を強いると思うが、見事な演奏であった。この様な作品を耳にしたのは初めての経験なので、心の中の評価を固めるのに時間がかかりそうなとまどいを感じた。 |
|
|
|
|
|
|
|
ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会 第2夜 2004年7月23日 北日本新聞ホール
Quadrifoglio(《四葉のクローバー》 第一バイオリン坂本久仁雄(オーケストラアンサンブル金沢)、第2バイオリン上保朋子(フリー)、ビオラ石黒靖典(オーケストラアンサンブル金沢)、チェロ大澤明(オーケストラアンサンブル金沢) |
|
オーケストラアンサンブル金沢のメンバーを中心としたQuadrifoglio(《四葉のクローバー》の意味とのこと)による演奏会。第一バイオリン坂本久仁雄(オーケストラアンサンブル金沢)、第2バイオリン上保朋子(フリー)、ビオラ石黒靖典(オーケストラアンサンブル金沢)、チェロ大澤明(オーケストラアンサンブル金沢)
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第2番ト長調、第11番ヘ短調「セリオーソ」、第12番ホ長調というプログラム。
富山でベートーヴェンの弦楽四重奏曲の全曲演奏会が開かれるという快挙にまず拍手を贈りたい。実行委員会の中心メンバーは、富山市岩瀬地区の町おこしに関わっているメンバーで、演奏会の第一夜は岩瀬の旧家で文化財の「森家」で行われたとのこと。残念ながら第一夜は機会を逃し聴くことが出来なかった。
第2夜は、初期、中期、後期各1曲づつ。各時期の特徴がよくくみとれ、ベートーヴェンの巨大さをあらためて教えてくれるプログラミングであった。
演奏は大変な熱のこもったもの。ベートーヴェンに正面からぶつかり、表現意欲の強い演奏となっていた。特に11番「セリオーソ」の第一楽章、アンコールとして演奏されたラズモフスキー3番の最終楽章など、激しさ、集中力、緊迫感に満ち満ちた快演であった。
ベートーヴェンの音楽の持つ革新性、激しい人間的な情熱と苦悩などの要素の表現は、演奏するものの作品への深い洞察と、同一化する表現力が要求され、楽譜をただ忠実に再現するだけでは、聴くものに対しての説得力が弱くなると考えるが、この演奏ではその一番大切な表現意欲が強く感じられ感銘の深い演奏となっていた。
第12番の第2楽章など、後期の入り口にあたるベートーヴェンの深遠な世界の表現に不足する点があったこと、全体のアンサンブルの緻密さにややほころびがあったこと、音程が不安定な部分か散見されたことなど、不満な点もあったが、ともかくこの巨大な世界に体当たりでぶつかり、表現しようとした意欲が、聴くものに感動を与えてくれ、ベートーウ゜ェンの世界の巨大さを示してくれたといえる。
オーケストラアンサンブル金沢があることで、北陸でもこのように意欲的な音楽会が開かれることは、聴くものにとって嬉しいことであり、オーケストラアンサンブル金沢の存在意義が大きいことを改めて感じさせてくれた。
今後の演奏会に大いに期待したい。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第163回定期公演 2004年6月28日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 オリヴァー・ナッセン |
|
マイスターシリーズの定期演奏会。イギリスの世界的作曲家、オリヴァー・ナッセンを指揮者に迎えての、自作のヴァイオリン協奏曲を中心としたプログラム。
ブリティンの「イギリス民謡による組曲“過ぎ去りしとき”」、ナッセンのヴァイオリン協奏曲、武満徹の「ハウ・スロー・ザ・ウィンド」、ラベル「マメール・ロア」という凝ったプログラム。
知的な興奮を呼ぶ一夜であった。
マメール・ロアを除いて、総て初めて聴く作品。
ブリティンは、イギリスの郷愁を感じさせる作品。ヴァグパイプを想起させる木管の扱い方、小太鼓、ドラ等の打楽器の効果的な使い方などで、古きイギリスを想起させる。ナッセンの指揮は、油彩を想起させるような、厚く、しかし緻密である。アンサンブル金沢も管楽器、打楽器を中心として、この作品の雰囲気を好く表出していた。
ナッセンのヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリンはイギリスの新鋭、クリオ・グリード。
全体の構成は古典的な連続して演奏される3楽章形式で書かれているが、内容は多彩。
作品全体は、かなり、構成として明確な柱をもっており、その柱を中心としてヴァイオリンが、多彩な管弦楽に彩られて、歌う。特に印象的なのは、管弦楽が独特の「ボーン」というような点描を描き出すこと。ナッセンの唄の根源には、この縦の和音の不思議な積み重ねがある様だ。
多彩な打楽器の扱い方、弦楽器の厚い響きなど管弦楽の扱いも興味深い。
ヴァイオリンは出だしこそ、やや不安定に聴こえたが、進むにつれてこの難曲を、自分のものとして弾きこみ、聴衆に表現しようとする意欲がよく聴き取れた。
ナッセンの音楽は、自作に流れるポリシーと、指揮者として他の作品を再現するポリシーと、同一のものが流れている気がする。これは当然のことといえばそうだが、かなり自分自身にこだわりと、表現意欲の強さがないと、出来ないことではないだろうか?
それは、休憩後の武満とラベルの作品によく表れていた。
武満の演奏については、プレトークで作曲家の猿谷氏が、岩城宏之氏との演奏の比較論を語っておられて、興味深く聴いたが、なるほどと思わせる演奏てあった。
従来の武満作品の印象としては、やはり極めて繊細なもので、管弦楽法は多彩であっても、色調はむしろ淡彩、その絹のようなデリケートさが、日本の能や水墨画の世界を、連想させると感じてきた。ナッセンの演奏では、緻密ではあるが、むしろもっと色彩的。音楽が線で流れるのでなく、点で描き出されるような響きを感じた。言って見れば、竹林の中を流れる風でなく、ヒースの荒野を吹き抜けるような風。しかも、それも油彩の世界を見るようであった。
ラベルの「マ・メール・ロア」も、ナッセン独特の世界。粋で、淡い水彩画のラヘルでなく、もっと厚く描かれた油彩のラベル。細かい部分まで、神経が行き届いた、緻密な演奏ではあるが、全体に生れる印象は、かなり厚ぼったく、大きい。
作品が、指揮者によって変化するのは、古典派からロマン派にかけての作品では、当然のことであり、それが再現芸術の面白いところであるのだが、現代の作品でもこのようにトーンがはっきりしてくることを、知らしめてくれた興味深い演奏会であった。
アンサンブル金沢は、現代作品を日常的に取り上げているだけあって、実に巧みな演奏。現代作品の紹介はアンサンプ゛ル金沢の大きなセールスポイントでもある。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢 第162回定期演奏会 2004年6月17日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮とピアノ フィリップ・アントルモン |
|
先月の定期を都合で欠席したので、OEKをヨーロッパ公演後初めて聴く演奏会となる。音楽堂・山腰館長によると、ヨーロッパ公演は大成功とのこと、会員としても嬉しい限りである。
今月の定期は、懐かしのピアニスト、フィリップ・アントルモンの弾きぶりによる演奏会。アントルモンは、若き日、LPレコードで、その洒落て洗練されたピアノを聴かせてくれた名ピアニスト。30年ぶりの再会の様な気がした。
プログラムはモーツアルトの交響曲題36番「リンツ」、ピアノ独奏でドヴュッシーの「ピアノのために」、後半がベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」という多彩なもの。
最初の「リンツ」の出だしの音を聴いた時、OEKの音が変わったことにびっくりした。実に大きく開放的で、スケール感を感じる。以前もアンサンブルは緻密であったが、なんとなくバランスが悪かったり、こせこせしたところがある感じがあったりで、少々欲求不満を感じたこともあった。しかるに、今回の演奏では、実に各パートとも堂々と弾いており、強奏と弱音のバランスもよく、特に管楽器が気持ちよく吹いており、音色が豊かでハーモニーが豊かになった感がした。これは、明らかにヨーロツパ公演で得た自信なのであろう。大きな舞台で演奏することが、オケをこんなに変化させることにびっくりする。この水準をずっと維持して欲しいものである。
さて、アントルモンの指揮、実にてらいのない典雅なモーツァルト。第一楽章はやや遅めのテンポを保ちながら、各主題を高貴に歌わせる。特筆すべきは管楽器の音色、オーボエも、フルートもホルンもトランペットも、実に滑らかで輝かしい音色、明らかにアントルモンの要求であろうが、フランスの管楽器の音色を聴くような雰囲気。第2楽章のアダージョも感傷的にならず、格調高いきちんとした演奏。第3楽章メヌエットは古典的な典雅な香りを感じさせ、最終楽章も堂々たるフィナーレ。全体的に各パートのバランスがよく、各パートが明瞭に聴こえながらきちんとした全体の調和を保っている。アントルモンの指揮者としての天性を感じさせてくれた。
アントルモンの独奏によるドヴュッシー「ピアノのために」。おはこなのであろう、磨きぬかれた音色とテクニック、なによりこの曲をいつくしみ弾きこんでいる自信。プレトークで「この曲を弾く怖さは、年齢が分かってしまう事」と冗談ぽく語っていたが、なるほどこの年齢でなければ表現できないであろう、円熟した、しかしながら、とても新鮮なドヴュッシーであった。。ドヴュッシーの印象派的な手法を古典的な形式で再現したような、難しい作品であると思えるが、古典的典雅さを保ちながら、ドヴュッシー独特の転がるような色彩的な音色が印象的。
後半は、ベートーヴェンの「皇帝」の弾きぶり。この大曲を弾きぶりするというのは、聴いたことがない。果たして細部のピアノとオケのやりとりなどうまくいくのだろうかという不安があったが、アントルモンは自分のオケの如く自在にオケをあやつり、とても弾きぶりとは思えない好演であった。OEKもアントルモンの要求に良く応え、ピアノをしっかりとサポートしていた。
全体の印象としては、やはり古典的端正さをしっかりと感じさせる演奏。アントルモンのピアノは堂々としてはいるが、決してけれんみを感じさせない誠実で暖かい印象。この人の音楽の特徴は、フランスのピアニストにありがちな感傷過多なところが無く、音色はきらびやかでありながら、暖かい人柄を感じさせる演奏である。これも、年輪であろうか。
アンコールのショパン2曲も同様の印象の好演であった。
最後に苦言を一言。最初の「リンツ」の1楽章が終わった際、後の係員が場外の係員に連絡しようとしたのだろうか、携帯マイクに向かって「終わりました」との声が聞こえた。楽章間の合間は終了ではなく、音楽は次の楽章に向かって連続しているのである。楽章間に遅れた観客を入れようという配慮は理解できるが、方法を考慮すべきである。多くの音楽の流れを大切にしている聴衆のことを考慮しなければいけない。これは、ここのホールだけでなく、他のホールでも色々な面で見られることだが、音楽を大切にしてほしいと思う。
思い出すのは、40年ほど前東京オリンピックの記念演奏会のN響演奏会で、岩城宏之氏が確か序曲レオノーレ第3番の途中で、観客席の中から子供の泣き声が聴こえたとき、演奏を中断して引っ込んでしまったことである。そして、暫くして、最初から演奏をやり直すとのアナウンスがあり、再び最初から演奏しなおした。音楽における緊張感を持続させるためには当然のことであるが、最近このような緊張感に欠けることが散見する。決して堅苦しく音楽を聴けということではないが、、聴衆は、それこそ演奏する側との一期一会のような感動的な出会いを期待して音楽会に足を運んでいることを忘れてほしくない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ハンナ・チャン 無伴奏チェロリサイタル 2004年6月3日 入善コスモホール |
|
珍しく、尚且つ大変な冒険である無伴奏のみの作品によるプロク゜ラム。
リゲティ「無伴奏チェロソナタ」、J・Sバッハ「無伴奏チェロ組曲第5番」、B・ブリティン「無伴奏チェロ組曲第1番」
ハンナ・チャンの艶やかで、伸びやかで逞しいチェロに圧倒された一夜。
非常に個性的で、演奏する側は勿論、聴くほうにとっても、緊張を強いられる演奏会であるが、チャンの強靭ではあるが、荒っぽくなく、艶やかで伸びやかなチェロに酔いしれた。
最初のリゲティ、初期の作品とのことであるが、イメージにあるリゲティの前衛的な激しさとは異なる、叙情的かつ民族的な一面を見せる小品。最初の一音が出た時から、尋常でない音の深さに心震える。
バッハは、チェロ奏者にとってバイブルのような作品であろうが、チャンは臆することなく、バッハに対する自らの心情の告白とも言えるような解釈を見せた。いわゆる、ゴシックの塔のごとく聳え立つバッハを演奏するのでなく、まるでこの作品にこめられている意味を自ら確かめていくような演奏。21歳のチャンが、この時点で解釈しえるバッハ像を、背伸びすることなく表現しきっていた。
ブリティンは、更に自由奔放な演奏。技術的にも大変な難曲であろうが、歌いかつ叫ぶチェロは爽快ですらある。
チェロのリサイタルも色々聴いてきたが、この楽器のもつ表現の世界がこんなにも幅広いものという体験は初めて。その裏にある技術的な確かさは驚異的なものであるが、技術のみにおぼれず、今その曲が生れてきたような新鮮な解釈を見せる音楽性にチャンの底知れない将来性を感じる。
今未完成なのではなく、今の時点の自分の解釈を100%聴衆に提示しえるところに凄さを感じる。
明日は又違う解釈を聞かせてくれるという期待を大いに抱かせてくれる。
アンコールはプロコフィエフとバッハ。これも、のりに乗った演奏。
地味なプログラムにもかかわらず、熱狂した聴衆の激しい拍手が印象的。 |
|
|
|
|
|
|
|
ドレスデン・シュターツカペレ 2004年5月18日 オーバードホール
指揮 ベルナルド・ハイティンク |
|
一昨日の金沢公演に引き続き、富山での公演。連続して、異なるプログラムで、ハイティンク・ドレスデンを聴ける、こんな機会は北陸ではまずない。今年は北陸も名オーケストララッシュ。秋には富山でゲルギエフ・ウィーンフィル、金沢で゜ラトル・ベルリンフィルと続く。
さて、待望のブルックナー8番。いつか、この作品を富山で聴きたいと、かなわぬ望みを抱いてきたが(恐らく富山初演であろう)、この名コンビで聴くことの出来る幸せに、心ときめかせてホールに向かう。
第一楽章の原始霧の出だしの弦のささやきから、その音の豊かさに心震える。pppからfffにいたるデクレッシェンド、その逆のディミヌエンドが、これほど自然に奏でられる例を聴いたことが無い。そして、ブルックナーの特徴の全休止が、なるほど次の部分への移行のための必然性があるのだということを納得させられる。
最高潮の強奏の重厚な輝かしさ、そこに至るまでの各パートの自然な盛り上がり方、ブルックナーはこうであったのかと、眼を開かせる。
そして、弦の中から木管が浮かび上がる様、ブルックナーはこんなに豊かな旋律を作っていたのだと思い知らされる。
弦から金管、打楽器にいたるまで総てモノトーンの音色をもっているため、音楽のマスの中での個々のパートの旋律が違和感なく響いてくる。ハーモニーと、各独奏の調和が絶品である。
そして、最強奏でも、音はにごらず濁らず輝かしく響く。
第2楽章のスケルツォの中間部の木管のソロなど、まるで見たことのないドイツの森のささやきを見るかのごとく、またドイツの民謡がどからかきこえてくるような叙情性をたたえている。
第3楽章の神々しい荘厳な静けさと高揚を経て第4楽章にいいたる。心躍る第4楽章である。コーダもかつてCDなとできいた演奏では、急ぎすぎて性急に終わる感の演奏が多く、納得がいかなかったが、今日の演奏ではエンディングにふさわしいテンポの悠揚さと、確固たる決然とした響きとリズムで、この大曲がしめくくられた。1時間20分の大曲であるが、緩むことなく、緊張感の糸が切れることなく、あつというまの1時間20分であった。そして各主題の旋律の意味をこんなに明確に示し、ブルックナーの音楽とは、こんなに心ときめくものと思わせてくれたハイティンクの力量に、さすがに凄い指揮者と脱帽する。
マタチッチ、チェリビダッケ、ヴァント、朝比奈と、この作品の名演を日本に残していったが、今回のハイテインクも後々語り継がれる名演と信ずる。そして、ハイティンクの凄さは、その演奏のムラの無さでなかろうか。巨匠タイプの指揮者にありがちな名演と駄演?の落差の少ない指揮者であろうと思う。非常に緻密に計算された演奏でありながら、そうは感じさせず、今生れたかのごとくの新鮮な感動をもたらす。
約40年前に、コンセルトヘボウを率いてヨッフムとともに初来日した折の若きハイティンクの演奏会を聞きに行った時の記憶、ドビッシーの「海」の最初の低音の、地の底から沸きあがるような音にびっくりした思い出を持ち続けていたが、あれから40年近くたち、ハイティンクの名演奏に再び出会えた感慨もひとしおであった。
金沢でのモーツアルト、R・シュトラウス、ワーグナー、そして富山でのブルックナーと、歴史的な名演奏に立ちあえた幸福を感じた。
残念ながら空席が散見されたが、拍手とブラボーの嵐、オーケストラが引っ込んだ後も、スタンディンク・オベーションを続ける聴衆の喝采にハイティンクは再三答えるため舞台に登場、舞台の照明が暗くなっても続く拍手に再度出てきたハイティンクは、、これで終わりですよというべく、最後に指揮台のスコアを閉じ頭上にかかげ、深々と礼をし、去っていった。
ブルックナーの大曲の後に、アンコールは無理と諦めるし、それが当然だろうが、あの金沢のマイスタージンガーをもう一度聴きたかったと、少々後ろ髪も引かれる気持ち。 |
|
|
|
|
|
|
|
ドレスデン・シュターツカペレ 2004年5月16日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ベルナルド・ハイティンク |
|
モーツアルト 交響曲第41番「ジュピター」
R・シュトラウス交響詩「英雄の生涯」
ドイツのオーケストラの真髄を聴かせてくれた、大名演。
この日の演奏を聴き、ベルリンフィルあたりのドイツのオケが失った、分厚く、底力のある響きが、本来ドイツのオケが持っている個性であることを認識させてくれた。そして、他の大半のオケが、巧くはあるが、いかにオケとしての個性を失ってきているかを痛感させられた演奏会。
更に、名指揮者と名オーケストラが出会ったときは凄い演奏を繰り広げることを目の当たりにした、生涯の記憶に残る演奏会であった。
演奏会の始まる前に、舞台上でコントラバス奏者が一人チューニングをしていたが、その音を聴き、びっくりしてしまった。深い、底力のある地の底からわきあがるような音。こんな、凄い音は記憶に無い。
さて、「ジュピター交響曲」、ハイティンクは全体的にテンポを落としているが、それでいて、緊張感にみちみちている。古典的な形式美を崩さない、堂々たる演奏。オーケストラの各パートが゜くっきりと浮かび上がり、ごまかしの無い演奏が、モーツアルトの音の綾を浮かび上がらす。ティンパニーを金管の隣に座らせた珍しい配置だが、テインパニが突出せず、オーケストラとしての音の統一感がティンパニも含めて出来上がっている。オケの音としては、重く暗いため、ウィーンフィルあたりのモーツァルトとは趣を異にしている。ウィーンフィルの明るく、官能的な響きのモーツァルトと、どちらが本当のモーツァルトかと考えてしまう。最終楽章の大フーガも、見事な音の重なりを響かせる。一人一人の奏者の力量の高さと、ドレスデ゛ンとしての音の色彩の統一感が、堅固なフーガの世界を築いていく。
「英雄の生涯」は、今まで印象の中にあるR・シュトラウスの音が違った音で生れてきた。R・シュトラウスの音は、豪華絢爛、官能的という印象できたが、この日の演奏は重く暗い。勿論、R・シュトラウスの巧みな管弦楽法はそのままであるのだが、出で来る音は、実に重い。バイオリンの、従来は甘くせつないと感じてきた独奏部分も、美しくはあるが、甘くない。R・シュトラウスが思い描いてきたオーケストラの音がこのようなものであったなら、今まではちょっと違うR・シュトラウスを聴いてきたのかも知れない。
「メタモルフォーゼン」や「最後の四つの歌」はR・シュトラウスが最後に到達した内面の世界であり、それまでのR・シュトラウスとは異なる世界という通説があるが、この演奏をきくとそうではなく、必然的に到達した世界であることが理解できる。
それにしても、分厚い音の響きであった。最後の静かに消えていく部分も、金管の分厚い響きが荘厳に曲を終結に導いていく。消え入るのではなく、堂々と人生を終えていくのである。
アンコールはワーグナー「ニュールンベルグのマイスタージンガー」第一幕への前奏曲。昔、ベームがウィーンフィルとの演奏会で、この曲をアンコールにとりあげびっくりした記憶があるが、最近の演奏会でこのような大曲をアンコールに聴いた記憶が無い。これが又凄い演奏。うねうねと流れる音の世界が自然に高潮していき、最後は大爆発する。ワーグナーの壮大な音の世界が、重厚なオーケストラで繰り広げられる。テンポはいわゆるイン・テンポ、遅く動かさない。もともと、演奏効果の高い曲ではあるが、このように遅くうねりをもって演奏されたのは、初めての体験。CDでの、クナッパーツブッシュの演奏を思い起こす。しかし、クナッパーツブッシュはもっと即興的、ハイティンクは確信犯的に演奏するのだから恐ろしい。
ブラボーが飛び交い、オーケストラが引っ込んだ後も。指揮者を呼び出す金沢では珍しい光景が繰り広げられた。
この後、18日に富山で「ブルックナー交響曲8番」が演奏される。
富山でブルックナー8番は記憶に無い。ブルックナーの演奏自体が珍しいが、大変な期待のもてる演奏会である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ファジル・サイ ピアノリサイタル 2004年4月17日 入善コスモホール |
|
スカルラッテイのソナタが3曲、モーツアルトのK331「トルコマーチ付」ソナタ、バッハ-ブゾーニ編曲「シャコンヌ」、ベートーヴェンの「熱情ソナタ」というプログラミング。残念だったのは当初予定のベートーヴェン29番のソナタ「ハンマークラヴィア」が「熱情ソナタ」に変更となったこと。滅多に聴くことの出来ない「ハンマークラヴィア」をサイがどのように料理するか楽しみだっただけに、残念ではある。理由は推測でしかないが、大曲を精神的に緊張を持続して演奏することに若干の不安があったのかもしれない。
当夜の演奏会、刺激的で、心躍るものであった。
サイのピアノは本能そのままという感じ。よく、グールドあたりと比較されるが、全く異なる。哲学的でなく、本能的、感覚的、ピアノの音が生々しく迫ってくる。
スカルラッティからして、既にサイ節が聴こえる、スカルラッテイ特有のころころ回転する楽想が、サイによって自由闊達に響く。
次のモーツァルトの「トルコマーチ付」ソナタに至っては、全く異型の世界。第一楽章の変奏が、サイの感覚により、自由自在に変形する。テンポ゛のとり方も、一定でなく動き回る。それでいて、音楽は真実の響きをもって訴えかけてくる。一般的にいわれるモーツァルトの世界とは異なるが、心酔わせる不思議な世界を持っている。第二楽章のメヌエットも、メヌエットらしからぬ官能的な世界。第三楽章のトルコマーチにいたっては、アクセントとリズムの極端な強調、トルコの軍楽隊の世界である。
バッハ-ブゾーニ編曲「シャコンヌ」では、凄いタッチでバッハの巨大な音響世界を築いていく。そしてゆっくりした部分にはブルースの息吹が感じられる。
ベートーヴェンの「熱情ソナタ」。サイのベートーヴェンへのオマージュが激しく感じられる。
これもテンポは自在、第一楽章のコーダの部分では思いっきりテンポをおとし、聴衆を引き込む。第2楽章は早めのテンポではあるが、やはり微妙な息遣いが聴かれる。そしてフィナーレ、激情の渦が駆け巡る。
モーツァルトもベートーヴェンも、いわゆる名演奏とは離れたものかもしれないが、音楽の表現は多種多様であることを確認させられ、演奏者の真情が表れた演奏はどんな形の演奏であれ、聴衆の心をうつことも確認させられた。音楽を化石の世界に埋めてはいけないということを、サイは教えてくれている。
アンコールは5曲、モーツァルト「きらきら星変奏曲」、サイ編曲の「トルコマーチ」、パガーニーニ・ジャズ、サイ自身の作品が2曲。どの演奏もピアノにサイの魂が乗りうつったような激演であった。残念ながら少ない聴衆であったが、サイは全力をステージにかけてくれた。
やはり、稀宇の演奏家である。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第159回定期公演 2004年4月16日石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 岩城宏之
チェロ ルドヴィード・カンタ |
|
ヨーロッパ公演を直前に控えての記念演奏会で、プログラムもヨーロッパ公演の一部をそのまま演奏。プロコフィエフの古典交響曲、ハイドンのチェロ協奏曲、ベートーヴェンの交響曲第7番。
指揮は岩城宏之氏。今回のヨーロッパ公演は、音楽の中心地であるドイツ、オーストリア、ハンガリー、チェコ、フランス、ベルギー等を約3週間かけての強行スケジュール。特にウィーン、ベルリン、ブタペスト、プラーハ等の音楽都市での公演があり、OEKの評価がどう出るか楽しみである。
この日の演奏会では、プロコフィエフの古典交響曲が秀逸。キリットした古典の表情と、プロコフィエフ独特の諧謔、皮肉などを的確に描き出し、アンサンブルも緻密、小オーケストラならではの醍醐味を味あわせてくれた。金管、木管共巧みなテクニックと音楽性。岩城氏の指揮もこの曲の面白さを見事に引き出していた。
これに比較し、ハイドンとベートーヴェンはやや冗長。
ハイドンはチェロのカンタ氏が印象が弱く、又やや音程が不安定。チェロにとってこの作品がいかに難曲であるか、逆にわからせてくれたような演奏。オーケストラはやや遅めのテンポで、しみじみと歌い、チェロを好サポートしていた。
ベートーヴェンの7番。昨晩N響定期のライブ中継で、スクロバチェフスキー氏が激演していた印象が強烈で、やや色あせて聴こえてしまった。岩城氏の指揮は、がっちりとまとめた隙の無い演奏ではあったが、この曲独特の熱い推進力にはやや欠けていた。又、楽譜通りではあるのだろうが、金管の強奏が、全体の旋律性を損なっている箇所が散見した。これは古楽器演奏の影響であるのだろうか。
アンコールはハイドンとグルック。
特にハイドンのセレナーデを、弦のピアニシモで、ささやくように演奏していたのが印象的。緊張感に満ちた演奏で、OEKの弦もはっとする美しさ。
OEKのヨーロッパ公演での健闘を祈りたい。 |
|
|
|
|
|
|
|
ピヒラーのはいどん オーケストラアンサンブル金沢 ウェルカム・スプリング・コンサート 2004年3月29日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ギュンター・ピヒラー |
|
の指揮により、ハイドンの後期ザロモンセットから交響曲第101番「時計」、協奏交響曲、交響曲第102番「軍隊」というプログラム。
OEKの昨年からの一連のハイドンシリーズの最後の演奏会。
しつかりとした構成と明快なアンサンブルのハイドンを聴かせてくれた。
先月の岩城宏之氏のどこか土臭くて庶民的なハイドンに比べ、典雅でしっかりとした壮麗なハイドン。
OEKのアンサンブルも緻密で気持ちよい疾走感があった。
ヴァイオリン、チャロ、オーボエ、ファゴットのための協奏交響曲。生で聴くのが珍しい曲目であろうが、アンサンブル金沢の各首席奏者を独奏者として、確かなアンサンブルを聴かせてくれた。
「軍隊交響曲」の金管、打楽器も思い切り鳴らしていたが、破綻も無く気持ちよく響いていた。
アンコールにベートーヴェンの「トルコ行進曲」。軍隊交響曲との関連性を感じさせ面白い選曲であった。
春の一夜、心地よい音楽の夕べであった。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第158回定期演奏会 2004年3月25日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ギュンター・ピヒラー
チェロ 石坂団十郎 |
|
ギュンター・ピヒラー指揮、チェロに石坂団十郎を迎えての定期。
モーツァルト歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲、シューマンのチェロ協奏曲、ベートーヴェンの交響曲第8番というプログラム。
昨年11月の定期の際のピヒラーの演奏の印象と全く異なった演奏。プログラミングにもよるのであろうが、(前回はメーンがペートーヴェンの6番、今回は8番)、感興がその時によって異なるのだろうか?
初めの「ドン・ジョバンニ」序曲の出だしから緊張感に溢れたトーンが響く。このオペラの異様な暗さを音に描き出した見事な出だし。グイグイと推進力をもって音楽は進み、 デモーニッシュな世界を作り出す。前回の「フィガロの結婚」序曲も雰囲気のある佳演だったが、この人は序曲にとても素晴らしい世界を描き出す。音楽の中にドラマを作り上げるのが見事な指揮者だ。
シューマンのチェロ協奏曲の石坂団十郎(本名なのだろうか?)は、難しいシューマンのチェロ協奏曲を熱演。鬱々たる情熱の塊のようなこの作品を、極めて抑制的に表現。響き自体が内に向かい、沈潜していこうとするような響きなので、この作品の雰囲気に非常に合っている。欲をいえば、響きがもう少し熱くなっても良いとも思えたが。ピヒラーの伴奏はむしろ熱い情熱をたぎらせており、チャロとの対比が面白い。
ベートーヴェンの8番、メーンデイッシュとしては珍しい選曲だが、熱い推進力に満ちた熱演。
この小交響曲が、ベートーヴェンの赤裸々な自己表現であり、激しい起伏をもった大曲であることを認識させてくれた。
やや早めのテンポで、ぐいぐいとオーケストラをドライブしていく。ベートーヴェン独特のたたみかけるような旋律を造形感をそこなうことなく描き出している。前回の6番の伝統的とは思えるがやや退屈してしまうような演奏とは様変わりであり、なるほどベルク四重奏団のリーダーと納得させられた演奏であった。ただ、前回の時もそうであったが、金管の突出した強調が、やや全体のアンサンブルの中で違和感を与えていた。ピヒラーの鋭さを求める為の意図と思えるがバランスが悪い。
前回の時はアドレナリンの分泌が悪かったのだろうか?と思わせる熱演であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
竹澤恭子ヴァイオリンリサイタル 2004年3月14日 入善コスモホール |
|
ヴァイオリンの竹澤恭子に、ギターの山下和仁、ピアノの江口玲を伴奏とした豪華なトリオコンサート。
竹澤の益々円熟し、のりにのったヴァイオリンである。ヴァイオリンを小柄の身体にたたきつけるような迫力のある演奏。
プログラミングは小品集であるが、かなり凝った中身の濃い小品集。
前半が、山下和仁のギター伴奏で、パガニーニ「チェントーネ・ディ・ソナタ1番」「カンタービレ」
ファリャ「7つのスペイン民謡」より、藤家渓子「青丹よし」「赤と黒」、後半が江口玲のピアノ伴奏で、ドヴォルザーク/クライスラー編曲「スラブ幻想曲」、スーク「愛の歌」、バルトーク「ルーマニア民族舞曲」、ワーグナー「ロマンツェ」、サラサーテ「チゴイネルワイゼン」。
全体に民族色を意識したプログラミングか。
前半は山下和仁のギターが出色。ヴァイオリンとギターが巧みにマッチング。ファリャなど、いかにもうら悲しい雰囲気を醸し出していた。竹澤のヴァイオリンは、太い意志を根底に感じさせる、まるで義太夫の太三味線のような野太い響き。藤家という作曲家は初めてだが、日本的な響きを感じさせながら、叙情性とドラマを感じさせる作品。「青丹よし」初演なのか?もう少し、作曲者の事など、プログラムに記載してほしかった。
後半は、スラブ系の小品が中心だったが、朗々と歌うヴァイオリンが圧倒的。最後の「チゴイネルワイゼン」の出だしなど、これまで聴いた事のないような、緊張感と底力に満ちた響きが、サラサーテの深い憂いを抉り出していて、この曲が単に技巧をこらしたエキゾチックな小品ではなく、深い内容をもった作品であることを感じさせてくれた。
総ての曲に竹澤の作品に対する深い共感と解釈がよく聴衆に伝わってくる真の意味でのプロの演奏家という感想。ピアノの江口は良くまとまった伴奏だが、竹澤の個性に隠れてしまったような感じ。アンコールのクライスラー「愛の悲しみ」、「タイスの瞑想曲」も小品名曲の枠を超えた名演。残念ながら少ない聴衆だったが、最後は熱狂的な拍手であった。
宝くじの文化公演ということで、2000円という低料金でのコンサート。企業メセナはこのようにあるべきである。 |
|
|
|
|
|
|
|
錦織健プロジュース・オペラ ロッシーニ「セビリアの理髪師」 2004年3月5日 オーバードホール
フィガロ:多田康芳、ロジーナ:森麻季、アルマヴィーバ伯爵:錦織健、バルトロ:志村文彦、ドン・バジリオ:三浦克次
オーケストラ:オペラ管弦楽団
指揮:現田茂夫 |
|
錦織健が、気軽にもっと多くの人にオペラの楽しさを広めたいと、オペラの大衆的普及をもくろみプロジュースした第二弾。第一弾はモーツァルトの「コシファントゥッテ」とのこと。
ソリストは総て日本人の実力者揃い。監督・指揮は現田茂夫。
全国で巡演するため、小ぶりな舞台装置。しかし、装置・美術とも良く出来ていて、ロッシーニの雰囲気を良く出していた。
という歌手陣。オーケストラはオペラ管弦楽団(なじみの無いオケだが、大阪音大のオペラハウスの専属管弦楽団とのこと)
全体的にまとまった良い舞台。錦織健が、さすがの美声と演技力、森麻季の厚みのあるコロラトゥーラ、ドン・゜バジリオの三浦克次のバスのとぼけた味など堪能させてくれた。
さすがに森麻季は巧い。ロッシーニの難しい転がすような装飾音を難なくこなし、役柄をくっきりと描き出す。フィガロがやや弱かったのが残念。
指揮の現田茂夫はロッシーニの音楽を端正に仕上げていたが、ロッシーニ独特のふつふつと沸きあがるような愉悦感に乏しい。オケの実力もあるのだろうが、例のクレッシェンドなど弱すぎる。
各歌手は熱演であり、美術・装置も優れており、まとまった舞台だったが、歌劇で肝心の伴奏オケの部分の弱さが、全体を薄味にしてしまっているのが残念。
海外オペラ座の引っ越し公演が多くなってきているが、このように小ぶりで安価で鑑賞できるオペラをもっと広めてほしい。ただ、S席12000円というのは、大衆向けオペラとして安いといえるのかという問題はある。オペラ公演は確かに大変な経費のかかることだとは思うが、難しいところである。公的補助が望めない現況では、企業メセナなどの努力も必要とされるのでなかろうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小川典子 ピアノの世界 2004年3月3日 石川県立音楽堂 邦楽ホール |
|
前半にムソルグスキー「展覧会の絵」、後半にOEKメンバーとのブラームスのピアノ五重奏曲という、ユニークなプログラム。邦楽ホールが満員で、補助席も出た程の盛況。
小川典子は優れた技巧をもつピアニストとしての印象があり、ベートーヴェン・リスト編曲の「第9交響曲」ピアノ版のCDなど面白い活動をしている。
この日はまず「展覧会の絵」に期待。さすがに、確かな技巧である。遅めのテンポの踏みしめるような「プロムナード」に始まり(プロムナードは終始遅めのテンポで、沈潜した雰囲気をただよわせていた。)各曲の性格をくっきりと浮かび上がらせていたのはさすが。特に、激しい部分の打鍵の確かさと強靭さは格別、ペタルの使い方も独特な響きをもたらしていた。ただ、メンタルな部分で、少々もの足りなさを感じる。特に「古城」のしみじみとした部分など、あっさりとながしており、味わいに乏しい。強弱のニュアンスが単調なため、全体に平板に聴こえてしまう。アンコールのドヴュッシー「亜麻色の乙女」でも、デリケートで繊細な音作りでありながら、やや色彩感にとぼしい。音楽のドラマ作りに工夫が欲しいと感じる。
ブラームスのピアノ五重奏曲。第一楽章の出だしから、少々弦楽器パートが不安定でもう一つ音楽に乗り切れないところがあったが、曲が進むにつれどんどん良くなってきた。プラームス独特の秘めたる情熱が熱く燃え、またさめていく。ピアノは激しく歌い、弦はしみじみとうたう。OEKメンバーの各パートがブラームス独特の厚みのあるアンサンブルを確かに表現していく。ブラームスの室内楽の醍醐味を十分に味あわせてくれた佳演。
※第9交響曲の編曲はリスト版でなく、ワーグナー版でした。2004年3月26日訂正。 |
|
|
|
|
|
|
|
ハイドン交響曲集 びっくり大編成「はいどん」 2004年2月29日 石川県立音楽堂コンサートホール
オーケストラアンサンブル金沢、地元特別編成学生オーケストラ(金沢大、金沢工大、北陸学院各オーケストラ)
指揮 岩城宏之 |
|
オーケストラアンサンブル金沢と地元特別編成学生オーケストラ(金沢大、金沢工大、北陸学院各オーケストラ)による150名の合同編成の特別オーケストラによるユニークなハイドンコンサート。指揮は岩城宏之氏。昨年からOEKが企画している、ハイドンのシリーズ。今年はこの演奏会と3月にギュンター・ビヒラー指揮による後期の交響曲集が予定されている。
パリ交響曲と呼ばれるハイドンの傑作群の中から、第85番「王妃」、83番「牝鶏」がOEKの単独演奏、82番「熊」とロッシーニの歌劇「どろぼうかささぎ序曲」が合同で演奏された。
ハイドンは同時代のモーツァルト、ベートーヴェンと比較し先駆的な役割とのみ評価され、その個性も両者よりやや薄いような印象をもたれており、演奏も端正なものが評価されてきたような印象があったが、この日の演奏はそんな印象を覆す、ハイドン音楽の本当の魅力を存分に味あわせてくれた演奏会。
ハイドンの音楽のもつ、疾走する様な激しさ、諧謔、そして悲哀は、ハイドンの音楽が将にこの時代の風を映し出していることを物語っている。フランス革命前後の疾風怒濤の時代に、ハイドンが単に貴族の御用音楽家としてではなく、その時代に生きる一人の人間として描き出そうとしたものが音楽の中に満ち満ちている。最近の古楽器演奏によるハイドン演奏もそのような面を端的に表現しようとしているように感ずるが、この日の岩城氏の演奏はモダン楽器によるものではあるが、ハイドンの音楽のモーツァルト、ベートーヴェンとは異なる、人間くささ、激しさ、暖かい朴訥さを見事に表現していた。そして、この作り方はOEKの単独演奏、最後の合同演奏でも同様であったが、82番「熊」の合同演奏では150名という大編成オケにより、この特徴がより増幅されていた。岩城氏とOEKのコンビの円熟ぶりを再認識させてくれた。
岩城氏はトークの中で〔パリ交響曲群〕が当時はパリの多くの市民で結成された大編成の下手糞なオーケストラで演奏されたことがあったことを紹介し、この演奏会の意図を、「その再現を是非やりたいという夢を持っていたので、今日の演奏会は決して遊びで行ったものではない」と、説明されていた。この日の演奏会の意図がよくわかるトークであった。
学生オケも十分に練習を積んだことが伺われる、立派な演奏。
最後にロッシーニの歌劇「どろぼうかささぎ」序曲が150名で演奏されたが、学生のパワーが爆発したような演奏。少しのアンサンブルの乱れなどものともせず、力のみなぎった、青春のアンサンブルであった。岩城氏が楽しそうに指揮をしていたことが、印象的。
3月のギュンター・ビヒラーによるハイドンの後期の交響曲集も楽しみとなった |
|
|
|
|
|
|
|
|
クァルテット・エクセルシオ演奏会 2004年2月22日 入善コスモホール |
|
桐朋学園大学在学中に結成されたクァルテットとのこと。
Vn.西野ゆか 山田百子 Vr.吉田有紀子 Vc.大友肇
昨年、入善町で滞在型のコンサートを実施、地区公民館などでプチ演奏会を開催、普段音楽に接する機会の少ない方たちに、音楽の楽しさ、素晴らしさを広めていこうとする活動をしてきたクァルテット。
今回はメーンホール、コスモホールでの演奏会。
地域演奏会でお馴染みとなった住民も集まってきているような、アットホームな演奏会だが、それでいてここの聴衆は、良い緊張感をもって、生の音楽会を楽しもうとしている、良い雰囲気の音楽会。ここのホールは響きも大変素晴らしく、また企画力、集まってくる聴衆の質の高さなど、ローカルなホールと思えないいい雰囲気を常に感じさせてくれる。
さて、今回の演奏会、弦楽四重奏曲の演奏の難しさを改めて感じた。
曲目は、ハイドンの作品33-3「鳥」、シューベルトの「ロザムンデ」の四重奏曲、ベートーヴェンの「ラズモフスキー第3番」というオーソドックスな、堂々としたプログラミング。
ドイツ・オーストリアの古典派から、ロマン派にかけての名曲ぞろいである。アンサンブルは安定しており、技術も確か、音量もあり、その意味では安定したクァルテットといえる。
ただ、各作品が総て、同じトーンに聞こえてしまうのは何故だろう。
この3曲は、時代が近接しているとはいえ、明らかにそれぞれの個性の相違がはっきりしている作品。ハイドンの明快な形式性と旋律、シューベルトの溢れるような歌、ベートーヴェンの人間のドラマと個性がはっきりしている。ところが、出てくる音楽が総ての作品がモノトーン、各楽章間の形式感の相違も明瞭に聴こえない。
おとなしすぎ゛るのである。
クァルテットの面白さは、各奏者の個性の発揮と、そこから生れる音楽的緊張と、主張、ドラマであると思う。このクァルテットには残念ながらそれが感じられないので、音楽が退屈してしまう。楽譜を表面的に合わせる以上のことが、プロには要求されるはずである。各奏者のもう一歩作品に踏み込んだ解釈を聴きたいと感じた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新潟ニューセンチュリーオペラ「てかがみ」 2004年2月17日 石川県立音楽堂邦楽ホール |
|
池辺晋一郎監督作曲によるオペラ。
実に重いテーマを、音楽劇(オペラであるが、むしろこの言い方のほうがこの作品にはふさわしい。)で、明快かつ率直に謳いあげた、日本オペラの傑作となるであろうことを予感させる作品。
イラクへの自衛隊派遣、憲法改定の動き等、時代が将に逆行しようとしている時期に、この様な重要なテーマ性を持った作品を作り上げた池辺晋一郎氏他スタッフに、拍手を送りたい。
地方制作オペラの多くが、その土地の民話等を題材にしたものが多い中で、新潟県の一市民が体験した悲惨な戦争体験を題材とし、戦争の本質を明らかにし、それを後世に伝えていくことの重要性を強烈に訴えかけたこの作品は、一地方の記念オペラの枠を超えて普遍的な時代の意味を持った作品となるであろう。
なによりも、わかりやすいセリフと歌唱、これはかつて日本の創作オペラの多くが、日本語を歌っていながら、まるで外国語を聴いているようであったことを考えると、この作品は見事に日本のオペラとなっている。池辺氏の作曲技巧の巧みさは勿論だが、各キャストの歌唱力によるところも大きい。各キャストとも、見事な歌唱力であった。
そして、オーケストラ-といってもヴァイオリンとチェロ、フルート、クラリネット、ピアノ、パーカッションの6パートのみであるが-の扱い方の巧みさ、台詞を音楽的に昇華していくため、歌唱の内容が音楽的感動をもって心に訴えかけてくる。これも、このオペラを感覚的にわかりやすいものとしている。特にフルート、チェロの表現力の大きさが際立っていた。指揮の牧村邦彦氏とOEKメンバーも好演。オペラとは本来こういうものだということを再認識させてくれた。フルオーケストラでなくとも、いやこの様な編成であるからこそ、十分に表現できることが可能なのだ。これも作曲者の技法の確かさを示している。
そして、各アリア(という言い方が正しいか?)、合唱曲の旋律の美しさとやさしさが聴き手の心に染入る。過去に、念仏を唱えているような創作オペラのアリアが多かっただけに、新鮮に聞こえる。
児童合唱、混声合唱とも立派。これから各地で気軽に上演していくために、合唱団の調達が問題となるだろうが、地方合唱団も立派な活動をしているところが多いので、協力は得やすいかもしれない。
このオペラのテーマ、「次の世代に伝えていくべきこと」を、このオペラの上演自体が主張しているのであるから、各地での再演、再々演を期待したい。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢 第155回定期演奏会 2004年2月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ロルフ・ベック
独唱 So.レンネッケ・ルイテン 松下悦子 Al.永島陽子 Te.佐々木正利 Ba.小原浄二
合唱.OEK合唱団 トランペット.ジェフリー・ベイン フルート.岡本えり子 |
|
ロルフ・ベックの指揮による、J・S・バッハの夕べ。
独唱 So.レンネッケ・ルイテン 松下悦子 Al.永島陽子 Te.佐々木正利 Ba.小原浄二
合唱.OEK合唱団 トランペット.ジェフリー・ベイン フルート.岡本えり子
曲目は 管弦楽組曲第2番、カンタータ「もろびとよ、神をたたえよ」、ブランデンブルグ協奏曲第3番、マニフィカト。
バッハをまとめて聴く機会は多くない。優秀な声楽パート、合唱団、技量のあるソリスト達が揃わないと、今晩のような演奏会は実現できないだろう。
ロルフ・ベックの指揮は、実に明確、バッハの音楽の壮麗な世界を築き上げていた。
バッハの音楽の複雑な要素、壮麗、緻密、荘厳、しかし中に秘めたる暖かさ、悲しさ、やさしさ、それらを十分に多面的に描き出すのは容易でないと思うが、ロルフ・ベックとアンサンブル金沢は見事に描き出していた。
管弦楽組曲第2番では、出だしこそやや生硬さを感じさせたが、音楽が進むにつれて、アンサンブルは緻密につむぎだされ、フルートもやや控えめながら他の楽器との調和を保ちながら、バッハの管弦楽曲の愉悦を与えてくれた。
カンタータ「もろびとよ、神をたたえよ」では、ソプラノのレンネッケ・ルイテンとトランペットのジェフリー・ベインのオブリガートの絶妙なかけあいが見事。ソプラノはボーイソプラノを想起させる、透明な声で、バッハの神に対する賛歌を歌い上げ゛る。トランペットの絶妙な技巧。相当難しいであろうパートを楽々と謳いあげていく。神への信仰が無い私にもバッハの神への賛歌が体感できるような演奏。明るい、開放感に満ちた演奏であった。
後半のブランデンブルグ協奏曲第2番。管弦楽組曲と異なり、少人数の演奏であるため、余計緻密なアンサンブルが要求されるが、各パートともくっきりと聴こえる素敵な演奏。アンサンブル金沢の高い技量を改めて感じた。
最後のマニィカートは圧巻。トランペットにティンパニーも加わり、オーケストラは高々と謳いあげる。OEK合唱団は、100名近い大人数だが、各パートのアンサンブルが良く鍛えられている。
ただ、これだけの大人数の合唱団を必要とするのか、疑問も残ったが。
ソリストもソブラノ2名、アルト、テノール、バスという布陣で完璧。佐々木氏のバッハの宗教曲に対する深い造詣を感じさせる歌唱を初めとして、各独唱者とも熱演。
最初のカンタータとともに、バッハの壮大な音楽の世界を体感させてくれた。
来年2月、ペーター・シュライヤーと共に、「マタイ受難曲」が予定されているそうで、期待が高まる。 |
|
|
|
|
|
|
|
JASRACコンサートin富山 「オーケストラが待っている」 2004年2月15日 オーバードホール
指揮:小泉和裕 ピアノ:熊本マリ 富山シティフィルハーモニー管弦楽団
司会とお話 山田美也子 吉松隆 |
|
演奏曲目
芥川也寸志 「交響管弦楽の為の音楽」
ガーシュイン 「ピアノ協奏曲ヘ長調」
吉松隆 「交響曲第4番 OP82」
指揮:小泉和裕 ピアノ:熊本マリ 富山シティフィルハーモニー管弦楽団
司会とお話 山田美也子 吉松隆
JASDAC(日本音楽著作権協会)が音楽文化の普及・振興のために全国で展開している音楽会。
地方オーケストラにプロとの共演を体験させること、日本人の作曲家の作品を演奏することで、新たな発展を促し、聴衆にも新たな音楽的感動を与えようと企画されている音楽会。無料招待。
まず、日本人の作品を聴く機会に恵まれない、地方の聴衆にとって貴重な体験を得られる音楽会であった。また、地域で活躍しているアマチュアオーケストラが、場合によっては高度な演奏が出来ることを知らしめてくれた演奏会でもある。本来なら、富山県、市、あるいは音楽文化振興事業団などがこのような演奏会を開催して然るべきだとも思う。
特筆すべきなのは、アマチュアオーケストラが日本人の高度な技術を要するであろう作品を見事に熱演したこと。指揮者の小泉氏も語っていたように、まだ未完成な部分、やらなければいけないことも当然あるだろうが、ここまで演奏するには相当な訓練を要したであろうと、感嘆した。
オーケストラの団員が、「仕事の傍らでオーケストラをやるのが大変なのではなく、オーケストラをすることが仕事への励みになっている」と語っていたが、アマチュアオーケストラの真髄を見る思いがする。
芥川也寸志「交響管弦楽のための音楽」
久しぶりに聴く作品。長い年月を経ても、色あせていない名曲。確か芥川也寸志も「新交響楽団」という、アマチュアオーケストラを率いて、自分の作品を発表していたと記憶するが、アマチュアオーケストラが演奏するには、向いている作品なのだろう。
芥川の作品は、日本音階をむき出しに使っているわけではないが、根本に流れる、郷愁のような日本の風景を感じる。第2楽章は、リズムが跳躍する、これも日本の祭りか。オーケストラは早いパッセージも、鋭いアンサンブルで熱演。小泉和裕のガッチリしたリードも見事。
ガーシュイン 「ピアノ協奏曲ヘ長調」
これも、演奏するに大変な難曲。金管、パーカッションとも、独特なガーシュインのリズムと節回し、スイング感を要求されるはずだが、見事にクリアーしていた。
ピアノの熊本マリも好演ではあったが、ややおとなし過ぎ。もう少し、暴れてもらってもよかった。
アマチュアオーケストラに気を使ったのだろうか。
吉松隆 「交響曲第4番 OP82」
今日の演奏会の目玉であり、一番注目していた作品。
現代に、このようにすっと耳に入ってくる聴き易い音楽を作るのは、逆に勇気がいることであろう。現代音楽が様々な試みを、作曲技法の上で行っているのは、自己の主張をどのようにして聴衆に追体験してもらうかの試みであり、試行錯誤であると考える。それが、自己満足に終わるか、普遍的な価値を持ちうるかは、技法の問題ではなく、その技法が作曲家にとってテーマを表現するにあたり必然であり、せっぱつまったものであるかどうかであり、もう一つはテーマが明確であるかどうかであろう。その意味では、表現されたものがいわゆる前衛であろうと、保守であろうと関係なく、後は聴衆がどう受け止めるかである。
吉松隆の作品は有名な「朱鷺に寄せる哀歌」以外は聴く機会が無く、交響曲は初の体験。
実に楽しく、美しい作品。芥川と同様に、あからさまな日本音階とは無縁だが、根底には日本人の民族性を深く感じさせる。そして、音楽を奏でることの楽しさを、嬉々として描き出している。
ベートーヴェンの4番、6番、マーラーの4番などを想起させる。作曲家には交響曲に対するそのような思いがあるのであろうか。対談の際、冗談に次の作品6番は「悲惨」としたいと言っていたが、今度は吉松のシリアスな交響曲も聴いてみたい。
これも演奏者にとっては過酷な曲と思われるが、小泉和裕と富山シティフィルは見事に演奏。大拍手。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第153回定期演奏会 2004年1月8日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 マイケルダウス
ソプラノ メラニー・ホリディー |
|
2004年最初の音楽会。
メラニー・ホリディーを迎えてのニューイャーコンサート。指揮はマイケルダウスの弾きぶり。
メラニー・ホリディーの一人舞台の様なコンサート。さすがに、声域は狭くなったようで、「春の声」など、苦しそうではあったが、そのエンターティーナーぶりは、さすがと言う他はない。
以前、富山でのブタペストオペレッタ劇場の「チャールダッシュの女王」公演の時の、聴衆が少ないにもかかわらず、劇場のスタッフがサービス精神を発揮して、少ない聴衆を熱狂の渦に巻き込んだことを思い出させる、熱演であった。オペレッタの伝統とは、こういうものなのだろう。
アンコールの「天国と地獄」では、一人でかんかん踊りを披露し、側転まで見せる始末。
さて、オーケストラは、生気にかけた演奏。ウィーーン音楽は、そうたやすいものでないことを見せつけられたようだった。
新年になると、この種の演奏会が多いが、ウィーンナワルツ・ポルカは、余程精緻なアンサンブルと共感がないと、人を酔わせることはできない。中途半端な演奏は退屈のみである。
ニューイヤーコンサートのありかたも、選曲を含めて一考の余地があるのでないだろうか。
別に、本家のニューイヤーコンサートに右倣えをする必要もないと思うが、いかがなものであろうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
エフゲニー・キーシン ビアノリサイタル 2003年11月28日 富山市オーバードホール |
|
キーシンは最近、ブリリアントより再発売された12歳から20歳にかけてのライブ演奏会のCDを聴いて、圧倒され、今回の演奏会を非常に期待していた。このCDでも、弾き始めから、人の心をぐいっとつかまえてしまい、離さずにおくべきかという気迫にのみ込まれたが、今回の演奏会では更にそこに円熟味が加わり、かつて聴いたことがないような音楽の世界が繰り広げられた。
今まで、この大きなホールが埋め尽くされたのはオーケストラでもオベラでもそんなに多くは無かったと記憶しているが、ピアノの演奏会でこれだけの聴衆を集めるキーシンの人気にあらためてびっくりする。もとより、世界で一番チケットの取りにくいピアニストといわれているキーシンであるので、恐らく東京、大阪でチケットの取れなかった人もここに集まっていたのかもしれない。いつもの富山のコンサートと異なり、舞台に駆け寄って花束を渡す人、立ち上がって拍手を送る人など、熱い光景が繰り広げられた。
さて、曲目はシューベルトの最後のソナタ、21番変ロ長調、同じくシューヘルトの歌曲集「白鳥の歌」から「セレナード」「わが宿」、「美しき水車屋の娘」から「さすらい」「どこへ?」(リスト編曲)、最後にリスト「ペトラルカのソネット104番」「メフィストワルツ」というプログラム。このプログラムは昨年カーネギーホールで大好評だったプロで、今年はロンドンでも大変な評判となり、昨年から一貫して世界各地で同じプログラムで演奏しているようだ。
最初のシューヘルトのソナタ21番、この長大な曲が、このように集中力と緊張に満ちて演奏されると、長いと全く感じさせない。第一楽章、確かに「モルト・モデラート」の指示なのだが、それ以上にゆったりとした緊張感に満ちた主題が、まるで一音一音確かめられるように弾き出される。時に高揚し、時に沈潜し深い息遣いが聴かれる。第2楽章は弱音の美しさと微妙な強弱のニュアンスが絶妙。第4楽章は、確かな技巧に支えられた悲しみを伴った愉悦が駆け巡り全曲を閉じる。シューベルトが意図したもの以上の世界が現出されたような演奏であった。歌曲集より4曲は、歌曲集の印象が強すぎ、何故ピアノ版に編曲する必要があったのか不可解な曲である。それでも、キーシンは最後の「わが宿」の演奏に見られるように、シューベルトの絶望を共感をもって表していた。
最後のリスト2曲は。凄い!!、のひとこと。リストの濃厚なロマンチシズムと、驚異的なテクニックとをあわせて表現できる人はそんなに多くないだろう。
かつて、リパッティにささげられた「このように演奏することが出来るのは、神に選ばれた楽器だ」という賞賛の言葉を思い起こさせるキーシンの演奏であった。
アンコールがなんと7曲、シューベルト、リスト、ブラームス、チャイコフスキー等々。30分あまりにわたるアンコールであった。
キーシンは聴衆を熱狂させることで、自らもその熱狂を共有し燃え上がるようなタイプのピアニト、その意味で本当のプロといえるだろう。
音楽の人をつき動かす力を改めて教えてくれた、感動の一夜であった。
|
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第151回定期演奏会 2003年11月22日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ギュンター・ビヒラー
ピアノ ルカーシュ・ヴォンドラーチェク |
|
指揮がベルク四重奏団の第一バイオリン奏者、ギュンター・ビヒラー、ピアノ独奏がルカーシュ・ヴォンドラーチェクで、モーツァルトが2曲、歌劇「フィガロの結婚」序曲とピアノ協奏曲23番、メーンがペートーヴェン「田園」という、オーソドックスなプロク゜ラム。
中では、最初の歌劇フィガロの結婚」序曲「が秀演。
ビヒラーの指揮は実にふくよかで、やさしい。ウィーンの正統をいくような演奏。フィガロの結婚」序曲は、典雅で、柔らかい トーンがモーツアルトの喜悦をくっきりと浮かびだし、歌劇のオープンにふさわしい華やかさをかもしだしていた。総ての楽器をくっきりと浮かび上がらせ、アンサンブル金沢も巧みなアンサンブルで応えていた。
ピアノのヴァンドラーチェクは17歳とのことだが、モーツァルトでは年齢以上の大人びたピアノを聴かせていた。欲を言えば、青年らしいみずみずしい感性が聴きたかったが、まずは無難な演奏だろうか。アンコールが面白かった。ラフマニノフかと思ったら、認識不足。チャイコフスキーの「くるみ割り人形」から「ロシアの踊り」とのこと。本当かよという感じ。ダイナミックさと繊細さを兼ね備えた演奏だが、音の色彩感は不足気味。
「田園」は、良く言えばオーソドックスだが、感興に乏しい演奏。こんな「田園」に接すると、ほっとした懐かしさを感じると同時に、「つまらないな」とも感じてしまう。ベルク四重奏団がペートーウ゛ェンを演奏すると、緊張感に満ちた、内面に鋭く迫る演奏を行うが、指揮では印象が全く違っている。ベートーヴェンの演奏は本当に難しい。オーケストラも金管パートが突出し、アンサンブルの乱れが気になった。 |
|
|
|
|
|
|
|
ラトヴィア国立交響楽団演奏会 2003年11月12日 高岡市民会館
指揮 テリエ・ミケルセン
チェロ ミッシャ・マイスキー |
|
独奏にミッシャ・マイスキーを迎えて、3曲、指揮はテリエ・ミケルセン。
ラトビアの現代作曲家ヴァスクスが2001年に作曲した「ヴィアトーレ」、マイスキーの独奏でドヴォルザークの「チャロ協奏曲」、最後にチャイコフスキーの交響曲第5番というプログラム。
指揮者もオーケストラも全く馴染みの無い、マイスキーを聴きにいくのが最初の目的というような演奏会。しかし、バルト3国のオーケストラということ、初来日ということに新鮮な期待をもって足を運ぶ。
最初のヴァスクスの作品は現代音楽と思えない、ロマンティックな小品。この曲の出だしの数十秒間を聴いたとき、ああ北欧の風だなと感じる。ラトヴィアは旧ソ連だが、地理的にも文化的にも北欧圏と認識させてくれた。曲はシベリウスを思わせるような、爽やかな風が吹く、弦楽合奏曲。オーケストラの弦楽パートも落ち着いた美しいいぶし銀のような弦を聞かせてくれた。なかなかのオーケストラである。
マイスキーのドヴォルザークは勿論おはこ。隙の無い、完璧な演奏である。が、どうしてか感動が起こらない。マイスキーのチェロは以前入善で聴いたときも同様の感がした。文句のつけようが無い、しかし、何か足りない。
音楽へのめりこむ一歩手前で、冷静に踏みとどまっているようなマイスキーの客観性が原因なのだろうか。一歩熱い演奏を聴きたい。
今年秋、富山にクレメル、アルゲリッチ、マイスキーと次々に来演し、総てを聞けたことは大変な幸せ。3人それそれの個性、なかでやはりアルゲリッチの音楽へ寄せる熱い共感が感動的だった。プロの演奏家が、聴衆を前にするとき、訴えたいことの切実さが感動の質を左右するのでないだろうか。
マイスキーのアンコール2曲、バッハは柔らかいトーン、祈りのような感情をたたえ、しみじみと心をうつ。ドヴォルザークより、この方が秀演。
さて、当日のメーン、チャイコフスキー。
絃の厚い響き、吼える管楽器、しかしながら総てのパートを明確に描き出す、しっかりとした熱演だった。指揮者のテリエ・ミケルセンは全く知らない指揮者だが、経歴をみるとマリス。ヤンソンスに師事とのこと。なるほど、ヤンソンスばりの、堂々とした指揮である。
ロシアの粘っこさは全く無い、かっちりとした、石の建造物を思わせる。
オーケストラはすごい馬力がある。少々のアンサンブルの乱れなど、気にせずの風ではあるが、音楽全体が鳴り響いているのだから、文句のつけようがない。世界には、またまだ凄いオーケストラが多くあるのだろうということを再認識させてくれた。
アンコールはグリーグと、もう1曲は不明。チャイコフスキーから一転してグリークの「アニトラの踊り」は、絃と管の絶妙な美しさが演じられた。
充実した一夜。。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ギドン・クレメルリサイタル 10月19日 入善コスモホール |
|
ピアノ伴奏、アンドリウス・ズラビス
演奏曲目、バッハ無伴奏パルティータ第2番より「シャコンヌ」、シュニトケ「クワジ・ウナ・ソナタ」、バッハ「前奏曲とフーガ」、フランク交響曲のヴァイオリンとピアノの為の編曲版
非常に、凝ったプログラミンク゜。壮麗な音世界の構築を意識したようなプログラミングである。
バッハ「シャコンヌ」は、春に同じコスモホールでギル・シャハムの演奏を聴いたが、全く対照的な演奏。シャハムが柔軟で、しなやかなバッハを聴かせたのに対し、クレメルは、シャープ、メリハリの利いた、堂々たるバッハの世界を聴かせてくれた。バッハの音楽の持つ、壮大な世界が、ヴァイオリン一つでこれだけ現出できるのは、驚異である。
シュニトケは、独特の音のぶつかりあいが凄まじい。ヴァイオリンとピアノの格闘のような演奏。メロディックな情緒的な部分をすぐ否定するかのような、音の塊が次々と押し寄せる。ピアノは打楽器的な使い方に終始する。更に、長い音の休止が、想像力をかきたてる。クレメルも、ズラビスも凄まじいと形容できる、熱演。
何回も繰り返し聴き、シュニトケのメッセージを確かめてみたいと思わせる曲である。
バッハ「前奏曲とフーガ」は、オルガン曲をリストがピアノ用に編曲したもの。
ズラビスは、ホール一杯に響くほどの音量でこの曲を弾きまくった。バッハのオルガン曲の壮麗な面を強調した演奏。その反面、ややデリケートさにかける大味な演奏ではあるが、曲の性格上こうなるのか。
最後のフランク「交響曲」 今回最も注目した曲である。
今回の演奏会のプログラミングを初めて見たとき目を疑った。あの、壮大な交響曲をヴァイオリンでどうして表現するのだろうと。
結果として、ヴァイオリンの技巧の限りをつくし、曲の骨格を明確に表現した演奏となっていたが、当然ではあるが、あまりにも原曲のオーケストラの印象が強すぎ、熱演ではあるが、この交響曲の魅力を十分に伝えるものとはなっていなかった。果たして、クレメルはこの演奏で何を聴衆に伝えたかったのか、少々、もどかしい気がする。知的好奇心のみでは、音楽的感動は得られない。クレメルの挑戦には敬意を表するが、それが自己満足に終わっては困る。
帰りの車中で、ブラームスやベートーヴェンのソナタが無性に聴きたくなったのは、何故であろうか? |
|
|
|
|
|
|
|
ミラノ・ジュゼッペ・ベルディ交響楽団演奏会 2003年10月12日 富山市オーバードホール
指揮 リカルド・シャイー
ピアノ マルタ・アルゲリッチ |
|
リカルド・シャイーが指揮、マルタ・アルゲリッチのピアノという、豪華顔合わせ。
シェーンベルク「ノットルノ」ハープと弦楽の為の、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第一番、ブラームスの交響曲第一番。
アルゲリッチがアンコールにシューベルトの小曲とスカルラッティのソナタ。オーケストラがアンコールにブラームスのハンガリー舞曲第3番、1番、10番の3曲を演奏という、サービスたっぷりの演奏会。
ベートーヴェンの協奏曲はチケット発売時には、何番か未定という、アルゲリッチらしいやりかただったが、結局第一番。アルゲリッチの得意な曲であり、恐らく一番好きな曲であろうと推察されるので、妥当な選曲だろう。
この一番が大変な名演。以前のアルゲリッチのように、派手に弾きまくるというのでなく、ひとつひとつの音を確かめ、いつくしむような演奏。深く沈潜しながら、ベートーヴェンの音楽の人間的な巨大さを描き出していた。特に第2楽章の自由自在な呼吸は、この曲を完全に自分のものとし、そこから聴衆に訴えかけてくる、主張のはっきりとした、酔わせる演奏だった。これだけ、テンポを遅くし、揺れ動いた演奏をすると、通常なら弛緩しきってしまいそうなものだが、その逆で息を呑むような緊張感に満ち満ちていた。アンコールの2曲、特にスカルラッテイは、やはり自由自在な名演。スカルラッテイというより、もうアルゲリッチの解釈を聴くような演奏であるが、それが一つも違和感がない。
数年前にヨーロッパ室内管弦楽団とシューマンの協奏曲を横浜で聴いたが、その時はさほど感動しなかったが、ムラがあるのであろうか。
シャイーは、芝居気たっぷりの演奏。ブラームスでは、各所で聴かせどころを作るのだが、それが逆にあざとく聴こえてしまう。統一感にかけた演奏。ワルベルク・N響がついこの間魚津で聞かせたブラームスとは全く違った演奏だった。
ワルベルクは何にもしていないようでいて、質実剛健なブラームス像を描き出していたが、シャイーは総てやりすぎて、ブラームスが聴こえてこない。音楽とは難しいものだ。
シェーベルクは、初めて聴く曲だったが、後のシェーンベルクと異なり、後期ロマン派の色を濃く感じさせる美しい作品。「浄められた夜」を想起させた。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラアンサンブル金沢第148回定期公演 2003年10月11日 石川県立音楽堂コンサートホール
指揮 ルドルフ・ヴェルテン
ヴァイオリン アナスタシア・チェボタリョーワ |
|
指揮がベルギー出身、ルドルフ・ヴェルテン、ヴァイオリンがロシア出身アナスタシア・チェボタリョーワ
ブラームス「ハイドンの主題による変奏曲」、チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲」、ベートーヴェン「交響曲第一番」というプロ。アンコールにベートーヴェン「エグモント序曲」
ヴェルテンはベルギー出身ということだが、同地出身の大指揮者クリュイタンスと同様、フランス的な明るさと明快さを備えた指揮者であった。
ブラームスはその明るさが逆作用し、この曲独特の陰影が聴こえてこなかったのは残念。各々の変奏のコントラストが弱く、明快ではあるが、単調な演奏となってしまったようだ。
ベートーヴェンの一番は、明快さが生き、力のこもった名演で、一番という、ベートーヴェンの交響曲の中で、どちらかといえば軽く見られがちな曲を、そうではなく、きわめて革新的な音楽であるということを明快に示してくれた。やや早めのテンポで、余計なアコーギック等は使用せず、素直で明快な演奏。
チャイコフスキーを弾いたチェボタリョーワは、ロシア出身ということだが、いわゆるロシアの泥臭さなど全く感じさせない、明るく華麗なチャイコフスキーを演奏してくれた。音は華やかで、可憐。テクニックも抜群、楽々とこの難局を弾いて行くさまは見事。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
オペラ「白墨の輪」 2003年9月27日 富山市オーバードホール |
|
林光作曲のものを、作曲者自身がフルオーケストラ版に改編したもの。
神奈川芸術文化財団と富山市民文化事業団の共同制作で、横浜と富山のみで公演とのこと。
林光のオペラは「こんにゃく座」を中心とした活動で知られており、富山でも数年前、「金色夜叉」の公演があり、非常に面白かった記憶がある。
林光のオペラは、旋律の単純さと明快さが際立ち、他の日本オペラの多くが、非常に構えて作られているのに対し、わかりやすさと楽しさを前面に押し出している特徴がある。もちろん、だからといって含まれている内容は単純ではなく、見終わった後に、考えさせられる内容を多く持ち合わせている。
今回はブレヒトの原作のものであり、劇の筋は単純だが、脚本のセリフが、非常に含蓄のあるものが多く、それを歌にするという困難さが透けて見えるようであった。台本を見れば理解出来るのだが、ただ聴いているだけでは、何の意味かわからない部分が多くある。これは、歌手の発声にも問題があったのであろうか。しかし、総じて歌手は明快に発声しており、やはり脚本のセリフの難しさが、消化されつくしていないのではなかろうか。
特に最終場面、人間の未来に対するささやかな希望を謳いあげる部分は、音楽が盛り上がって感動的であるのに対し、言葉が聴き取りにくく、ブレヒトと林光、脚本家の思いが、聴衆に伝えきれていないもどかしさを感じた。
オーケストラ(神奈川フィルハーモニー)、合唱(東京オペラシンガーズ)とも、巧みで熱演。主演の塩田美奈子も、声が伸びやかで明快、裁判官アツダクの工藤博が、キャラクターを良く出した熱演であった。 |
|
|
|
|
|
|
|
NHK交響楽団演奏会 2003年9月24日 新川文化ホール
指揮 ハインツ・ワルベルク
フルート 工藤重典 ハープ 早川りさこ |
|
ハインツ・ワルベルクの指揮、工藤重典のフルート、N響団員の早川りさこのハープによって行われた。
びっくりしたのは、まだ中堅かと考えていたワルベルクが、もう80歳となること。私の考え違いであったが、それにしても月日の過ぎるのは早い。
ワルベルクは年相応に円熟味を増してきている。
特にブラームスの4番。テンポはインテンポで、ほとんど動かさないが、動かないテンポの中で音楽は堂々とうねっている。無理に高揚させようとするのでなく、ブラームスの音楽自身の持っている力を淡々と表現することで、十分に起伏のある音楽が作られていく。これは、ヴァントなどと同じ方向性で、ワルベルクも巨匠の道を歩き出したようだ。
モーツアルトの「フルートとハープの為の協奏曲」はその面が逆に音楽をつまらなくさせていた。典雅で愉悦に満ちたこの曲を、淡々と演奏されると、モーツァルトのはじけるばかりの喜びと悲しさが聞こえてこない。フルートは佳演、ハープはやや地味であった。
最初に演奏された、マーラーの5番からの「アダージェット」はN響・ワルベルクの円熟味を聞かせる名演であった。
久しぶりにN響を聴いたが、日本のトップオケの面目を聴かせてくれた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ドイツマグデブルグ歌劇場「アイーダ」公演 2003年9月21日 富山市オーバードホール |
|
ドイツのローカルな歌劇場が、何故ベルディーをとりあげたのか、まず疑問がわく。
歌手の水準は、ダブルキャストのBであるが、水準は高い。
演出、装置等はおそまつのひとこと。そもそも「アイーダ」は2幕第2場の凱旋の場が売り物のグランドオペラである。前後の愛の悲劇の静謐な場面も、この幕の華やかさとのコントラストでこそ生きる。この場面のおそまつさは、装置、美術のおそまつさ、アイーダトランペットの人数の不足等、致命的である。
海外公演という制約上なのか、舞台装置を極力簡略化しているが、そもそも昨年同歌劇場のプレミアム公演では野外で行ったとのことで、それを海外公演用に焼きなおすことに無理があったのでないか。
ドラマとしての起伏が何も感じられない、平板な舞台となったのは、そこに原因があるようだ。
特に最終幕の地下牢の場面は、演出にも納得がいかないし、美術・装置ともおそまつである。
まず、地下牢の雰囲気が何も無い。ただ、平面での演技では緊張感も無い。最後に、巫女達の合唱が、聞こえて来る場面では、なんと抱き合った二人の周りを、精霊達のように巫女が歌いながら踊る。新解釈ではあろうが、改悪である。
オーケストラも、平凡。天沼裕子の指揮もドラマが感じられない。
久しぶりに、退屈するオペラを見たというのが、率直な感想。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ダニエル・ハーディング指揮 マーラーチェンバーオーケストラ 2003年9月14日石川県立音楽堂 |
|
待望のコンサート
ハーディングはCDでベートーヴェンの序曲集を聴いて以来、期待していた指揮者。
ベートーヴェンの3番「英雄」と5番。
非常に新鮮な演奏。古楽のピリオド奏法に準拠した演奏とのことだが、ベートーヴェンの音楽が、今生まれたばかりのように響く。フルトヴェングラーを頂点としたいわゆるロマン的な演奏は、いきつくところまで行きついてしまった感がある。今までの演奏の垢を洗い落とし、新鮮な感動をベートーヴェンの音楽から得ようとすれば、このような方向性しかないのかもしれない。かといって、決して機械的な冷たい演奏ではない。きちんとした様式を保ちながら、熱い感情が溢れている。
5月に聴いた金聖響、一昨年聴いたラトル・ウィーンフィル、いずれも同様の感がしたベートーヴェンである。
5番が特に素晴らしかった。強い緊張感を保ちながら、一気呵成に駆け抜ける、しかし決して底の浅い演奏ではない。ベートーヴェンの音楽の理念と精神性を見事に表現している。特に第4楽章の歓喜のテーマの提示部の繰り返しがこんなに新鮮に聞こえたことは無い。従来の多くの指揮者はこの提示部の繰り返しがうるさいとばかり、繰り返さないことが多いが、ハーディングの演奏は繰り返すことにより、「苦悩を通じて歓喜に至れ」というベートーヴェンの主題を強く印象付けている。
ベートーヴェンを聴いて、涙するばかりに感動するということは、最近の演奏ではまれである。それほど、ベートーヴェンは軽く扱われてきている。そうではないということを改めて示してくれた演奏会であった。マーラーチェンバーオーケストラも若手中心ながら大変な力量のある、オーケストラである。 |
|
|
|
|
|
|
|
第4回現代日本オーケストラ名曲の夕べ 2003年9月13日 石川県立音楽堂コンサートホール
オーケストラ 「オールジャパン・シンフォニーオーケストラ」
指揮 岩城宏之、外山雄三 |
|
アンサンブル・金沢を中心とした、特別編成のオーケストラ「オールジャパン・シンフォニーオーケストラ」を、岩城宏之と外山雄三が指揮してのコンサ-ト。
これだけまとめて、日本人の現代オーケストラ作品を聴ける機会は貴重である。岩城宏之氏が金沢で、アンサンブル金沢を中心として活動している、大きな成果であろう。
武満徹「夢の時」
「Dreamtime」が正式名で、「夢の時」では、曲の性格(オ-ストラリア原住民アポリジニの神秘的な歴史)と違うと岩城氏が語っているが、それなら「Dreamtime」を正式名としてしまったほうが良いのでないか。曲の雰囲気もそれにぴったりである。武満の作品の特徴である。透明さと、繊細なロマンチシズムが強く感じられる作品。
夏田昌和「アストレーション」
2001年作曲とのことで、ついこの間である。武満の作品が1981年であり、時代の推移を感じた。
たかが、20年余りであるが、その間の日本の状況は大いに変わったのでなかろうか、
まだ、夢の持てた高度成長期から、混乱と不安の21世紀へと。武満と野田という作曲家の性格の違いもあるが、それ以上に時代の相違を感じさせる作品であった。管弦楽は多彩で、飽きさせない。
湯浅譲二「ピアノコンチェルティーノ」
非常にしゃれた一品。上品さと、モーツァルト的な機智も感じさせる小協奏曲。木村かおりのピアノも秀演。
「尾高尚忠」ピアノと管弦楽のための狂詩曲
尾高の作品は、30年ほど前にN響が録音した吉田雅夫さんをソリストとした「フルート協奏曲」のLPを愛聴していたのを思い出し、懐かしくなった。あの頃は日本人の現代作品でもこんなに親しみやすい曲があるのかと新鮮に感じられたが、今聞いてみると時代の古さを感じてしまう。
メロディーが豊富で、親しみやすい曲であるが、歴史の評価に耐えられる作品とは思えない
。
石井眞木「響層」
フルオーケストラを鳴り響かせた、強烈な印象をもった作品。まさに、響きの饗宴である。
日本人の作品と感じられる民族性と、更にそれが昇華したインターナショナルを感じさせる作品。その意味では、武満の作品と似ているが、石井の作品には彼独特の音の分厚さ、豪快さがある。今年、4月に亡くなったが、もっとこの人の作品を聞いてみたい。
非常に興奮した一夜であった。もっとこの様な機会を作ってほしい。当日ほぼ満員の聴衆の数にもびっくりした。 |
|
|
|
|
|
|
|
オーケストラ・アンサンブル金沢第146回定期演奏会 2003年9月10日 石川県立音楽堂コンサートホール
仙台フィルとオーケストラアンサンブル金沢の合同演奏会
指揮 岩城宏之、外山雄三 |
|
仙台フィルとOEKの合同演奏会。春の大阪センチュリー交響楽団(小林研一郎指揮)との合同演奏会もそうであったが、OEKはこのような試みで全国のオーケストラの先駆的な役割を果たしているのでないだろうか。
指揮は岩城宏之と外山雄三。
曲目はポピュラー名曲と外山雄三の作品。
まず、面白かったのは両オーケストラの性格の違い。仙台フィルはきりっとした、フレッシュな響き、アンサンブル金沢はむしろ落ち着いた円熟した響き。歴史は仙台フィルの方が古いのだろうが、この性格の違いはどこから来るのであろうか。
仙台フィルが外山雄三の指揮で、ワーグナー「タンホイザー序曲」、サンサーンス「序奏とロンドカプリチオーソ」(独奏マイケル・ダウス)、アンサンブル金沢が岩城宏之指揮でウェーバー「クラリネットと管弦楽のためのコンチェルティーノ」(独奏日比野裕幸)、外山雄三「管弦楽のためのディヴェルティメント」
合同演奏で岩城宏之指揮チャイコフスキー「スラブ行進曲」、外山雄三の指揮で、外山雄三「管弦楽のためのラプソディー」。アンコールになんスポーツマーチ2曲、「コバルトの空」と「NHKスポーツ行進曲」。
外山雄三は本当に久しぶりに聴いた。昔より風格が音楽に出てきた。昔は几帳面だが生硬なだけの感がしたが、今回は几帳面な点は変わらないが、その中に音楽の堂々たる枠組みがはっきりと示されている立派な演奏となっている。
外山雄三の2作品は、N響がアンコールピースとして海外演奏会へ持っていったこともある、日本民謡を組み曲風にアレンジした、外山雄三の才気が感じられる作品。「管弦楽のためのディヴェルティメント」の方が、後に作曲されただけあってより巧妙に作られている。このような曲の評価は非常に難しいが、理窟無しに楽しめるという点では、音楽の一面でもある。
独奏の二人は日比野裕幸のクラリネットが曲ともども面白かった。いかにもドイツの森を思わせるクラリネットのほの暗い響き。マイケル・ダウスのバイオリンは無個性なバイオリン。巧さは認めるが゛、音楽の華が感じられない。
岩城宏之は「スラブマーチ」で彼独特の圧倒的なスケールの音楽を作り上げた。120人以上という大オーケストラで演奏されると、さすがにド迫力で、生の演奏会ならではである。
アンコールはご愛嬌であった。(阪神優勝を意識したのかな・・・・)
楽しい演奏会であった。
|
|
|
|